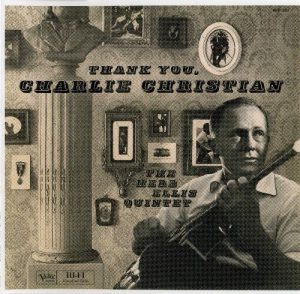2018.09
2018.09.20 Thu
今回はアルトサックス奏者Cannonball Adderley Sextetの1963年東京公演を収録したライブ盤「Nippon Soul」を取り上げたいと思います。as)Cannonball Adderley cor)Nat Adderley ts, fl, oboe)Yusef Lateef p)Joe Zawinul b)Sam Jones ds)Louis Hayes
1) Nippon Soul (Nihon No Soul) 2)Easy To Love 3)The Weaver 4)Tengo Tango 5)Come Sunday 6)Brother John On#1, 4~6 July 15, #2, 3 July 14, 1963 Sankei Hall, Tokyo Producer: Orrin Keepnews Riverside Label


日本は60年代に入り大物外タレの来日が始まりました。61年1月Art Blakey And The Jazz Messengers、62年1月Horace Silver Quintet、63年1月再びArt Blakey And The Jazz Messengers、そして同年7月Cannonball Adderley Sextetです。ジャズを真摯に受け止め、ジャズプレイヤーを本国とは比較にならない歓迎ぶりで受け入れる日本の聴衆の姿勢に、来日したミュージシャン達は精一杯の熱演で応えていました。本作も例外ではありません。後年なおざりの演奏でお茶を濁す来日ミュージシャンによる演奏も無くはありませんでしたが、本作の演奏の充実ぶりは特筆に値します。当時の東京で来日ミュージシャンの演奏を受け入れる事の出来るキャパのハコはサンケイホール、厚生年金会館、銀座ヤマハホールくらいで、現在では枚挙にいとまがありませんが、本作はサンケイホールにて超満員の聴衆の前に初来日のCannonball Adderley Sextetはその全貌を明らかにしました。このメンバーで活動し始めておよそ1年半、脂の乗った素晴らしいコンビネーション、アンサンブル、インタープレイ、メンバー個々のアドリブソロ、選曲の妙、洒脱なCannonnballのMC、全てにバランスの取れたコンサートです。
1曲目はCannonballのオリジナルにしてタイトル曲Nippon Soul (Nihon No Soul)、和風のテイストは全く存在しない曲です。多分来日直前、若しくは来日中に曲が出来上がってタイトルがまだ決まっておらず、「大歓迎で迎えてくれた日本の聴衆へサービスしなきゃ。ついこの間出たHorace (Silver)の新作もThe Tokyo Blues(62年11月リリース)なんてタイトルだったし。Too Much Sake, Ah! Soなんて日本語のタイトルの曲も入ってたな、我々も負けちゃいられないよ。Tokyo Soulじゃあ二番煎じだからNippon Soulってのはどうかな」とばかりにこのタイトルを付けたのでしょう、ジャズご当地ソングの走りです。でも内容は相当ユニークなブルース・ナンバーに仕上がっています。「アメリカのミュージシャン、名前はCannonball Adderleyが書いた新曲をお送りします」と上機嫌のCannnonball自身によるありがちなギャグMCがあり(笑)、アメリカのジャズグループによる名誉ある最初の東京でのライブレコーディングを行う旨を伝え、実際日本フィリップス〜フォノグラム社がレコーディングを担当しました。曲がスタートします。曲の4小節目の1, 2拍目に可能な限り全員参加によるキメと吹き伸ばしがテーマ〜アドリブの最中毎コーラス入り、メチャメチャインパクトのあるアクセントになっています。管楽器によるメロディをピアノが受け継ぐのもジャズの基本であるコール・アンド・レスポンスを感じさせます。テーマが終わり、Sam Jonesのベースラインが浮き立ち、少しソロっぽいラインが聴かれます。Paul Chambersを彷彿とさせるタイムのOn Topさ、気持ち良いですね。ソロオーダーが決まっていなかったので途中からソロが始まったのかと思いきや、その後のアドリブ奏者全員アクセントの入る4小節目でソロを終えているので、ソロの開始は5小節目からという事になり、Jonesは先発ソロまでのリリーフだった訳です。その後5小節目から先発Natのコルネットソロ、やはりソロオーダーはしっかり決まっていたのですね。彼の正統派然としたスタイルには爽快感があります。続くソロはCannonball、それにしても物凄い音色です!これで生音が小さかったとは到底信じられません!強力にマイク乗りの良い音、効率の良い楽器の鳴らし方、アルトサックスの低音域から中音域を中心に、前人未踏の図太い音色、艶があってコクがあり、音の輪郭もくっきり、タンギングも絶妙です!常にクリエイティヴなチャレンジ精神を忘れないフレージングのアプローチはBenny Carterの流れを汲んでいますが、One & Onlyなテイストを確立しています。因みにCharlie Parkerの具体的な影響は殆ど感じられません。当時の彼の使用楽器ですがマウスピースはMeyer Bros. New York5番、リードはRicoかLa Voz、楽器本体はKing Super 20 Silversonic。彼のMCでの話しっぷりに通じる滑舌の良さ、明快な発音、聴衆を常に意識したはっきりとしたメッセージを受けて、ここで思い浮かぶのがサックス奏者Gerald Albrightのプレイです。実際AlbrightはCannonballのスタイルに影響を受けていると感じますが、正確なタンギングに裏づけされた超滑舌の良いフレージング、はっきりとしたメッセージ性、大好きなサックス奏者の一人です。余談ですがある日僕が楽器店に買い物で立ち寄ったところ、知っている従業員の女性が店の電話で話をしています。どうやら国際電話のようで会話にちょっと困ったような雰囲気です。僕を見かけるなりいきなり「達哉さんは英語喋れますよね?」「挨拶ができる程度ですよ」「私よりもきっと話をすることができるでしょうから、電話を代わってもらえませんか?」「マジっすか?」電話を代わると「Hi!, this is Gerald Albright!」いやはやびっくりしました。何に驚いたかと言えばAlbrightが電話口の向こうにいる事よりもその発音と滑舌の良さにです!彼の演奏をまさに耳にしているかの如く、猛烈な早口にも関わらず明瞭なイントネーションとはっきりとした話し方、電話は相手の顔が見えないので細かいニュアンスが伝わり難いはずですが、Albrightは相手に何を伝えたいかが明確に根底にあるので、実に聞き取り易い英語です。電話の内容は購入したマウスピースを交換したいという事だったと従業員嬢に伝えましたが、Albrightの英語が分かり易かっただけなのに彼女には僕が英語をよく喋れる人と思われました(爆)。Albrightとの電話で話し方と滑舌、喋る内容のメッセージ性は確実に演奏に出るものだと強く実感しました。話が些か横道に逸れてしまいましたが、素晴らしいCannonballのアルトに続くのはLateefのフルートソロです。声を出しながらフルートを演奏するのはRoland KirkやJeremy Steigを彷彿とさせますがLateefの方が寧ろ先駆者かも知れません。Cannonball, Nat, Lateefの3管は全く異なった個性を表現してCannonball Sextet内でしっかりと自分達の役割分担を行なっています。ソロのラストの「吹き切った!」感がハンパなく、オーディエンスのアプラウズが然もありなんです。続くJoe Zawinulのソロ、オーソドックスなスタイルに専念しています。この人はソロプレイヤーというよりも常にコンポーザー、オーガナイザー、プロデューサー的な立ち位置で音楽に向かっているように聴こえます。Cannonballとはウマがあったのでしょう、61年からおよそ9年間バンドに在籍していました。
2曲目、さあお待ちかねCannonball On Stageです!♩=330! 超高速アップテンポのナンバー、本作白眉の名演Cole PorterのEasy To Love、冒頭ドラムスとアルトのデュエットで始まりテーマに入りますがなんと艶やかでブリリアント、猛烈なスピード感でいてリズムがどっしりしているのでしょう、そして何しろ色っぽいのです!63年の東京でこんな演奏が行われていたなんて、日本人として大変名誉な事です!未聴の方はとにかく一度耳にして下さい!僅か3:46の収録時間にジャズの醍醐味を全て感じることが出来る演奏です!テーマやソロ中で聴かれる管楽器のアンサンブルもカッコ良くて適材適所です。一人吹きっきり状態でリズムセクションが悲鳴をあげる寸前にドラムスと4バースが始まりますが、物凄い集中力でCannoballと丁々発止のやり取り、その後ラストテーマに無事到達しました。レギュラーグループだからこそなし得ることが出来る超絶ハイクオリティな演奏です。

3曲目はLateefのオリジナルThe Weaver、CannonballのMCによるとメンバー全員の友人New York在住のLee Weaverに捧げられたナンバーだそうです。こちらもブルース、エキゾチックなイントロから何ともユニークなテーマに突入します。Weaverさんの雰囲気のようなサウンドの曲だそうですが、一体どんな人物なのでしょうか、興味が尽きません。先発Cannonnballのソロは絶好調ぶりを遺憾なく発揮しています。続くLateefは野太い音色でフレージングに時折マルチフォニックス(重音奏法)や効果音的なオルタネート・フィンガリング、タンギングを駆使し、他の二人には無い危なさ、異端ぶりを聞かせてくれます。Natのソロの実に安心して聴けるスインガーぶりが場面を活性化させています。彼のフレージングにはDizzy Gillespieの影響も感じます。オーソドックスなスタイルでの演奏に徹するZawinul、後に展開するWeather Reportの片鱗を微塵も感じさせません。ここまでがレコードのSide Aです。
4曲目はAdderley兄弟の共作によるジャズタンゴTengo Tango、新曲でNatのネーミングだそうです。速いテンポのタンゴですが曲の中身はこちらもブルース、当時のジャズメンはジャズに様々なリズムを持ち込もうと健闘していたように感じます。Cannonballのゴージャスにしてアグレッシブなソロのみフィーチャーされた短い演奏ですが曲想、メロディ、リズム、ソロのバックグラウンドの構成、いずれにも緻密な工夫がなされ印象に残る演奏に仕上がっています。

5曲目はZawinulとJonesの二人をフィーチャーしたDuke Ellingtonの名曲Come Sunday、Zawinulのアレンジが光ります。このような6人編成の大所帯バンドでピアニスト、ベーシストのみにスポットライトを当てられるのはレギュラーバンドならではの特権です。曲の終わりの方に出てくる3管によるハーモニーがまさにEllingtonサウンド、そしてアンサンブル内で聴こえるCannonballのアルトの音色からEllington楽団の名リードアルト奏者、Johnny Hodgesばりの芳醇なビブラートやニュアンスを感じます!美しい!
6曲目アルバムの最後を飾るのはLateefのオリジナルで彼の仲の良い友人John Coltraneに捧げたBrother John、アップテンポ3拍子のややモーダルな雰囲気の曲です。Lateef自身のoboeによるメロディ奏がフィーチャーされます。ジャズサックス・プレイヤーでoboeを巧みに扱えるのはこの人くらいでは無いでしょうか?Coltraneのソプラノサックス演奏を感じさせますが、中近東近辺のエスニックサウンドのようにも聴こえます。その後Natのソロ、最低音域を使ってトロンボーンの様な音色を聴かせます。Cannonballも曲想に相応しいアプローチを取るべく健闘していますが、本作収録63年はColtraneのモーダルなサウンドが熟した頃、その演奏を聴いてる耳にはこの演奏はハードバッパーが頑張ってモーダルサウンドに挑戦しているように聴こえてしまいます。確かに餅は餅屋ですがCannonballがMiles Bandでの盟友Coltraneの音楽を、日本のファンに自分なりの形で披露したかったのかも知れません。
2018.09.16 Sun
今回はピアニストBobby Timmonsの1966年録音、リリース作品「The Soul Man!」を取り上げたいと思います。
66年1月20日録音Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey Prestige Label
1)Cut Me Loose Charlie 2)Tom Thumb 3)Ein Bahn Strasse (One Way Street) 4)Damned If I Know 5)Tenaj 6)Little Waltz
p)Bobby Timmons ts)Wayne Shorter b)Ron Carter ds)Jimmy Cobb


35年フィラデルフィア生まれのTimmonsは50年代からサイドマンとして実に様々なミュージシャンと共演作を残し、60年代に入ってからはリーダー作を数多く発表しましたが74年、アルコールとドラッグの過剰摂取に起因する肝硬変で、38歳の若さで生涯を閉じました。時代も良かったのですが50年代〜60年代初頭、全盛期のジャズシーンを全速で突っ走っていたミュージシャンの一人です。
タイトルやジャケットデザインが恥ずかしい位に何とも60年代を反映しています(笑)。参加メンバーを知らずしてしかも未聴での場合、間違いなくソウル、ジャズロック系のアルバムと取り違えてしまう事でしょう。しかし本作の目玉は何と言っても59~61年に共に在籍していたArt Blakey And The Jazz Messengersでの共演者、名テナーサックス奏者Wayne Shorterの参加です。彼の演奏により作品のクオリティ、品位が桁違いに高まりました。Timmonsの他の作品には無い人選です。TimmonsはJazz Messengersに58年から61年まで在籍し、Moanin’, Dat Dereといったオリジナル曲を提供しレコーディング、結果空前のヒットを果たし、それに伴いJazz Mesengersも名門バンドへと転身します。Shorterの方も59年から64年まで在籍しバンドの音楽監督も務め、Jazz Messengersの音楽性を高めるべくやはり自身のオリジナルやアレンジを提供しました。TimmonsはJazz Messengersを離れてから自己の作品をトリオ編成中心に発表、一方ShorterはJazz Messengers脱退直後64年にMiles Davis Quintetに参加しMilesの作品「Miles In Berlin」「Live At The Plugged Nickel」「E. S. P.」を録音、自身のリーダー作としては「Night Dreamer」「JuJu」「Speak No Evil」と言った代表作を立て続けにレコーディングし、彼の第10作目「Adam’s Apple」録音直前(2週間前)が本作のレコーディングです。「Hey, Wayne, ジャズロック調のオリジナルがあったら今度のレコーディングの時に持って来てくれないかい?」「Oh, yeah, Bobby, 自分のアルバムでレコーディング予定の新曲があるから持っていくよ」みたいなノリの会話があって(爆)、Tom Thumbが収録されたと推測できますが、Shorter自身のリーダー作でTom Thumbは翌67年3月10日録音 3管編成による「Schizophrenia」に収録される事になり、それまではお預けになりました。もしかしたらジャズロックのテイストが強い作品「Adam’s Apple」でTom Thumbを演奏する予定だったとも考えられますが、本作「The Soul Man!」でのレコーディングしたテイクを鑑みて、Shorterは「Tom Thumbはカルテットよりも大きな編成で演奏するのが良さそうな曲なので、今回はレコーディングせずに次作に持ち越そう」と判断したかもしれません。いずれにせよTom Thumbの収録はこの作品のハイライトの一つではあります。


Timmons, Shorterの二人はもともと音楽的志向にかなりの違いが感じられますが、Jazz Messengersに在団していた頃はさほど気にならない、と言うかクインテット〜セクステットの編成の大所帯、そしてBlakeyお得意のナイアガラ・ロールに紛れて(笑)その差異が目立つことはありませんでした。でも本作のようにカルテット編成では顕著です。更に6年以上の時の経過がスタイルや演奏レベルの違いをくっきりと明らかなものにしています。意欲的なリーダー作、ジャズ史に残るような名盤を立て続けに発表し、同時にMiles Davisの薫陶を受けて音楽性を磨かれ、一層研ぎ澄まされた表現力を持つようになったShorter、他方その変わらぬスタイルを良しとされ、「Bobby、我々は君のその演奏を聴き続けたいんだ。スタイルが変わることなんて望んでいないよ」とでも周囲から言われていたのか、十年一日の演奏を聴かせるTimmonsとでは差が歴然です。
収録曲を見て行きましょう。1曲目TimmonsのオリジナルCut Me Loose Charlie、Ron Carterの印象的なベースライン、60年前後Miles Band在団中よりもシャープで的確なドラミングを聴かせるJimmy Cobbのシンバルレガートからイントロが始まるのは、8分の6拍子のブルースです。しかしここで聴かれるShorterのテナーサックスの音色は一体何と表現したら良いのでしょうか?猛烈な個性と存在感、誰も成し得ない唯我独尊、しかし本人はいたって自然体で音楽に立ち向かい、気負うところ無く自分のストーリーを語っています。Otto link Metal Mouthpiece 10番、Rico Reed 4番を使用しているとは到底考えられない楽器コントロールの素晴らしさ、マエストロぶりを発揮しています!一方TimmonsはShorterの個性的で、全てがクリエイティヴな演奏に平然と、いつものやり方のバッキングで答えているのは、然るべき対処法の引き出しが無いからでしょう。空疎な瞬間を感じる時もありますが、やむを得ません、寧ろShorterの演奏がくっきりと浮き上がります。
2曲目は前述のShorterオリジナルTom Thumb、可愛らしいひょうきんな曲調のナンバーです。Shorterのソロは曲の持つ雰囲気を確実に踏まえ、ジャズのアドリブの原点である即興、その瞬間での作曲を行なっているが如きです。テナーサックスのザラザラ、加えてこもった成分が特徴的な音色が、何故かユーモラスさを誘います。「Schizophrenia」でのバージョンと聴き比べてみると3管編成でのサウンドの厚みが曲想に大変マッチしていています。James Spauldingのアルトのメロディ奏とテナー、トロンボーンのユニゾンとの対比も面白いです。ワンホーンでの「Adam’s Apple」の編成拡大版が「Schizophrenia」と言えますが、曲作りやサウンドは前作よりも格段に進化しています。Shorterのテナーの音色もShorter色が一層増しています。
3曲目はCarterのオリジナルEin Bahn Strasse (One Way Street)、同じくCarterのオリジナルThird Planeにどこか似たテイストを感じるのは同じ作者だからでしょう。でもShorterのオリジナルに関しては何れもが個性的、一曲づつしっかり顔があり、似た曲風のものを探すのは困難、と言うか存在しません。Shorterのソロは何処からこのラインが出て来るのかと感心させられる、相変わらずのユニークさを発揮しています。Carterのソロもフィーチャーされていますが、いつものテイストの他に珍しくスラップのような技を披露しています。実際Miles BandではCarterのソロは殆どなく、あったとしてもソロ中にスラップを入れようものなら後からMilesに何を言われるか分かりません。うるさいオヤジが不在だとミュージシャンはリラックスしていつもとは違う演奏になるものです。60年代中頃Miles Davis QuintetがVillage Vanguard出演の際、Milesがインフルエンザに罹り欠場、Carterも同じくインフルエンザでトラにGary Peacockが出演し、Herbie Hancock, Tony Williams達とWayne Shorter Quartetという形で一晩演奏、その時の演奏テープを聞いたことがありますがThe Eye Of The Hurricane、Just In Time, Oriental Folk Song, Virgo等を演奏、メンバー全員Milesの呪縛から解き放たれた素晴らしい演奏を聴くことができました(呪縛時はそれはそれで、緊張感漲る演奏で素晴らしいでのすが)。ここまでがレコードのSide Aです。
4曲目はTimmonsのオリジナルDamned If I Know、軽快なアップテンポのスイングで演奏され、Shorterワールド全開の演奏です!感じるのはJimmy Cobbのドラミングのバネ感の素晴らしさ、Tony Williams張りのビートの提示感とでも言いましょうか、Cobb自身もMiles Bandで自分の後任のドラマーの演奏には少なからず影響を受けた事でしょう。この曲ではCarterの無伴奏ソロがフィーチャーされています。
5, 6曲目はCarterのオリジナルTenaj とLittle Waltz、Tenajはやっぱりバンド用語でJanetの逆読みでしょうか?Carterに新しい彼女が出来て名前を捧げたのかも知れませんね(笑)。ワルツのリズムでテーマやソロの途中テンポが無くなり、ルパートになったり、倍テンポでドラムスソロが織り込まれるような構成で工夫されていますが、次曲Little Waltzに何処か雰囲気が似ています。2曲とも同一の作曲者によるワルツ、曲の並びとしてはちょっと避けたかったパターンですね。Little Waltzの方は彼の69年10月録音のリーダ作「Uptown Conversation」で再演されています。

2018.09.04 Tue
今回はStan GetzとOscar Peterson Trioの豪華な組み合わせ、1958年リリース「Stan Getz And The Oscar Peterson Trio」を取り上げたいと思います。
Recorded October 10, 1957 at Capitol Studios in Los Angels Verve Label Produced by Norman Granz
ts)Stan Getz p)Oscar Peterson g)Herb Ellis b)Ray Brown
1)I Want To Be Happy 2)Pennies From Heaven 3)Ballad Medley: Bewitched, Bothered And Bewildered / I Don’t Know Why I Just Do / How Long Has This Been Going On / I Can’t Get Started / Polka Dots And Moonbeams 4)I’m Glad There Is You 5)Tour’s End 6)I Was Doing All Right 7)Bronx Blues


ドラムレスの編成にも関わらず強力なスイング感を押し出すアルバムです。以前にも述べたことがありますが、Oscar PetersonとRay Brownの双生児のように似た超On Topのリズムを、ドラマーEd Thigpenが二人を同時に羽交い締めにして、リズムが前に行き過ぎるのをギリギリ制している構図で成り立っているのがThe Oscar Peterson Trioです。陸上100m競争のスタートラインに着いた走者がスタート合図を待つ直前のエネルギー抑制感と言いましょうか。この作品でのThigpen役がギタリストHerb Ellis、素晴らしいカッティングから繰り出されるタイトなリズムがPeterson, Brownと合わさり鉄壁のスイング感を聴かせています。ここに文句なしのリズム・ヴァーチュオーゾ、Stan Getzのテナーサックス・プレイが加わることで、リズムの縦軸〜横軸がしっかりと組み合わさり、音の空間に恰もつづれ織りの織物が編まれる様相、三つ巴ならぬ四つ巴状態でタイムを聴かせる演奏に仕上がっています。タイムの良いプレイヤーは間違いなく演奏内容も素晴らしいものです。本作の充実ぶりはジャケ写ミュージシャンの笑顔に如実に現れていると言えます。さぞかしメンバー全員レコーディング中に楽しく充実した時間を過ごした事でしょう。
収録曲の内容に触れて行きましょう。1曲目I Want To Be Happy、ここでの演奏に当メンバーでのスイング感のエッセンスが全て凝縮されています。猛烈なリズムの坩堝、その中でもEllisのカッティングを聴くとギターは強力なリズム楽器なのだ、と再認識してしまいます。よく聴けば2, 4拍のアクセント付けの他にさり気なくお茶目な技を沢山披露しています。この業師のリーダー作「Thank You, Charlie Christian」はタイトル通り、尊敬する先輩ギタリストCharlie Christianに捧げられた作品です。本作でのバッキング担当の側面よりも、前面に出てソロイストとしての本領を発揮しています。
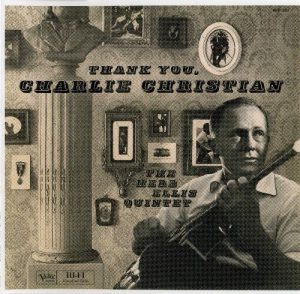
PetersonのトリッキーなイントロからGetzの付帯音まみれの素晴らしい音色でテーマ奏が始まります。う〜ん、何とカッコ良くスイングしてるのでしょう!演奏が始まったばかりなのにこの時点で既に納得してしまいます!この位の速さのアップテンポでリズム、ビートの要がドラムスのトップシンバルやハイハットではなく、フルアコ・ギターのカッティングとは実に見事です!勿論その分野の名手でなければやり遂げる事はできませんが。テーマ部の最後のブレークでのピックアップ以降、ベースがそれまでの2ビートから4ビート〜スイングに移ります。はじめの1コーラスはピアノのバッキングはお休み、Ellisのカッティングが繰り出すビートの独壇場です。2コーラス目途中からピアノのバッキングが始まりサウンドが厚くなりますが、その間ずっと続くGetzのソロのリズミックでメロディアス、巧みなフレージング、その展開に舌を巻いてしまいます!Getzの最後のフレーズを受け継いでPetersonのソロが始まります。ピアノを楽々と弾きこなし、鳴らしているのが手に取るが如く伝わります。ピアノを弾くために生まれて来たかのような恵まれた体格、迸るゴージャスさ、生来のテクニシャン。そして8分音符の滑舌、グルーヴに独自のものがあるスタイルはArt Tatum, Nat King Coleの直系ですが、ワンアンドオンリーなテイストを確立しています。その後再びGetzのソロが始まりますがPetersonのソロにインスパイアされたのか、やり残した諸々を的確に披露し更にスイングしています。ラストテーマは再び2ビートフィールに戻り、エンディングの仕掛けにも工夫がなされ、テナーのHigh F#音(Getzの使用楽器ではフラジオ音です)、メジャ−7thの音で終わっています。
3曲目は5曲連続のバラード・メドレー、参加ミュージシャンが一人ずつフィーチャーされます。メドレ−1曲目はGetzの演奏でBewitched, Bothered, Bewildered、この人はバラードが異常なくらい上手ですね、素晴らしい!フェイザーがかかった如きスモーキーな音色、意表をつくメロディフェイクで1コーラスを歌い切ります。続く2曲目EllisをフィーチャーしたI Don’t Know Why I Just Do、16小節ほどの短い演奏です。そしてPetersonの出番、How Long Has This Been Going Onを饒舌さと切なさを混じえて聴かせてくれます。次はBrownのピチカート演奏によるI Can’t Get Started、とても「言い出しかねて」とは思えないハッキリとした、むしろ「仕切りたがり」屋のメッセージを持ったプレイです(笑)。メドレー最後はGetzの再登場でしっかりと締めています。曲はPolka Dots And Moonbeams、テナーの上の音域を生かしたハスキーな語り口、グリッサンドやハーフタンギングを用いつつ美の世界を徹底的に表現しています。
ここまでがレコードのSide Aになります。
4曲目もバラードI’m Glad There Is You、冒頭EllisとGetzのDuoでメロディが演奏されますが、Getzはここでも信じられない程のイマジネーションでメロディを、更にドラマッチックに奏でています。本当にこの人のバラード演奏はいつも聴き惚れてしまいます!他のプレイヤーとは違う別な特殊成分が鳴っているので、何かがテナーサックス楽器本体の中に施されているのでは、とまで考えてしまうほどの音色です!サビをEllisに任せ、ギターの最後のフレーズをBrownがキャッチして反復、「おっ!」とばかりに一瞬出遅れて途中からGetzも参入(これは二人とも凄い瞬発力です!)し、メロディに戻ってFineです。前曲のバラード・メドレーの番外編ですが、また違ったテイストを聴かせてくれました。
5曲目はGetzのオリジナルTour’s End、スタンダードナンバーSweet Georgia Brownのコード進行に基づいています。リズムセクションの仕掛けが面白いです。この曲でもEllisのギターカッティング、Brownのベースが実にグルーヴしています!テナー、ピアノ、ギターとソロが続きますが、伴奏ではあれほど気持ち良いタイムでのカッティングを聴かせるEllisですが、ソロになると若干タイムが早く、音符も短めに感じます。コンパクトな演奏時間にジャズの醍醐味がぎゅっと詰め込まれた演奏に仕上がっています。
6曲目I Was Doing All Right、Gershwinの古いスタンダードナンバーをGetzが小粋に唄い上げます。A-A-B-A’構成、サビであるBの6~8小節目、コード進行が他よりも細かく動くところで、Getzは敢えて音量を小さくしてメロディを吹いています。複雑なコード進行を聴かせるためなのか、何なのか、これはソロコーラス時のフレージングやラストテーマの同じ箇所でも行われており、元々音量のダイナミクスが半端でないGetzにして、一層さり気ない表現のコンセプトを感じます。テナーソロが1コーラス演奏され、ピアノソロが半コーラス、サビからラストテーマになり、エンディングはイントロに戻ります。力の抜けたGetzの鼻唄感覚の演奏を楽しむ事が出来ます。
ラストの7曲目はGetzのオリジナルBronx Blues、取り敢えず曲のキーだけ決めて演奏を始めた感じのラフなテイクです。特にテーマらしいメロディが無いので録音に際して手慣らしで始めたテイクかも知れません。ギターのソロからベース、ピアノ、テナーと加わって行き、各々の短いソロのトレードを繰り返して行きます。Getzのソロで終わりかと思いきや、もう1 コーラス続いてFine、他の収録曲に比べて緊張感を欠いているように聴こえます。90年CDでリリースされた際に4曲が追加されましたが、Bronx Bluesを収録するよりも、よりクオリティの高いテイクがあったと思います。例えばCD10曲目の Sunday、Ellisのギタータッピングによるバッキングが聴かれますが、これは秘密兵器、飛び道具です!全曲タッピングでは飽きてしまうかもしれませんが、1曲だけ入る事で他の曲との対比になり、スリリングなバラエティに富んだ作品に変化します。Getzのソロの途中から普通のカッティングに戻り、ピアノソロで再びタッピング、Ellisさん器用な方ですね!演奏中のPetersonの唸り声も大きくなっている気がします。という事でこの曲をラストの締めに持ってくるべきだったと感じます。