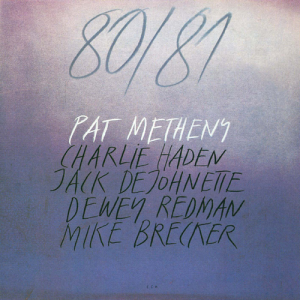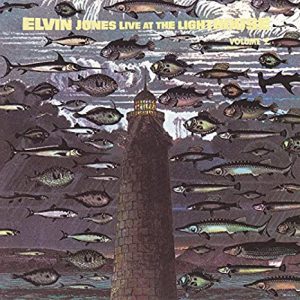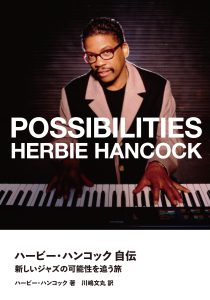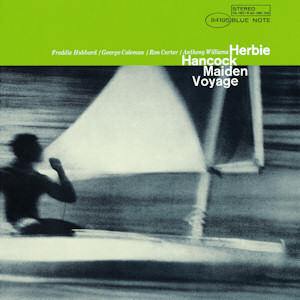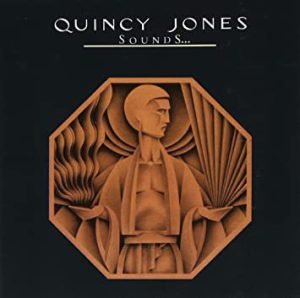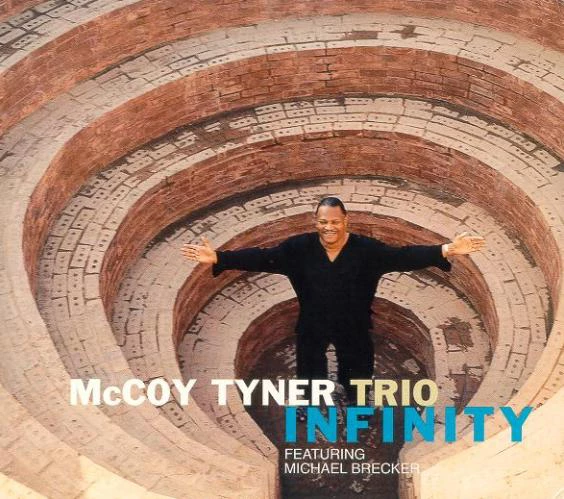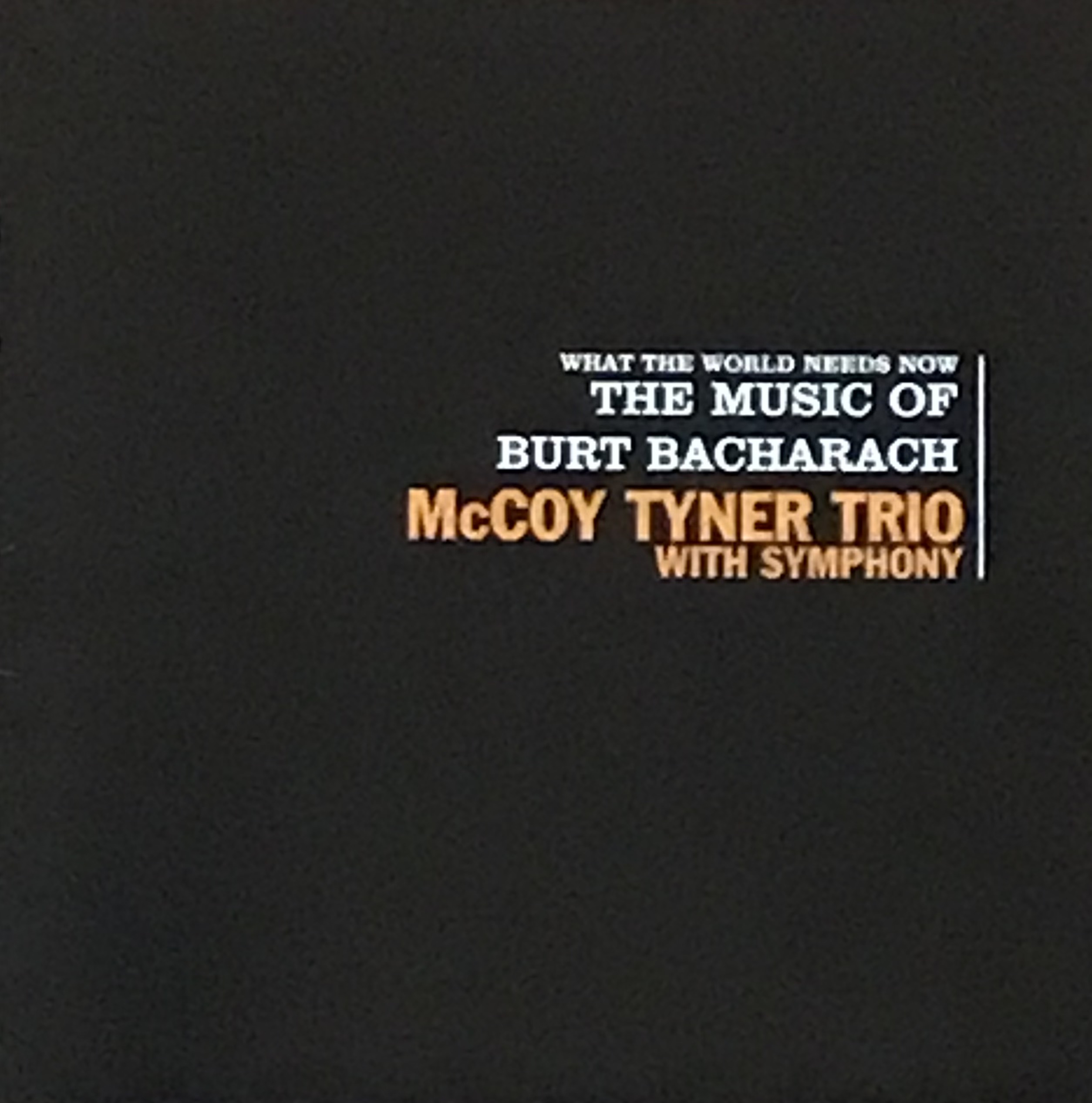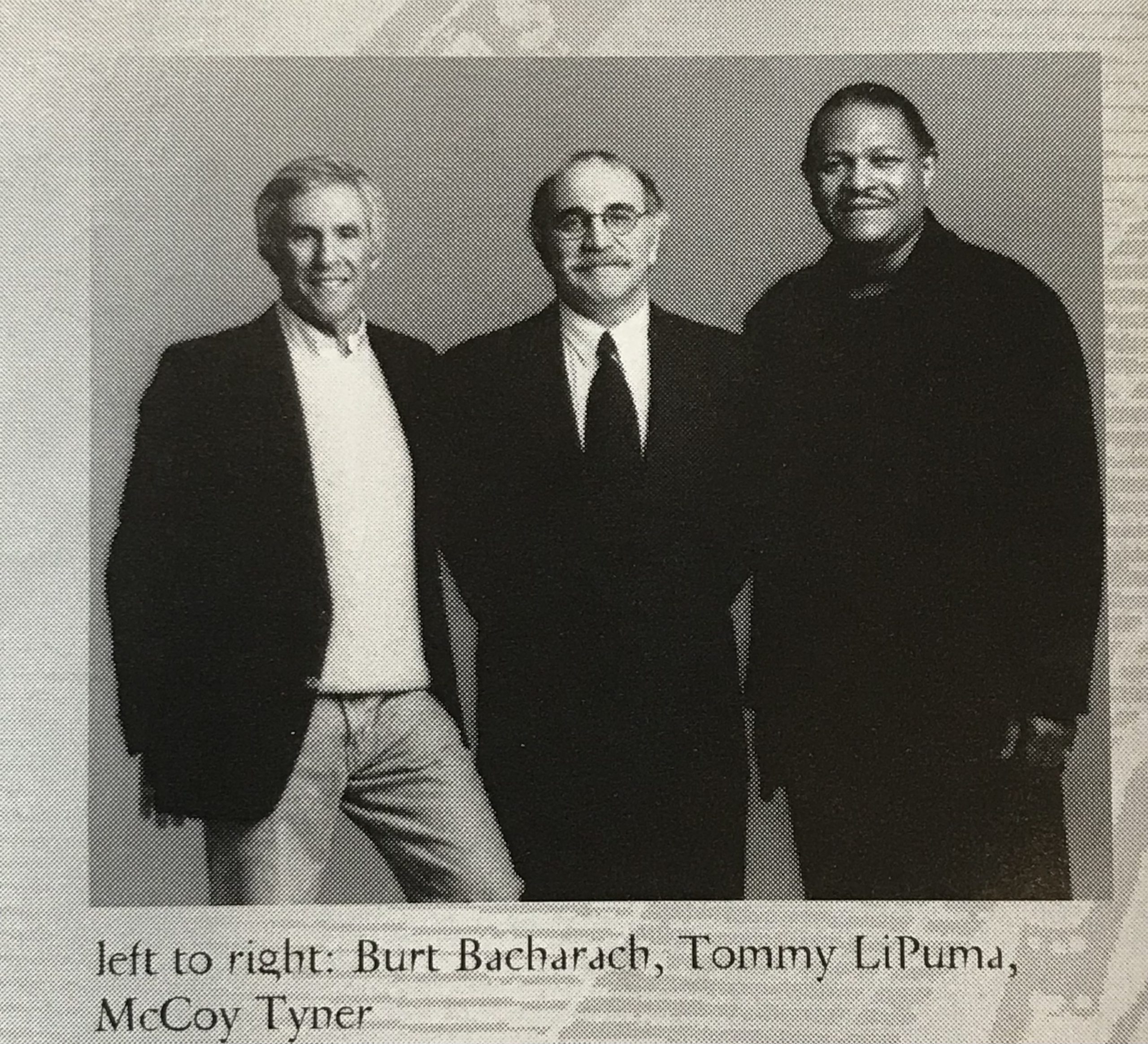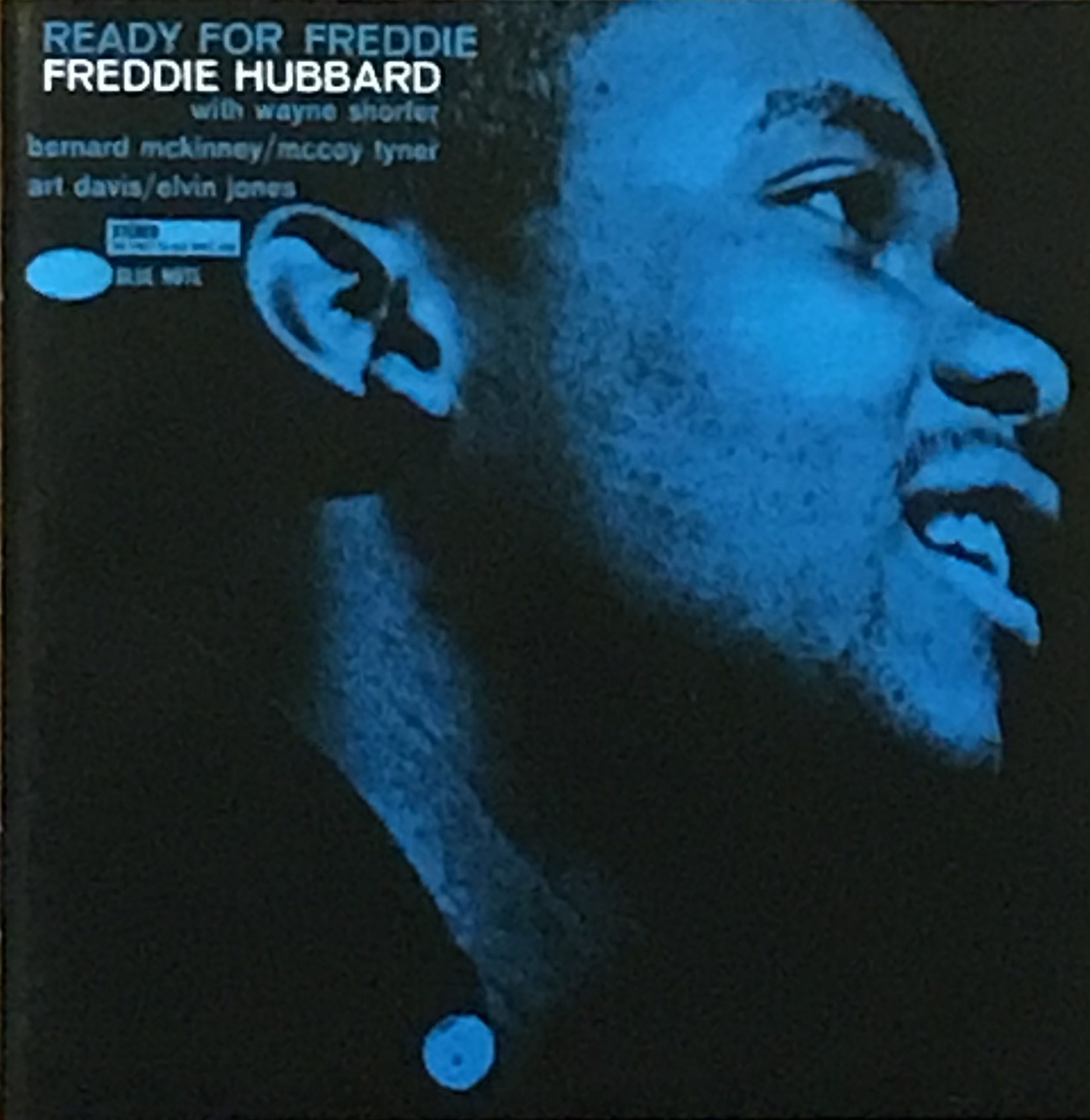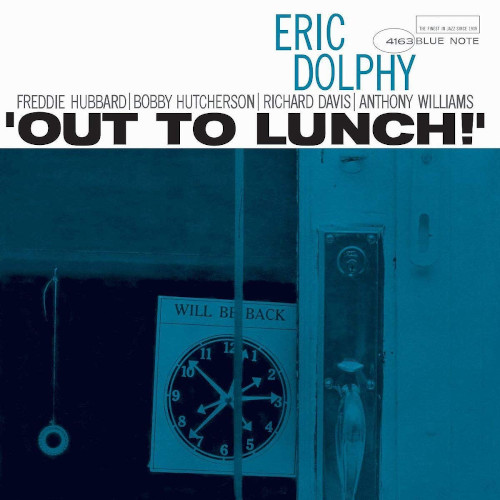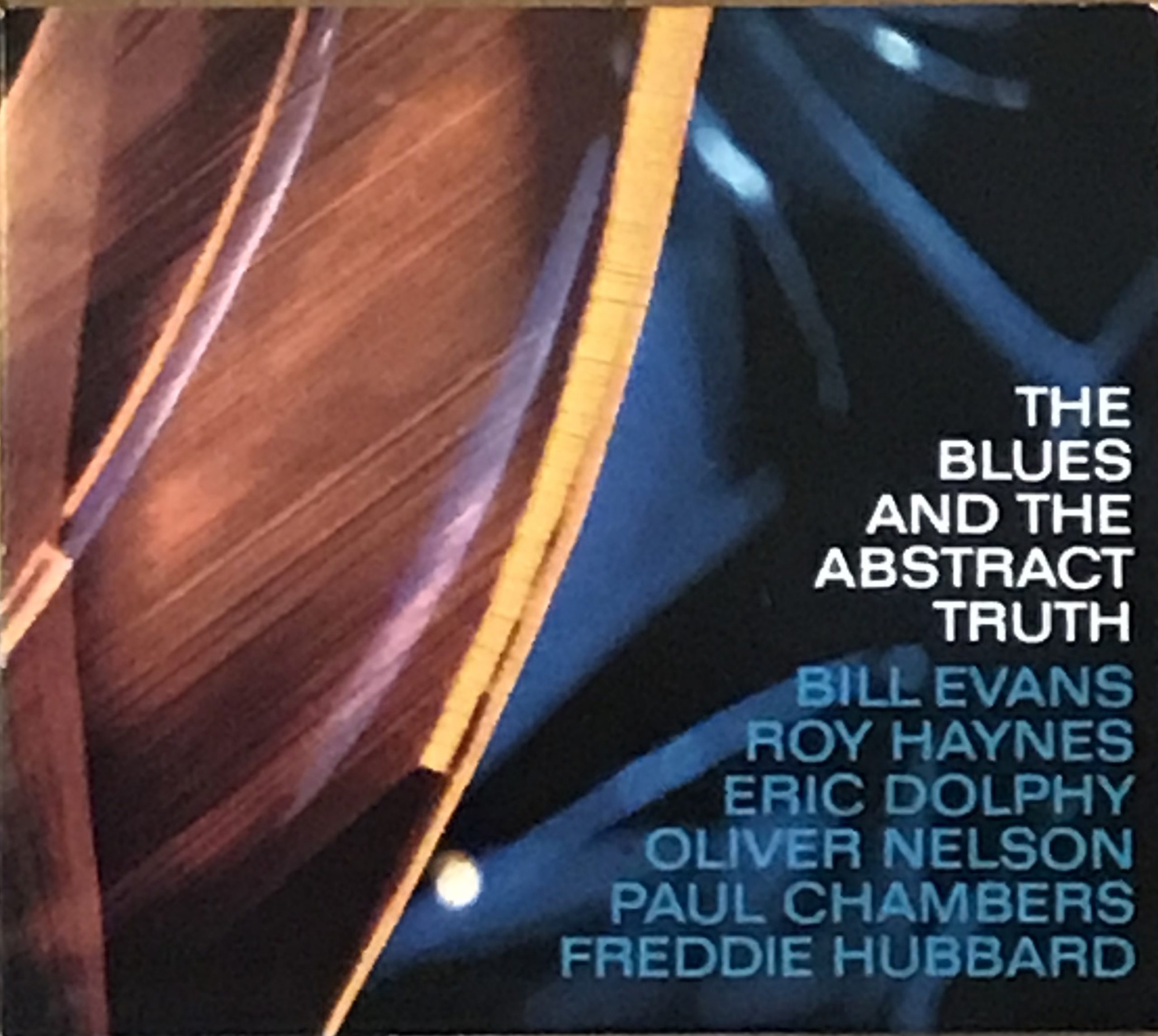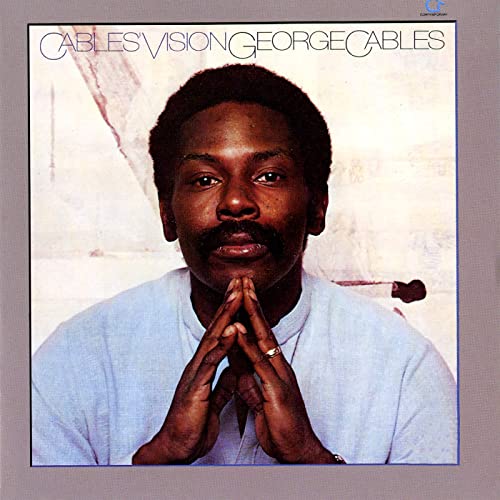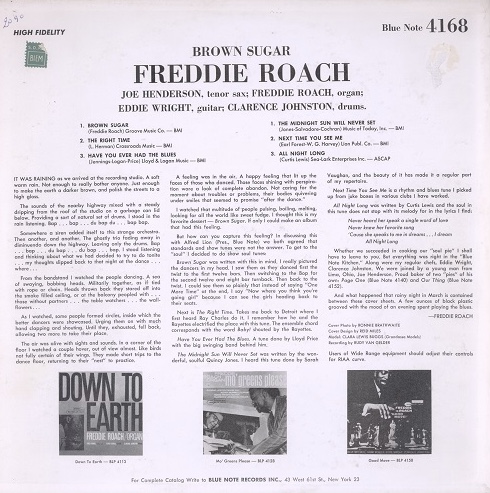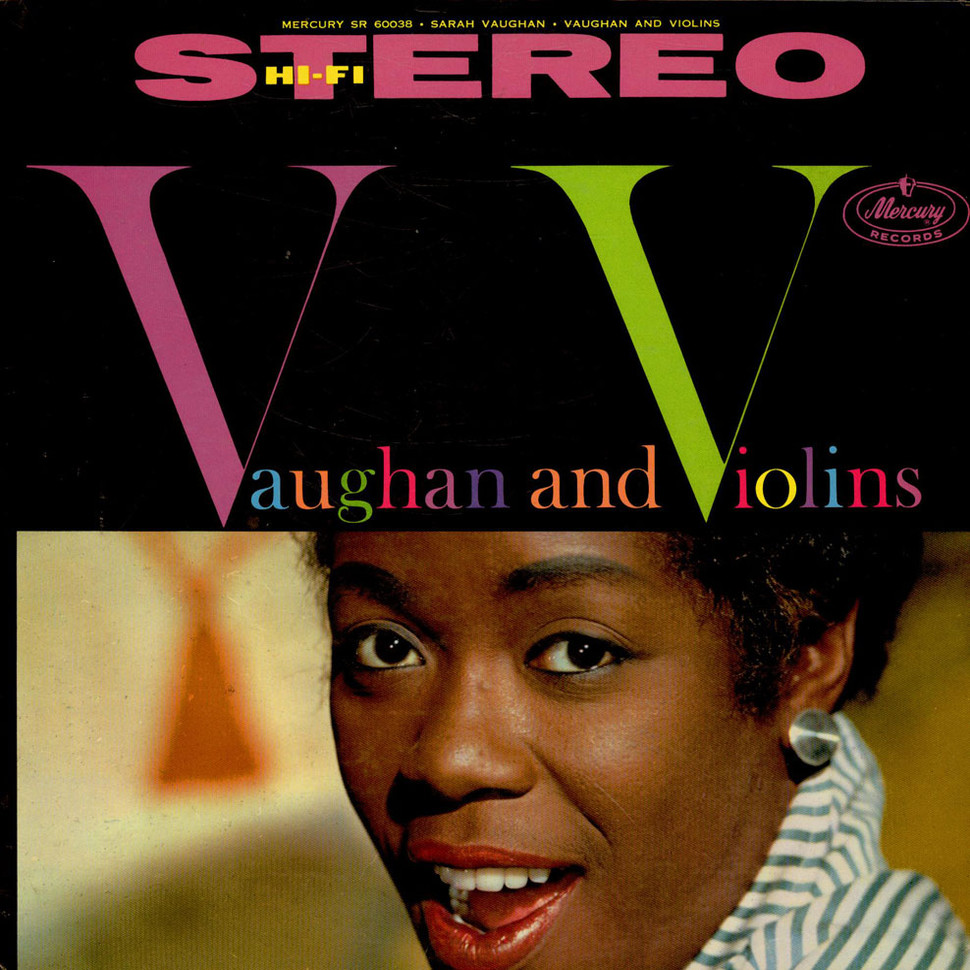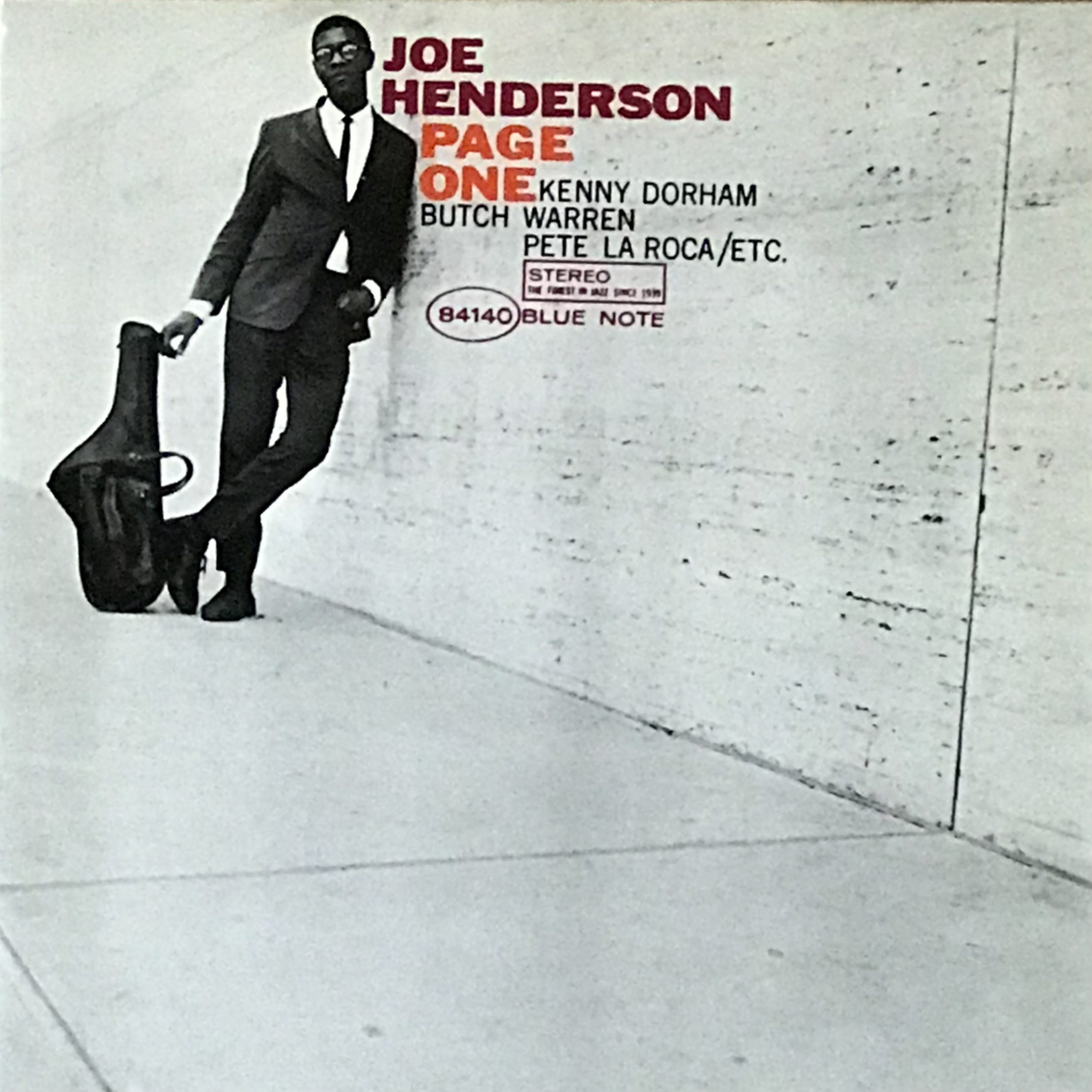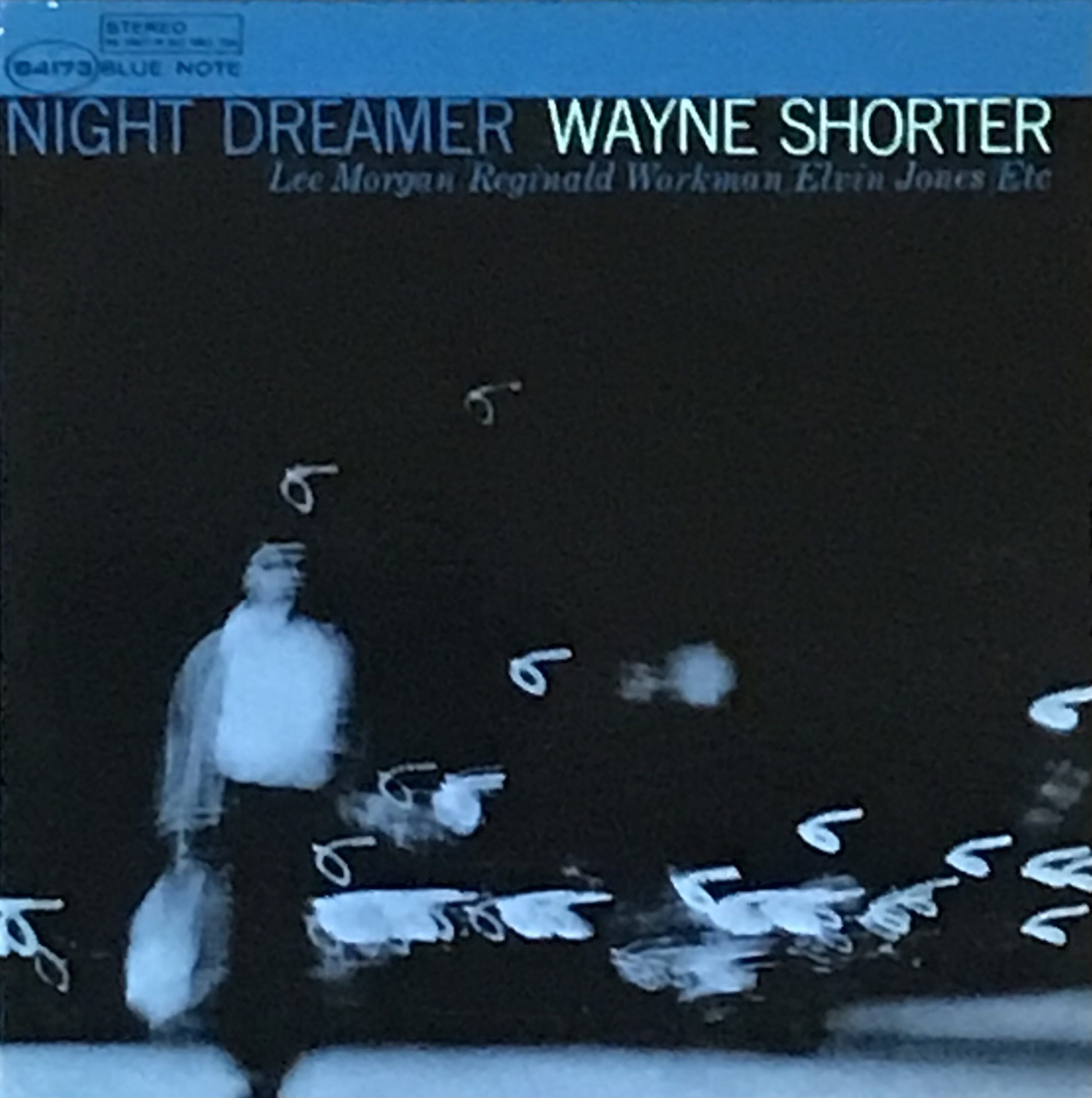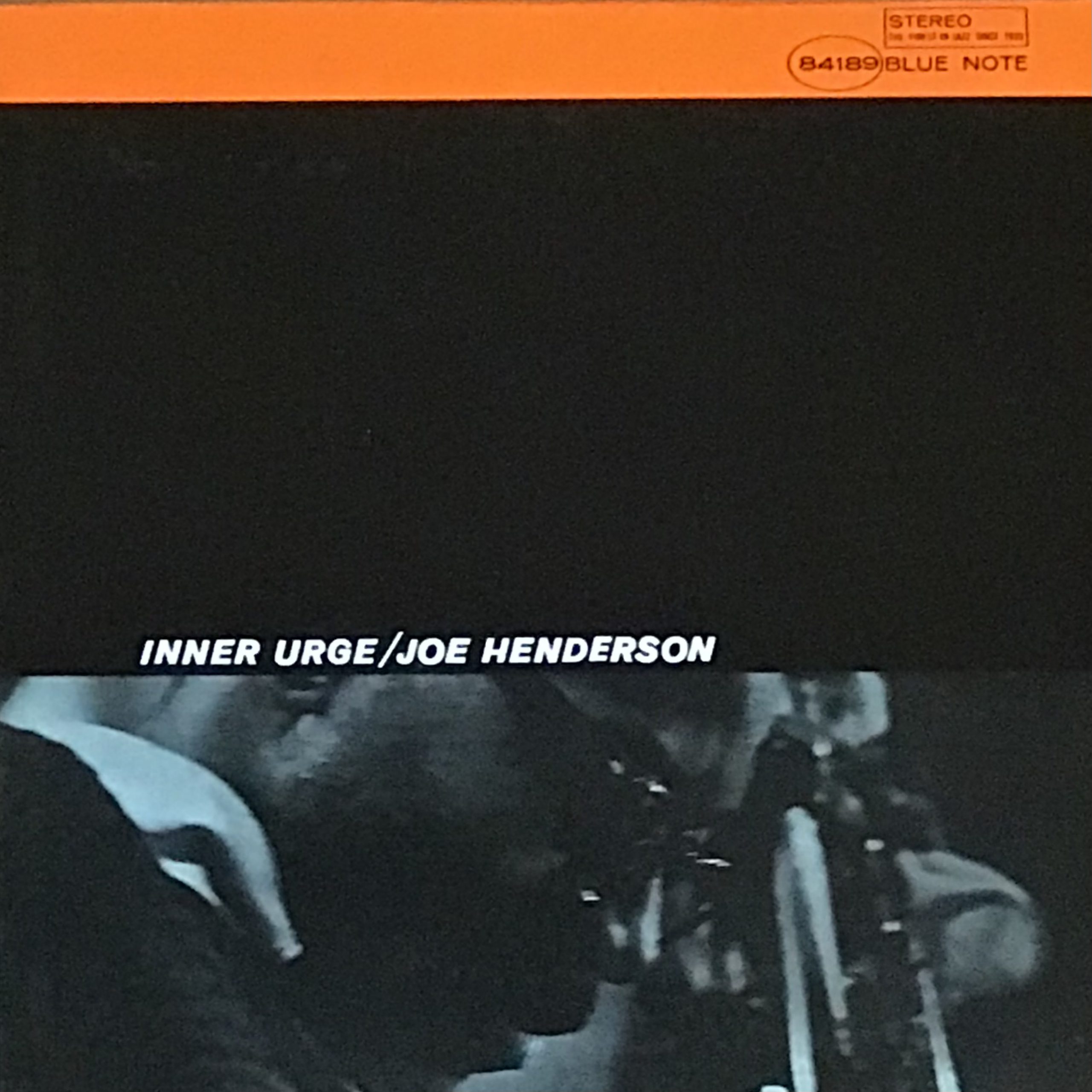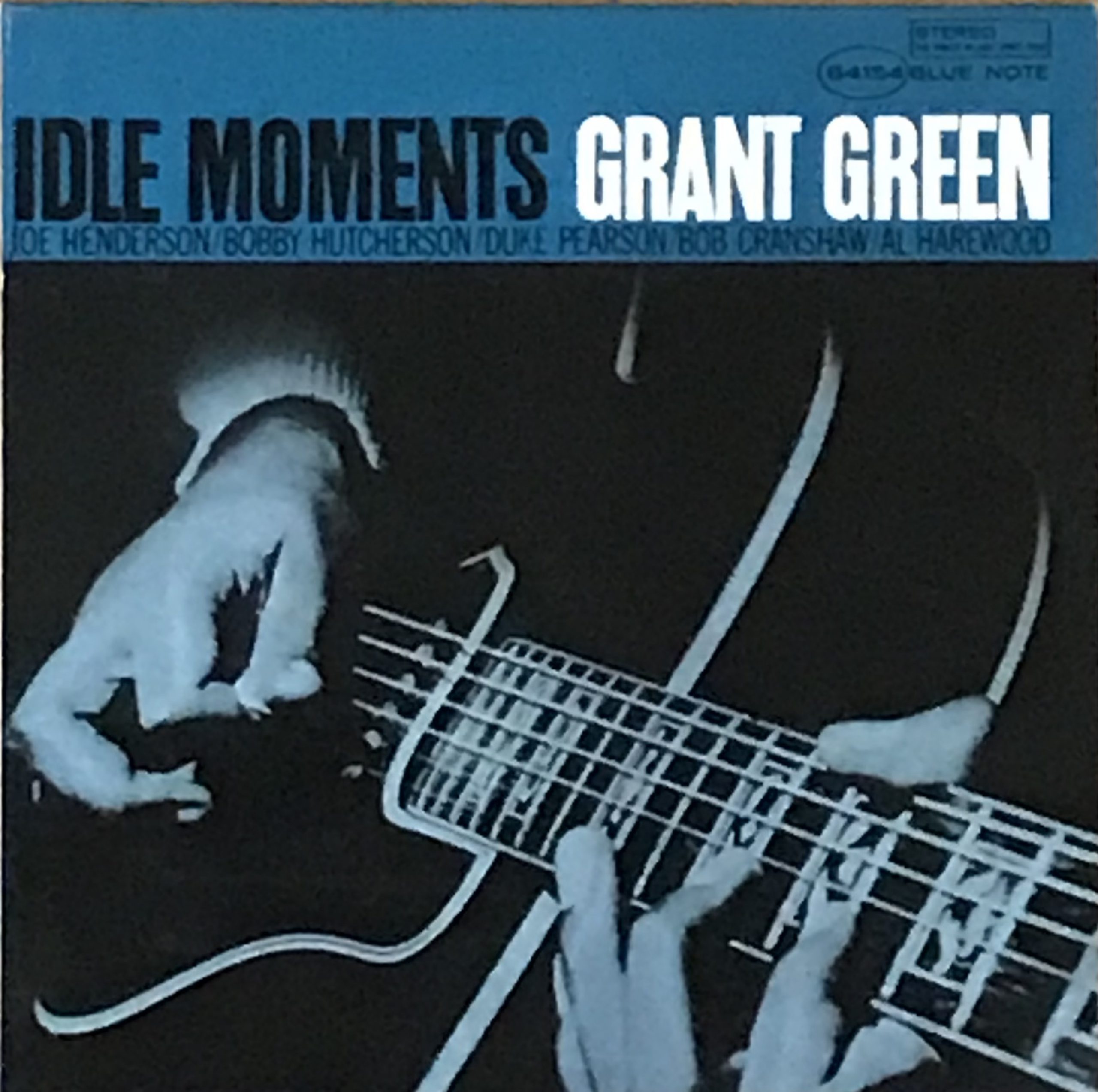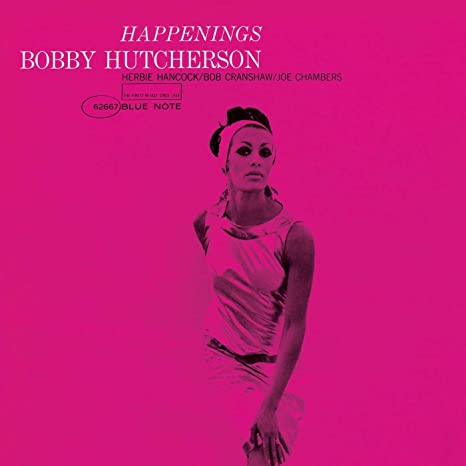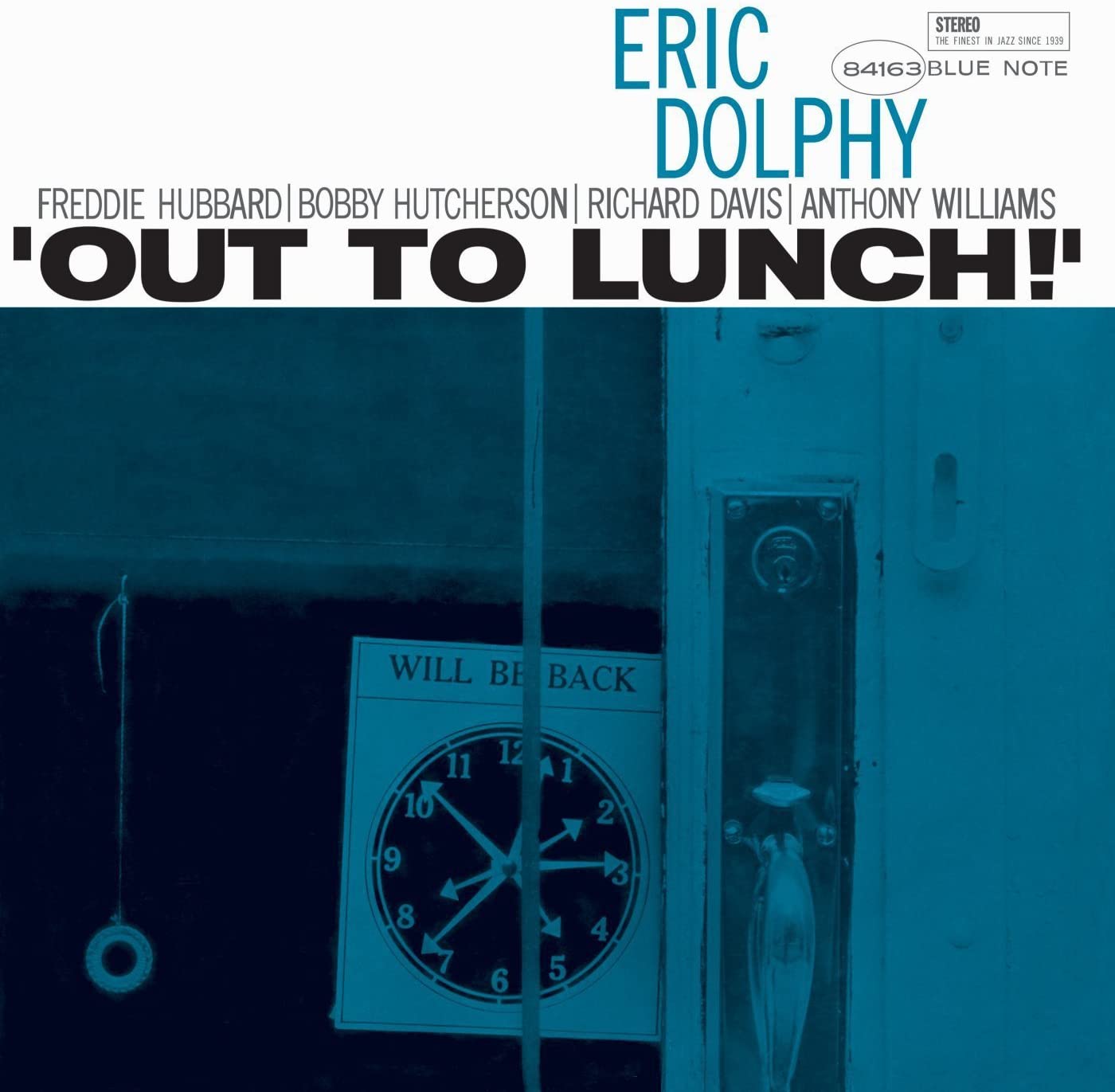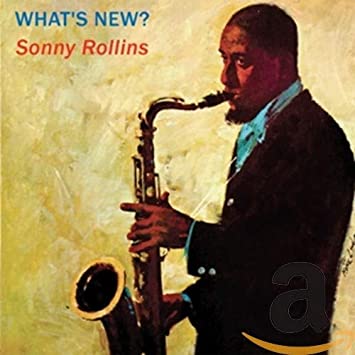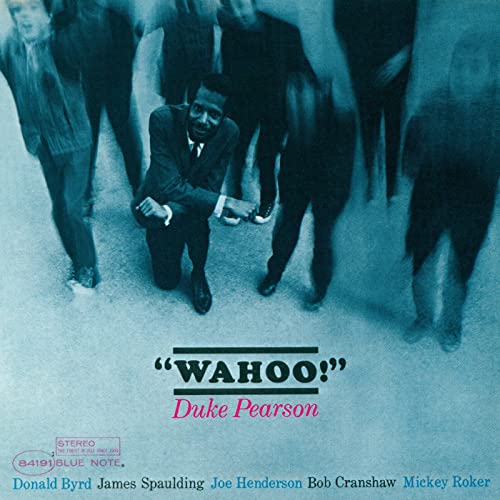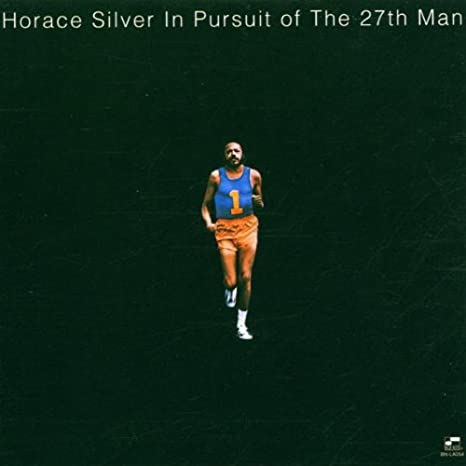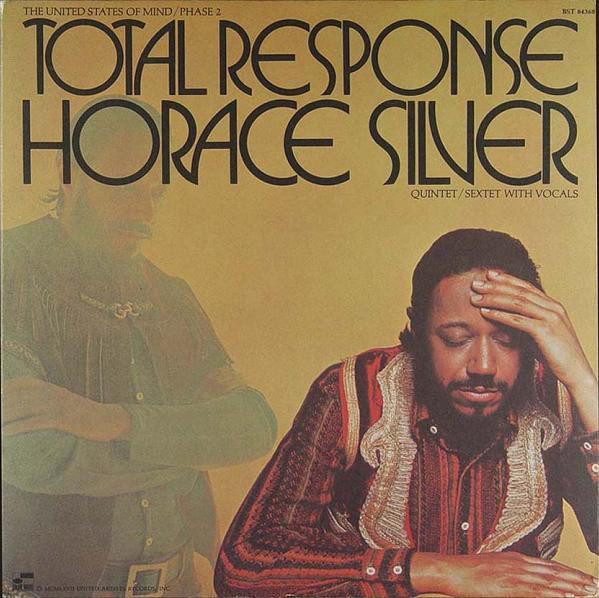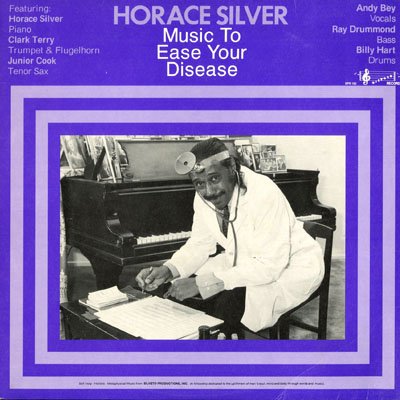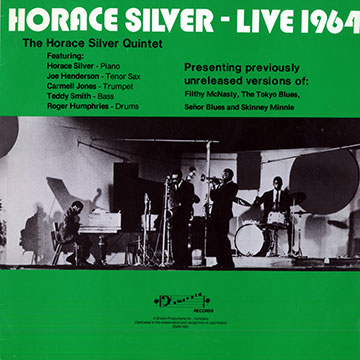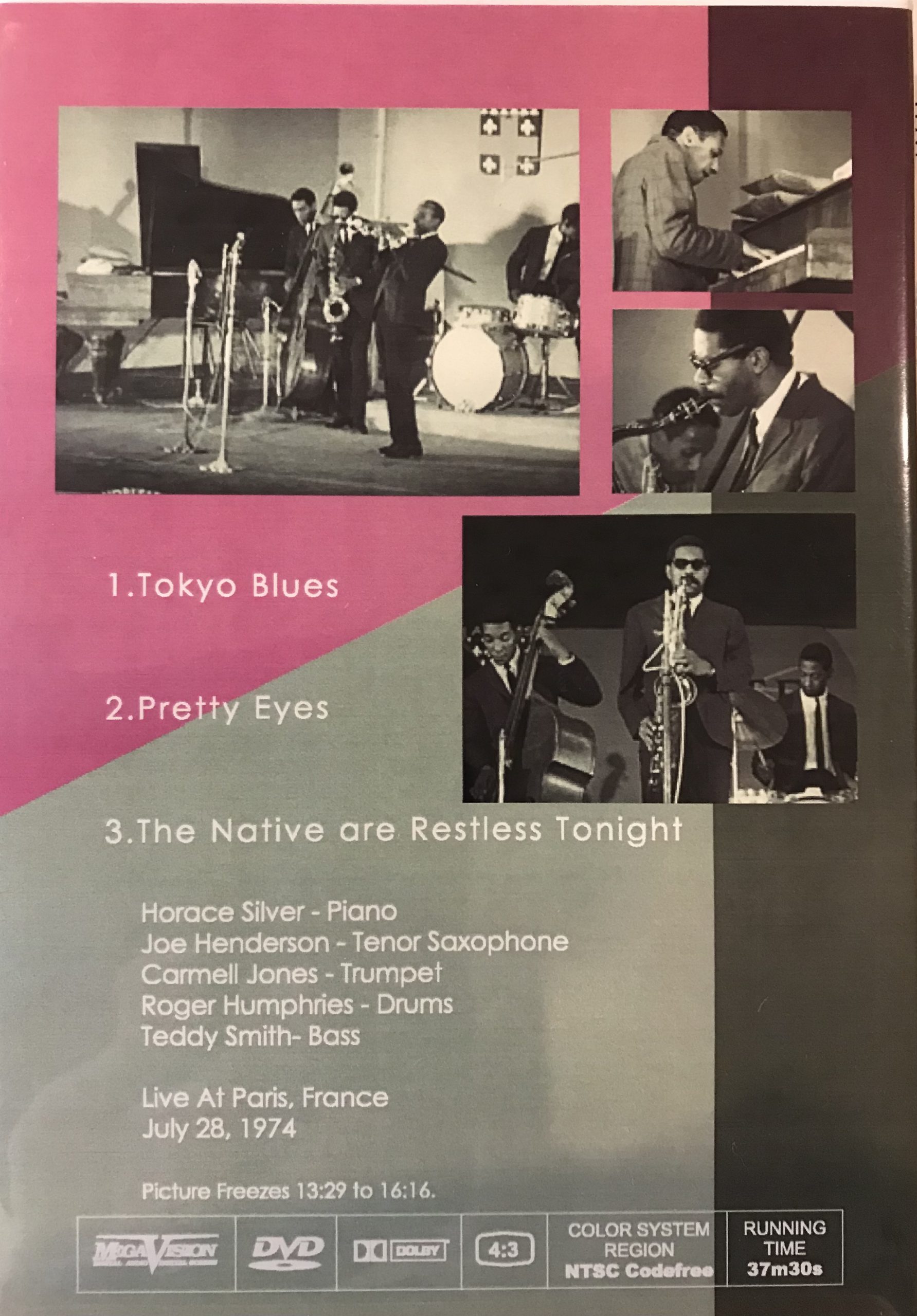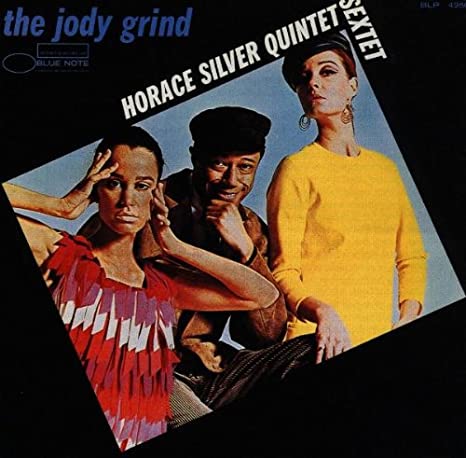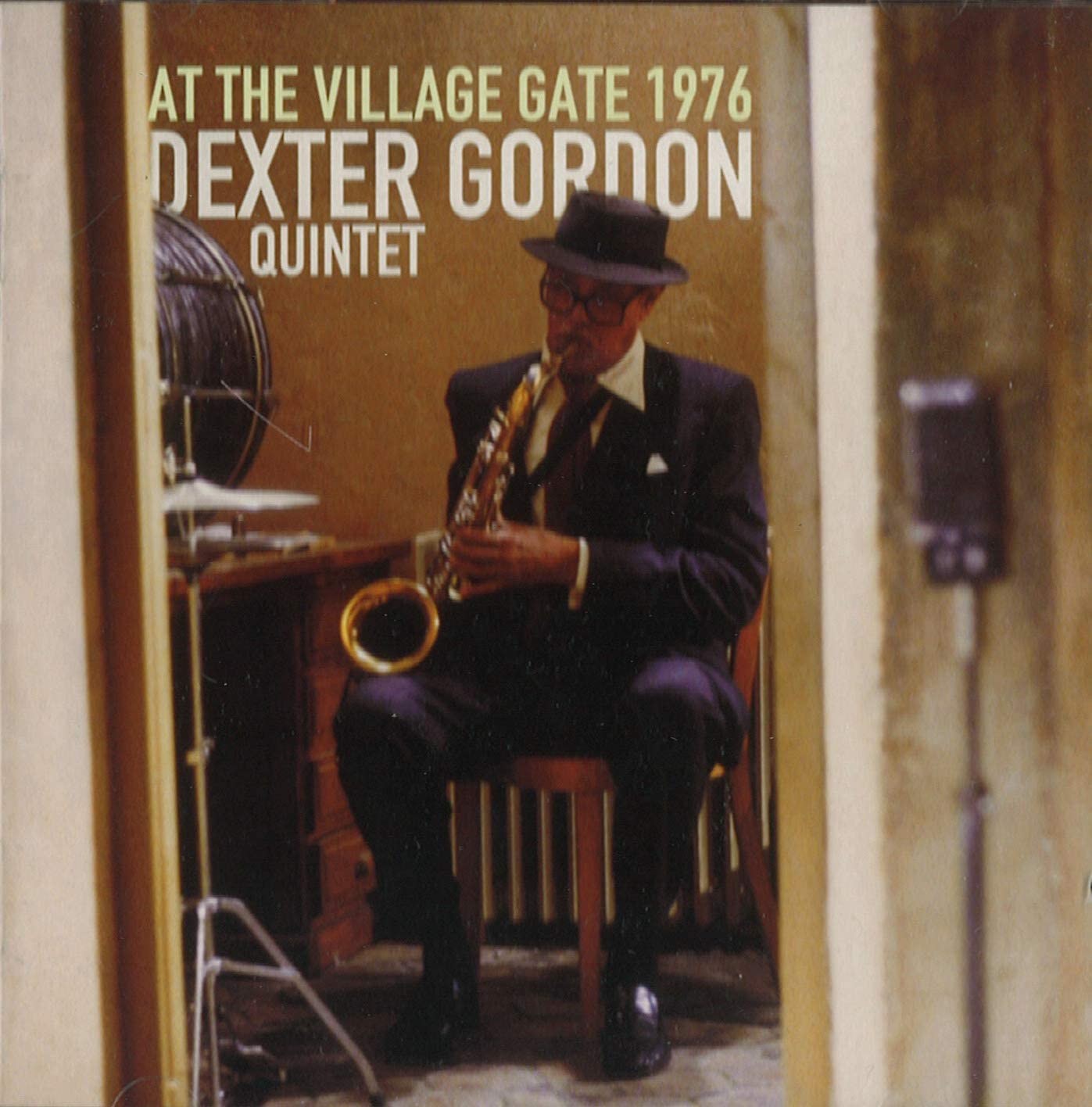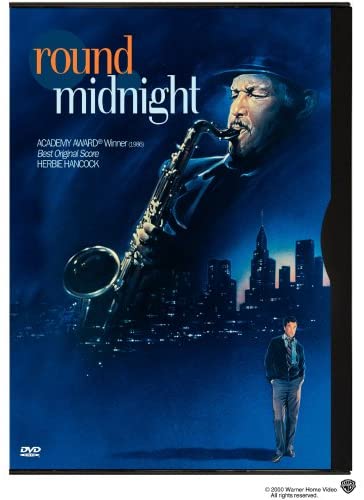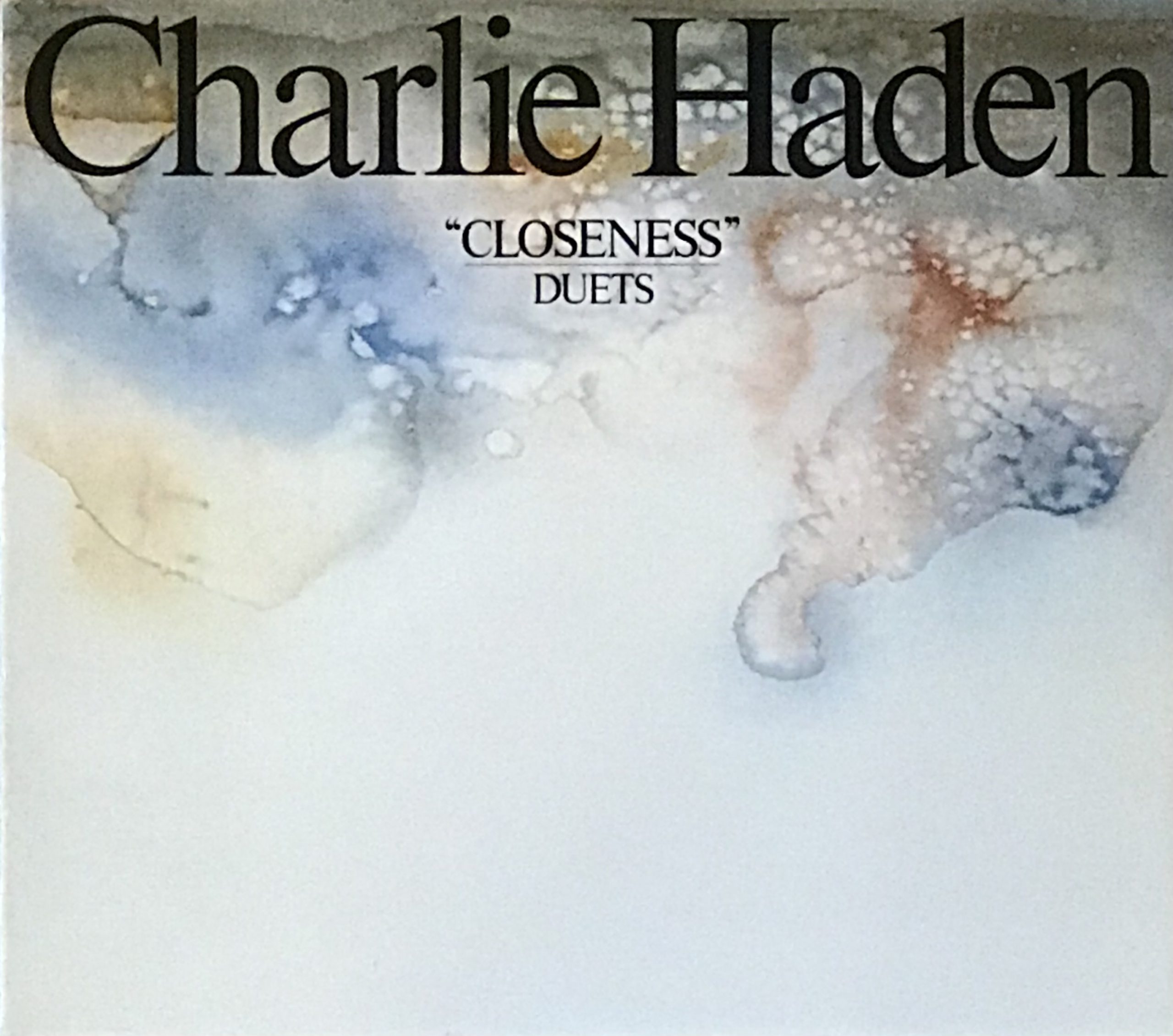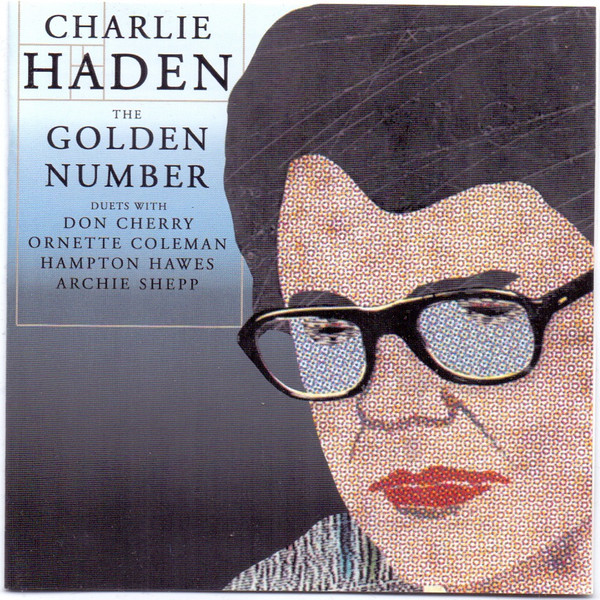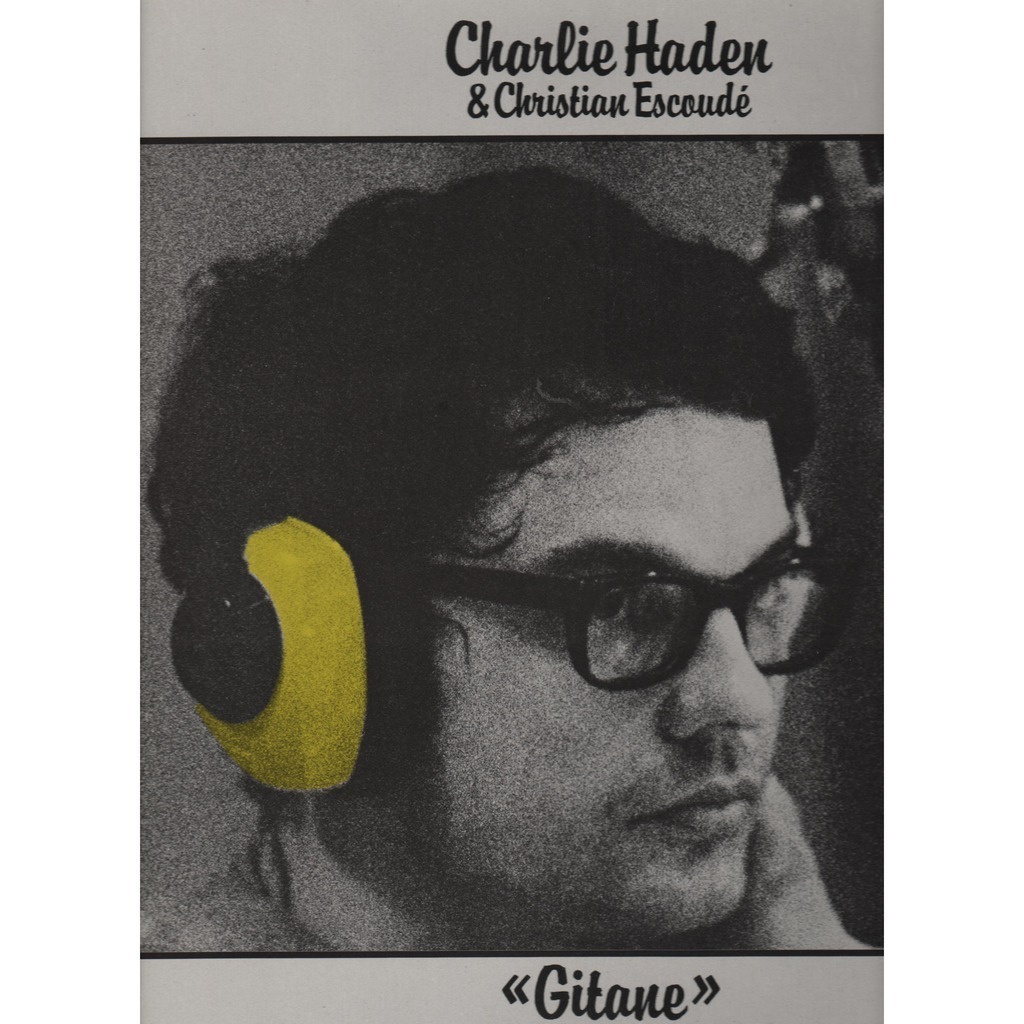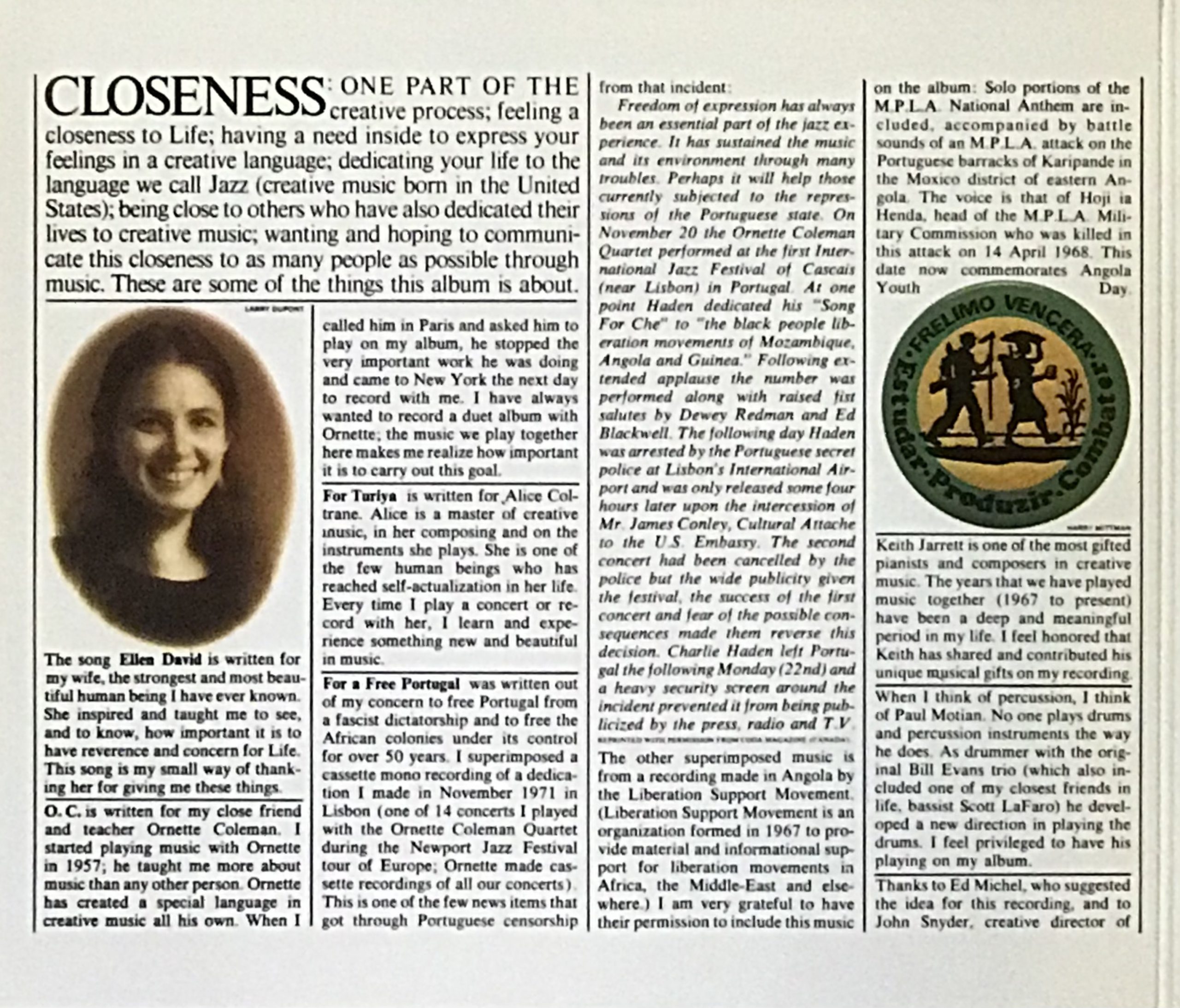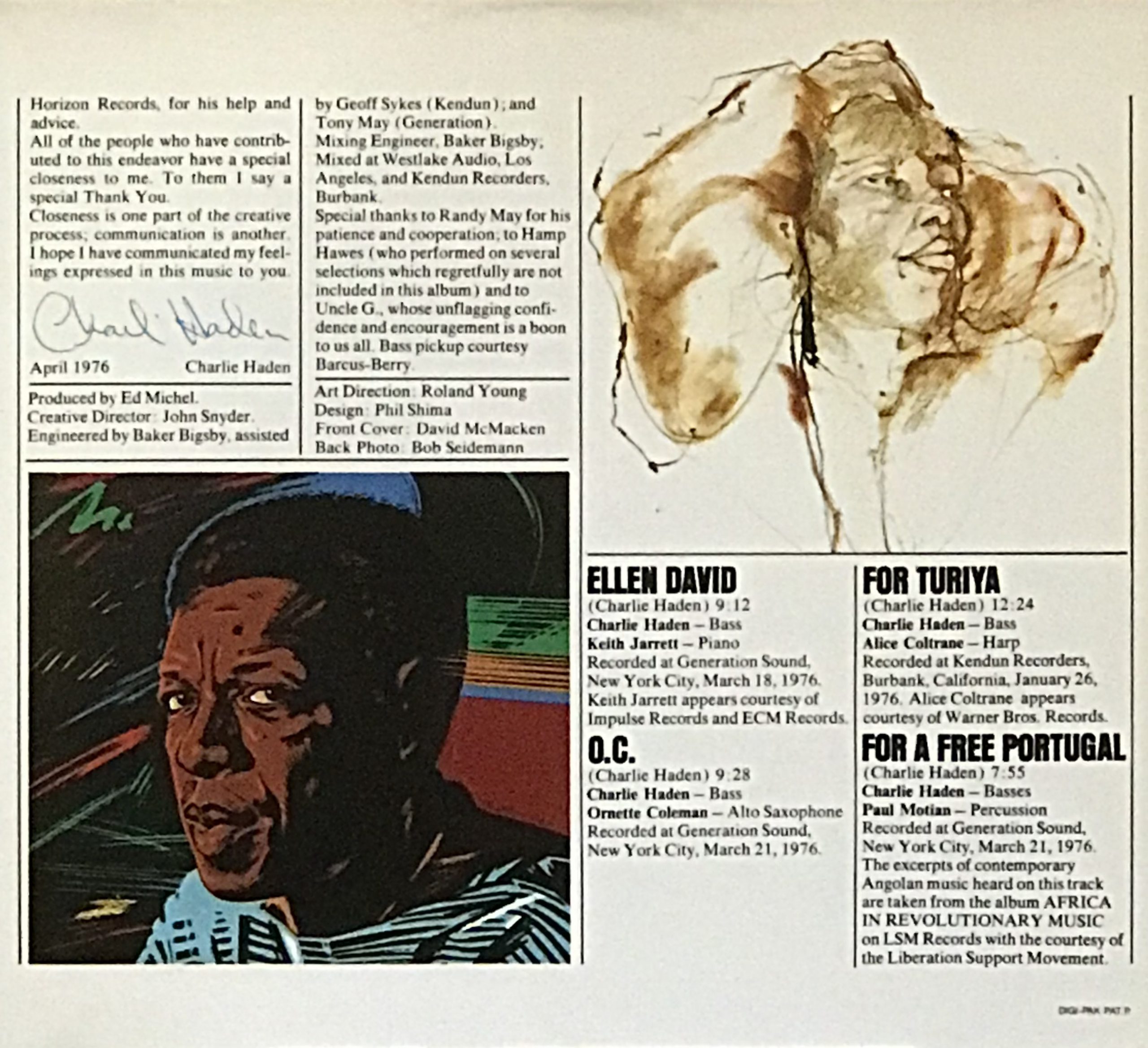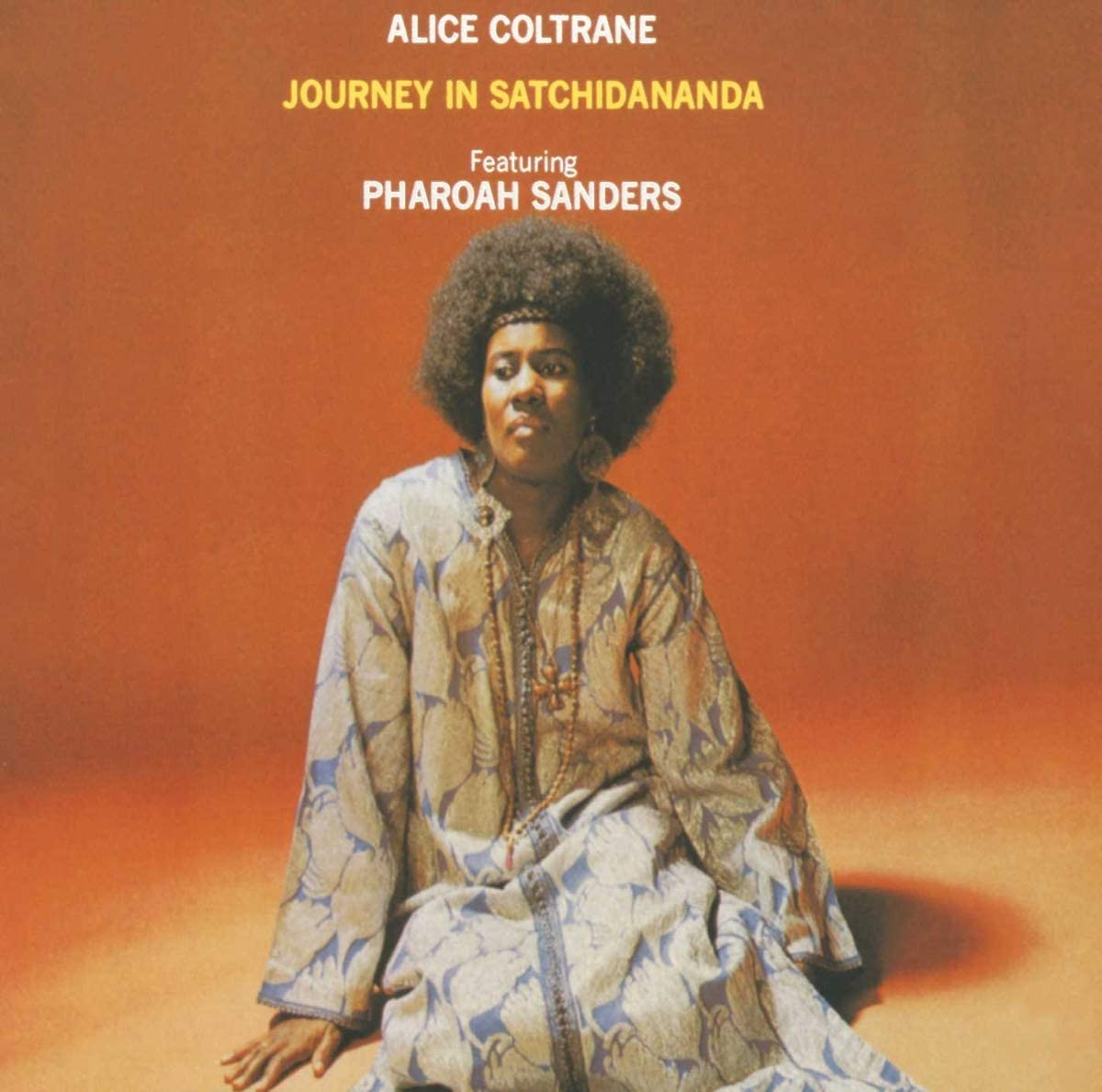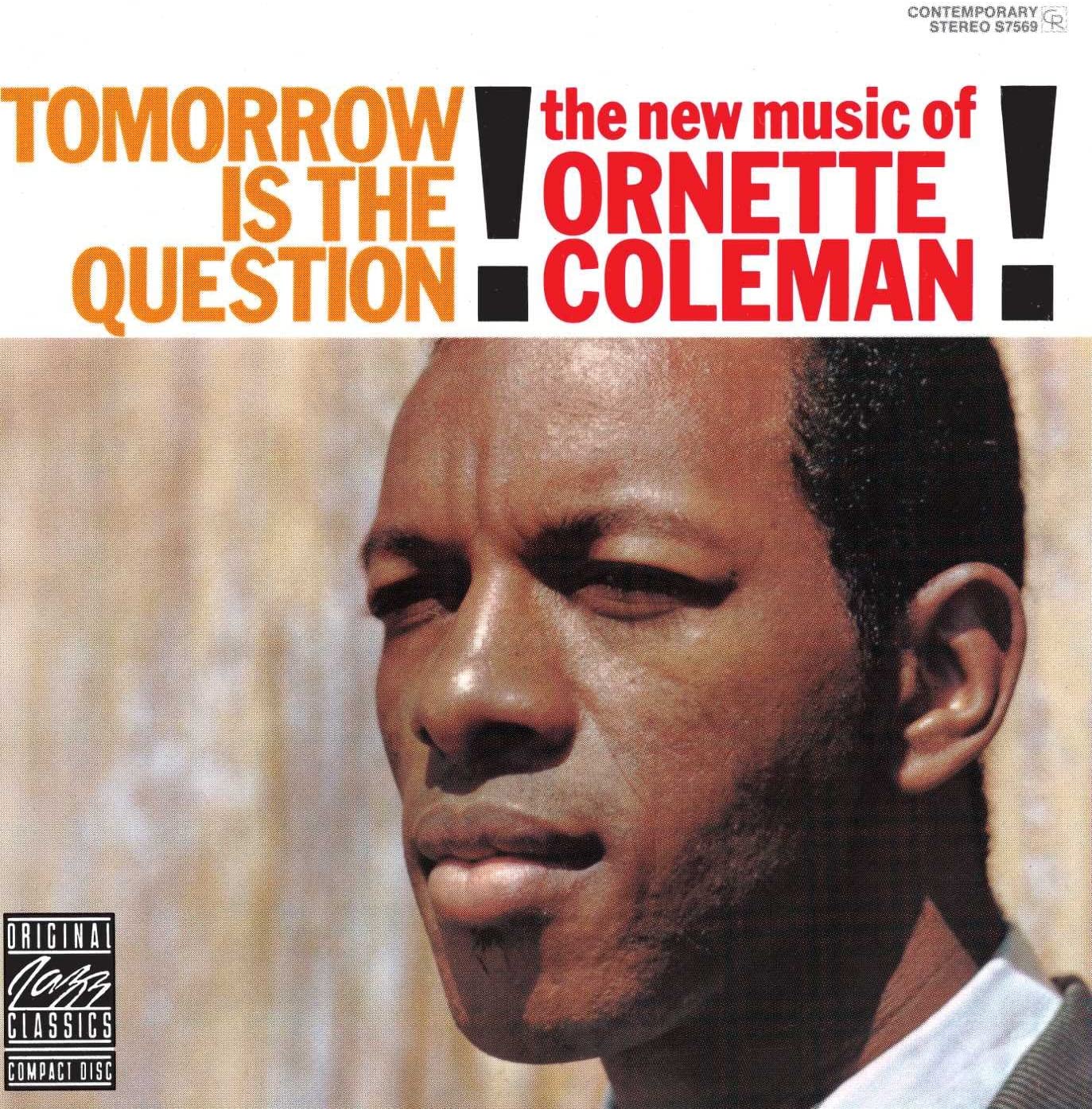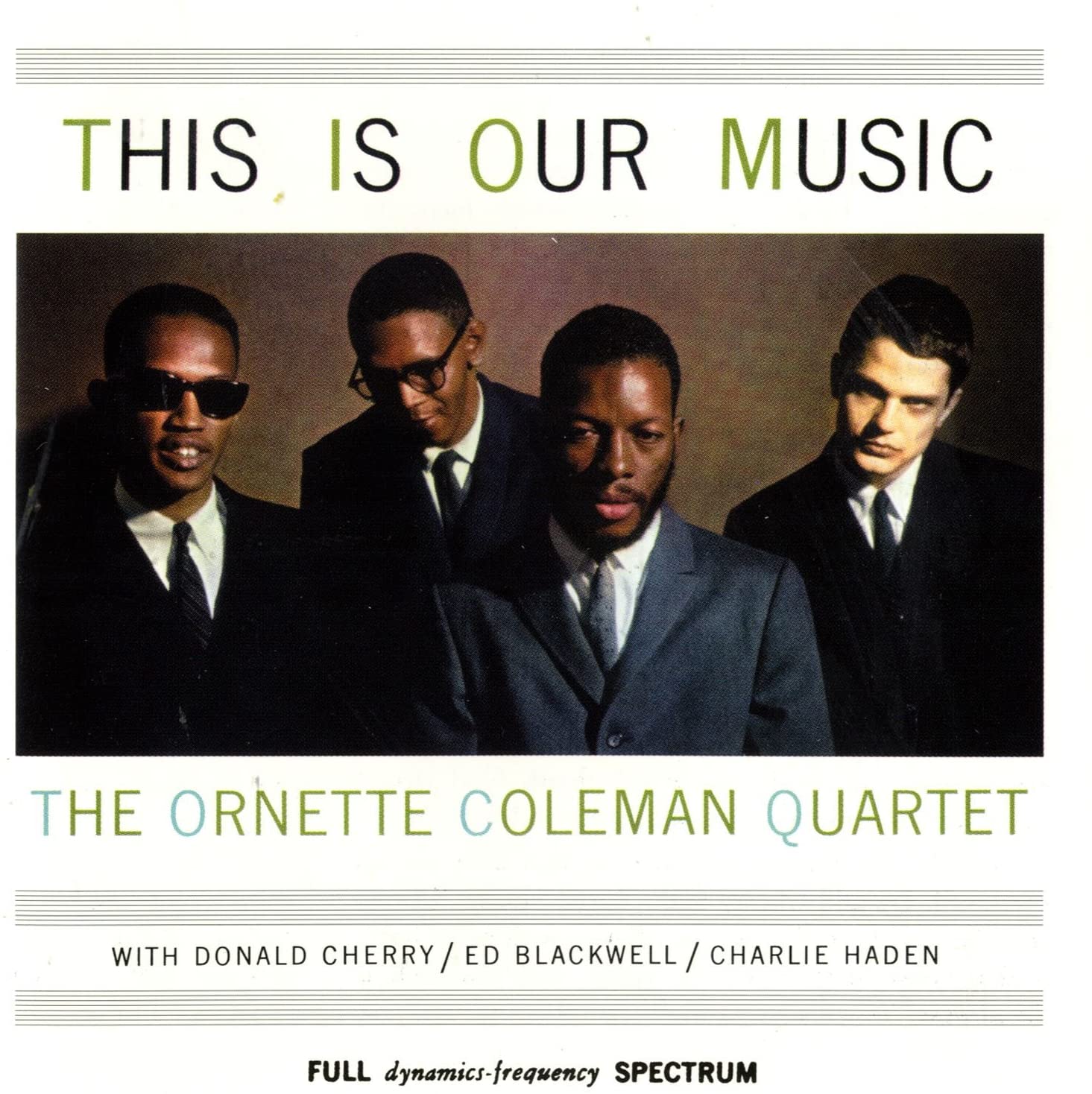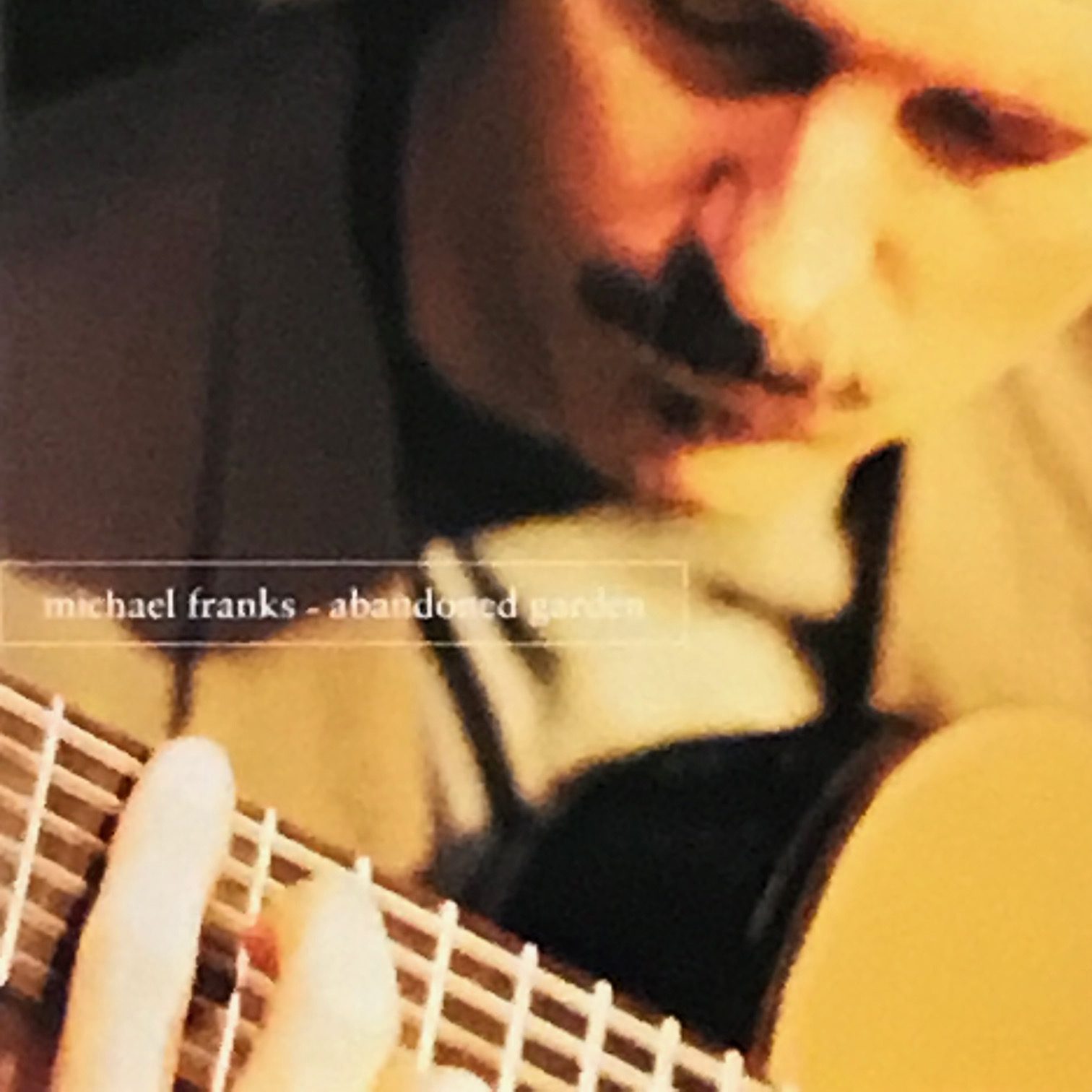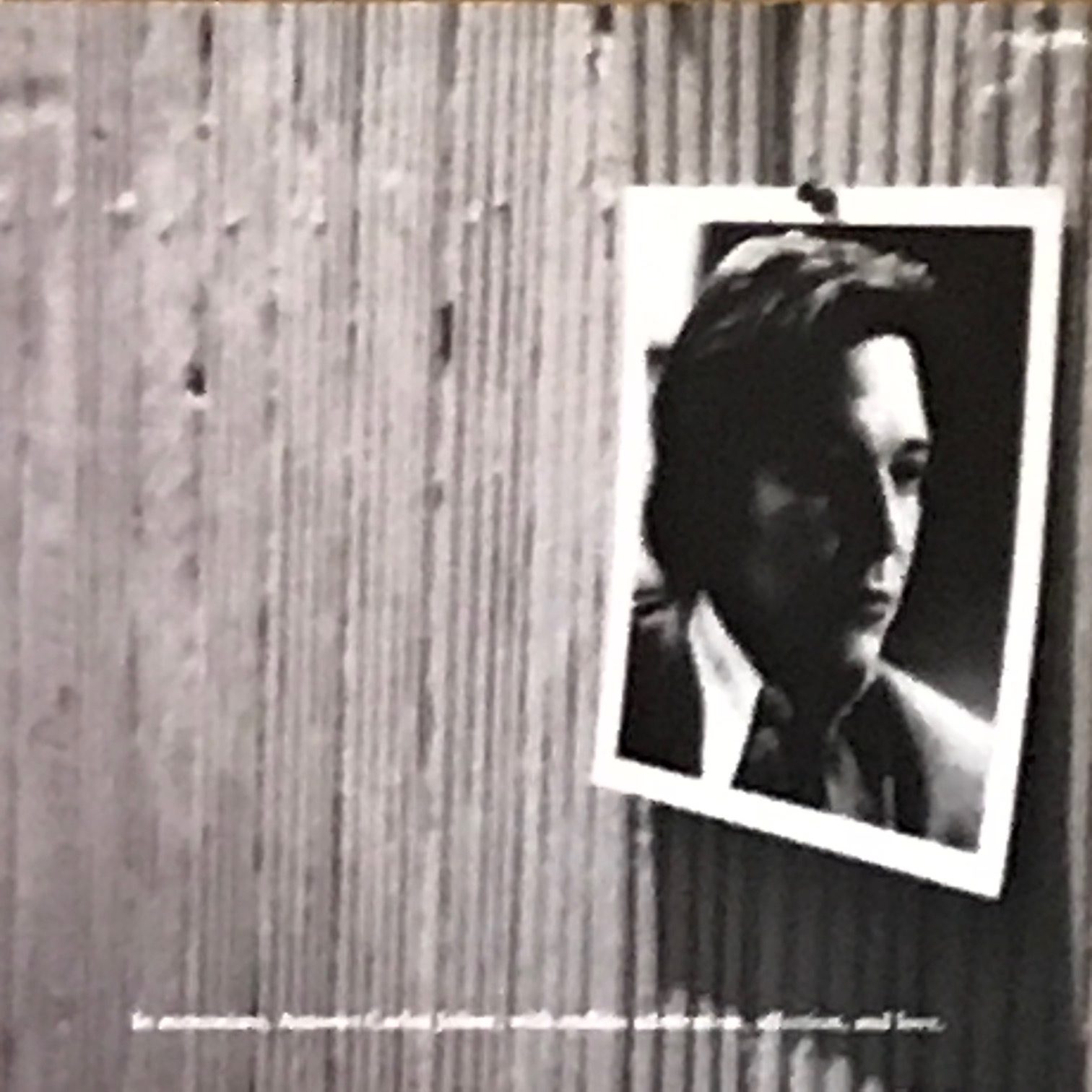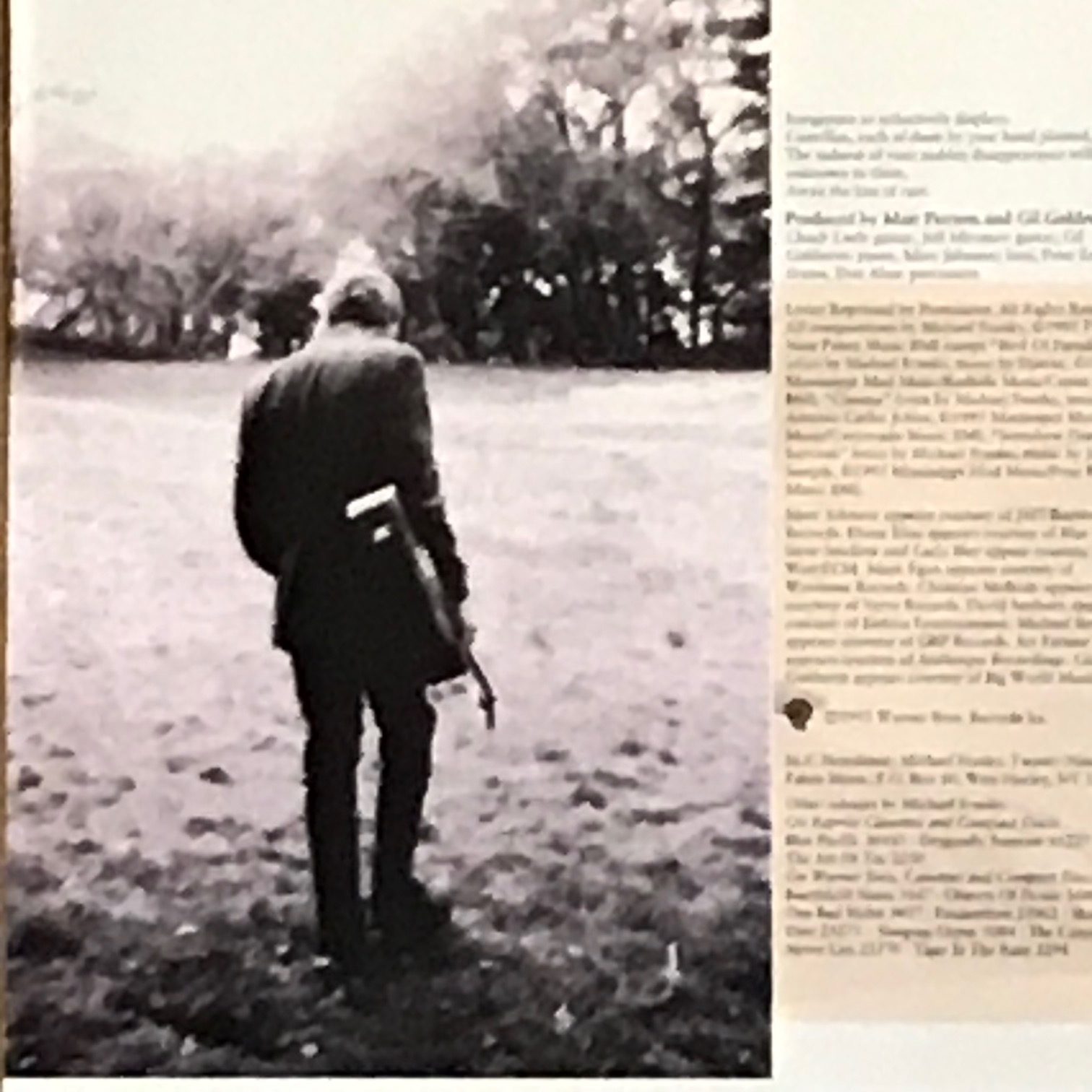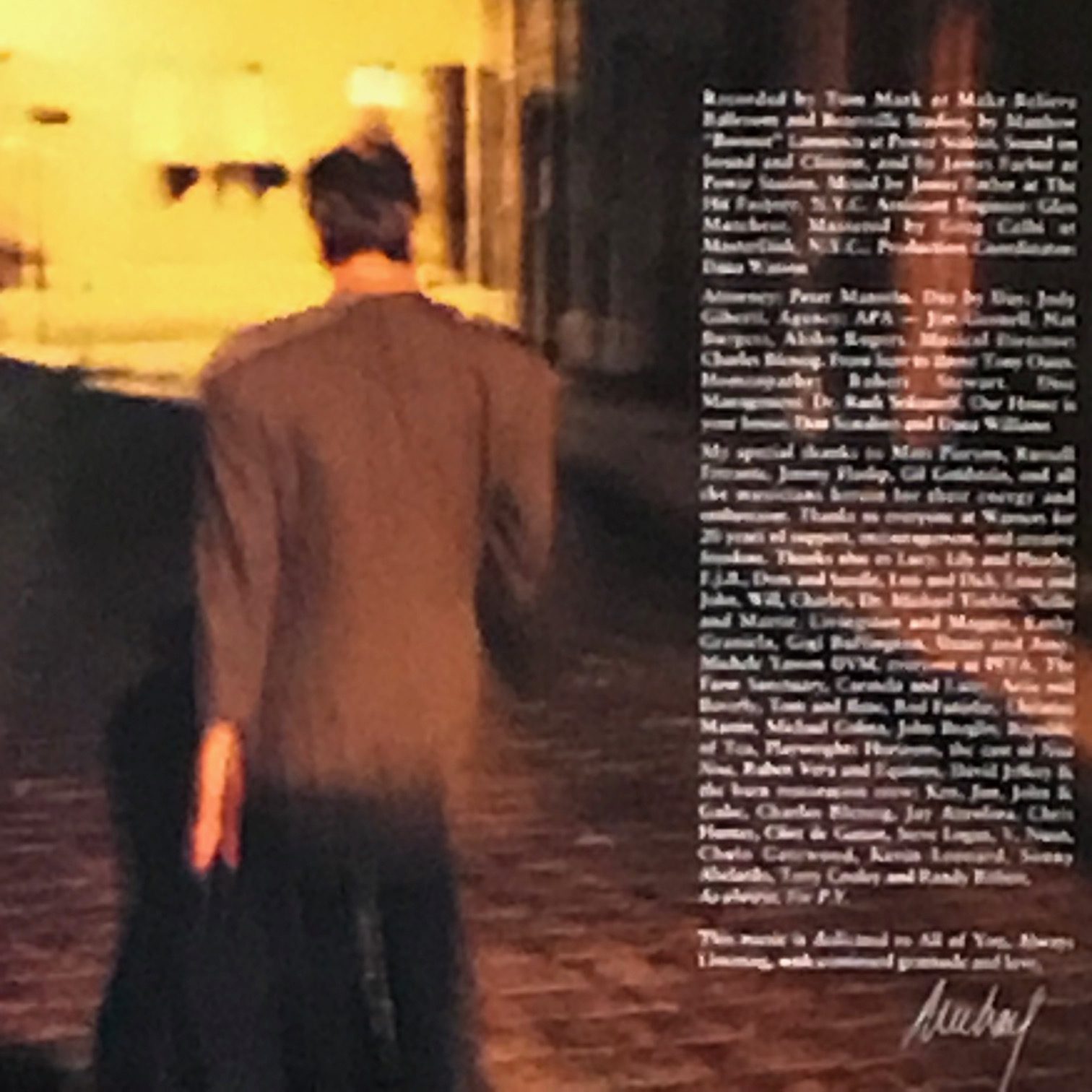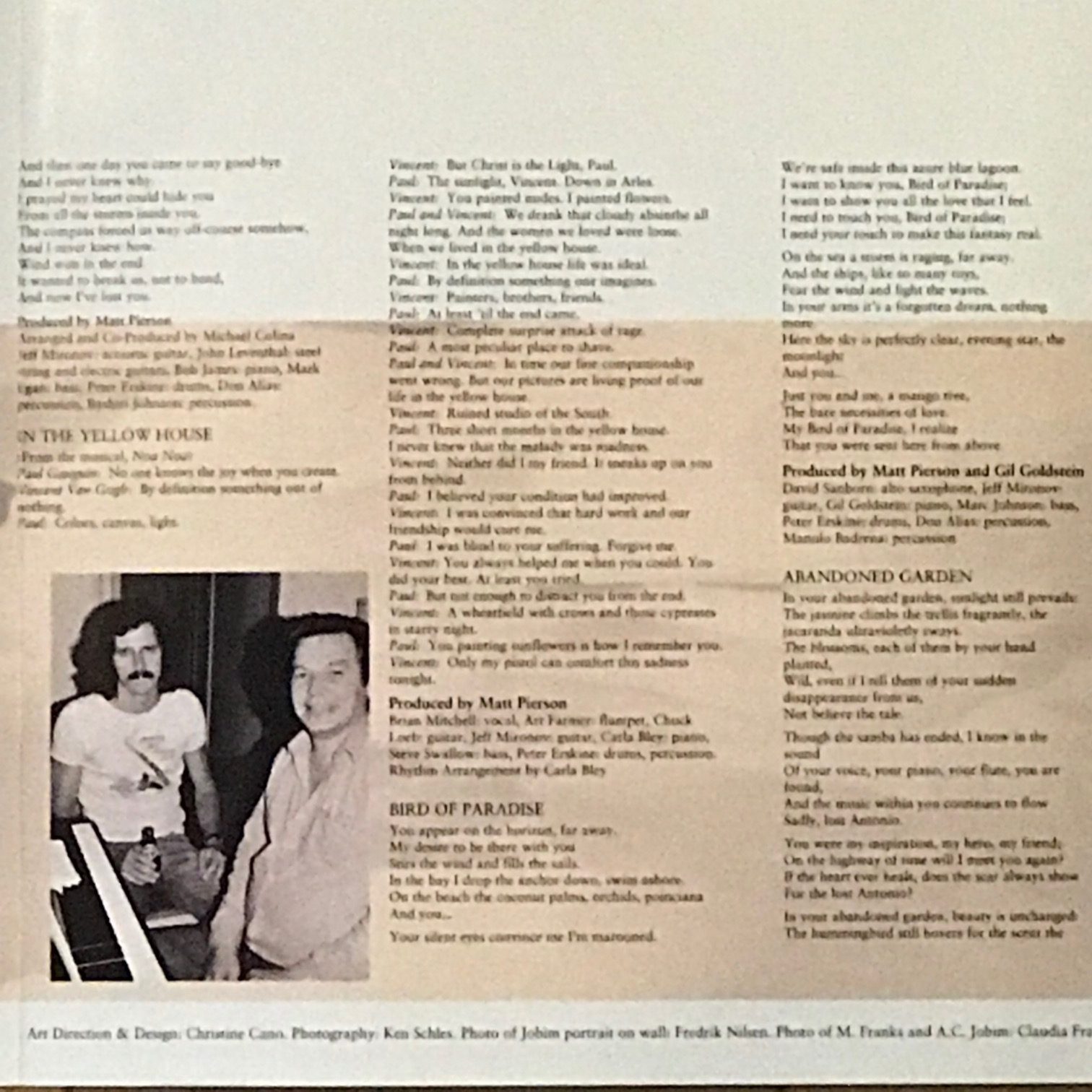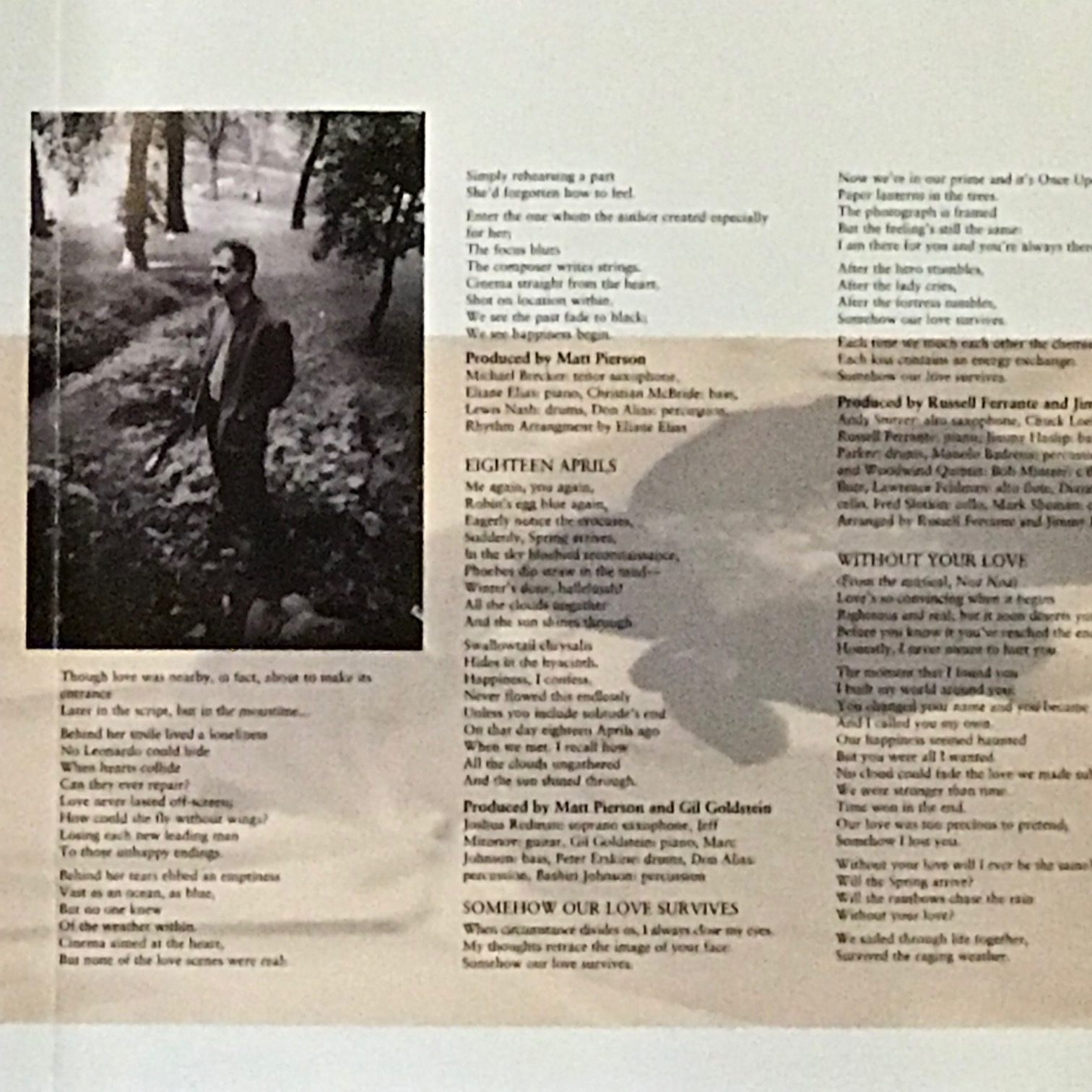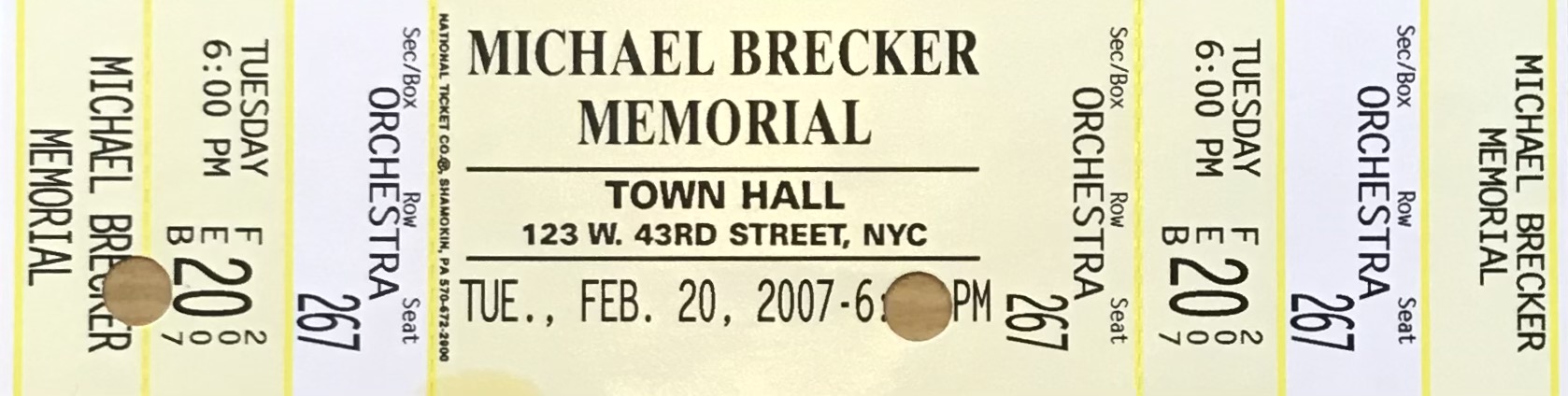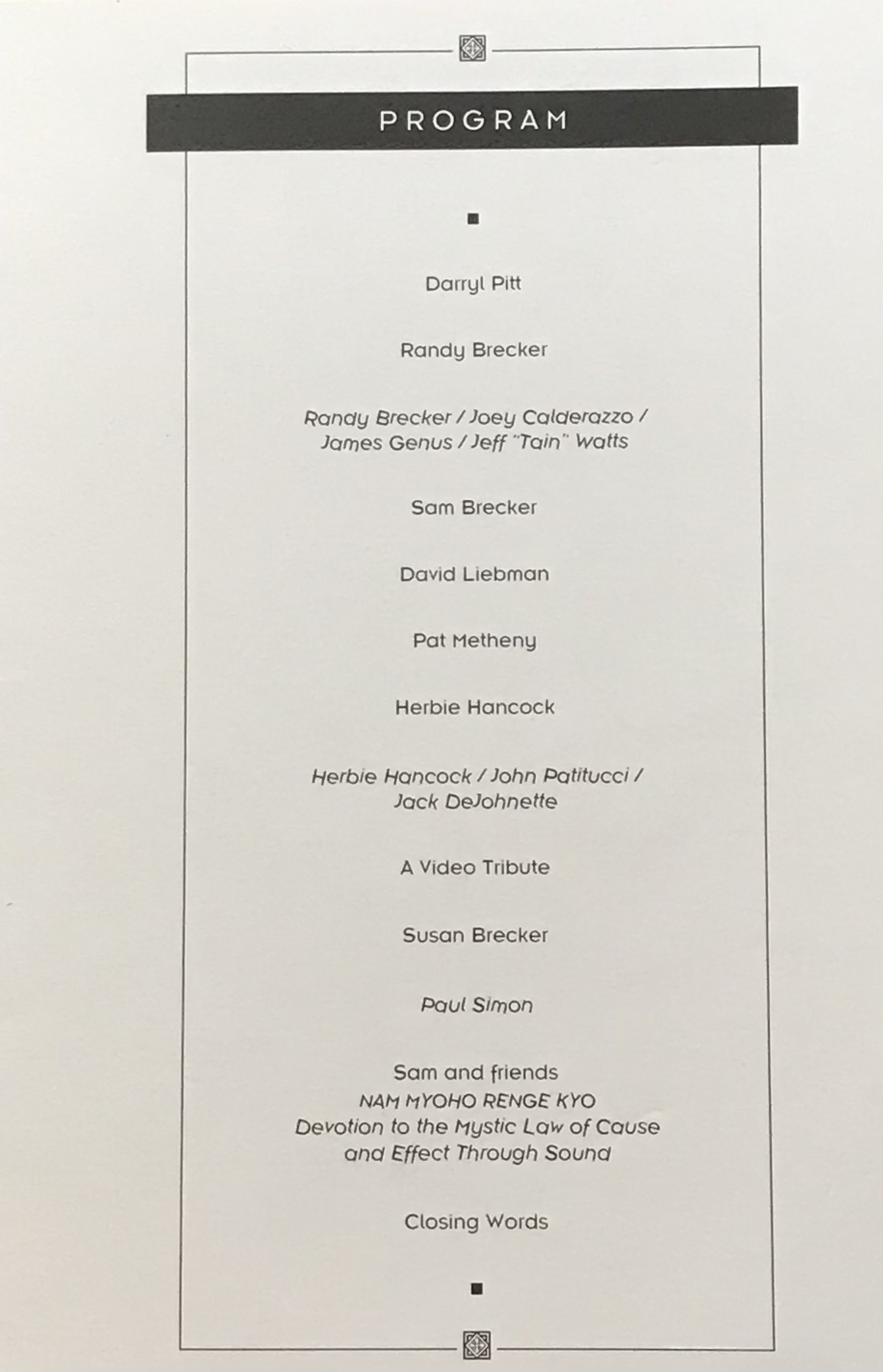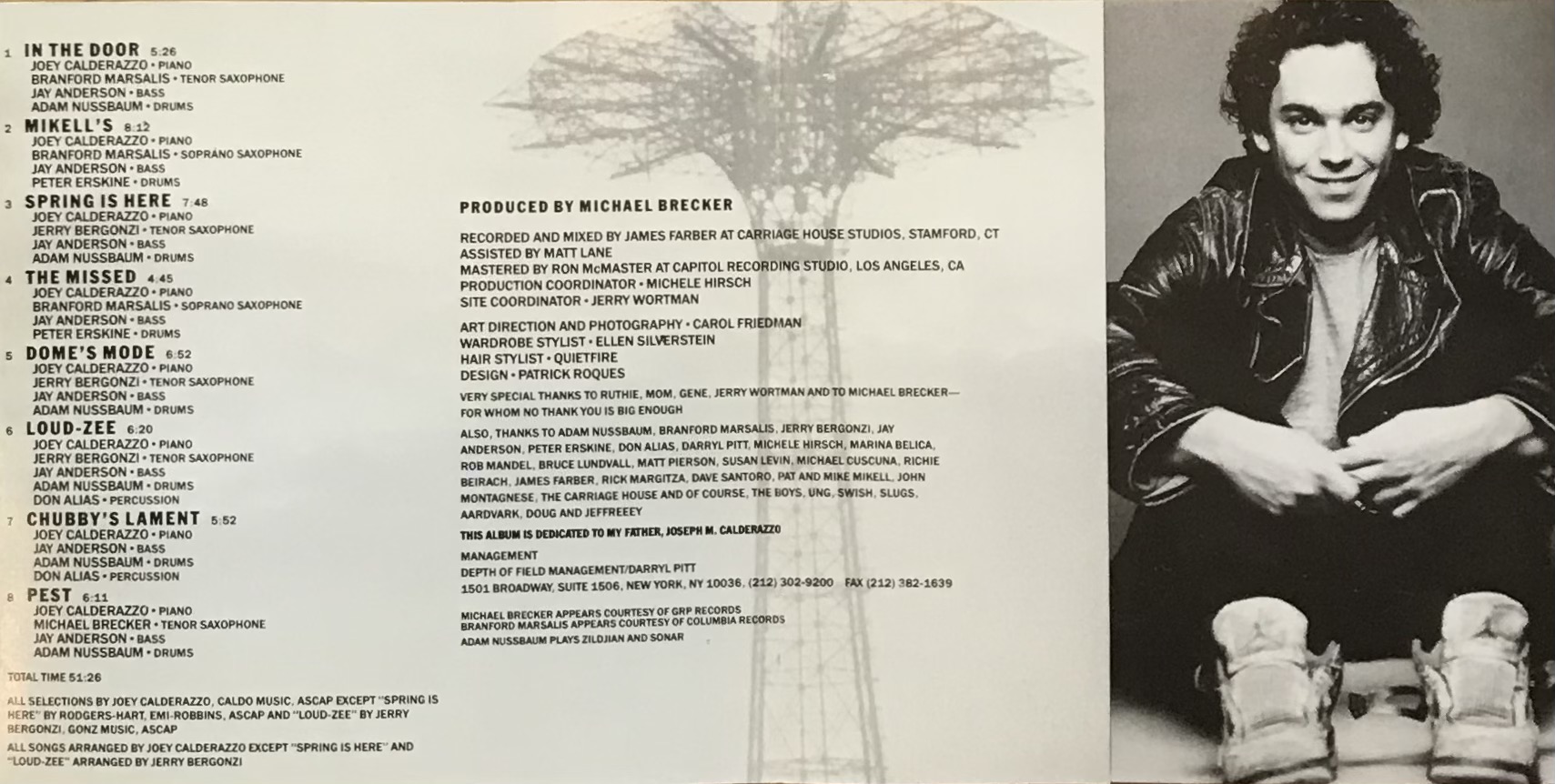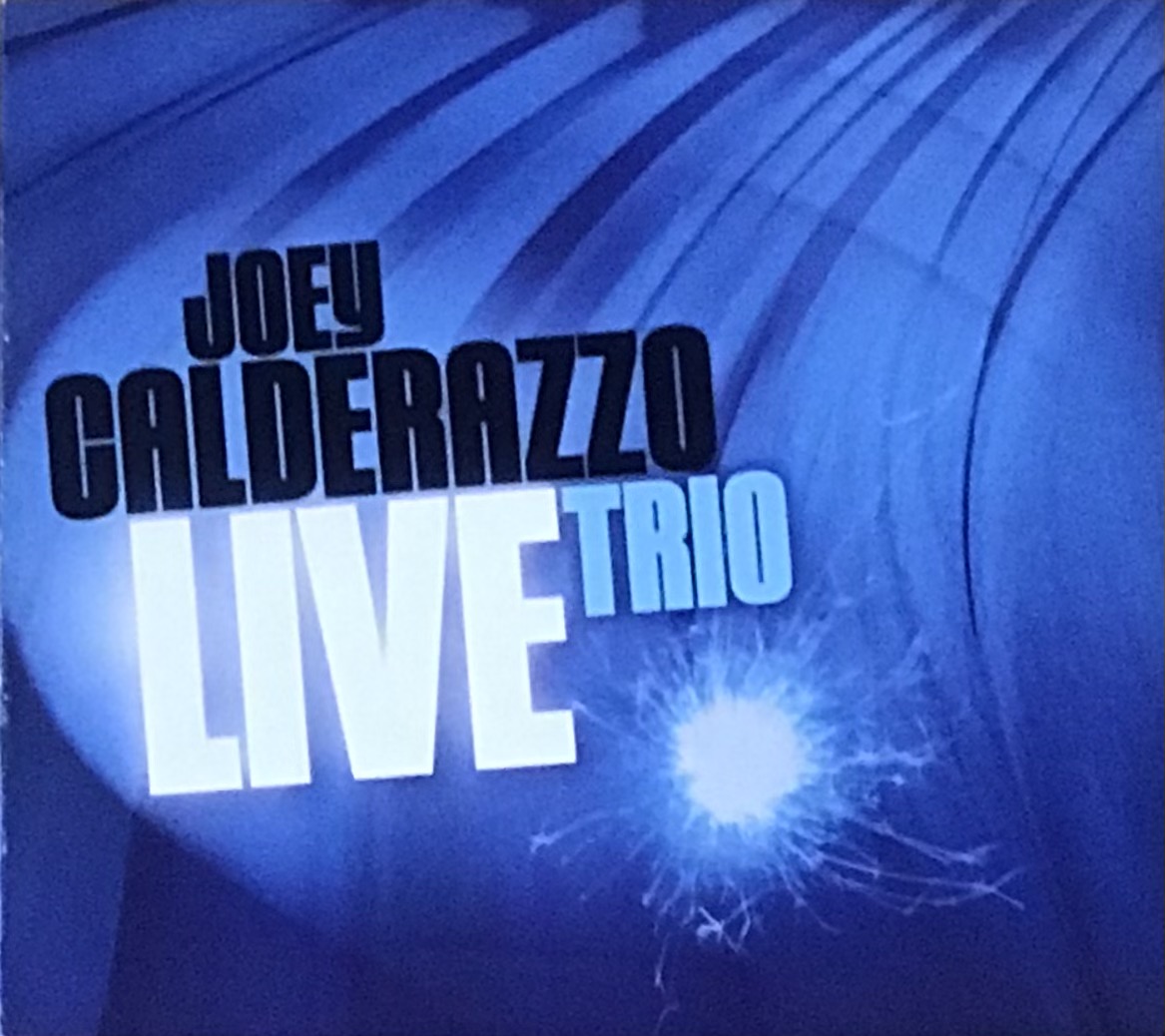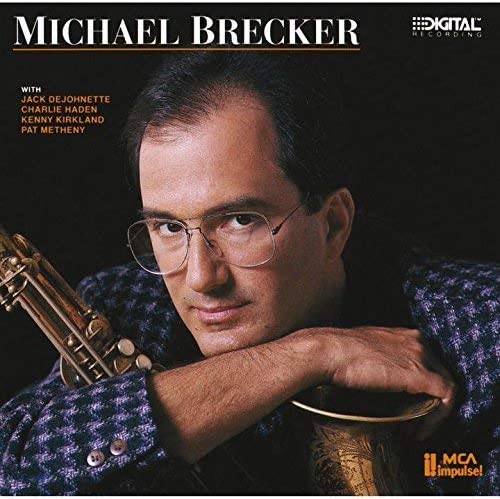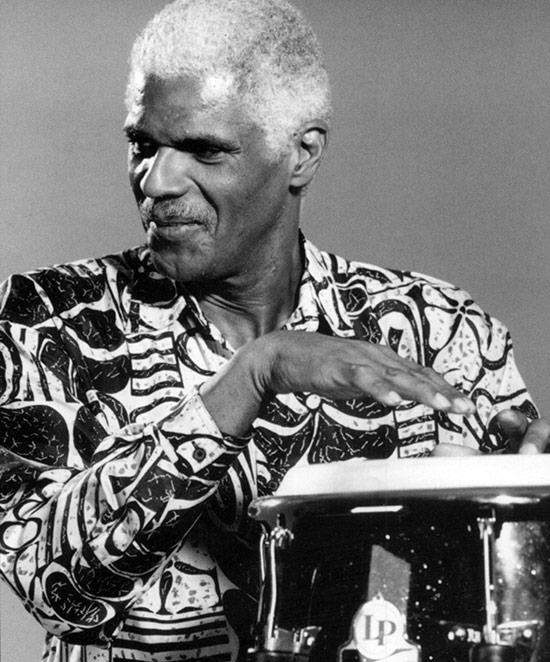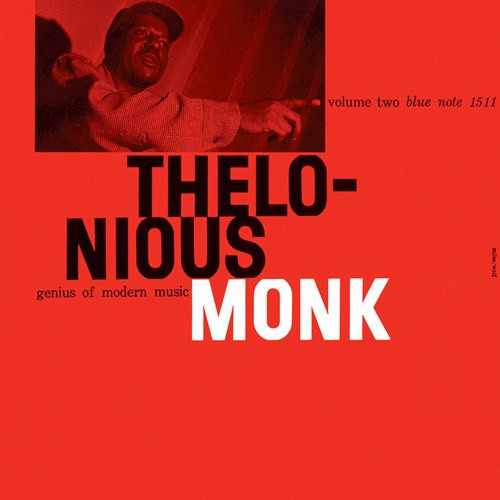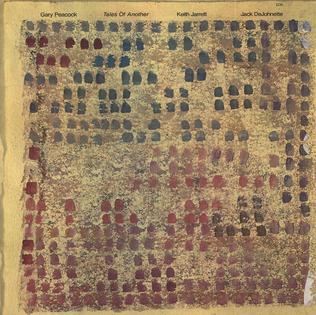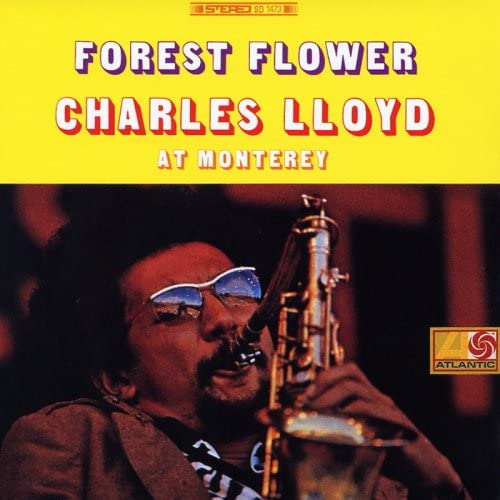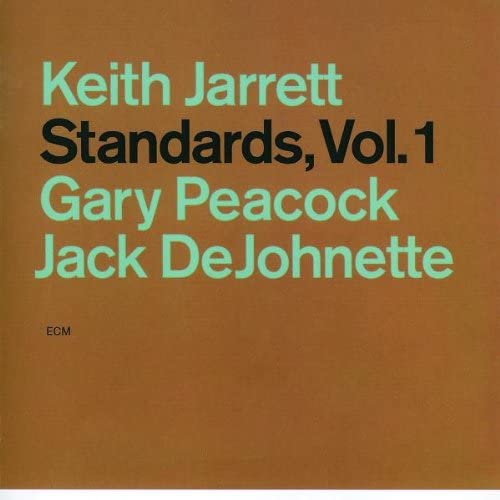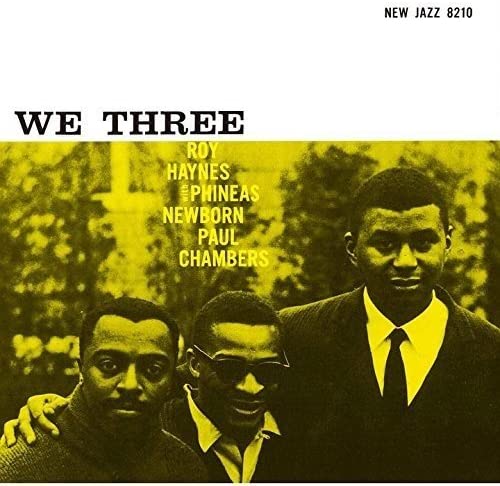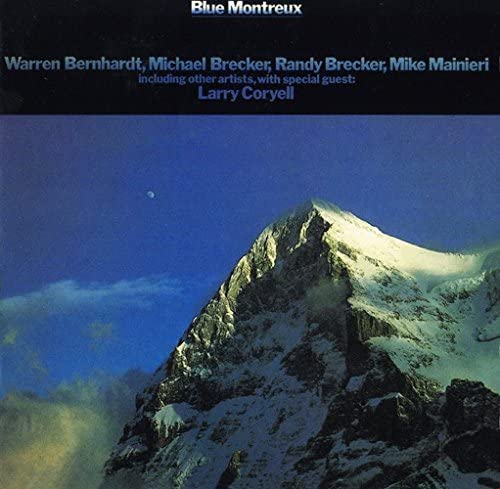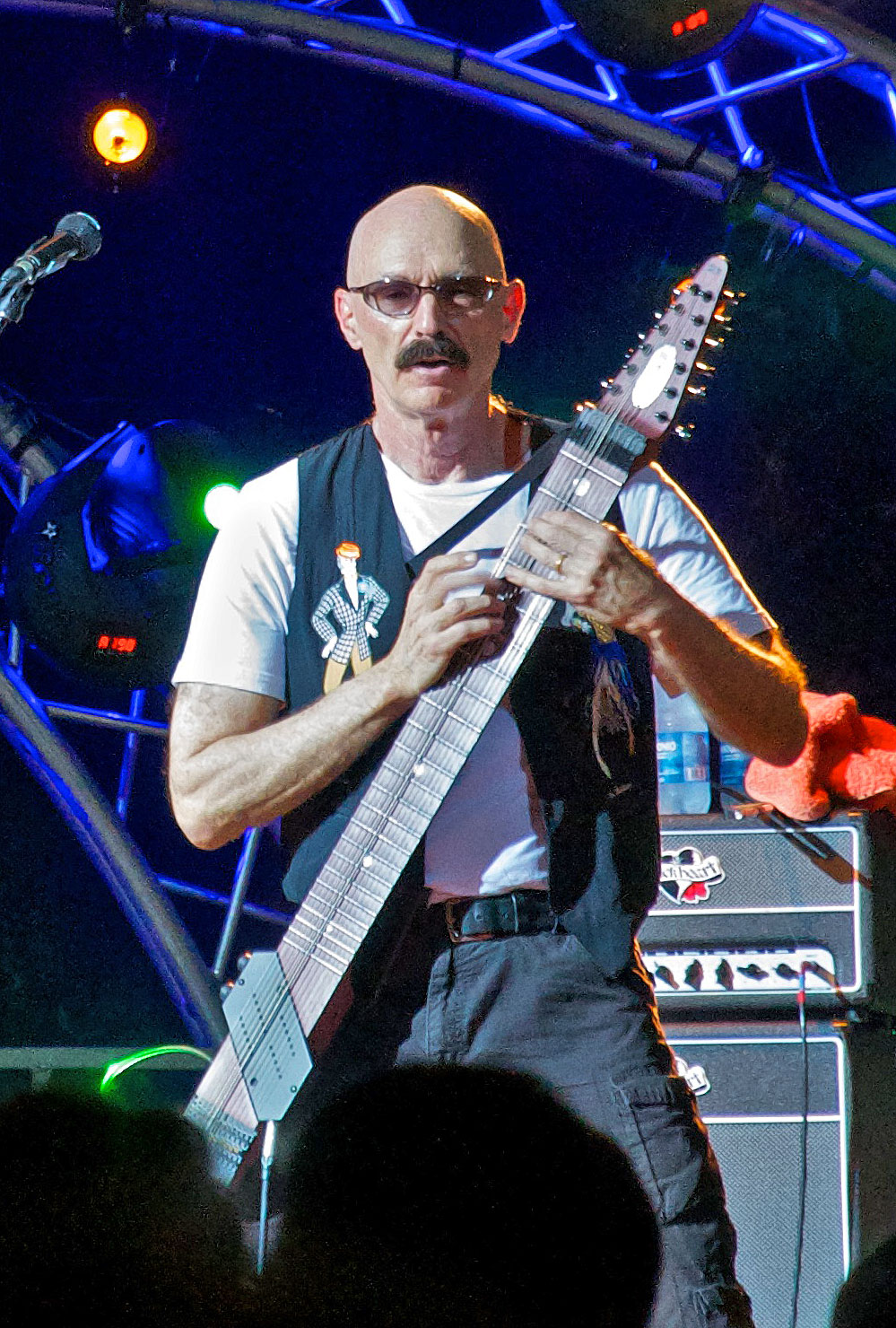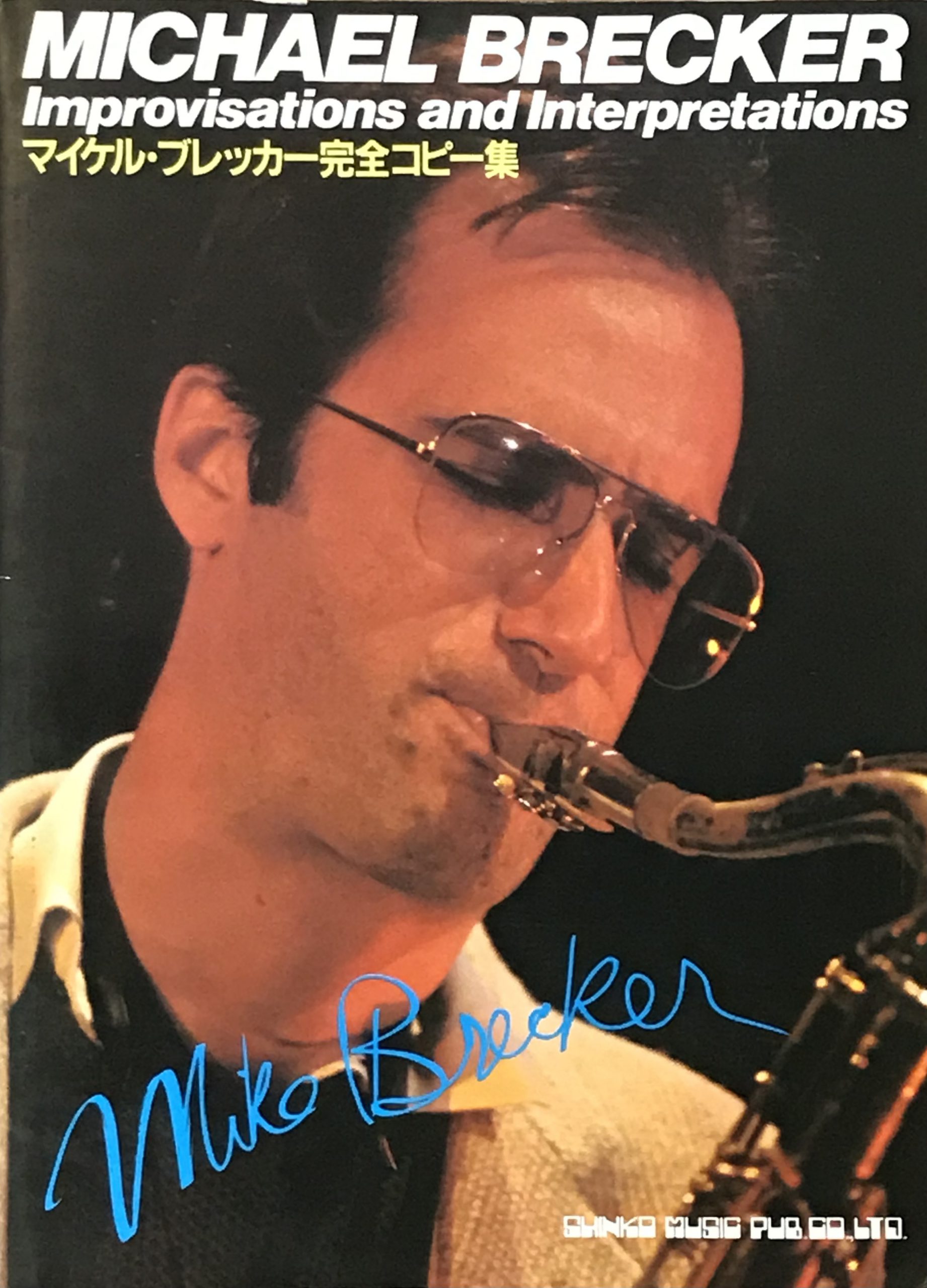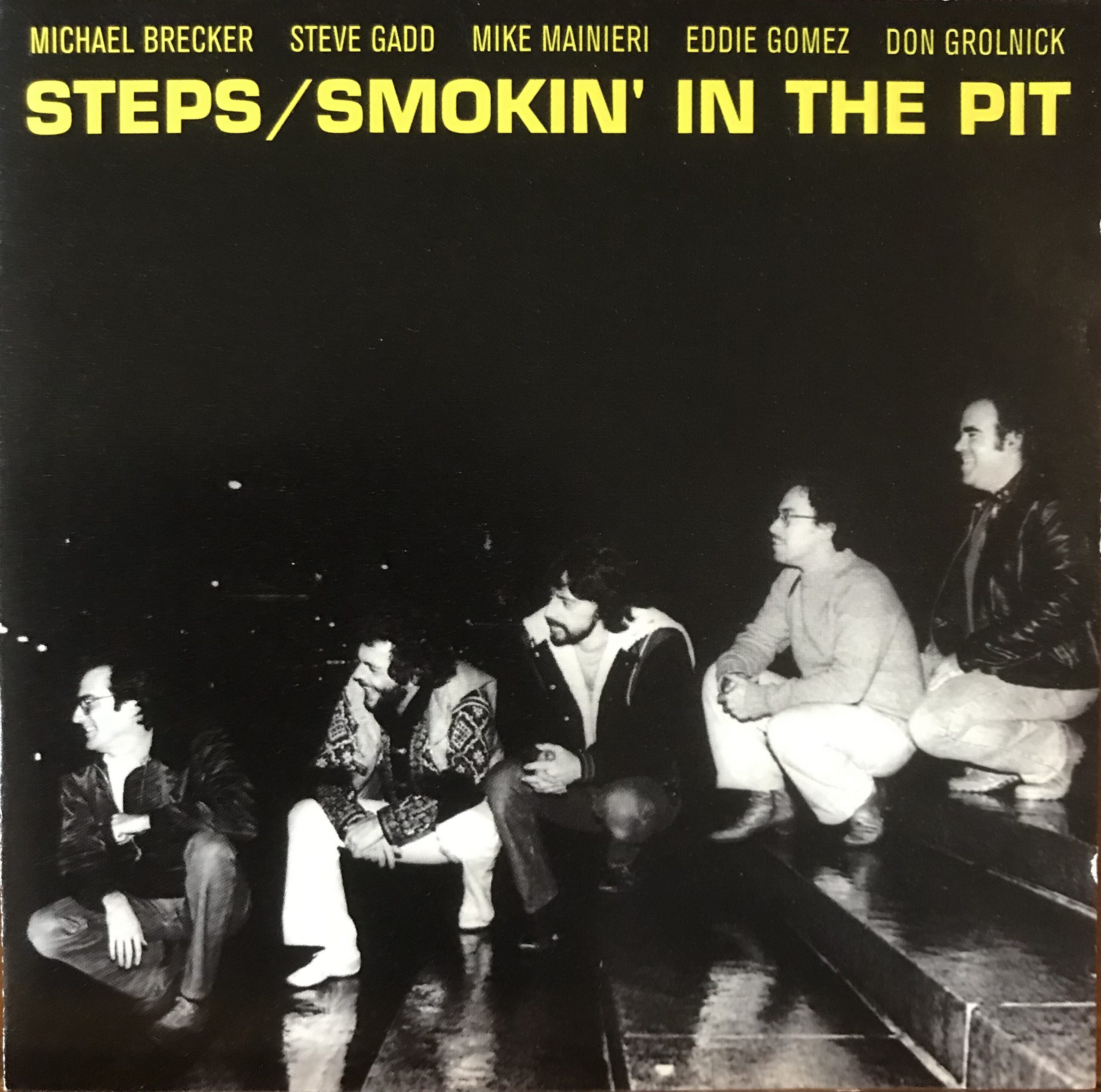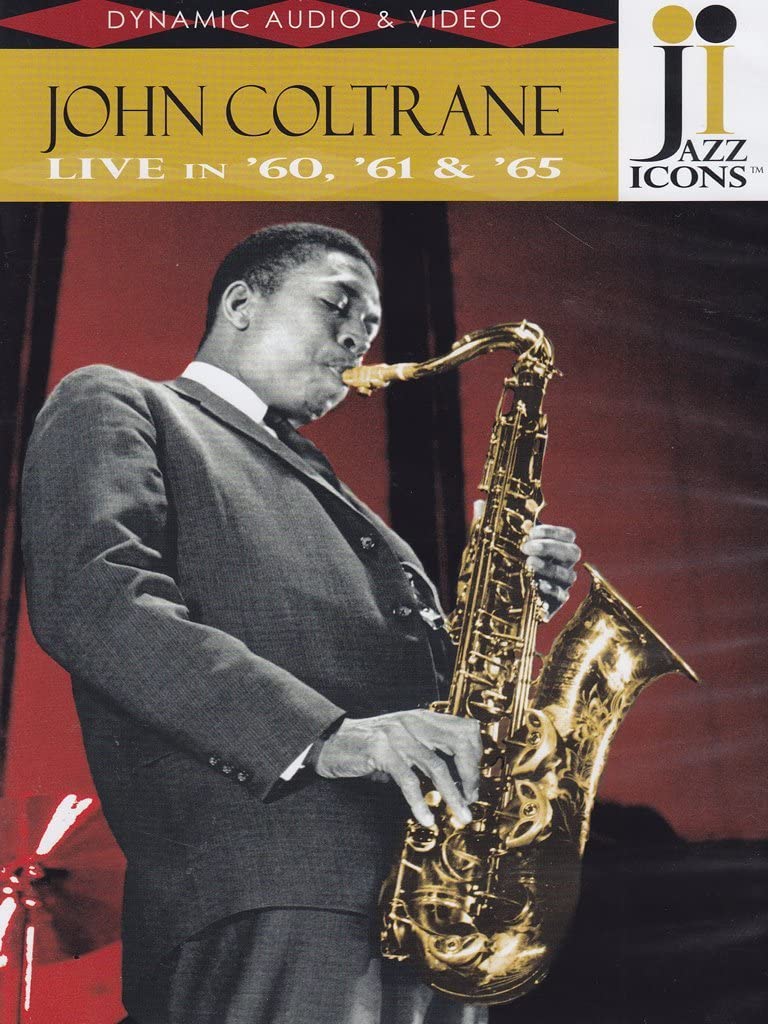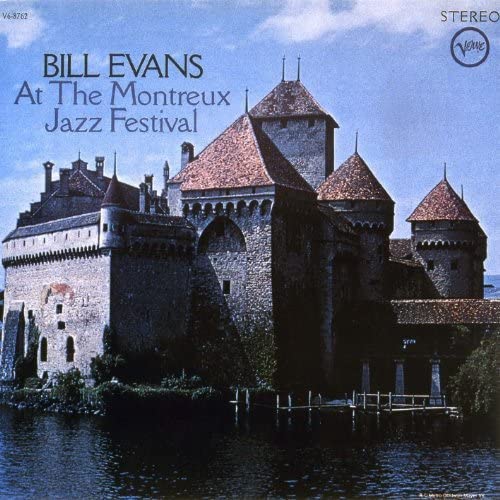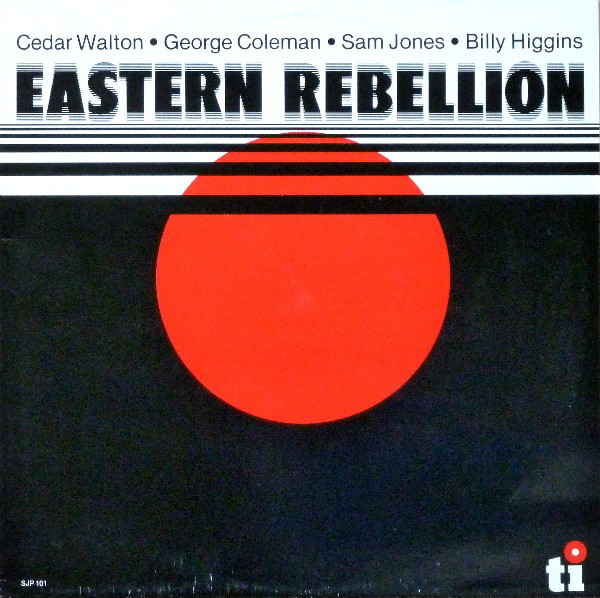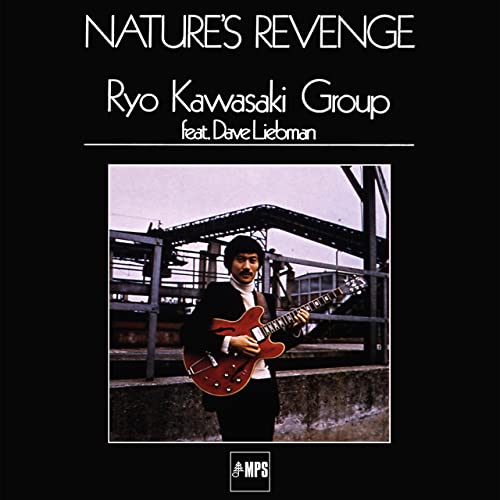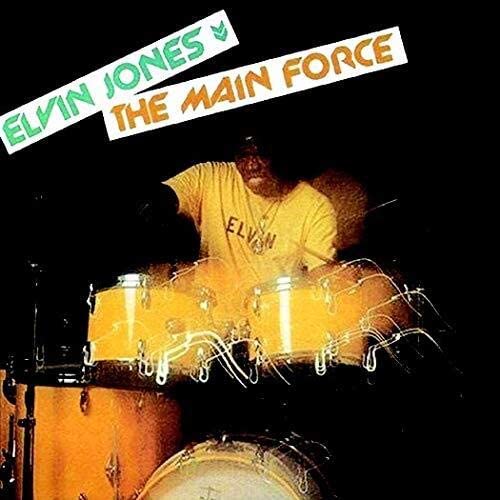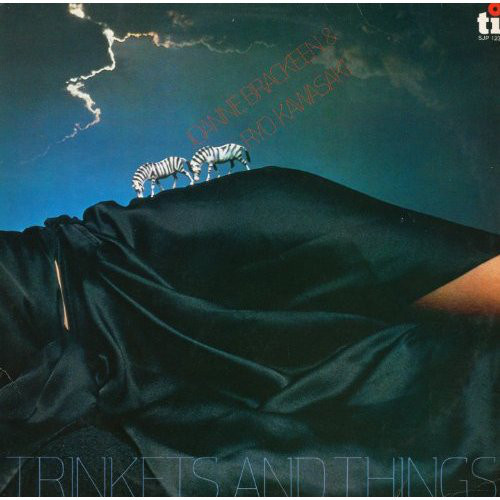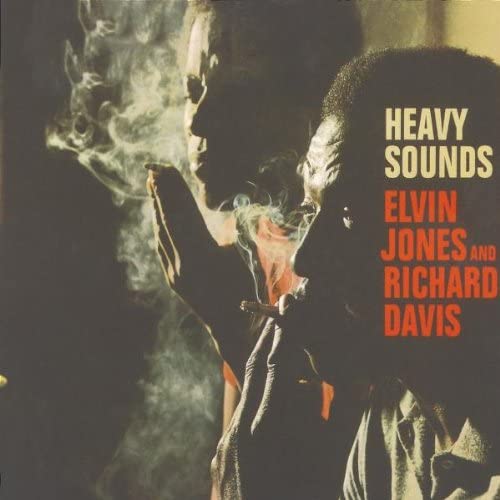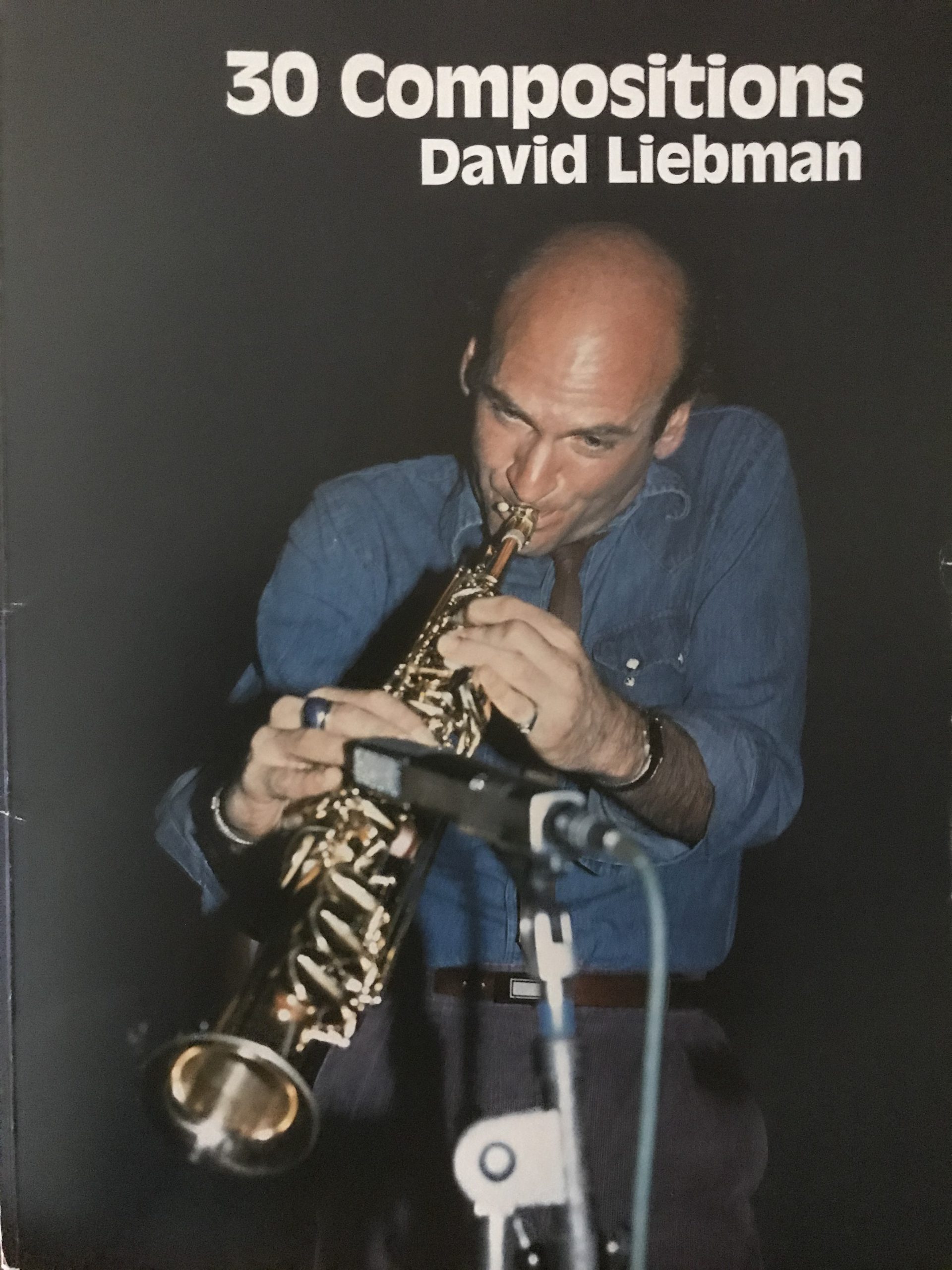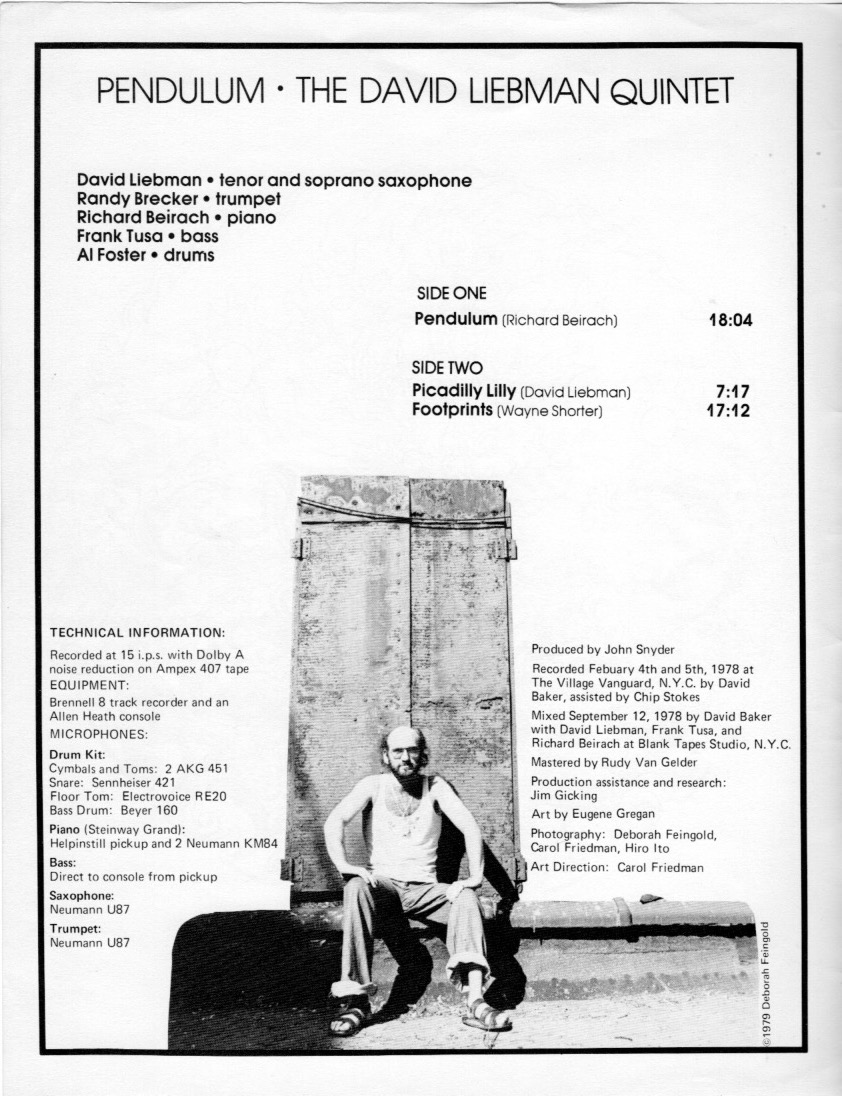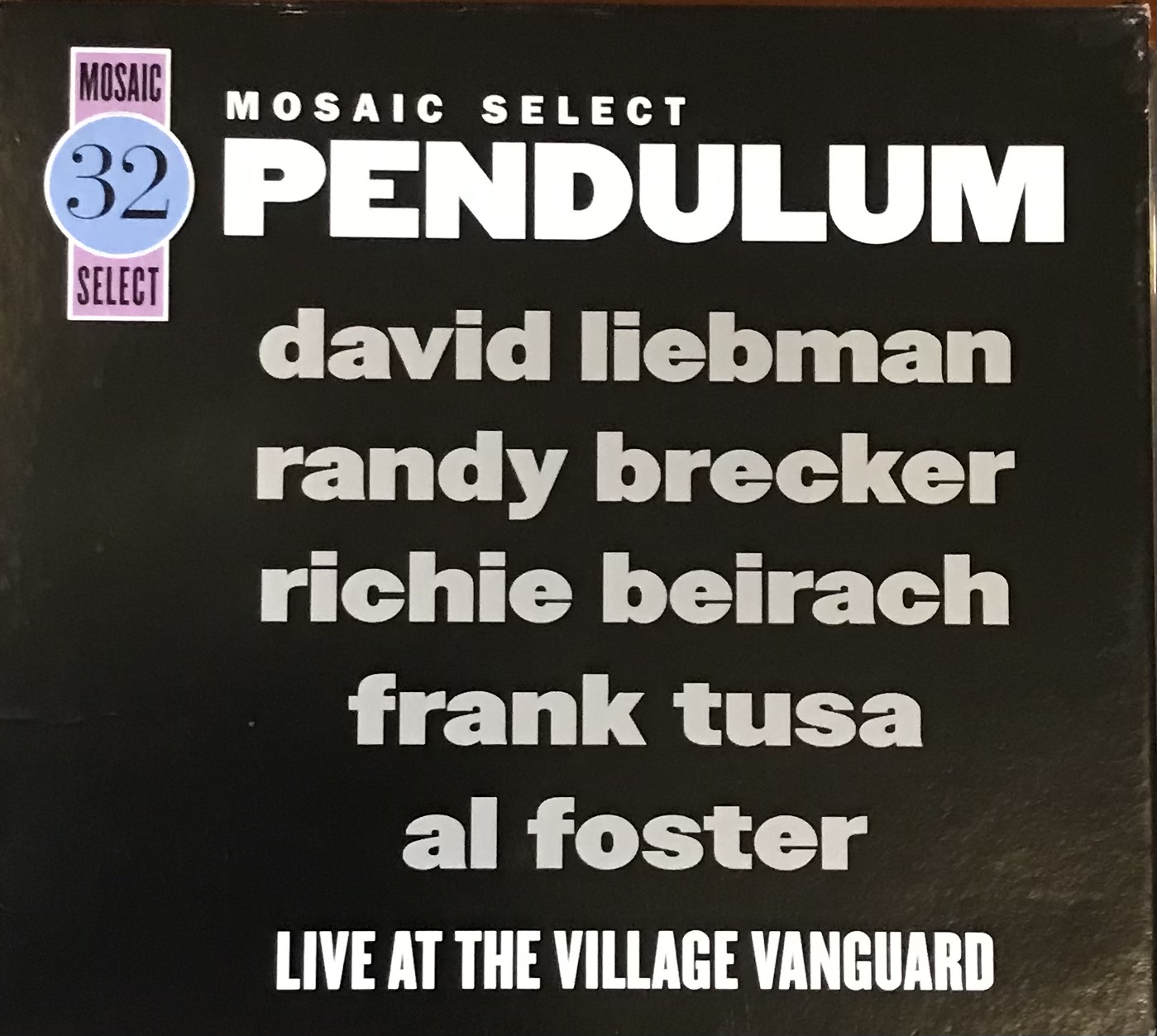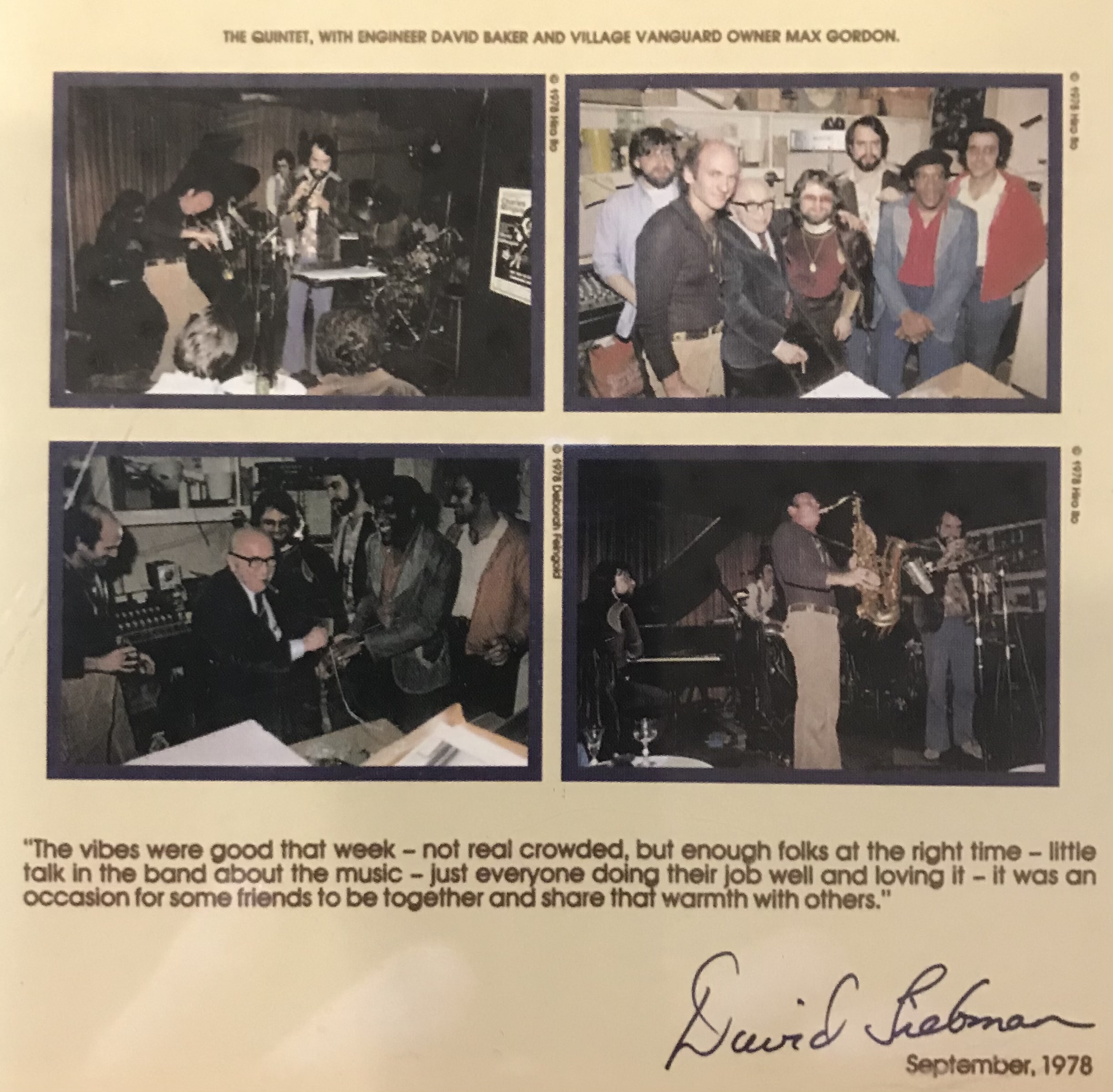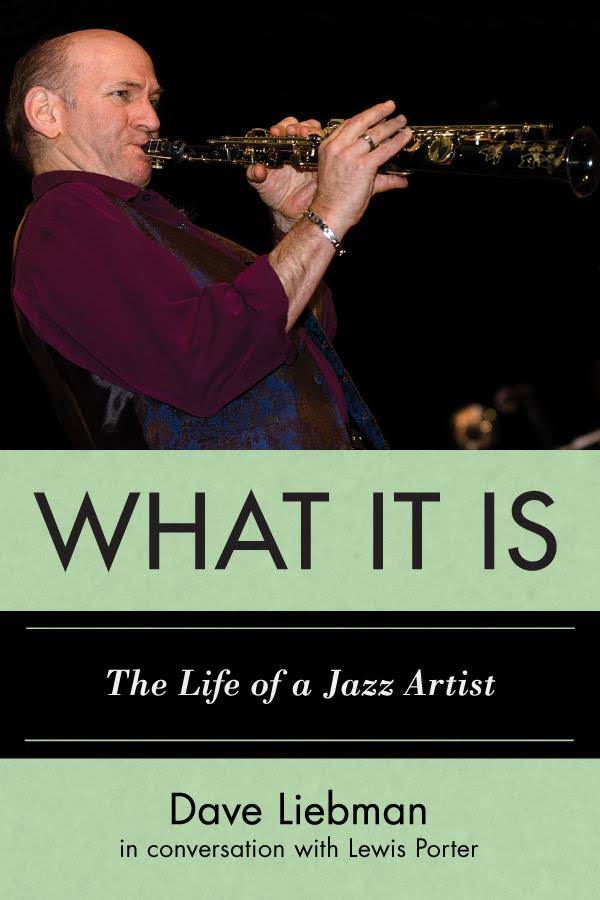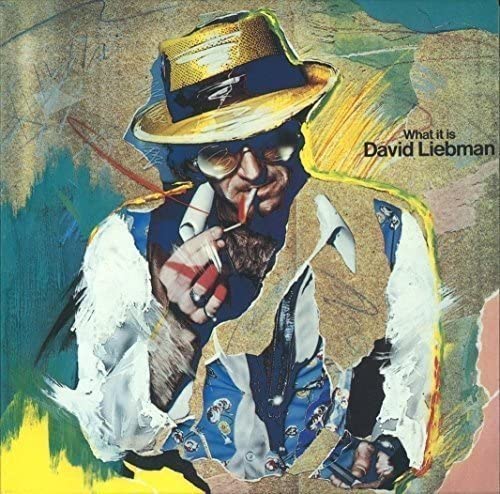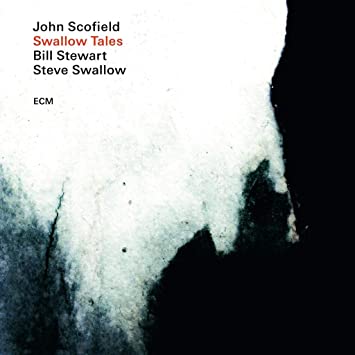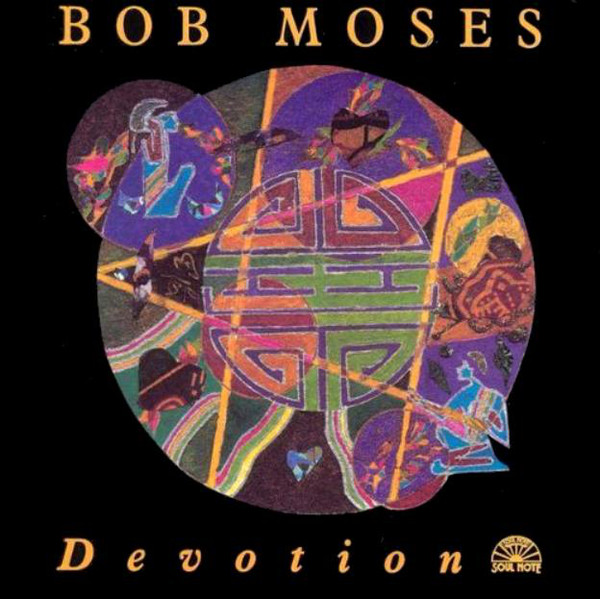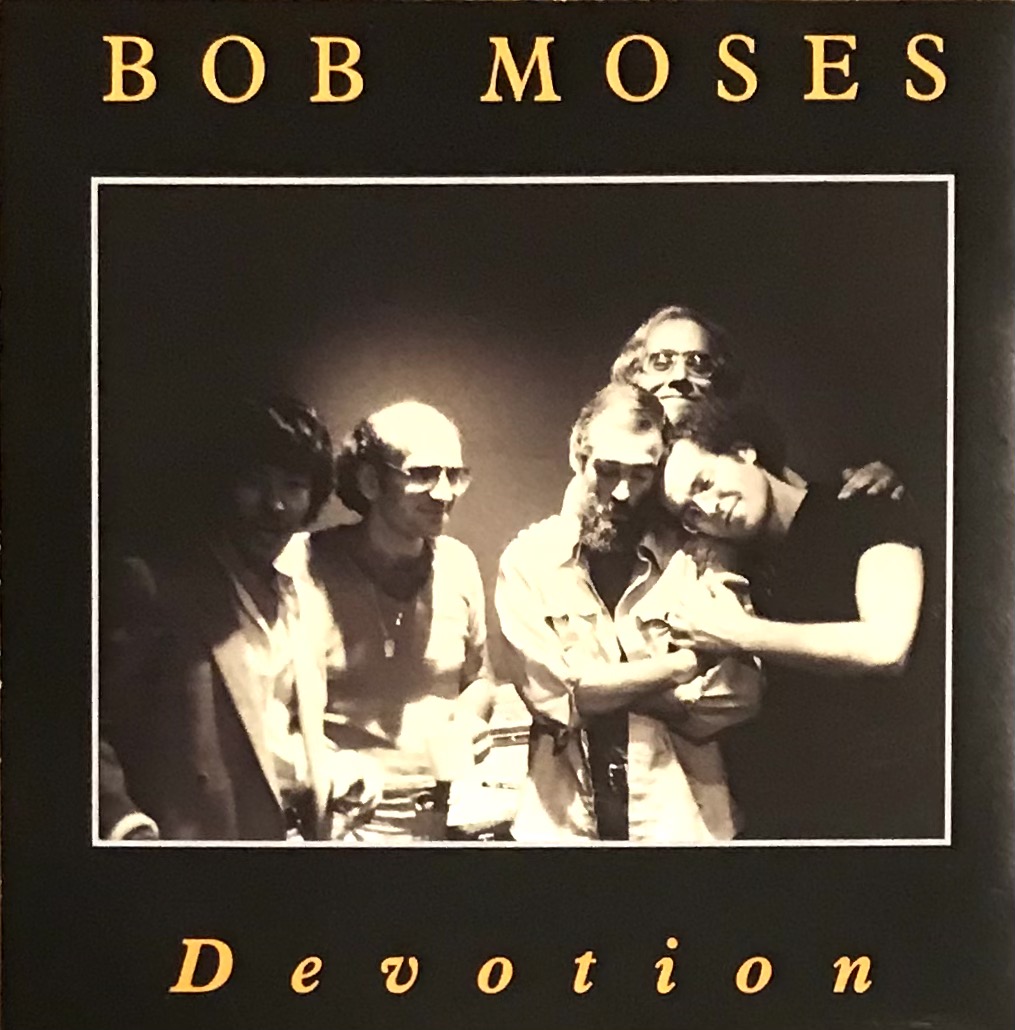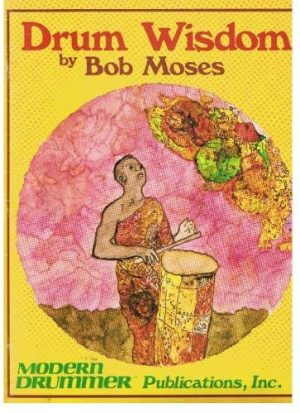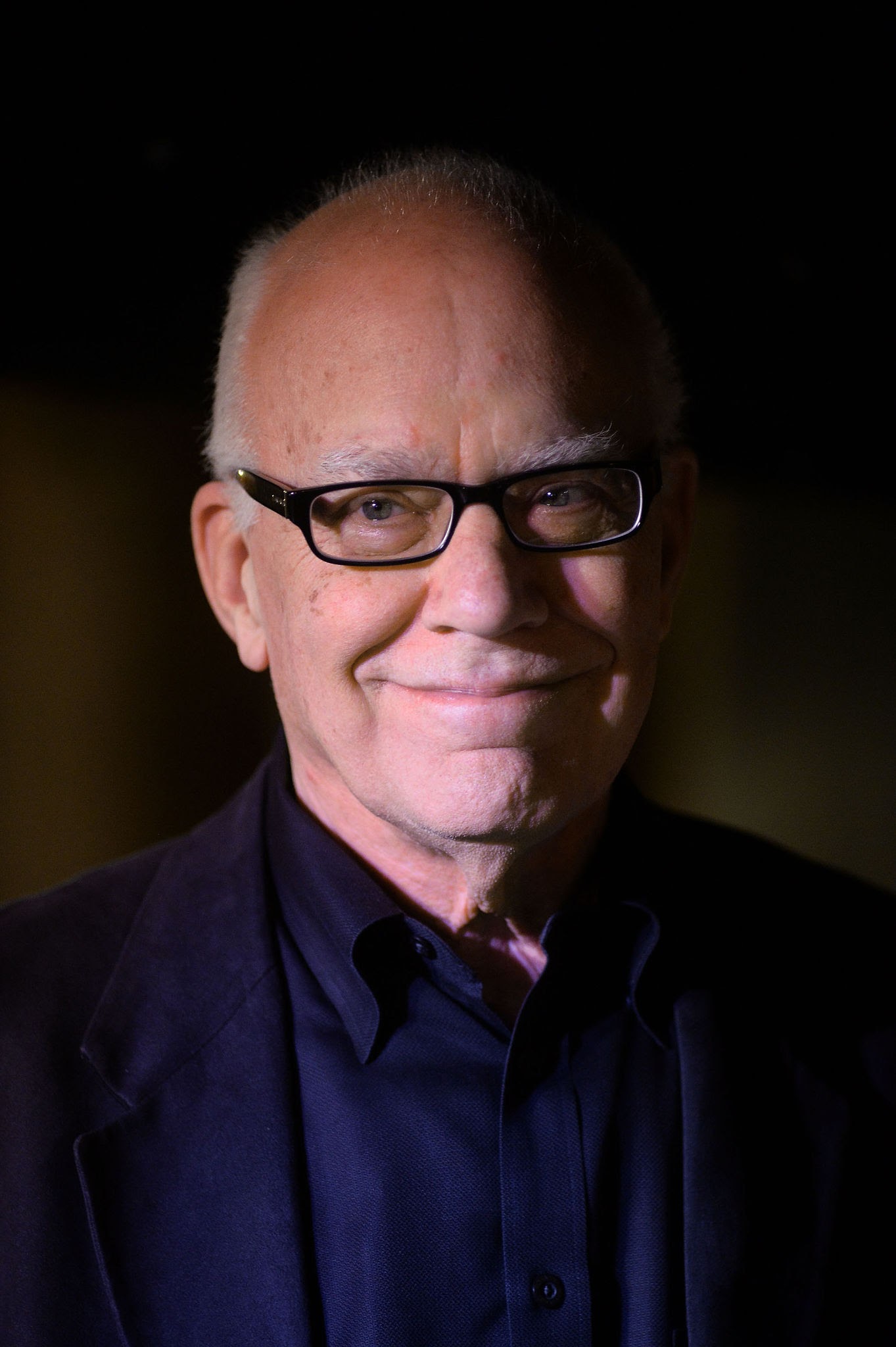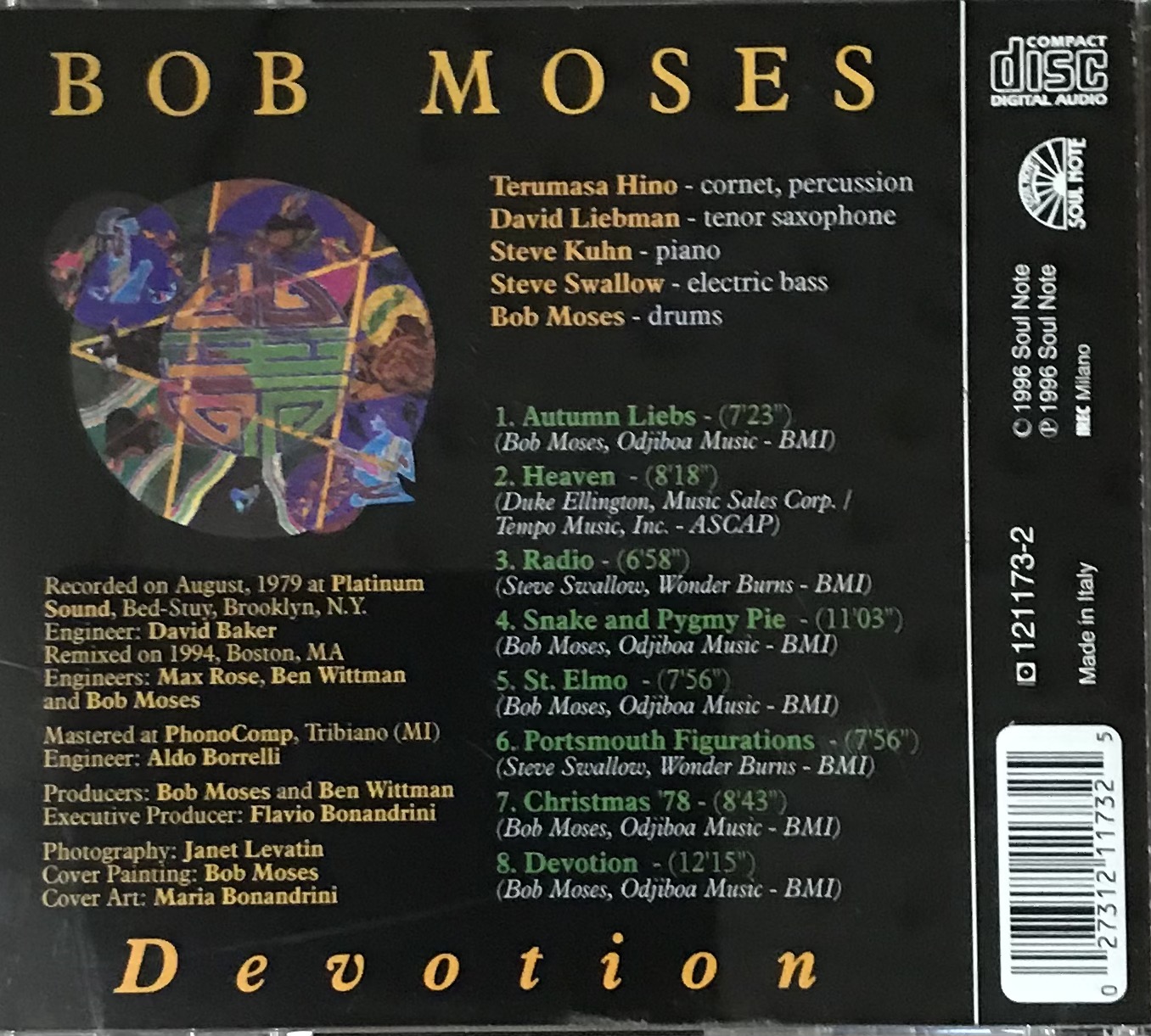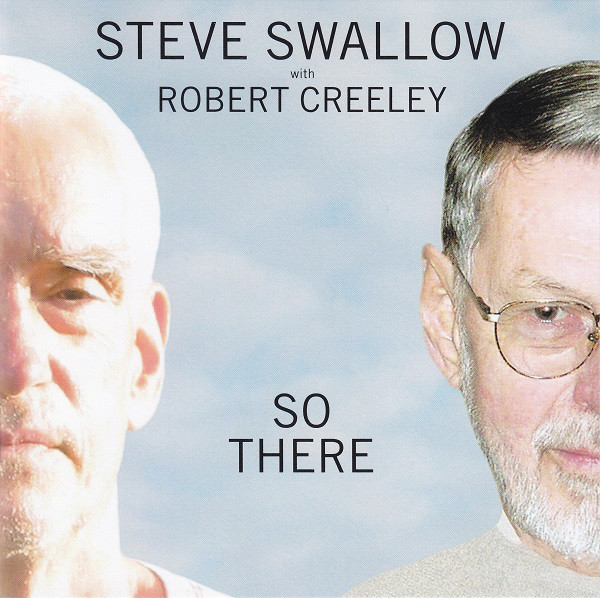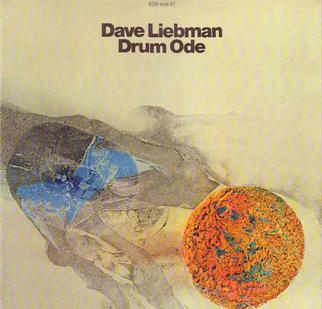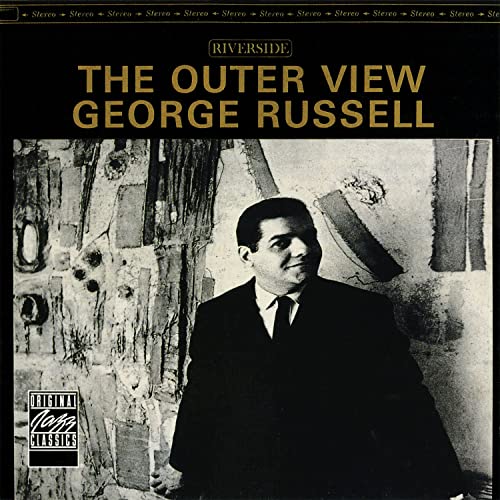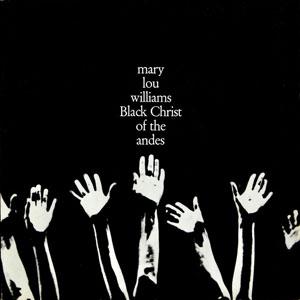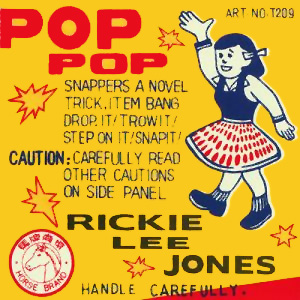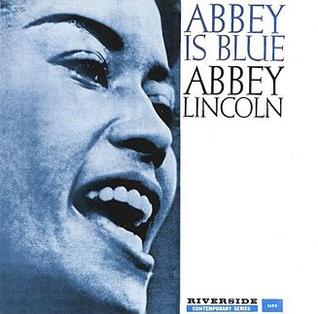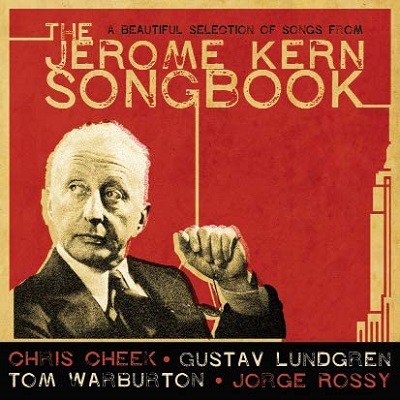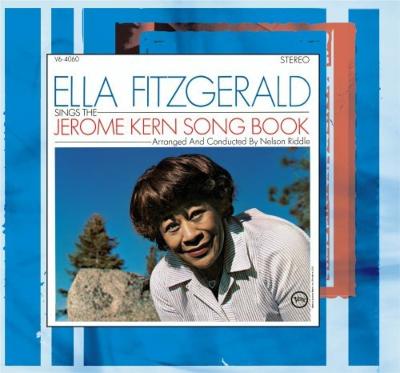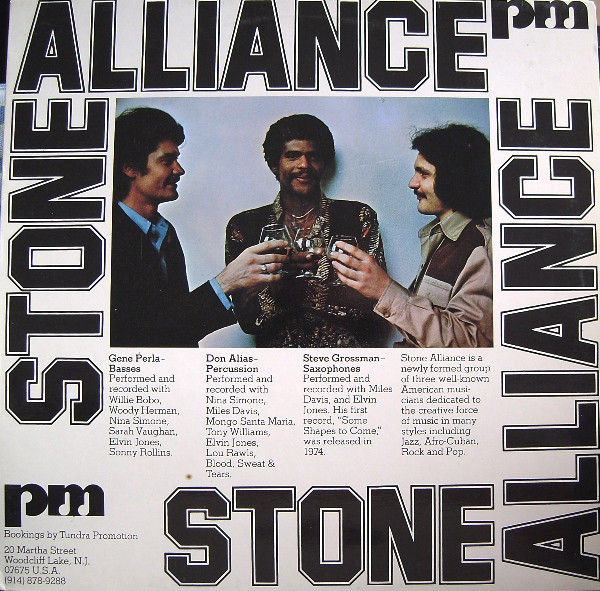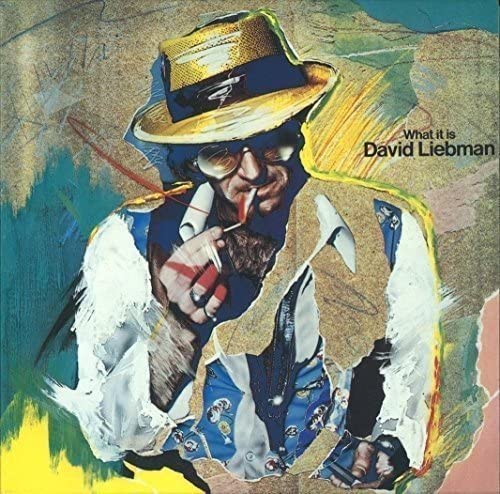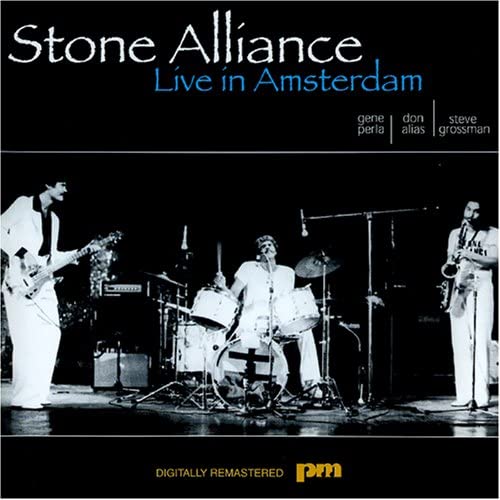2021.12
2021.12.21 Tue
今回はOrnette Coleman 1968年作品「New York Is Now!」を取り上げてみましょう。Elvin Jones, Jimmy GarrisonたちJohn Coltrane Quartetのリズム隊を得て、素晴らしいインタープレイを展開しています。
Recorded: April 29 & May 7, 1968 Studio: A&R Studios, New York City Engineer: Dave Sanders Label: Blue Note Producer: Francis Wolff
as)Ornette Coleman ts)Dewey Redman b)Jimmy Garrison ds)Elvin Jones
1)The Garden of Souls 2)Toy Dance 3)Broadway Blues 4)Broadway Blues(Alternate Version) 5)Round Trip 6)We Now Interrupt for a Commercial

本作には同日同じメンバーで録音された兄弟アルバム「Love Call」が存在します。内容的な遜色や残りテイクを寄せ集めた感はなく、コンセプト的にも明確な区別があるようには判断出来ません。2枚組でリリースされても良かったように思います。
Love Call / Ornette Coleman

58年「Something Else!!!!」で鮮烈なデビューを行い、ジャズシーンに一石を投じたOrnette、名作60年12月録音の「Free Jazz」でひとつのピークを迎えましたが、その後も数々の問題作を発表し60年代のジャズシーンの牽引役を担いました。
Something Else!!!! / Ornette Coleman

Free Jazz / Ornette Coleman

フリージャズの旗手とされる彼のプレイ・スタイルは多くの論議を呼び、シーンでは賛否両論を巻き起こしました。筆者自身も以前は彼が何を表現したいのか、どのような手法を用いているのか、そしてどのように捉えるべきなのか、皆目見当がつきませんでした。ただ他のプレイヤーと比して訴えかけるもの、説得力には格段の違いを感じていました。
ジャズを長く聴き、演奏者として携わった経験で得た耳を元に、自分なりに分析を試みると、コード進行に対する調性を超越し、例えばアベイラブル・スケール、裏コードや代理コード、テンションといったロジカルな方法論をも排除した(本人に言わせれば異なるのかも知れませんが)、実は真の即興演奏に徹していて、常にフレッシュなラインを構築していたのです。彼自身は自分のプレイ・スタイルの基本はフレーズを吹く事だ、と述べていますが、あの超個性的な音色とニュアンスで演奏されると、フレーズという概念が吹き飛んでしまいます。
Ornette Coleman

彼の特徴の一つはフリーフォームであっても、タイムのキープ感がずば抜けており、リズムを外したり見失う瞬間は殆ど存在しない事です。フリー=リズムが無いと解釈されがちですが、Ornetteに関してそれは誤りです。良い例を挙げれば「Free Jazz」でCharlie Haden, Scott LaFaro, Billy Higgins, Ed Blackwellらのダブル・リズムセクションが繰り出す、端正でスインギー、かつディープなリズムに対し、大きくリズムを捉え、見事なタイム感で演奏しています。
後年彼は「ハーモロディクス理論」を唱えました。72年4月録音リーダー作「Skies of America」のライナーノーツに初めて具体的な記述が掲載されており、当作はその手法を用いて演奏されたそうです。ミュージシャンによる音楽理論としてはGeorge Russellが唱えたLydian Chromatic Concept(LCC)が存在します。以前Russellの弟子(Russellが認定した師範代でなければ、LCCを教えることは許されないそうです)である米国人から、彼がピアノを弾き、自分もサックスを演奏しながらLCCのレクチャーを受けたことがあります。「あらゆる音使いの正当性」「どのような音を使っても良い」ことを理論的に解明していたようなのですが、僕の理解力を超えたところで話が進んでいました。「ハーモロディクス理論」についても自分は勉強不足で、残念ながら補足説明をする事は出来ません。
Skies of America / Ornette Coleman

Ornette出現後に雨後の筍のごとく現れた前衛サックス奏者たちの中には、彼の模倣を行いつつも何処か勘違いし、個性を曲解した音色で、意味があるとは思えない音符を吹き散らし、肝心なリズムを蔑ろにしていました。しかしOrnetteは言ってみれば自分の演奏に対し常に責任を持ち、音楽の3要素(リズム、メロディ、ハーモニー)を彼なりに遵守していたと考えています。Free Jazzというカテゴリーの中でしっかりと!確実に!
リズムをキープする事に対するこだわり、またメロディという点ではあまりにも独創的ではありますが彼なりの美学を遂行し、ハーモニーに至っては他の追従を許さない境地でサウンドさせています。そのハーモニーという観点ではCharlie HadenのベースラインがOrnetteのプレイに瞬時にして確実に寄り添い、ジャズ史上あり得ない次元でのインタープレイを行なっていました。具体的には彼が吹くフレーズに於ける和声や和音を即座にキャチし、ベースラインで対応するのです。意外性を伴ったプレイが頻繁に現れるOrnette、さぞかしアプローチするのに骨が折れた事と思いますし、彼を心から尊敬するHadenにとっては試練であり、修行の場でしょう、しかし究極Hadenにとっては至福の時だったに違いありません!
ごく初期には彼のバンドにピアニストが参加しましたが、以降はピアノレスの編成でプレイし続けました。Ornetteの吹くラインに、より自在性を持たせる事が主眼ですが、コードワークはtoo muchで、彼にとっては束縛になるゆえでしょう。Hadenは彼の良きパートナーとして音楽的に提携し合い、優れた演奏を数多く残しています。
Charlie Haden

本作に於いてHaden的役割を演じるのがElvin Jonesです。多くのセッションで彼のドラミングがバンドを活性化させ、推進力を発揮して演奏のクオリティを高めました。同時にメロディやリズムを彩るカラーリングを巧みに施すと言う、アーティスティックなプレイを展開し、彼が参加したアルバム全てが名作の域に達していると言って過言ではありません。総じて伴奏者としてのElvinのドラミングで右に出る者は存在しないのです。
65年9月録音の作品「Live in Seatlle」を最後にJohn Coltraneの元を離れフリーランスとなり、以降彼との共演はありませんでしたが67年7月17日、わずか40歳で夭逝したColtraneへのトリビュート、ないしはその音楽的継承を果たすべくJimmy Garrison(彼はColtraneバンドに最後まで在籍していました)とのコラボレーションを再開し、Joe Farellを迎え本作と殆ど同じ頃、68年4月同じコードレストリオで「Puttin’ It Together」を録音します。
Puttin’ It Together / Elvin Jones

その後もピアノレス編成が基本でリーダー活動を行い、Dave Liebman, Steve Grossmanたちテナーサックスが2管に増員されたカルテットで、彼の傑作ライブアルバム「Live at the Lighthouse」を72年9月9日(彼の45歳の誕生日です!)録音します。
Elvin Jones Live at the Lighthouse
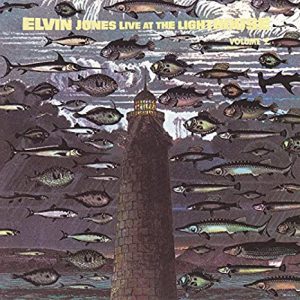
タイム感、グルーブ感、スイング感、シャープでたっぷりとしたシンバルレガート、一聴Elvinの演奏と即断できる彼のプレイは、フロント奏者との絡み具合に真骨頂を発揮します。とは言え常に寄り添いつつ演奏を鼓舞するわけではなく、端正なレガートとスネアのアクセントのみに徹し、ビートを繰り出すだけで、無反応の放置的(笑)演奏に終始する場合もあります。フロント奏者のコンセプトや意向、ソロのラインが醸し出すサウンドから判断しているのかも知れません、ですがこの時のシンプルさにもElvinの美学がふんだんに散りばめられ、3連符を主体としたビートと、他のドラマー誰も持ち合わせない、ずば抜けたポリリズムのセンス、そしてスピード感が堪りません!こちらではLee Konitzの作品61年8月録音「Motion」を挙げたいと思います。
Motion / Lee Konitz

本作の聴きどころのひとつはOrnetteとElvinのコラボレーションです。Garrisonというベスト・パートナーを得たElvinは躊躇という文字を辞書から消し去ったかの如く縦横無尽に、大胆にOrnetteに寄り添い、音楽を構築しています。
それでは演奏内容について触れて行きたいと思います。1曲目The Garden of Souls、メンバー全員によるゆったりとしたルパートのテーマ奏、Garrisonはアルコでサポートします。ここでは芒洋としてはいますが、しっかりとしたメロディが存在し、Ornetteがコンダクトしながら進行しているように聴き取れます。その後Ornetteのフレージングに合わせてElvinが徐にミディアムテンポでシンバルレガートをプレイし、アルトソロが始まります。脱力しつつも気持ちの入ったプレイは、独特のラインを演奏しながら内面に湧き起こる衝動を起爆剤として徐々に展開して行きます。同じサック奏者の観点として、指クセやお決まりの音使いを極力排除して臨んでいると推測できます。そうで無ければマンネリに陥り、自身もインプロビゼーションに入魂できず、演奏のフレッシュさをキープする事は困難です。
Ornette Coleman

Garrisonも次第に演奏に参加しますが、ドラムのフレージングに煽られるかのようにリズム・モジュレーションが行われ、ベースが率先しテンポアップします。Elvin, Garrisonのグルーブ感の素晴らしさと言ったら!引き続きOrnetteのラインに反応するElvin、はたまたその逆もありつつ一つのピークを迎えた後、Ornetteがクールダウンするのに呼応し再び元のテンポに戻ります。当初からのお約束ごとだったのか、自然発生的なインタープレイか、スリリングです!再びOrnetteが仕掛け、再度テンポがアップします。この際のGarrisonの弾くラインの見事さ、加えてElvinのバスドラム連打の凄み、Ornetteのフレーズに確実に応えるElvin、そして更なるテンポアップをGarrison仕掛けますが、これは一瞬にしてElvinに却下されたようです(笑)。落ち着きを取り戻したかのように三位一体がしばらく継続され、その後行われる倍テンポにての演奏、Ornetteのプレイを一音たりとも聴き逃さないリズム隊の真剣さを痛いほど感じます。それにしてもここで聴くことの出来るOrnetteのフレージングの独特さ!そしてアクセントの位置にもオリジナリティを認める事が出来ます。Elvinの締めフレーズで一度収束し、ミディアム・スイングでブルージーな音使い、続いて明るい7th的フレージングの最中でGarrisonが弾き始めたラインに、Elvinが更なる速いテンポでレガートを叩き始め、グルーブが安定し始めるとしばしElvinの猛攻、そして再びクールダウンが訪れます。OrnetteのモチーフをキャッチしたElvinが倍テンポでレガートし、Garrisonがon topでリズムを刻みます。ここで認められるOrnetteのレイドバックしたプレイには、リアル・ジャズマンとしての本質を垣間見ることができます。音楽の森羅万象が行われたが如き、その後フェルマータし短いドラムソロが行われますが、謎の雄叫びが突如として現れます!Dewey Redmanがそれまで行われたOrnetteワールドを一新すべく、テナーサックスのベルをオンマイクにし、声を交えながらブロウしているのです。
Dewey Redman

あれだけの世界をOrnetteに構築されては、特殊技法や離れ業を駆使しなければ自身の存在感を誇示する事は出来ません(笑)!自己主張が強いのはミュージシャンの常、そう言えばPat Methenyの名作「80/81」の欧州ツアー時のプライベート録音では、Methenyや相方のテナーサックスMichael Breckerのプレイに負けじとばかりに、Redmanはひとり延々とソロをプレイしていました(汗)!
80/81 / Pat Metheny
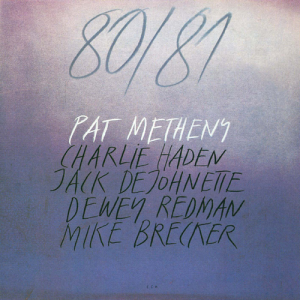
ミディアムテンポに乗りながらのソロ、途中Elvinが倍テンポでレガートし始め、Garissonが追従します。Redmanのフリークトーンに呼応しElvinが連打します。Ornetteとは異なり、フレーズのラインを用いずにフリーフォームを表現しているようです。ほど良きところ、これ以上は蛇足になりかねないと言う所でラストテーマに入ります。エンディングではGarrisonのアルコが、見事に展開されたインタープレイの世界を名残惜しむように、独奏を続けます。
Jimmy Garison

2曲目Toy DanceはいかにもOrnetteらしいテーマを有する、どこか楽しげなナンバー。2管のメロディは本来ユニゾンだと思われますが、微妙にずれたりハーモニー(?)に聴こえたりするのはアレンジなのか、たまたまなのか、ラフに演奏し揺らぎを念頭に置いているのか分かりませんが、寧ろディレイ的な効果から音の厚みを感じさせます。
先発Ornetteは奇想天外でイマジネイティブなフレージングを駆使し、音量の大小も操り、レスポンスを踏まえてリズム隊との会話を楽しんでいるかのようです。彼の吹く8分音符は的確なタンギングが必ず施され、その結果リズムのメリハリが付けられており、その点では伝統を踏まえたジャジーな奏法と言えます。
続くドラムソロはいつものElvinなのですが、Ornette的なリズムのアクセントを踏襲したフレーズも聴かせていて、継続した流れを感じさせます。
続くRedmanのテナーソロは極太な音色と付帯音の豊富さで存在感を示しますが、8分音符にあまりタンギングが施されないためにエッジが効かないレガート感が強く、またリズムもOrnetteに比してラッシュし、前のめりな音符の位置からもリズムの提示度合いが希薄です。この二人の音楽的コンビネーションにはいろいろな捉え方があるように思いますが、Ornetteの「正統派ぶり」を逆に際立たせているとも感じました。
Elvin Jones

3曲目はOrnetteの代表的ナンバーBroadway Blues、本作タイトルともリンクしています。オーソドックスな中にも斬新な感覚が導入された佳曲、Methenyは前述の「80/81」欧州ツアーでもレパートリーとして取り上げていましたが、そもそも彼の75年録音初リーダー作「Bright Size Life」にて次曲Round Tripとを2曲カップリングした形で演奏しています。この2曲をデビュー作で取り上げるMethenyはかなりのOrnetteフリークに違い無いでしょう!
しかもWeather Report入団直前のJaco Pastoriusをベーシストに迎え、ドラマーがBob Mosesというトリオのメンバーで!Jacoの既に凄まじいまでのプレイが印象的ですが、ここではOrnetteのアーシーなテイストは排除され、洗練されたクリエイティブさを表現しています。
Bright Size Life / Pat Methny

ごく初期からOrnetteの音楽に心酔していたMethenyは、彼を迎えた85年12月録音作品「Song X」でOrnette愛を結実させています。彼の音楽に欠かすことの出来ないCharlie Hadenを迎え、そして息子Denardoと名手Jack DeJohnetteのドラムも加えて!
Song X / Pat Metheny

Elvinの得意とするシャッフルのリズムでテーマが演奏されますが、ソロに入るとOrnetteのフレージングの意向を汲んでか、タイムはキープされつつも、様々に変化して行きます。一体どの様にプレイ前にOrnetteがサジェストして、若しくはディスカッションを行い、演奏に臨んだのかに、とても興味を惹かれます。曲ごとにリズム隊のアプローチが明確に変化し、明らかに毎曲コンセプトを変えているからです。
Ornetteは情感たっぷりにブロウし、七変化するElvin, Garrisonのプレイに即していますが、ふたりは二人でOrnetteの演奏を瞬時に捉えてアプローチしており、総じて三人は真の即興演奏を繰り広げているのです!
Redmanのプレイは再び前出の「効果音」奏法を交えて、ホンカー・テイストを感じさせる演奏を聴かせています。暫しの間の後、徐にOrnetteが現れ再びソロを取りますが、Redmanとの説得力の違いを感じます。突然ラストテーマを迎え、Fineとなります。
Ornette Coleman

4曲目には90年CD化された際に追加された、Broadway Bluesの別バージョンが収録されています。オリジナルバージョンよりも幾分遅いテイクで演奏時間も短く、コンパクトな演奏に仕上がっていますが、フォーマットや構成が同様なので寧ろ凝縮された演奏と言えましょう。OrnetteやRedmanのプレイの密度、リズム隊のフレッシュさを鑑みるとこちらが最初のテイクで、演奏の出来が良かったのでもうワンテイクプレイしよう、とオリジナルテイクが録音されたと推測しています。筆者がプロデューサーであればこちらの別テイクを採用したいと思いますが、恐らく冒頭のテーマ・メロディをRedmanが出そびれたり、後半吹き切れていないので、その点が採用基準として考慮されたのではないでしょうか。
Ornette Coleman

5曲目Round Trip、こちらもフロント二人のテーマ奏の微妙な揺れがメロディに幅を持たせています。本作中最も速いテンポのナンバー、リズム隊のコンビネーションの素晴らしさとスピード感、グルーブ感を堪能出来ます。先発Ornetteが比較的短いソロをプレイした後、Redmanがソロを取り、その後サックス奏者達のソロが同時進行で行われますが、その際のElvinの猛攻ぶりと言ったら!疾風怒涛とはこの事を言うのでしょう!程なくラストテーマを迎えます。
Elvin Jones

6曲目We Now Interrupt for a Commercialは本作中最もフリージャズ・テイストの強いナンバー、特にテーマらしいメロディは存在せず、全員同時進行で即興演奏を行います。途中に突然のブレークがあり、曲名がアナウンスされます。彼にしては珍しくビートが存在しない演奏、他とテイストの異なる楽曲は実はアルバムのクロージングに相応しく、to be continued感を表出していると思います。
2021.11.28 Sun
今回はHerbie Hancockの1973年録音作品「Head Hunters」を取り上げたいと思います。彼の最初の大ヒット作、キャッチーにして高度な音楽的内容を讃えた傑作です。
Recorded: September 1973 Studio: Wally Heider Studios Different Fur Trading Co. San Francisco, California Recording Engineer: Fred Catero, Jeremy Zatkin Label: Columbia Producer: Herbie Hancock, David Rubinson
key)Herbie Hancock ts, ss)Bennie Maupin b)Paul Jackson ds)Harvey Mason perc)Bill Summers
1)Chameleon 2)Watermelon Man 3)Sly 4)Vein Melter

膨大な数の作品を発表しているHancock、本作は彼の12作目のリーダー作に該当しますが最初の大ヒットを遂げ、Billboard top 200の13位まで登り詰めました。ジャズファンのみならずロックやR&Bファンにも熱狂的に支持され、以降の彼の音楽的方向性の一つを決定付けました。
初リーダー作62年5月録音「Takin’ Off」でBlue Note Labelから華々しくデビュー、収録曲Watermelon Manがヒットしました。ジャズロックがシーンに流布し始めた時流に上手く乗り、Mongo Santamaria楽団レパートリーにも取り上げられ、以降ヒット街道を突き進むことになりますが、著作権による印税収入が彼の自伝「Possibilities」にて事細かに書かれています。当時New Yorkで共同生活をしていたDonald Byrdのサジェスチョンにより、自作曲の著作権をレーベルに預けず、自己のものにして管理した事が功を奏しました。他にもジャズファンの心をくすぐる逸話が満載で、それこそWatermelon Manのメロディは、スイカを売り歩く行商人の掛け声「スイカはいらんかね〜」が元になったと言われていましたが、実は逆にスイカ売りに声を掛け、呼び止める女性の声「ヘ〜イ、スイカ屋さ〜ん」と知り、この曲に対するイメージが変わりました。またEric Dolphyの64年6月Berlinでの客死の真相については、大きな驚きがあります。
Takin’ Off / Herbie Hancock

Possibilities / Herbie Hancock
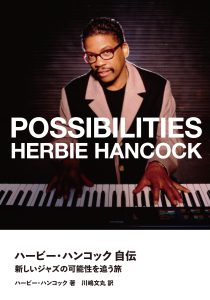
以降アメリカンドリーム、サクセスストーリーをまさに絵に描いたようなHancockのミュージックライフですが、いずれの作品も単なるヒットだけではない、高い音楽性に裏付けされた内容が魅力で、「作品を制作するならばオーディエンスが心から楽しめ、そしてアルバムの購買意欲にアピールする中身を伴わせよう」という強い意志を感じます。ハリウッド映画の如きエンターテイメント性を踏まえ、時代が求めるムーブメントを見極める力、尚且つ自分のやりたい音楽に聴衆を巻き込む吸引力を伴わせる先見性、その結果彼自身がジャズシーンや時代性を作り上げたと言って過言ではありません、しかも楽しみながら、ワクワクしながら!彼に会って話をした事はありませんが、彼の身のこなし、表情や話し振りから大変フレンドリーな人物とイメージしています。溢れんばかりの才能の持ち主ですが、誰にも愛される人柄、そして真摯に音楽に立ち向かう努力家の側面が成功へと導いたと思います。
Herbie Hancock

それでは本作に至るまでの作品群に触れ、大ヒットに至るまでのプロセスを紐解いてみる事にしましょう。63年3月録音の第2作目「My Point of View」は初リーダー作と同様に未だ確固たる音楽性を確立していなかったHerbieをバックアップすべく、Donald Byrd, Hank Mobley, Grachan Moncur Ⅲ, Grant GreenらBlue Note Labelご用達All Starsを配した、同様なジャズロックのコンセプトを掲げています。メンバー中、以降頻繁に顔合わせをする当時未だ17歳(!)の盟友Tony Williamsの参加にHancockの采配を感じます。
My Point of View / Herbie Hancock

この作品直後の同年4月Miles Davis Quintetに入団、Tony Williamsそして Ron Carter, George Colemanらと名盤「Seven Steps to Heaven」をレコーディングします。以降Miles Magicにより飛躍的にHerbieの音楽性が成長し、彼の音楽性を決定付ける事になりました。
Seven Steps to Heaven / Miles Davis

63年8月録音リーダー第3作目「Inventions & Dimensions」録音の頃は前述のキューバ出身パーカッション奏者Mongo SantamariaがカバーしたWatermelon Manがヒットし、Billboard Hot 100で10位、BillboardのR&Bシングル・チャートで8位にランクインされました。その余波でしょうか、ラテン・パーカッションの名手Willie Boboとのコラボレーション作品制作となりました。いわゆる過渡期を感じさせる内容ですが、既にMilesとの共演で培った音楽性を表出させています。
Inventions & Dimensions / Herbie Hancock

64年6月録音第4作目「Empyrean Isles」では遂にHancockの音楽性が明確に提示されました。Freddie Hubbard, Ron Carter, Tony Williamsを擁したカルテットでの演奏、そして魅力的かつ高度な音楽性を湛えたオリジナル曲の表出、間違いなく以降の彼のアルバム制作の原点と言えるでしょう。収録曲One Finger Snapのあり得ないほどのフレッシュさ、スピード感、カッコ良さ!Watermelon Manのマイナー調バージョンと言えるCantaloupe Island、このタイトルもマスクメロンの島という事で、Hancock流のシャレでしょうか(笑)?以降の彼の重要なレパートリーの1曲となりました。
Empyrean Isles / Herbie Hancock

第5作目65年3月録音、彼の代表作である「Maiden Voyage」は前作「Empyrean Isles」にMiles Band共演者のGeorge Colemanを加えたクインテット編成、作曲の才能も一層冴え渡り、名曲のヒットパレードと相成りました。表題曲のほかThe Eye of the Hurricane, Survival of the Fittest, Dolphin Danceと海洋にまつわる楽曲を配した初めてのコンセプト作品、メンバーの秀逸なプレイも相俟って、ジャズプレーヤーとしての彼の一つの頂点として、またモダンジャズのエバーグリーンとしても君臨する作品であります。
Maiden Voyage / Herbie Hancock
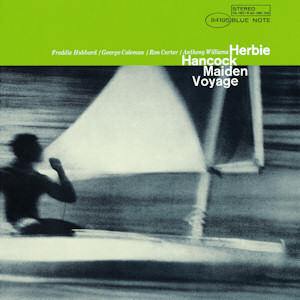
Miles Quintetや様々なバンド、セッションで引くて数多であったHancock、それまでの作品ではフロント楽器がメロディを奏で、その後ろでバッキングを行うサポートが主体だった彼が、68年3月録音第6作目「Speak Like a Child」では自ら前面に立ちオリジナル曲のメロディを弾き、バックにホーンのアンサンブルを従え朗々と演奏します。そのホーン・セクションの構成楽器がまたユニークです。フリューゲルホルン、バストロンボーン、アルトフルート、この3管編成が奏でる柔らかくも深いサウンド、アンサンブル、ハーモニーは通常のホーン・セクションとは異なり、ピアノ演奏を邪魔せずブレンドし、むしろ消されがちな倍音域を持ち上げ、ただでさえ美しいHancockのプレイを一層ゴージャスに彩ります。楽曲のチョイスを含むアレンジャーとしての成熟ぶりも感じさせます。収録曲Riot, The SorcererはMilesの元で既に録音されていますが、ここではまた別次元の演奏を繰り広げ、本作のために書き下ろした表題曲Speak Like a Child, Toys, Goodbye to Childhoodではコンポーザーとしての存在感も見事に表し、演奏、アレンジ、作曲がバランス良く三位一体と化しています。こちらも次なる頂点を極めました。
Speak Like a Child / Herbie Hancock

69年4月録音第7作目「The Prisoner」ではユニークな管楽器編成がバージョンアップし、フリューゲルホルン、トロンボーン、バストロンボーン、フルート、アルトフルート、バスクラリネットの6管編成は通常では考えられない構成によるユニークなサウンド、当時Hancockが研究していたGil Evans, Stravinsky, Ravelからの影響が顕著です。68年5月録音のMiles作品「Miles in the Sky」から既にFender Rhodesを弾き始めましたが、リーダー作では初めてになります。ここでは芸術的で崇高な音楽美を存分に表現していますが、同時にそれまでの作品に比べて難解さの表出は否めません。
Miles in the Sky / Miles Davis

ジャズ的なスパイスが在りつつ耳には心地良く入り、キャッチーで口ずさみたくなるメロディラインを湛え、辿りたくなるような魅惑的なリズムのキメを有するHancockのオリジナルは、聴衆に確実にアピールするテイストを持っていますが、残念ながらここではいつもより希薄です。ジャズミュージシャンに限らず芸術家は自身が探求する対象を掘り下げれば掘り下げる程、孤高の世界に入りがちです。本作で聴かれる内容はむしろ「音楽的に行き着くところまで行ってしまった」ミュージシャンの表現の発露です。
The Prisoner / Herbie Hancock

69年10月〜12月録音第8作目「Fat Albert Rotunda」は長年在籍していたBlue Noteを離れWarner Bros.レーベルからのリリース、米国子供向けテレビ番組のサウンドトラックになります。参加メンバーは前作を踏襲し、曲によってはスタジオミュージシャンを増員して対応しています。アニメ番組のための音楽ゆえ明るくキャッチーな作風の曲目ばかりですが、緻密にして良く練られたアレンジ、曲構成が光り、オーディエンス側に立ったかの如く、前作の反省を踏まえたとも言える作風で「Head Hunters」に繋がるプロダクションを感じます。収録曲Tell Me a Bedtime Storyは名曲ですがQuincy Jones 78年作品「Sounds…and Stuff Like That!!」で取り上げられ、Hancockのソロを採譜しストリングス・セクションが演奏するアレンジには感動しました。
Fat Albert Rotunda / Herbie Hancock

Sounds…and Stuff Like That!! / Quincy Jones
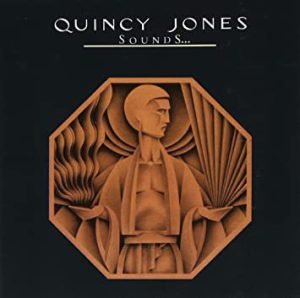
71年1月録音第9作目「Mwandishi」ではレギュラーバンドを組織しました。メンバー全員にスワヒリ語の名前を付け、エスニック色の強いモーダルな演奏を行いましたが、当時のMilesのアルバム「Bitches Brew」「On the Corner」からの影響を感じさせます。全体を覆うおどろおどろしさの中にも実験的な要素を感じさせ、次なるステップ、飛躍の予感を匂わせます。
Mwandishi / Herbie Hancock

第10作目72年2月録音「Crossings」は前作のレギュラーバンドと同一メンバーによる作品、バンドとしての更なる一体感を感じさせます。
Crossings / Herbie Hancock

前作を最後にWarner Bros.を離れ、以降長い付き合いになるColumbia Labelに移籍します。72年後期録音第11作目「Sextant」は3作連続でMwandishi Bandでの演奏、そしてこのバンドの最終作になります。自伝にもこのバンド活動での思い出や逸話が数多くあり、彼自身かなり思い入れがあったのでしょう。芳醇にして緻密、微に入り細に入りアレンジが施され、シンセサイザー演奏、楽器操作やプログラミングに凝り始めた時期でもあるので、様々に実験的な試みが行われていますが、ファンクの要素は未だ皆無です。
アルバムジャケットにも表されていますが、メンバーのルーツであるAfricaのリズム・テイストが基本になっています。
リーダー自身のソロ、バンドアンサンブルもある種極まったものがあり大変素晴らしいと思うのですが、どうでしょう、些かマニアックな方向性を感じます。Hancockのやりたい音楽的方向性は確実に表出しているのでしょうが、多くのオーディエンスに受け入れられるかどうかは別問題です。
Sextant / Herbie Hancock

ミュージシャンとしての表現の発露とポピュラリティーの両立は究極の問題です。Hancockはこの事に対する明確な答えを導き出してくれました。それが今回取り上げたリーダー第12作目にあたる「Head Hunters」です。
1曲目Chameleonはワウを施したシンセサイザーが印象的なベースラインを演奏し始めます。ギターのカッティングと思しきサウンドは恐らくPaul Jacksonのエレクトリックベースによるもの。Harvey Masonのタイトにしてヒューマン、心地良いファンクのグルーヴを聴かせるドラミング、Hancockによるクラビネットを用いたキレの良いリズムの刻み、Mwandishi Bandから唯一の留任Bennie Maupinの、他では聴くことの出来ない豊かな倍音を多く含む極太テナーサウンドによるテーマ奏、何と印象的でキャッチーなのでしょうか!ペンタトニック・スケールを基にした誰もが口ずさめるメロディ、複雑なコード進行を排除したワンコードによる曲の流れ、延々と同じモチーフの繰り返しには一切難解さは含まれず、ひたすらダンサブルである事にJames Brownからの影響も感じます。
もう一つのメロディ・モチーフ、テーマ2がほど良きところで登場し、場面が活性化されつつドラムのフィルインが入り、Hancockのソロへとつながります。この時点で冒頭よりもテンポが幾分早まっているので、クリック〜メトロノームは使用せずに演奏していることが分かります。延々と、淡々とリピートするパターンの上でHancockは縦横無尽にARP Odysseyシンセサイザーを使いリズミックなソロを展開しますが、物凄いストーリーテラー振りです!Mwandishi Bandとは全く異なる、R&Bやソウルバンドと思しきエンターテインメント性を発揮した、新生Hancockサウンドの誕生です!
Herbie Hancock
 さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。
さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。
ファンク・ビートによるノリ易いシンプルなメロディラインの連続でオーディエンスの心を掴み、心地良い高揚感が続く最中に自分達が本当に演りたいジャズ的要素、バンドのインタープレイをとことん、これでもかと行い、素知らぬ顔でファンクビートに戻る。ファンク〜ジャズ〜ファンクのサンドイッチ状態とは良くぞ発案したものです!
それにしても何と凝った構成でしょうか!この曲、そして演奏があったからこそ、その後のHancockが存在するのです。
Herbie Hancock

2曲目はWartermelon Man、アレンジはMasonが担当しています。意表をつくSummersのヒューマンボイスとシンセサイザーによるイントロから重厚なリズム隊がグルーヴを作ります。それらが彼方に向かうかのようにフェードアウトし、メロディが始まります。旋律自体は幾つかの楽器による分業体制、凝っています。曲自体はWatermelon Manですが、全てがリニューアルされ、既存のアレンジを知っているHancockファンには新たに楽しめる要素満載に仕上げられ、Masonの繰り出すリズム、カラーリングは実に楽曲に相応しくサウンドしています。Jacksonのベースの素晴らしさは彼が在日中、自分が何度か共演の機会を持てたことで既知でしたが、本作での演奏を改めて聴くとその物凄さを再認識させられます。ビート感とチャレンジャブルなアイデアが尋常ではありません!
Paul Jackson

3曲目はSly Stoneに捧げられたその名もSly、Hancockが具体的にミュージシャンに捧げて曲を書くことは珍しいと思います。それだけHancock自身も彼の音楽を研究し、尊敬していたのでしょう。曲自体の構成も大変ユニークでリズミック・アンサンブルやテンポが変わり、ソプラノ・ソロが開始しますがリズム隊とのやり取り、クラビネットの刻みとベースが音符を奏でる位置の絶妙さは特筆モノです。オリジナリティ溢れるMaupinのスタイルには当然ですがWayne ShorterやJoe Hendersonとは全く異なるテイストを聴く事が出来ます。74年の初リーダー作品「The Jewels in the Lotus」では美しく奥行きのある世界を提示しています。
The Jewels in the Lotus / Bennie Maupin

Maupinが着火し、更にHancockのソロでリズム隊に火が付きバンドの一体化が有り得ないレベルにまで達していますが、Masonの炸裂ぶりとJacksonのサポートを得てHancockは別次元にワープしそうな勢いです!クールに冒頭のテンポに戻り、無事にFineとなりました。
Harvey Mason

4曲目ラストを飾るのはVein Melter、マーチング風のリズムが印象的な中にミステリアスなムードを湛えた佳曲、シンセサイザーの用い方に独特さを感じます。Maupinはバスクラリネットに持ち替え、マルチリード奏者ぶりを聴かせます。レコード発売当時にChameleonが45回転シングル盤でリリースされた際の、B面に収録されました。淡々と音楽が進行し、最後にバスドラムだけが残り、フェードアウトして行くところに作品のエピローグを感じさせます。
2021.11.14 Sun
今回はMcCoy Tynerの1997年作品「What the World Needs Now: The Music of Burt Bacharach」を取り上げてみましょう。彼のトリオにシンフォニー・オーケストラが加わり、Burt Bacharach珠玉のメロディをMcCoyが華麗に、豪華に奏でるアルバムです。
Recorded: March 5 & 6, 1996 at The Hit Factory, NYC Produced by Tommy LiPuma Recorded and Mixed by Al Schmitt Label: Impulse! All compositions by Burt Bacharach Arranged and Conducted by John Clayton p)McCoy Tyner b)Christian McBride ds)Lewis Nash 1)(They Long to Be) Close to You 2)What the World Needs Now Is Love 3)You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart) 4)The Windows of the World 5)One Less Bell to Answer 6)A House Is Not a Home 7)(There’s) Always Something There to Remind Me 8)Alfie 9)The Look of Love

1962年初リーダー作「Inception」から50年近くに渡り、70枚以上の作品をリリースした多作家McCoy、しかし本作のように特定のミュージシャンの楽曲に拘って制作されたアルバムは殆どありません。尊敬するDuke Ellingtonのナンバーを取り上げた64年12月録音の「McCoy Tyner Plays Ellington」が存在しますが、他にはバンドに在籍し、そこで培われた音楽性がその後のMcCoyの礎となったJohn Coltrane、トリビュートとして彼の楽曲を演奏した87年7月録音「Blues for Coltrane」、91年2月録音「Remembering John」、97年9月録音「McCoy Tyner Plays John Coltrane」3作が挙げられます。1曲から数曲Coltraneナンバーを取り上げたリーダー作品はかなりの数に上りますが、Coltraneの楽曲は彼にとって特別な存在なのです。
McCoy Tyner Plays Ellington

本作はMcCoyのラインナップ中異色の1枚となるわけですが、前作である95年4月録音「Infinity」、当時のレギュラートリオにMichael Breckerを迎えた作品、翌96年グラミー賞Best Jazz Instrumental Performanceを受賞、またColtrane作のImpressionsでMichaelが同じくBest Jazz Instrumental Soloを受賞ということでダブルウイナー、アルバム自体もさぞかしヒットしたことでしょう、そのご褒美として(笑)、大編成によるアルバム録音に結び付いた形になります。
おそらく一度も取り上げた事のないBacharachナンバーを名手McCoyに弾かせ、プレイだけでも十分に表現力がありますが、John ClaytonによるBacharach, McCoy両者の音楽性を細部まで把握した緻密にして大胆なオーケストラ・アレンジにより、今までになかった側面を表出させようとする企画ですが、見事なまでに結実しています。
McCoy Tyner / Infinity
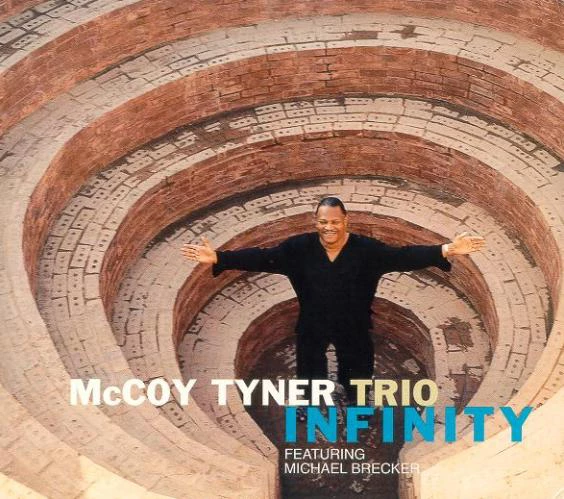
Bacharachは米国を代表する作曲家の一人、彼のナンバーをカバーしたアーティストは1,000以上にものぼるそうです。ジャズミュージシャンもBacharachナンバーを好んで取り上げていますが、本作の様に1枚丸々彼のナンバーとなると限られ、Stan Getzの68年リーダー作「What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David」くらいでしょう、Getzの演奏は元よりRoy Haynes, Grady Tateの華麗なドラミング、当時若手のHerbie Hancock, Chick Coreaの溌剌としたプレイ、そしてRichard EvansとClaus Ogermanのアレンジが燦然と輝く名盤です。
What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David

Stanley Turrentineの68年作品「The Look of Love」は2曲だけですがBacharachナンバーを取り上げています。他にもThe Beatles等のポップス・ナンバーをTurrentineの豪快にしてメローなテナーに存分に歌わせた、こちらはDuke Pearsonの都会的で小粋なアレンジ、オーケストレーションが光るアルバムです。ともすると耳に心地よいだけのBGM演奏に陥りがちな作風が、Turrentineの益荒雄振りにより別次元にまで高められています。
The Look of Love / Stanley Turrentine

60年代後半からこれらの作品の様に、大編成を従えて耳に心地よいメロディを朗々とプレイする演奏スタイルが流行し始めました。枚挙には遑がありませんが、個人的な好みで2作ほど上げたいと思います。
66年11月録音Zoot Simsのリーダー作「Waiting Game」はGary McFarlandの洒脱なアレンジによる、ストリングスを中心としたオーケストレーションが、Zootのスタンダード奏を華やかにバックアップしています。
Waiting Game / Zoot Sims

68年Oscar Peterson Quartetの作品「Motions and Emotions」ではBacharachナンバーとしてThis Guy’s in Love with You、他にSunnyやThe BeatlesナンバーからYesterday, Elenor Rigby等を取り上げ、Claus Ogermanの崇高なオーケストレーション・サウンドと、Petersonの軽妙な演奏がバランス良くブレンドされています。
Motions and Emotions / Oscar Peterson

様々な色合いに輝く宝石の如きBacharachナンバー、あまりにも名曲の数々ゆえ、いずれを選曲するかが問題です。本作のセレクションも妥当であると思いますが、以下は個人的にMcCoyのプレイで聴いてみたかったナンバーです。Raindrops Keep Fallin’ on My Head, This Guy’s in Love with You, Walk on by, The April Fools, Do You Know the Way to San Jose?, I Say a Little Prayer, Wives and Lovers…
McCoy Tyner

本作で素晴らしいアレンジを提供しているJohn Claytonはベース奏者でもあり、2歳年下の弟でアルトサックス奏者Jeff、そして息子Geraldがピアニストを務め、The Clayton Brothersとして8枚のリーダー作を発表しています。またドラマーJeff Hamiltonとタッグを組んだビッグバンドThe Clayton-Hamilton Jazz Orchestra(CHJO)での活躍も目覚ましく、10作以上のアルバムを送り出しています。
John Clayton

これだけ聴き応えがあり、バラエティさ、かつ雄大なシンフォニー・オーケストラ・アレンジ、サックス・アンサンブルをベーシストが書き上げ、指揮した事に驚きを感じますが、ひとえにCHJOで培われたアレンジ能力からでしょう、85年に結成し30年以上に渡りビッグバンドを主催し続けるパワーにも裏付けされています。
The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

本作参加メンバーはMcCoyのピアノの他、ベーシストはChristian McBride、ドラマーにLewis Nash、ビッグバンドやシンフォニー・オーケストラのメンバー記述は一切ありません。ただMcCoy自身のライナーノートに”John had brought excellent people from California”とあるので、活動の本拠地が同地であるCHJOのメンバー参加を意味していると思います。同じく”Jill del Abate had band-picked top caliber New York musicians”との記載はシンフォニー・オーケストラに関し、歌手にしてミュージシャン・マネージメントも行うJill del Abateが、New Yorkトップクラスのスタジオ・ミュージシャンのブッキング手配を行った事を述べているのでしょう。
McCoy独自のコードワーク、4thインターバル、ピアノタッチ、一方Bacharachの複雑なコード進行を内包しつつ、崇高なまでに美的センスを湛えたナンバー群、あまりにも存在感が強く超個性的なこの二者をミックスさせる、貼り合わせる、融合させる役割をClaytonのアレンジが成し得ていて、加えるに有り得ないほどの化学的反応まで引き出しています。下手をすれば水と油になりかねない両者、McCoyに好きなように演奏させるのを主眼に置き、Claytonが自己の叡智を集結させて(バラエティさがハンパありません!)Bacharachの楽曲を膨らませ、再構築し、ピアノプレイとのブレンド感を完璧にしているのはアレンジャーと言うよりも、もう一人の共演者の如きです。ベーシストは文字通り縁の下の力持ち、CHJOでのベースプレイやビッグバンドと言う大所帯を組織して行く技量にも長けている彼は、周囲からも熱い信頼を寄せられる人物、ナイスガイに違いありません。
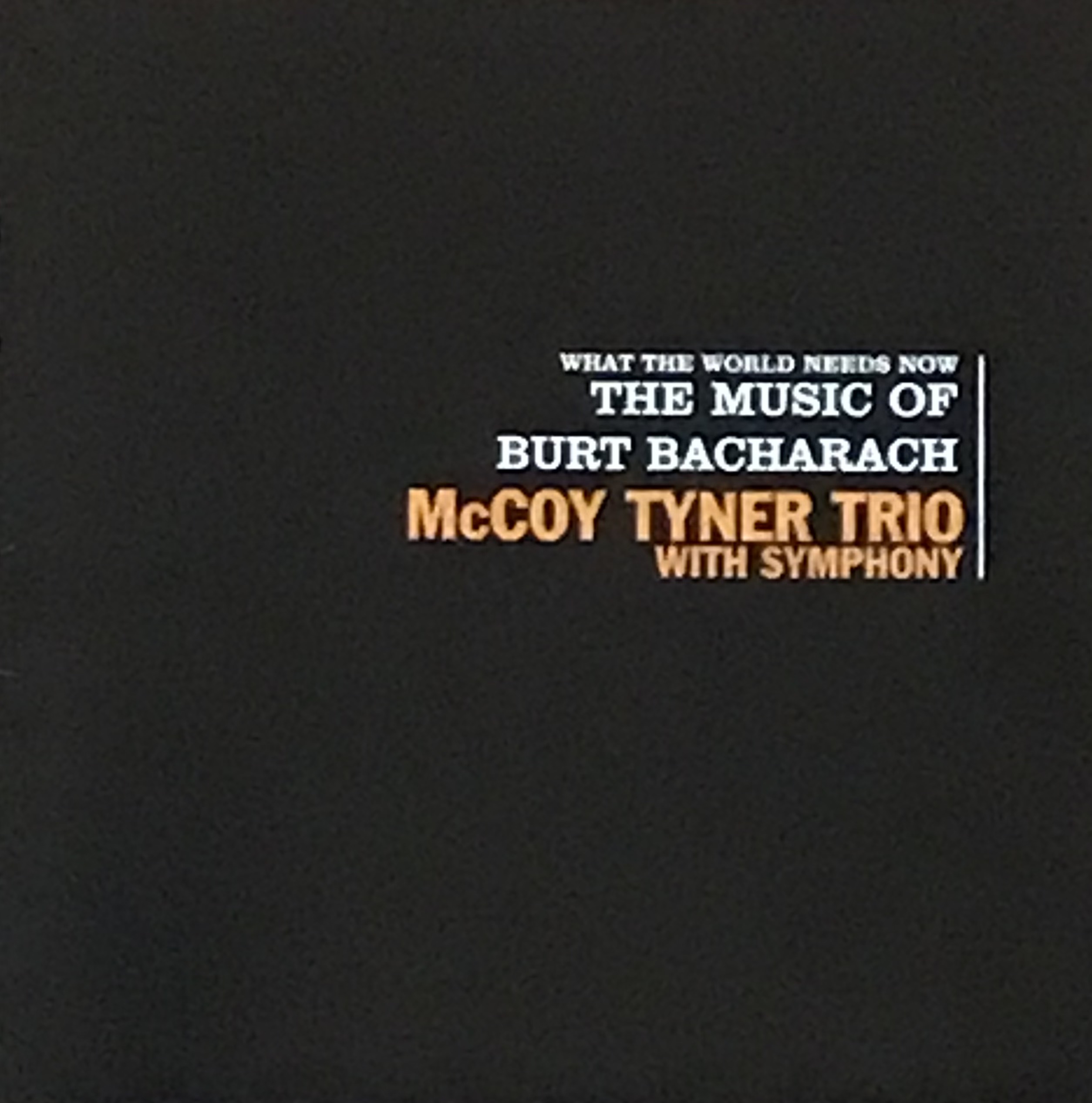
それでは演奏内容について触れて行きましょう。1曲目(They Long to Be) Close to You、早速ストリングスによる重厚で広がりのあるサウンドが迎えてくれます。ドラムの呼び込みフレーズからピアノトリオがイントロを6/8拍子でプレイ、次第にストリングスが覆いかぶさるようにアンサンブルを聴かせ始めます。一瞬のブレークの後、アウフタクトからメロディが始まります。いや、何と甘美な、心地良いメロディでしょう!McCoyが長く音符を伸ばす際にトレモロ奏法を用いているのが新鮮です!テーマ繰り返し時からアンサンブル、ピアノのフィルインが入り、サビではスイングにリズムが変わります。ベース、ドラムの二人はお手のもののグルーブを聴かせます。再び主題に戻りますが、その直前のベルトーン・ライクなアレンジにClaytonの繊細なセンスを感じます。「Go ahead, McCoy!」というメンバーの声が聴こえてきそうな勢いでそのままソロに突入、強力な左手のプレイがMcBrideのベースと確実にぶつかっていますが、それで良いのです!McCoyが雇うベーシストは、歴代彼の左手のプレイを極力邪魔しないタイプの奏者でした。これだけゴージャスに、しかもカラフルなサウンドが鳴り響いていれば低音が不足気味に聴こえてしまいますから!
曲はClose to Youのはずですが全く違和感なくMcCoy World全開です!Nashの堅実でスインギーなドラミングとのコンビネーションも格別です!時々男性の低い声が聴こえますが、これはMcCoyが発していますね!Keith Jarretteのようにのべつ幕なしではなく、感極まった声で雄々しさを感じますが、演奏中に声を出しながらピアノを弾くとは知りませんでした。次第にアンサンブルが鳴り始め、主役はシンフォニー・オーケストラとなります。リタルダンドし、厳かにクラシカルなテイストを湛えたルバートのメロディ奏の後はドラムのロールに導かれ、McCoy再登場、ピアノソロがしばし続いた後、アウフタクトの断片を用いてラストテーマ状態へ、どこを切ってもMcCoyフレーズから成るソロとストリングスが絡みつつ、Fade Outです。
Lewis Nash

本作のタイトルは2曲目What the World Needs Now Is Loveに由来しています。ここでは前奏部分が後の展開を暗示するが如く、厳かに気品を保ちつつ演奏されます。ピアノが訥々と語るように、シンプルにメロディを弾き始め、アンサンブルと対比しながら曲が進行して行きます。アレンジの采配による弦楽器、ウッドウインドとの絡み具合が見事ですね!その後バックでのMcBrideのベースの活躍ぶりは流石です。曲のコード進行に概ね基づきソロが開始されます。プレイが盛り上がりながら、McCoyの声がだんだんと大きくなりますが、入魂ぶりが明瞭ですね、分かり易い方です(笑)。カットアウトされたかの様にソロが終了し、オーケストレーションがクッションとなり、ラストテーマへ。始めと比べかなりテンポを早めていますが、ごく自然なアッチェルと感じました。次第に収束へと向かいますが、シンプルなメロディのナンバーをこれだけ聴かせられるのは、McCoyとClaytonのコンビネーションならではです。
Christian McBride

3曲目You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)ではいきなりアクティブな、4拍目裏のシンコペーションを活かしつリズムセクションが活躍するイントロから始まり、Nashのソロを短くフィーチャーしています。ストリングスに続きサックスアンサンブルが登場し、普通のシンフォニー・オーケストラではない事を宣言しています。オーケストラにはサックス・セクションは存在しませんから。
その後のMcCoyオンステージ、次第にサックスによるバックリフが加わり音量も増して行きます。ピアノによるテーマ奏ではMcCoyがメロディを気持ちよさそうにハミングしています!さぞかし楽しいのでしょう!ピアノソロはテーマの雰囲気を踏襲しつつ、しかし自己の語り口をこれでもかと、聴かせます。次第に物陰に隠れていたかの様に身を潜めていた(笑)、サックス隊のバックグラウンドが鳴り始め、クレッシェンドし、ピアノソロを鼓舞しています。ブレークと共にピックアップ・アンサンブルが鳴り響きます。ジャジーなカラーを存分に表現しつつダイナミクスが半端ない、うねる様に、ねぶるが如くベース、ドラムと絡み合い、ブラスセクションも加わりビッグバンドの完成形を従え(間違いなくCHJOの演奏でしょう!)、グッと音量を抑えてから再びピアノソロへと展開します。ビッグバンドのアンサンブルに十分対抗しうる迫力あるピアノソロはMcCoyならではのもの!ストリングスも付加されゴージャスさが倍増しながらテーマのサビへ、McCoy先ほどよりも声が大きくなった様です!エンディングはひたすら小粋に、スイングジャズのテイストにてFine、終始感を得るべく演奏されるアンサンブルの豪華なこと!最後の最後まで聴き逃すことの出来ないアレンジの妙です!
McCoy Tyner

4曲目The Windows of the World、不安感を煽るかの様な緊張感に満ちたストリングスのサウンド塊からゆったりとしたボレロのリズムが現れます。ピアノのコードワーク、木管楽器のアンサンブル、遠くから聴こえるクラベスの音、本作は各楽器の配置、音像、臨場感等の録音バランスも音楽的です。ピアノが奏でるメロディの合間に入るストリングスやハープ、木管楽器のハーモニーの豊かさや音量のダイナミクス、実に緻密に練られています。
McCoy Tyner

5曲目One Less Bell to Answerはピアノソロから始まります。こんなにも美しい音色でピアノが弾けたらさぞかし気持ちが良いでしょう!木管アンサンブル、ストリングスが包み込み、徐にベースのランニングから意外なインテンポへと繋がります。アレンジ担当Claytonが惜しみなく音楽的アイデアを投入した感が伺えます。シンフォニーのアンサンブルが優しく鳴り響き、基本メロディをピアノが奏でますが、対旋律、オブリガード、コントラバスのアルコに一瞬メロディを担当させたりと、様々な工夫がなされてメロディを浮かび上がらせているのは、楽曲に対する慈愛と受け止めています。何と美しいテイクでしょうか。かつてのボスであったColtraneもこの演奏を聴いたらさぞかし喜んだ事でしょう、もちろんMcCoyの成長ぶりと言う観点です。
McCoy Tyner & John Coltrane

6曲目A House Is Not a Home、個人的にこの曲が大好きです。美と哀愁と崇高さ、これらの絶妙なバランスに何とも言えずグッと来てしまいます!タイトルも意味深で、直訳「家は家庭にあらず」では、不仲な夫婦の住む家を意味しているかの如きですが(汗)、むしろ「貴方が居ないとこの家はただの家、我が家じゃない」のような意味合いで、失恋の唄でしょう。Dionne WarwickやLuther Vandrossの歌唱も素晴らしいですが、本演奏も匹敵しうるクオリティだと思います。
ここではメロディをシンプルに演奏した事で、曲の持ち味を寧ろ明確に表出しています。ソロは60年代のバラード奏がそうであった様に、倍テンポのグルーブを感じさせますが、曲想に相応しくないと判断したのでしょう、ムードが変わるのをグッと抑えています。McBrideが縦横無尽にサポートし、Nashのブラシワークにもセンスを感じます。シンプルであった分、ラストテーマのシンフォニー・オーケストラの活躍が際立ちます。
McCoy Tyner

7曲目(There’s) Always Something There to Remind Me、冒頭ではこれぞ交響曲と思しき勇壮なイントロが演奏され、その後ピアノトリオでストレートにテーマが奏でられます。挿入されるアンサンブルはイントロのムードを踏襲し統一感を感じさせます。それにしてもMcCoyの声の大きな事!ここでは声量が気持ちの入り方のバロメーターです(笑)!前作「Infinity」でのレギュラートリオのメンバー、Avery Sharpe, Aaron Scottたちも優れたプレーヤーですが、本作のようにスタジオミュージシャン的に臨機応変にカラーリングをこなすことは難しかったでしょう。McBride, Nashの職人芸的演奏があってこそです。ピアノソロ後に聴かれるドラムソロがその事を物語っています。ラストではイントロの交響曲がバージョンアップし、アウトロとして付加されています。
Lewis Nash

8曲目AlfieはBacharachが書いたバラードの中でも最高峰のナンバーです。独自なメロディラインと転調、意外性のある旋律の展開はThe BeatlesのYesterdayの上昇するメロディ部分に通じるものを感じます。それでいてしっかりと地に根ざしたオーソドックスさも内包する、曲としての完成度が別次元に位置する数少ない曲の様に思います。
Bacharach曲集を企画してこのナンバーを除外しようものなら、アルバムの売れ行きが半減するのではないでしょうか(笑)。多くのリスナーに愛されているこのナンバーを、McCoyはメロディの一音一音をまるで噛み締めるかのように、愛でながらリリカルに演奏しています。これだけストレートに、メロディフェイクもなくピアノを弾くのはそれだけこの曲が特別な存在であることの証でしょう。LiPumaやClaytonは今回BacharachナンバーをMcCoyに弾かせるに当たり、この曲だけは本当にシンプルに、アンサンブルも必要最小限に絞り、彼のピアノタッチだけで演奏する事を念頭に置いていたように思います。素材の持つ素晴らしさゆえ他の味付けは不用ですから。
Burt Bacharach, Tommy LiPuma, McCoy Tyner
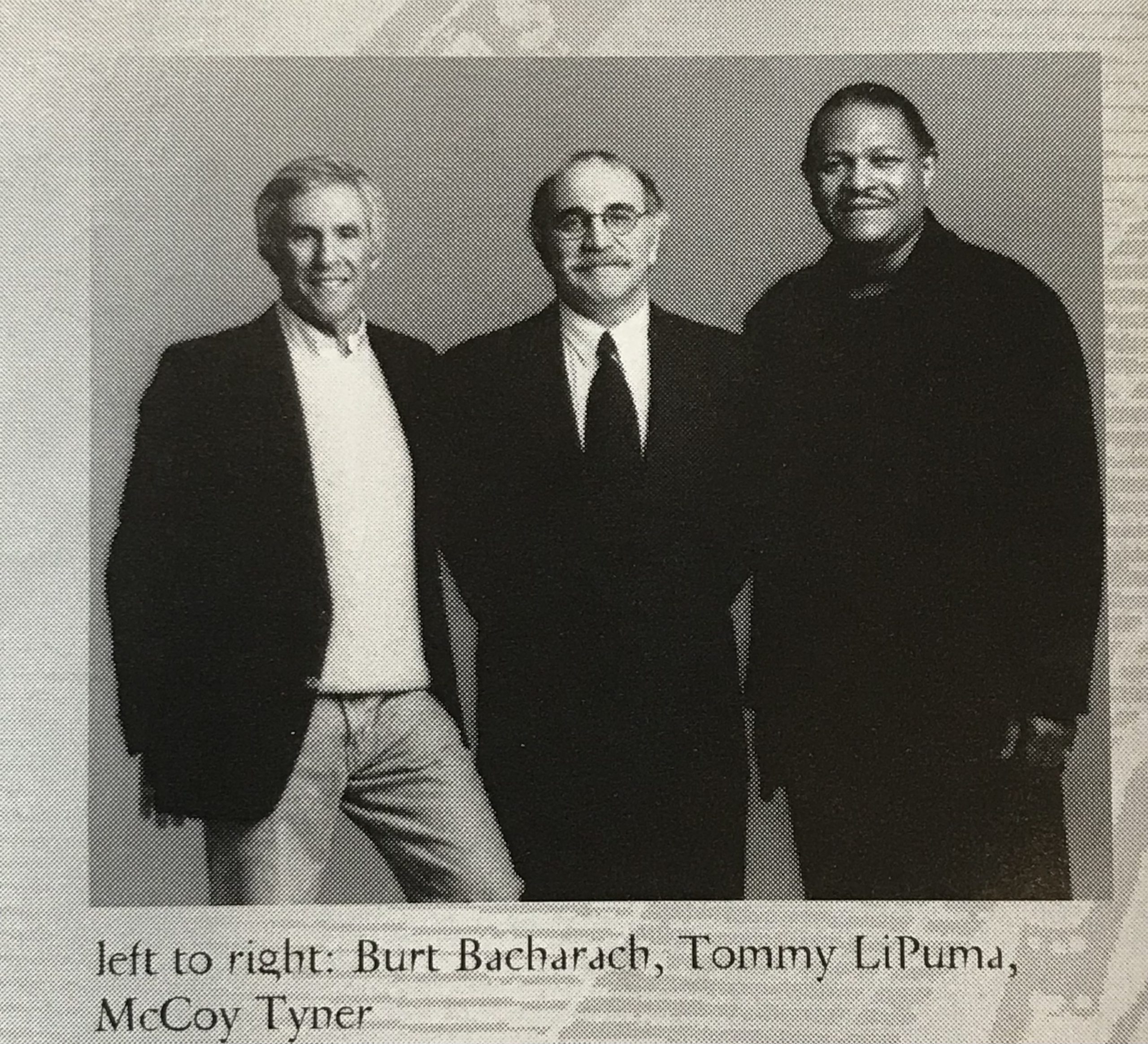
9曲目The Look of Loveも名曲中の名曲です。本作収録のナンバーは基本的にオリジナルなコード進行を尊重していましたが、テーマでは幾つかのリハーモナイズが施され、趣の違ったテイストを聴かせます。
冒頭いきなりのフォルテシモはオーディエンスの気を引くに相応しく、実はシンフォニーに良くある手法のひとつです。アレンジングのアイデアが泉の如く湧き出るClayton、ここでも眩いばかりにアンサンブルを伴った数々のメロディ・フラグメントが提示され、引き続きドラムがEven 8thのリズムを叩き始めます。いかにもMcCoyらしいピアノのイントロが始まり、そのままテーマ奏へ。この曲も同様に美しさが堪らないメロディです。対比としてフルートにもメロディを担当させることで、ピアノの音色の異なる色合いをアピールさせています。
ソロ中お分かりのようにMcCoyの声が凄いですが、彼の書くオリジナルにも美しいメロディが多く、この曲は恐らく自身もかなりのお気に入りで、好みに合致したのでしょう、音楽に猛烈にのめり込んでいるのが伝わります。Nash, McBrideのサポートも全く相応しく、McCoyワールドが盛り上がり切ったところで冒頭のモチーフを再利用し突然にシンフォニー開始、それにしてもここでのClaytonのライティングは本当に素晴らしい!ジャズ的なラインやメロディも交えた壮絶なアンサンブルは難易度が超高く、さぞかし演奏者泣かせだった事でしょう(笑)。オーバーダビングなしの一発録音の様に自分には感じるのですが、であれば演奏者の力量にも神がかったポテンシャルを痛感します!コンダクティングのClaytonもさぞかし大変だったでしょう!シンコペーションを伴ったアンサンブルから、全くナチュラルにMcCoyのソロに戻りますが、手に汗握る瞬間でした!暫し後ラストテーマに繋がり、エンディングにもこれでもか、とモチーフを投入するClaytonの鬼才ぶりに再び惚れぼれしました!凝りまくりのアレンジを施したこの曲、クロージングに相応しい演奏に仕上がりました。
2021.10.31 Sun
今回はFreddie Hubbardの61年8月録音リーダー作「Ready for Freddie」を取り上げたいと思います。オリジナルを含む佳曲揃い、申し分ないメンバーとのインタープレイ、そして弱冠23歳リーダーFreddieのフレッシュさ、炸裂するトランペットが輝く作品、彼の作品群の中でも筆頭に挙げられるべき秀逸なアルバムです。
Recorded: August 21, 1961 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey Label: Blue Note(BST 84085) Producer: Alfred Lion tp)Freddie Hubbard euphonium)Bernard McKinney ts)Wayne Shorter p)McCoy Tyner b)Art Davis ds)Elvin Jones
1)Arietis 2)Weaver of Dreams 3)Marie Antoinette 4)Birdlike 5)Crisis
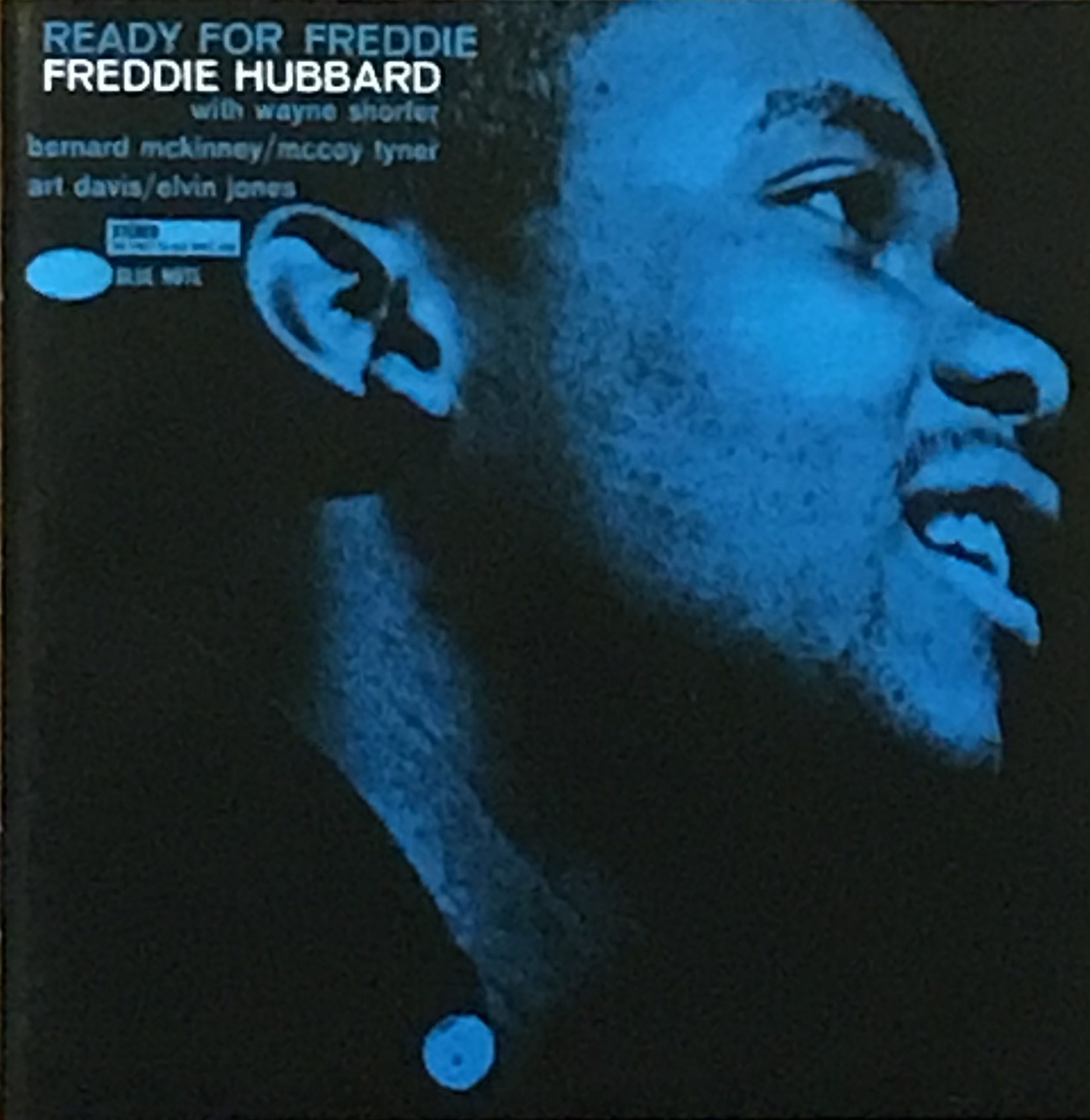
50年代からジャズシーンには早熟で個性的なトランペッターが続々と現れました。Clifford Brownに始まりLee Morgan, Booker Little, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Randy Brecker, Tom Harrell, Wynton Marsalis, Nicholas Payton…Freddieは彼らの中でも突出した音楽性と音色、テクニック、タイム感を引っ提げてデビューしました。ドラマーにも神童を多く輩出していますが、特にトランペットは若くしてその才能を発揮出来る楽器なのでしょう、60年6月22歳にして初リーダー作「Open Sesame」を録音、鮮烈なデビューを遂げ同年11月に「Goin’ Up」、61年4月「Hub Cap」と立て続けに半年間のスパンでリーダーアルバムを録音しました。1~3作目は共演者やスタンダードナンバーに演奏曲目を負うところがありましたが、本作では作曲能力が開花し、代表的なオリジナルを披露しています。以降も多くの名曲を生み出す彼、本作はそのスタートラインとなりました。
多くの若手ミュージシャンに共通する、短期間での著しい成長、トランペットプレイにその事は顕著で、歯切れの良い明瞭なメッセージと豊かなイメージのインプロビゼーションを繰り広げ、驚異的に正確でスインギーなタイムの取り方が他のトランペッターよりも頭一つ、いや二つも三つも抜きん出た個性となり、圧倒的な存在感を示しています。
59年21歳から始まるサイドマンとしてのプレイも充実しています。そこではソロプレーヤーだけではなく、ホーン・アンサンブルでのリード・プレイにも長け、Art Blakey’s Jazz Messengersでは10作に参加しており、Lee Morganの後釜としてWayne Shorter, Curtis Fullerとの3管編成で、いずれに於いても素晴らしいアンサンブル、ソロを聴かせます。61年録音「Mosaic」ではFreddieのオリジナルDown Underと本作収録Crisisの2 曲、「Three Blind Mice」では自身の名曲Up Jumped Springを披露しています。
Mosaic / Art Blakey & the Jazz Messengers

Three Blind Mice / Art Blakey & the Jazz Messengers

Eric Dolphyとは60年4月録音「Outward Bound」、64年2月録音のDolphy没後に発表された傑作「Out to Lunch」にも参加しています。
Outward Bound / Eric Dolphy

Out to Lunch / Eric Dolphy
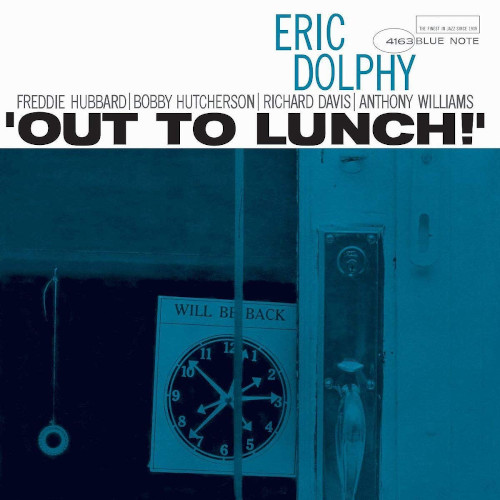
J. J.JohnsonとはClifford Jordanを加えた3管編成による60年4月録音「J. J. Inc.」、最初期の演奏ながらソロとアンサンブルに非凡さを示します。
J.J.Inc. / J.J. Johnson

John Coltraneの61年録音「Ole」では盟友Dolphyと共にクリエイティブなプレイを聴かせます。
Ole / John Coltrane

Ornette Colemanの歴史的問題作にして傑作60年12月録音「Free Jazz」に参加、フロント陣Ornette, Don Cherry, Dolphyたちに比較して調性的にインサイドなテイストを感じさせます。ひとりFree Jazzには徹しきれていないとも言えますが、端正なビートを繰り出すリズムセクション上でのフリーフォーム演奏、Freddieは美しい音色で誰よりもグルーヴしています。
Free Jazz / Ornette Coleman

Oliver Nelsonの傑作61年2月録音「Blues and the Abstract Truth」ではセンス、音色、タイム感、他の追従を許さないトランペット・プレイを展開しています。
The Blues and the Abstract Truth / Oliver Nelson
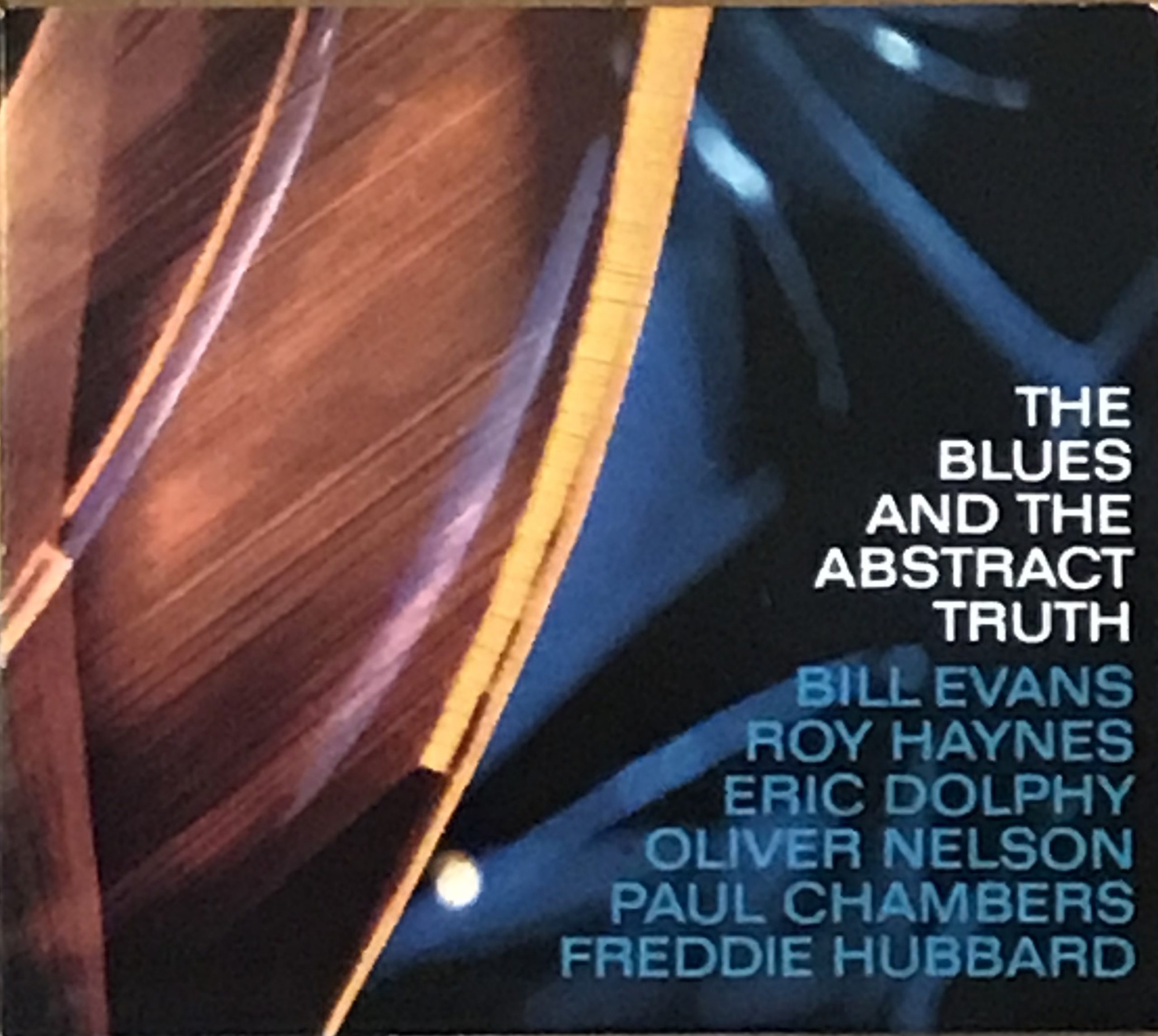
渡欧する直前のKenny Drewを捉えた60年11月録音「Undercurrent」では、外連味なくハードバッパーとしての本領を発揮しています。
Undercurrent / Kenny Drew

Freddieは以降も精力的に演奏活動を続け、リーダー作、サイドマン、ライブやコンサートと、変わらぬスタンスでブリリアントなプレイを展開しました。しかしどんなミュージシャンにも旬はあるでしょう。またプレーヤーとして同じ所に留まっていることに抵抗があるのは当然の事です。Freddieを心から敬愛し、彼のプレイを追い続けている大勢のトランペッターに共通する発言があるので、ここでご紹介しましょう。
「Freddieの演奏はどれも良いね。特に60年代中頃までが本当に素晴らしく、Herbie Hancockの「Maiden Voyage」頃までのプレイは神懸っているよ。以降の演奏も悪くはないし、凄いのだけれど、彼は何か変わってしまったように感じるんだ。どうして変わってしまったのだろう?何が違うのかな?」褒め言葉と批判とが混じり合う的確な意見、実は僕も同じ見解です。
例えば76年6月Hancockの代表作「V.S.O.P」での演奏、どの部分を切り取っても、紛れもないFreddieのプレイ、素晴らしい事この上ない、至上のテイクばかりで、ハイノートや多種奏法を含めたハイパーな楽器テクニックから、トランペットの腕前に飛躍的な向上を確認出来ます。
V.S.O.P. / Herbie Hancock

ですが60年代中頃までと比較すれば何かが大きく異なります。これは感覚的なものなので文章で表現するのは難しく、不十分な点もあるかも知れません。
初々しさを原点とし、自身が演奏する内容に関しての新鮮さ、そして自分の演奏、吹くラインに意外性を感じ、結果刺激され、更なる別なラインが湧き出てくる。当時の彼の頭の中には実に様々で独創的なサウンド、ハーモニー、フレージングが誰よりも鳴り響いていたのだと思います。共演者の演奏や楽曲により、彼の創造性に着火し、それらが全く自然に引き出されます。トランペットを手にし、息を吹き込む直前に「一体この後どの様な展開が待ち受け、オレはどんな事を吹くのだろう?それにしてもエキサイティング、楽しいぜ!」と頭を過ぎり、プレイに臨んでいたのではないでしょうか。60年代のプレイは常にワクワク感が彼の演奏を支配していたのです。
60年代後半から70年代以降、Freddieのプレイは凄みを増して行きますが、反面次第に定型化に向かいます。本人はその事への葛藤が必ずやあったと思いますが、不定型の極みであった彼の演奏、言わば天から振り降りてくるジャズ・スピリットをトランペットを媒体としたイタコ状態での表現でした。
一般のオーディエンスには彼の心の不協和音は伝わる事はなく、圧倒的な演奏からスーパートランペッターとして君臨していました。漸次ワクワク感が希薄になり、しかし盛り上がった演奏を提供しなければならない、「こうあらねばならぬ」使命感を持った彼は形を成すためにテクニカルな手法で表現するに至りました。とはいえ他のトランペッターとは比べものにならない程、ポテンシャルとして豊かな表現力が備わっています。どんな時でも聴き応えのある、ウタを感じさせるプレイを繰り広げる事が出来ます。演奏の深さは別として。
赴くままにトランペットを自在に吹きまくった当時20歳そこそこの天才トランペッターの旬は、実はデビューから数年であったかも知れません。
もうひとつ、64年6月Berlinにて医療ミスが原因で36歳の若さで客死した盟友Eric Dolphy、彼についてFreddieがインタビューを受けた記事を読んだことがあります。Dolphyの逝去に対し哀悼の意を述べつつ、しかしはっきりと、あれだけの才能がありながら、彼は貧しさの中で亡くなった。自分は彼のようにはなりたくない。金儲けをしながら音楽活動を続けていきたい、のような趣旨の発言だったと記憶しています。人間誰でも貧困は回避したいものです。経済的安定があってこその生活、トランペット・プレイ、しかしこの事はジャズを演奏する上で不可欠なハングリーさとは真逆な方向の場合もあります。金銭のために音楽を演奏することは至極当たり前な事ですが、もしかしたらFreddieの場合はそちらの方が主体になってしまったのかも知れません。
Freddie Hubbard

それでは収録演奏について触れていきましょう。リーダーFreddieの他メンバーは、ジャズでは珍しいユーフォニウムにBernard McKinney、彼はトロンボーン奏者でもあります。テナーサックスに盟友Wayne Shorter、ピアニストはMcCoy Tyner、ベーシストArt Davis、ドラムスにElvin Jones、リズム隊はJohn Coltrane Quartetのメンバー、Davisは準レギュラーとしてColtraneがベーシストを増員し、ダブル・ベース・フォーメーションにする際駆り出されていましたが、レスポンスの早い巧みな伴奏を行うプレーヤーです。McCoyの初リーダー作62年6月録音「Inception」はこのメンバーで演奏されています。
McCoy Tyner / Inception

1曲目FreddieのオリジナルArietis、いや〜カッコ良いナンバーです!イントロの構成からしてアイデアをふんだんに盛り込んでいて、3管のハーモニーが実にサウンドを豊かにしています。ユーフォニウムはトロンボーン的に扱われ、アンサンブルの一番下のパートを担当しているようです。McKinneyとは59年録音Slide Hamptonの初リーダーアルバム、7管編成にしてピアノレスの意欲作「Slide Hampton and His Horn of Plenty」にて共演、ここでのアンサンブル力を買われて抜擢されたのだと思います。本作には61年23歳にして夭逝した天才トランペッターBooker Littleも参加し、熱い演奏を聴かせています。
Slide Hampton and his Horn of Plenty

テーマにも同様に工夫がなされ、実に聴きどころ満載の佳曲ですが、アップテンポにも関わらずごく自然な音量の大小から成るダイナミクスが設けられ、Freddieの曲作りに対する美学も感じます。ソロの先発はFreddie、いや、これまた素晴らしいタイム感で、申し分の無い8分音符の長さ、位置の提示、そして音符の推進力に思わず脱帽してしまいます!前述の「J. J. Inc.」とは比べ物にならない成長ぶりです!何をどの様に練習すればこんなタイム感を習得出来るのでしょうか?そしてアドリブソロの構成の巧みさ、ストーリーの語り口、フレージングの終止感、ニュアンスの豊富さ、いずれも素晴らしく、最高得点の5つ星を進呈したいと思います(笑)
McCoyの的確なバッキング、Elvinのどっしりとしていてシャープなドラミング、Davisのプレイも申し分なく、リズムセクションは万全の大勢でサポートします。続くソロイストはShorter、Freddieの吹いたフレーズをキャッチして極太でダーク、コクがあって存在感のある音色を携えての登場、フレージングやアイデアにone & onlyを聴かせます。
それまでのFreddieリーダー作のテナー奏者はTina Brooks, Hank Mobley, Jimmy Heathと続きましたが本作で真打登場です!以降両者は親密な関係を築き、音楽的にも絶妙なコンビネーションを聴かせることになります。
続くMcKinneyのソロはユーフォニウムという難しい楽器を巧みに扱い、ジャズ・テイストを織り込んだソロを聴かせます。McCoyはクリアーで端正なタッチと共に比較的オーソドックスではありますがスインギーなソロを奏で、ラストテーマへと続きます。
Freddie Hubbard

2曲目はスタンダードナンバーWeaver of Dreams、この曲はA Weaver of DreamsやYou Are a Weaver of Dreamsとも表記されるVictor Youngのナンバー、John Coltraneの59年2月録音の名演奏(Cannonball Adderley Quintet in Chicago収録)を忘れることは出来ません。
Cannonball Adderley Quintet in Chicago

イントロではテナーとユーフォニウムのアンサンブルから始まり、最後にトランペットが加わりその後テーマが始まります。何と澄み切ったストレートな音色で、メロディを奏でているのでしょう!23歳の若者の表現とは思えません!その後比較的唐突に、倍テンポに持って行くべくターンバックがあり、トランペットソロが始まります。この当時バラード奏はテーマ後に倍テンポでプレイされる事が多かったと思います。流麗にして饒舌、しかし楽器の発音や絶妙なタイム感が作用し、決してtoo muchにはならないショウケースを聴かせて行きます。続くFreddieと同い年のMcCoyのソロもリリカルにして当時最先端のセンスを駆使したプレイを聴かせます。ラストテーマは再びバラードに戻り、フェルマータを経てトランペットのcadenzaが始まりますが、Elvinのスネアドラムの一発が絶妙です!このアクセントは他のドラマーではまず入ることはありません。さすがElvin!その後はFreddieふくよかなトーンを響かせてFineです。
Elvin Jones

3曲目はShorterのナンバーMarie Antoinette、16小節を繰り返した32小節のフォームから成る比較的シンプルなナンバー。とは言え3管編成からなるジャジーで重厚なアンサンブルと、ピアノのフィルインが印象的です。ソロは作曲者自身から、含みを持たせた独特な音色とタンギング、ミステリアスなフレージングは曲のセカンドメロディをその場で吹いているかのように、フレーズを吹くというよりも作曲を行なっている様に聴こえます。それにしても決して流麗ではなく、ゴツゴツとした8分音符によるラインはShorter以外の何者でもない個性を振りまいています。続くトランペットソロは一転して滑らかで流暢な8分音符による淀みないプレイ、フレーズの抑揚やコントロール感は、あり得ないほどのテクニシャンぶりです!ユーフォニウムソロの朴訥感が対照的に聴こえます。McCoyのソロは美しいタッチとFreddie的なリズムのツボを押さえたタイム感で、スインギーにプレイします。その後のDavisはエッジの効いた深い音色で、テイスティなソロを聴かせ、ラストテーマに入ります。この間Elvinの抑制の効いた、しかし様々な表情を見せるシンバル・レガート、スネアのフレーズが隠し味となり、各ソロイストを徹底的にサポートしています。
エンディングはCm7とA♭7を繰り返してフェード・アウトです。
Wayne Shorter

4曲目はFreddieの書いた名曲Birdlike、Charlie Parkerのフレージングやリズミックなフィーリングを用いて書かれたブルース・ナンバー、タイトルもそこに由来します。その後もV.S .O.P.のレパートリーとして、またGeorge Cablesの79年録音作品「Cables’ Vision」でも再演されていますが、盟友であるトランペッターDonald Byrdに捧げて後年タイトルをByrdlikeと変更しました。
イントロもキャッチーで印象的、テーマのメロディはFreddieならではのワクワク感がここでも強力に発せられています。先発ソロはトランペットから、迸るフレーズとアイデアは淀みなく止まるところを知らず、聴き惚れてしまうほど達人ぶりを発揮していて、スピード感があるのに音符の位置は後ろというタイムに只管脱帽です!McCoyのバッキングも的確なサポートぶりを聴かせます。続くShorterのソロ、ニュアンスや語法は彼そのものですがFreddieの演奏に刺激されたのか、いつもより明確にフレーズを吹く、具体性を伴ったアプローチを聴かせます。ソロを終える際にシングルタンギングを用いたフレージングがユニーク過ぎです!ユーフォニウムのソロでは「お猿のかごや」的フレーズが聴かれるのが微笑ましいです。その後はMcCoyの端正でスイング感溢れるソロに続き、ベースのソロではピアノとドラムがバッキングを次第に止め、アカペラでプレイされますが、トリッキーなフレージングによる演奏にも関わらず、「せえの!」と全員見事にラストテーマに突入します。ジャムセッション形式でソロ回しが行われましたが、ここでも徹底したElvinの伴奏が各ソロイストの持ち味をくっきりと浮かび上がらせています。
Cables’ Vision / George Cables
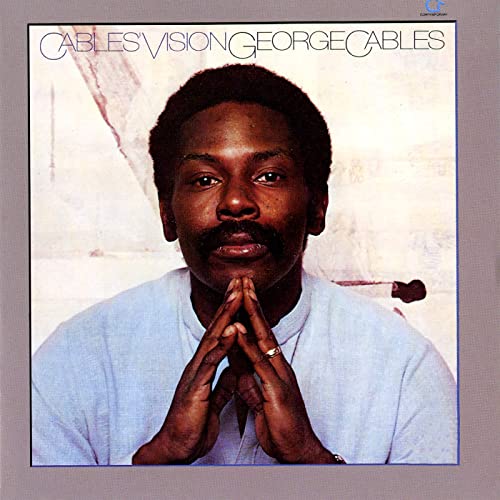
5曲目もFreddieのオリジナルCrisis、2ヶ月後に前述の「Mosaic」で再演されますがElvin, Blakeyという2大ドラマーでの演奏の比較も面白いです。テンポ設定はほぼ同じか「Mosaic」の方がやや早め、タイム的にはElvinの方がたっぷり、どっしり、そしてバックビート感が素晴らしいですが、Blakeyの方は例のナイアガラロール、更に曲のTutti的アンサンブル部分でダイナミクスを極端に付けているので、かなりインパクトがあります。初回テイクのプレイを踏まえて、更にJazz Messengersでの演奏ということで方向性を明確にしたのでしょう。各ソロイストもBlakeyのドラミングに触発され、いずれもコンパクトではありますが派手なプレイに徹しています。Shorterは「草競馬」のメロディを引用、実は初演時既に若干匂わせており、ここでは明確に吹いているのがご愛嬌です(笑)。個人的にはFreddie, Shorter共に落ち着いて内省的なソロを展開し、特にMcCoyのピアノのバッキング全般、そしてソロが曲のカラー、サウンド的に合致している点で初演の方に軍配を挙げたいと思います。「Mosaic」には無いドラムソロもElvinだからでしょう、音楽的な充実感を演奏に添えています。
Bernard McKinney

04年発売The Rudy Van Gelder Edition CDには1曲目Arietisの別テイクが収録されています。本テイクよりも早めのテンポ設定、その分収録時間も短めですが各人のソロもホットなテイストを感じ、特にFreddieのソロはテンポアップした分一層スリリング、Elvinのアプローチにもアグレッシブなものが聴かれます。推測するに、良いテイクを録音出来たのでテンポを早くしてワンモアテイク、のような雰囲気で再チャレンジしたのでしょう。しかしオリジナルテイクの方が他メンバーがリラックスしてスポンテニアスに演奏に臨んでいますし、テンポが曲想に合致している様に聴こえます。本テイク採用の判断基準はこちらでしょう。
2021.10.17 Sun
今回はオルガン奏者Freddie Roachの1964年リーダー作「Brown Sugar」を取り上げて見ましょう。テナー奏者Joe Hendersonの参加が異色ですが、彼の冴え渡る演奏が魅力的な、隠れた名盤です。
Recorded: March 18 & 19, 1964
Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Label: Blue Note(BST 84168)
Producer: Alfred Lion
org)Freddie Roach ts)Joe Henderson g)Eddie Wright ds)Clarence Johnston
1)Brown Sugar 2)The Right Time 3)Have You Ever Had the Blues 4)The Midnight Sun Will Never Set 5)Next Time You See Me 6)All Night Long

ジャケットの黒人女性はClara Lewis Buggs、Grandassa Models(GM)と呼ばれる60年代から70年台にかけてNew YorkのHarlemで開催されたアフリカ系アメリカ人女性の美を競うコンテストに参加した、オリジナル・メンバーの一人です。本作に次ぐ64年10月録音のRoach5作目アルバムで、コーラスをフィーチャーした「All That’s Good」、こちらのジャケットにはRoachとGMの女性たち6名がおさめられています。美女に囲まれてさぞかしご機嫌だった事でしょう(笑)。おそらくRoachは彼女たちのファッションショーでの演奏や、付随する音楽団体The African Jazz-Art Society & Studioのコンサートに出演したのがきっかけで、GMとのコネクションが出来たのだと思います。

タイトルのBrown Sugarとは黒砂糖などの白色でない砂糖の総称、また別の意味、スラングとして黒人女性や阿片を指します。
実は際どい意味のタイトルを冠した本作のリーダーFreddie Roachは、生涯8作のリーダーアルバムをリリースし、うちBlue Note Label(BN)から5枚を発表しており本作は4作目に該当します。
一連の作品はコンセプトを感じさせる選曲やアレンジの妙、構成の面白さからエンターテインメント性ある作品に仕上がっています。
基本的なバンド構成としてオルガン、テナーサックス、ギター、ドラムの4人編成、作品によってはトランペットやコーラスが加わる事もありました。こちらはその4人編成、オルガン奏者がリーダーでリズム&ブルースが基本にあり、かつジャズのテイストも表現する場合に最も相応しいフォーメーションです。
BNの5作では全てClarence Johnstonがドラマー、タイトで実に小気味好いグルーヴを聴かせています。ギタリストにはKenny Burrellが演奏する事もありましたが、本作ではEddie Wrightが参加、テナー奏者はHank Mobleyのクレジットも見られますが、同じオルガン奏者Jimmy Smithとも共演しているPercy France、Roachと何作か共にしているConrad Lester、彼らのテナープレイには強力な個性がある訳ではないのですが、さりげなくブルージーなプレイを聴かせる事を信条とした、何方かと言えば地味で裏方的な、言わばサイドマン・タイプのサックス奏者です。それだけに本作だけが突出したかのように、超個性派Joe Henderson参加が意外性を有し、どこまで彼のオリジナリティ豊かなスタイルが発揮されるのかに興味が集中します。
まさかオルガンサウンドにテナーが埋没することはないでしょうし、バランス感を大切にする彼ですから独壇場もあり得ないでしょう、リーダーのオルガンを立てつつ、Joe Henカラーがどの程度、どのように披露されるかイメージが膨らみます。
Joe Henderson

BNにはJimmy Smithを筆頭に多くのオルガン奏者が名を連ねています。Jimmy McGriff, Reuben Wilson, Baby Face Willette, Richard Groove Holmes, Ronnie FosterそしてLarry Young。彼らの作品が数多くリリースされ、同傾向のアーシーなプレイを聴くことが出来ます。唯一”オルガンのColtrane”と呼ばれたYoungはモーダルでアグレッシブな演奏、Youngの作品にもJoe Henが参加し、名演奏を繰り広げています。65年11月録音「Unity」、盟友Woody ShawにJoe Henと相性抜群のElvin Jones、申し分のない共演者を得て縦横無尽にブロウしています。
Larry Young / Unity

その後のYoungは69年にThe Tony Williams Lifetimeで「Emergency!」、Miles Davis「Bitches Brew」といった歴史的作品に参加します。
Larry Young

Youngの活動の更なる発展形がLarry Goldingsのオルガンをフィーチャーし、Jack DeJohnette, John Scofieldたち名手が脇を固めたバンド、Trio Beyondの04年録音「Saudades」、Tony Williams Lifetimeに捧げたプロジェクトの素晴らしいライブレコーディングです。

Smithにはオルガンの第一人者としての風格あるプレイが、Youngの演奏には従来のオルガン奏者らしからぬ個性を湛えたサウンド、ハーモニー感がありますが、Roachも含めた他のオルガニストたちに突出した個性を見い出すことは難しいです。それでも多くの奏者が存在し、アルバムがリリースされ続けたのは、米国ではオルガン〜Hammond B3という楽器が大変ポピュラーな存在だからです。そもそもが教会では高価だったパイプオルガンの代替として登場し、日曜礼拝やミサで日常的にその音を耳にしていた事の効能でしょう。教会音楽〜ゴスペル〜R&Bに根ざしたブルージーな演奏スタイルを多くの聴衆が受け入れ、愛聴していたのも当然の流れです。米国だけではなく英国に於いてもロック〜プログレッシブ・ロックのジャンルでオルガンは人気を博し、シンセサイザーが台頭するまでその存在感は不動のものでした。
Jimmy Smith

オルガンジャズ演奏は様式美で成り立っています。4o年代から50年にかけてのビバップからハードバップも同様に様式美に根ざしていますが、特にビバップではごく狭い範疇に属する、エリア内でのしきたりを踏まえない限りビバップにはなり得ません。しかし同時にそこから抜け出そうとする動きも必要になるのですが、ハードバップに関してその様式美はややルーズで許される傾向にあると思います。
オルガンジャズに関してはどうでしょうか。感じるのはビバップよりもっと狭いエリア内での様式美であり、というか楽器編成がビバップ〜ハードバップよりも制限(されているのかどうか、実際のところ分かりませんが)されているので自ずと定まった様式になります。そこに起因するのかも知れませんが、様式の中から抜け出そうとするジャズ的なムーブメントは必要なく、ひたすら保守的に、オルガンが奏でる重厚で支配的なサウンドの伴奏を務める事で音楽が成立しています。
そういったしきたり内で演奏することがオルガンジャズの流儀と察知していたのか、本作でのJoe Henのプレイはとことんオルガンの繰り出すサウンドのサポートに徹しています。いつもの彼の演奏と照らし合わせてみると、かなりアプローチを変えてブルージーさ、ファンキーさのテイストを表出していますし、テナーの音色さえも異なった色彩を感じさせています。
しかもそれらは無理なく、至極自然に発せられ、寧ろ楽しげな雰囲気さえ漂わせています。Joe Henのプレイからはホンカーを感じたことはあまりなかったのですが、ここではかなりの度合いで発色されています。
Joe Henderson(and Eric Dolphy)

そもそも含みを持ち、極太にしてハスキーな成分がトーンをデコレーションし、益荒男ぶりが半端ない音質にホンカーの要素が内包されていましたが、彼独自のフレージング、ソロのアプローチがホンカー色を隠蔽していたように思います。本作でのオーソドックスなプレイにより、Joe Henのホンカー体質が露出したと言えましょう。
他にもここでの普段は聴かれないニュアンスや、至る所で聴かれるフレージングの捻り、そして何よりバラード演奏での「Joe、今までその吹き方を隠していたでしょう!」とまで感じさせる(笑)、かつて聴いたことのない奏法に、鳥肌が立つほどの感動を覚えるのですが、同時に彼の表現の幅広さに唖然としてしまいます!
71年に短期間ではありますが、かのBlood, Sweat and Tearsに参加していたことがあり、いくらホーンセクションを有したバンドとはいえ、ロックバンドにJoe Henの参加を俄には信じられませんでしたが、翻って考えてみると、自身を様々に変容させて柔軟に音楽に対応させていく姿勢の持ち主であることを感じ、本作でそのカメレオン・スタイルの本質をはっきりと捉えることが出来たのです。
Blood, Sweat and Tears

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目は表題曲RoachのオリジナルBrown Sugar、ストップタイムを効果的に用いた変形のブルースナンバー。リズムとしてはツイスト、ダンスのためのナンバーです。RoachのフットワークによるベースとJohnstonのドラミングのコンビネーションの素晴らしさに、まず耳が奪われます。トップシンバルがon topに位置しスピード感をもたらしており、オルガンプレイもタイトで軽快なので、とてもスインギーです。ギターのカッティングが隠し味的にプレイされており、グルーヴのタイトさに貢献しています。
そこにJoe Henのテナーメロディが加わるのですが、何かいつもと異なります。よくよく聴けばチューニングがかなり低めに設定されています。彼は通常高からず、低からずの丁度良いところのピッチで演奏しているのですが、たまたまなのか、低めにチューニングする事によりブルージーさを出そうと狙ったのか分かりませんが、僕にはかなり低めに聴こえます。
演奏は吹き過ぎず、抑え過ぎず実に曲想に合致したコンセプトでプレイしています。Joe Hen節と言える譜割りのトリッキーさを表現したアプローチは影を潜め、8分音符をかなりハネ気味に吹き、ジャンプナンバーの如くブロウする様に、チューニングの低さも合わさり「Joe Henの影響を受けた未知のテナー奏者か?」とまで思ってしまいます(笑)。途中に聴かれるオルタネート・フィンガリングを用いたフレーズ、これはホンカーのお家芸です!
続くRoachのプレイも素晴らしいタイム感で説得力を感じさせます。Joe Henのバックリフも効果的、もっと聴きたいところでラストテーマが登場、途中いきなりのブレークがありRoachが”Now where you think you’re going girl”と呟きます。実際にダンスをしている人たちを思い描き作曲したこの曲、彼自身の設定としては最初の12小節でツイストを踊り、次の12小節でバップに変わり、8小節で折り返し、そしてツイストに戻ります。盛り上がっているはずなのに人々の様子があまりに平静で、女の子たちが席に戻るのも見えたので”One more time”と言う代わりにこの言葉を述べたそうです。
Freddie Roach

2曲目The Right TimeはRay Charlesバンドのブルースナンバー、オリジナルよりも遅めにテンポが設定され、Rayの歌の部分をオルガンが、女性コーラスをJoe Henのテナーが担当します。
オリジナルの途中女性の声でシャウトされる部分はオルガンの分厚いハーモニーと、テナーのどこかユーモラスなフィルインによって表現されています。続くテナーソロは間を活かしつつ、比較的Joe Hen度の高いテイストでプレイされます。再びシャウト・コーラスを経て、オルガンソロもひょうきんさを忘れないセンスで演奏されラストテーマへ、テナーのピアニシモでのバックリフとその後のシャウトでの音量の違い、ダイナミクスが印象的なテイクです。
Joe Henderson

3曲目Have You Ever Had the BluesはLloyd Price楽団のナンバー、Priceの歌をテナーとギターがハーモニーで奏で、オルガンがビッグバンドのアンサンブル部分を演奏します。ほぼ原曲に忠実に再現されますが、4人編成とは思えない分厚く緻密なプレイを聴かせ、オルガンソロもイケイケ、テナーも随所にバックリフを吹き、豪華さを演じています。ソロはオルガン、テナーと続きますが、Joe Henは本作中最も彼らしさを表現しています。しかもホンカーテイストもふんだんに交えながら!同じフレーズの繰り返し、反復がホンカーの特徴の一つですが、見事にホンカーとJoe Hen節が両立した演奏に仕上がっています。バックのサポートともよく絡み合っており、そのバランス感に敬服してしまいます!
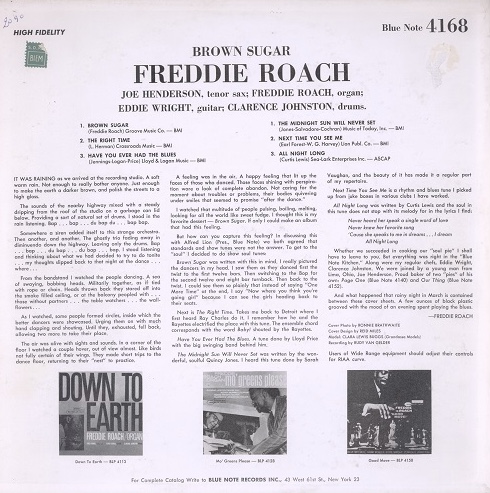
4曲目The Midnight Sun Will Never SetはQuincy Jonesのペンによるナンバー、この演奏収録が本作の価値を圧倒的に高めました。逆にこのテイクが存在しなければ、ごく普通のオルガン・アルバムとして多くの中に埋没していたかも知れません!
まず曲自体が素晴らしいです。Quincyが北欧の白夜を目の当たりにし、その印象で書き上げた名曲、曲想とメロディライン、タイトルが三位一体で合致しています!
Roach自身はSarah Vaughanの歌を聴き、あまりの美しさに打たれてレパートリーに加えたそうです。そのテイクは58年7月録音、Quincyがアレンジ、指揮も担当したアルバム「Vaughan and Violins」に収録されています。
Sarah Vaughan / Vaughan and Violins
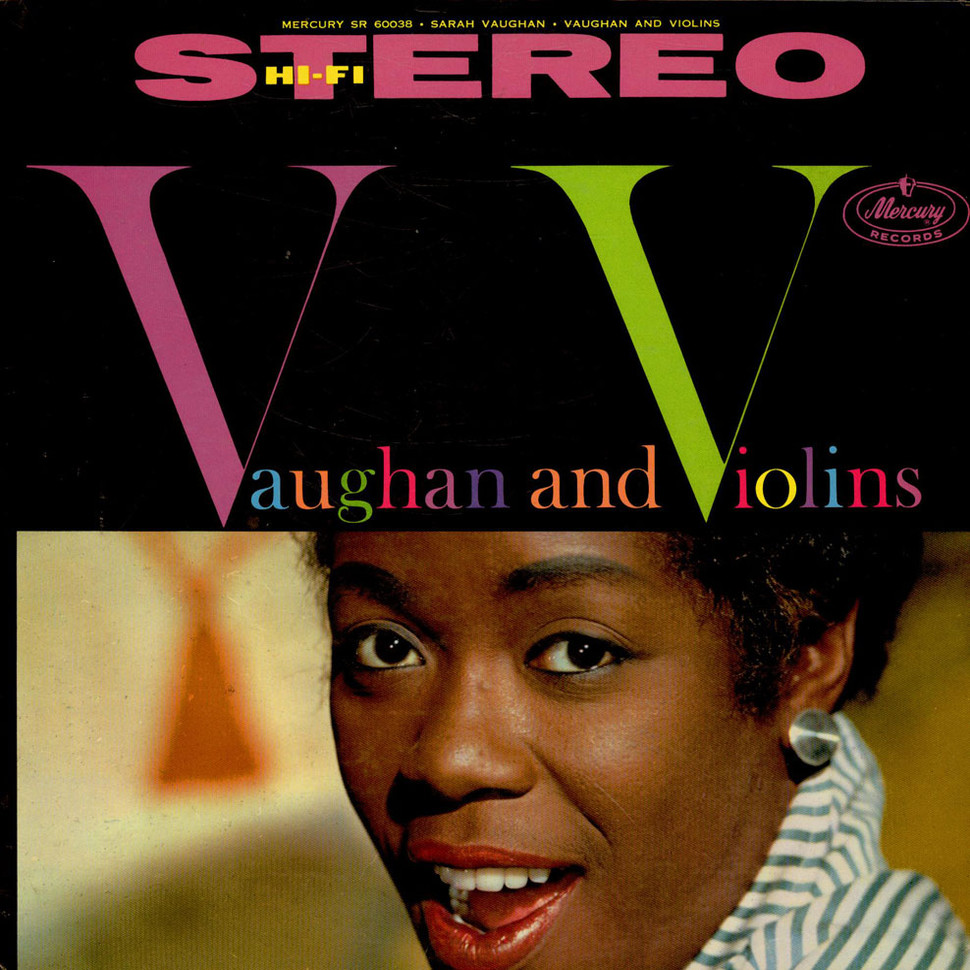
Count Basie楽団の名リードアルト奏者、Marshall Royalの名演奏も大変印象的、59年作品「Basie One More Time」に収録されています。蕩けるようにスイートなプレイはDuke Ellington楽団の同じくリードアルト奏者Johnny Hodgesと並び称されました。こちらでもQuincyがアレンジャーを務めています。
Count Basie / Basie One More Time

Vaughanの歌唱、Royalのアルトプレイも素晴らしいのですが、本作の演奏も全く引けを取りません。それどころか実はこちらの方が真打ちかも知れないと思っています。Joe Henの繰り出す崇高な美学がオルガン演奏とケミカルに反応し合い、この曲にまた違った生命を吹き込みました。
イントロはギターとテナーの織りなすユニゾンと対旋律から始まります。この時点でJoe Henの吹き方、音色がいつもと違う事に驚かされます。まずおそらく限界まで、これ以上小さく吹いたら音にはならない、という超ピアニッシモで低音域を吹いています。表記としてのピアニッシモはppですが、ここでのJoe Henはppppほどのピアニッシモ振りを聴かせます(笑)
「ジュワー」「シュー」「スー」という息の音から音になりかける臨界点での発音、こんな吹き方のJoe Henを聴いたことがありません!しかしこの吹き方でオルガンの音とのブレンド感が何倍にも増幅したと感じます。
ドラムが2, 4拍目に比較的強くアクセントを入れています。このアプローチは純然たるジャズドラマーではまず行われない奏法ですが、この演奏ではオルガンジャズゆえでしょう、too muchには感じません。ギターのバッキングにもカッティングに近いアプローチが聴かれますが、同じようにバラードにも関わらず音の多さが気になりません。
アウフタクトから始まるテーマはまずオルガンが担当、対旋律をテナーが吹きつつ、次のメロディのセンテンスではテナーがリードしギター、オルガンがハーモニーに回ります。ビブラートを極力排したメロディ奏はMarshall, Sarahとは真逆のプレイです!この部分をリピートし、繰り返し時にはJoe Henのニュアンスが微妙に変化しますが、ここに男の色気を感じます!
サビの8小節はテナーがメロディを担当、同様にストイックなまでに抑揚を排除したストレートな吹き方は、素晴らしい音色を持つサックス奏者だけに許されるもの、トーンのクオリティが勝負です!
サビ後の主題部分ではまた同様に演奏され、オルガンのソロが始まります。ピアノと違い音を幾らでも伸ばせるのはバラード奏時の特権です。
その後サビからのテナーソロは、特殊奏法を然りげ無くメロディに用いた出だしから開始、しかし幾らでも多種多様なアプローチを取ることの出来るJoe Henですが、ここではまるでその素晴らしい音色を聴かせるために、そしてオルガンジャズにコンセプトを合わせて、敢えて長い音符を中心に演奏しているかのようです。音量もppをずっとキープし、エアリーなサウンドを徹底的に聴かせます。サビではオルガンがメロディを演奏し、続く主題部分は冒頭と同様に演奏されます。
演奏は何度聴いても次から次へとまた別な音が聴こえてくる、永遠に枯れない泉のごときニュアンスの宝庫たるプレイ、全てがナチュラルな所以に違いありません。
Quincy Jones

5曲目Next Time You See MeはR&Bナンバー、56年にJunior Parkerが録音したものがヒットしました。ここではそのバージョンを踏襲し、ボーカルパートをテナーとオルガンが演奏、ブルースフォームをシャッフルのリズムで演奏しています。Roachは彼が出演していた色々なジャズクラブのジュークボックスからこの曲を拾い上げたと言っています。全員とても楽しげに演奏しているのが伝わって来るリラックスしたプレイ、ドラムやオルガンのフィルイン、ギターのカッティングの確実なハマり具合、Joe Henの吹かなさ加減(笑)、レイドバック感、どれも絶品です!
Joe Henderson

6曲目All Night LongはCurtis Lewis作曲、Ray CharlesやAretha Franklinの名唱があり、メロディだけにとどまらず、歌詞の内容自体も素晴らしいとRoachが述べています。
本作2曲目のスローナンバー、分厚いオルガンの和音とギターのメロディによるイントロから始まります。RayやArethaは情感たっぷりに、比較的声を張って歌唱していましたがJoe Henはムーディに、サブトーンを中心にピアニッシモで演奏しています。マイナーの曲調に合わせブルージーに、ベンドやグリッサンド、またビブラートを多用しており、先程のThe Midnight Sun Will Never Setとは全く別な側面を存分に披露しています。
極めて渋いテナープレイの後ろでは、ドラマチックにオルガンがサウンドを鳴らし、メロディに合わせたストップタイムも効果的に行われます。しかしこれだけ「シュウシュウ」「シュワー」と情感たっぷりにR&Bナンバーを演奏し、大変な説得力を聴かせるとは、Joe Henの懐の深さを痛感しますが、しかしこの時26歳!早熟にして、人生の酸いも甘いもを知り尽くしているかのようです。
2021.10.03 Sun
今回はJoe Hendersonの66年1月録音リーダー作「Mode for Joe」を取り上げてみたいと思います。
Recorded: January 27, 1966 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs Label: Blue Note(BST 84227) Producer: Alfred Lion
ts)Joe Henderson tp)Lee Morgan tb)Curtis Fuller vibes)Bobby Hutcherson p)Cedar Walton b)Ron Carter ds)Joe Chambers
1)A Shade of Jade 2)Mode for Joe 3)Black 4)Caribbean Fire Dance 5)Granted 6)Free Wheelin’

63年Blue Note Label(BN)にて「Page One」でセンセーショナルにデビューを飾ったJoe Henderson、本作は同レーベル5作目に該当します。作品中編成が最も大きいトランペット、テナーサックス、トロンボーン、ビブラフォンのフロント4人にリズムセクションが加わった7ピースになります。フロントの厚みのあるアンサンブルの豪華さ、メンバー書き下ろしの素晴らしいオリジナル、スリリングなソロの応酬、なかんずくJoe Henのインプロビゼーションのハイクオリティさが光り、諸作の中でもキャッチーさが抜きん出ています。
しかし本作を最後にBNを離れ、66年に設立されたOrrin Keepnewsが主催するMilestone Labelに移籍します。そこで更なる意欲作を発表し続ける事になるのですが、本作はBN在籍3年にしてレーベルお抱えの代表的ミュージシャンを擁した総括的作品と言えるでしょう。
リーダー作のほか、BNにはサイドマンとして短期間で25作以上に参加し、しかもその多くがレーベル代表作でした。Joe Henのエグく、かつジャジーな演奏があってこそ成り立つこれらの作品群により、自身はBNの顔として君臨していました。Joe Henロスに創設者Alfred Lion, Francis Wolffの二人はさぞかし肩を落とした事と思います。とは言えその後もBNのレコーディングには参加し、67年McCoy Tyner「The Real McCoy」、69年Herbie Hancock「The Prisoner」等での名演奏で引き続き存在感を示しました。
Alfred Lion and Joe Henderson

本作内容に触れる前にBNリリースのリーダー4作について、その足跡をざっと辿ってみましょう。記念すべき第1作目「Page One」、テナーケースを置き、取っ手を指で軽く持ちながら壁にもたれ掛かり、上着のラフさを気にせずポーズを取る印象的なジャケットには初々しさを感じます。63年7月3日録音Kenny Dorham, McCoy Tyner, Butch Warren, Pete La Roca、Joe Henが尊敬するDorhamとのコラボレーション第一弾でもあります。名曲Blue Bossa, La MeshaのDorhamオリジナル2曲を取り上げ、自身のオリジナルで以降も取り上げる機会の多かったRecoda Meほか、Homestretch, Jinrikisha等の佳曲を披露しています。
演奏は良く言えば比較的穏やかに、端的にはいつものJoe Henのキレをさほど感じさせません。何かに拘っていたのか、共演者のプレイに気になる事があったのか、後年顕著に現れる、如何なることがあろうとも「委細構わず」邁進する明快なアプローチは影を潜めています。初リーダー作ということで緊張感が支配したのかも知れません。とは言えJoe Henの演奏は明確に自己のスタイルを聴かせ、オリジナル曲を中心に、気鋭のミュージシャンとクリエイティヴな演奏を展開するという定型を、既に披露しています。
「Page One」
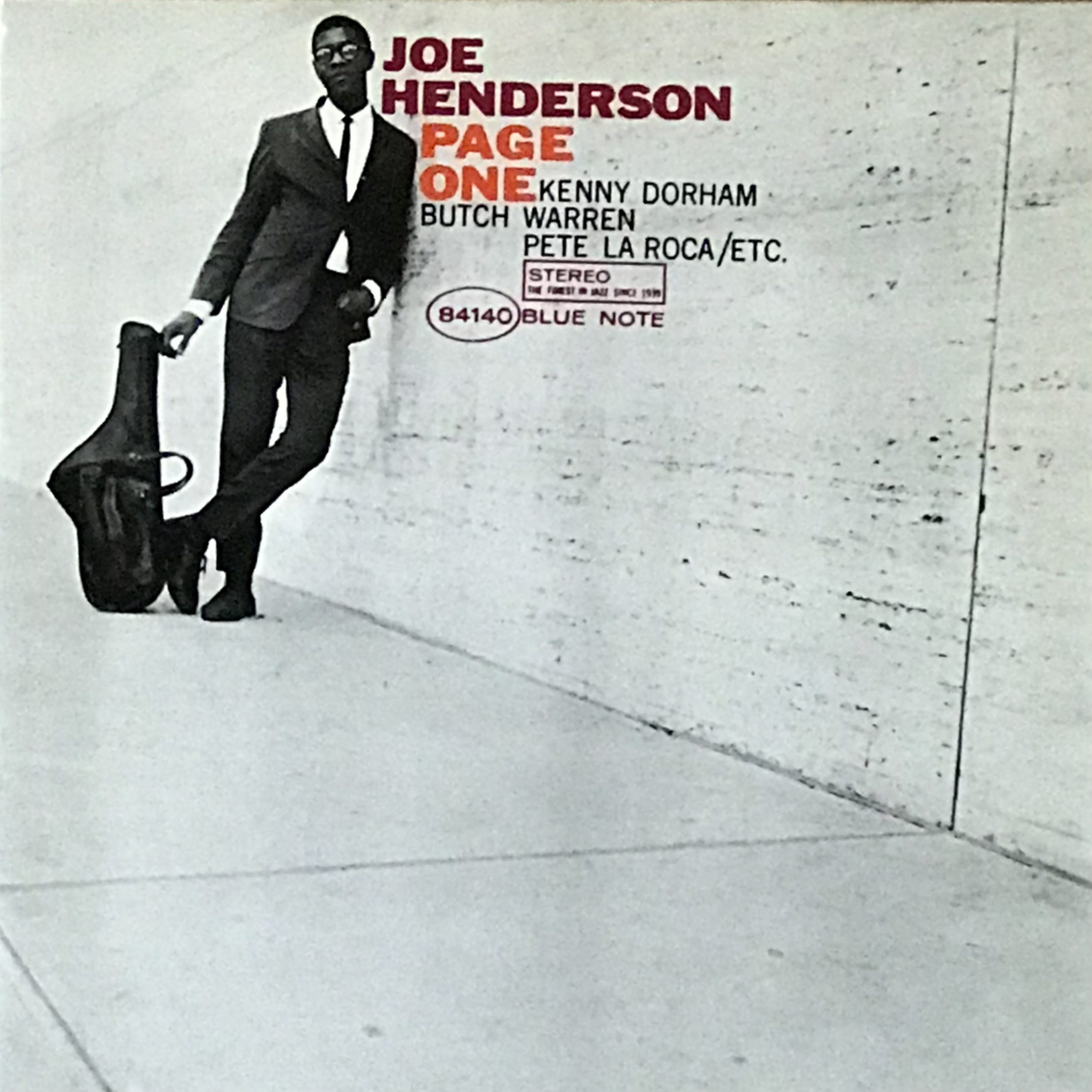
第2作目「Our Thing」、初リーダー作から僅か2ヶ月、同年9月再びスタジオ入りしました。メンバーはDorham, La Rocaが残留しベーシストにEddie Kahn、ピアニストにはその後Joe Henとの共演が頻繁になる鬼才Andrew Hill、彼が参加の場合の多くはオリジナル曲演奏を伴いますが、本作では演奏者としてだけになります。ここではDorhamが3曲、Joe Henが2曲持ち寄りました。
曲自体は凝った内容なのですが、メロディラインやリズムに今ひとつ華がなく、収録曲全てに同様な印象を受けるので、BNリーダー作の中で最も地味な感触を持ちます。1, 2曲Hillのアブストラクトなオリジナルを収録すれば、カラフルな作品に仕上がったように感じます。
BNにはレコーディングを行なったもののオクラ入りし、後年リリースされたケースの作品がかなりの数あります。中には30年以上経過してから発掘され、やっと日の目を見たアルバムも存在しますが、作品の出来栄えに何らかの不満を抱いたプロデューサーの判断によるものでしょうか。もしかしたら本作も危うくオクラ入りするところだったかも知れません。
「Our Thing」

第3作目はReid Milesの秀逸なジャケットデザインが輝く「In ‘n Out」。 BNはシンプルにしてアピール度が高いジャケット・デザインの宝庫ですが、本作はその最たるものです。Milesは56年から67年まで10年以上BN最盛期のジャケットデザインを手がけ、そのアルバム数は400枚を超えます。54年にAlfred Lionのもとにデザインを持ち込んだ事から始まるそうで、自身の売り込みがあった訳ですね。そのセンスから彼はジャズ好きと思われがちですが、意外にも殆ど興味を示さず、クラシック音楽を好んで聴いていたそうです。
BNのレコードはRudy Van Gelderの録音、Alfred Lionのプロデュース、統率力、Francis Wolffの撮影するミュージシャンの写真、そしてReid Milesのアルバムデザイン、この4者が土台となり、その上に絶妙なバランス感で名演奏の数々が構築されたのです。
Reid Miles

64年4月10日録音、Dorhamだけが残りリズムセクションは一新されます。McCoy Tyner, Richard Davis, Elvin Jonesの重量級トリオを迎えて、人選に違わぬ素晴らしい演奏を繰り広げています。そしてJoe Hen書き下ろしのオリジナル3曲のいずれも素晴らしい事と言ったら!表題曲In ‘n Outは独創的なイントロ、バンプが挿入されるブルースナンバー、斬新なメロディラインと崇高な雰囲気、スピード感が同居しますが、Joe Henの書くブルースのテーマは本当にどれも素晴らしい!!
残念なのはDorhamがテーマを吹き切れていない点です。この事で折角のハイパーなメロディラインの印象が半減してしまいました。彼の書く曲とDorhamのテクニック、表現力にかなりの開きが生じ始めたのでしょう。
Elvin jones

Elvinの強力なシンバル・レガートとポリリズムが鳴り響くドラミング、McCoyの4度のインターバルを強調したフローティングなバッキングの連続、Davisの重厚でElvinとのコンビネーションも抜群なベースワーク、このトリオを従えたJoe Henのプレイはまさに水を得た魚状態、続くMcCoyのソロもこれまた炸裂しています!物凄いです!ひとえにJohn Coltrane Quartetでのコンビネーションの成せる技でしょう!続くDorhamのソロは悲しいかな、このメンバーの中では埋没せざるを得ないクオリティです。
続くPunjabの曲構成も秀逸です。イントロのトリッキーさには目を見張るものがあり、リズムセクションとのメロディ輪唱も行われています。曲自体はナチュラルさを湛え、ストレートに耳に入ってくるのですが、様々な事象を緻密に組み合わせたブレンド感が絶妙、まさしくJoe Henのアドリブそのもの、美しく、イマジネイティブでしかも毅然とした音楽です。彼の作曲能力の充実ぶりはそれは見事なもの、格段の進歩を感じさせます!自身のソロも曲想を踏まえつつ、しかし遥かその向こうの次元にまで飛翔するほどの、スケールの大きさを感じさせるものです。”ブッ飛んでいる”と表現するのが相応しいでしょう!リズム隊とのコンビネーションも申し分なしです。
そしてSerenityは50年代の古き良きジャズのテイストと、時代を反映した斬新さのバランス感にしてやられます!ミュージシャンの間でも流行ったJoe Henチューンの一曲です。
「In ‘N Out」

余談になりますが「Page One」でも同様に、ジャケットに記載されるべきMcCoy Tynerのクレジットがこちらでもetc.と扱われているのは、当時所属していたImpulse!レーベルとの契約上の措置なのでしょう、63, 4年発売のMcCoy参加アルバムでの特徴です。64年リリースWayne Shorterの「Night Dreamer」でもEtc扱いが見られます。
「 Night Dreamer」
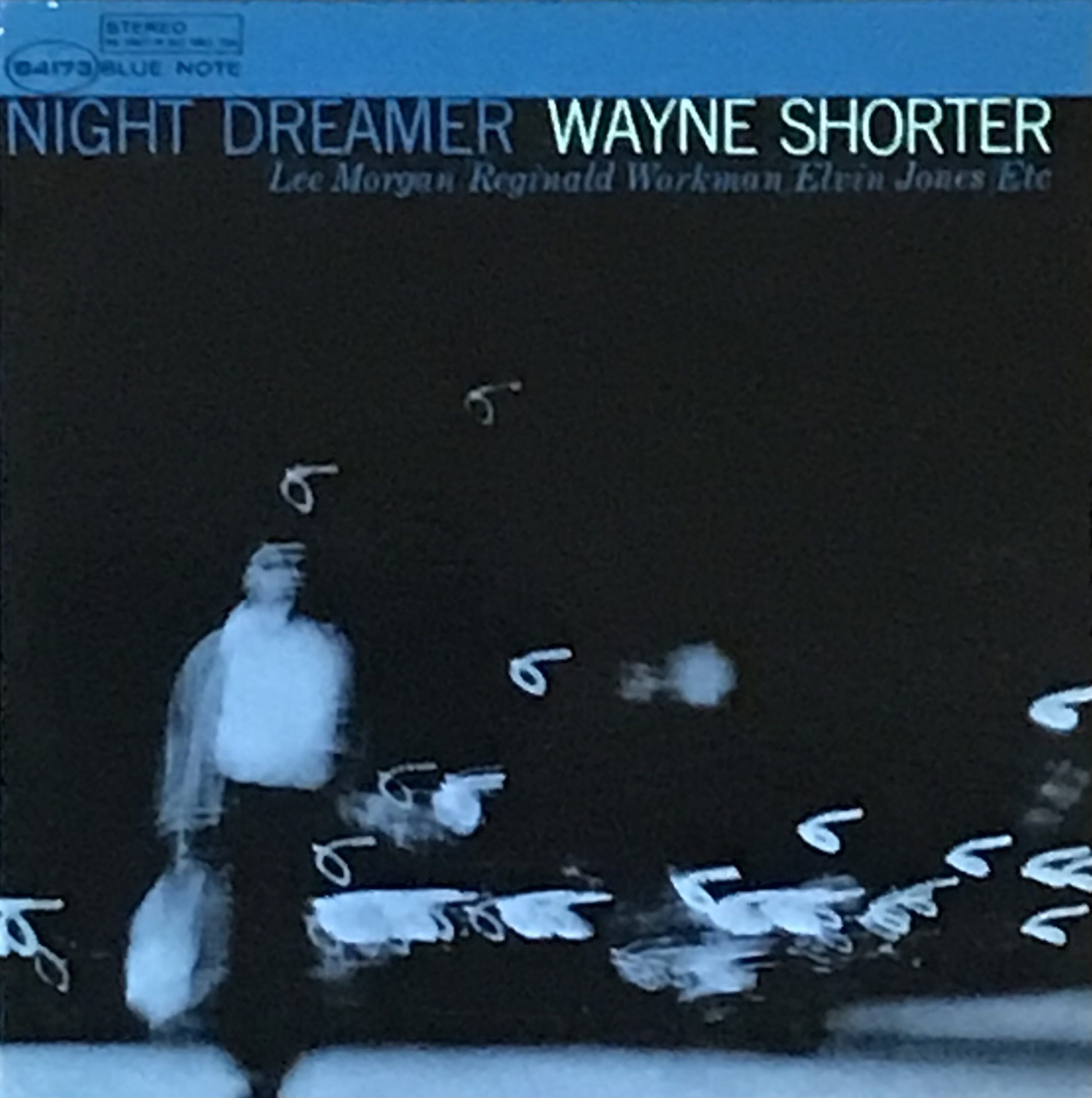
第4作目は半年後64年11月27日録音の「Inner Urge」、いよいよJoe Henのワン・ホーン・カルテット作品登場です!リズム隊は要のMcCoy, Elvinが留任、ベーシストがBob Cranshawに替わります。表題曲の斬新さ、強烈なインパクト、難解ではあるけれど何処かポップさ(笑)を湛えた曲想、オリジナル・ライティングには更なる進化を明確にします。一体どのような音楽を聴いて、研究してこのような作風に至ったのかに、実に興味を惹かれるところです。
「Inner Urge」
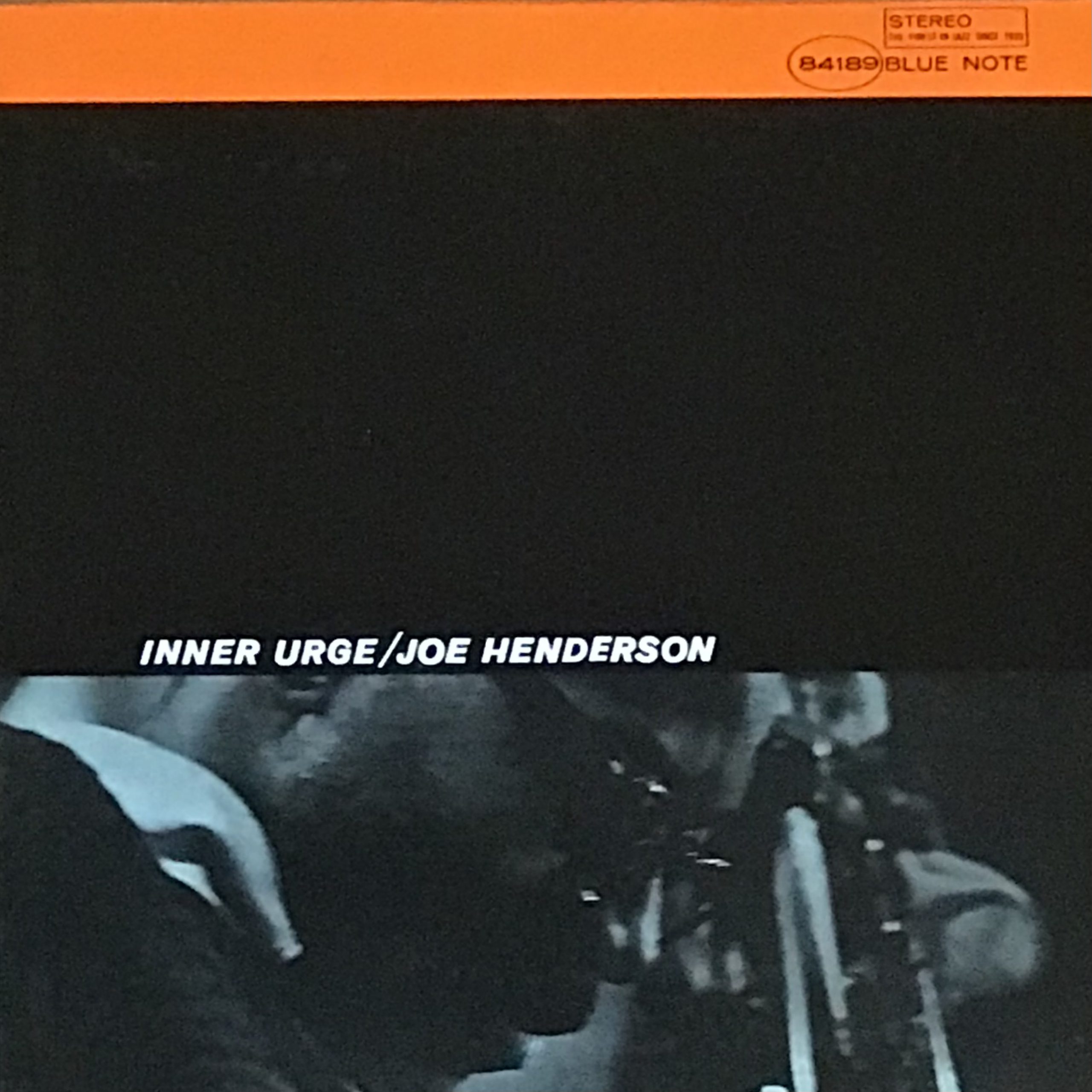
間違いなくElvin, McCoyの伴奏があってこそのナンバー、Joe Henのソロも楽曲同様に新たな境地を聴かせ、より一層の高みに登るべく進化を遂げています。短期間に急速に成長し、留まるところを知らぬが如しです。
McCoyのソロはElvinの繰り出すビート、ポリリズムと共に、Coltraneのカルテットでのプレイ以上の炸裂ぶりを聴かせています。左手低音部と右手アドリブラインのクロスするピアノ奏に、手に汗握るスリルを感じます。Elvinはリズムの森羅万象を繰り出すかのような物凄いソロを展開、その後の再登場のテナーソロには、ラストテーマに流れ込む必然を見事に作り上げました。
McCoy Tyner

Isotopeもブルースですが、このテーマの持つイメージは一体どこから来るのでしょう?曲想はThelonious Monk的と言えなくもありませんが、僅か12小節の中に伝統とファンキーさと革新性が渾然一体となった音楽、凄過ぎる楽曲です!タイトルには放射性同位元素の意味がありますが、他に「実によく似ているいる人、うり二つの人」という意味もあり、Joe Henがいみじくも評論家Nat Hentoffに語ったところによると、確かにMonkにトリビュートしたナンバーで、彼の音楽的ユーモアを用いて作曲したそうです。という事で「Monkとうり二つ」という意味合いなのでしょう。
El Barrioは幼少時に過ごしたOhio州Limaでの、Spanishムードを表現したナンバーです。彼には後年ラテン・テイストが開花しますが、その発端でもあります。
Duke Pearson作のバラードYou Know I Careのドライな美しさ、Cole PorterのナンバーNight and Day選曲の意外性等、バラエティに富んだアルバムに仕上がりました。
因みに半年前、同年5月に録音された作品「Stan Getz & Bill Evans」のドラマーもElvinが起用されています。ここでもNight and Dayを演奏していますが、共演者によるドラムのアプローチの違い、異なるスタイルのテナー奏者の演奏を比較してみるのも面白いです。
「Stan Getz & Bill Evans」

以上BNリーダー諸作を足早に紹介しました。もう1作、後年91年3月録音のアルバムになりますが、Rufus Reid, Al Fosterを擁したテナートリオ作品「The Standard Joe」は後期の総決算的演奏、そしてオリジナル、スタンダードナンバーの選曲が眩いばかりに光る傑作です。Blue Bossa, Inner Urge, In ‘n Out, Round Midnight, Body and Soul, Take the A Train、笑いが止まらないほどに(笑)抜群のコンビネーション発揮の3人による名演奏の数々。是非こちらもお聴きください!!
「The Standard Joe」

それでは「Mode for Joe」について触れて行きましょう。
前作から1年強を経た66年1月27日録音、Joe Henは新たな素晴らしいオリジナルを引っ提げ、強力な布陣を引き連れ、参加メンバーの楽曲も本作に相応しい楽曲をオファーし、周到な準備を行いレコーディングに臨みました。レーベル参加ファイナルというモニュメンタルな意味合いもあったと思います。
1曲目A Shade of Jade、Joe Hen更なる深淵なコンポジショニングの境地を聴かせてくれます。何と意欲的なナンバーなのでしょう!変拍子的テイストを感じさせるメロディラインのユニークさ、3管編成のハーモニー・ライティングの絶妙さ、加えてサウンドのカラフル感に貢献しつつ、管楽器のアンサンブルにも参加するビブラフォンの効果的な用い方、コード進行や曲のフォームも魅力に溢れています。
何よりリズムセクション3者が繰り出すビート、スピード感、スイング感の一体感が曲自体に猛烈に推進力を与えています。Elvin, McCoyのチームも本当に素晴らしいですが、管楽器が多く、アレンジされたアンサンブルが音楽のかなりの部分を占めるので、タイトで合奏のカラーリングに長けたCedar Walton, Ron Carter, Joe Chambersのトリオは全く適任であります!
先発ソロはJoe Hen、そのクリエイティブさに聴いている方は悶絶寸前です!何と独創的な演奏でしょうか!リニューアルされたJoe Henフレーズのオンパレード、そして楽器をコントロールするテクニックにも一層の安定感が!早い話、サキソフォンの更なる上達ぶりが顕著で、加えてタイム感、ストーリーの語り口が何倍にもバージョンアップされました!
続くMorganのソロもスピード感が際立つ、ブライトなテイストでのスムースなプレイです。その後のWaltonのピアノソロは実に端正で、さまざまな色合いを脱力を伴って提供してくれます。そのバックでのon topなCarterのベース・サポートがクールでカッコよく、こちらも堪りません!
ホーンのアンサンブルではCurtis Fullerのパンチあるトロンボーンが低音部を確実に支え、迫力を聴かせます。
Joe Henderson

2曲目Waltonのナンバーにして表題曲Mode for Joe、いや〜カッコいいオリジナルです!Waltonの抱くJoe Henのイメージの具体化でしょうか。テーマは3管編成+ビブラフォンもハーモニーに加わった4ボイス、分厚いゴージャスなアンサンブルを聴かせます。シンコペーションを多用し、音の強弱もふんだんに付けられたダイナミクスも魅力で、壮大なイメージを感じさせます。
先発のテナーソロはいきなりの、当時としては特殊奏法であるオーバートーンを駆使したアバンギャルドなフレージング、音のインパクトが物凄いです!後年Michael Breckerがこの奏法を洗練させて拡大し、大幅に取り入れていました。実はMichaelは若い頃にJoe Henに何度かレッスンを受けたことがあるそうで、多大に影響を受けていると思います。
その後のソロの展開では絶好調ぶりを徹底的に発揮し、もう誰も彼のスイング魂を止めることは出来ない次元にまで到達しています!
フリーフォームにまで手が届きそうな所のギリギリで留まり、伝統的なジャズの範疇に居ながらもそこから抜け出そう、飛び出そうとするモーションを常に感じさせるアドリブスタイルには、真のジャズマンを感じます。
続くビブラフォンのソロはJoe Henの盛り上がりを特に意に介する事なく(汗)、いつものように淡々と打鍵して行きます。バックで聴かれるホーン・アンサンブルがサウンドの豊かさを聴かせます。
Fullerのソロは実にテイスティな、まるで会話をしているかのような、ヒューマンな味わいを感じさせますが、人柄も大変ハッピーだったと聴いています。ソロ中に一瞬トランペットがバックリフを吹き始めましたが、他が追従しなかったようです。この部分をエディットしないところに60年代の大らかさを感じます(笑)。
続くベースソロでは、その分かなり早い時点でバックリフが演奏されます。そのままラストテーマへ、ビブラフォンはテーマとユニゾンに回ったり、ハーモニーに加わったりと、忙しくアンサンブルに参加します。
Cedar Walton

3曲目もWaltonのナンバーBlack、重厚で激しいアンサンブル、ドラムのロールを聴かせるイントロは続く楽曲の大変良きプレビューになりました。ベースとピアノのユニゾンによるパターンが提示され本編がスタートします。こちらも素晴らしい楽曲、このテーマでは特にホーンとビブラフォンのアンサンブルが光り、それに対するテナーのメロディ独奏が実にバランス良く映える構成となっています。オクターブ上がったアンサンブルには大変な迫力を感じます。
Joe Henの先発ソロはアップテンポにも関わらずゆったりとしたリズムのノリを聴かせます。彼はプレイはスピード感があり、スインギー、オリジナルなフレージングの妙も聴きどころではありますが、フレーズの始まる、終わる箇所にこそ実は大変な工夫がなされています。聴き取ることはなかなか難しいのですが、4小節、8小節の単位を跨いで繰り出すラインの開始、終始の位置の絶妙さは、他のプレーヤーとは異なる音楽性を提示しています。しかもごく然りげ無く!これはCharlie ParkerやLester Youngのコンセプトを洗練させたアイデアから来ていると理解しています。
JoeHenのプレイには何か得体の知れないオーラ、雰囲気、表現を聴き手は感じ取ると思いますが、ここにこそ彼の主張が込められていると信じています。
Joe Henderson

朝日の如く爽やかにのメロディを引用しつつ、唯我独尊状態でソロが展開されます。シンコペーションを多用したフレージングはそのタイム感の見事さに鳥肌が立つほどです!リズム隊との合致度も信じられないレベルで遂行されています。
Morganのソロも流麗に行われますが、この人は大変良く楽器を鳴らしているのでしょう、マイクに乗る音が他のトランペット奏者とは異なります。ここでのプレイはいつもの彼のテイストが基本ですが、Joe Henのソロに影響を受けたのでしょう、異なったアプローチを聴かせます。
作曲者Waltonのソロに続きますが、ここでも安定したプレイを聴かせます。例えばAndrew Hillのような革新的なプレイヤーとは真逆を行く、インサイドの中でいかにクリエイティブにプレイするかを信条としています。
ラストテーマの前にJoe Henがソロを締め括るべく1コーラスプレイします。ラストテーマの繰り返しの後は再びイントロに戻り、熱いアンサンブルを聴かせています。Morganのリードトランペット・プレイは確実で的を得ていると思います。
Lee Morgan

4曲目Caribbean Fire DanceもJoe Henコンポジションの新機軸、エキゾチックな中に彼らしいリズムの捻りが入る名曲、しかしこんな曲は聴いたことがありません!物凄い曲想ですが、そもそもが曲のトーナリティがはっきりしない、フローティングでミステリアスな構造のナンバー、Joe Henにとっては重要なレパートリーの1曲となりました。70年9月ライブレコーディング「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」にてWoody Shawとの2管編成で、ぐっとテンポを早めメチャクチャ熱い、彼ら二人のベストとも言える名演奏を繰り広げています。
「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」

リズム隊はカリプソ風のリズムを繰り出し、比較的淡々と演奏します。Joe Henのソロは出だしからトリッキーに攻めています。Morganも同様に動物の咆哮の如き割れた音色でインパクトを示しています。これはカリブ海沿岸に生息する猛獣のイメージでしょうか?Fullerも影響を受け、いつになくアグレッシブなブロウを聴かせるので、リズムセクションのクールさと溝を感じてしまいます。Hutchersonのテンションはピアノトリオと合致しているかも知れません。セカンドリフが演奏され、合間に短いドラムソロが演奏されラストテーマへ。
Joe Henderson

5曲目Grantedは本作中最もハードバップ色の強いJoe Henのナンバー、New YorkのWABC-FMのスタッフだったAlan Grantに捧げられました。NYに来たばかりのJoe HenとDorhamをAlfred Lionに紹介したばかりか、彼がNYで企画していたコンサートにJoe Henをリーダーとして出演させるなど、ニューカマーに便宜をはかりました。親切にしてくれた恩人に敬意を表したこのナンバーは、フォームとしては倍の長さのマイナーブルース、ソロはMorgan, Fuller, Joe Henと続きますが、Joe Henのアプローチの凄まじさ、イメージには並外れたものを感じ、圧倒的な演奏の構成力に思わず唸ってしまいます!その後Hutchersonに続き、セカンドリフが演奏された後Waltonのピアノ奏、短いCarterのソロにまた別なアンサンブルが絡み、ラストテーマへ。
Curtis Fuller

6曲目アルバム最後を飾るのはMorganのナンバーFree Wheelin’、印象的な6拍子のベース・パターンから始まるこちらも変形のブルース・ナンバー、軽快なテンポ設定によるセッション形式でソロが続きます。Joe Hen, Morgan, Fuller, Hutchersonとフロントの4人が伸び伸びと、屈託なくプレイしているのが伝わります。
Lee Morgan

2021.09.19 Sun
今回はBobby Hutchersonの63年録音リーダー作「The Kicker」を取り上げてみましょう。
Recorded: December 29, 1963 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ Label: Blue Note Producer: Alfred Lion
vibe)Bobby Hucherson ts)Joe Henderson g)Grant Green(#4-6) p)Duke Pearson b)Bob Cranshaw ds)Al Harewood
1)If Ever I Would Leave You 2)Mirrors 3)For Duke P. 4)The Kicker 5)Step Lightly 6)Bedouin

Bobby Hutchersonがリーダーですが全面にフィーチャーされたJoe Henderson, Duke Pearson、後半3曲に登場するGrant Greenたちの存在感も大きく、リーダーを特に決めないメンバー全員が対等なレギュラーコンボの様相を呈しています。
本作の約1ヶ月前に全く同じメンバーでBlue Note(BN)に録音されたGrant Greenのリーダー作「Idle Moments」と双子のような関係にあり、こちらも素晴らしい内容のアルバムです。演奏もさることながら選曲が良いですね。Pearson作の表題曲やGreenのオリジナル、John Lewis不朽の名曲Django等、これら哀愁を帯びたナンバーをメンバーは楽曲に吸い寄せられように、何の迷いもなくスインギーにプレイ、とりわけ絶好調のJoe Henが思う存分ブロウします。
レコーディングから1年強を経た65年2月にリリースされましたが、こちら「The Kicker」の方は何と36年間もオクラ入りし、99年にやっと発売され日の目を見ます。
内容的に2作は60年代初頭のモダンジャズの雰囲気を存分に湛えた、ナチュラルでテイスティな演奏です。寧ろ「The Kicker」の方がバラエティに富んでいる作品ですが、当時のBNはアルバムを多発していたので、リーダーは違えど同じメンバーによる同一傾向の作品では売れ行きを懸念したのかも知れませんし、もしかしたら他の理由があったのかも知れません。
2枚の大きな違いは「Idle Moments」の方がマイナーのダークな曲調、「The Kicker」がメジャーの明るめな曲調を中心とした点です。
Idle Moments / Grant Green
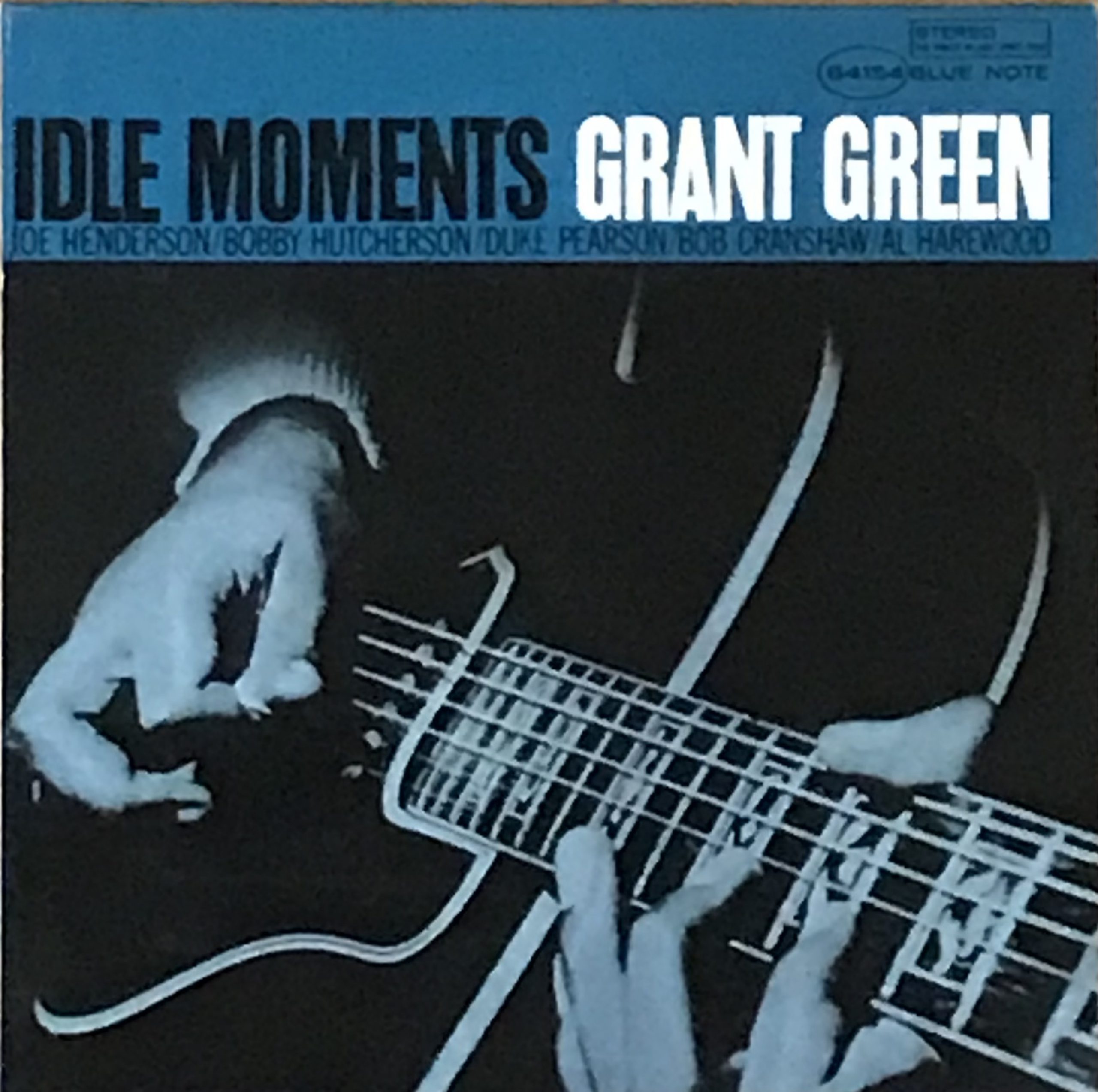
BNから再びお呼びがかかった彼らは再会を喜んだかも知れませんが、個々でも多くの共演を行なっていました。当時のBNでビブラフォンはHutcherson、テナーはJoe Hen、ギターもGreenたちが筆頭アーティストなので、顔を合わせる機会は多かったと思います。
Pearsonもプレーヤーとして活躍しましたが加えて作曲家、アレンジャーとしても諸作に携わっていて、巧みなピアノプレイ、都会的なセンスを有したオリジナル曲、ピアノトリオからビッグバンドまで緻密にして洒脱なテイストを聴かせる知的なアレンジを多く披露しました。
BNには優れたピアニストが数多く在籍し、その数には枚挙にいとまがなく、ある種ピアニストのレーベルと言っても過言ではありません。
創設者でありプロデューサーでもあるAlfred Lionが67年リタイアし、レーベルをLiberty Recordsに売却した際にPearsonは後釜を引き受け(実は63年からA&Rとしてアーティストのスカウトも担当していました)、BNのプロデューサーとしても数年間活躍し、レーベルの顔として広く知られました。
50年代から60年代中頃にかけてBNは時代を代表する名作、名盤を数多く発表していました。 BN自体がジャズを牽引していたと言っても過言ではありません。しかし60年代後半から次第に音楽シーンが混沌を極める中でそのステイタスに翳りが生じ始めました。
その最中のプロデューサー就任はさぞかし大変だったと思います。71年BNのもう一人の創設者であるFrancis Wolffが逝去するまでPeasonは在籍しました。
Duke Pearson

本作はBobby Hutchersonの初リーダー録音に該当するのですが、リリースがずっと後になるので、次作65年4月録音のアルバム「Dialogue」が事実上の処女作になります。
Dialogue / Bobby Hutcherson

ピアノに鬼才Andrew Hill、Alfred Lionのお気に入りですね、彼を迎え収録6曲中4曲Hillの超個性的なオリジナル、2曲Joe Chambersのこれまたユニークなナンバーを取り上げた、しかしリーダーHutchersonのオリジナルは含まれない作品です。
彼のプレイはHillを始めとしてFreddie Hubbard, Sam Rivers, Richard Davis, Joe ChambersたちBNの花形ミュージシャンの影に埋没気味です。
それはそうですね、本人はどちらかと言えば強く自分を押し出して演奏するタイプではなく、加えてビブラフォンという楽器の特性上、管楽器以上には音のエッジが立たず、ピアノほどの複雑な和音を演奏出来ず、その上これだけ音楽的に主張のある、アクの強いメンバーを集めたのであれば、どうしても脇役に収まらざるを得ないでしょう。
アルバム自体のクオリティは本当に高いのですが、一体誰が作品の主人公なのかと、ふと考えてしまいます。
リーダーアルバムは本人が音楽性を発揮し、存在感が主張されている事が前提だと思うのですが、豪華な入れ物を用意し中身もしっかりと収容したにも関わらず、容器に書いてある名目とは異なる収容物が納められていたかの如しです。
後にも挙げますがBNの重要作品に連続参加したHutcherson、ひょっとしたら前衛的な演奏スタイルが彼の本質と曲解され(前衛の傾向は確かにありますが、本質はオーソドックスなプレイヤーだと思います)、Lionの秘蔵っ子である前衛と主流派の狭間を行き来するHillを筆頭に据え、フロントやリズム隊にChambersほか柔軟性のあるミュージシャンたちを配して、Hutchersonの前衛方向の音楽性を開花させ、華々しいデビューアルバムをプロデュースする算段であったと推測できますが、実態は異なりました。
Andrew Hill

同じビブラフォン奏者で強力なスイング感とタイム感を有し、打鍵テクニックも圧倒的であったLionel Hamptonは、ビッグバンドを率いて自身をフィーチャーしても管楽器のアンサンブルに埋もれる事なくソロを聴かせていました。リーダーに成るべくしてなったと言えるHampton、華があり、派手さゆえにその存在感は誰よりも抜きん出ていたように思います。
Lionel Hampton

Hutcherson自身が単独でフロントに立った作品である、66年2月録音の3作目に該当する「Happenings」で初めてその存在を誇示したと言って良いでしょう。
ビブラフォンとピアノトリオによるカルテット編成でHerbie Hancockの名演奏も光りますが、自身のオリジナルの秀逸ぶり、そしてHancockの名曲Maiden Voyage収録!選曲の良さも魅力のアルバムで、ジャケットの色合い、デザイン、雰囲気と見事にリンクした名作です。
Happenings / Bobby Hutcherson
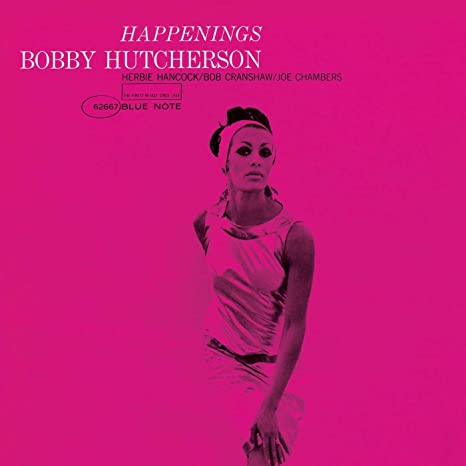
Lionel Hampton, Milt Jacksonらの流れを汲む左右1本づつのシングル・マレット・スタイル(Gary Burton, Mike Mainieriらは左右2本づつを駆使するダブル・マレット・スタイル)のHutchersonは、41年1月Los Angeles, California生まれ、12歳の時にMilt Jacksonが参加したMiles Davisのアルバム「Miles Davis All Stars, Volume 2」を聴き、啓示を受けビブラフォンを開始、後にかのDave Pikeに楽器の手解きを受けたそうです。
Hutchersonの姉が当時Eric Dolphyのガールフレンドだったので(!)彼に弟を紹介した事があるそうです。Dolphyの作品への参加にはこんな伏線があったのですね。
60年代に入りNew Yorkに活動の場を移し、タクシードライバーをしながら音楽活動を始め、幼馴染みのベーシストで先にNew Yorkに移住していたHerbie Lewisを通じシーンに進出しました。その後次第にミュージシャンに演奏を認められ、彼らのバンドに参加します。
63年4月録音、若干17歳Tony Williamsの名演奏も光る新生Jackie McLeanを表出した「One Step Beyond」、64年1月録音、Elvin Jonesのドラミングが冴え渡るAndrew Hillワールド全開にして代表作「Judgment!」、64年2月録音、リーダー本人の欧州客死後に発表されたモダンジャズ永遠の問題作Eric Dolphy「Out to Lunch!」、以上のBNを代表する傑作に矢継ぎ早に参加、これらで聴かれる演奏はビブラフォン従来のオーソドックスさを排除したかの如き革新性を持ち、一躍脚光を浴びました。幸先の良いスタートを遂げたのです。
One Step Beyond / Jackie McLean

Judgment! / Andrew Hill

Out to Lunch! / Eric Dolphy
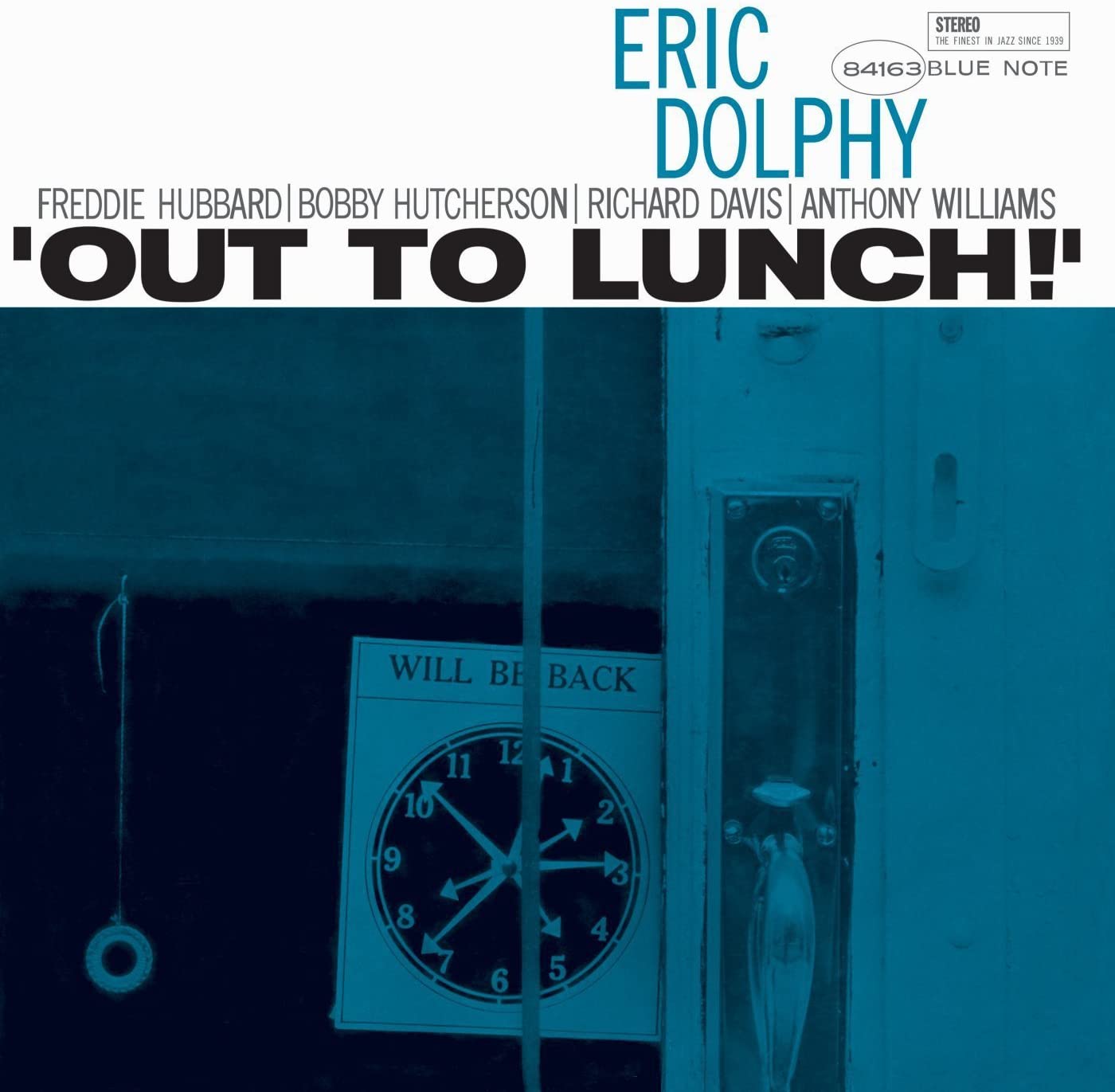
それでは演奏曲について触れて行くことにしましょう。1曲目スタンダード・ナンバーIf Ever I Would Leave You、渋いナイスな選曲です。この曲は60年のミュージカルChamelotで初演され、62年にSonny Rollinsが自身のリーダー作「What’s New?」で取り上げました。リリース直後のTV映像で素晴らしい演奏も残されています。
https://www.youtube.com/watch?v=-iPMqJuGQes (クリックしてください、視聴出来ます)
What’s New? / Sonny Rollins
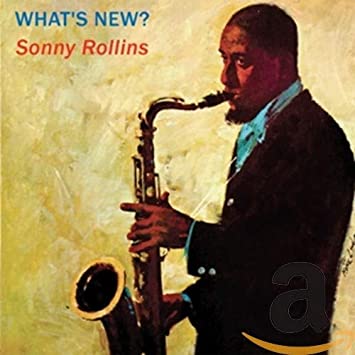
Kenny Dorhamも63年4月録音「Una Mas」で演奏していますが、こちらはCDの追加テイクとして87年に初めて日の目を見ました。他の収録曲とは異なった雰囲気の演目、演奏ゆえにレコードリリース事にオミットされた模様です。本作同様Joe Henも参加しています。
Una Mas / Kenny Dorham

Don Grolnickの95年作品「Medianoche」でもMichael Breckerをフィーチャーして演奏されています。タイトルがIf Ever I Should Leave Youと微妙に異なっていますが、Would, Should両方で流布しているようです。ここではラテンでプレイされており、Michaelはかなりon topに演奏していて、個人的には共演者のDave Valentinのフルート奏のように、もう少し後ろのタイミングでソロを取ってくれたのなら、より心地良かったと感じています。
Medianoche / Don Grolnick

ピアノのメロディアスでリラックスしたイントロ、要所をベースが合わせつつ、テーマが演奏されます。Joe Henのジャジーでいて個性的、正統派でありながら異端を内包した音色によるメロディ奏は実にスインギーです!当たり前ですが前出のRollinsのプレイとは全く異なります。スイングとラテンのリズムの違いも含め、ぜひ聴き比べてみてください。
テーマ後のピックアップソロからして既にアイデア満載、ひょうきんさとファンキーさ、リラクゼーションを掲げ、あたかもソロの本編はとことん聴かせちゃいますよ!と宣言しているかのようです。以降の演奏のコンセプトを明確に提示してくれました。
知的にコードのテンションを散りばめたアドリブラインは、フレーズとフレーズの間を実に的確に取りつつ、適度なユーモアや遊びを感じさせながら脱力感を保ちつつ、何と言っても曲想に相応しくナチュラルに展開されます。
Joe Henderson

続くHutchersonのプレイは思わずアドリブを採譜したくなるような魅力に満ちた、フレージングの構成音にオシャレな音が散りばめられたソロを聴かせています。彼以前のビブラフォン奏者とは明らかに一線を画す演奏と認識しています。同時に彼のインプロビゼーションからは真面目な人柄を垣間見る事ができます。
そのあとのPearsonのソロ、イントロでも聴かせたリラクゼーションを全面に感じさせ、メロディの断片をスムースに用いつつ、Joe Henよりも更に力の抜けた、言ってみれば大人の演奏を展開しています。
ソロイストの演奏を巧みにサポートするリズム隊、特にBob Cranshawの立ち上がり良くon topなベースが要になっています。
Bob Cranshaw

始めのテーマではピアノだけがバッキングしていましたが、ラストテーマではビブラフォンも加わり、両者のバッキングはバランスを保ちつつ、決してtoo muchにはなりません。サビのメロディをビブラフォンに任せたのも効果的です!
エンディングにはこれまたコピーしたくなる巧みなシカケが施され、演奏を楽しんだ余韻を一層印象付けてくれますが、サウンドやアイデアから、これはPearsonのアレンジによるものではないかと踏んでいます。
アルバムの1曲目にこれだけ魅力的な演奏を位置させた事で、本作のクオリティはグッと上がりました。この後どんな演奏が来ようが全てを吸収する緩衝材としてワークする事でしょう!
Bobby Hutcherson

2曲目はChambersのナンバーMirrors、98年自身のアルバム「Mirrors」でも取り上げています。こちらはかなり早いテンポでの演奏なので、別曲と見紛うばかりです。

哀愁を感じさせるメロディをHutchersonが美しくプレイし、Joe Henがテーマ最後に付随するバンプ部分でハーモニーを吹く、ユニークなアンサンブル構成です。
ソロはそのままビブラフォンが引き続き淡々とプレイ、スローテンポをCranshawのベースがタイトにキープします。Joe Henのソロは自身は演奏しなかったテーマのメロディを随所に用い、これまた強力なイメージを保ちつつムーディに、スペーシーに、演奏します。Pearsonの目立たなくともスパイスとしての確実なバッキングも印象的です。
Joe Henderson

3曲目はHutchersonのオリジナル、Pearsonに捧げたマイナー調のハードバップ・テイストを感じさせる、しかしsomething newを巧みに織り込んだ佳曲For Duke P.、ソロの先発は作者から、快調にプレイします。Hutchersonの生真面目さを随所に感じますが、個人的にはもっと弾けてやんちゃな面を聴かせて欲しいと願う時があります。
続くJoe Henのソロには流石です!素晴らしい!と思わず頷いてしまう流麗さ、スイング魂、意外性を心底感じます。Pearsonの演奏には様々な事象が頭の中で鳴り響いているのでしょう、奏でるラインには度重なる音やコードの取捨選択を認識することが出来、ハーモニーやライン組み立ての達人ぶりを聴かせています。
Duke Pearson

4曲目はJoe Hen作の名曲The Kicker、Horace Silverの「Song for My Father」でも取り上げられていました。自身のアルバムでもこの名前を冠したアルバムがありますが、Grant Greenの64年録音作品「Solid」にも収録されています。ここでは作曲者の他、Elvin Jones, McCoy Tynerの超弩級を擁して演奏していますが、プレイやアンサンブルが総じてあまり噛み合っていない、何処か隙間風の吹くセッションに感じます。こちらもオクラ入りし15年後の79年にリリースされましたが、その理由を推し量る事は出来そうです。
Solid / Grant Green

本作の演奏についても、テナー、ギター、ピアノでイントロのメロディを演奏しますが難しいラインで、今ひとつ合奏に問題があるように聴こえます。テーマでのPearsonのバッキングには小粋なセンスを感じましたが、これは脱力の成せる技の一つです。
この位の早いテンポになるとHarewoodのグルーヴに難を感じ始めます。いくらCranshawがon topとは言え、ドラムはもう少しタイムが前に位置しないと演奏のスピード感を削いでしまいますし、ドラミングのセンスが些かcorny(新鮮味のない)に聴こえ、アンサンブルでシカケを合わせる際のカラーリングやフィルインにもっと工夫が欲しいところです。ましてやソロイストとインタープレイを丁々発止の次元には、かなり距離があります。
「Idle Moments」録音の時はリラックスして演奏を楽しんでいる風を感じましたが、ここでは多少ナーバスな印象を受けます。
先発のJoe Henはほぼ無反応で、リズムをキープするのが精一杯(?)のドラムを相手にクリエイティブに、構成力を持たせて自己の世界を表現していますが、彼の演奏はCallを表し、共演者、特にドラマーにはResponseを担当してもらわないと究極、Joe Henのインプロビゼーションは成り立たないのではないでしょうか。ジャズの様式美のひとつがCall & Responseですから。
とは言えコンパクトに纏めて次のビブラフォンへ、律儀なHutchersonのアプローチにはHarewoodのドラミングにさほど違和感を感じず(他者の介入がなくとも、自分一人の世界だけで演奏するタイプゆえと言えるでしょう)、続いてこの曲から参加したGreenのギターソロにも同様に違和感を覚えませんが(フレーズを紡ぎ、順列組み合わせでソロを組み立てるタイプなので自己完結しています)、Pearsonのプレイにはこのドラミングはあまり相応しくないと感じました。クリエイティブさを発揮しているからでしょう。タイムやグルーヴ感、音楽に対するコンセプト等、色々と作用していますが、特に斬新な感覚をふんだんに織り込んだこの曲、Harewoodのテイストでは対応し切れていません。
Grant Green

5曲目もJoe HenのオリジナルStep Lightly、Blue Mitchellの63年8月録音リーダー作「Step Lightly」、同じくMitchellの64年7月録音、若きChick Corea参加で名高い「The Thing to Do」(こちらはJoe Hen不参加)にも収録されています。
Step Lightly / Blue Mitchell

The Thing to Do / Blue Mitchell

本作最長の14分以上の演奏時間を有します。変形のブルースで、リラックスしたジャジーなムードの中、レイジーさと変形のブルース・フォームが生み出す新鮮さをソロイストは楽しみつつ、伴奏者もそれを共有しています。ピアノのイントロが一節あり、テーマ奏開始です。
この類の曲想はHarewoodの演奏に良く合致していますし、Cranshawのベースワークがあってこそ、安定したタイムを供給する事が出来ています。
先発はPearson、オーソドックスなスタイルでのアプローチの中にノーブルなテイストを感じさせます。続くHutchersonのソロにも同様なものを見出せ、Greenのプレイではブルーノートを効果的に用いたフレージングを存分に聴くことが出来ます。
淡々とした雰囲気が続いたところでJoe Henの登場、それまでのムードを継続させつつも新たな世界を設けようとする試みを次第に感じさせますが、あくまで自分はサイドマン、とことん盛り上がって主役を奪ってはマズイとばかりに、盛り上がりの五合目辺りで下山し始めました。
とは言えJoe Hen本作中の演奏では全てハイレベルな音楽性を光らせており、間違いなくアルバムの主人公ではありますが。
Bob Cranshaw

ラストを飾る6曲目はPearsonのオリジナルBedouin、自身の作品では64年11月録音「Wahoo」にてJoe Henを含めた3管編成で、編成を拡大し67年12月録音「Introducing Duke Pearson’s Big Band」にてフルバンドで素晴らしいアレンジを伴って演奏しています。
Wahoo / Duke Pearson
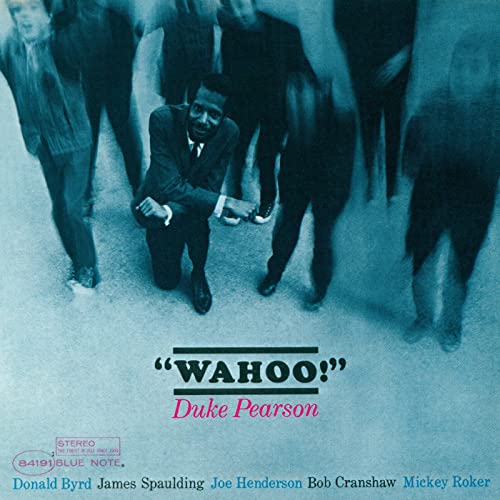
Introducing Duke Pearson’s Big Band

タイトルは砂漠の住人を意味し、普通アラブの遊牧民族に対して用いる名称で、メロディラインやサウンドも中近東を感じさせます。テナー、ギター、ビブラフォンによるテーマはかなりユニークに響き、エスニックなリズムにHarewoodのドラミングは対応し切れるか懸念するところですが(汗)、スイングにチェンジし、ひとまず胸を撫で下します。
Joe Hen, Green, Hutcherson, Pearsonと順当にソロが続き、ソロ交代時に演奏されるアンサンブルが効果的です。
Joe Henのプレイの革新性、そしてピアノソロには流石コンポーザーとしての深い演奏解釈を聴き取ることが出来ました。
Al Harewood

兄弟アルバム「Idle Moments」での成功を踏まえて1ヶ月後に同一メンバーを揃え、「今度はまだリーダー作を出していないBobby名義でやってみるかい?」のようにオファーし、「えっ?オレがリーダー?」のようなノリで録音されたのかも知れません。と言うことで本作は柳の下の二匹目のドジョウを目指しましたが、メンバーの力量を超えてしまった選曲に全体のバランスを些か欠いた出来になり、お蔵入りしてしまったと見るのが妥当かもしれません。
2021.09.05 Sun
今回はMichael, RandyのBrecker兄弟を擁したHorace Silver Quintet 1973年のライブ2枚組アルバム「The 1973 Concerts」を取り上げてみましょう。
CD 1, 1-3: Live at The Jazz Workshop, Boston, March 27, 1973 CD 1, 4-5 & CD2, 1: Live at the 8th International Jazz Festival, Pori, Finland, April 14, 1973 CD 2, 2-7: Live at the Wollman Memorial Skating Rink, New York, July 3, 1973 CD 2, 8: Live at Pescara Jazz, Pescara, Italy, July 15, 1973
p)Horace Silver tp)Randy Brecker ts, fl)Michael Brecker el-b)Will Lee ds)Alvin Queen
CD 1 1)Liberated Brother 2)In Pursuit of The 27th Man 3)Big Business 4)Acid, Pot or Pills 5)Gregory Is Here
CD 2 1)Song for My Father 2)Introduction 3)Liberated Brother #2 4)Introduction 5)In Pursuit of The 27th Man #2 6)Gregory Is Here #2 7)Song for My Father #2 8)Gregory Is Here #3

本作は2015年に忽然とリリースされ、話題になりました。正規の録音ではなくBootleg盤、録音状態が不十分なテイクもありますがRandy Breckerのホームページでも紹介され、そこから直接購入できるようにもなっています。彼もアルバムの内容を気に入っているからでしょう。
Michael, RandyのBrecker兄弟はHorace SilverのBlue Noteレーベル(以降BN)72年録音作品「In Pursuit of The 27th Man 」(27th Man)に3曲参加しています。若手のトランペット、テナーサックス奏者を積極的に起用するのがHoraceのスタイルでしたので、当時New Yorkで活躍し始めた、新進気鋭の二人に白羽の矢が立ったのは当然の成り行きでありました。
作品参加メンバーはBob Cranshawがエレクトリックベース、Mickey RokerがドラムスというBN御用達のリズム隊で、安定したプレイを聴かせています。
当時主流だったジャズロック・テイスト満載の内容、Cranshaw, Rokerたちジャズ屋が演奏するジャズロックのビートには独特のグルーヴがあり、この二人は特にBNのハウス(お抱え)ミュージシャンでしたので、レーベルを代表するリズムをほか多くで聴かせました。
「In Pursuit of The 27th Man」
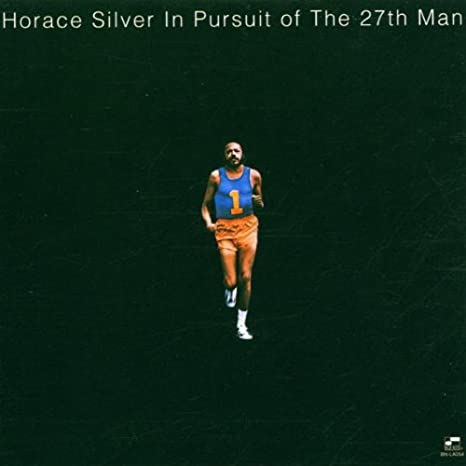
本作ではフロントと同様に若手リズム隊を採用しており、フレッシュな躍動感ある演奏を展開しています。エレクトリックベースには何とBrecker兄弟の盟友Will Lee、当時若干20歳!既に後年聴かれるタイトなビートを繰り出し、インタープレイに於いて豊かで先鋭的なアイデアを提供しています。
伝説的バンドDreamsやThe Brecker Brothers Bandほか様々なセッションで兄弟と行動を共にしました。
ドラムにはAlvin Queen 22歳、69年頃からBilly Cobhamの後釜でHoraceのバンドに参加していましたが、レコーディングではRokerが使われ、Willも同様ですが正式なレコーディングは残されていません。堅実でタイトな演奏、これはHoraceが採用するドラマーの全てに見出すことが出来ます。
因みにRandyは27歳、Michaelが24歳とサイドマンは全員20代、Horaceが42歳で脂が乗り切っていた頃なので、バンマスの経験豊富な音楽性のもと、胸を借り、若手4人は大いに演奏を楽しみ、ツアーではさぞかし盛り上がっていた事でしょう。
のちにも紹介しますが、Brecker兄弟はギグ終了後に演奏可能なライブハウスを訪ね、ツアー先であれば地元のミュージシャン達と屈託なくジャムセッションを繰り広げます。演奏することが大好きなのですね、とことんセッションを楽しんだテイクも世に残されています。
このメンバーでパーマネントに演奏していたのはどうやら73年の1年間だけのようです。どんなにバンドが成長し、まとまり、素晴らしい演奏を繰り広げたとしても、Horaceはガラッと音を立てるように、まるでバンドを破壊するが如くメンバーを一新します。
クインテットの演奏には一回一回のプレイを大切にし、コツコツと音楽性を広げ、積み重ね、次第に緻密な構造の高層建築物を打ち立てるが如きの展開を、目の当たりする事が出来ます。
Horaceはひょっとしたらこれらのプロセスを繰り返す事が好きなのかもしれませんね。常に新たなメンバーを雇い入れ、バンドに相応しいナンバーを作曲し、メンバーを指導する。ギグやツアーを重ね、若き逸材を育て、プレイが頂点に達したところで「この辺りで良いだろう」とばかりにバンドを解体する。メンバーに解散宣言をするのかも知れませんし、フェードアウトで済し崩し状態に持って行く事もあったでしょう。
そして再び新たな若手を探し、オーディションを行いメンバーを決めてバンドを作り、仕上げて行く。そこには必ずかなりのワクワク感が伴うと思います。Horaceはそこに音楽活動の魅力を見出していると睨んでいます。
以降HoraceはWill, Queenと一緒に演奏することはありませんでしたが、しかしBrecker兄弟とは彼の晩年に邂逅します。96年2, 3月録音「The Hardbop Grandpop」ではMichaelが加わった4管編成、翌97年3月録音「A Prescription for the Blues」では兄弟二人による久しぶりのクインテット演奏、和気藹々とした雰囲気でレコーディングが行われ、メンバー全員、特にMichaelが上機嫌だったと伝え聴いています。
「The Hardbop Grandpop」

「A Prescription for the Blues」

ジャズ・レジェンドに対するリスペクトが半端ないMichaelにとって、Horaceのような巨匠のバンドへの参加は初めてになり、本人は大変名誉な事と感じていました。
どこかで既に紹介したエピソードですが、再び。
テナー奏者を探していたHoraceはオーディションを行いました。恐らく72年の事でしょう、Michaelの記憶では横一列になって7~8人のテナー奏者が並び、順番にソロを取りました。Horaceが「はい次、はい次、次はお前!」と言った具合でソロを取らせたようです。Michaelに他にはどんな人がいたの?と尋ねましたが「横一列だったから分からないよ」と言っていました。むしろ緊張で周りを見る余裕が無かったのかも知れませんね、しかし結果採用となり、既に参加していたRandyと目出たく合流しました。
レパートリーは新作である「27th Man」収録曲や直近の作品からのナンバーほか、Horace最大のヒット曲Song for My Fatherはどんなステージでも必ず演奏しなければならなかったようです。
余談ですがドラマーにしてシンガー、作詞作曲家でもあるつのだ☆ひろさん、素晴らしいプレーヤーです。彼のオリジナルMary Janeは大ヒットし、ライブでは必ず演奏したそうです。
でも誰しも同じ曲を演奏したくない時もあるでしょう、とあるギグでプレイリストから外した時がありました。最後の演目やアンコールが終了しても名曲Mary Jane聴きたさに、満員のお客様は一人も帰らなかったそうです!
さてジャズ・ジャイアントとの共演は毎回がエキサイティングな勉強の場、学ぶべき事がさぞかし沢山あったことでしょう、間違いなく張り切って演奏に臨んでいたと思います。以下はMichael本人が語ってくれた逸話、張り切り過ぎプレイの巻です。
あるコンサートでいつものようにSong for My Fatherを演奏していると、普段より演奏に入り込んだのでしょう、長いソロになりました。するとHoraceが「Go on, Go on!」と大声を発したそうです。Go onとは続けるという意味ですが、連呼することにより意味が強調され、「もっと続けろ!」となります。「おっ!今日のオレはイケてるのかな?」とばかりにソロをご機嫌にプレイします。するとまたHoraceが「Go on, Go on!」と今度は叫ぶように連呼したそうです!「これはもっと頑張らないと!」物凄い長さのソロになり、再び「Go on, Go on!」とHoraceの声が聴こえたのです。イケてるMichael君、天にも登るような気持ちで徹底的に吹き切りました!
でも演奏終了後にHoraceに呼びつけられ、「お前は何故あんなに長い演奏をしたんだ?!」と物凄い剣幕で怒られたそうです。Michaelは「だってあなたがGo on, Go onと何度も僕に言ったじゃないですか」「おいMichael、俺はお前にGo on, Go onとは言っていないぞ、Goneと言ったんだ!」Goneとは消えろ、止めろの意味です。その後のMichaelはさすがに平身低頭、193cmの長身を折り曲げ(汗)、謝りまくったたそうです。
その超長かったSong for My Fatherの演奏、どこかに残っていませんか?イケてるテナーソロ、とことんバーニングした、彼史上有数のライブ演奏だと確信しています(笑)
Michael and Randy Brecker

それでは演奏に触れて行くことにしましょう。CD 1の1曲目はWeldon Irvine作曲のLiberated Brother、「27th Man」収録のナンバーです。
IrvineはMaster Welの称号を持つピアニスト、コンポーザー、アレンジャー、代表作76年「Sinbad」にはBrecker兄弟も参加し、かのStuffのメンバーも勢揃い、彼らに全面的にバックアップされ、ホーンセクションも豪華な名盤です。
Sinbad / Weldon Irvine

Horaceが自分以外のナンバーを取り上げるのは珍しい事ですが、72年当時の彼の音楽的嗜好に合致したのでしょう。ピアノのパターンから曲が始まりベース、ドラムが加わります。「27th Man」のリズム隊よりも切れ味の鋭い、シャープさを感じますがこれはWillのベースプレイに負うところが大でしょう。Queenのドラミングも素晴らしいグルーヴを繰り出していますが、ジャズ屋のロック・テイスト感を拭うのは難しいです。ですがHoraceのタイム感には良く合っていると思います。
キャッチーなメロディとコード進行、構成、Horaceのハマりまくっている伴奏も効果的で、魅惑的でダンサブルな曲に仕上がっています。
ソロの先発はMichael、何とエグい音色でしょうか!Steve Grossman, Dave Liebmanたちユダヤ系テナー奏者(本人も含む)と全く同系統のサウンドです。それもその筈、使用マウスピースが同じなのです。1930年代に作られたOtto Link 最初期のMaster Model、ないしはFour Star Modelをリフェイスし恐らく5★から6番程度に広げたもの、かのElvin Jones 「 Live at the Lighthouse」のGrossman, Liebmanチームを意識したのか、出元がたまたま同じなのか、リードは多分La Voz Med. Hard、楽器本体はAmerican Selmer、シリアルナンバー13~14万番台でネックにピックアップのソケットがレギュラー装備されたVaritoneモデルを使用していました。
Michael plays Varitone Saxophone, Master Link Mouthpiece

もう一つ付け加えるならば、彼らは教えを乞うた先生も同じ、Joe Allardです。ほかの門下生ではEric Dolphy(!), Eddie Daniels, Bob Bergたち個性派サックス奏者の名前を列挙することが出来る、レジェンド・インストラクター、本来はクラシックのサックス、クラリネット奏者です。
Michaelが半分冗談めかして「知ってる?今Joeのレッスンでは僕のことが悪い見本として紹介されているって」と話すとDave Liebmanが「(笑)それは仕方がないんじゃない…?」と答え、Michaelは「別にいいけど…」仲の良い二人ならではの会話です(笑)
Joe Allard

Michaelのソロは「27th Man」のテイクも素晴らしかったですが、レコーディングを意識したコンパクトなサイズでした。こちらはスペースをたっぷり取り、数々のクリエイティヴなチャレンジも行いつつ思う存分ブロウしています。リズム隊、特にQueenとのコンビネーション、インタープレイに充実したものを感じます。
続くRandyの絶好調ぶりにも目を見張るものがあります。まずソロの歌い方に確立されたものを見出せますが、オリジナリティを十分に聴かせるフレージング、何よりタイムの安定感が素晴らしい!ビートに対する音符の位置、メトロノームが体内に埋め込まれているのでは(笑)、と言われても信じてしまいそうな程のタイトさ、この頃のMichaelのタイム感がまだ前後に揺れ気味だったのに比較し、タイムに関しては兄の方が抜きん出ています。
続いてピアノソロになりますが、ブルーノートを巧みに用いたHorace節炸裂状態、Willの縦横無尽なベースワークと相俟って魅惑のラテンワールドへようこそ、と誘っているが如しです!
ホーンを交えたセカンドリフ後、ラストテーマへ。エンディングではWillがベースでギターのカッティングのような音を発しています。
Will Lee

2曲目In Pursuit of the 27th Man、オリジナルではBrecker兄弟が参加せずにビブラフォン奏者David Friedmanが加わりテーマ、ソロを演奏、テンポもずっと遅いバージョンでした。
ここでのテーマ部分はビブラフォンが奏でるサウンドに合わせたのか、Michaelがフルートに持ち替え、Randyのミュート・トランペットとアンサンブルを聴かせます。それにしても随分と速いですね!
ラテンとスイングビートが混じり合ったナンバー、Willの繰り出すビートはラテンとスイングを全く自在に行き来します。Queenのプレイも実に的確、小気味良いシンバルレガート、フィルインは個性こそ希薄ですが、オールマイティにギグをこなせる職人タイプのドラマーです。
先発はRandy、ミュートを外し、お得意のネコの鳴き声奏法からソロをスタートします。早いテンポでもリズムのスイートスポットが常に見えている演奏を聴かせています。
続いてMichael、少し間を空けてからスネークインしプレイ開始です。兄のタイトなリズムの後だけに、on top感が目立ち、やや忙しなさを感じますが、something happenを起こすべく、自分自身の内面に語りかけて、魅力あるエキサイティングなアプローチを捻り出そうとする姿勢を見出すことが出来ます。フレージングの歌い方、ニュアンスの付け具合、ビブラートのかけ方いずれも大変に気持ちの入っています。
Horaceのソロはいつもの彼らしさをたたえているので、どうしてもWillのベース・プレイの方に耳が行ってしまいます。そのままドラムソロに突入、名前が一文字違いのElvinライクなテイストを聴かせつつ、巧みにプレイを展開します。ラストテーマへ、アウトロではテナーとトランペットのコレクティブ・インプロビゼーションに突入しバーニング、誰がリーダーか判断不能状態です!
Horace Silver

3曲目Big Businessは70年11月録音Horaceの作品「Total Response」(BN)に収録されています。
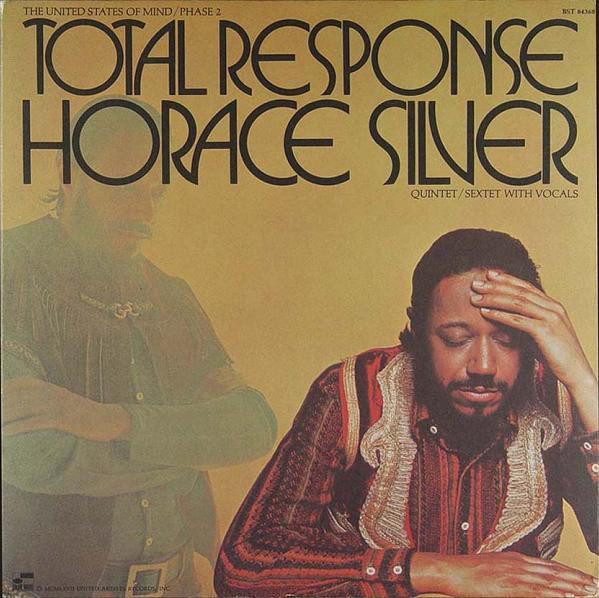
レイジーな雰囲気の中にもキラリと光るキメが冴える、大きく捉えれば変形のブルースナンバー、なかなかの佳曲です。先発Michaelは先程の演奏の不完全燃焼を挽回すべく、力のこもったプレイ、入魂ぶりが半端ありません!激しくアウトするフレージング、深いビブラートを伴ったエグいまでのニュアンス、加えて32分音符の超絶ラインが強力に存在感を提示します。イーブン系の16ビートでのMichaelのノリは実にスムースです。
その後のRandyは継続して絶好調をアピールします。アイデア、センス、ひょうきんさ、メリハリ、そしてタイム感!いずれも申し分ないスインガーぶりを聴かせます。後年のThe Brecker Brothersで聞かれるフレージング、アプローチを既にいくつも提示しています。
Horaceも若手に負けじとばかりに奮闘しており、ラストテーマに入ってもテンポが変わっておらず、リズム隊のタイトさを再認識しました。
Alvin Queen

4曲目Acid, Pot or Pillsも「Total Response」収録ナンバー、それにしてもドラッグ関係の単語を連ねた凄いタイトルです(汗)。この曲と次曲、CD 2の1曲目はロケーションが変わり、FinlandのPoriにて行われたジャズフェスティバルでの模様を捉えたものです。録音状態も多少良いように聴こえます。
アルバムの方では女性ボーカリストSalome Beyをフィーチャーし、Horaceはエレクトリック・ピアノを弾き、ギターがソロを取り、ホーンセクションが淡々とバックリフを吹いている、耳に心地良い、いわゆる売れ筋の音楽です。こちらではボーカルのメロディをピアノが担当して弾き、ホーンズはオリジナルを踏襲しています。
Michael, Randy, Horaceとソロが続きますが、Willのグルーヴィーで躍動感溢れるベースプレイが要となっています。
Will Lee

5曲目Gregory Is Hereも「27th Man」収録、Horaceの幼い息子に捧げたナンバーです。実父に捧げたSong for My Fatherの続編ですね。
憂いを帯びたホーン・メロディはロング・ノート主体なのに対し、対照的な細かいピアノのコンピングがスペースを埋めています。オリジナルの演奏はMichael 23歳、最初期の名演奏として名高いテイクです。こちらでも常にチャレンジ精神を翳しつつソロに臨む姿勢を感じさせる、クリエイティブな演奏を聴かせます。Randyにも全く同様なテイストを見出せます。
コーラスが長い曲ゆえでしょう、続くHoraceも含め全員1コーラスずつのソロになります。
Michael and Randy Brecker

CD 2, 1曲目Song for My Father、テーマの最後にMichaelが吹いたフィルインをHoraceが受け継ぎソロが始まります。途中にも何度かそのモチーフを取り入れつつプレイ、Willは水を得た魚のように表情豊かにラインをキープします。比較的短めに終えた後Randyの出番です。ここでもイマジネイティブなソロを繰り広げ、Willと結託してQueenもあわや倍テンポに突入しそうな勢いを見せます。
Michaelは少し離れた場所で兄のソロを聴いていたのでしょう、しばらく間があってからプレイ開始です。十分に温まっていたリズム隊は一触即発状態、Michaelも盛り上がっていますが、ここでソロが終了か、と感じさせるようにバンドの音量がディクレッシェンドして行きます。するとHoraceが伴奏を止めるではありませんか!常にバッキングでスペースを埋め尽くすスタイルの彼、彼のピアノが鳴っていないHoraceバンドの演奏は初めてです!
そしてコード進行はワンコードになり、テナー、ベース、ドラムの3人で全く異次元の世界に突入、フリージャズに突入せんばかりに、これはエグいです!Randy, Horaceもチャチャを入れた頃にテンポがなくなります!ワオ!もっと聴きたいのにも関わらずFade Out、この後は一体どのような展開になったのでしょうか?
Horace Silver

2曲目に司会者のアナウンスが入りますが、ここからはNew York Manhattan, Central Park南側にある、公共スケートリンクであるThe Wollman Memorial Skating Rinkにて行われたコンサートを収録したものです。ちなみに夏場なのでもちろんスケート客はいません(笑)。
メンバーにとってはホームグラウンドでの演奏、家族や仲間が大勢聴きに来ていたことでしょう。
3曲目Liberated Brother #2、録音クオリティがより改善されたので、各楽器の音像をはっきり聴き取ることが出来ます。
先発Randyはブリリアントな音色で快調にソロを展開、Michaelの音色もそれまでよりもクリアーさを感じさ、含みあるトーンを聴かせます。初めからハイテンションでスタート、ユダヤ系テナーマンの面目躍如のアプローチ、歌い方を繰り広げます。リズム隊のサポートもバッチリで実に楽しげです!
Horaceのソロ後セカンドリフを経てラストテーマへ、エンディングにもうひと盛り上がりあり、和気藹々の雰囲気でオーディエンスも演奏を堪能していた事でしょう。
The Wollman Memorial Skating Rink, New York

4曲目にHoraceの丁寧なメンバー紹介があり、5曲目In Pursuit of The 27th Man #2、先発はMichael、新たな表現を試みるべく出だしから尖っていますが、前出のテイクよりもタイムが安定しているように聴こえます。Horaceのバッキングも呼応していつになくアグレッシブ、リズム隊も実に的確にグルーヴを提供しています。
快調に飛ばし、Randyのソロに続きます。安定感この上ないプレイは彼の個性の一つ、そこを乗り越えて別な世界に突入してくれたらと思うのは贅沢でしょうか(汗)。
Horaceも二人に刺激を受け、アグレッシヴなソロを展開しています。
その後のドラムソロは比較的コンパクトにストーリーを作り上げて行きます。ラストテーマ後に猛烈なバンプを経てFineです。
Alvin Queen

作曲者自身の曲紹介に続き6曲目Gregory Is Here #2、こちらも録音状態の良さから演奏の細部にまで入り込めそうな勢いです。Randy, Michael, Horaceと好調ぶりを聴かせながら演奏が続きます。
Horaceの弾く引用フレーズは突拍子もないメロディが登場することがありますが、ひょうきんなお人柄ゆえなのでしょう。
Horace Silver

7曲目Song for My Father #2はHoraceのMCにもありましたが、あまり時間が残されていないと言うことで、ショートヴァージョンで演奏されました。
会場に来ていた先輩格のミュージシャン、ボーカリストのBabs Gonzalesに敬意を表して紹介しています。
テンポも幾分早め、テーマもリピートせず1度だけ、ソロはMichaelから、出だしレイジーさも感じさせる色っぽいブロウを聴かせますが、何しろ時間がありません!すぐさまターボが入り、熱きプレイの後半は何と前出のヴァージョンと同じくピアノレス・トリオでMichaelオンステージ!ここでのリズム隊のグルーヴの素晴らしさは特筆モノです!吹っきりで超盛り上がり、一度フェルマータしてから気を取り直したようにインテンポに戻りラストテーマへ、こちらも1度演奏しただけでアウトロへ、ワンコードでHoraceがソロを取り、エンディングのシカケは予め決めたあったのでしょうか、トリオでキメを演奏しFineです。
と言うことで、前出のフェードアウトしたテイクも同様にテンポがなくなり、フェルマータ後に復帰してラストテーマへ入ったと思われます。
それにしてもSong for My Fatherのコンサート・ヴァージョンのコンパクトサイズが聴けるとは思いませんでした。まだまだ色々な演奏が日の目を見ず、隠れているのでしょうね、きっと。
Michael Brecker

ラスト8曲目Gregory Is Here #3はItaly, Pescaraで開催されたPescara Jazzの模様を収録したテイクで、Bonus Trackとなってますが、僕にとっては本作の全曲がボーナスです(笑)!先発Michaelの音色は明らかに深みを増し、ソロのアプローチにも変化があり、何より余裕というか落ち着きを感じるのです。
サックスの音色に関しては録音状態や会場の箱鳴り、楽器、リードのコンディションにも左右されますが、それらを差し引いても演奏に明らかな変化を見出すことが出来ます。
クインテットのツアーで大いに得るものがあり、演奏に確実にフィードバックしたのでしょう。
この事を顕著に確認できる演奏が存在します。
Pescara Jazz演奏終了後の同日、同地のEsplanade Hotelにあるクラブ・ラウンジに場所を移しセッションが催されました。
Esplanade Hotel, Pescara

Horaceは参加せず地元のピアニストが代わりに伴奏を務め、WillとQueenを伴ってSonny RollinsのDoxyをプレイ、Brecker兄弟の熱いソロが収録されたアルバム「The Fabulous Pescara Jam Sessions 1970-1975」がそれです。

ちなみに別セッションのメンバーは50~60年代に活躍したミュージシャンばかりで、Brecker兄弟たちの参加はめちゃくちゃ異色です!熱狂的な彼らのファンがクラブ内にひしめいていたのでしょう、兄弟の一挙手一投足を見逃すまい、聴き逃すまいと言う猛烈な熱気を、歓声や拍手に認めることが出来ます。テーマ後のRandyのソロ、これは彼のスタンダード・プレイの中でも有数のクオリティを聴かせる素晴らしいものです。「さあRandy、どうぞ思いっきりスイングしてください!僕らは貴方の熱烈なファンです!」とばかりのオーディエンスの熱意に全く素直に応えています。さすが熱きラテン系Italy人、乗せ上手も国民性です!
ソロ終わりの感極まった一際目立つ大声は、先程のPescara Jazzの会場にも聴かれました。同一人物が発したものでしょう、やはり熱狂的です(笑)。続くMichaelのソロ、いや〜ありえないほどに素晴らしいです!これまたMichaelのスタンダード演奏史上に残る出来栄え、なんと物凄いのでしょう!実にスケールの大きさを感じさせ、これは若者の表現ではないですね。出だしからして違っています。
とにかく驚かされるのが8分音符の見事なまでのレイドバックです。本作「The 1973 Concerts」でのタイムは全般的にラッシュする傾向にあり、前のめりになりがちですが、このDoxyでの演奏は全く別人のように感じます。
Dexter Gordonと見紛うばかりのタイム感、Michaelこの頃には既にある程度レイドバックを習得していたのかも知れませんが、実は当日のPescara Jazzコンサートにて、ステージを分かち合ったのがまさしくDexter Gordon !!!彼のワンホーン・カルテットを目の当たりにし、あり得ないほどに背水の陣に位置するレイドバックを、早速イメージして演奏したのでしょう。
百聞は一見に如かず、自分にも経験がありますがリハーサルやステージ横でレジェンドのプレイを目の当たりにする事は、演奏家にとって最高の学びの一つです。
「Pescara Jazz 1973プログラム」

16分音符で聴かれる、アウトする、Steve Grossman, David Liebmanライクなフレージングのタイトなこと!実はDexterの吹く16分音符は8分音符と異なり、いささかラッシュし、on top気味です。あまり16分音符を演奏しないので目立たないだけなのですが。
Michaelは16分音符も実に正確、というかリズムのスイートスポットを捉えて、心地良さを伴ってまでブロウしています。
Grossmanが80年代中頃から、Sonny RollinsとJohn Coltraneの融合と言えるスタイルでプレイしていましたが、ここでのMicahelのスタイルは言ってみればDexterとGrossman、そしてホンカー・テナーの融合、これらをMichaelのアーバン・テイストが光るメルティング・ポットで一度しっかり溶かした後、バランス良く再調合したプレイと言えましょう!
これは誰もなし得なかった表現で、本人は元より他の誰かも含め、この演奏でしか聴く事が出来ません!
フレージングのメリハリ、高度な音楽性に裏付けされたラインの数々、研究熱心なMichaelは徹底的にジャズフレージングの構造や仕組みを分析、研究し、しかし決して頭でっかちになる事はなく、常に「歌う」「スイングする」を念頭に、音楽性豊かに演奏していました。
2021.08.22 Sun
今回はHorace Silverの65年リリース作品「Song for My Father」を取り上げたいと思います。
Recorded: October 26, 1964 on 1, 2, 4, 5 / October 31, 1963 on 3, 6
Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs
Label: Blue Note(BST 84185)
Producer: Alfred Lion
tp)Carmell Jones ts)Joe Henderson p)Horace Silver b)Teddy Smith ds)Roger Humphries
On “Calcutta Cutie” tp)Blue Mitchell ts)Junior Cook p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks
On “Lonely Woman” p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks
1)Song for My Father 2)The Natives Are Restless Tonight 3)Calcutta Cutie 4)Que Pasa 5)The Kicker 6)Lonely Woman

Horace Silerの代表作にしてモダンジャズのエバーグリーン、収録曲いずれも名曲であり名演奏、また構成力抜群のアルバムとしてもバランスに長け、永く鑑賞し続けるのに申し分ない作品に仕上がっています。
本作は彼の最大のヒット作となり、全米ヒットチャート95位、Top R&Bチャート8位にランクインされた、初めての栄誉でもあります。
多作家Silverの15作目に該当し、レーベルは1作目からリリースし続けているBlue Note(BN)、録音エンジニアもジャズの音を録音させれば右に出る者なし、名手にしてアーティストの如き超個性派Rudy Van Gelder、セールスはレーベルに大きく貢献し、以降もBNが存続する限り作品をリリースし続けました。本人曰く「BNはやりたいようにやらせてくれたし、3年毎の契約更新の度にギャラをアップしてくれた」破格の待遇で28年間の長きに渡り在籍出来たのは彼だけになります。
Horaceの作品にはピアノトリオ、3管編成もありますが、そのほとんどがモダンジャズ黄金のコンビであるトランペット、テナーサックスをフロントに擁したクインテット編成、BN最後期にはブラスセクション、ウッドウインド・セクション、コーラス・アンサンブル、パーカッション・アンサンブル、ストリングス・セクションを加えたいずれも大編成「Silver ‘N」シリーズの作品も録音されていますが、それらの基本となる編成もやはりトランペット、テナーのクインテットです。
彼の書くオリジナルはメロディラインとその音域、2管のハーモニーを響かせるのに丁度良いレンジ等、トランペット〜テナー、楽器の機能性を熟知したライティングに徹しています。
「Silver ‘N Brass」

クインテットの特徴として継続して同じフロント陣が続けてプレイする事が少なく、作品毎に入れ替わり、その当時の若手有望株がピックアップされて演奏する傾向にあります。
去来したトランペット奏者挙げるとKenny Dorham, Donald Byrd, Joe Gordon Art Farmer, Blue Mitchell, Carmell Jones, Woody Shaw, Charles Tolliver, Randy Brecker, Cecil Bridgewater, Tom Harrell, Bobby Shew, Clark Terry, Ryan Kisor…
同じくテナー奏者はHank Mobley, Junior Cook, Clifford Jordan, Joe Henderson, Tyrone Washington, Stanley Turrentine, Benny Maupin, George Coleman, Houston Person, Harold Vick, Michael Brecker, Bob Berg, Larry Schneider, Eddie Harris, Ralph Moore, Branford Marsalis, Red Holloway, James Moody, Jimmy Greene…
この錚々たる布陣はまるでフロント奏者の紳士録、そしてバンドは若手の登竜門として間違いなく機能していました。
繰り返し起用されても2~3作、1作でチェンジされてしまうフロント奏者がほとんどの中、例外なのがBlue MitchellとJunior Cookのフロント・チーム、彼らは59年「Finger Poppin’」を皮切りに、同年「Blowin’ the Blues Away」60年「Horace Scope」62年「The Tokyo Blues」63年「Silver’s Serenade」の5作、足掛け5年に渡り連続して参加しており、その間に彼らを擁して62年初来日も果たしています。名コンビぶりを発揮した彼らとの共演作は基本的にハードバップ・スタイルでの名盤です。
「The Tokyo Blues」

Horaceはフロントを変える事によって演奏を常に新鮮なものにするのを念頭に置いていたと思います。と言うのは彼のピアノプレイが基本的に生涯変わることなく、”味”で聴かせるスタイルを貫いていましたから。
オリジナリティに富んだナンバー、独創的なメロディライン、リズムの解釈、ユニークな構成を有し、それでいてキャッチーな楽曲を数多く世に送り出したHorace、加えてバンドを率い、自らの楽曲をレパートリーに演奏活動を精力的に続け、アルバムも継続的にリリースしました。同じ活動スタイルを貫き通したピアニスト、Herbie Hancock, Chick Coreaにも並び称されます。
この二人のピアノ演奏、インプロビゼーションにかける執念には凄まじいものがあり、素晴らしい成果を常に聴かせていました。でもHorace自身の演奏に関してはその表出は少なく、ピアノプレイに対してある種の無頓着さを否めません。
Horace Silver

ハードバップど真ん中から、次第に彼のエッセンスを凝縮した、エグいまでに捻りを効かせた作曲スタイルに変化を遂げるHorace、さらには時代を反映したコンテンポラリーな要素、例えば前作「Silver’s Serenade」で確認できる、それまでは聴かれなかったモーダル的なサウンドにコンポーザーとしての領域が広がり始めました。
ここでのMitchell, Cookはアンサンブルでは息の合ったプレイを聴かせますが、ソロのアプローチに於いては旧態依然に響きます。Horaceの楽曲とフロント陣の表現出来るアドリブの能力に溝が生じ始めたのです。
「Silver’s Serenade」

何か今までとは違う新しいサウンドがHoraceの頭の中で鳴り始めています。そして一度聴こえ始めてしまったらもう後には戻れません。本作録音の1年前、63年10月にMitchell, Cookのコンビで本作収録のCalcutta Cutieを録音しています。しかし彼らはアンサンブルのみで参加し、ソロはありません。
本作収録曲はそれまでのHoraceの作風よりもずっと斬新さを湛えています。レコーディング1年前にまだ本作収録ナンバーは形を成してはいなかったと思いますが、ある程度のイメージは本人の頭の中にあったでしょう。
Calcutta Cutie録音から3ヶ月後の64年1月にもMitchell, Cookでのテイクが存在します。想像するにHoraceは5年間行動を共にした連中と、出来れば自分の描く新しいサウンドを共有したかったのだと思います。メンバーとの仲もさぞかし良かったのでしょうし。
もしかしたら本作収録曲に近いコンセプトのナンバーを彼らで一旦は演奏してはみたかも知れません。しかし彼らのアプローチでは物足らず(特にCookのテナー演奏が)、メンバーを一新すべく以前からミュージシャン仲間で噂のあったJoe HendersonとCarmel Jones、Teddy SmithとRoger Humphriesに白羽の矢を立て、パーマネントなバンドとしてリハーサルやライブに臨み始めたのです。
とは言えCookとは良い友人関係を継続させていたのでしょう、出戻りが滅多にないHoraceのバンドですが88年3月録音「Music to Ease Your Disease」に20年ぶりに彼を招き、Clark TerryとのフロントでHoraceのオリジナルをプレイしています。もっとも演奏内容としては全曲男性ボーカルをフィーチャーしたファンキージャズ路線ですので、むしろCookのテナー奏が相応しいアルバムですが。
ちなみにここでHoraceが作詞した歌詞は(いつの頃からか、彼は作曲だけではなく作詞も手掛けるようになりました)ボーカリストAndy Beyのテノール・ボイスに良く合致し、Terryの流麗でスインギーなトランペット・プレイに加え、Ray Drummond, Billy Hartのリズム隊も大健闘しています。
ジャケットで見られる医師に扮した(!)Horace自身のアナウンスまで付加され、これは医事漫談の創始者でジャズ好きな今は亡きケーシー高峰を連想させますが(汗)、実に楽しげな作品に仕上がりました。
「 Music to Ease Your Disease」
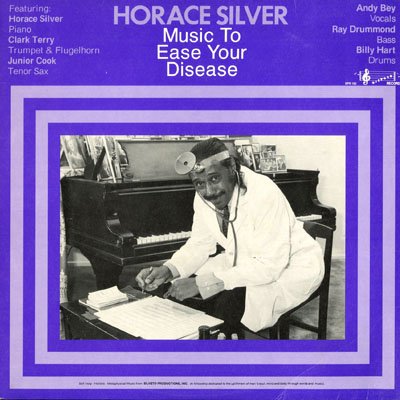
話をもとに戻しましょう、実際にレコーディング前の演奏が残されています。「Live 1964」は4ヶ月前64年6月6日New Yorkのライブハウスで収録したBootleg盤、演奏曲はHoraceの旧作Filthy McNasty, The Tokyo Blues, Senor Blues, Skinney Minnieです。多少冗長な部分もありますが、Joe HenとJonesの新フロント陣は旧メンバーとは一線を画すアプローチを聴かせます。
「Live 1964」
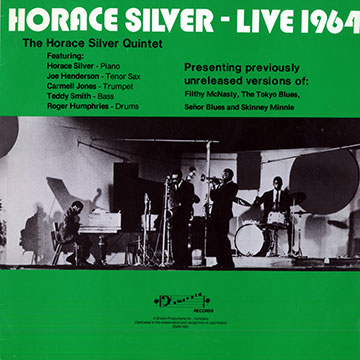
同じく64年7月28日同一メンバーによるParisでのライブを収録したDVDもリリースされています。こちらの収録曲はTokyo Blues, Pretty Eyes(次作The Cape Verdean Blues収録です!)、新作よりThe Natives Are Restless Tonight、バンドの纏まりも素晴らしく、既にレコーディング・クオリティをクリアーしています。
「Paris 1964」

メンバーチェンジを挙行した新生Horace Silver Quintetはリーダーの狙い通り確実にワークし始めました。Joe Henのプレイが殊更素晴らしく、クリエイティブにしてスポンテニアス(全曲壮絶なまでのイメージの連続です!)、ライブDVD収録Pretty Eyesでの炸裂ぶりには神がかったものがあります!
そして本編「Song for My Father」ではまたガラッと違ったアプローチを見せるJoe Hen、彼の演奏に触発されたリズムセクションも実に創造力と集中力に満ちたプレイを繰り広げ、歴史的な名盤の制作に貢献しました。
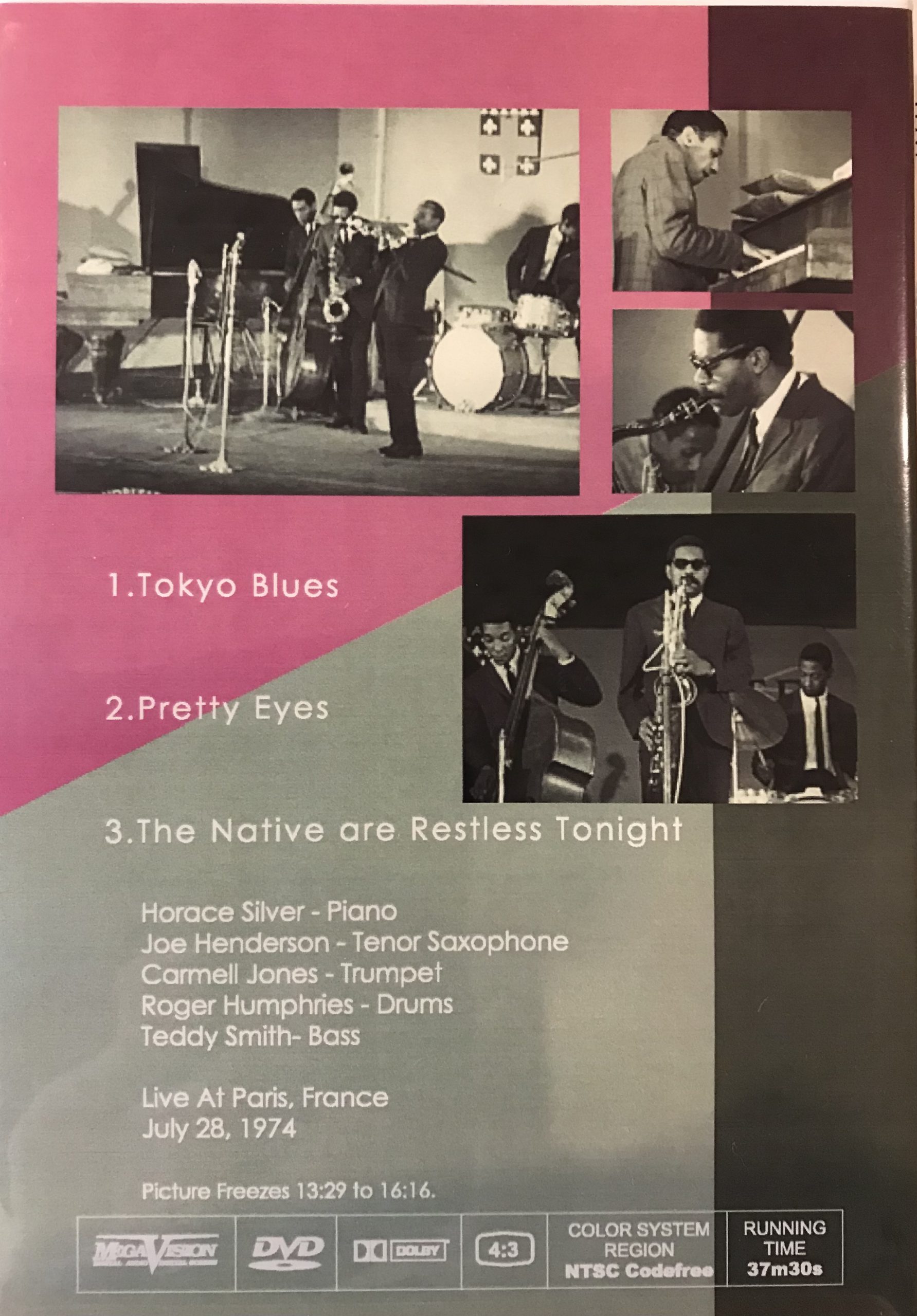
それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。
1曲目表題曲Song for My Father、その名の通り彼の父親Johnに捧げたナンバー、父本人が写った名高いジャケットはHoraceの親孝行ぶりを物語っています。
息子はJohnをNew Yorkのライブハウスでの演奏に招待し、まだ未録音であったSong for My Fatherを「親愛なる父親に捧げて書いたものです」とアナウンスして演奏したと言うことで、それはそれはお父様お喜びになった事でしょう、ですがしばらくして彼は逝去します。その後この曲のレコーディングを行い、追悼の意味合いを込めてBNにかけ合い、ジャケ写にも登場させたのでしょう。
Wayne Shorterの同じくBNからの作品「Speak No Evil」のジャケット・デザインはShorterたっての願い、不仲だった当時の奥方Teruko Ireneに愛情表現を発するべく、フォーカスを甘くした彼女の写真と、インパクトが強烈なキスマークの掲載をプロデューサーAlfred Lionに懇願して実現させました。
「Speak No Evil」

カーボベルデ共和国出身、ポルトガル系アフリカ人で米国に移民したJohnは趣味でギターを演奏し、歌を唄い、彼や叔父たちが良くホームパーティーでポルトガル民謡を披露し、Horaceは幼い頃から家で子守唄のように耳にしていました。
父親は大活躍中の息子に、自分の楽曲にポルトガル民謡を取り入れたらどうかと進言していたようですが、それはそれで照れ臭いもので、息子は後回しにしていました。
似たようなシチュエーションですが、アルゼンチン出身のGato Barbieriは米国に進出してからも、母国の代表的音楽アルゼンチンタンゴを封印していました。自分のルーツに目覚めてからは積極的に演奏するようになり、寧ろ「Last Tango in Paris」などのタンゴを取り上げたオリジナル曲がトレードマークになりました。
「Last Tango in Paris / Original Sound Track」

Song for My Fatherの誕生について、HoraceがBrazilへ64年2月、同地出身のパーカッション奏者Dom Um Romaoと一緒に訪れた際に、ポルトガル語圏であるブラジルがBossa Novaブームに沸いていた事にインスパイアされ、リズム的にはブラジルから、メロディとしては古いポルトガル、カーボベルデの民謡からの影響を受けたと紹介しています。
そしてこの曲には自身の音楽的ルーツを思い出させる匂いがあるとも語っています。
印象的なベースとピアノの左手によるパターンから曲が始まります。何と表現したら良いのか、その後のメロディラインが発するインパクトは何度聴いても減衰する事なく、Horace Silverワールドを徹底的に印象付けます。
よく引き合いに出す芋焼酎の話ですが、酒を呑み始めた頃には臭みで一切受け付けず、加齢と共に酒の味が分かる様になり、いろいろな種類の酒を経て究極芋焼酎に辿り着いたが如く(笑)、Jazz演奏も独特の匂いが大切で、若い頃に拒絶していた臭うが如き楽曲やプレイにこそ魅力を感じるのですが、それにしてもこんなオリジナルはどこを探しても存在しないでしょう!

Song for My FatherではBossa Novaのリズムが採用されていますが、HoraceがBrazilで目の当たりにし、衝撃を受けたもう一つのリズム、Sambaは65年10月録音の次作「The Cape Verdean Blues」の表題曲で用いられています。
文字通り自らのルーツを冠したこの作品は、Song for My Fatherで覚醒した自分のオリジンを更に推し進めたアルバム、続投Joe Hen、名手Woody Shawに加え、レコードのSide B 3曲では巨匠J. J. Johnsonを迎えた申し分のない3管編成による名盤、個人的には彼の最高傑作と捉えています。
ちなみにJoe Henはこのアルバムを最後にHoraceの元を去ることになりますが、2作だけの参加になり、以降共演する事はありませんでした。
「 The Cape Verdean Blues」

更に次作、1966年11月録音の「The Jody Grind」ではMexico特有のリズムであるマリアッチを取り入れた名曲Mexican Hip Danceを収録、Shawのトランペット・ソロが鮮烈ですが、ラテン音楽が有する様々なリズムに対するHoraceのあくなき探求心を痛感しました。
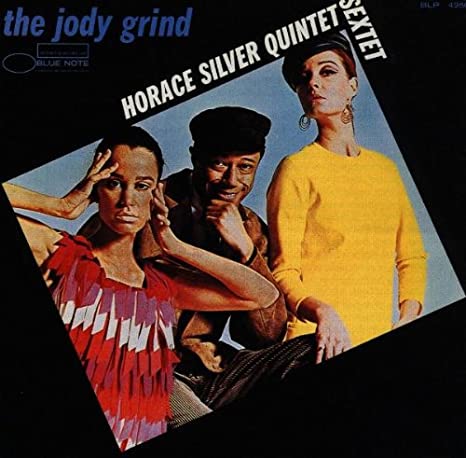
閑話休題、テーマを繰り返したのちソロの先発はHorace、独特の”つんのめった”リズム、音符を拍に置くかの如き8分音符のスピード感とは無縁のユニークなタイム感、一聴Horaceと判断出来る個性ではあります。
続くJoe Henは漆黒の如きダークでテイスティ、極太にして付帯音の塊のテナートーン、こちらも一聴してJoe Henと即断出来る個性を振り撒いています。
リズムに対しゆったりと、忍足で近寄るかの如くソロを開始します。音の間合いを取りながら次第にフレージングが細かくなり、聴かせどころのブレークでは3連符を用い活性化を試みています。
音域も広がりつつ更にフレーズが細分化され、Joe Hen節のオンパレードに移行します。フレージングに用いる音の選択、ソロの構築の大胆さといい意外性を内包したストーリー性、センス、これは新生Horace Silverクインテットのオープニングに全く相応しいプレイです!
僕も参加させて貰っている日野皓正氏の94年作品「Spark」、こちらでも「Song for My Father」を取り上げています。リズムの解釈をユニークなものにすべく、スタジオ内で試行錯誤を繰り返したのを覚えています。日野さん自身もHoraceのクインテットに参加していた経験があり、その時の貴重な話も伺いました。
「Spark」

2曲目The Natives Are Restless Tonight、テンポの早い変形マイナーブルースです。Horaceが子供の頃、隣に住んでいた一家がパーティ好きで、明け方までよく騒いでいた情景を曲にしたそうです。
そう言えば聴いていても「さあ、今宵はパーティで一晩中盛り上がろうぜ!」のような、ウキウキする高揚感が感じられるユニークなナンバー、ピアノの興味深いキメ、テーマ後のファーストソロに食い込んだリフの用い方、発想がありきたりではなくHorace流の捻りが効いています。
この曲も前出「Spark」でプレイした覚えがあります。今は亡き名ピアニスト、アレンジャー鈴木”コルゲン”宏昌氏が採譜した譜面で演奏し、彼もピアノで参加、日野元彦氏のドラミングが冴え渡っていて、録音も行ったように記憶していますがCDには収録されませんでした。
先発はCarmell Jones、ブリリアントでスピード感あふれるトランペット・ソロを展開します。フレージング的にも自分らしいウタを唄おうという強い意志を感じるアプローチ、彼はジャズの逸材を多く輩出したKansas City出身、スタジオミュージシャンとしても60年代活躍しました。
Carmell Jones

続くJoe Henのソロは出だしからトリッキーに先制攻撃、彼のリズミックなアプローチを聴いているとあまりのシャープさにリズムを取り始め、椅子から腰が浮いてしまいます!その後細かくフレーズを繰り返し、フラジオ音域、フリークトーンにまで至り、ソロ第一のヤマ場を設けました。Roger Humphriesもナイス・サポートです!
次のヤマ場に至るためにJoe Henはアウトするフレーズ、そしてリズミック・シンコペーションを多用しハーモニー、リズム的に緊張感を持たせながら小刻みに、しかし大胆にストーリーを構築し、高いテンションを維持しながらあたかも名山が連なる連峰、山脈の如き音のシリーズを披露しています。聴き惚れてしまうほどの素晴らしい構成力を持ったソロ、本作ハイライトの一つです!
続けてピアノソロへ、テーマのメロディを交えながらソロを開始、テナーソロにインスパイアされたのかアグレッシブなソロを展開、左手のパーカッシブな用い方に表れています。
ベースソロに受け継がれますが予想よりも短く終わったのでしょう、一瞬の空白があり、そのままドラムソロに突入します。堅実ながら小気味良いスティックさばきでエキサイティングなフレージングを繰り出し、職人然たるクールなブレークを経てラストテーマのイントロに入ります。
テーマ後にはアウトロが設けられており、ゆったりしたテンポでのテーマに基づいたメロディはホームパーティ終了後の余韻を、ないしは騒いで散らかしまくった自宅を翌日の昼間、二日酔いで後片付けしている様を表現しているが如しです(笑)。
Joe Henderson

3曲目Calcutta Cutie、こちらはポルトガルやブラジルでもないインドのCalcuttaですね。彼の地に楽旅で赴いた際、気になるCutie(かわい子ちゃん)がいたのでしょう(笑)
前述の通りこの曲はフロント陣、そしてリズム隊も一新します。
誰かがパーカッションを鳴らしているSong for My Father風なイントロを経て、メロディが登場します。エキゾチック、ミステリアスでいて安堵感と不安感が共存する、何とも言えぬ色気を発する佳曲、Horaceの書く曲に新たな作風を見出しました。
ソロはHoraceから、曲の裏メロディとも解釈できる興味深いラインを演奏し、サビに入ります。サビ後もこのラインを弾き続けても良かったのでは、と感じました。セカンド・リフ的な効果が成立したと思います。その後はGene Taylorのドラムソロへ、皮ものを中心とした演奏にはMax Roachの影響を見出しました。
長めのイントロ〜バンプを経てラストテーマへ、ホーンのソロが入らずピアノとドラムのソロだけに絞ったことでむしろ曲のメロディ、サウンド、ムードがくっきりと現れました。
この曲も「Spark」に収録されています。手前味噌で恐縮ですが、アルバム録音の翌年New Yorkを訪れた際、ホテルの部屋でJazz専門のFM局WBGOを聴いていると、新譜紹介で「Spark」を取り上げているではありませんか!このCalcutta Cutieが選曲されオンエアされているのを聴き、Jazzの本場のラジオ局で自分が参加している演奏が流れているのには感無量でした。
Horace Silver

4曲目Que Pasa、英語でWhat’s Up?の意味のスペイン語です。と言うことで本作に登場する国名は多岐に渡ります。
こちらもSong for My Father風のイントロをベースに、それまでに無かった新たなピアノのパターンを加えた構成になっています。フロントのハーモニーを伴ったメロディがエキゾチックさを醸し出し、メロディをCallとすれば対するイントロで用いられたピアノ・パターンがResponseに該当し、ジャズ表現の重要な要素であるCall & Responseを表現しています。
繰り返されるバンプ部分ではドラムソロも挿入され限られた曲のパーツを上手く使い回していると思います。Humphriesのカラーリングもメリハリの効いた様々な表情を見せており、これはライブを繰り返し行った結果に違いありません。
ソロの先発はHorace、いつもの彼らしく転びがちなタイム感による、でも普段より朴訥としたテイストを聴かせます。
続くJoe Henソロの冒頭唐突に現れるアプローチ、動物の鳴き声のようなサウンドに引き込まれてしまいますが、一体どんなイメージの具現化なのでしょう?またその後のシングル・タンギング連続のフレージングに思わずレコードの針が飛んでしまったのでは?と連想しましたが、これはCDでした(笑)。
巧みにして多彩な、そして何よりも意外性を最重要項目に置いているかのような、そしてレコーディングという限られたサイズの中で最大限の効果を生むようにも、いずれにせよJoe Henの表現は曲の持つ雰囲気に決して埋没する事なく自己主張を遂げ、むしろ楽曲に対して問題提起を行なっているかのようにも感じ、結果絶妙なバランスで演奏曲への溶け込みを成し得ているのです。
リズム隊は巧みにダイナミクスを設定しながら、構成としてはシンプルなこの曲に存分にメリハリを付けています。Horaceのドラマー、ベーシストに対する人選も狙い通りです!
極上のテイクに仕上がったこの演奏に対し、エンディングは終わりそうでなかなか終わらず、トリオは名残惜しさすら感じているのでしょうか?
Roger Humphries
5曲目はJoe Henの作曲によるアップテンポの、こちらも変形ブルースThe Kicker。本作直後の12月にJoe Hen参加のBobby Hutchersonリーダー作「The Kicker」や、自身も67年録音リーダー作で同じく「The Kicker」で再演しています。
「The Kicker」


HoraceはJoe Henのプレイはもちろん、楽曲にも一目置いていました。次作「The Cape Verdean Blues」でも再び彼のオリジナルであるMo’ Joe’を取り上げています。
ペンタトニック・スケールを基本用いたメロディラインですが、Joe Henらしい捻りが効いたナンバー、こちらもThe Natives Are Restless Tonightと同様でテーマ後に、シンコペーション・フレーズがはみ出してソロ1コーラス目に食い込んで演奏される構成、しかも同じく2コーラス目にもです!これはビッグバンドのアンサンブル、Tutti的なアイデアから来ている様に捉えられます。
ブレークやリズム隊の仕掛けも実に有効にワークしています。
Humphriesの巧みなカラーリングに導かれるようにJoe Henがソロの口火を切ります。何と言うスピード感、リズム感、スイング感でしょう!4拍子のナンバーですが、3拍子揃ったとはこのソロの事を言うのでしょう(汗)。その後もトランペット、ピアノ、ドラムにも2コーラスのブレークが効果的に用いられたソロの応酬、ソリッドなアンサンブルを存分に聴かせています。
Joe Henderson

6曲目アルバムのラストを飾るのはLonely Woman、Ornette Colemanにも同じタイトルの名曲がありますが、そちらは肖像画に描かれていた寂しそうな表情の、ノーブルな女性をイメージして書かれたナンバーです。
こちらの方はHoraceの父親が亡くなり、残され未亡人となった母親に捧げたオリジナルです。ピアノトリオ編成で演奏されているのは母親に対する敬愛の念から頷けますが、総じてこの作品はHoraceの家族や育った環境がテーマになった、いわゆる私小説的なアルバムと言えましょう。
2021.08.08 Sun
今回はDexter Gordonの1976年ライブ作品「At the Village Gate 1976」を取り上げたいと思います。
Live at the Village Gate, New York, October 25, 1976
Label: Domino Records
ts)Dexter Gordon tp)Woody Shaw p)Ronnie Mathews b)Stafford James ds)Louis Hayes
on Bonus Track “Bags’s Groove” ts)Dexter Gordon tp)Woody Shaw vib)Milt Jackson p)Kirk Lightsey b)David Eubanks ds)Eddie Gladden “Playboy Jazz Festival”, Hollywood Bowl, Los Angeles, June 20, 1982
1)Fried Bananas 2)Gordon introduces the band 3)Strollin’ 4)You’ve Changed 5)Bags’ Groove
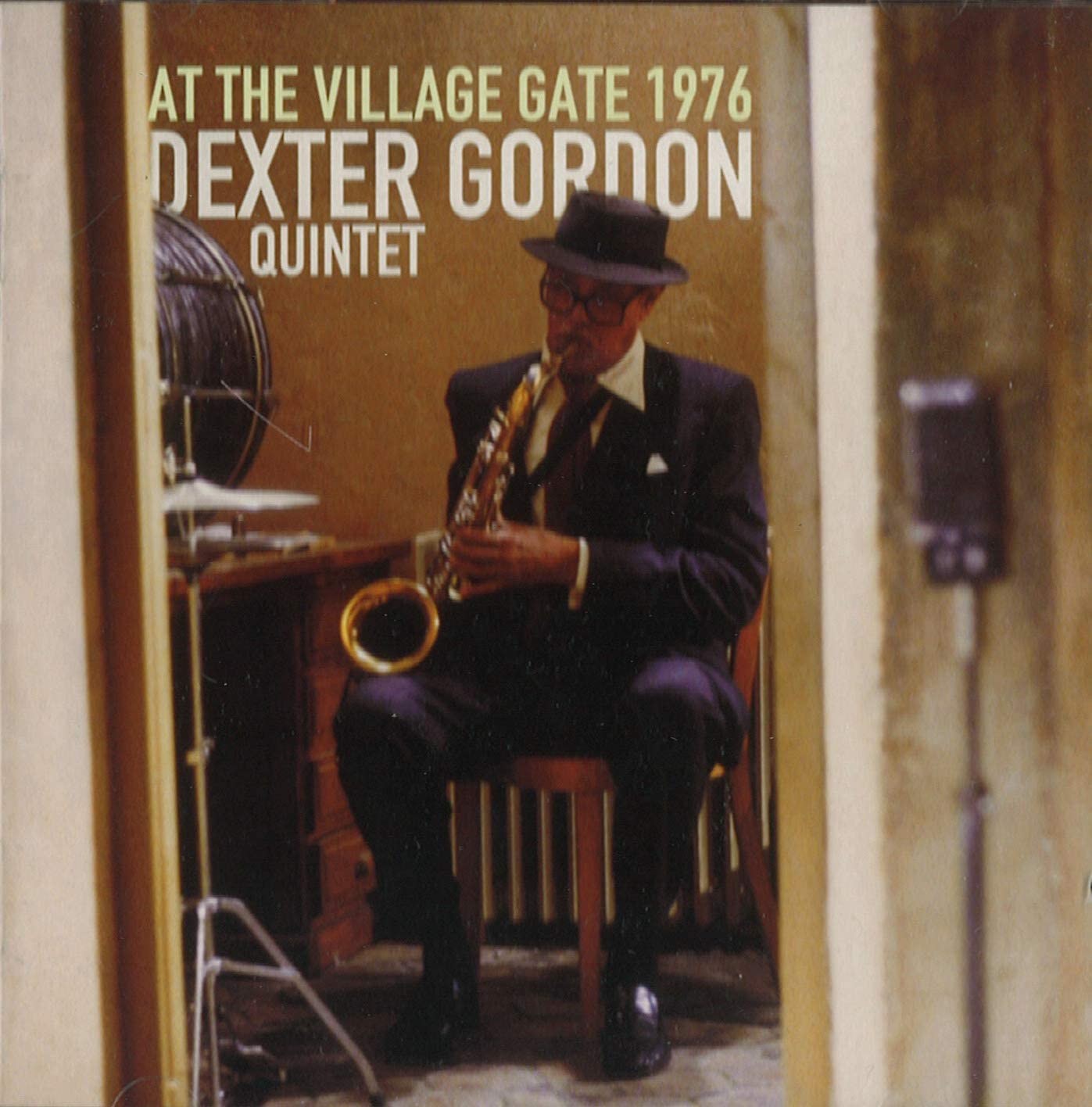
Dexterはジャズシーンが停滞していた米国を60年代初頭に離れ欧州に移住し、ParisやCopenhagenに居を構え悠々自適に演奏活動を送っていました。
同じ渡欧組であるKenny Clark, Bud Powell, Kenny Drew, Horace Parlan, Albert Heath, Bobby Hutchersonら、また本場のジャズプレイヤーからの薫陶を受けた優れた欧州ミュージシャンTete Montoliu, Niels-Henning Pedersen, Pierre Michelot, Alex Rielらとも演奏を重ね、足掛け15年の長きに渡り欧州で音楽活動を展開していましたが、しかしこの辺りが潮時と感じたのかもしれません、故郷の音楽シーンも随分と様変わりしたのもあり、76年10月頃に本国に戻りました。
とは言え65, 69, 70, 72年といずれもごく短期間ですが米国に戻り、Blue NoteやPrestigeにレコーディングを行っており、Dexterはこれらの一時帰国で合計10枚以上のアルバムを残しています。
渡欧はしたものの、one & onlyな魅力満載のDexterの演奏は米国ファンに求められており、ニーズによりアルバムをリリースし続けたと言う事です。このバックグラウンドが存在したからこそ帰国してからも華々しくカムバック出来たのでしょう。
欧州でもSteepleChase Labelを中心にライブ、スタジオ録音を30作品以上をリリースしており、多作家ぶりを印象付けています。
想像するに本人の売り込みは全く無く(そもそも熱心に自己アピールするタイプのプレイではなく、ごく自然体での演奏ですから)、レコード会社の方から作品制作の依頼が舞い込んで来るのでしょう、彼ほどの個性と風格、気品、音楽性、人気、存在感、しかし何よりこれは時代の成せる技に違いありません。
一時帰国盤では65年5月録音「Gettin’ Around」69年4月録音「The Tower of Power!」70年8月録音「The Jumpin’ Blues」を挙げたいと思います。



76年12月、本作と同一メンバーでNYC, Village Vanguardでのライブ演奏を収めたアルバム「Homecoming」が文字通りの帰国第一声でしたが、本作は遡ること1ヶ月半、帰国直後の10月真にフレッシュなDexterを捉えた演奏で2011年に発掘、リリースされました。正規の録音ではないので音質やバランスは決して良くありませんが、何しろバンド全員の一丸となった勢いが素晴らしく、個人的には本作の方に軍配を挙げたいと思います。

70年7月Swiss Montreux Jazz Festivalにて、Junior Manceとの演奏を収録した「Dexter Gordon with Junior Mance at Montreux」はワンホーン・カルテットによる絶好調のDexterを捉えた作品、ライブのオープニング・ナンバーが同じFried Bananasなので似たような印象を受けますが、本作ではトランペット界の鬼才Woody Shawを迎えたモダンジャズ黄金のコンビネーションによる2管編成、両者のユニゾン演奏だけでも相乗効果で何倍にもメロディが分厚く聴こえます。
Dexterのどちらかと言えば穏やかで朗々としたサウンドに強力なスパイスを加える効果を生んでいます。しかもShawのアグレッシヴでスポンテニアスなプレイは決してtoo muchではなく、むしろDexterのプレイと素晴らしいコンビネーションを生み出し、対極を行く演奏を信条としていますが、互いに無い部分を補い合うかの如く絶妙なバランス感を伴い、オーディエンスを興奮の坩堝に誘い込みます。
DexterはFreddie HubbardやDonald Byrd、Benny Baileyら他のトランペット奏者とも共演を果たしていますが、Shawほどのプレイの相性の良さは感じられません。ふたりの人間関係が大変良好だった故のように思います。

DexterとShawのそもそもの出会いはSwiss出身のピアニスト/アレンジャーGeorge Gruntzの72年録音アルバム「The Alpine Power Plant」です。Phil Woods, Rolf Ericson, Benny Bailey, Sahib Shihabらを擁しBaden, Switzerlandで録音されたビッグバンド・プロジェクト、ここでの共演で互いに惹かれ合うものを感じたふたりは「ぜひとも一緒にバンドをやろう!」と約束を交わしたのだと想像しています。

Shawが共演したサックスプレーヤー、テナー奏者ではJoe Henderson, Benny Maupin, Azar Lawrence, Billy Harper, Carter Jefferson、アルト奏者ではEric Dolphy, Jackie McLean, Gary Bartz, Rene McLean, Anthony Braxton, Kenny Garrettたちモーダルや前衛スタイルのプレーヤーで、Dexterのようなハードバップ・スタイルのサックス奏者との演奏は珍しい例です。しかし本作に於ける、特にFried Bananasでの両者の一体感はジャズ史に残る素晴らしいコンビネーションだと思います。
スタイル的には全く異なる語法、方法論ですが、迎合することなく徹底的に自分を出した演奏を展開しても違和感がないのは、ひとえにお互いのプレイを尊重した結果に違いありません。
ドラマーLouis HayesとDexterは何度もセッションを重ね気心の知れた間柄、ベーシストStafford JamesとピアニストRonnie Mathewsは恐らく初共演になるので、Hayesの推薦があったのかも知れません。何しろ米国のジャズシーン、ミュージシャンの人脈にはDexter疎くなっていましたから。
Dexter Gordon

それでは演奏内容について触れて行きましょう。1曲目Fried Bananas、スタンダードナンバーIt Could Happen to Youのコード進行を元に書かれたDexterのオリジナル、早い話替え歌ですね(笑)、メロディアスかつリズミックな名曲、自身は機会あるごとに取り上げて演奏していますが、前述の69年4月レコーディング「The Towe of Power」と同時録音「More Power!」が初演になります。

冒頭司会者のアナウンスが入りDexterの紹介が始まります。『Copenhagenから来た若者(この時49歳ですが)、one and only, Dexter Gordon!』その直後に聴かれるShawによるファンファーレ、さりげにこの音色の素晴らしいこと!リズムセクションも音を出して歓迎の意を表しています。
オフマイクで『Fried Bananas』とメンバーに演目を伝え、その後何故か仏語(CopenhagenはDenmark語が公用語ですが)での挨拶の後、マイクに向かい演奏曲目のアナウンスが始まります。2回続けて曲名を紹介していますが、Dexterはステージでタイトルやメンバーの名前を連呼する傾向があります。
通常よりも速いテンポでスタート、Shawがテーマをちゃんと吹けていないのはバンド発足が間も無いからでしょうか(汗)。Dexterはテーマのメロディ奏から既に抜群のレイドバックを提示しており、この事に動揺したShawがテーマを間違えたのかも知れません。テーマの後半はShawもDexterのレイドバックに合わせ始めました。
ピックアップソロからDexterのアドリブが始まります。前述の通りIt Could Happen to Youのコード進行をベースにした曲ですが、いきなり半コーラス、16小節間ほとんどそのままに原曲のテーマを吹いています。引用フレーズの達人Dexterの面目躍如、というよりダジャレオヤジ現る!と言った方が相応しいかも知れません(汗)。
それにしても何という素晴らしい音色でしょう!誰よりも恵まれた豊かな体軀(身長198cm!)、分厚い唇によりマウスピースを容易く咥える事の出来るルーズなアンブシュアー、この事から生じる豊かな倍音を含んだ音色、脱力とレイドバック、長い8分音符ゆえのタップリ感、ユーモアのセンス、味わい深いニュアンス、そして決して枯渇する事のない砂漠のオアシスに湧き出る泉の如きフレージングとアイデア、ここでの演奏はこれら全てが文句の付けようのないバランスで表出されています。
リズムセクションのサポートも素晴らしく、on topのビートを繰り出すトリオに対しビハインドに位置するDexterとのバランスが絶妙、そして全編に於いてLouis Hayesのカラーリング、特にバスドラムのレスポンスが良い味を出し、Dexterとのスリリングなコンビネーションを聴かせています。
滞欧中のライブ盤の中には、地元のピアノトリオを相手に孤軍奮闘しているDexterの演奏を耳にする事があります。彼の演奏に対し何を行ったら良いのか、どんなレスポンスすれば適切なのかがほとんど分からない、マイナス・ワン状態、馬の耳に念仏の如きリズムセクションに対して、怯まず可能な限りのスイング・スピリットを注入するDexterがいます。
でもこんなことが続けば、素晴らしいリズム隊が大勢待つ母国に帰りたくもなるのも当然でしょうね。
Louis Hayes

テナーソロ後しばしスペースを置きShawの登場です。こちらもまた一聴彼と判断出来る素晴らしいトーン、ハスキーさと抜け切らないこもった成分、反するブライトネス、スピード感、これらがあり得ない次元でのバランス感を伴い発出されている、物凄い個性の塊です!
4分半にも及ぶロングソロではShaw独自のインプロヴィゼーションの方法論、ハーモニー感をとことん聴くことが出来ます。
ハーモニーに対してインサイドなアプローチではいわゆるリック的なフレーズも演奏されていますが、アウトする音使い、Shaw節フレージングでは全く独自な彼の世界に突入しており、Ornette Colemanのインプロヴィゼーションにも通じる、真の天才のみがなし得るオリジナリティを確認することが出来ます。
加えて、えも言われぬニュアンス、ビブラートから発せられる男の色気(堪りません!)、絶妙なタイム感、16分音符フレージングに於ける超絶ぶりとその確実なコントロール。これらの放出を誰も止める事のできないレベルで聴くことが出来るのです。
彼の吹くフレーズは毎回トランペットの機能の限界に挑むかのような難易度を極め、時としてミストーンが目立つ場合があります。フレーズの方が難しすぎてトランペットの機能が追いつかないとも言えるでしょう。
でもここでの演奏は全くパーフェクトと言って言い過ぎではなく、Dexterと共演できる事の喜びがShawにリラクゼーションを与え、肉体的、精神的コンディションが楽器の発音やコントロールに影響を与えがちなトランペット奏を、万全なものに仕立てたと判断しています。
Woody Shaw

引き続きRonnie Mathewsのピアノソロが始まります。Art Blakey and the Jazz Messengers他多くのバンドに参加し、職人タイプのピアニストとして活躍していました。ここでも堅実な素晴らしいプレイを聴かせています。彼の第2作目75年アルバム「Trip to the Orient」はドラムLouis Hayes、ベースに我らがYoshio “Chin” Suzukiを迎えた日本制作盤、自身の音楽性を存分に発揮しています。

Stafford Jamesのベースソロ後、フロント陣とドラムとの8バースが聴かれますが、巧みなHayesのドラミングにインスパイアされたのか、ふたりとも大健闘、本編とはまた異なる素晴らしいプレイを繰り広げますが、惜しむらくはDexterが一度用いた引用フレーズIt Could Happen to Youのメロディを再奏した点です。引用フレーズを同曲で複数回用いるのは法律で禁じられていますから(嘘)。
Fried BanansのエンディングにはDexter入魂のアレンジが施され、この曲の価値をグッと高めました。
Stafford James

続いてDexter本人によるメンバー紹介があり、3曲目Horace Silver作の名曲Strollin’に繋がります。こちらは彼の74年欧州録音の作品「The Apartment」に既収録されています。

The Apartmentでの演奏も好演ですが、コード進行の難しいStrollin’を実はセオリー通り無難にこなしている感を否めません。本作でのプレイはチェンジを超越し、ウタを歌うが如くナチュラルに、まるで帰国出来た充実感を噛み締めるかのように味わい深く演奏しています。
ミディアムテンポでのDexterのリズム感はテナーサックス奏者全員の憧れ、実に素晴らしいタイム感をキープしつつ、前半ではオクターヴ下の音域を中心に演奏しており、音色の極太感からバリトンサックスと見紛うばかりのトーンです。ソロが盛り上がるにつれ次第に音域が上がりますが、相変わらず8分音符を主体としたソロを展開、数カ所で引用フレーズも披露し、聴衆が彼のスイング魂に聴き惚れているのが伝わり、リズム隊も相応しいバッキングで徹底的に対応しています。
ソロ終わりの盛大なアプローズ後、やはり暫くの間があってShawのソロがスタートします。始めは16分音符を用いたラインが多かったのですが、次第にDexterの影響を受けたのか8分音符主体の朗々としたアプローチへと変化します。
ピアノソロに移行する手前にテープ編集の跡を確認しました。まだまだトランペットソロが続いていたようですが、前曲のプレイに比べると冗長さを感じさせるので、ソロをカットされたと想像しています。
続くMathewsのソロは倍テンポをプレイ中提示し、しっかりと二人が追従しています。その後徐に元のテンポを出し再びミディアム・スイングに戻りますが、幾分予定調和と聴こえてしまいます。ベースソロまでしっかりと回り、ラストテーマを迎えます。
Ronnie Mathews

4曲目はバラードでYou’ve Changed、61年5月Blue Note Labelで録音したアルバム「Doin’ Allright」ではFreddie Hubbardを迎え、トランペットがバックグラウンドを吹き、テナーが訥々とメロディを奏でるスタイルで同様に演奏しています。Dexterのバラード名手ぶりを堪能できるテイクです。

アナウンスの前にDexter自身がBud PowellのUn Poco Locoのイントロ・メロディを吹き、ピアノとドラムが追従しています。その後もう一度同じメロディを拍を少しずらして吹き始めます。わざとなのか、間違っただけなのか、これが妙に新鮮に聴こえました。彼らにとってPowellの曲はバイブルのようなナンバーなのでしょうね、このまま同曲を演奏してくれても良かったのに、とも思いましたがおもむろにYou’ve Changed、とDexterがタイトルを述べ、何とこの曲の歌詞を口ずさみ始めたではありませんか!低音の渋い声で!ここでその歌詞をご紹介しましょう。
『You’ve changed That sparkle in your eyes has gone Your smile is just a careless yawn You’re breaking in my heart You’ve changed You’ve changed』
Dexterはバラード演奏時にメロディはもちろん、歌詞も覚えてその意味を自分なりに解釈して演奏しています。『それはLester Youngから学んだ事なんだ」と言う本人の弁もあるように、彼が主演の86年映画「Round Midnight』、音楽担当のHerbie Hancockがアカデミー作曲賞を受賞、Dexter本人もアカデミー主演男優賞にノミネートされた作品です。街角でバラードを朗々とアカペラで吹いていると突然吹くのを止め『いかん、歌詞を忘れちまったぜ』というシーンには説得力があります。
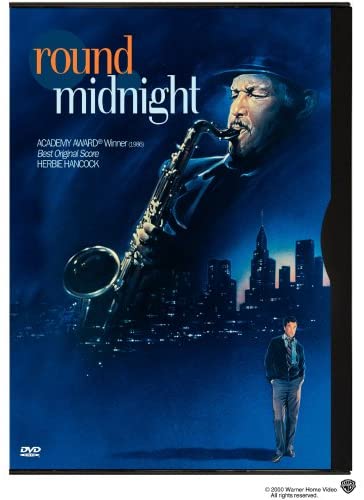
歌詞朗読はオーディエンスに大受けし、会場のムードが更に和んだところで演奏開始です。いや〜それにしても何という凄い音色でしょう!Dexterのバラード奏は天下一品、朴訥さとニュアンス、感情移入が堪りません!プレイはライブという事もありオープンなテイストを聴かせますが、「Doin’ Allright」時よりも渡欧生活で蓄積されたのでしょう、深みを感じさせます。
続くトランペットソロはしっかりと倍テンポで行われます。こちらも唄心をとことん感じさせるプレイ、明らかにDexterのスピリットに啓発された入魂ぶりを聴かせています。
ピアノソロを経てラストテーマへ、エンディングでのCadenzaのこれまた素晴らしいこと!Dexterの芸歴の中でもベストに挙げられるプレイです!サブトーン、実音の巧みな音色の使い分け、ジャジーなフレージングのオンパレード、最低音からフラジオを含めた高音域までバランス良く演奏し、センテンスの間に投げかけられる、感極まった熱狂的ファンの歓声が次第に大きくなり、ストーリー性をもった演奏はドラマチックに、ダイナミックに、申し分なく挙行されました。

ラストはBonus TrackのBags’ Groove、本編の約6年後に当たる82年6月、Los AngelesにあるHollywood Bowlにて行われたPlayboy Jazz Festivalでの演奏です。
Milt Jacksonをゲストに迎え彼の代表曲を選び、Shaw以外は全員メンバーが入れ替わったジャムセッション形式での演奏になります。
作品としての一貫性を持たせるべく、是非ともVillage Gateでのテイクで統一して欲しかったところです。何処かに存在するとは思うのですが。
ジャズ・フェスティバルでの広い会場の演奏はそれなりの盛り上がりは期待できますが、ライブハウス・ギグとは異なり、緻密さにかける傾向は否めず、どうしても演奏は大味なものになりがちです。こちらはどうでしょうか。
それまでよりも録音の音質はクリアーですが、案の定やや「お仕事」、「見せ物興行」的に演奏が進行していて、残念ながらsomething happensは起こっていません。
2021.07.25 Sun
今回はベース奏者Charlie Hadenの1976年作品「Closeness」を取り上げてみましょう。
Recorded: January 26, 1976 at Kendun Recorders in Burbank, California (track 3) and on March 18 (track 1) and March 21 (track 2 & 4), 1976 at Generation Sound in New York City
Label: Horizon
Producer: Ed Michel
b)Charlie Haden p)Keith Jarrett(track 1) as)Ornette Coleman(track 2) harp)Alice Coltrane(track 3) perc)Paul Motian(track 4)
1)Ellen David 2)O. C. 3)For Turiya 4)For a Free Portugal
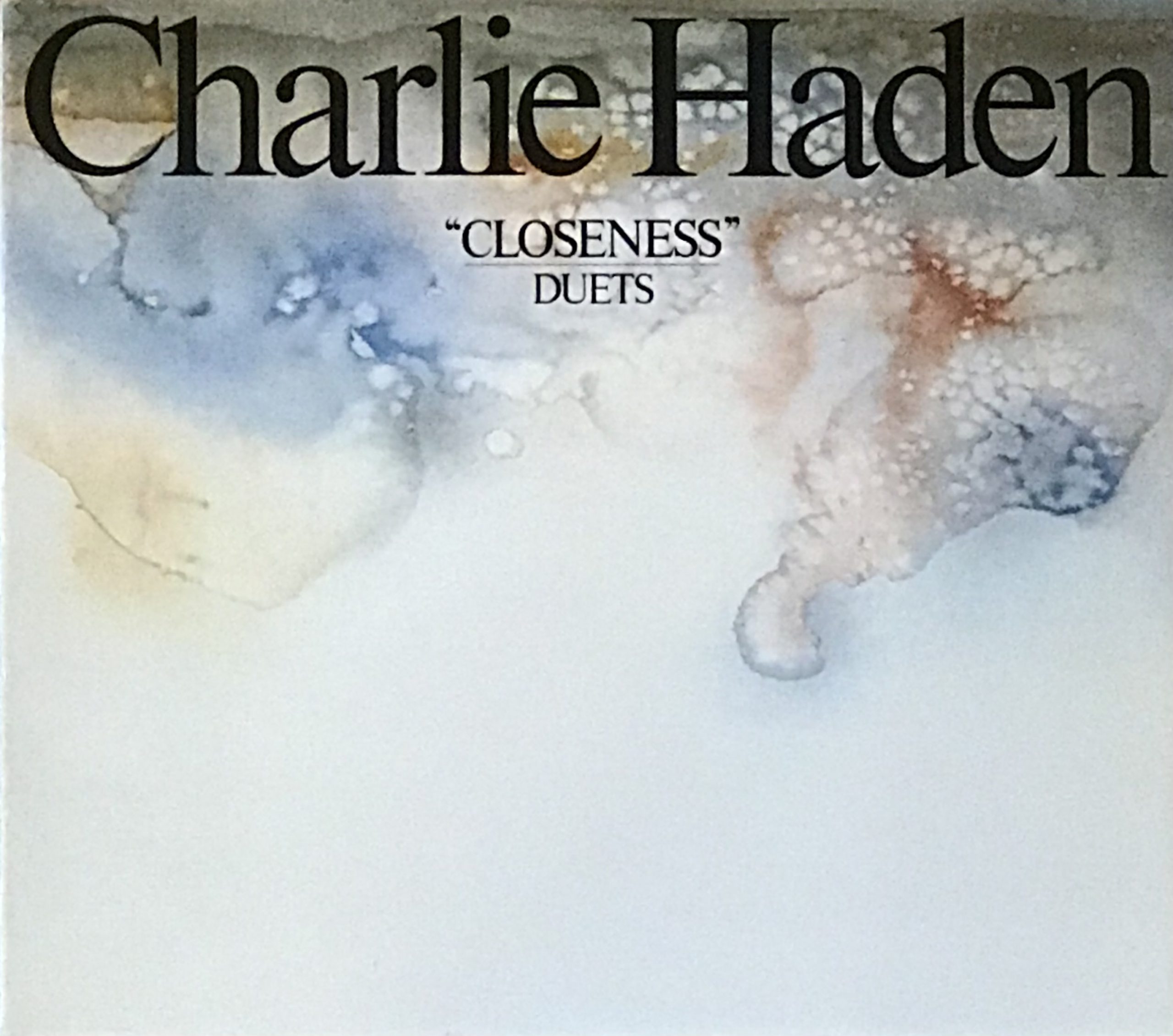
Charlie Hadenが4人のミュージシャンとDuo演奏を行なった作品です。Duo形態で彼は色々なミュージシャンとのレコーディングを残しており本作もその一つ、直近では同76年Hampton Hawesと「As Long as There’s Music」、翌77年本作の続編とも言うべき「The Golden Number」ではDon Cherry, Archie Shepp, Hampton Hawes, Ornette Colemanたちと、そしてOrnette Colemanと全編サシで「Soapsuds, Soapsuds」、78年Christian Escudeと「Gitane」。以降も多くのDuo作品を手掛けていますが、いずれも大変高い音楽性を湛えています。

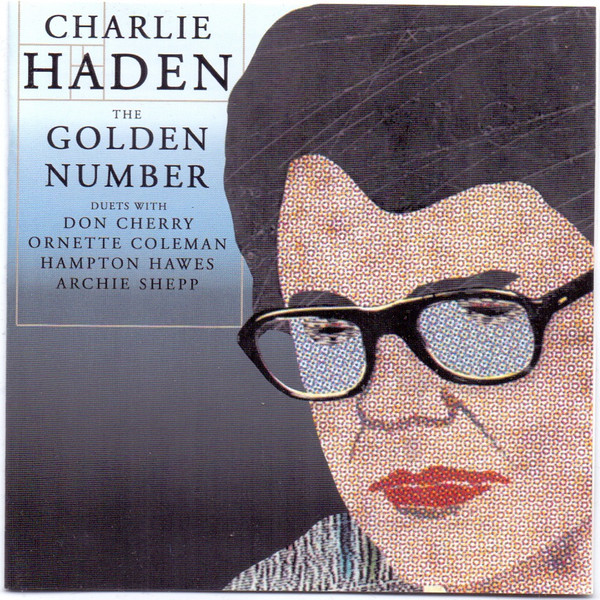

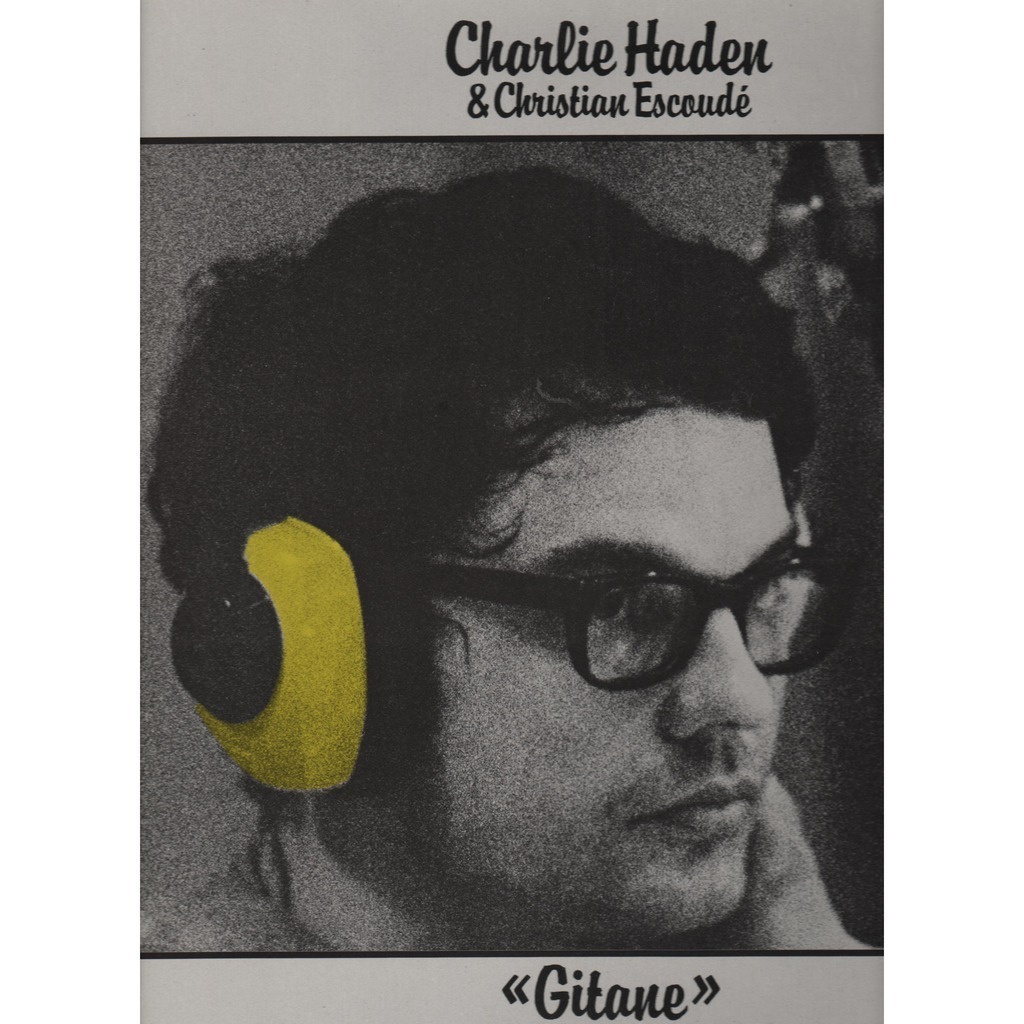
もう1枚紹介したい作品が81年録音Denny ZeitlinとのDuo「Time Remembers One Time One」(ECM)、San Francisco, Keystone Kornerでのライブレコーディングを収録したアルバムです。二人の音楽性が結実した演奏で、選曲にも工夫がなされています。ユニークなHadenオリジナルChairman Mao(毛沢東主席)、OrnetteのBird Food、Zeitlin作の表題曲、Ellen Davidの再演、アレンジされもはや別曲のCole Porter作Love for SaleやJohn ColtraneのオリジナルSatelliteとHow High the Moon(Satelliteの原曲です!)のメドレー、ボサノヴァの名曲Luiz Eca作The Dolphinなど、ライブ録音ではありますがアルバムリリースを考えて演奏をコンパクトに纏めており、両者のカラーがバランス良く凝縮しています。

Duo活動だけではなくHadenはCarla Bleyと67年に結成した13人編成のラージ・アンサンブル・バンド、Liberation Music Orchestra(LMO)も並行して活動を続けていました。対極に位置する編成を組織していたわけです。大は小を兼ねる、ならぬ小は大を兼ねる、サポートの達人であるHadenは大きな編成でも遺憾なく自身の音楽性を発揮しました。
70年作品「Liberation Music Orchestra」は参加メンバーGato Barbieri, Dewey Redman, Don Cherry, Roswell Ruddらの素晴らしくも個性的な演奏から、豊かなアンサンブルとインプロヴィゼーションを聴く事が出来、ユーモアに富みサウンドも充実したBleyのアレンジ、楽曲がとても魅力的です。
同時に反戦、反骨精神を躊躇することなく掲げ、スペイン内乱、キューバ革命のErnesto Guevara、戦争孤児やベトナム戦争をテーマに、組曲風にも仕上げています。ジャケットのセンスも秀逸、メンバー全員が並ぶなかBleyとHadenがバンド名を記した旗を両脇で支えています。

2005年の同バンド作品「 Not in Our Name」のジャケットはLMOのデザインを踏襲しています。
こちらではBleyとHadenの立ち位置が入れ替わっているのにどこか可笑しみを感じ、そして背の高いメンバーが加わったために旗の高さも20cmは上がり、背景のブルーも合わさって成長と開放感を感じます(笑)。

LMOはHadenの逝去まで40年以上の長きに渡り継続され、作品を計6枚リリースしました。11年のライブ録音2曲とHaden死後のトリビュートとしてBleyのオリジナルが3曲追加された(ベーシストは適任であるSteve Swallowが代役を務めました!)「Life/Time」がラスト作です。

Hadenのベースプレイはユニークな経歴に由来する独自なスタイルを聴かせます。
37年8月米国中部Iowa州で生まれ、家族全員がミュージシャンという環境、カントリーミュージックやフォークソングを演奏していたそうで、2歳の時にラジオのショーに家族で出演、ボーカリストとしてデビューしたそうです。15歳の時にポリオを発症するまで家族と共に歌い続けました。
08年にはHaden永年の夢であった彼の妻や4人の子供たち、親しい友人ミュージシャンRosanne Cash, Elvis Costello, Bruce Hornsby, Pat Methenyらとカントリー・ウエスタンを演奏したアルバム「Rambling Boy」を発表、楽しげに演奏している雰囲気が手に取るように伝わります。ここではメンバーを統率するリーダーシップに加え、家長たる威厳と愛情を感じます。
またOrnetteのバンドやKeithと演奏している時と全く異なり、コードの1度と5度しか弾いていないのですが(汗)、絶妙なビート感と音の立ち上がり、いつもの深い音色、彼のルーツはこれに違いないと実感しました!

14歳でCharlie ParkerやStan Kentonのコンサートに触れ、ジャズに興味を持つようになり、後にポリオの症状を克服してからベースを独学で演奏し始め、ハーモニーやコードをBachの作品から学びました。
Los Angelesで本格的に音楽を学ぶべく、その費用を貯めるためにMissouri州にあるテレビ局のハウス・ベーシストとして演奏していた経歴は、彼の早熟ぶり物語ります。
20歳の時にLAに居を移し、Hampton Hawesを尋ねRed MitchellやPaul Bleyと親交を持ち、Art Pepperとも共演、かの名ベーシストScott LaFaroとはアパートの部屋をシェアしていたそうです。Ornetteの60年録音作品「Free Jazz」はLaFaroとのツーベースでの演奏を収録した、奇跡の名演奏です。

様々なミュージシャンと交流できたのは演奏能力はもちろん、彼のフレンドリーな性格からでしょうが、Ornette Colemanとは音楽の方法論やコンセプトに合致するものを見出し、運命的な出会いを感じていたようです。
59年にOrnetteの代表作「The Shape of Jazz to Come」のレコーディングに参加します。Hadenのプレイは幼い頃から経験したカントリーやフォーク・ミュージックに影響されたスタイルとTexasブルースの要素、そしてOrnetteのMicrotonalと言われる音楽的方法論とが合わさり、初期の段階からオリジナリティを獲得していました。

その後Ornetteのカルテットと共にNew Yorkに移り、ジャズクラブFive Spotでの6週間に渡る演奏の中で即興演奏時に新たな方法論を見出しました。
Haden曰く「我々の初めの頃の演奏は即興演奏時に曲のパターンの類を追い求めていたけれど、OrnetteがNew Yorkに移るなり曲のパターンを演奏しなくなった。曲のブリッジやインタールードの類もだ。言ってみれば耳だけを頼りに演奏すると言うことで、それからは徹底的に彼について行くように心がけ、彼がその瞬間、瞬間に感じた事で発生した新たなコードの構造、提示するコードチェンジを追うように、とにかく努めようとしたんだ」。
60年にドラッグ問題でOrnetteのバンドを離れ、自らの意思で薬物リハビリテーションプログラム施設Synanon(Joe Pass, Art Pepper, Chet Bakerたちも入所しました)で63年まで治療を受け、その後社会復帰を果たします。施設で出会った女性Ellen Davidと後に結婚しました。
64年に音楽活動を再開しJohn Handy, Denny Zeitlin, Archie Shepp, Attila Zollar, Thad Jones/Mel Lewisたちとプレイし、67年にOrnetteのグループに返り咲きます。バンドは70年代初頭までアクティヴに活動しており、HadenはOrnetteの複雑なアドリブ・ラインの転調に実に器用に対応することが出来るとベーシストと、評判が立つほどでした。
ベース奏者は基本的にコードのルート音を強拍(1, 3拍)に演奏し、コード感の基音を提示する役割を担います。
サックスを擁したカルテットであればその上にピアノのコード音が成り立ち、サックスが奏でるラインがコード感というデコレーションを纒い音楽が成立しますが、HadenのベースはOrnetteとの長年の共演で培われたアプローチから、演奏者が想定するサウンドやコード進行、構造に対して即座に反応し、瞬時に寄り添い、都度に的確な音をプレイします。
時にはコードのルート音を演奏せずにそのコードのサウンドとはかけ離れた音を弾きますが、ソロイストやバッキングのサウンドとの関係から、興味深いテンション感を伴って〜ジャズの醍醐味のひとつです〜音楽的に成立するのです。
他のベーシストと演奏を聴き比べてみてください。誰よりも深淵な音色、スピード感が半端ない音の立ち上がりとon topさはもちろん、決してリック(指癖)やパターンではない常にスポンテニアスでクリエイティヴな音使い。ベースと言う楽器を鳴らす、操るテクニックに関しては常にマエストロぶりも発揮しますが、共演者に触発された際の瞬発力、独自のラインを構築するセンスで右に出るものは存在しません。一般的なベーシストとは全く異なる演奏を聴かせているのです。
DuoはHadenにとって、彼の個性である「相方のアプローチを瞬発力を伴って引き立てる」を、最も的確に表現できるシチュエーションなのです。

それでは収録曲の演奏に触れて行きましょう。1曲目のDuo相手はKeith Jarrett。Keithとは彼のトリオで67年「Life Between the Exit Signs」からの共演歴になり、ドラマーにはPaul Motianを迎えたKeith Jarrett Trioとしての演奏のほか、Dewey Redmanを迎えたいわゆるAmerican Quartetとしても名作を数多くリリースしています。Quartet作品では「Treasure Island」を挙げたいと思います。


演奏曲はHadenの代表ナンバーEllen David、前述のSynanonで出会い、奥様となった女性に捧げたナンバー。
美しいメロディとドラマチックな構成を有すコード進行、Keithのピアノが実に叙情的に歌い上げます。
Haden自身も作曲したときにKeith以外にこの曲を弾きこなせるピアニストは存在しないと思ったそうです。
イントロはベースのトレモロから始まり、良く伸びる太くふくよかな音色で奏で、ムードを高めます。ベース自体の音色は多少ピックアップ音が混じりますが、生音の迫力を聴かせています。
聞くところによると彼の使用コントラバスは大変歴史的価値のあるヴィンテージ楽器、移動のことを考えると容易くツアーには持って行くことが難しいそうです。
弘法筆を選ばずではありますが、やはり良い楽器はそれなりの音がするのです。
Keithの力強く、しかしリリカルなピアノタッチから繰り出されるライン、コード、リズムはジャズピアニスト史上最高峰に位置するクオリティ、デュエットで対等に共演出来るのはHadenを置いて他には考えられません。
作曲者自身であるので、曲の解釈をどのようにするかは全権委任されて然るべきですが、それにしてもKeithの演奏するメロディやラインに対処していくアプローチは小気味良いまでに自由奔放です!
Keithを主体としてHadenがどのような音を繰り出しているのか、Keithのフレージングとの関連性、リズム的なアプローチを体感しつつ両者の絡み具合を認識する、また放置し出しゃばらずにKeithの成り行きを見守る部分の必然性(なぜ弾かないのか、どうして抑制しているのか)を考えてみる、などなど演奏の中により入り込み、音が耳に飛び込むのに身を任せるだけでなく、より一歩演奏に入り込んでプレイを聴くことをお勧めします。
TVのバラエティやお笑い番組は見ていて殆ど間違いなく楽しく笑わせて貰えます。そのように構成、プログラムされているから当然ですが、でも視聴後何も残りません。慣れとは恐ろしいもので「何をあんなに笑っていたのだろう?」とさえ考える事も無くなるのは、全てが受動であるからです。
Jazzにもそれらに近いテイストを持つものもありますが、少なくともHadenとKeithの音楽は真逆の位置にあります。自ら音楽に入っていかない限り彼らの真髄を体感する事は出来ません。
ベースソロが始まりHadenはメロディの断片を演奏します。Keithはまるで輪唱のように同じメロディをプレイ、Hadenはそれに対応するべく再びメロディの断片を弾き始めます。互いにメロディの応酬を行いますが、その間に聴かれるHadenのアドリブライン、繰り出すフレーズの崇高さ、Keithのフィルインの相応しさ、美しさには鳥肌が立つほどです!
Ellen David
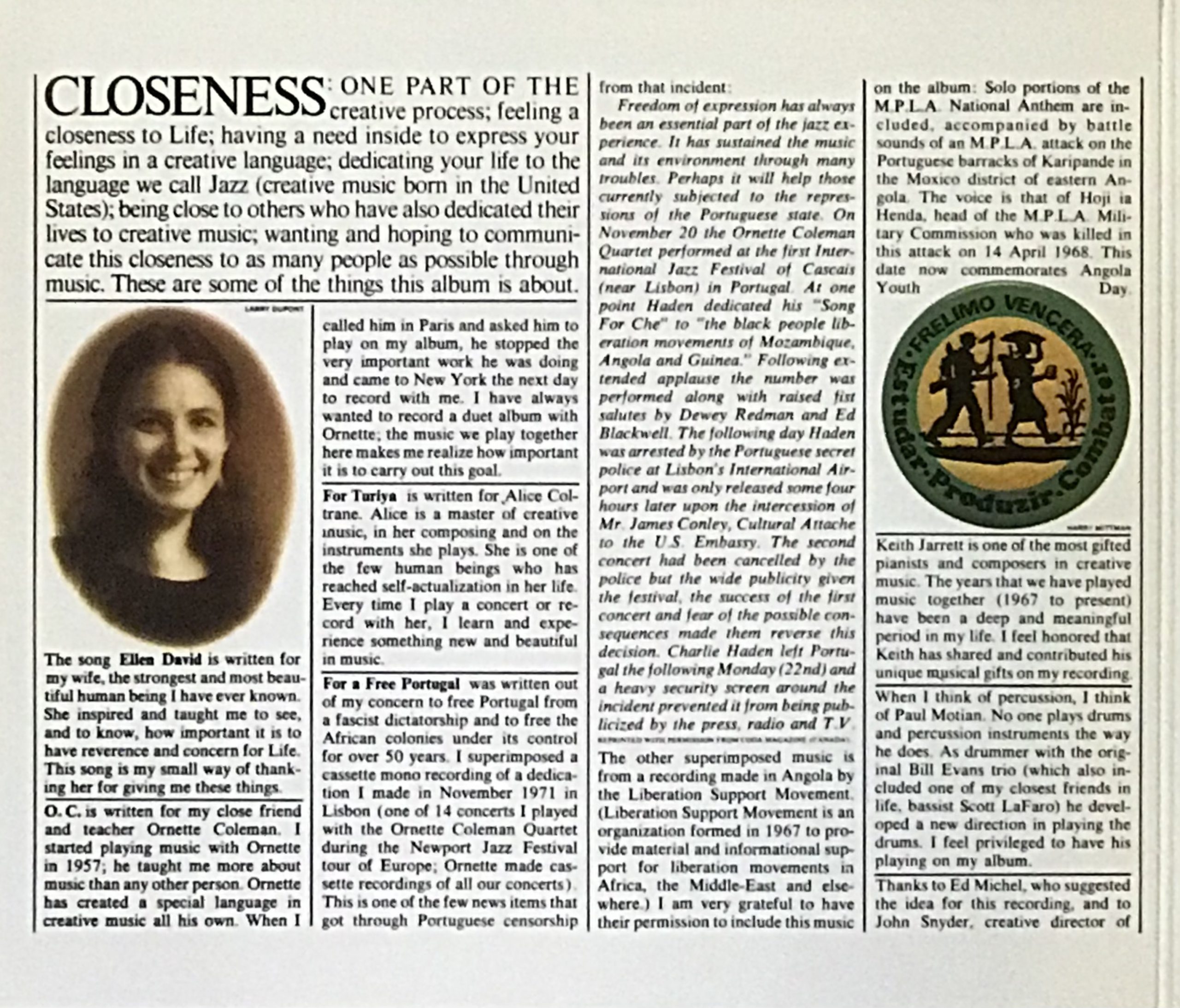
2曲目は盟友Ornette ColemanとのDuo、曲のタイトルも彼のイニシャルからO. C.です!HadenのナンバーですがまるでOrnetteが書くオリジナルの如きメロディライン、雰囲気、HadenがOrnetteの作風をイメージして作曲したのでしょうか。印象的なテーマ後、アップテンポのスイングでカンバセーションが開始されます。
Ornetteの吹くラインは独創的、Ornette節も感じさせますが、何より常にクリエイティヴにフレッシュなラインを構築している事に驚かされます。決して指癖の類の手なりではなく、毎回違ったアプローチで対応しているのです。
何かのインタビューでOrnetteは「Charlie Parkerはコード進行に対する横の流れを重んじて演奏しているけれど、僕の演奏はコードに対するフレーズだ」と言うような趣旨の発言だったと記憶していますが、彼にとって自身の吹くアプローチがフレーズという捉え方は驚き以外ありません。僕自身のフレーズの概念が揺らぐほどです。Parkerの演奏こそがまさしくフレーズによるアプローチと捉えていました。
Parkerスタイルの継承者Sonny Stittは全てがフレーズによるアドリブ、膨大なフレーズをストックし順列組み合わせの巧みさを活かして流暢な演奏を聴かせます。Parkerはフレーズの組み合わせも素晴らしいですが、スポンテニアスなアプローチも随所に聴かれるフレキシブルな方法論ではあります。これらを踏まえるとOrnetteのフレーズとは、解釈の全く異なる次元に存在しています。ジャズ界の革命児と呼ばれる所以でしょう。
Hadenの猛烈なスピード感を伴った独創的ラインの上で、これまた異次元から発せられたかのような「フレーズ」をOrnetteが奏でます。常に一触即発、Ornetteが主体ではありますが互いを良く聴き合い、Ornetteの音楽性を100%信頼し尊敬するHadenならではの追従アプローチ、転調したキーに確実に合わせています。翻ってみればOrnetteもHadenに対し全く同様です。
ひとしきりの会話後Hadenのソロ、アルトソロの余韻をしっかり残しながら、テーマの断片も交えつつ深い世界を語ります。
突然アルトが切り込み第二楽章がスタートします。暫しHadenはファスト・スイングを提示しますがOrnetteは朗々と吹き、先ほどとは異なったアプローチを模索しているようです。Hadenは様々に仕掛けますがテンポ的にはもう少し遅いスイングをイメージしているようで、Ornetteは動かざること岩の如し。アルトのアッチェルランドやリタルダンド、ルパートに合わせる、フレーズに呼応したり、これらの様は長年の共演歴の成せる技以外の何者でもありません。そしてほど良きところでテーマを吹き始めます。
ごく初期の「The Shape of Jazz to Come」の時とは全く異なる次元での深遠な世界、この演奏は本作の価値を全く高めました。
Ornette Coleman
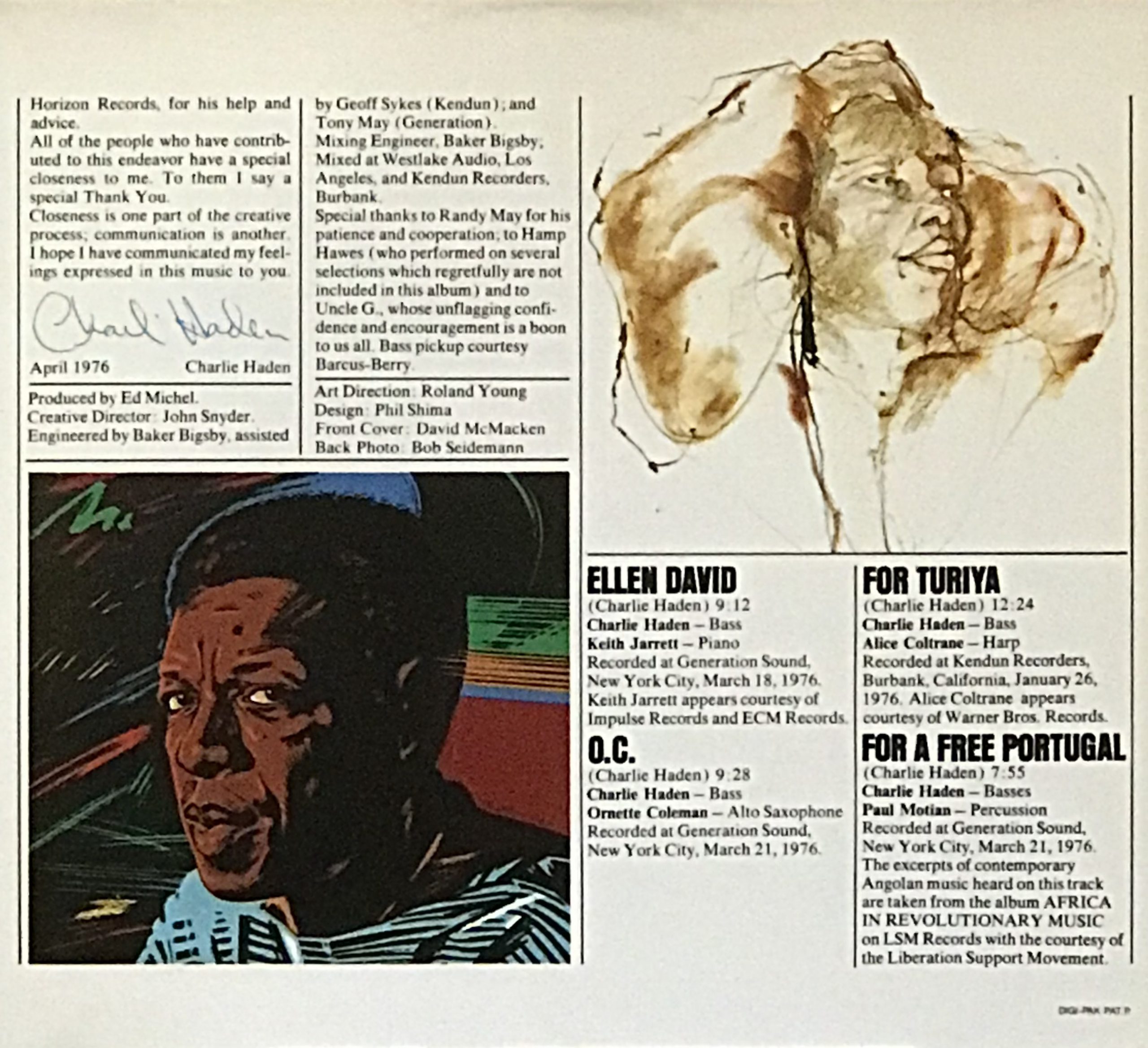
3曲目はAlice Coltrane、彼女はピアノ奏者ですがここではハープを用いてのDuo、タイトルFor Turiyaとは彼女のサンスクリット語名Turiyasangitanandaに由来します。
Hadenが彼女のアルバムに参加したのは70年録音「Journey in Satchidananda」収録Isis and Osiris、New YorkにあったThe Village Gateでのライブ録音になります。
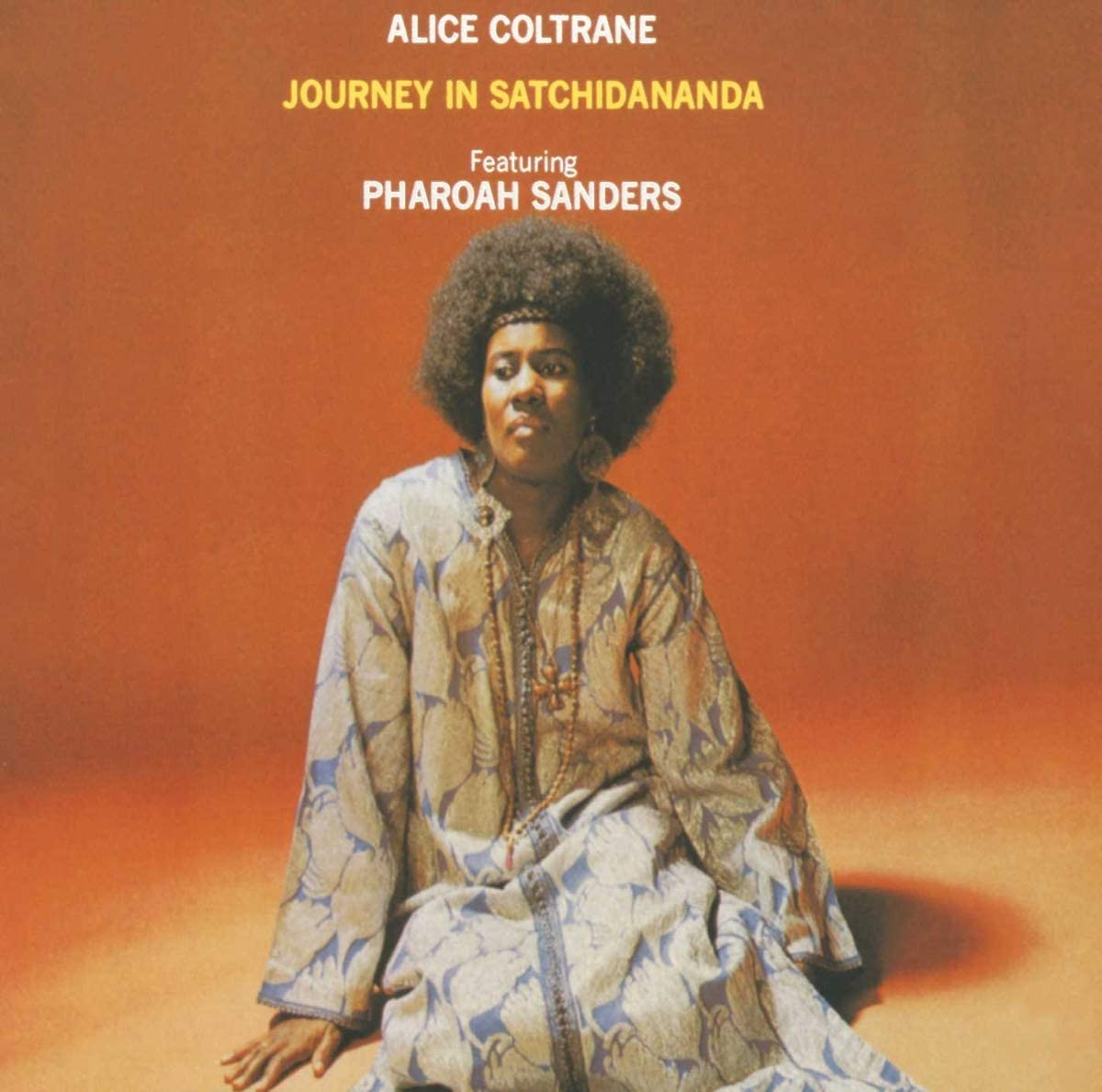
Aliceのハープ演奏に感銘を受けたHadenが彼女に捧げて曲を書きました。
とは言ったもののメロディを弾くのはHaden、Aliceは主にバッキング担当、テーマ後、Hadenの壮大なソロが聴かれます。Aliceは小さめの音量でバッキングを入れますが、そもそもハープの音色自体が効果音的なので、ジャズ演奏で用いられることはあまりなく、難しい楽器のチョイスです。Hadenひとしきり語ったところでルート音を決め、ハープソロへ。ラインを紡ぐように弾き、スペーシーな演奏を展開しますが、ハープのうねるような音階のラインは大海原を泳ぐイルカのようで、水中で回転したり時たま水上に顔を出したり、二人は気持ち良さそうに演奏を繰り広げます。

4曲目For a Free Portugalは盟友Paul MotianとのDuo、Motianはパーカッションで参加します。しかしこれは演奏というよりもメッセージ、しかも政治的なものとして収録されています。
曲の冒頭に聴かれるアナウンスメントは聴衆に対するHaden自身のスピーチ「この曲をモザンビーク、ギニア、アンゴラの黒人民族解放戦運動に捧げます」。
Ornetteが録音していたテープから起こされたものですが、71年Portugal Cascadeで行われたインターナショナル・ジャズ・フェスティバルにHadenはOrnetteのカルテットで出演します。
その時にLMOで演奏していた自身のオリジナルSong for Che(Guevara)を演奏し、Dewey Redman, Ed Blackwellたちと反戦のために抗議姿勢を示したのです。
演奏の途中にはオーバーダブされたアンゴラ解放人民運動のテーマ曲と、68年人民運動軍がPortugal軍と交戦した際の銃声も聞くことができます。
Portugalはかつてアフリカから奴隷要員を南北アメリカ大陸に輸出していた最大国であり、アフリカ大陸植民地化を率先して行いました。
Hadenの挙げた3つの国はかつてのPortugalの植民地で、50年代以降激化するアフリカ大陸の黒人開放と共和国独立にPortugalは大変ナーバスになっていました。
当然の成り行きといえば違いないのですが、翌日HadenはLisbon空港でPortugal秘密警察に逮捕されます。しかし4時間後に米国大使館の猛烈な抗議で即釈放となりました。
この出来事が動機となり、この演奏が生まれたのです。本演奏は70年代初頭の時代のなせる技ですが、反戦運動家Hadenならではのテイク、曲自体はスパニッシュ調のムードを8分の6拍子で演奏しています。
2021.07.10 Sat
今回はアルトサックス奏者Ornette Colemanの1961年作品「Free Jazz: A Collective Improvisation」を取り上げたいと思います。
Recorded: 21 December, 1960 at A&R Studios New York City
Label: Atlantic
Producer: Nesuhi Ertegun
Left channel: as)Ornette Coleman pocket tp)Don Cherry b)Scott LaFaro ds)Billy Higgins
Right channel: b-cl)Eric Dolphy tp)Freddie Hubbard b)Charlie Haden ds)Ed Blackwell
1)Free Jazz 2)First Take

ジャズ界数ある問題作の中で、最も存在感のあるアルバムの一枚が本作「Free Jazz」と思っています。
Jazzという言葉の定義は実に広範にしてしかも曖昧ですが、Ornetteは大胆にもここにFreeと形容し、これ以上は考えられない適任のメンバーを集め、相応しい内容の独自の演奏フォームを考案し、やり遂げてしまった異端と革新性を高く評価しています。
明確なヴィジョン、それをとことん貫き通す強靱な意思、精神力。
揶揄されたり誹謗中傷とは切っても切り離せない状況下で、とことん信念を持って表現し続ける男の美学。
米国内には天才が数多く出現していますが、彼も間違いなくその中のひとりです。そして私が心から尊敬するミュージシャンのひとりでもあります。
Ornette Coleman

米国50年代末の出来事です。Modern Jazz黄金期の終焉と共に仕事を求め欧州に拠点を移す第一線のハードバップ・ミュージシャンたち移住組、何とか母国での活動をベースにするべく演奏スタイルを状況に柔軟に則した適応組、Charlie Parkerが唱えたJazzスタイルは60年代以降も継続されますが彼の登場から10数年を経て米国の社会情勢、音楽環境が変化し、プレイヤーにも変革が求められていました。
Lennie Tristano, Thelonious Monkらに端を発する、Jazzの様式に根ざしつつも枠から抜けようとするミュージシャンたちが50年代現れ始めました。Cecil Taylorもその一人ですが彼はクラシック・ピアノや作曲、編曲、和声学を学び、欧州近代クラシック〜Bartok、現代音楽〜Stockhausenに親しんだ楽理派、60年代以降はOrnetteと共にシーンのけん引役を担いました。
そのOrnetteはほとんど独学で14歳の時にサックスを始めました。40年代はテナーサックス奏者としてもローカルのR&Bや bebopバンドで演奏活動を行い、当初は貧しかった家族を養うことが目的でしたが次第に音楽的な目標を見出し、アルトサックスではCharlie Parkerからの影響を受け、テナー奏者としてはIllinois JacquetやBig Jay McNeelyばりのホンカー・テナーを吹いていたそうです。彼の演奏からは確かにホンカーの影を感じる事が出来ますし、後年の作品77年「Dancing in Your Head」に於けるFunkのリズムのルーツを感じることが出来ます。

周囲の仲間の発言によれば47年頃には彼自身の音を見つけ、49年には既にコードの置き換えについて研究を始め、「どうしてこれはこうじゃなければならないんだ?」のような質問をして来たそうです。一聴彼のプレイはハーモニー感やコード感とは掛け離れているようですが、彼なりのサウンドが確実に鳴っているのでしょう。
あごひげを長く伸ばし、長髪で痩せっぽちの独特な風貌は黒人ミュージシャンらしからぬもの、「イエス・キリストを彷彿とさせるイメージ」で、しかも菜食主義者、真夏でもコートを着込むおかしなファッション、人種差別主義の警官たちや異端を良しとしない輩から随分と攻撃を受けました。
49年Louisiana州Baton Rougeで演奏後に襲われ、楽器を破壊された逸話が残っています。その頃から型にハマらない後年のスタイルで演奏していたそうなので、彼の演奏を良く思わない黒人に暴力をふるわれ、テナーを取り上げられ投げ捨てられたそうです。この後アルトサックスに転向することになります。
ひたすら異端の演奏に没頭し、生活のために音楽を演奏しているにも関わらず、例えばダンスミュージックを演奏中にも閃いた自分のアイデアを優先させるのでバンドを解雇させられました。彼の信念である「Freedom」を実践する方法を見つけようと、自身を受け入れてくれそうな所に行っては意に反し冷たい仕打ちを受けました。黒人で髪の毛が長かったという理由だけで留置所に入れられた事もあります。
自分のやりたくない事はやらず、ミュージシャンから自身の音楽を否定され続け孤独でしたが、それでも数少ない崇拝者は存在し、次第に彼の音楽に共感するプレーヤーも見つかり始めました。トランペット奏者Don Cherry、デビュー作からOrnetteの相棒、もう一つのヴォイスとして長きに渡り活動を共にする盟友ですが、当初Ornetteは気がふれていると本気で考えていたそうです。ドラマーBilly Higgins, Ed Blackwell、ベーシストCharlie HadenはOrnetteとの出会いを運命的なものと感じていました。
58年に転機が訪れます。西海岸Los Angelsの名門レーベルContemporaryにベーシストRed Mitchellの口利きがあり、Ornetteが作曲したナンバーをレーベルに売却しに行くことになりました。当時の彼は音楽の仕事がなく気も滅入っていて、母親に電報を打ち故郷へ帰るためのバスの切符を送ってくれるように頼み、切符が届いたまさにその日、レーベルオーナーLester Koenigから連絡がありました。取るものも取り敢えずDon Cherryと二人でComtemporaryスタジオに赴き、Koenigに自己紹介をしました。
後にKoenigが語っていますが、彼をピアノの前に連れて行き自分の曲を弾いて見るように言うと、Ornetteはピアノを弾けないと答え、「ピアノが弾けないのならどのようにして君の作った曲を私に聴かせるんだい?」と尋ねると彼は白いプラスチック製のアルトサックスをケースから取り出してCherryを伴って曲を吹き始めました。
Koenigは彼の曲を気に入り7曲、1曲につき25ドルで買い取りました。さらに彼らの個性的なプレイに興味を持ったKoenigはOrnetteにレコーディングをしてみないかと持ちかけたのです。
Contemporaryレーベルはリリースされたアルバムのカラーから、どちらかと言えば保守的な傾向にあるレコード会社とイメージしていましたが、Koenigは調性音楽を脱し、無調に突入し12音技法を創始したことで知られるオーストリアの作曲家Schonbergの古くからの友人であり、本人もレコード会社を経営する前は2度アカデミー賞を受賞した映画プロデューサーであり、Hollywoodの「共産主義シンパの追放」に反対しブラックリストに載せられるほどのアクティヴな知識人でした。Ornetteは彼にとって全く相応しいレコード会社に作品を持ち込んだのです。
Koenigはレーベルお抱えのミュージシャンを起用してレコーディングをしたかった模様ですが、彼らには楽譜が読めてもOrnetteの曲をどのように演奏して良いかまでの理解は難しいだろうとして(いわゆるスタジオ・ミュージシャンですね)、Ornetteのバンド〜Don Cherry, Billy Higgins, Walter Norris, Don Payneのクインテットでレコーディングに臨みました。
演奏曲は全てOrnetteが50年〜53年の間に書いたスタンダード形式の9曲を、58年2月から3月の間3回にかけて録音しました。
ハードバップの匂いを感じさせる、しかし独創的なオリジナルの数々をリズムセクションは軽快に伴奏し、フロント二人、特にOrnetteはその個性を十分に表現しCherryもいつもの彼らしい淡々とした前衛性を聴かせています。Ornetteのソロ・アプローチが際立てば際立つほど、他者との溝を感じさせる原因の一つにピアノのバッキングがあります。テーマのメロディには間違いなくコード感が存在し、その時にはバッキングは相応しいものとして聴こえますが、Ornetteのソロ・アプローチには元のコード進行と全く別なサウンドが鳴っており、ピアノのヴォイシングはアルトのラインに対し明らかにサウンドせず、むしろ邪魔をしています。第2作目からピアノレス編成になるのは自明の理だったのです。

Ornetteは「Something Else!!!!」でセンセーショナルなデビューを飾りましたが、アルバムの売れ行きはさほどでもなく、プロデューサーKoenigは当初の考え方の通り、次作でレーベルが抱える売れっ子の二人Shelly Manne, Red Mitchellと共演させることにしましたが、Ornetteの音楽には不要であるピアニストを排除したカルテット編成となり、彼の音楽表現はかなり核心に近づきました。
第2作目「Tomorrow Is the Question」は59年1月から3月にかけて9曲録音されました。楽曲は前作とは一掃された革新性を持ち、フロント二人のプレイは更なる煌びやかさを放っています。
何と言ってもOrnetteのアルトサックスの鳴り方が素晴らしい!太くダークで実に様々な倍音が含まれ、アルトサックスらしい響きを聴かせつつ同時に、全く異なる人の叫び声や動物の鳴き声と思しきトーン、ひとつの音色にこれだけ複雑に色々な成分を同居させる事が出来たアルト奏者はかつて存在せず、誰にも似ていない真のオリジナリティを感じさせるサウンドです。前作からほぼ1年が経過し、楽器の習得度合いが格段に向上した結果です。前作同様使われている白いプラスチック製の楽器は英国製Grafton、彼のサウンドを決定付ける大変ユニークな楽器です。本人曰く金属製のサックスよりも澄んだ音が出て、今ではプラスチック製以外吹く気がしないけれど、自分のような吹き方だとせいぜい1年しか保たないので、壊れたら英国から取り寄せている。
ある音を出すとその息の形まで見える気がするが、金属製ではそれがない。金属の管の中では息が消えてしまうからだ。プラスチックの管の中はまるで真空のようだ、とも発言しています。
安価な楽器、白いプラスチック製であるため、見た目からおもちゃのようで、彼の特異なプレイスタイルも加わり奇異な印象を与えますが、本人が出したい音を確実に出せる、やりたい音楽に真摯に立ち向かえる重要なツールでした。楽器選びからして超個性的だったのです。
Charlie Parkerが53年Canada, TorontoのMassey Hallに於けるコンサートで使用したモデルと同じこのサックス、Ornetteはこれに4.5から5番のリードを付けたオープニングのかなり広い(番号、メーカー不明)マウスピースを使用していました。仲間のプレーヤーがOrnetteの楽器を試奏しましたが、ハードなセッティングのために全く音が出なかったそうです(汗)。
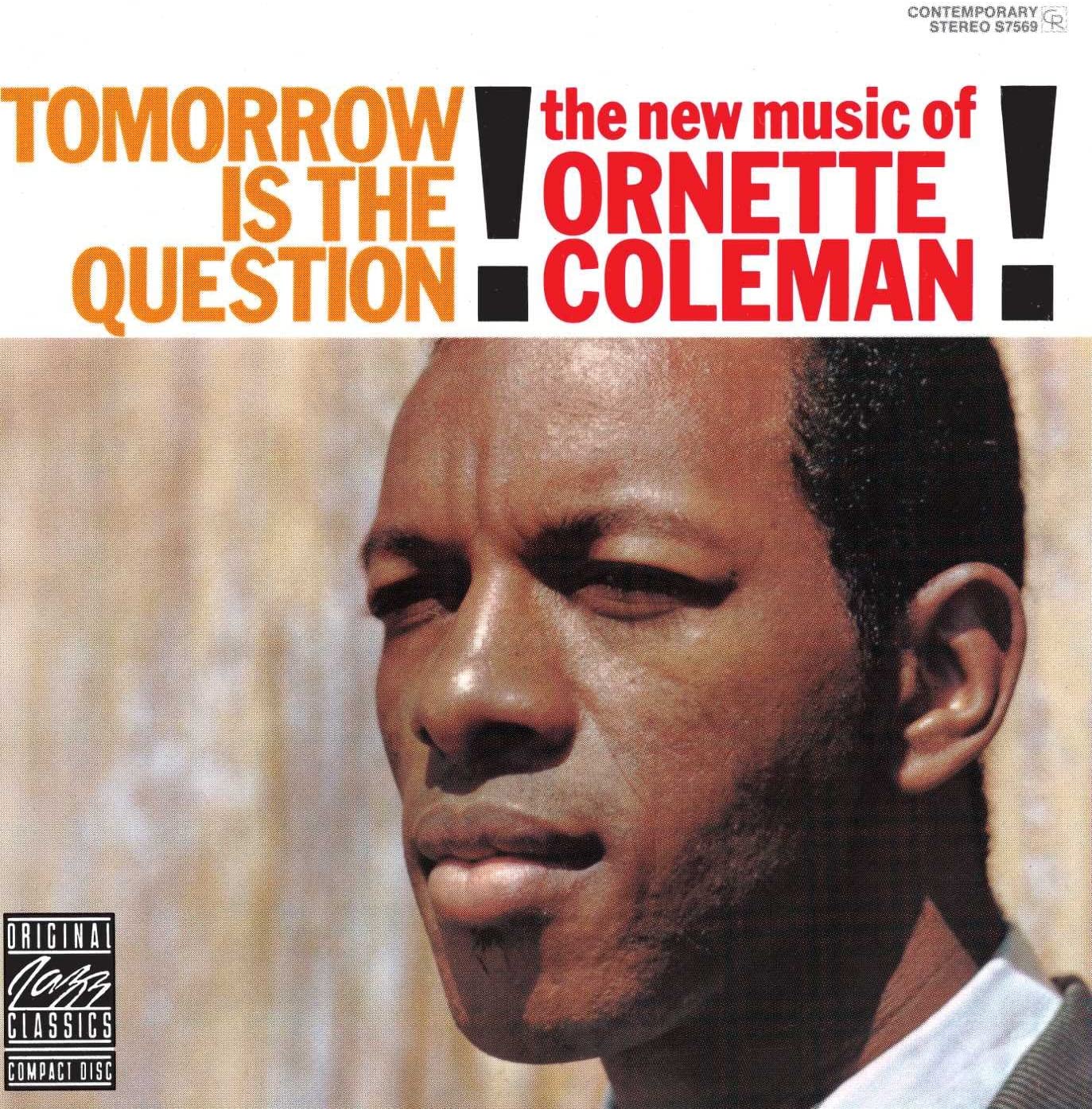
本作での飛翔には凄まじいものがあります。それに合わせたかのように状況はさらに良くなります。本作でのもう一人のベーシストPercy Heathが参加するバンドModern Jazz Quartet(MJQ)のリーダー、John LewisがOrnetteの演奏を気に入り、Cherryと共にSan FranciscoでMJQとの共演が実現しました。MJQは素材としてクラシックのナンバーをJazz的に演奏することを信条とする保守的なスタイルのバンド、彼らとOrnetteのコラボレーションは実に意外な気がしますが、人間の相性には計り知れないところがあります。
LewisはOrnetteのことを自分達が所属するレーベルAtlanticのオーナーNesuhi Ertegunに紹介しました。ErtegunはかつてContemporaryレーベルに勤めていた事もあり、Koenigとは友人関係で信頼も厚かったので移籍は極めて穏便に行われました。ちなみにKoenigは「後年あれ以上我が社がOrnetteの面倒を見ることは不可能だった。Los Angelesには彼のバンドが仕事をする場がなかったからだ」と発言しています。またOrnetteは80年代初めまで作曲者印税をContemporaryから得ていましたが、会社は彼の印税を払うと常に赤字が出ていました(汗)。「Tomorrow Is the Question」レコーディングが行われてからわずか2ヶ月半後にErtegun自身がLAに向かい、Ornette第3作目にしてAtlantic第1作目、そして初期の傑作「The Shape of Jazz to Come」をレコーディングします。メンバーはOrnette, Cherry, Charlie Haden, Billy Higginsから成るJazz史に残る名バンド、Ornette Coleman New Quartet、その初レコーディングです!
前作とは異なり、Ornetteの音楽を十分に理解したリズムセクションとの共演は、アルバムから表出する芸術性に桁違いの真実味が加わりました。

冒頭1曲目はOrnetteの代表曲Lonely Woman、彼の伝記にこの名曲を作曲するきっかけが記載されているのでご紹介しましょ。その頃彼はデパートの在庫品係(ストックボーイ)として働いていました。ある日Ornetteがデパートの昼休みに街に出た時に次のような事がありました。”通りを歩いていると、画廊があった。そこのショーウインドウに、上流階級のとても裕福そうな白人女性の肖像画が飾ってあった。その人は目に涙を浮かべ、とても寂しそうな表情でそこに座っていた。誰もが望むものを、全て持っているかのようだった。私は、つぶやいた。「なんてすばらしいんだ。この絵から曲ができないだろうか」”音楽家が新たな創造を行う場合、強力な刺激が引き金になります。
曲のイメージ、演奏、2管編成のアンサンブル、ドラムスの倍テンポ、対するベースのハーフリズムのキープ感、Ornetteのアルトサックスの入魂プレイとその凄まじいまでの音色!名演奏の誕生です!2曲目Eventually、Hadenのベースが繰り出すon top感とスピード、深い音色、そして柔らかくともシャープさとビートと、一拍のたっぷりさが半端ないHigginsとが織りなす驚異的なビート感、スイング感、その上でのOrnetteの咆哮、馬のいななきにも聴こえるプレイは同業者として信じられない、あり得ないレベルでの表現法です!Cherryの演奏はOrnetteが表現しきれなかった部分を的確に補うべくの、アディショナルを聴くことができます。
MJQはOrnetteの楽曲も気に入っていました。このLonely Womanをレパートリーとして取り上げ、しかも表題曲として62年Atlanticからリリースしています。ちなみにOrnetteの演奏とは全く異なる、いかにもMJQらしいテイストでの演奏です。

そして同一メンバーで約5ヶ月後の10月に録音されたOrnette第4作目が「Change of the Century」です。
Ornetteの作曲センス、バンド・サウンドは数々のギグを重ねた結果に違いありませんが、前作からさらに格段の進歩を遂げています。

さらに翌60年7月、8月にドラマーをEd Blackwellに変えてレコーディングした作品が第5作目「This Is Our Music」です。
名曲Blues Connotation、Gershwinの名曲バラードEmbraceable Youを含む更なるOrnetteバンドの進化系の演奏が収録されています。
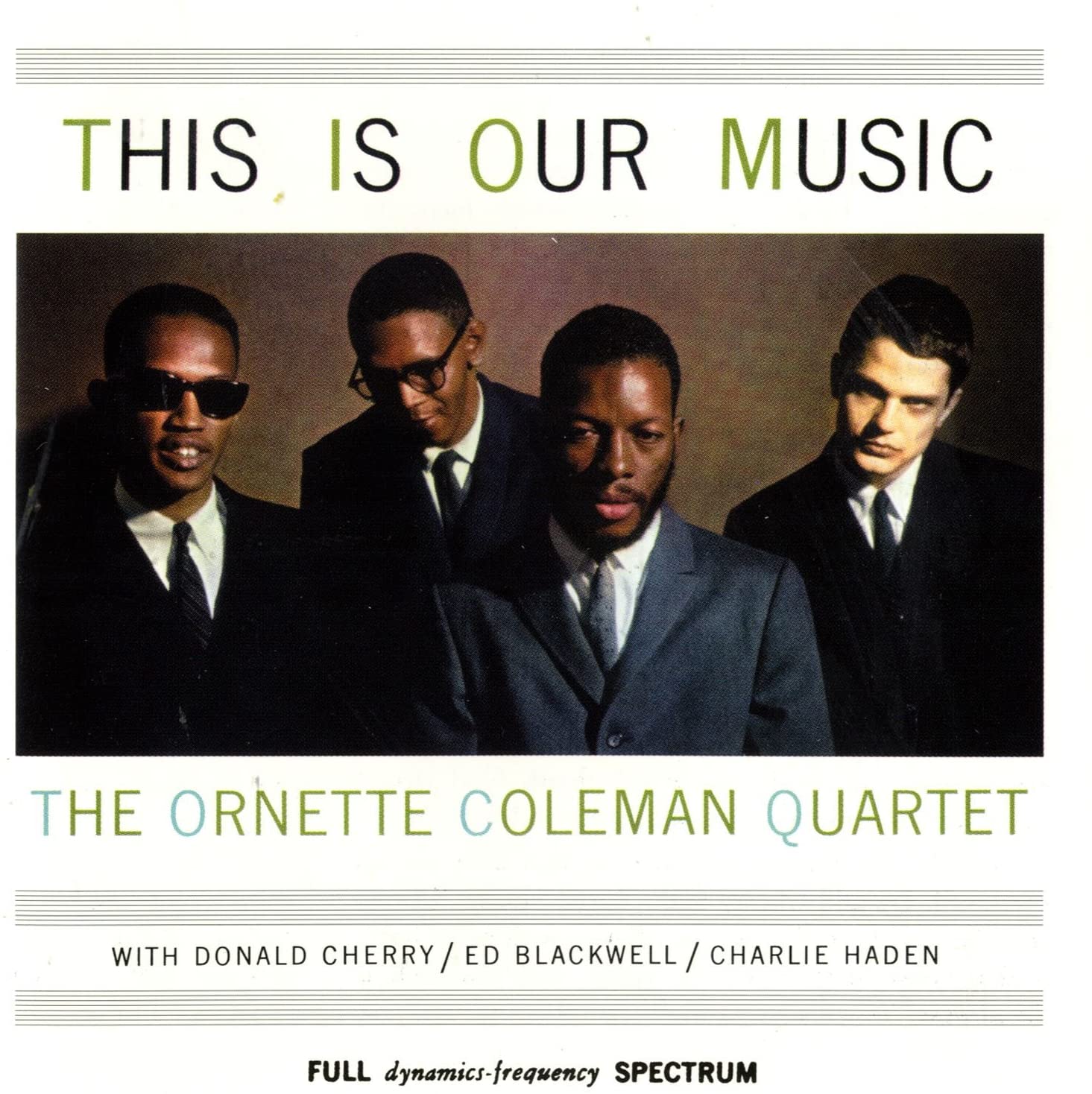
そして前作からわずか4ヶ月後、いよいよ世紀の傑作「Free Jazz」の登場です!
まず編成、構成からしてユニークです。ステレオ左チャンネルにOrnette, Cherry、そしてベースScott LaFaro、ドラムBilly Higginsの4人、右チャンネルにバスクラリネットEric Dolphy、トランペットFreddie Hubbard、ベースCharlie Haden、ドラムEd Blackwellの4人、彼らによるダブルカルテット!
ピアノレス・カルテット編成を4作続けて発表したOrnetteのこの時点での集大成、8人全員による集団即興演奏、発案者のOrnetteも凄いですが実現させたAtlantic Labelも大英断です!
Eric Dolphy

60年12月21日8人はNew YorkのA&Rスタジオに集まりました。おそらく別日にリハーサルを行い、レコーディングのコンセプト、演奏方法についてもOrnetteから説明があった事と思います。
実際に98年CD化に際し演奏をコンパクトにまとめたダイジェスト編、First Takeが発掘されました。
Free Jazzという名称でありながら実に用意周到であったOrnette、と言うかFreeであるからこそ筋の通った構成が必要になるのです。
録音当日、本テイク収録前に設計図を提示し、メンバーにはこのフォーム、ソロの順番を順守し、各ソロイストのバックで自由にブロウし、本テイクでは骨組みに自由な発想で躯体工事を施す旨、リーダーから指示があった事でしょう。
Jazzは基本的に最初の演奏が最もフレッシュで説得力があるとされます。随所に施されたアンサンブル・パートやソロ・オーダーの確認が主たる目的であったはずのFirst Takeですが、実はというか、やはり本テイクよりも演奏にパワーが感じられる部分もあり、各ソロもコンパクトながらより熱気を帯びています。
Don Cherry

それにしても各プレーヤーの素晴らしさといったら!Dolphyの前人未到のバスクラの鳴り、エッジ感、難楽器を容易くコントロールする驚異のテクニック。Dolphyと当時ルームメイトであったHubbardの熟れた果実のごとき魅惑的な音色と輪郭豊かな鳴らし方、加えての全くスムーズな楽器コントロール。Ornetteの唯我独尊状態のフレージングとアプローチ、そして何より凄みさえ感じさせるアルトの音色。Cherryの常に優しさを欠かさないアグレッシヴさ。アクティヴなラインと深い音色でメンバーのソロ中も鼓舞し続けるLaFaro、そしてそして、Hadenとのダブルベースですよ!何と美しいコンビネーションでしょうか!大好きなベース奏者ふたりの競演、これだけでも垂涎モノです!Hadenが基本的なビート、LaFaroの方がアグレッシヴなビートを刻んでいるように聴こえますが、時折逆転してプレイしています。二人はきっと相性も良かったのでしょう。
さらにさらに、BlackwellとHigginsのツードラム、軽快で繊細、時として穏やかな海原に突然現れたストームの如き大胆なビートを繰り出すリズムの2大巨匠、役者のレイアウトは万全です!
Freddie Hubbard

冒頭全員による不協和音でのイントロ、この時点ではまだリズムは定まっていません。恐らくOrnetteのコンダクトによるアンサンブルが00:06から始まりますが、これはいったい何と表現したら良いサウンドでしょうか?ホーンの強者どもにしか成し得ないエグくて強力なアンサンブルです!
引き続きDolphyを主体としたソロが開始、彼の吹く8分音符のバウンス感は実に心地よいですね!リズムが定まり、LaFaroは倍テンポのスイングでラインを刻みますが実にon topでカッコいいです!
メインのソロイストは決して吹き捲ることをせず、スペースを大切にしながらプレイし、他のホーン奏者も実に様々なライン、アイデアを提供しつつ、バッキングをしながら合わさり離れて、放置しながらメイン奏者を刺激します。
この演奏の素晴らしいところは、フロント陣はFreeにブロウしているのに対し、リズムセクションはずっとインテンポで正確なビートをキープしている点です。Free FormでテンポもFreeになってしまうと、オーディエンスには苦行でしかありません。Ornetteの音楽は基本的にこのスタンスで成り立っていると言えます。そしてリズムセクションには常にビート・マスターを採用しているのです。
Charlie Haden

05:11からアンサンブルが演奏され、Hubbardのソロになります。彼の演奏がメンバーの中で最もラインをラインらしく吹いているので、オーソドックスさを感じさせます。
Dolphyのバスクラの音域が管楽器中一番低いので、他のプレーヤーに対するサポート感が抜きん出ています。
Hubbardのソロの終わり頃に管楽器が集約し始め、09:53からメインテーマと思しきメロディとアンサンブルが始まり、そのままOrnetteのソロに突入します。このメロディの陽気さ、7thコード感はOrnetteの特徴のひとつです。
Scott LaFaro

リズムセクションは相変わらず軽快なビートを繰り出していますが、ベースとドラム各々二人づつとは感じられない一体感を聴かせます。Ornetteのソロは時たまテーマのメロディを引用しつつ、本レコーディング発案者としてのウタを感じさせる演奏を展開しています。彼の吹くシンコペーションは豊かなリズムを伴っているので、思わず引き込まれるように管楽器3人、合いの手を入れています。
19:35でいきなりメインテーマが再演奏され、Cherryのポケット・トランペット・ソロになります。メンバー全員様子を伺いつつ、虎視眈々と何を吹くべきかを狙っているのが気配から察知できます。
25:20にメインテーマのショート・ヴァージョンが演奏されHadenのソロへ。LaFaroが伴奏しますが二人同時にソロを取っているかのようですが、真っ先に両者の美しいベースの音色に感動してしまいます。前出の管楽器奏者たちのソロ、Collective Improvisationも本当に素晴らしいですが、本演奏はリズムセクションの同じ楽器同士のやり取りが異なったカラーを放っていて、実はこちらがメインイベントと見紛うばかりの美の世界を構築しており、Free Jazzという名称はむしろ相応しくないと思います。
Billy Higgins

29:51に突如としてアンサンブルが鳴り響き、今度はLaFaroのソロが開始されますが、こちらも二人同時のソロ、LaFaroの弾いたラインに的確にHadenが答えます。いや〜実にスリリングでベース・ファン冥利に尽きる場面です!HadenのWalkingラインの上でLaFaroのピチカートソロ、このアルバムでしか聴くことの出来ない超レアな演奏です!
この二人だけで作品を作って貰いたかったと、思わず有り得ぬことを考えてしまいます!
Ed Blackwell

33:46で再び場面を変えるべくアンサンブルが聴かれ、Blackwellのソロが開始します。こちらはタムを中心とした何やら楽しげなサウンド、Higginsは金物を叩いて呼応しています。
35:18でドラムソロ交代のアンサンブルが鳴り響き、Higginsの出番です。Blackwellとは全く異なるアプローチでシンバルを中心にパーカッション的なソロを展開し、Blackwellはシンバルレガートとスネアでリズムをキープし、相方のソロを際立たせようとしています。
その後Free Jazzを締め括るべくCollective Improvisation、そしてどこまで書かれていたのか、リフ的なアンサンブルが聴かれ37分以上に及ぶ歴史的セッションは終了します。
2021.06.27 Sun
今回はシンガーソングライターMichael Franksの1995年作品「Abandoned Garden」を取り上げてみましょう。
Producer: Matt Pierson, Gil Goldstein, Russel Ferrante, Jimmy Haslip
Recorded at Bearsville Studios, Clinton, Make Believe Ballroom, Power Station, Sound on
Audio Mixer: James Ferber
Label: Warner Bros.
vo)Michael Franks flumpet)Art Farmer flg)Randy Brecker ts)Michael Brecker ss)Joshua Redman as)David Sanborn, Andy Snitzer al-fl)Lawrence Feldman fl, al-fl)Bob Mintzer tb)Keith O’Quinn p)Eliane Elias, Russel Ferrante, Gil Goldstein, Bob James, Carla Bley g)John Leventhal, Chuck Loeb, Jeff Mironov b)Jimmy Haslip, Chrisian McBride, Marc Johnson, Mark Egan, Steve Swallow cello)Diane Barere, Mark Orrin Shuman, Frederick Slotkin woodwinds, perc)Manolo Badrena ds, pec)Peter Erskine ds)Chris Parker, Lewis Nash perc)Don Alias, Bashiri Johnson vo)Brian Mitchell arr)Jimmy Haslip, Michael Colina, Russel Ferrante
1)This Must Be Paradise 2)Like Water, Like Wind 3)A Fool’s Errand 4)Hourglass 5)Cinema 6)Eighteen Aprils 7)Somehow Our Love Survives 8)Without Your Love 9)In the Yellow House 10)Bird of Paradise 11)Abandoned Garden
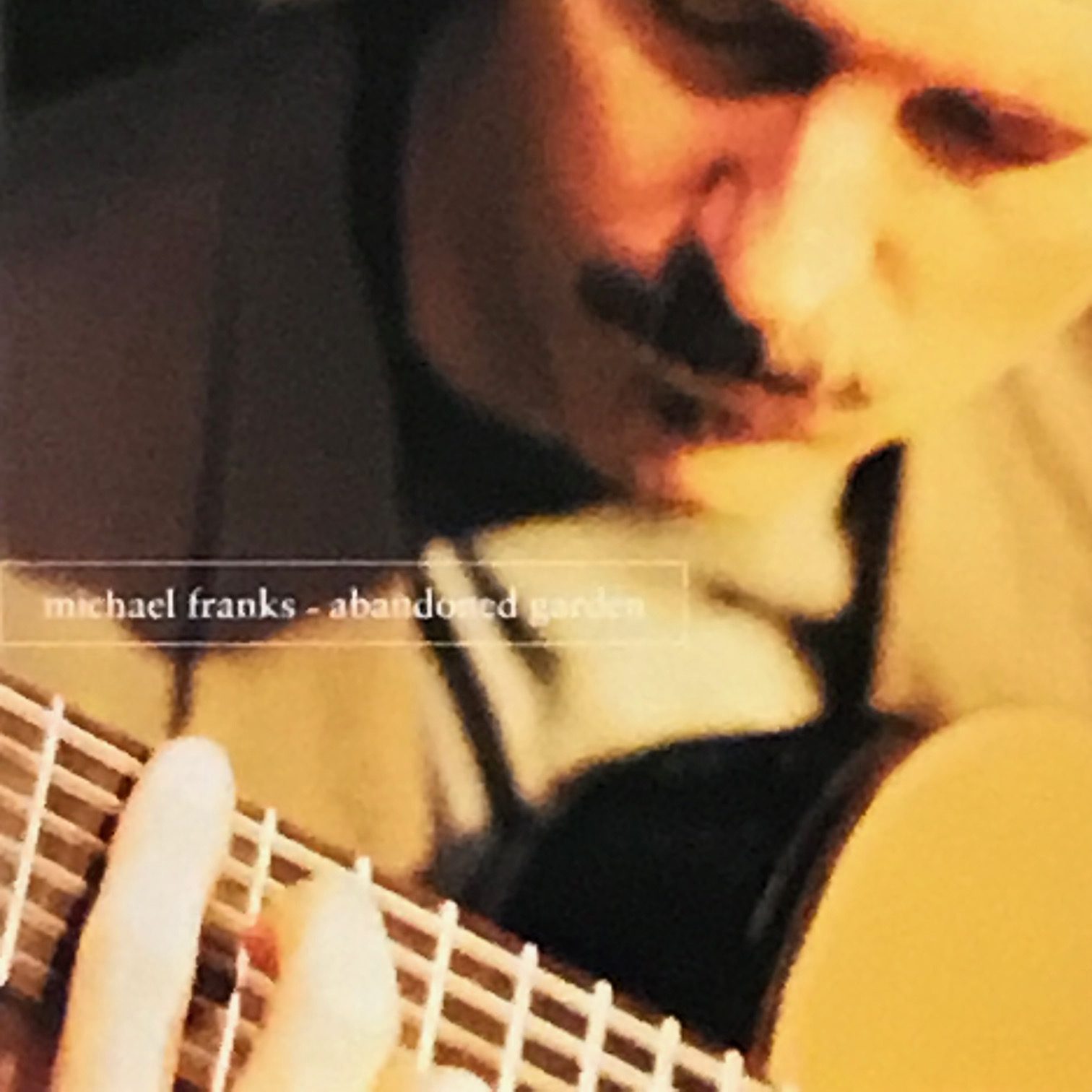
ビッグバンド編成ではないにも関わらず合計34名という参加ミュージシャンの多さ、しかもジャズ、フュージョン・シーンの精鋭ばかり、こちらにまず目が惹かれますが、充実したメンバーを贅沢に配し、曲毎のソロイストも演奏に極上のスパイスを加えるべく配合の度合いを計りながらの絶妙なプレイ、また毎曲のプロデューサーをサウンドのコンセプトに応じて替えるという至れり尽くせり〜綿密、微に入り細に入り、痒い所に手が届く豪華なアルバム制作に徹しています。
Franksが多大な影響を受けたBrazilが誇る偉大なシンガーソングライター、Antonio Carlos Jobimが作品の前年94年12月8日に67歳で逝去し、ミュージシャンとして、人間として心から尊敬していた彼に捧げた形になります。因みに彼が亡くなった時にはBrazil大統領令が発され、国民は3日間喪に服したそうです。Brazil国民だけではなく世界中の多くのファン、ミュージシャンも黙祷を捧げたと思います。
ライナーノーツにはJobimの写真と共に”In memoriam, Antonio Carlos Jobim, with endless admiration, affection, and love”と追悼の一行が掲載されており、1曲Jobimの書いた名曲Cinemaが収録されています。
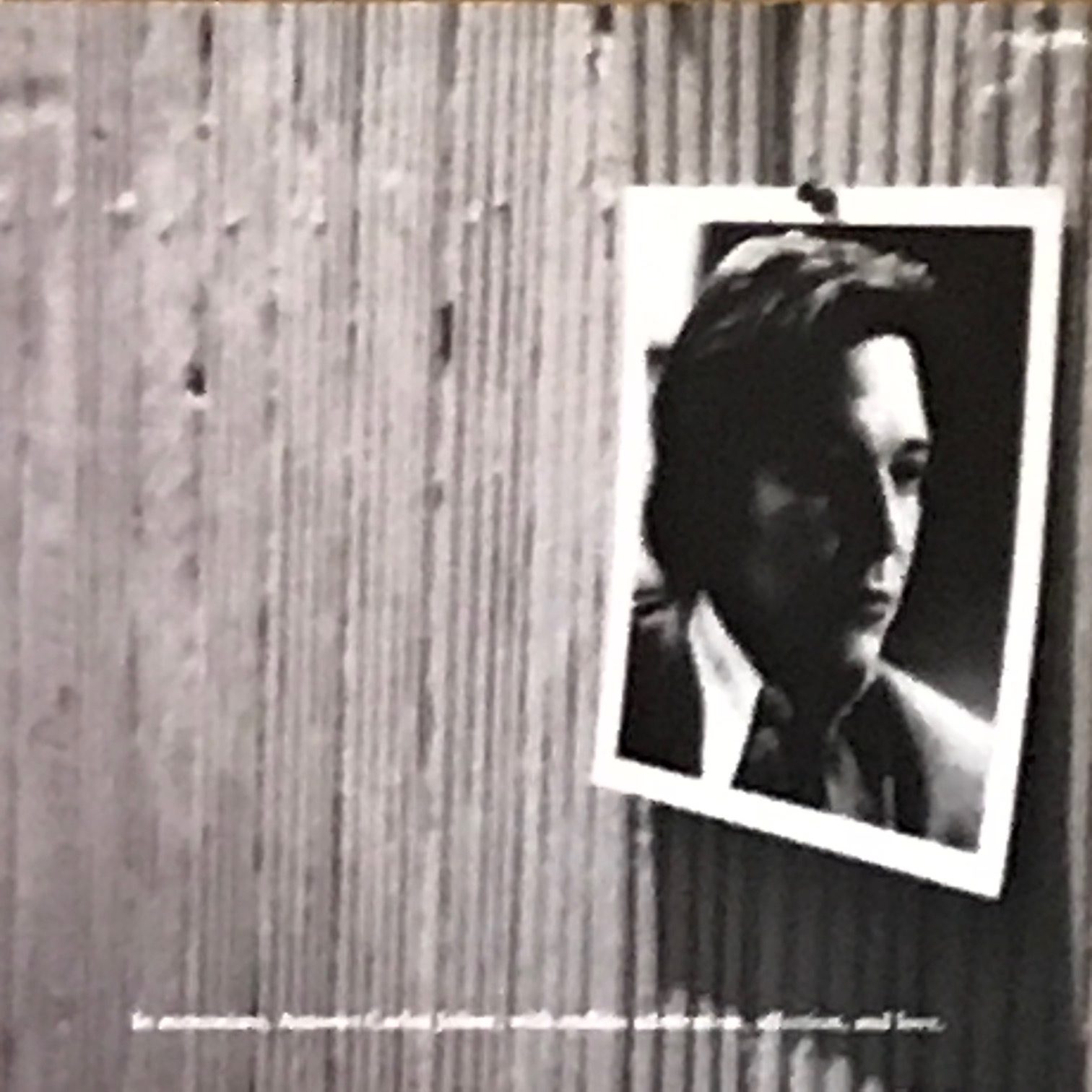
77年リリースの第3作目「Sleeping Gypsy」にはJobimに捧げたFranks作ボサノヴァの名曲Antonio’s Songが収録されていて、キャリアのごく初期から彼に対する敬愛の念を窺うことができます。曲の持つムード、哀愁を帯びたメロディ、そしてここではDavid Sanbornの申し分無い「泣き」の間奏、オブリガートが輝き、この曲は歴史的名演奏の次元にまで高められました。

Franksの作品群はいずれも彼の音楽性やイメージがバランス良く表され、佳作揃いのラインナップですが、本作はかつて発表したどのアルバムよりも作品を貫く崇高な雰囲気と演奏のクオリティの高さが抜きん出ており、これは間違いなくJobimへのトリビュートに起因するものでしょう。筆者自身も長年の愛聴盤ですが、今回Blogを執筆するに当り改めて聴き直し、作品の持つ芸術性の高さにとことん身の引き締まる思いを抱きました。追悼、哀悼の念は演奏に深く作用し、オーディエンスには滲み出るが如くとつとつと語り掛けます。
ジャズミュージシャンはプレイに際しどれだけ気持ちを入れる事が出来るかが問われる作業を、日々生業としていると言えますが、ここでの演奏はまさにそのそのショーケースと言えましょう。入魂の度合いゆえに演奏のいずれもが慈愛に満ちているのです。
そもそも僕自身Franksのアルバムは第2作76年「Art of Tea」と前述の「Sleeping Gypsy」からの付き合いになります。クロスオーバー、フュージョン真っ只中の学生時代に良く聴いたのを覚えており、当時我々の間で自分達を評した演奏形態〜ど根性フュージョン(笑)、むやみに気合の入った、汗が飛び散らしながらの自己満足的な熱い演奏(爆)、ステージングをモットーとしていたので、Franksの決してシャウトしないクールでAOR的なボーカル(クワイエット・ストーム・ムーブメントとも言うそうですが、知りませんでした)、都会的でスマートな曲作りやアレンジは言わば「真逆への憧れ」でした。そして参加ミュージシャンMichael Brecker, David Sanborn, Joe Sample, Larry Carlton, Wilton Felder(テナーサックス奏者ではなく、エレクトリック・ベース奏者として!)たちもFranksの音楽性に合致したプレイを展開、彼らの演奏もお目当てに「自分達もこんな大人な演奏を繰り広げる日が本当にやって来るのだろうか」とも良く自問自答したものです(汗)
これら最初期の2枚からFranksは作品に対して変わらぬ一貫したスタンスで取り組み、13作目に該当する本作も基本的にいつものMichael Franksですが、ゴージャスな編成、プロデュース力、そして何と言ってもJobimへの敬愛の念から彼のベスト作の1枚と認識しています。

一般的にシンガーソングライターは歌詞を書き、作曲し、自ら歌唱する。本質的にはそこにギター1本あれば表現方法として十分に足りてしまいます。この自己完結的な創作行為にFranksは素晴らしい音楽仲間を必ず伴って自分の音楽を何倍、何十倍にも増幅させていますが、本作の共演者の多くはその継続的なパートナー、そしてかつてのSample, Carlton, Felderたち、そしてプロデューサーTommy LiPuma, Matt PiersonらとのコラボレーションによりFranksは稀有で充実した創作活動を続けています。
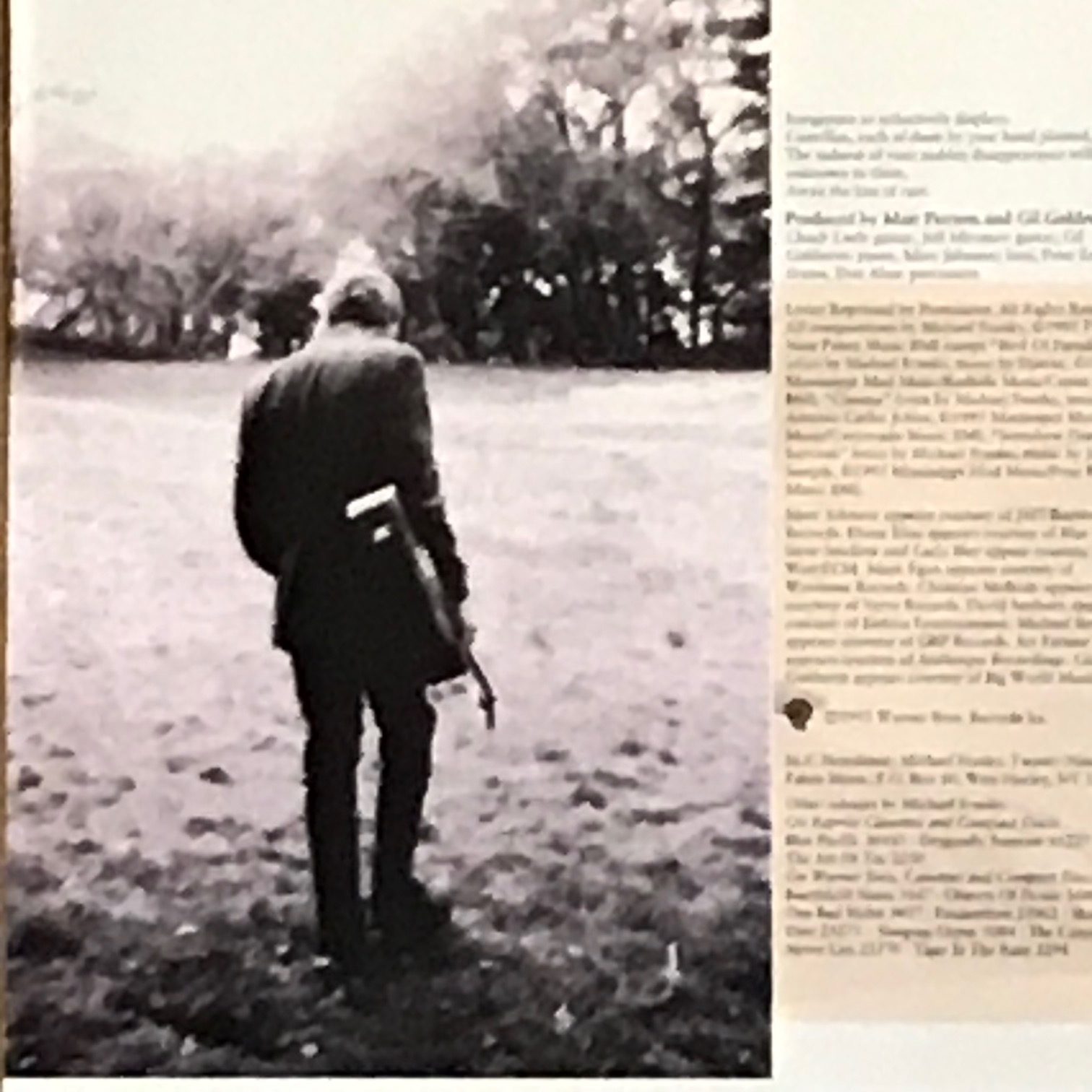
それでは収録曲について触れて行きましょう(収録曲のタイトルをクリックすると視聴する事が出来ます)。1曲目This Must Be Paradise、プロデュースと演奏にはRussell FerranteとJimmy Haslip、ホーンセクションにBob Mintzerのフルートを配し、アレンジもFerranteが担当するYellowjackets色が強いセッションですがFranksの音楽に見事に昇華しています。フルートやチェロによるウッドウインズ・ストリングス5重奏アンサンブルも緻密で心地よく響き、Chuck Loebのアコースティック・ギター演奏、随所に散りばめられたManolo Badrenaによるパーカッション・サウンド、Chris Parkerの柔らかく且つタイトなドラミング、そして何よりFranksの物憂げなボーカルが素晴らしい!多少専門的な話になりますが、ジャズボーカリストは腹式呼吸を基本に、声帯から発した声を身体を響かせてパンチのあるサウンドに変換します。女性ボーカルではElla Fitzgerald然り、Carmen McRaeやSarah Vaughan、男性ではMel Torme、Tony Bennettに代表されますが、Franksはむしろ腹式呼吸を控え、胸式呼吸で囁き系の持ち味を聴かす、英語の子音がマイクロフォンに良く乗るように配慮しているが如き唱法をトレードマークとしています。楽曲全体を通しボーカル、バンドのサウンド、アレンジ、曲想が全て有機的に絡み合い、纏まり、One & OnlyなMichael Franksワールドを構築しています!
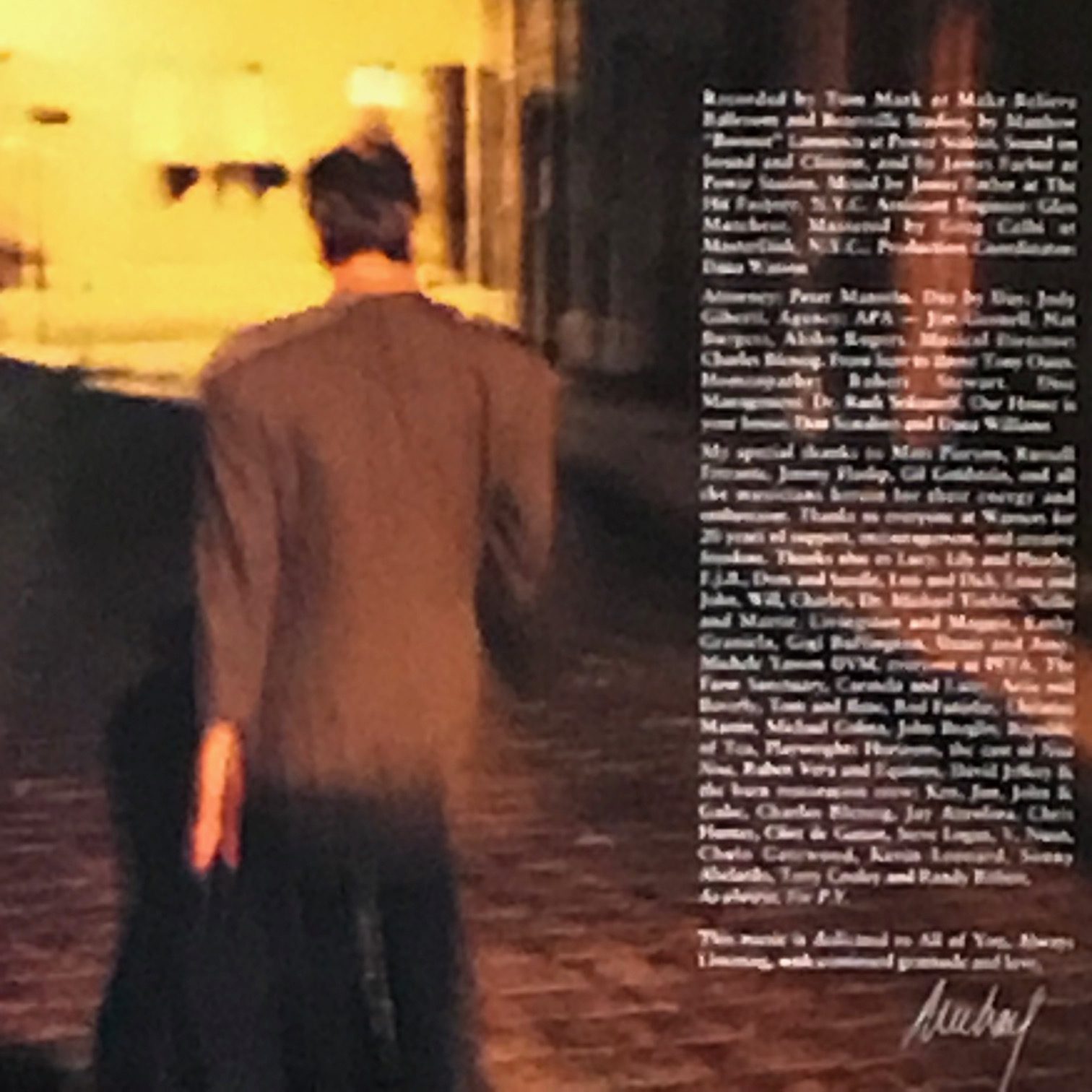
2曲目Like Water, Like Windは同じメンバーによる演奏、アレンジやプロデュースのクレジットも同様です。前曲が静とすればこちらは動かも知れません、兄弟のような関係の2曲ですがJobimの思いを切々と語った内容の歌詞がより印象的、オーヴァーダビングも含めアクティヴなFranksの唄を、ウッドウインズ+ストリングス・セクションもボーカルをしっかりとサポートしています。前曲ではギターソロがフィーチャーされましたがここではFerranteのピアノ・フィルインが活躍しています。
Russel Ferrante

3曲目A Fool’s Errand、タイトルの意味は徒労、骨折り損。歌詞の内容もそうですが曲の構成、アレンジにも凝ったものを聴くことができます。テナーサックスMichael、ピアノにEliane Elias、ベースChristian McBride、ドラムLewis Nash、加えるにRandy Brecker, Mintzer, O’Quinnのホーンセクション、こちらのアレンジはMintzer自身、大変ユニークな曲想に相応しくMichaelの間奏が実にのびのびと気持ち良さそうに響きます。推測するに演奏の資料を前もってFranksから渡され、彼お得意の綿密な準備の元、ネタを確実に仕込みレコーディングに臨んだソロでしょう。決してフレーズを吹き切らない、まるで体言止めの連続のようなフレージングの処理、これまでのMichaelのソロで聴いたことの無い斬新なアプローチに感動し、思わずコピーし譜面にした覚えがあります。ミディアムスイングのリズムはMcBride, Nashには実にお手の物、心地よく響き、ボーカル、リズムのシカケ、ホーンセクション、曲想との合致感が堪らないテナーのソロ、オブリ、全てに寸分の隙のない完璧な構成の演奏で、全くタイトルの意味する徒労には終わらず(笑)、100点満点を進呈しましょう!
Michael Brecker

4曲目HourglassはPiersonとGoldsteinの共同プロデュース、Jeff Mironovギター、Goldsteinピアノ、Marc Johnsonベース、Peter Erskineドラム、AliasとBashiri Johnsonパーカッション、こちらもJobimの喪失感を唄った情緒的なナンバー、曲中のフェルマータ、スットプタイムが何と効果的なのでしょう!ボーカルの感情移入がよりナチュラルに行われ、聴き手にとっても押し寄せる情感ではなく、小刻みな、遠くから次第にやって来る波動のように、FranksのJobimに対する思いが徐々に、そして深く浸透します。ボーカルのオーバーダビングによるコーラス、ピアノとギターの交互に演奏されるメロディも哀愁を感じさせるこの上ない名曲、情感豊かに歌い上げられ、何度繰り返し聴いてもフレッシュさが失われないばかりか、ますます身体の奥に染み入るばかりです。
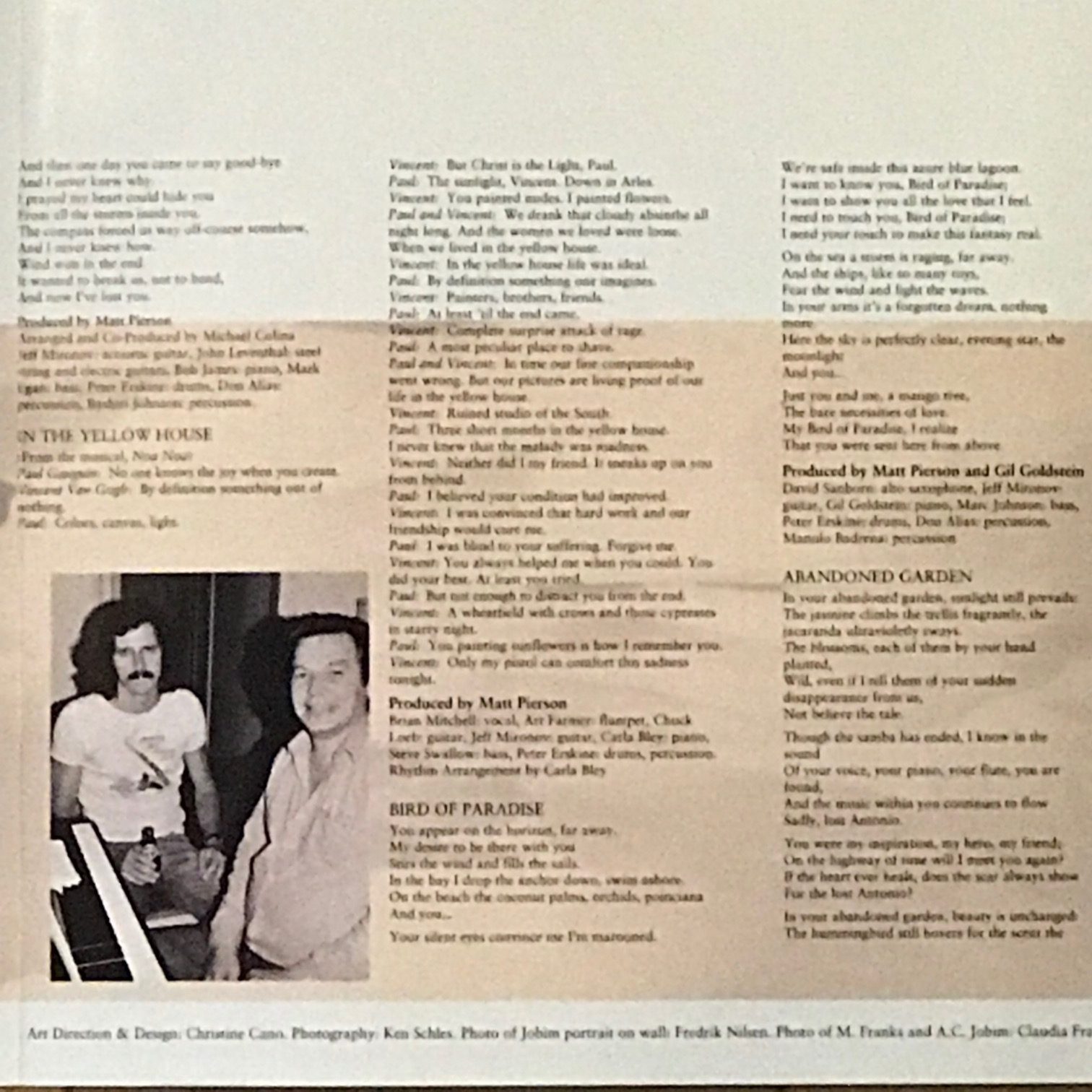
5曲目は本作白眉の演奏Cinema、Jobimの申し分無い名曲をElianeがリズム・アレンジ、PiersonがプロデュースしMichaelテナー、Elianeピアノ、McBrideベース、Nashドラム、Aliasパーカッションのメンバーでストレートに演奏されますが、ここまでトリビュートの気持ちが込められた演奏を未だかつて聴いたことがありません!
Jobinと同郷Brazilでボサノヴァに造詣の深いElianeをピアニスト選んだのはまさしく適任、と言うか彼女しかあり得ません!
Franksの本作に対する思いが彼に確実に伝わったのでしょう、イントロはMichaelのいつも以上に優しさに溢れたオブリガート的ソロから始まります。その後バンプ部分が設けられFranksが歌い始めます。Elianeがフィルイン的に弾くラインにMichaelが反応し呼応しているのが微笑ましいです。主題部分に入る直前のMcBrideのグリッサンドの絶妙さと言ったら!
感じるのはFranksの声質、歌い方、ムードがこの曲に見事に合致している点です。決してtoo muchに感情移入せず通常の彼らしい歌唱ですが、格別の思い入れをスパイス的に随所に感じさせます。
そしてElianeのバッキングのこれまた見事なこと!深い煌びやかさとでも表現出来るでしょうか、彼女もJobimには特別な思い入れがあるに違いありません、情感を込めつつ曲のイメージを最大限に膨らませボーカル、テナーソロに全く過不足なく的確に、ハイパーなコードワークを用いつつアプローチしています。
テナーソロにも新境地を見出す事が出来ます。膨大な量の歌伴の演奏を経験したMichael、しかしこれほどの”ウタ”を感じさせるプレイは存在しなかったでしょう。しかも優しさ、スイートネス、音色やニュアンスの素晴らしさ、曲の持つムードとFranksの歌唱との合致感を湛え、こちらも恐らく綿密な予習の賜物とはいえ、鳥肌が立つほどの感動を聴くたびに覚えます。
Aliasのパーカッションがボーカルの時には隠し味程度でしたがテナー、ピアノソロ時にしっかりと調味料として登場、それは見事なカラーリングを行っています。この人はどんな所にも、あらゆるシーンにごく自然に登場してパーカッションを演奏していますが、その理由、本質をここでの演奏とセンスで確認出来たように思います。その後はあと唄、そしてアウトロでピアノが登場、Herbie Hancockのテイストを感じさせつつクリアーでリリカルなタッチでのソロを聴かせます。フェードアウトの位置が早かったようにも感じますがあくまで主体はボーカル、この辺りでの退席が出しゃばらず丁度良かったと思います。
Eliane Elias

6曲目Eighteen Aprilsは4曲目のメンバー、プロデューサーと同一、そこにJoshua Redmanのソプラノサックスが加わります。Joshuaは93年に本作と同じWarner Bros.からリーダー作をリリースしていますが、デビュー作をリリースして間もない彼を単に対外的演奏に起用したような雰囲気があります。演奏のクオリティ、楽器の音色、ピッチ感、センス、歌い回しにどうも納得が行きません。早い話他のフロント奏者よりもレベルが下がり、演奏自体も足を引っ張られかねないように感じますが、そこは万全の体勢でのリズム隊、何が加わっても美の世界を構築し続けてはいます。ひょっとしてこの曲はリズムセクションだけの伴奏でも良かったように思います。without
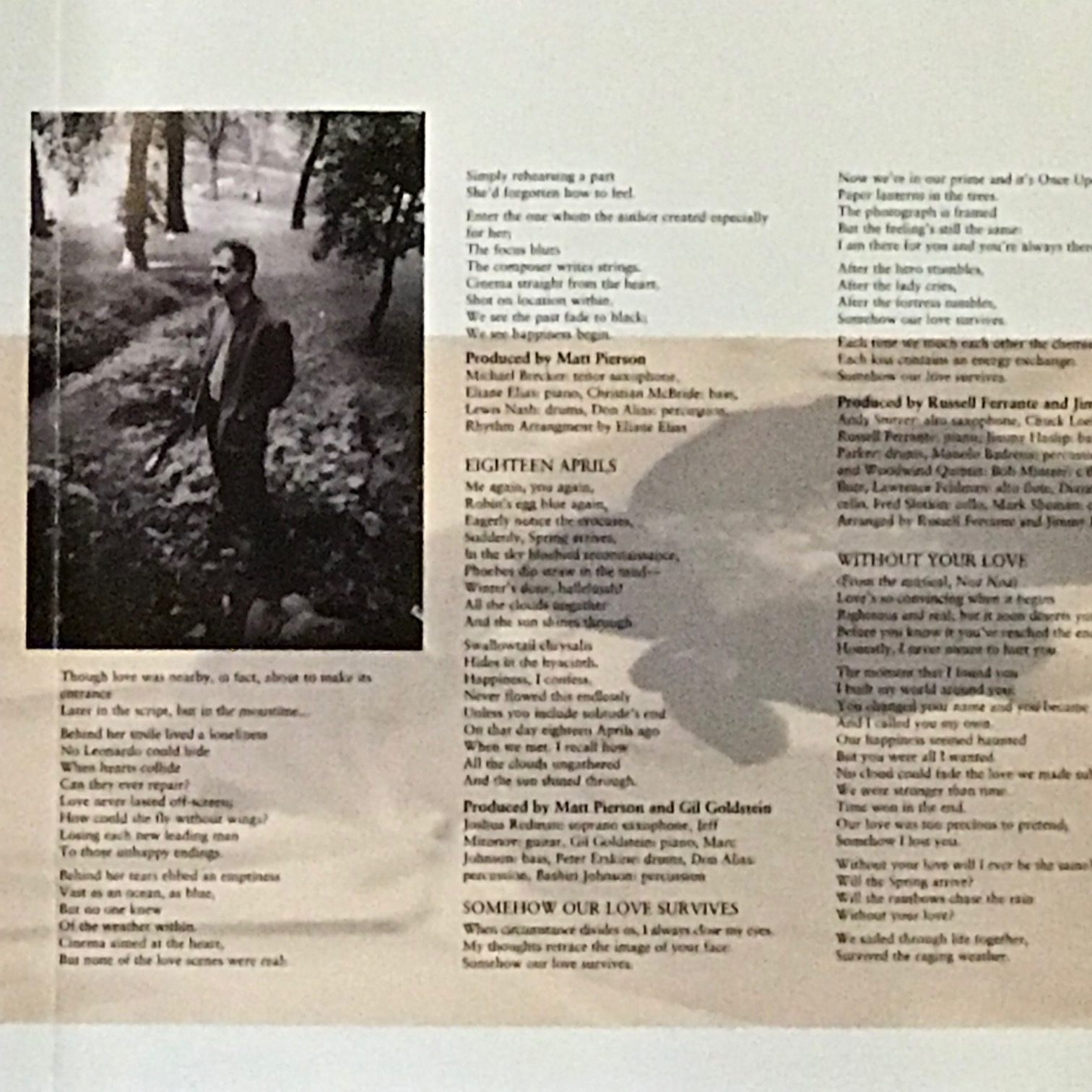
7曲目Somehow Our Love SurvivesはJoe Sampleのナンバーです。1, 2曲目と同様の布陣、ここにアルト奏者Andy Snitzerが加わりファンク色の強い演奏を聴かせます。Snitzerは本来テナー奏者ですが、スムース・ジャズ・サックス奏者にありがちな両刀遣いぶりを披露、ファズやバズの効いた音色、フュージョン・スタイル正統派を感じさせるフレージング、間の取り方で曲想に相応しいソロを聴くことが出来ます。リズム隊のグルーヴもダンサブルで、こちらではFerrante, Haslipの参加からThe Yellowjackets的テイストを垣間見る事も出来ます。
Andy Snitzer

8曲目Without Your Loveはガラリと演奏者が変わります。PiersonにMichael Colinaが共同プロデュースで加わり、Mironov, John Leventhalのギター、Bob Jamesピアノ、Mark Eganベース、Erskineドラム、Alias, Johnsonのパーカッションというメンバーでのテイク、Noa NoaというMusicalで用いられたのナンバーのようです。
アコースティック・ギターのアルペジオに導かれFranksの登場、ピアノも美しいフィルインを入れています。本編に入りベース、ドラムが加わり曲の全貌が新たになりますが実に美しいメロディラインの曲、メロディの合間に入る各楽器のフィルインがいずれもまた、これ以上は考えられないという次元での合致度を聴かせます。ボーカルのオーヴァーダビングもユニゾン、コーラスとの使い分けも効果的。Jamesのピアノソロ、フィルも美学に貫かれています。
Bob James

9曲目In the Yellow Houseはこちらも前曲と同じMusical Noa Noaからのナンバー。もう一人のボーカリストBrian Mitchellが加わり、Paul Gauguin役にMitchell、Vincent Van Gogh役でFranksが対話形式で語り合いつつ、コーラスも行いますが、Mitchellの方はいかにも長年Musicalを手掛けているかのような対照的な(腹式呼吸による音圧感も含めて)歌唱を聴かせます。ここにArt Farmer(!)のフランペット(!)ソロ、Loeb, Mironovのギター、Carla Bley(!)のピアノ、Steve Swallow(!)のベース、Erskineのドラム、パーカッションで演奏されます。
プロデュースはPierson、なんと言ってもGauguineとGoghの対話です!本作中異色なナンバーですがとても印象深いテイクとなりました。
Art Farmer

10曲目Bird of Paradiseは同じくBrazil出身のDjavanのナンバー、Franksの盟友David Sanbornのアルトサックスを迎え、Mironovギター、Goldsteinピアノ、Johnsonベース、Erskineドラム、Alias, Badrenaのパーカッションで演奏されます。
Sanbornはさすがこのスタイルのパイオニア、美しい独自の音色とメロウな歌い方、タイム感、そして脱力感とイマジネーションで風格ある演奏を聴かせます。Snitzerのプレイも良かったですが、こうして比較すると否応なく格の違いを感じさせます。曲自体もまさしくSanbornが活躍出来るテイスト、土壌を持った佳曲です。
David Sanborn

ラストを飾る11曲目表題曲Abandoned Garden、Pierson, Goldsteinコンビのプロデュース、Loeb, Mironovのギター、Goldsteinピアノ、Johnsonベース、Erskineドラム、Aliasパーカッションと本作の核となるミュージシャンによる演奏です。
4曲目Hourglassと同一なコンセプトでフェルマータ、ストップタイムを駆使した楽曲、Jobimにトリビュートした歌詞の内容もかなりイメージの世界に埋没した状態のようです。
本作中最も彼の逝去を嘆いたナンバー、Franks音楽性に於けるJobimの重要性を耽美的に語っています。
2021.06.13 Sun
今回はJoey Calderazzoの1991年初リーダー作「In the Door」を取り上げたいと思います。
Produced by Michael Brecker
Recorded and Mixed by James Farber at Carriage House Studios, Stamford, CT
Label: Blue Note
p)Joey Calderazzo ts, ss)Branford Marsalis(on 1, 2, 4) ts)Jerry Bergonzi(on 3, 5, 6) ts)Michael Brecker(on 8) b)Jay Anderson ds)Adam Nussbaum ds)Peter Erskine(on 2, 4) perc)Don Alias(on 6, 7)
1)In the Door 2)Mikell’s 3)Spring Is Here 4)The Missed 5)Dome’s Mode 6)Loud – Zee 7)Chubby’s Lament 8)Pest

才能豊かな若きピアニストの処女作に相応しい素晴らしいミュージシャンが集い、申し分のない演奏を展開しました。リーダー本人も伸び伸びと外連味のない王道を行くプレイを聴かせています。
アルバムには有能な新人を紹介するに足る的確な選曲、アレンジ、構成が施され、様々なテイストの楽曲に対しBranford Marsalis, Jerry Bergonzi, Michael Breckerたち個性派ボイスを湛えたテナー奏者を贅沢に配することで、Joeyの持つ幅広い音楽性を巧みに、そして深く表現しています。
彼をシーンに引っ張り出した張本人Michael Breckerが本作のプロデューサーを務めます。自身のリーダー作やThe Brecker Brothers Bandの作品以外で彼のプロデュースによる作品を見かけた事がありません。おそらく唯一のアルバムになりますが、それだけJoeyに対する思い入れがあり、サポートすることで彼を世に送り出したかったのでしょう、以降MichaelとJoeyはMichaelが逝去するまで演奏活動を共にしました。
僕は2007年2月20日Town Hall, New York Cityで行われたMichael Brecker Memorialに参列しました。彼の没後(同年1月13日)およそ1ヶ月後に催されたのですが、それはそれは充実したセレモニーでした。
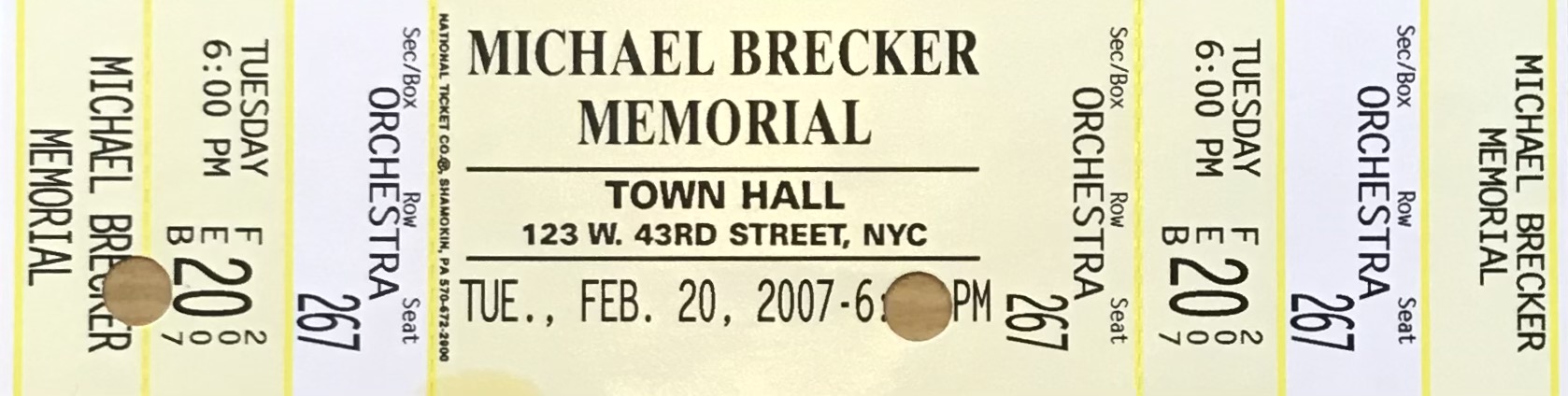
兄Randy、息子SamuelやSusan夫人のスピーチを交え、Dave Liebman(Michaelに敬意を表しサックスは吹かずに笛を演奏しました), Pat Metheny, Herbie Hancock, John Patitucci, Jack DeJohnette, Paul SimonらMichael所縁のミュージシャンによる素晴らしい演奏、James Taylorの収録ビデオによるメッセージ等彼を愛する人たちの哀悼の意を痛烈に感じました。
JoeyはRandy, James Genus, Jeff “Tain” Wattsらとのカルテット〜Michaelのレギュラーバンド〜で演奏しましたが演目は彼の書いた名曲Midnight Voyage、 Michaelの代表作「Tales from the Hudson」収録ですね、Michaelの名演奏でも名高く、ここでのプレイが全く相応しい追悼になったのを今でも克明に覚えています。

Memorial当日、入場するべく入り口に並んでいるとウインドウ越しに娘Jessica(父親似の背の高い美人さんで、Michaelに写メを見せて貰った事があり、すぐに彼女と分かりました)、小学生のSam、そして黒い喪服に真珠のネックレスを付けた60代の女性がいるのが見えます。JessicaとSamは手を握ったり時折笑顔を浮かべながら仲良さそうに何か話をしていますが、もちろん彼らも黒い喪服を身に付けていました。
Michaelの奥方Susanには一度会ったことがあり、彼自身から紹介済だったのでSusanではないこの女性は誰だろうと考えていながら、ちょうど喪服の女性の視界に僕が入ったのでしょう、何故か僕の事をじっと見つめ、何かに気付いたように黒人のホールスタッフと思しき女性に指示をしています。その後すぐにウインドウを黒人女性が開け、喪服の女性がこちらに歩み寄り僕に何か話しかけ始めました。
「あなたの事をどこかで見たことがあると思ったら、Mikeの家にある写真で一緒に写っていた人ね、彼のお友達でしょ?そんなところで並んでいないでこっちにお入りなさい」と言われ、スタッフ女性を促し、会場の中に入れてくれたのです!
いきなりの出来事に呆気に取られ、流れに身を任せて入場しましたが間違いなくこの女性こそBrecker三姉弟、長女のEmily Brecker Greenbergでしょう!
Michaelが僕と一緒に写っている写真を自宅に飾っていてくれたのも嬉しかったのですが、その写真を見たことがあり、一緒に写っている人物を覚えていて、大勢が並ぶ列の中でその当人と判断できるお姉様も物凄い認知力です!さすがMichaelのお姉さん、ユダヤ系の方の頭脳明晰さをここでも実感することが出来ました!
その後関係者席に案内してくれましたが、周りは最先端のミュージシャンばかりです!目視確認できただけでもWill Lee, Peter Erskine夫妻(奥方日本人です), Mike Mainieri, Brad Mehldau, Mark Egan, Wayne Shorter, Buster Williams, James Carter, Pat Metheny, Shunzo Ono, Gil Goldstein, Mike Stern, Ravi Coltrane, Bill Stewart…そして僕の右隣にはKenwood Denardが座っていました。
当日の式次第は以前何かに書いた覚えがありますが、またいずれかの機会にもご案内したいと思います。
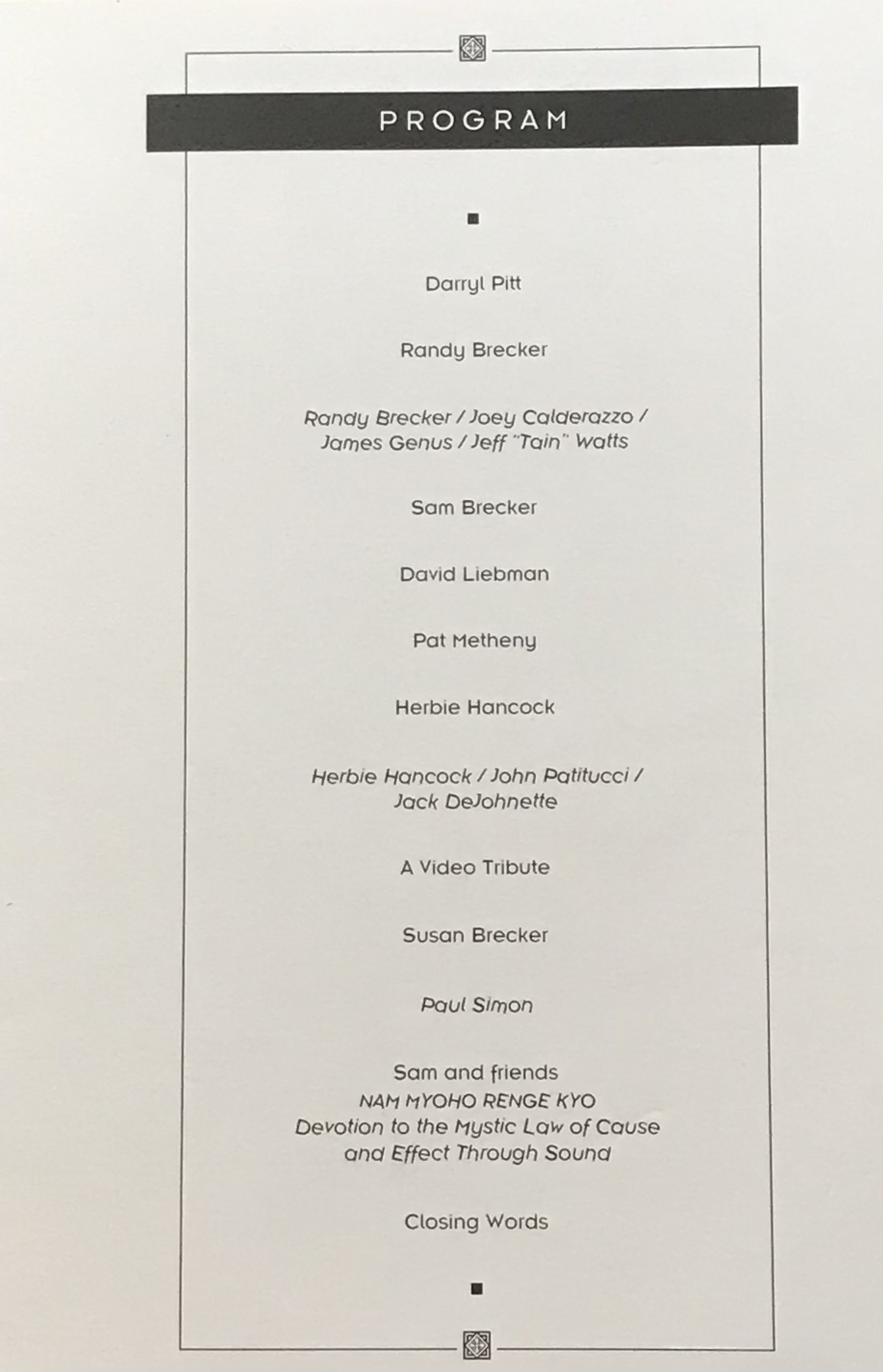
MichaelはJoeyの音楽性をこよなく愛し、Midnight Voyageほか彼のナンバーEl Nino, Pest(Nervous Opus), 彼のアレンジによるAutumn Leaves Funk Versionをライブで頻繁に取り上げていました。Autumn Leavesのアレンジがあまりにもカッコ良いので初めて聴いた時に「あのアレンジは誰が書いたの?Mike?」と尋ねると「僕の書いたアレンジ、と言えたら良いんだけど、Joeyのなんだ」とはにかみながら答えてくれました。
かなり前の話ですがBlue Note Tokyoが移転する前の店舗の時、Michael Brecker Bandを聴きに行きました。演奏前であったか休憩時間中か、ロビーにいるとMichaelがやって来て、「やあやあ」のような感じで挨拶を交わしました。暫くしてJoeyが現れ、僕に近寄りタバコをねだります(初対面でしたが)。その頃は僕も喫煙真っ只中、また殆どの飲食店内では禁煙になっておらず、Blue Note Tokyoも例外ではありませんでした。彼にタバコを差し出し火をつけると何も言わずそのまま背をむけ、プイっと立ち去るではありませんか。Michaelに「Joeyはいつもあんな感じなの?」と尋ねると「そうなんだよ、ごめんなさい、気にしないでね」と彼のことをリカバーします。その日の演奏はMichaelはもちろん、Joeyも実に素晴らしく、心ゆくまでパフォーマンスをエンジョイ出来ました。
後日Michaelと会う機会があり、当夜のライブについての感触を尋ねました。充実感に漲っている旨を柔和な表情で語ってくれ、話は彼のマネージメントや所属の事務所についてに及びました。長年彼の写真を撮り続けているカメラマンDarryl Pittが立ち上げ、彼がトップを務めるオフィス〜Depth of Field(写真用語で被写界深度)が管理しているそうです。音楽家に限らずマネージメントはタレントの良き理解者、長きに渡り堅い信頼関係の絆で結ばれた人物が相応しいです。Darrylには何度か会いましたがスマートで周りへのさり気ない気配りの出来る人物、何よりMichaelの事が大好きなので、全くの適任者です。
オフィスにはMichael以外に所属ミュージシャンはいるのかと尋ねると、Dianne Reevesがいるという返事、「他には?」「いや、彼女一人だ」、ふと思い付き「Joeyは所属していないの?」と尋ねると柔和な表情が一瞬曇り「彼はかつて所属していた」と過去形で言うではありませんか。「立ち入ったことを尋ねるけれど何故彼のマネージメントは外されたの?」「いや、良い質問だよ、Tatsuya、知っての通り彼は素晴らしいピアニスト、ミュージシャンで僕も心から尊敬しているんだ。彼なしでは僕の音楽は存在しないとまで思っている。でも彼は素行に問題があり、我々のオフィスに所属させておくことは出来ないと結論付けたんだ」。素行とは具体的に何を指すのかまではさすがに尋ねませんでしたが、前述のタバコの一件にその片鱗を垣間見られるかも知れません、Joeyの才能を鑑みるとマネージメントを外すに至ったのはDarrylとMichael、さぞかし苦渋の選択だった事でしょう。でも解雇があったにも関わらずその後も音楽的に良い関係をキープできたのは、ひとえにJoeyとのプレイの相性とクオリティの高さでしょう。
CDジャケットにもクレジットされていますが本作録音の頃はDarrylがJoeyのマネージメント管理をしていた蜜月の時期、演奏にもその充実感が表出されています。
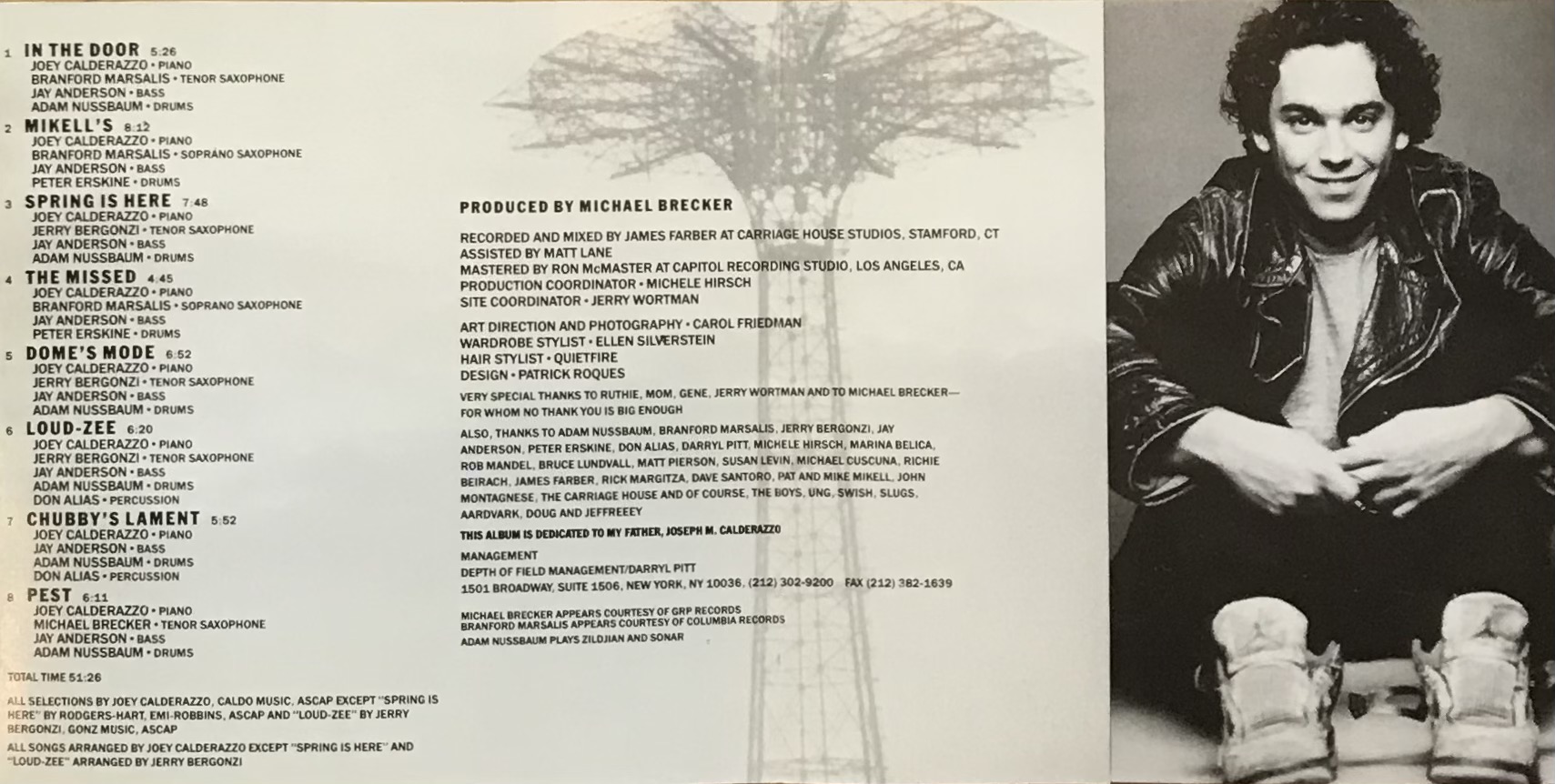
レコーディングメンバーについて、90年に活動していたMichael Brecker QuartetがJoeyの他、ベースJay Anderson、ドラムAdam Nussbaumが本作のリズムセクションだった事もあり、こちらが母体となりました(Peter Erskineも2曲参加してます)。人選はプロデューサーの特権です。同年3月19日〜24日Blue Note Tokyoに同じメンバーで来日を果たし、Michaelはテナーの他EWIを、Joeyもアコースティック・ピアノの他にシンセサイザーも演奏しいつもながらの素晴らしいパフォーマンスを繰り広げました。
演奏曲目は2作目のリーダー・アルバム「Don’t Try This at Home」のナンバーを中心に、3作目「Now You See It… (Now You Don’t)」レコーディング直前に該当するので新作から「The Meaning of the Blues」も披露、カルテット編成というソリッドなフォーメーションでメンバー一人ひとりのプレイを堪能する事ができました。


初めて聴くAndersonの堅実なベース・プレイが印象に残り、Michaelに尋ねたところ「彼はそんなに個性的なプレーヤーではないけれど(He is not so indivisual)、何しろサポートに抜群の安定感があるからね」と評していました。彼は現在も多忙を極めるベーシストでWoody Herman, Joe Sample, Lee Konitz, Frank Zappa(!)等、共演者や参加作は膨大な数に上ります。
Jay Anderson

それでは内容について触れていく事にしましょう。1曲目In the Doorはアップテンポのモーダル・チューン、Branfordのテナーをフロントに迎えたJoeyのオリジナル。前回取り上げた「Kenny Kirkland」の1曲目Mr. J. C.もBrannfordのワンホーンによる同様なコンセプトの楽曲、リズムセクションのグルーヴの違いが顕著です。両者の場合ドラマーに起因するところが大ですが、個人的には「Kenny Kirkland」でのJeff “Tain” Wattsのジャジーなグルーヴ感に惹かれます。
スイングのリズムはタイムの縦軸と横軸のバランスが重要で、繊維の縦糸、横糸に例えられると思います。さらに加えて1拍の長さも欠かす事のできないファクターです。Nussbaumは縦軸〜オンが強力に聴こえてきますが横軸〜バックビートがやや希薄、1拍の長さも同じくコンパクトです。それに対してWattsは縦軸と横軸が縦横無尽に張り巡らされた、360°全面に強力な磁場が働いているが如きドラミングで、拍の長いたっぷり感も聴かせています。
言ってみればNussbaumの方はイーヴン系、スイングビートよりもファンクや16ビート、ボサノヴァに個性を発揮出来るドラマーですが、本演奏ではon topなAndersonのベースワークが横軸に長け、ビートのたっぷり感も提供しているので、これだけの速さでもスイング感を聴かせることが出来たと睨んでいます。
以上を踏まえながらIn the DoorとMr. J. C.を聴き比べてみると、タイム感、ベースとドラムの相関関係、ビートの位置等、ジャズのリズムの謎解きに近づくことが出来ると思います。ぜひお試しあれ。
ソロの先発Branford、大健闘していますがリズムセクションにせっつかれたのか「こうあらねばならぬ」を感じる場面もあり、いつもより余裕を欠いたプレイに聴こえます。とは言えJoeyはリズミックに、テナーソロの間隙を巧みにCall & Response的にバッキングして場面を活性化しています。
因みにJoeyの兄Gene Calderazzoはジャズドラマー、Berklee音楽院在学中はBranfordとルームメイトだったという事で、兄を通じてJoeyはBranfordとは旧知の間柄でした。Joey自身もBerkleeやManhattan音楽院で学び、個人的にRichie Beirachにもレッスンを受けていた楽理派です。
そして続くピアノソロの素晴らしさといったら!ベース、ドラムとの三位一体によるon topなスピード感とグルーヴ、例えて言うならばOscar PetersonとRay Brownのコンビに同じベクトル方向を持つドラマー、あの頃の時代で思いつくのはTony Williamsでしょうか?(もちろん実際には存在しない組み合わせですが)。25歳の若者のプレイと俄には信じられないクオリティ!物凄いです!
Branford Marsalis

2曲目Mikell’sはおそらく91年までNew Yorkに存在していた同名ジャズクラブの事でしょう。Branfordの美しいソプラノをフィーチャーしたチャーミングなナンバー、ここではドラマーがPeter Erskineに代わり、カラーリングの妙、そしてレスポンスの巧みさを聴かせます。Andersonも自在なアプローチを伴ったラインを聴かせ、ソプラノとの一体感を繰り出しています。Joeyのソロもイメージ溢れる、繊細にして大胆なテイストを提供しています。ラストテーマ後に聴かれるBranfordとJoeyのソロのトレードは、気の合った仲間同志の楽しい会話のように、華が咲いています。
Peter Erskine

3曲目Richard Rodgersの名曲Spring Is Hereでは一転してダークなテナーサウンドが登場します。Jerry Bergonziをフィーチャーしたこの演奏、リハーモナイズされたコード進行が彼のテナーサウンドと実にマッチしており、この曲の新たな解釈として魅力を放ちます。アレンジもBergonzi自身によるもので、然もありなんです。Joeyのバッキングも実に多彩に、様々な表情を見せており、彼の持つ「エグい部門」でのBergonziとの相性の良さを感じさせます。
ホゲホゲしたテナートーンを湛えたBergonzi、巧みなストーリー展開を聴かせ、続くJoeyはリリカルにしてコンテンポラリー、極上のタイム感を伴いながらしかし怪しげに、自身も唸り声を上げつつ、同様に優れたストーリー・テラーぶりを堪能させてくれます。
Jerry Bergonzi

4曲目The Missed、こちらもBranfordのソプラノの魅力が発揮されたナンバーです。メロディの可憐さとニュアンス、美学と音色が合体し、心地よさと崇高さが同居した世界に案内してくれます。ここでのドラマーもPeter Erskine、どうやら彼はその巧みなカラーリングの才を買われてこれら2曲でプレイしているようです。
テーマ後Joeyのソロへ。ここでもピアノタッチの粒立ち、美しさが抜きん出ています。続いてソプラノの出番かと思いきやラストテーマへ、Branfordはアウトロで深い美意識を内包したソロを展開しています。
Branford Marsalis

5曲目Dome’s ModeはこちらもBergonziの登場が相応しいモーダル・チューンです。印象的なイントロに誘われてテーマへ、テナーとピアノのユニゾンのメロディは幅と奥行きを感じさせます。ソロの先発はJoey、タイム感とフレージングのセンスの良さに、否応なしに聴き惚れてしまいます!続くBergonziのソロ・アプローチには自己のスタイルの他、Joe Henderson, Steve Grossman, John Coltraneのプレイ〜フレージングを明らかに感じさせ、どこかテナー・オタク的センスを見出せるのですが、それはそれで親近感を覚えます(笑)。ラストテーマ後はJoeyが再登場、曲中ソロの続編とも言うべきプレイを聴かせFade Outの巻です。
Joey Calderazzo

6曲目Loud – ZeeはBergonziのオリジナル、プレーヤーがチョイスしたくなる名曲です。ボサノバ〜ラテンのリズムが心地よく、ここではパーカッションにDon Aliasが加わり、曲想とソロに色彩を施しています。Bergonziは流麗に世界を構築し、クライマックス時にはリズムセクションとのコラボレーションが聴かれます。続くJoeyは暫しBergonziテイストからのリフレッシュ化を行い、スローダウンしてから徐に世界を作ります。ラストテーマ後はBergonziのソロとなり、案の定のエグい盛り上がりを聴かせています。
Don Alias

7曲目Chubby’s LamentはピアノトリオにAliasが加わった編成によるスローナンバー、Joey作曲の才も映える佳曲です。Andersonのベースがファクターとなリ曲が進行し、ベースソロも聴かれます。Nussbaumの軽やかなリムショットも印象的です。
Adam Nussbaum

8曲目ラストを飾るナンバーPestは90年3月のMichael Brecker Quartet来日時にNervous Opusというタイトルで演奏されていました。この曲を演奏する際MichaelがJoeyに「新曲のタイトルは?」と尋ね、まだ決まっていなかったのでしょう「Nervous Opus!」と聴いてMichaelが「えっ?」と驚いていたのが印象的でした(笑)。
Nervous Opusもすごいタイトルでしたが、Pest(疫病のことではなく、手に負えない子供、厄介者の意味)とは自分の事を揶揄したのでしょうか(汗)。
こちらも1曲目同様に難易度が超高いナンバー、いかにもJoeyが作りそうな構築系のコンセプトを感じます。
テナーはプロデューサーMichael自身が担当し、熱くプレイしますがこちらも1曲目のBranfordと同じく「こうあらねばならぬ」を感じます。普段よりもMichael氏頑張り過ぎて力が入っているように聴こえ、BranfordやBergonziよりもずっ凄いテクニックでの圧倒的なプレイですが、何処か心ここに在らず、彼の演奏を徹底的にフォローしている僕にとってはちょっと辛いプレイです。個人的にはプロデューサーに徹し、ソロを取らずとも良かったのではと思います。
Michael Brecker

先日Joeyの2013年作品「Joey Calderazzo Trio Live」を入手しました。初リーダー作から22年を経て幾多のバンド、ギグを重ねた彼、やんちゃ坊主から成熟した大人のプレーヤーへの変貌ぶりを
目の当たりに出来る素晴らしいライブ作品です。やはりミュージシャンはどんどん変化して行くのです!!
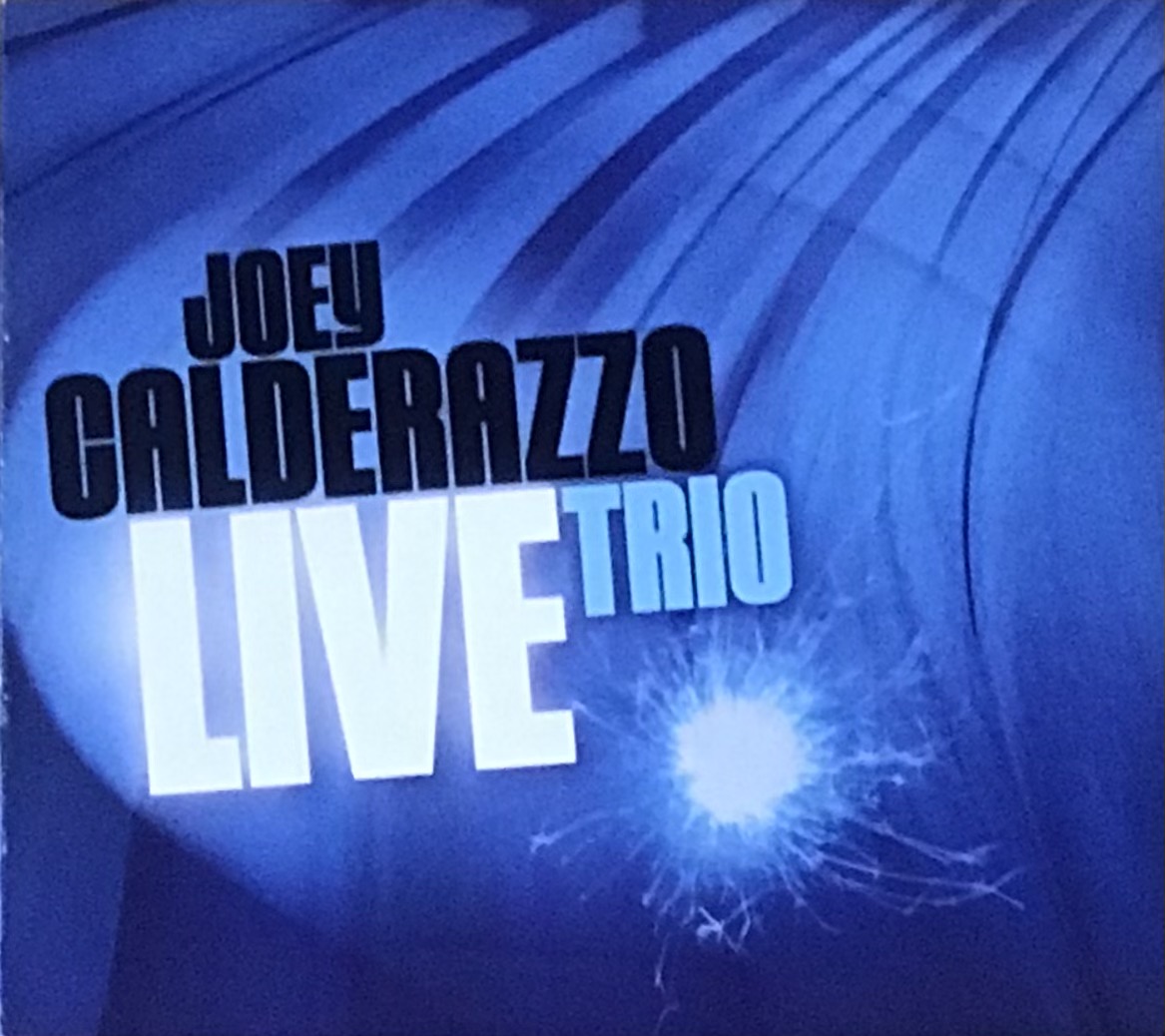
2021.05.30 Sun
今回はピアニストKenny Kirkland唯一のリーダー作91年リリース「Kenny Kirkland」を取り上げてみましょう。
Released: October 1, 1991
Studio: BMG Studios A & B, New York City
Producer: Delfeayo Marsalis, Kenny Kirkland
Executive Album Producer: Ricky Schultz
Label: GRP Records
p, key)Kenny Kirkland ts, ss)Branford Marsalis ds)Jeff “Tain” Watt(on 1~4, 6, 7, 9) ds)Steve Berrios(on 8, 10) perc)Don Alias(on 5, 8, 11) perc)Jerry Gonzales(on 8, 10) as)Roderick Ward b)Charnett Moffett(on 1, 4, 7) b)Andy Gonzalez(on 8, 10) b)Christian McBride(on 6) b) Robert Hurst(on 9)
1)Mr. J. C. 2)Midnight Silence 3)El Rey 4)Steepian Faith 5)Celia 6)Chance 7)When Will the Blues Leave 8)Ana Maria 9)Revalations 10)Criss Cross 11)Blasphemy

Kenny Kirklandの幅広く豊かな音楽性、魅力が詰まった素晴らしい作品です。
55年9月New York City, Brooklynで生まれた彼は6歳でピアノを始め、Manhattan School of Musicでクラシック・ピアノと音楽理論を学びました。その後僅か22歳でPoland出身の名バイオリニストMichael Urbaniakの欧州ツアーを経験し、東欧を代表するベーシストMiroslav VitousのECMアルバム79年「First Meeting」80年「Miroslav Vitous Group」にも参加します。この時既にソロ、バッキングで自己のスタイルを発揮しています。


美しくクリアーなピアノタッチ、Herbie Hancockをルーツとしていますが明確なオリジナリティを聴かせるスタイル、一聴彼と即断出来る8分音符のフィギュア、申し分のないタイム感、思わず引き込まれてしまう麻薬的魅力と言える独特の色気、そしてリーダーの音楽性に確実にブレンドし、変幻自在、柔軟にバックアップするサイドマンとしての資質が認められ、その後も数多くの優れたミュージシャンと共演を重ねます。
枚挙にいとまがありませんがざっと思い付く限り、Dizzy Gillespie, Terumasa Hino, Elvin Jones, Kenny Garrett, Sting, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Michael Brecker, Carla Bley, Hiram Bullock, Franco Ambosetti, Dave Liebman, John Scofield, Stone Alliance…いわゆる売れっ子ピアニスト、旬のアーティストとして最先端ミュージシャンのツアーに参加し、彼らの代表作と言える作品で優れた演奏を数多く残しています。個人的にお気に入りの作品を挙げておきましょう。
Stone Alliance / Live in Berlin(83年), Wynton Marsalis / Black Codes(85年), Sting / The Dream of the Blue Turtle(85年), Michael Brecker(87年), Branford Marsalis / Crazy People Music(90年), Kenny Garrett / Black Hope(92年)




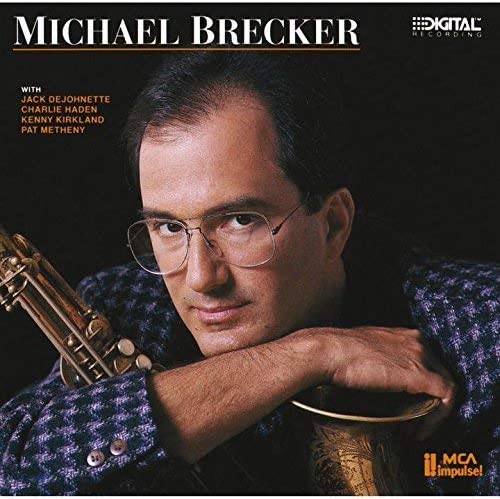


まさに将来を嘱望されていた音楽家ですが、残念なことに98年11月鬱血性心不全の発作を起こし、43歳の若さで帰らぬ人となります。直前まで変わらず元気に演奏活動を行なっており、青天の霹靂、発作の原因は諸説ありますが定かではありません。
Branford Marsalisのリーダー作98年録音「Requiem」は同年8月にKirklandほかベースEric Revis、ドラムJeff “Tain” Watts当時のレギュラー・カルテットで録音されました。すぐさま彼らはレコーディングされた楽曲を携えてツアーに出ましたが、直後の10月にKirklandが急逝、12月に残された3人で彼に捧げたナンバーElysian(理想郷、至上の幸福)をレコーディングしアルバムに追加して発表しました。

彼の演奏をこよなく愛していたリーダーたちは突然のKenny Kirklandロスにさぞかし呆然とした事でしょう。彼のプレイの素晴らしさ、One & Onlyなアプローチから、Kirklandの演奏が無ければ自分の音楽が成り立たないとまで考えたプレーヤーもいた事でしょう。しかしいつまでも悲しみに暮れている訳にはいきません。時間も音楽もどんどん前に進行して行きます。
彼の後釜探しはさぞかし難航したことでしょう。知る限りではMichael Brecker BandやBranford Marsalis QuartetにてJoey Calderazzoが紛失したパズルのピースを埋めるが如く適材適所で活躍し始めました。そしてBranfordのバンドにはその後不動のメンバーとして、Joeyが参加します。
そのJoeyですがKirklandと同じく91年に初リーダー作「In the Door」をリリースしています。作品プロデューサーは彼を「発掘」したMichael Brecker、クリニック演奏を行った先の大学で彼を見つけ、ピックアップしたと言っていました。Joeyをバックアップすべく1曲プレイも行なっていますが、他にもBranford, Jerry Bergonziと重量級テナーサックスをフロントに迎えて、コンテンポラリーな楽曲やアレンジされたスタンダードナンバーを演奏しています。
作品「Kenny Kirkland」ではBranfordがアルバムのメインボイスとして5曲プレイしており(1曲アルト奏者Roderick WardがOrnette Coleman役で参加していますが)、彼のテナー、ソプラノが作品のカラーのひとつを決定付けているように聴こえます。複数のテナー奏者の参加はアルバムにバラエティさを添えますが、サウンドの志向的にはフォーカス感は希薄になります。若くしての(25歳)デビュー作ですので本人の音楽性も然程定まっていなかったでしょう、色合いの多彩さを聴かせようと言うプロデューサーMichaelの采配だったと思います。
因みに本作のプロデューサーはBranfordの弟でMarsalis兄弟三男Delfeayo、兄Wyntonのアルバムもプロデュースするトロンボーン奏者でもあります。

87年4月14日Michaelが初リーダー作「Michael Brecker」をリリース(同年6月25日発売)する直前、場所は今はなき六本木Pit Inn、”Michael Brecker Special Session”と銘打ったコンサートで僕も生Kirklandの演奏に至近距離で触れることができました。ts, EWI)Michael Brecker, g)Mike Stern, p)Kenny Kirkland, el-b)Jeff Andrews, ds)Omar Hakim、素晴らしいメンバーによる来日公演でした!
何と言っても当夜はOmarが炸裂し絶好調、煽られたメンバー全員凄まじい演奏を繰り広げていました。例えばライブ1曲目はアルバム収録のNothing Personal、テナー、ギターソロと盛り上がりに盛り上がり二人の演奏に全てを持って行かれ、ステージには雑草も生えていないような荒涼としたツンドラ大地を感じましたが(汗)、しかしKirkland全く意に介さず、ひたすらマイペースにアプローチし、更なる山場作りを模索しつつストーリー性をしっかりと感じさせながらソロを巧みに構築して行き、煽り役のOmarを寧ろ扇動するプレイを展開、遂には六本木Pit Innのステージに青々とした樹々が生い茂った熱帯雨林のように見えたのを覚えています(爆)。
後日Michaelとその日の演奏について話をしました。本人かなり手応えがあったようでStern, Kirkland, Andrewsらの演奏を絶賛していましたが、Omarのドラミングが音量、音数的にもtoo muchで個人プレイに走り気味と話していました。そして何といっても女性にモテモテ(爆)だったのが気に入らなかったようで、「Omarは女の子にちょっかいを出し過ぎる」と嘆いていたのが印象的でした。単に羨ましかっただけなのかも知れませんね(笑)。
「Kenny Kirkland」は彼が36歳の時にリリースされました。収録全11曲中いずれもが高い音楽性を放つ自身のオリジナル6曲、他にBud Powell, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Thelonious Monkたちジャズジャイアンツのナンバーも素材として取り上げ、独自の解釈によるアレンジを十二分に施し、曲毎に編成を変え様々なカラーを持たせ、またシンセサイザーをサウンド付けに巧みに用いアコースティックと融合させ、自身の音楽として表現しています。
本作のレコーディング日程に関するディテールがクレジットされていないのは残念です。幾つかのセッションで成り立っているので複数日を費やした事でしょうが、Kenny Kirklandリーダー作プロジェクトとして他にもアイディアがきっとあった事でしょう。それは恐らく次作に持ち越されたのではないかと睨んでいますが、プレイヤーとしての資質に恵まれているのは当然として、ジャズジャイアンツのオリジナル選曲にどこか「いち」ジャズファンの匂いを感じさせるのです。実現しなかった2作目のリーダーアルバム、演奏内容は言うに及ばず、ジャズファンの心をくすぐる選曲の一枚になったのではないかと勝手に想像しています。
Kenny Kirkland

それでは演奏について触れて行く事にしましょう。1曲目アップテンポのナンバーMr. J.C.、ピアノ左手の印象的なパターンから始まるアグレッシブな楽曲、曲のフォームとしては基本的に倍の長さのマイナー・ブルース、前述のMichael BreckerオハコのNothing Personalと構成が被る部分もあります。
ところでJ.C.とは誰の事でしょうか。イニシャルから連想されるのはJohn Coltrane、そう言えば彼のアルバム「Giant Steps」収録のオリジナルCousin Maryのメロディとリズムのフィギュアが良く似ています。
Branfordの深いテナーサウンド、Jeff Wattsのタイトかつ超弩級ヘヴィーなドラミングとCharnett Moffettの極太でon topなbassが織りなすビートが相俟って、これは盛り上がらない訳がありません!
ソロの先発はKirkland、端正で音の粒立ちが半端ない8分音符、脱力感とスピード感、テンションが並走するプレイは聴き手をナチュラルにジャズの真善美へと誘い、豊かなリズムはスイングの極意を提示しているかのようです。
比較的クールに対処していたリズム隊ですがソロ半ばからはKirklandの知的でリズミックなラインにインスパイアされ、とうとうレスポンス炸裂、しかしもう少しイケそうなところ手前で、続くソロイストBranfordに華を持たせるべくソロを終えますが、この辺りも伴奏の達人ぶりを物語っていると思います。
Kirklandのタイム感が素晴らしいのもありますが、それにしてもベーシスト、ドラマー共にピアニストの提示するリズムのセンターの捉え方が実に確実で、その結果三者の織りなすスイング感は絶品です!
その後Branfordのテナーがパターンに乗って悠然と現れますが、まずこの音色の魅力にしてやられます!極太、ダークでダブルリップ奏法ならではの艶や付帯音の豊富さ、柔らかさとエッジのバランスがまるで化学的処理を施したかのような配合の絶妙さを感じさせ、テナーのトーンだけで既に十分に説得させられます。ピアノソロが構築したリズム、サウンドの世界に、更なるケミカル・リアクションを起こすべく同じベクトル方向を描く強力な因子を加わえたかのように、カルテット演奏が次のグレードに向かい始めているのが分かります。Kirklandのバッキングはテナーソロを俯瞰しつつ、決してtoo muchにならずほど良きスタンスを保ち、巧みな即断の合わせ技としての合流部分と放置箇所の選別、バックアップと自己主張の狭間を全くスムーズに往来します。
WattsのドラミングはサウンドとしてコンテンポラリーなElvin Jonesと評しても良いでしょうし、重厚なリズムとスピード感、繊細なカラーリング、レスポンスの良さは歴代ジャズドラマーの系譜に間違いなくノミネートされる事でしょう。Elvin~Tony Williams~Jack DeJohnette~Steve Gadd~Peter Erskine~Jeff “Tain” Watts!!Branfordとのコンビネーションの素晴らしさはここでも群を抜いています。ラストテーマ後のバンプ部分ではやはりとんでも無いことが行われていました。
Branford Marsalis

2曲目Midnight Silenceは彼のピアノとWatts, Branfordの3人で演奏が行われますが、ベースが鳴っているのでシンセベースをKirklandがオーバーダビングしたのでしょう、カルテット状態です。リリカルなピアノイントロに導かれシンセサイザーとシンバルが加わり、その後ソプラノサックスがソロを取りつつメロディを奏でます。シンセの音がホーンセクションやストリングスを聴かせ、サウンドに厚みを持たせています。その合間に聴かれるいかにも彼らしいピアノのバッキングやソロ、ここではコンパクトな楽曲に仕上げ、引き続きWattsの短いドラムソロをフィーチャーした3曲目El Reyへ。このドラムのフレージングはまさしくElvinスタイル!しかもこの上なくタイトな!それもそのはず、RayはElvinのミドルネーム、彼に捧げたテイクなのです!
そして組曲のように4曲目Steepian Faithに繋がります。シンセの織りなすラインがイントロとして演奏され、ソプラノがフィルインを入れつつピアノ共々テーマを演奏しますがアコースティック音とシンセサイザーのブレンド感が見事です!そのままピアノのソロへ、たっぷりしたタイムとレイドバック感がゴージャスさを引き出し、バックグラウンドに挿入されるシンセの音がジャジーなムードを高めます。その後はソプラノのソロへ、誰でもない、Branfordそのもののトーンが曲想に合致しています。SteepとはBranfordのニックネーム、こちらは彼に捧げられたナンバーなのでした。
Jeff “Tain” Watts

5曲目CeliaはBud Powellのナンバー、Don AliasとのDuoで演奏です。多重録音を駆使しAliasはパーカッション、シェイカー、コンガ、ボンゴ等を、Kirklandはピアノとシンセサイザー、ベースを重ねラテンジャズ・バンドの様相を呈していますが、何とタイトでグルーヴィーなリズムでしょう!思わず椅子から腰が浮き上がり、リズムに合わせて踊り出しそうになります!
Kirklandはスイングのリズム感も素晴らしいですが、ラテンミュージックに関してはマスターの称号を与えるべきではないでしょうか。シンセサイザーの使い方も巧みで楽しげにそして遊び感覚満載、効果的な音色やサウンド、こちらも一切の作為的な用い方のない、全てに必然性を感じさせるエフェクトです!
そしてAliasもラテンパーカッションのマエストロです!彼とは日野皓正さんの作品「Spark」で共演しましたが、気さくな人柄で、物静かな中に内に秘めた熱いスピリットを感じさせる、素晴らしいミュージシャンでした。
本テイクは粒立ちの良いプリプリとした音符によるリズムの洪水を、Powellのプリティなナンバーを素材に、ふたりのラテンプレーヤーが面白おかしく丁寧に音を重ねて作り上げた演奏と言えます。
Don Alias
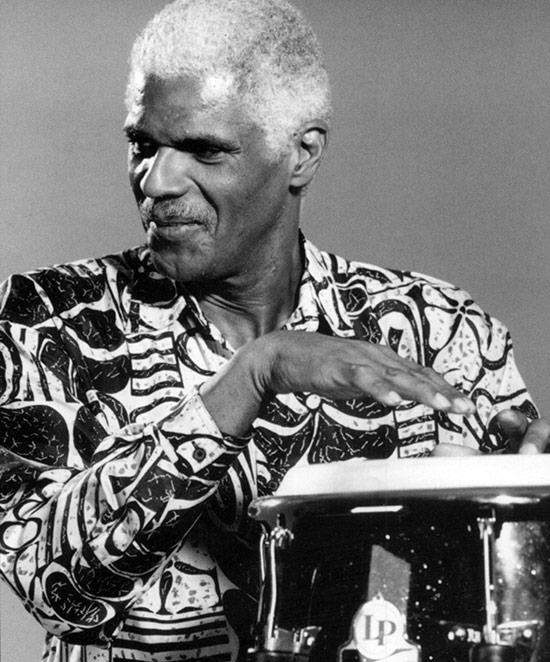
6曲目Chanceはミステリアスな雰囲気を湛えたワルツナンバー、ベーシストがChristian McBrideに交代します。
ピアノのリズミックなイントロに誘われ、曲が始まります。Wattsはブラシでリズムを刻みますがこちらでもElvinのテイストを感じます。Wattsがスティックに持ち換えたのにリンクするように演奏が熱気を帯び始めます。McBrideのベースワークは巧みで重厚、Wattsとのコンビネーションも申し分ありません。それにしてもKirklandのフレージングの長い事と言ったら!「息を呑む」とはこちらの事を指すのかも知れませんが、3連符、16分音符の洪水、緻密にして大胆、猛烈なテクニックと音楽理論の集大成的アプローチです!ベースやドラムのソロはなく、Kirklandの独壇場で演奏されており凝縮された彼のプレイが聴かれます。
Christian McBride

7曲目When Will the Blues LeaveはOrnette Colemanのブルース・ナンバー、この演奏は作品中異彩を放ちます。アルトのRoderick Wardは音色、フレージング、ソロのアプローチともOrnetteからの影響を強く感じさせますが、本演奏参加Charnettの父親Charles MoffettがOrnetteバンドのドラマーです。因みにChaernettの名前は父親のCharlesとOrnetteを合成させたものです。
ここでのWardはかなり健闘しており、Ornetteのサウンドを再現するのが目的なのであれば十分に成功していると思います。一方のKirklandは比較的オーソドックスなブレースプレイに終始しており、個人的にはもっとフリーフォームにまで突入して欲しかったところではあります。
Ornette Coleman Trioはピアノレス、コード感のない編成なので、オーソドックスなピアノ奏者が加わればこのような演奏になるという、デモンストレーションの様相を呈してはいます。
Charnett Moffett

8曲目Ana MariaはWayne Shoterのオリジナル、かの大名盤「Native Dancer」収録のナンバーです。オリジナル演奏に肖りBranfordのソプラノにShorter役を任命したのかと思いきや、Kirkland自身のピアノがフィーチャーされた極上のラテン・ジャズに変身しています。ベーシストAndy、パーカッションJerryのGonzales兄弟にドラマーSteve Berrios、ボンゴにAliasとメンバーが一新されています。
オリジナルよりも早いテンポが設定され、パーカッション、ボンゴの繰り出すビートが演奏の核となり、気持ちのこもったピアノソロが実に心地良く、どこまでも美しいこの名曲に新たな解釈を施した名演奏が誕生しました。
Native Dancer / Wayne Shorter

9曲目RevalationsはBranfordのソプラノをフィーチャーしたカルテットによる演奏、ベーシストがRobert Hurstに交代します。まずはソプラノの魅惑的音色に惹かれますがピアノソロが先発、ひたすらしっとりと抒情的に歌い上げ、Branfordもコンセプトを引き継ぎ美の世界を構築しますが、1曲目Mr. J. C.のアグレッシヴさから同一人物の演奏とは到底思えません。Hurstのベースが終始好サポートを聴かせています。
Robert Hurst

10曲目Thelonious Monkの名曲Criss Cross、Monkのオリジナル演奏は51年7月録音「Genius of Modern Music vol. 2」に収録されています。
実にユニークな楽曲、Monkならではのナンバー、僕自身彼の楽曲中フェイバリットな1曲です。オリジナルはミディアム・スイングでしたがここではCeliaと同じラテンの饗宴、ゴージャスにプレイされています!
Ana Mariaと同一メンバーによる演奏ですがAliasの代わりにBranfordがテナーで参加します。Celiaは多重録音を駆使してるとは言え二人で演奏したテイクでしたが、こちらは参加人数が多いので自ずとバンドのグルーヴはより深く、そしてリズムの奥行きがぐっと増します。
面白いもので、人間が奏でるリズムはその参加者数が多くなればなるほど密度や重厚感が対数的に増加して行きます。こちらは実に見事な総勢5人によるリズムのシンポジウムです!合奏感が半端ありません!
想像するにCeliaではクリック(メトロノーム)を用いてタイムを統一させていますが(全体的に限りなくデジタル的に正確ゆえ)、Criss Crossの方はテンポが結構速くなっていることからクリックを用いていません。こちらの方が人間の繰り出すビート感が合わさり、グルーヴし易くなるのです。
印象的なテーマ後Kirklandのピアノソロ、リズミックに快調に飛ばしつつもその後おもむろにモントゥノのリズムを弾き始め伴奏に回り、その上でシンセサイザーのビブラフォン・ライクな音色でソロを開始するのですが、興味深いトライアルです。オリジナル演奏にMilt Jacksonのビブラフォンソロがあるのでひょっとしたら敬意を表しているのかもしれません。
その後ラストテーマ終了してからBranfordが登場、ピアノの伴奏が抜け、しばらく後ベースも演奏を止め打楽器群を相手にブロウします。おそらく延々と続いたのでしょうが短く収められてFade Out、こちらも面白いアプローチです。
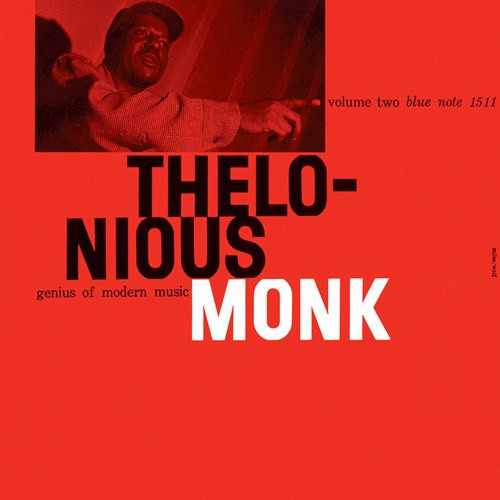
11曲目Blasphemyは再び多重録音を用いたKirklandとAliasのDuo、タイトルの意味は神・神聖な事物に対する冒涜。何やら意味慎重ですがこちらも作品中異色なナンバーです。陽気なはずのラテンのリズムが背徳的な匂いのするサウンドで満ちています。Kirklandはキーボードを駆使し様々な音色で色付けを行い、対してAliasはシンプルにリズムを刻み対応します。どこかWeather Report的なムードを感じさせますが作品のエピローグとして余韻を残し、to be continuedとしています。
2021.05.16 Sun
今回はKeith Jarrettの2009年ライブ録音「Somewhere」を取り上げてみましょう。
Recorded: July 11, 2009 at KKL Luzern Concert Hall, Lucerne(Switzerland)
Label: ECM Records [ECM 2200]
Producer: Manfred Eicher, Keith Jarrett
p)Keith Jarrett b)Gary Peacock ds)Jack DeJohnette
1)Deep Space/Solar 2)Stars Fell on Alabama 3)Between the Devil and the Deep Blue Sea 4)Somewhere/Everywhere 5)Tonight 6)I Thought About You

KeithのレギュラートリオStandards〜Gary Peacock, Jack DeJohnetteによる、21作目に該当する作品です。厳密に言えば同じメンバーでの録音第1作目、Peacock名義の77年2月録音の名作「Tales of Another」が存在するので計22作になりますが、いずれにせよこれだけ数多く作品をリリースしバンドを継続できるのはメンバーの音楽的一体感ゆえに違いありません。そして現時点でこのトリオが残した最新録音に該当するのですが、Peacockが昨年(20年)9月4日、85歳にして逝去したためにもはや同メンバーでの新作を望むことは出来ず、加えてKeithが18年に脳卒中を2回発症して麻痺状態となり、今でも左半身が部分的に麻痺してピアノ演奏に復帰できる可能性が低く、新しいベーシストを迎えて活動を再開することも難しい状況です。ですがおそらく全てのコンサートをアルバム・リリースを前提にプロデューサーManfred Eicherがライブレコーディングを行なっていて、スタジオ録音もかなりの数が残されていると想像出来、今後KeithあるいはEicherのプロデュースのもと、旧録音による新作が日の目を見ると思います。
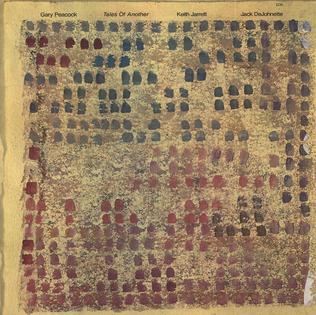
このトリオはTales of 〜が初顔合わせでしたが、KeithとJackはかのCharles Lloyd Quartetからの付き合い、66年にLloydがベーシストにCecil McBeeを加えNew Yorkでバンドを作りました。このバンドの作品66年ライブ録音「Forest Flower」が大ヒットを遂げたのは皆さんご存知の事と思います。リーダーの演奏も個性的ですがリズムセクション、特にKeithのピアノソロとJackのドラミングの素晴らしさが光ります。
相性が良いのでしょう、二人は71年5月Duoアルバム「Ruta and Daitya」を録音しています。ここでのエピソードがあるのでご紹介しましょう。
同年Miles DavisのグループはLos AngelesにあったジャズクラブShelly’s Manne Holeに出演しました。ちなみにクラブのオーナーは西海岸を代表するドラマー、Shelly Manneです。Manneはスインギーでオーソドックスなスタイルを信条とするプレーヤーだったので、当時のMilesバンドの出演には多少の違和感を覚えますが、話題沸騰のバンド人気には敵いません。
そうです、音楽的内容はエレクトリック真っ只中、アルバム「Miles Davis at Filmore」「Live Evil」の頃です。リズム自体は8ビートでハードロック的ではありますが、新しい音楽を作り上げて行く過程には必ず伴う音のカオス状態の中で、メンバーであったKeithとJackの二人はMilesの求めるサウンドにチャレンジしつつ、同時に自己のアイデンティティーも模索していた事でしょう。「Ruta and Daitya」の牧歌的な音楽はひょっとしたらMilesの音楽に対する反動、そして自分たちが表現したいサウンドのナチュラルな表出であったように聴こえます。Keithの牧歌的なアプローチはJan Garbarekを始めとする、いわゆるヨーロピアン・カルテットにて表現し続けています。
米国のライブハウスは通常1〜2週間のスパンで同一バンドが演奏しますが連夜の出演終了後でしょうか、彼らはHollywoodのスタジオSunset Sound Recordersの友人に誘われ、自由にスタジオを使用することを許され、クラブにあったドラム、パーカッション、エレクトリック・ピアノ、オルガンといった機材を持ち込み演奏し、作品として録音テープを作りました。この出来栄えに自信があったのでしょう、Keithは同年11月、以降親密な付き合いを現在まで40年以上保つECMレーベルへの初めてのレコーディング「Facing You」をOslo, Norwayにて、ソロピアノで行います。この時に彼がレーベルのプロデューサーManfred Eicherにテープを渡し、アルバムとしてリリースすべくミックスダウンを依頼します。レーベル作品発表には特別な拘りのあるEicher、音楽内容での対立からミュージシャンとの確執をも厭わない彼がリリースを快諾したのは、作品の内容から当然の成り行きでした。
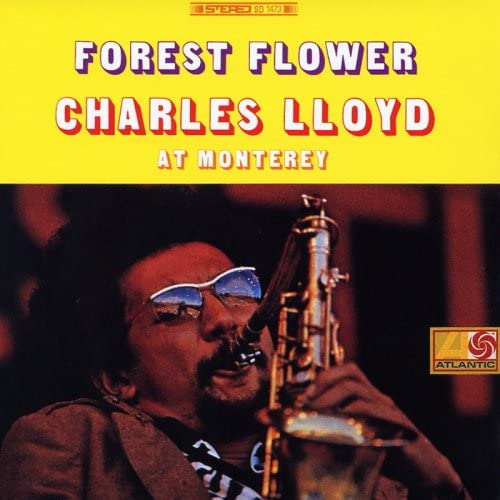




Milesバンド後の二人は自己のグループを組織し演奏を続けていましたが、再びEicherにより集合がかかり、Garyと共に83年1月、3作分のレコーディングをNYCにある名門スタジオPower Stationで行い、83年「Standards, Vol.1」84年「Changes」85年「Standards, Vol.2」と毎年立て続けに発表します。3人はオリジナリティな音楽性を持つ一国一城の主としてのミュージシャン、彼らがトラディショナルなピアノトリオというフォームでオーソドックスな、言ってみれば「懐かしさや懐古趣味、手垢にまみれたジャズ・スタンダード」を取り上げて正面から真にクリエイティヴに演奏し、作品を発表するというのはさぞかし意外な事だったでしょう、ジャズシーンはにわかに湧いた事と思います。名手たちならではの王道を行く共同作業、Standards Trioは80年代以降彼らの代表する活動となり、コンスタントにプレイを継続しました。
長きに渡り継続するバンド活動は、ミュージシャンが自発的に組織する場合が多いですが、レーベルのプロデューサーがオーガナイザーとなり、音楽を俯瞰しつつメンバーと共に作り上げて行く作業を20年以上も続けるのは珍しく、Eicherの堅牢な意思を感じます。
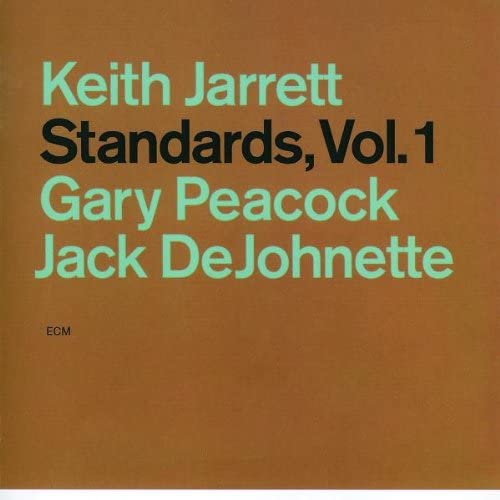


これらで聴かれる濃密な演奏は一聴Keithのピアノ演奏に耳を奪われ、Garyの闊達なサポートと寄り添い感、放置感にも納得させられますが、Jackのプレイが比較的大人しく、サポートに回ったように感じられますが寧ろ「叩けるけれど叩かない」凄みに圧倒されます。彼を筆頭とする真にクリエイティブなドラマーは、音数を多く叩くことやトリッキーなフレージングの連発に価値を見出してはいませんし、自分の演奏ばかりが目立つような個人プレーに走ることは決してありません。Keithのプレイに正面からレスポンスする事も勿論ありますが、全くフィルインを入れずにシンバルレガートだけでプレイを支えることが多々あります(そのシンバルレガート自体も誰にも真似の出来ないビート、スイング感、アタック、音色を有していますが)。それが結果的にメッセージやイメージの情報量が他の誰よりも膨大なKeithのプレイを確実に表出させるのです。彼の粘っこく奥行きのある8分音符、裏拍や弱拍のアクセント感、ある種理想のジャズに於ける「ノリ」を極めたプレイ、それらが1拍の長さが圧倒的なJackに全く持って比肩し、Keithの繰り出すインプロビゼーションのラインとJackのリズムキープだけで十分に音楽が成り立ってしまうように聴こえます。
音楽の三要素=リズム、メロディ、ハーモニー、これらが極論Keithの右手から繰り出されるラインと、同じくJackの右手によるシンバルレガートとの融合で完璧に成立しています。ここにおいてジャズの表現とは全ての音に必然が必要で、同時にストーリー性やウタが何より大切なのだと宣言しているかのようです。
ラストテーマの前に行われるピアノとドラムの8小節、4小節交換、ここでのKeithのフレージングも凄まじいですがJackのソロのありえない次元でのクリエイティブさ、スポンテニアスさには常に開いた口が塞がらないのです!

しかし蜜月がずっと続くことはありません。彼らは86年10月の来日公演を最後に一時休止した事がありますが、その後比較的間も無く再活動を遂げています。どんな名人達人でもマンネリに陥り、迷宮に入り込み出口を見いだせない状況に困窮することがあります。特に彼らの題材がスタンダード・ナンバーでは尚更のことです。オリジナルナンバーであれば如何様にでも色付け可能ですが、彼らは素材にアレンジを施す事は殆どなく、いわゆるリズムの仕掛けやコード進行の変更もまずありません。例えばエンディングで思いもよらぬバンプが用いられるのは予定調和ではなく、ごく自然発生的に演奏に至るのでしょう。調味料を極力使わず、素材の持つ味わいを最大限に引き出した自然食を提供するシェフのように、ひたすら正統派として正面からスタンダード・ナンバーに取り組む彼らです。
3人はディスカッションを繰り返しリーダーであるKeithの方向性の確認を幾度となく繰り返したように思います。
ひとつの私見としてですが、Keithの演奏するアドリブ・ライン、そして方法論について、いわゆるジャズ的なアプローチ、過去の先達のラインを踏襲したものも聴かれますが、それは結果としてであって、このトリオではごくシンプルに、頭に浮かんだメロディラインをそのまま演奏すると言う、インプロビゼーションの原点とも言える手法を念頭に置いていると思います。これはとても高度な音楽性とセンスが必要となり、楽器を弾きこなす確実なテクニックと強靭な精神も併せ持つ事が不可欠です。JackはKeithの意向を汲み、即興演奏という名の究極の作曲行為を鮮明にすべく、ピアノソロのバックでは必要不可欠な音しか演奏しないと決めているのかも知れません。
58年録音名ドラマーRoy Haynesのリーダー作でPhineas Newborn Jr., Paul Chambersを擁したピアノトリオ作品「We Three」、我々3人にしか出来ない演奏、音楽がここにあるという気概がタイトル、演奏内容から感じられますが、KeithのStandards一連の作品からはより強く芸術家の自己主張を感じるのです。
「行けるところまでとことん行こうじゃないか!」とまで宣言したかどうかは分かりませんが、軌道修正をしつつプレイをし続けることの重要性を高度な次元で捉えている彼ら、でも最も大切にしているのは演奏時に新鮮さを失わないナチュラルさであり、最先端のプレーヤーのみがなし得るルーティン化に対する打開策を模索し続けた結果なのでしょう。
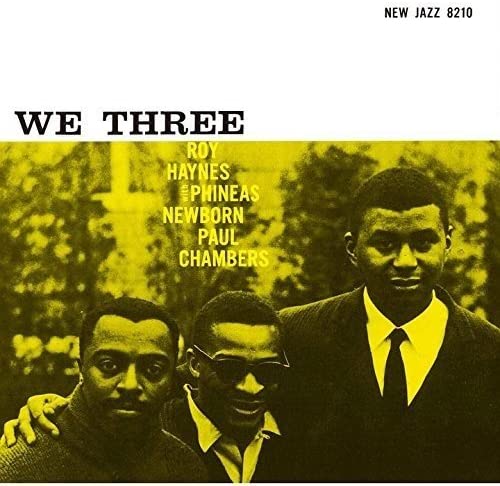
それでは収録曲について触れて行く事にしましょう。1曲Deep Space/Solar、メドレーのようなクレジットですがMilesのオリジナルSolarのイントロとして演奏されたソロピアノのパートに、曲名を付けたと思われます。美しくピアノを響かせ、幻想的でクラシカルな第一楽章と言えるパートの後、Solarのメロディラインを匂わせつつ第二楽章へ、その後左手と対旋律で徐にテーマを弾き始め、ベース、ドラムが加わります。ピアノのラインと交錯するようにベースソロがスタート、ベースが主体ではありますがピアノ、ドラムの合いの手は全く対等のようです。その後ピアノが主導権を握りソロを取り始めますが十分にスペースを取っているので二人が巧みにフィルを入れます。Keithのソロが次第に熱を帯び始め、前人未到の世界に突入し、恐らく2千人規模のコンサートホールの聴衆全員を崇高な美の世界に誘います。それにしてもフレーズの長さが半端ありません!聴いている方も合わせて無呼吸でいると息が詰まりそうになります!酸素ボンベを用意して鑑賞に臨むべきかも知れません(汗)。
例の唸り声の発生回数、声量も増し、入魂ぶりが伺えます。フレーズにユニゾンして唸り声を発する他に、ここでは演奏に対しての「同意」「納得」として発しているように聴こえます。
ちなみに他の演奏では「ため息」「掛け声」「声援」「感嘆」「悲鳴」「哀願」「失笑」「発見」「歓喜」「脅し」「落胆」「賞賛」「追憶」…としても聴こえ、彼のピアノ演奏同様に様々なニュアンスを表現しています(笑)。その後短くベースソロを挟み、エンディングへ。ラストテーマは荘厳にかつ短くメロディを演奏しFineです。

盛大なアプローズを受けピアノが徐にメロディを弾き始めます。2曲目Stars Fell on Alabama、オーディエンスはこの意外な選曲にさぞ驚いた事でしょう、しかし聴衆の歓声に敏感なKeithに対し礼儀正しくここではじっと発声せず固唾を飲み込んで聴き入っています。古き良き米国南部の雰囲気を湛えた美しいナンバー、Georgia on My Mindにも通じるテイストを感じますがこちらはAlabama州のお隣Georgiaの州歌にもなっています。Aメロをソロで弾き、2回目のAからベース、ドラムが参加し始めます。Keithも若かりし頃この曲を耳にしたでしょう、感性の書庫に仕舞い込んでいた楽曲の断片を引っ張り出して、イメージを最大限に膨らませて脱力と崇高な美の世界を以って表現しています。Garyの地を這うが如きラインがKeithのプレイを鮮明に浮かび上がらせ、Jackの全く無駄のない、音使いを厳選したかのようなブラシによるバッキングが演奏を引き締めています。シンコペーションを用いたメロディからベースソロへ、Keithのコンセプトを確実に受け継ぎ巧みに歌い上げ、ラストテーマへと続きます。いや〜聴き惚れてしまうほど素晴らしいです!

3曲目Between the Devil and the Deep Blue Sea、ミュージカル的な明るく華やかで、おしゃれなナンバーを取り上げました。50年代のNew YorkのBroadwayの街並みがイメージ出来そうですが、実はミュージカル・ナンバーではありません。31年にCab Callowayにより初レコーディングされたポピュラー・ソングです。
1コーラスをソロでピアノが演奏し、その後トリオでテーマを演奏します。この演奏もStandardsの真骨頂が見事に表現されています!テーマは2ビート・フィールで演奏され、ソロの1コーラス目は引き続き2ビート、ドラムは若干セカンドライン風に叩いています。その後スイング・フィールになり世界が開けた感じでグルーブして行きます。なんとゴージャスなタイム感、超安定走行を保ちつつ排気量の大きいアメ車で郊外を悠然とドライブするかの如き優雅さ、Keithも8分音符を中心に鼻歌を口ずさむかのように小粋なアドリブを展開、ジャジーなフレージングは用いられていますがテンションはあまり用いられず、ダイアトニックなインサイドの音使いが中心となり、前述の「頭に浮かんだメロディラインをそのまま演奏する」手法のショーケース、これは!物凄い音楽性です!
ソロの終盤戦ではスピード感溢れる3連符や16分音符の応酬がJackとなされますが、シンバルレガートを中心としながらKeithのラインに纏わりつくように叩いているプレイ、実に細やかなサポートの連続です!これは神経を集中させなければ聴き取ることが難しいかも知れません。
ソロが終わり聴衆の声援が聴かれますが、然もありなんとばかりの掛け声です。Garyのソロを挟んでJackとの8バースが始まりますが、いずれも玩具箱をひっくり返して次は一体何が飛び出て来るだろう、と実に楽しみなフレーズ&ポリリズム祭り状態です!Keithもインスパイアされ16分音符のエキサイティングなフレージングの嵐です!それにしても猛烈な音符の粒立ち!ピアノの筆頭マエストロです!ドラムソロ中にさりげなくテーマの断片を挿入する小粋さ!2コーラスを終え、その後ラストテーマへ。エンディングも曲想に合った可愛らしさを聴かせます。

4曲目Somewhere/Everywhere、Leonard BernsteinのナンバーSomewhereとそのエンディングが長く伸び、曲の様相を呈したEverywhereとのメドレー。曲のタイトル付けが素敵です。
BernsteinとKeithの透徹な音楽性は実に良くマッチしていると思います。数多くのジャズミュージシャンがBernsteinの楽曲を演奏していますが、演奏家の持つムードと解釈、表現力でKeithの右に出る者はいないでしょう。美しくも優雅、このサウンドにずっと浸っていたい気持ちになります。
いきなりメロディからスタートします。バラードですがJackはスティックで対応し、音量がごく控えめ、スティック先端のチップが小さめのものを使用しているかも知れません。テーマ後Garyのソロから、そのバックで奏でるKeithのメロディックなラインがSomewhereの裏メロディの如く、全く的確に響きます。その後ラストテーマ、そしてバンプが繰り返されこの部分がEverywhereに該当します。Keith十八番の牧歌的なアプローチで厳かに、祭儀的に演奏されます。延々と同じモチーフを辿りつつ、Jack, Garyは巧みに様々な表情を保ちながらプレイし、ディクレッシェンド、クレッシェンドを繰り返しFineとなります。これは感動的なテイクに仕上がりました!

続けて2曲Bernsteinのナンバーが聴けるのは至福の喜びです!5曲目Tonight、Somewhereと同じWest Side Storyからのナンバー、本作白眉の名演奏になります。イントロ無しでKeithのカウントに続き曲がスタート、天から舞い降りてくるメロディを恐山のいたこ状態で身体に受け入れ、ピアノフォルテの完璧な演奏者が脱力、鼻歌でプレイしますが、これはジャズというよりもジャンルを超えた純粋音楽の領域に達しています!!
ソロは右手のシングルノートを中心とし、左手のコードはあくまで最小限に、でもラインから聴こえるコード感は実に確実、これに申し分のないタイム感、グルーブ感が合わさり、さらにJackとGaryの完璧なサポートが加わり、ジャズ史上最強のスイングを聴かせています!
ソロが終わっても聴衆はあまりの素晴らしさに茫然自失、これは致し方ありません!全員しばし拍手や歓声をあげる事さえも忘れてしまいました!
その後ドラムソロが2コーラス行われますが、こちらもKeithのスピリットを踏まえた範疇の中で、タイムモジュレーションをさり気なく交えながら行われラストテーマへ。このモジュレーションをKeithが返礼としてでしょう、ラストテーマで採用していますが、Garyが術中にはまりリズム的に一瞬危うい場面もありました。実は危うい場面は始めのテーマにもあり、メロディが終わりピックアップソロのためのブレーク時、珍しくJackが2拍ほど溢れました。曲の小節数がもう4小節あると勘違いしたように感じますが「おっといけねえ!」とばかりに急停車、でも何事も無かったかのように演奏は継続して行きます。エンディングは比較的トラディショナルなリックを辿り、ハッピーエンドです!

6曲目I Thought About Youはアンコールで演奏されたのでしょう、コンサートの山場を終えた落ち着き、安堵感を感じる演奏です。こちらもイントロを演奏せずに徐にピアノがテーマを弾き始め、ベース、ドラムが加わります。美しいメロディを極上のセンスとピアノタッチ、ベースとドラムの見事なサポートで壮大な絵画を鑑賞するかのようです。テーマを前半演奏した後そのままピアノがソロを後半取ります。JackのシンバルによるKeithのソロと同期したカラーリングの妙、Garyが底辺を支える事で成立するサウンドの数々、3人だけがなし得ることの出来る世界のエピローグとして相応しい演奏に仕上がりました。
2021.05.03 Mon
今回はピアニスト、ボーカリストBen Sidranの78年ライブ録音リーダー作「Live at Montreux」を取り上げたいと思います。豪華メンバーを迎えた極上のライブパフォーマンスを聴くことが出来ます。
Recorded: July 23, 1978 at the Montreux Jazz Festival, Switzerland
Produced by Ben Sidran
Executive Producer: Steve Backer
p, vo)Ben Sidran ts)Michael Brecker tp)Randy Brecker g)Steve Khan vib)Mike Mainieri b)Tony Levin ds)Steve Jordan
1)Eat It 2)Song for a Sucker Like You 3)I Remember Clifford 4)Someday My Prince Will Come 5)Midnight Tango/Walking with the Blues 6)Come Together

シンガーソングライターやプロデューサーとしても活躍しているSidran、本作で聴かれるようなユニークなスタンスでのジャズやフュージョンへの取り組みを行なっています。
43年8月14日Chicago生まれの彼は学生時代Steve MillerやBoz Scaggsらとバンド活動を行い、大学卒業後に英文学の博士号を取得するべく英国名門Sussex大学に留学します。彼のニックネームDr. Jazzはそこで取得した博士号、そして音楽全般、特にJazzに対する造詣が深いことに由来して付けられました。
渡英の際にはEric Clapton, The Rolling Stones, Peter Frampton, Charlie Wattsらと既にセッションを行なっています。
その後米国に戻り、旧友Steve Millerのバンドにキーボード奏者、作曲者として参加し、多くのヒット作を手がけます。同時にMose Allison, Van Morrison, Rickie Lee Jones, Diana Rossらのアルバムをプロデュースします。
彼の主だった活躍はポップスのフィールドになりますが、米国のブラックミュージックや20世紀におけるユダヤ人のポピュラー音楽に対する貢献度を分析した著書(本人もユダヤ系米国人)、Miles DavisやArt Blakeyらを始めとするジャズのレジェンド達との会話を録音したCDを発表と、ジャズへのこだわりを感じさせつつ、多岐に渡ります。
どう答えたのかまでは覚えていないのですが、何かの本で読みました。Milesに「あなたの書いた名曲Nardisを逆から綴ると僕の名前のSidranになるのですが」のような事を質問したそうです。いや、むしろ彼の答えは決まっていますね、口癖であった「So What?(だからどうした?)」(笑)。
前作に該当する77年作品「The Doctor Is In」を紐解くと、本作に繋がる流れを垣間見ることが出来ます。ここでも本作のSong for a Sucker Like Youが収録されていますがメンバーが異なり、ストリングスも加わったことに起因する異なるグルーヴやテイストから、かなりポップな印象を受けます。
しかし以下のインスト演奏がアルバムのジャズ度や品位を高め、Sidranが単なるポップスのミュージシャンではないことを証明しています。まずHorace Silverのナンバー63年録音の名曲Silver’s Serenade、何とオリジナルでも演奏していたトランペッターBlue Mitchellを起用することで作品に敬意を表し、ドラムTony Williams、ベースRichard Davisという素晴らしいメンバーを迎え重厚でスインギー、躍動感あふれるグルーヴを聴かせ、本来スイングでの演奏をカラフルなラテンリズムを用いて躍動感を持たせ、ゴージャスなストリングスやパーカッションによるデコレーションを施しつつ、しかし曲の持つジャジーな雰囲気を損なうことなく、Sidran風のポップな味付けを加えることに成功しています。彼のバッキングやリズムアレンジも大きく功を奏していて、CTIのプロデューサーCreed Taylorライクなアレンジを想起させなくもありませんが、これはまた異なるテイストです。
次にCharles Mingusの名曲 、Lester Youngに捧げられたGood Bye Pork Pie Hatの演奏、自身のピアノをフィーチャーし、外連味なくジャズテイストを表現しています。ここでは同じドクターであるDr. Johnのピアノ演奏をイメージさせる部分もありますが、似た音楽的立ち位置ゆえなのかも知れません。
加えてCharlie’s BluesではSidran自身のボーカルをフィーチャーしつつ、ここでもT. Williams, R. Davisコンビを迎え、ジャジーで華やかな演奏を展開しています。


更に一作前、76年作品「Free in America」ではかのカリスマ・トランペッターWoody Shawを招き、何とBilly JoelのNew York State of Mindで間奏をプレイさせています!誰もが知るポップスの名曲にまさかのコアなジャズプレイヤーの起用、このセンスに敬服しました!

「Free in America」「The Doctor Is In」で表現した音楽のライブバージョン、そしてジャズメンとの共同作業が本作になります。それまでは米国西海岸のスタジオ系ミュージシャンを起用しての作品作り、ハイクオリティの「ジャズっぽいポップ・アルバム」を制作し続けたアーティストの、一つの纏めとしてのアルバムと言えましょう。
そしてこの流れの総決算が以前Blogで紹介した79年作品「The Cat and the Hat」、本作で共演のMike Mainieriをプロデューサーに迎え素晴らしい選曲、意外性も伴った考えうる最高のメンバー、コンパクトにして最大限に凝縮された演奏、緻密で大胆なアレンジ、さらにゴージャスな流れとしてのベクトル、音楽的方向性とも全く自然な展開を遂げた結果の大名盤。見事に結実しています。

Sidranは当時の所属レーベルAristaのアーティストとしてMontreux Jazz Festivalに出演しました。彼以外の本作メンバーにLarry Coryellを加え、Arista All Starsとして演奏された「Blue Montreux」「Blue Montreux Ⅱ」の2枚は当時のフュージョンシーンを代表する傑作として存在(君臨)し、またこの時の映像や音源がyoutubeを始めとするネットや海賊盤で多く流布しています。
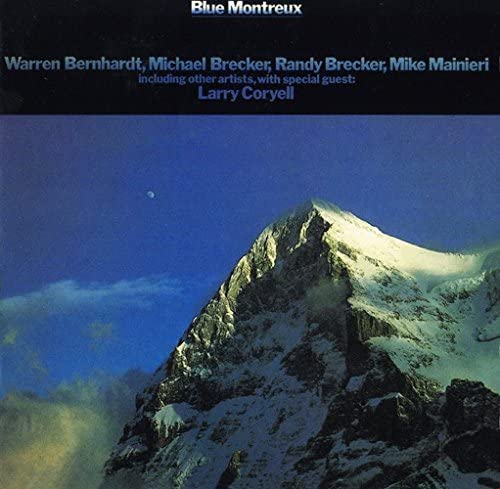

それでは演奏内容に触れて行きたいと思います。1曲目Eat ItはTony Williamsのために書かれたSidranの新曲、司会者の熱のこもった紹介からピアノのイントロが始まります。
この作品はライブレコーディングでありながら、ホールの残響等アンビエントの成分が少なく、スタジオで録音されたが如きドライさを聴かせ、耳に心地良い個々の楽器の音色、セパレーション、バランス感を有しています。
Steve Jordanのドラミング、音符が「丁度良い所」に位置するある種理想的なタイム感、的確なグルーブ、Tony Levinのタイトでユニークなラインを駆使したベースの素晴らしさにインパクトを覚えます。この時21歳(!)のJordanは以降The Rolling StonesやJohn Meyerのトリオで大活躍、Levinの方は本作直後にかの歴史的プログレッシブロック・バンド、King Crimson(!)に参加する事になり、Stick Bassを携えて大活躍、ふたりの優れたリズム隊の飛翔寸前を捉えた形になります。
Steve Khanのカッティングやフィルインが隠し味になり、Sidranのモントゥーノ(若干リズムが軽めですが)や随所に聴かれる倍テンポでのドラム、ベースの巧みさ、Mainieriのソロのスピード感、ライブで演奏されたとは思えないクオリティの連続です。エンディングは急停止したかのようにカットアウトでFineです。
Ben Sidran

Tony Levin with his stick bass
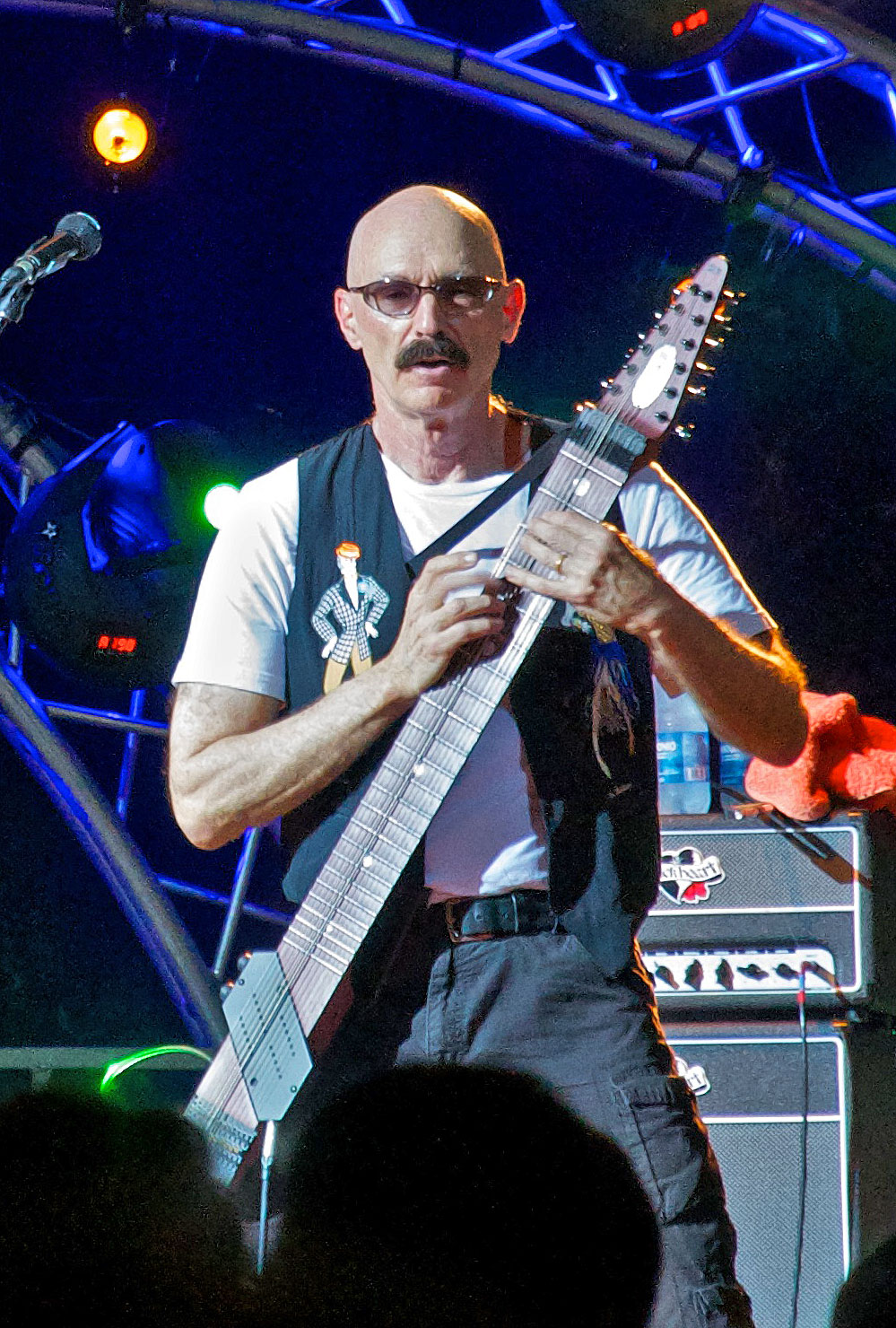
Steve Jordan

2曲目 Song for a Sucker Like You、Brecker兄弟のホーンアンサンブルが加わります。リズム隊のグルーヴ、Breckersの絶妙なセクションプレイ、オブリガード、そしてオーディエンスのアプローズも加わりオリジナルの演奏とは一線を画します。素材自体は優れた楽曲ですが調理の方法、スパイスの効かせ方で随分と印象が変わるという見本のような演奏です。
Michael & Randy Brecker

3曲目RandyとSidranのデュエットによるBenny Golsonの名曲I Remember Clifford、ごく普通に、特にキメやセクションを設けたわけではなく、Randyがこのような形でストレートにスタンダードナンバーを演奏するのは珍しいです。
彼はClifford Brown, Lee Morgan, Miles Davis, Freddie Hubbard, Woody Shawたちレジェンド・トランペッターの演奏を愛聴し研究していましたが、何かのインタビューで「CDショップで昔聴いていたトランペット奏者のアルバムを見つけると思わず買ってしまう」のような発言をしていました。とりわけトランペッター誰しもが敬愛してやまないBrownieへのトリビュート・ナンバー、思い入れがあって演奏出来たのでしょう、素晴らしいパフォーマンスを聴かせています。トランペットのcadenzaではジャズマンとしての真骨頂を披露しています。
Randy Brecker

4曲目は本作白眉の名演奏Someday My Prince Will Come、本来ワルツで演奏されるこの曲を大胆にも8ビートにアレンジ、これはSidranならではの粋な味付けです!
実はこの演奏には編集が施され、ソロを大胆にカットしてあります。まず先発Michaelのソロ、計4コーラス演奏しましたが後半2コーラスをカットし前半の2コーラス収録、続くSidranは2コーラス演奏の後半1コーラスをカットで1コーラス目のみ、続いてRandyとMainieriが3コーラスづつソロを取りましたがそれらは全てカットされています。テープ編集はあたかも手芸名人が織り成したかのようなパッチワークに仕上がり、つなぎ目の不自然さや拍手と歓声の唐突感は全くありません。
youtubeに編集前の完全な映像がアップされています。https://www.youtube.com/watch?v=R3zx5SwLIe4(クリックすると見られます)
短縮されたテイクの倍以上の長さ13分超を有す演奏時間です。
画質自体はあまり良くありませんが、演奏者の細かな動き、表情を十分見ることが出来、当時28歳、Michaelの勇姿がダントツに光ります。
それにしても収録された2コーラスのプレイはフレージングの流れ、ニュアンス、コード進行への巧みなアプローチ、ストーリー性と、この時点で完璧な演奏に仕上がっているのは間違いありません!この曲のキーは通常B♭メジャーですがここではMichaelの最もフェイバリット・キーであるFメジャー、これもソロの歌い方にファンキーさをもたらすポイントになっています。
3, 4コーラス目のソロも素晴らしいのですが1, 2コーラス目のクオリティとはかなり落差があります。以前にBlogで書いた内容と重複する部分もありますが、こう推測しました。Sidranのバンドはライブ録音を行うので演奏曲を予めリストアップしました。レコードの収録時間は最長でも45分程度、ライブではどうしても演奏時間が長くなります。ユニークな曲が多いバンドなのでなるべく曲数を多く入れたい、すると1曲の演奏時間は限られるので編集を施す事になりますが、当時はライブ録音でもごく普通にテープを切り貼りしていました。「Someday My Prince Will Comeは面白いアレンジなのでぜひ収録しよう。ついては演奏時間は6分程度なのでMichaelのソロは収録出来ても2コーラスかな」のようなやりとりがレコーディングのスタッフやディレクターとあったと思います。
Michaelお得意のギグに臨む際の情報収集=レコーディング前に演奏曲の概要〜コード進行、リズムのフィギュア、グルーヴ、演奏の長さ、共演者等を可能な限り把握しておき、ソロのコンセプトを煮詰め、ある程度のガイドラインを書いておく、ないしはしっかり書き上げておく。いわゆる予習に余念がなく、加えて演奏後に納得がいかなかった場合、徹底的に不十分だった点、出来なかった部分を復習し決して放置をすることはありません。
自分の持ち分2コーラスの中に粋で小洒落た、でも音楽的に高度な内容も織り込み、そしてなんといっても8分音符のレイドバック感をたっぷりと考えたのでしょう。この目論見は大成功!King Curtisを彷彿とさせるテキサステナー・サウンド、Coltrane的コード分解のテイスト、Dexter Gordonばりのリズムのノリ、それらがMichaelの中でメルティングポットとなり、彼独自のスタイルを表出させています。2コーラス目の終わりに少しスペースがあり、その後3コーラス目に入りますが、テープ編集の糊代を用意したようにも感じられます。彼だったらそこまでの配慮ができるプレーヤーです。実は実は、僕が深読みのし過ぎで、本人は全く考えないで演奏したのかも知れません、それはそれで78年真夏のスイス・レマン湖の畔で若きテナーサックス奏者の天才的な閃きが存在した証という事になるでしょう。カットされたRandy, Mainieriの演奏はもちろん悪かろうはずはありませんが、いかにもセッション的なプレイでMichaelの演奏との差を感じさせ、むしろ彼の凄さを際立たせています。
Michael Brecker

5曲目はSidranのオリジナルメドレー、Midnight Tango / Walking with the Blues。Midnight〜の方は74年4作目「Don’t Let Go」に、Walking〜は73年3作目「Puttin’ in Time on Planet Earth」に収録されています。ここでもMichaelのオブリが曲の品位をグッと高め、華やかで熱く都会的なソロが「ジャズっぽいポップス」を確実にジャズサウンドへと昇華させています。
Walking〜でSidranの歌うフレーズの一節をSteve Khanがユニゾンで演奏し、決め事ではなかったのでしょう、彼に受けている場面や、エンディングのソロでMichaelが珍しくOld Devil Moonのメロディを引用していたりと、和気藹々な雰囲気が漂っています。
July 22, 1978 (L to R) members of the band Air, Tony Levin, Steve Backer, Ben Sidran, Warren Bernhadt, Mike Mainieri, Steve Khan, Michael Brecker, Muhal Richard Abrams

6曲目はMainieriのヘッドアレンジが施されたJohn Lennonの名曲Come Together、Sidran自身の曲紹介に続き例のイントロが始まります。Breckersのホーンセクションの後、テナーのイケイケ、ゴリゴリのソロ、実際MichaelはJohn Lennonのバンドに参加し、アルバムも残しています。73年作品「Mind Games」、思い入れもあった事でしょう。

余談になりますが僕は81年4月にシンコーミュージックから「マイケル・ブレッカー完全コピー集」を出版しました。前年12月9日午後、おりしもAurex Jazz Festival ’80で来日中のマイケルにコピー集に掲載する記事のインタビューを行う事になり、雑誌社担当の方、通訳の方、僕とで宿泊先の東京プリンスホテルに集合しました。
挨拶もそこそこに担当者が開口一番「ジョン・レノンがニューヨークの自宅前で暗殺された」と話してくれました。今ではSNS等世界中の情報が瞬く間に個人の手元に届きますが40年以上前の話、どんなにショッキングなニュースでも流布するにはそれなりの時間を要します。音楽出版社ならではの情報網で迅速に収集したのでしょうが、The Beatlesフリークの僕には衝撃的でした。
暗殺されたのが米国東部標準時12月8日午後10:50、 インタビューが日本時間9日午後4:00からだったので事件から数時間後、全くの最新情報です。その時マイケルは知る由もなかったと思いますが、おそらくインタビュー当日の夜には情報を得てはいたのではないでしょうか。
この時彼がジョンのバンド在籍者とは残念ながら知りませんでした。当然インタビューにはこの話は持ち上がりませんでしたし、30分という短い所要時間、しかもコピー集のためのインタビューでしたから。
当時まだタバコを吸っていたマイケルは「ちょっと待って、タバコを買ってくるから」と中座し自販機でマイルドセブンだったかセブンスターを購入、戻ってから火を付ける前に「インタビューの時間はどのくらい?」と尋ねました。「30分です」と僕が答えると、わざとタバコの箱を机に落とし、そんなに短いんだ、とばかりに戯けましたが、お茶目な彼に触れられた最初の仕草です。
もしかインタビュー時にジョンの死が話題に上がっていたら、彼は一体どんなことを話してくれただろう、そして纏わる思い出話は尽きなかったのでは、と思います。
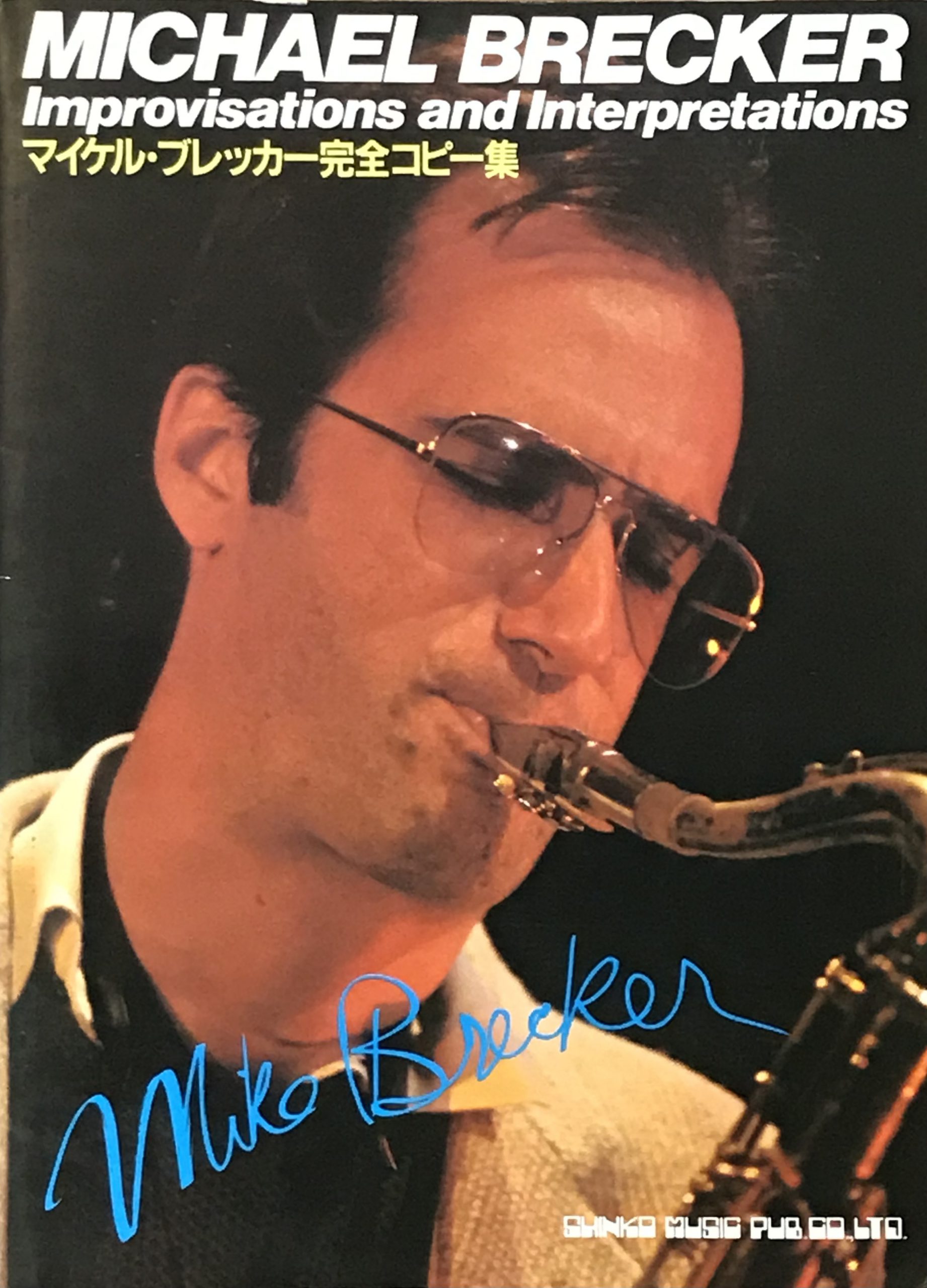
2021.04.19 Mon
今回はDavid Liebman, Wayne Shorterふたりのサックス奏者をフィーチャーしたコンサート=1987年開催されたLive Under the Sky ’87のプログラムをライブレコーディングした作品「Tribute to John Coltrane」を取り上げたいと思います。
Recorded: 26th of July, 1987 at Yomiuri Land East
ss)David Liebman ss)Wayne Shorter p)Richie Beirach b)Eddie Gomez ds)Jack DeJohnette
1)Mr. P.C. 2)After the Rain / Naima 3)India / Impressions

John Coltrane没後20年、そして当時日本Jazz夏の風物詩となったLive Under the Sky 10周年に企画されたコンサート、豪華メンバーが集まりColtraneのオリジナルを演奏しました。節目の年に偉大なミュージシャンへのトリビュート・コンサート、しかも夏の屋外フェスティバルともなれば出演者も聴衆も否応なしにテンションが上がると言うもの。プレーヤーはオーディエンスの熱狂的なアプローズを受け歴史に残る名演を残しました。
Coltrane研究家であり、自身の音楽的ルーツを彼に持つDavid Liebmanが核となった形で盟友Richie Beirachをピアニストに迎え、Live Under the Skyに当日出演したWayne Shorter(自己のグループ)、同じくSteve GaddのグループThe Gadd Gangで出演のEddie Gomez、Jack DeJohnette’s Special Editionで出演のJack DeJohnetteをメンバーにバンドが組まれました。
プログラムの売りとしてはLiebmanとShorterのツー・ソプラノサックス、一体どんなコラボレーションやバトルを聴かせてくれるのだろうか、音楽仲間とは前評判で持ちきり、高鳴る胸の鼓動を感じながら僕もよみうりランドに足を運びました。
当日はMiles Davis GroupでKenny Garret、The Gadd GangでRonnie Cubar、Jack DeJohnette’s Special EditionでGreg Osby, Gary Thomas、World Saxophone QuartetでHamiet Bluiett, Julius Hemphill, Oliver Lake, David Murrayと、弩級サックス奏者大集合による真夏の祭典でもありました。
同年9月にHerbie Hancock Quartetのメンバーで来日したMichael Breckerと話をしていると「そのプログラムは僕にも出演依頼があったけど、スケジュールが入っていてNGだったんだ」との事。彼のChronogicを紐解くと自身のバンドで欧州ツアーが入っていました。彼もColtrane派テナー奏者筆頭のひとり、オファーがあって然るべきです。ファンとしてはMichaelがLiebman, Shorterどちらの代わりだったのか興味を惹かれれるところ、もしかしたら彼のバンドでの出演依頼もあったのかも知れません。また本作でのサックス奏者の組み合わせも素晴らしいですが、コンビとしてMichael〜Liebman、Michael〜Shorterの可能性もあった訳で、どう転んでも物凄い組み合わせには違いないのですが、Coltrane Tributeとしてのサウンド、コンセプトに大きな違いが現れそうです。
「もしかこうであったならば…」と考えると物事キリがないのですが、この組み合わせに関しては想像を巡らせない訳には行きません(笑)!!
Michael〜Liebmanの組み合わせはユダヤ系サックス奏者組、知的で構築的な、論理が支配するハイパーな、そして情念が見え隠れする場面が表出する物凄い演奏になること間違いなし!
このふたりのオフィシャルなツーテナー演奏は残されていませんが、実は80年12月六本木Pit InnでのStepsのライブに日野皓正バンドで来日中であったLiebmanがなんとシットイン!あろう事かMichaelのオリジナルNot Ethiopiaでバトルを繰り広げました!方法論、アプローチや音色の違い、高次元でのやり取り、一音たりとも聴き逃すわけには行きませんでした!案の定佳境に達した場面では「バヒョバヒョ、ボギャー、グワー、ギョエギョエ〜」とフリークトーン祭り(汗)、60年初頭からのColtraneの足跡を辿りながら、65年以降のFreeに突入したスタイルで締め括るというストーリーです。
この演奏はライブレコーディング「Smokin’ in the Pit」の未発表テイクに必ずや残されているはず。近年大活躍の発掘王Zev Feldmanの手により、発掘される事を願ってやみません!
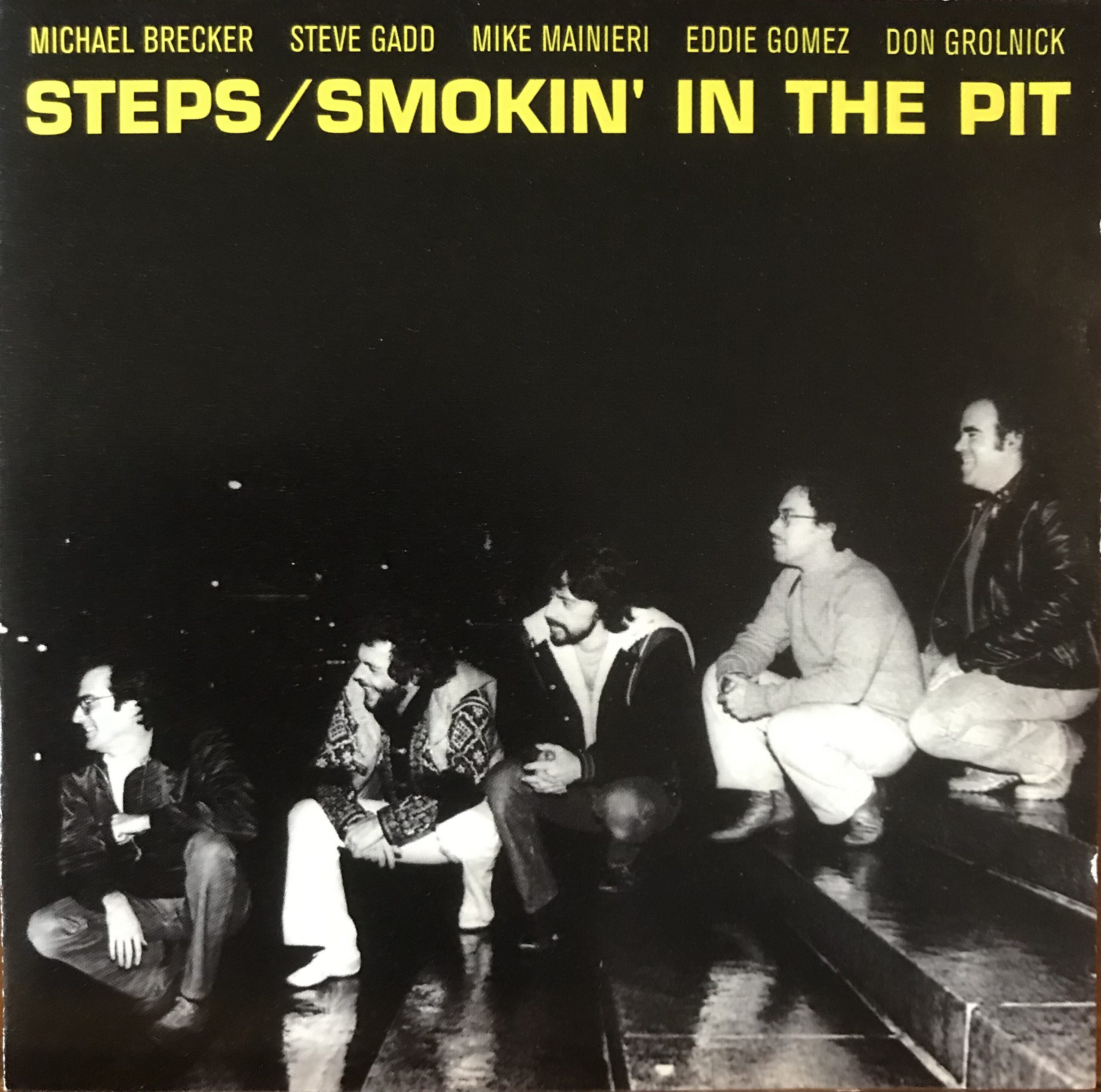
もう一つ、Shorter〜Michaelのサックスバトル、これはJaco Pastoriusの作品「Word of Mouth」の1曲目Crisisで既に行われているのですが、こちらは実際にその場で演奏した訳ではなく、ソロイストがお互いの音を聴かずにJacoのベーシックなトラックだけを聴いて演奏し、ミキシング時にプロデューサーであるJacoが任意に各人のフレーズをチョイスし出し入れさせ、コラージュのように重ねた演奏です。結果的にバトルのように聴こえるだけで純然とした共演ではありません。
このふたりに関しては横綱相撲的な大取組になること請け合いです!大変な盛り上がりを見せながらも互いを尊重しつつ、決して個人プレーは行わず相手の出方を見ながら、しかし常にマイペースのShorterを前にしてMichaelは彼流のアプローチの中でもしかしたら手玉に取られるかも知れません?

テナーの大御所ふたりによる演奏、ColtraneとStan Getzが60年JATPで渡欧した際にドイツで収録された映像も間違いなく横綱相撲です。Miles Davis Quintetリーダー抜きでColtraneをフィーチャーした編成にGetzが加わりバラード・メドレー、そしてThelonious MonkのナンバーHackensackではバトルを繰り広げています!
穏やかな雰囲気の中で柔和な眼差しを向けながら、互いのプレイを尊重しつつの取り組み(笑)、異国の地での偶発的な演奏であったかも知れませんが、後にジャズシーンを牽引する両巨頭のモニュメント的な共演です。
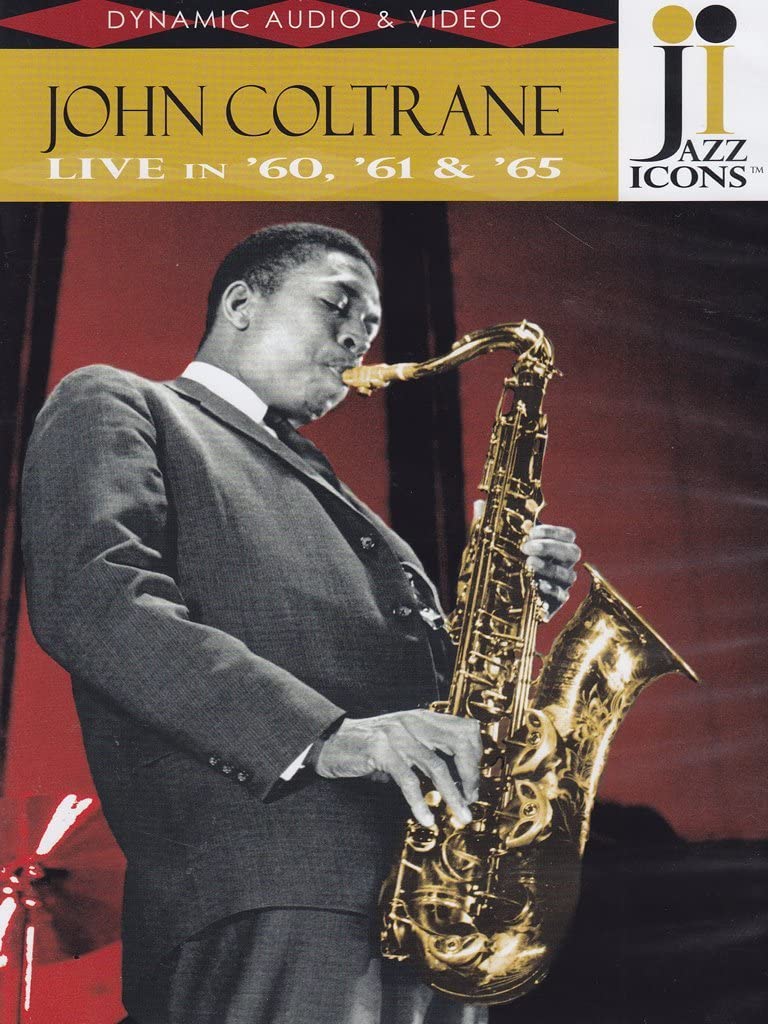
リズムセクションに関して、Beirach, Gomez, DeJohnetteのトリオは本演奏が初顔合わせになりますが、Gomez, DeJohnetteのふたりは68年Bill Evans Trio「At The Montreux Jazz Festival」での名演が燦然と輝いており、近年クオリティに遜色のないスタジオやプライヴェート録音が続々と発掘され、僅か6ヶ月間の存続期間でしたがさらにトリオの演奏価値が高まりつつあります。
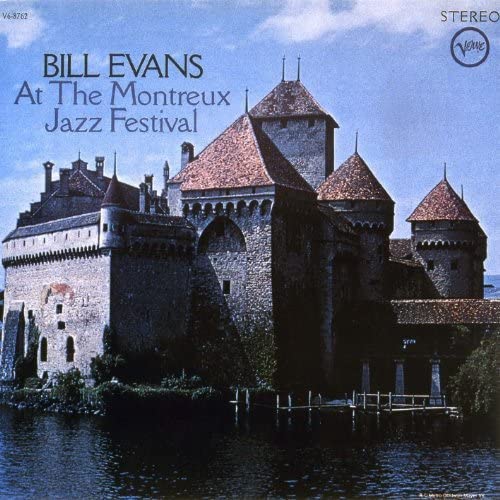




もう1作、以前Blogで取り上げたピアニスト、ボーカリストTom Lellisの89年録音作品「Double Entendre」ではGomez, DeJohnetteふたりの、また違ったアプローチでの素晴らしいコンビネーションを堪能する事が出来ます。

Beirach, DeJohnetteの共演は79年録音「Elm」、全曲BeirachのオリジナルをGeorge Mrazと共に演奏した名盤、Beirachの代表作として彼の魅力を余す事なく表現しています。

Liebmanは本作と同じ87年1月に「Homage to John Coltrane」を録音、同年リリースされています。レコードのSide AがGomezを起用したアコースティック・サイド、Side BがMark Eganのエレクトリックベースをフィーチャーしたエレクトリック・サイド、本作収録のAfter the Rain, IndiaほかColtraneのオリジナルを演奏しています。
このアルバムの存在が契機となり、本コンサートのプログラムが組まれたのでは、と睨んでいます。

それでは演奏内容に触れて行く事にしましょう。1曲目はお馴染みMr. P.C. 、59年録音Coltraneの代表作にして名盤「Giant Steps」に収録されているマイナー・ブルース。Miles Davis Quintet時代からの盟友である名ベーシストPaul Chambersに捧げられたナンバー、皆さんよくご存知の事だと思います。作曲者自身その後もバンドのレパートリーとして頻繁に取り上げました。
Liebmanのカウントに続き曲がスタート、「お〜待ってたよ、期待していたぜ!」とばかりにワクワク感満載のオーディエンスの、数万人規模での響めきに近い歓声が聴こえます。オープニングに相応しくテンポもColtraneの演奏が♩=250、こちらはそれよりも速い♩=280に設定されています。

寸分の隙も無いとはこの演奏のためにある言葉なのでしょう、プレーヤー5人の発する音全てが終始有機的に絡み合い、アイデアを提供しつつ互いにインスパイアされ、相乗効果のショーケースと思しきインタープレイの数々です!
テーマに続きLiebmanが先発ソロ、エッジの効いた鋭角的なサウンド、主たるトーナリティの他に全く別のスケールが織り込まれたかの如き異彩を放つアドリブ・ライン、ここではグロートーンやオルタネート・フィンガリングも交え、シャウトし、耳に痛いまでに(汗)届くプレイを聴かせます。この頃の彼の楽器セッティング、マウスピースがDave Guardala Dave Liebman Model、リードはBariプラスティック・リード、本体はCouf(Keilwerthの米国向けモデル)。テナーサックスを封印してソプラノに専念していた時期です。
リズム隊について、まずGomezのベースが絶妙なOn Topに位置し、これまたエッジーなDeJohnetteのシンバルレガートと素晴らしい一体感を聴かせます!そして拍の長さが圧倒的に長いDeJohnetteのドラミングがバンドのリズムの奥行き感を深めています。コンビネーション抜群のふたりに加え、管楽器に対するバッキングの天才Beirachが美しくもダイナミックなピアノタッチを駆使し、実に楽しげにまで自由な発想で、枯渇することのない砂漠のオアシスの如く迸るアイデアを提供し、ソロイスト、メンバーを鼓舞します。別の言い方をすれば茶々入れ名人、お囃しの達人でしょうか(笑)?
Liebmanの最後のフレーズを受けつつ続くShorterのソロ、これは一体どう表現したら良いのでしょう?まず音色が相方とは全く異なります。使用楽器、マウスピースがOtto Link Slant 10番、リードはRicoでしょうか。本体はYAMAHAセミカーブドネックSilver Plated。ラバーのマウスピース使用なのでよりウッディではありますが、音の太さと艶、コク感が尋常ではありません!Liebmanのテナーサックス封印とは異なり、この時Shorterはテナーも自分のヴォイスとして普通に用いていました。今回ソプラノに専念したのは自身の発案か、主催者やLiebmanに要望されたのかは分かりませんが、対比という観点からソプラノ2管編成は結果としてふたりの演奏をフォーカス出来たと思います。
フレージングに関して、ジャズ的なアプローチの範疇に入っているようで実は枠外では?とも十分に感じさせ、奏法的には”もつれている”かのような独特なタンギング、かと思えばシングルタンギングの連続、フリーキーでアグレッシヴなライン、フラジオ音、小鳥の囀りの如き発音、いきなり小唄のようなメロディ奏、常人では考えられない展開の連続は真の天才の降臨でしょう!
この猛烈な演奏の伴奏担当リズム陣、凄まじいまでの瞬発力の連続、間違いなく3人とも全く何も考えずその場で鳴った音を受け(反射神経と手足が直結しています!)、インスピレーションを頼りにサポートしていますが、その確実性と高い音楽性はあり得ない次元です!
特にBeirachの、とんでもない事象を目の当たりにしても、尚且つ悠然とカウンターメロディを入れられる大胆さには鳥肌が立ちます!
Shorterのソロはまるでおもちゃ箱をひっくり返したような、どんな玩具が飛び出して来るか分からない意外性を持った展開ですが、一応彼なりの起承転結と次のソロイストに受け渡すための手筈の用意はされていました。続くBeirachのソロにはそのためスムーズに移行し、Shorterソロの余韻を残しつつ、真っ白なキャンバスに絵を描き始めるべく体制の立て直しを図り、そして徐に演奏開始です。
フロント陣の猛烈な演奏の後にも関わらず、Beirachは更なる強烈な展開をベース、ドラムを巻き込んで、リズム隊3人組んず解れつをとことん聴かせます!GomezもDeJohnetteも仕掛ける、受けて立つのアプローチを繰り返し、真夏のよみうりランド上空には激しい雷鳴が轟きそうな勢いです!いや、既に演奏自体が雷鳴でしたね!(爆)
ここまで奇想天外にイキまくっている演奏を聴くと、お囃子の達人は鳴物師であると同時に主たる芸能の達人でもあると再認識しました(笑)!まさしく三位一体の演奏なのですが、あまりにも各々が素晴らしいので出来れば一人ひとりのプレイを個別に聴きたい気持ちです(笑)。
密度の濃い演奏では時間の経過は加速します。ピアノソロ後ラストテーマへ、えっ?もう終わりですか?もっと聴きたいんですけど(涙)。Coltrane Tribute Concertのオープニングは歴史的な名演で開始されました。
聴衆の大歓声の後にLiebmanによるMCが始まります。Coltraneに対する思いを込めた内容をカタコトの日本語を交え(サービス精神旺盛です)、熱く語り、そしてデュオを開始すべくBeirachに促します。
David Liebman

2曲目はAfter the RainとNaimaのメドレー。After the Rainは「Impressions」に収録され、ここではドラマーがElvin JonesからRoy Haynesに交代しています。

Naimaは前出の「Giant Steps」で初演され、こちらも自身の重要なレパートリーとして生涯演奏されました。
本作での演奏は長年デュオ活動を継続しているふたりの絶妙なコンビネーションを聴くことが出来ます。冒頭にはピアノの弦を直接指で弾く効果音的奏法を聴かせ、Liebmanもフリーキーな音色で呼応しデュオの雰囲気を高めています。
ピアノのイントロに続き美しいメロディが始まります。ルパートを基本にゆったりと揺らめくように、アグレッシヴなトリルも交えながらテーマを演奏しています。コンパクトにプレイをまとめ、Beirachのリズミカルで豊かな響きのイントロに導かれてNaimaが始まります。彼等の演奏は85年録音「Double Edge」でも聴くことが出来ます。

こちらの演奏はスタジオ録音ということもありリリカルで落ち着いた雰囲気、本作の演奏は臨場感あふれるライブならではの内容です。本来バラードであったNaimaをボサノバやEven 8thのリズムで演奏するようになったのは、Cedar Waltonのトリオ作品73年1月録音「A Night at Boomers, vol.2」収録の演奏からではないでしょうか。

Waltonは75年12月録音「Eastern Rebellion」でGeorge Colemanをフロントに迎え、カルテットでも演奏しています。
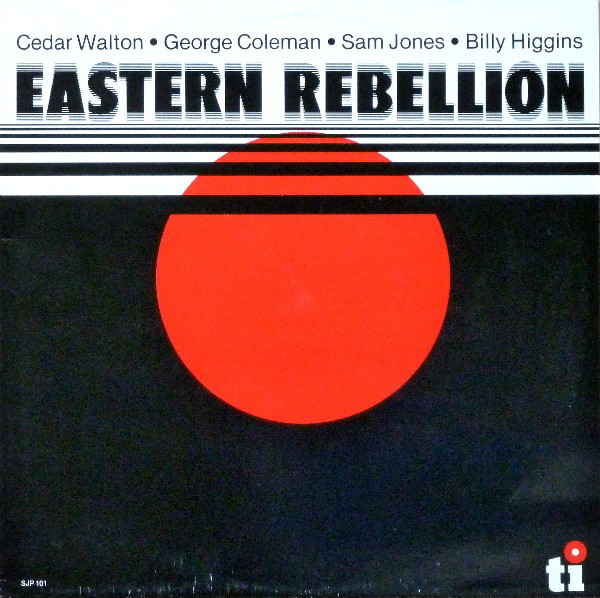
ここでのソプラノサックスの音色には「シュワー」という音の成分(付帯音)が聴こえます。ドラムのシンバルと被る成分が多いのでバンド演奏では消えがちな付帯音ですが、デュオならではの良さ、音色に豊かさが増します。
ふたりの絶妙なコラボレーションにより音量のダイナミクス、互いのフィルインやフレージングの駆け引き、Liebmanのラインに対するBeirachの反応、放置、またピアノのサウンド付け、コードワークに対するLiebmanの対応のバリエーションの豊かさ、ナチュラルさ、全てがあり得ない次元で昇華しています!オーディエンスの掛け声にも感極まった感が聴き取れます。そして続くBeirachのソロの何と素晴らしいこと!崇高な美学に基づいたリハーモナイズの妙、いみじくもLiebmanが名付けたBeirachのニックネーム”The Code”、面目躍如の異次元コードワークの連続です!音楽的にも超高度な世界、しかも美しいピアノタッチで!これは堪りません!ラストテーマも意外性に富んだアプローチを聴くことが出来ます。
Richie Beirach

LiebmanのBeirachと自身の紹介、そしてShorter, DeJohnette, Gomezの名を呼びあげステージに戻るように促しています。
Wayne Shorter

3曲目はIndiaとImpressionsのメドレー、これら2曲も前述の「Impressions」に収録されています。Gomezの深い音色によるベースソロから始まリ、重音やハーモニクス奏法等様々なアプローチを用いますが、恐らくColtraneが演奏したバラードをモチーフに、と言う主題を自身で掲げメロディの断片を交えながらソロをプレイし、My One and Only Loveを聴き取ることが出来ます。
その後スラップのような奏法を披露しソロ終了と同時にドラムがリズムを刻み始め、イントロ開始です。スペースの多い曲なのでソプラノふたりが互いを聴きながら、被ることなくフィルインを入れますが、内容的には各々我が道を歩んでいます。
ソロの先発はShorter、素晴らしくインパクトのある音色でMr. P.C.以上にアグレッシヴなフレーズを繰り出しますが、時折聴かれる小唄的メロディに安堵感を覚えます。リズム隊のバッキングのアイデアは尽きるところを知らず、Shorterを徹底的にサポートしますが、Gomezのアプローチには敬服してしまいます!
Eddie Gomez

リフが入りBeirachのソロへ、案の定無尽蔵に溢れ出るアイデアが聴衆を別世界へと誘います。ここではDeJohnetteが率先してBeirachの後見人とも取れるアプローチを見せており、ソロイスト毎に役割分担を行っているかのようです。まだまだ続けられるにも関わらずBeirach余力を残しLiebmanのソロへと繋げます。初めからこめかみの血管が切れそうなテンションでのプレイ、フリージャズに突入したかのようです!バッキングを止め、暫し音無しの構えを見せていたBeirach、Liebmanのアグレッシヴなフレージングの合間にとんでもないラインを弾き始めたじゃありませんか!まさしく長年連れ添った(笑)このふたりにしかあり得ない阿吽の呼吸です!このバッキングで更に火のついたLiebman、悶絶しそうな勢いですが、プレイに決して乱れを見せず正確なタイム感をキープしています。
その後ラストテーマ、実にゆっくりとリタルダンドしてドラムソロへと繋げています。激しくも音楽的なフレーズを繰り出し、Elvin Jonesスタイルを彷彿させながらテンポをアッチェルさせImpressionsに繋がります。
テーマをLiebmanが吹き、Shorterはオブリガードを演奏します。ソロはShorterから、一触即発でDeJohnetteが反応します。このふたりは60年代後期のMiles Davis Quintetで同じ釜の飯を食べた仲、久しぶりの共演かもしれませんがそこは昔取った杵柄です。
続くBeirachは端正にして凛々しく、正面を見据えてひたすらスイングする事に全身全霊を傾けているかの如きプレイ、実にカッコいいです!そこにLiebmanが怪しげに斬り込んできました。リズム隊は新たなカンフル剤を注射されたかの如く、活性化して行きますが、Beirachがバッキングを止め、Coltrane Quartetでテナーソロが佳境に入った時の、ピアノの椅子に座り続けるだけのMcCoy Tyner状態です!
その後再びドラムソロに移行しそうになりますが、DeJohnette本人は再度のソロを望まないであろうし、何より演奏時間が長くなると判断したBeirachが(メンバーには1時間で収めて欲しいと主催者側からオファーがあったのでしょう)パターンを弾き、ラストテーマに持っていきます。激しいエンディングを伴い歴史的コンサートは大団円を迎えます。
Jack DeJohnette

2021.04.06 Tue
今回はギタリストRyo Kawasakiの78年録音リーダー作「Nature’s Revenge」を取り上げてみましょう。
Recorded at Tonstudio Zuckerfabrik, Stuttgart, Germany, February/March 1978
Engineer: Gibbs Platen
Producer: Joachim-Ernst Berendt
Label: MPS
g)Ryo Kawasaki ts,ss)David Liebman b)Alex Blake ds)Buddy Williams
1)Nature’s Revenge 2)Body and Soul 3)Choro 4)The Straw That Broke the Lion’s Back 5)Thunderfunk 6)Prelude No. 2 7)Snowstorm
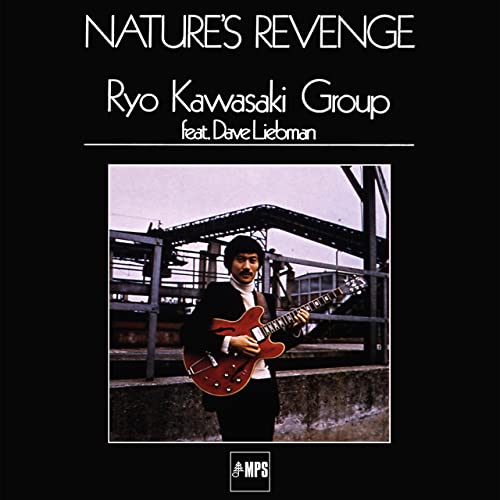
ユニークな構成の作品です。ギタリストRyo KawasakiのグループはDavid Liebmanのテナー、ソプラノサックスをフィーチャーし、エレクトリック、アコースティック・ベースAlex Blake、ドラムBuddy Williamsらのメンバーを擁したカルテットで、ほかギターとテナーのデュオ、アコースティック・ギターのソロ演奏を収録しています。
時代を反映したフュージョン・テイストのオリジナル・ナンバーやLiebmanの美しくドラマチックなオリジナルをカルテットで、ジャズバラードの定番にしてテナーサックスの魅力を最大限に引き出せる名曲Body and Soulをデュオでプレイし、これらの曲間にBrazil出身の大作曲家Heitor Villa-Lobosのクラシック・ナンバーを2曲アコースティック・ギターで独奏しています、ジャズチューンの中にクラシックのソロギター、一見節操のない選曲・構成のようですが、アルバム全体を通して鑑賞してみるとこれが殆ど違和感を感じず、むしろ濃い目のバンド演奏(笑)の良いクッション的役割を果たしています。
この当時Kawasakiはクラシックのギター演奏に力を入れ、よく独奏を重ねていたようです。クラシックギターの専門家、名だたる巨匠に比べればテクニカルな部分、音色、表現力の面で聴き劣りは否めませんが、多くのジャズピアニストが自己鍛練のためにクラシックを練習し、ピアノという楽器をコントロールするための確実な基礎を身に付けたのと同様に、彼も更なる高みを目指してアコースティックギターに集中し、クラシックの楽曲にチャレンジすることでジャズプレイに良いフィードバックを得られるよう、トライしていたのでしょう。本作ではこの時点での結実した演奏に触れる事ができます。
Kawasakiは47年2月東京生まれ。外交官を勤めた父親、海外生活を経験した国際派の母親との間に生まれ、ジャズミュージシャンとして日本で多忙を極めたのち73年にNew Yorkに活動拠点を移します。ほどなく米国ジャズシーンで認められGil Evansの名作 74年「Plays the Music of Jimi Hendrix」76年「There Comes a Time」、Elvin Jonesとは77年「The Main Force」「Time Capsule」、ほかJoanne Brackeenとは78年「Aft」「Trinkets and Things」で演奏します。
米国では他国籍者の場合、音楽活動を行うにはグリーンカード(永住権、労働許可証)所有が不可欠ですが取得に際して厳しい制限が課されています。彼の場合まずGil Evansのバンドに正式に加入するにあたり、Gilがスポンサー(保証人)になり尽力し、73年10月頃から書類上のやり取りを行いました。ところがNew YorkのMusician’s Unionがこれに反対し「米国に良いギタリストが存在するのになぜ日本人を採用するのか」とクレームをつけました。Kawasakiの力量や人間性を認めていたGilは「メンバーは自分に必要なサウンドや人物で決めるのであって、国境は関係ない」としてUnionも承諾し74年半ば以前に取得出来たそうです。大岡裁きですね。


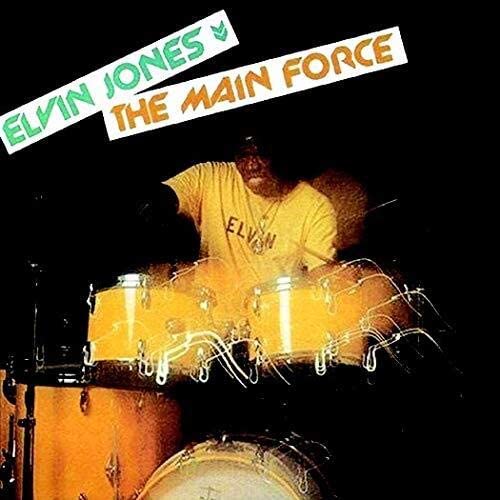


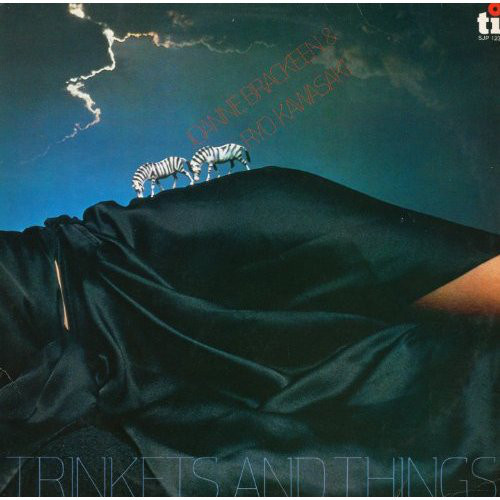
本作のレコーディングのきっかけは76年から77年にかけての長期にわたるElvinとのツアーの際、欧州各都市のクラブやジャズ・フェスティヴァルなどに出演し、それらが当地のレーベルやブッキング・エージェントたちの目に留まり、彼らからのオファーが来たそうです。
その中のひとつが独MPSのプロデューサーJoachim-Ernst Berendtのアルバム制作依頼でした。それはかなり具体的なもので、予算と録音日程、その直後に録音メンバーによる2週間以上にわたる独語圏内(ドイツ、オーストリア、スイス)の各都市を回るツアー、「音楽内容やメンバーのチョイスはご随意に」といった依頼で、New Yorkで活動していた自身のライヴ・グループからAlex Blake, Buddy Williams、そしてElvinのバンドで共演を重ねたDavid Liebmanに白羽の矢を立て、メンバーが決まりました。ドイツ人は物事に対してはっきりとした考えを持ち行動する国民性なので、当初から仕事がやり易かった事でしょう。本作の特徴であるアコースティックギターの使用は77年録音の前作に該当する「Ring Toss」で既に行われています(クラシック音楽は未演奏)。因みにBlake, Williamsのリズム隊も既に起用されています。

実は彼の10歳ほど年上の従兄弟がクラシックギターの名手(プロではなかったそうです)で、Kawasakiも幼い頃からこの楽器に魅せられ、いつかは弾けるようになりたかったそうです。Elvinの長期間に渡るツアーの際、プレイしている以外は時間があったので持参したアコースティックギターを練習し、更にはElvinもクラシックギターが大好きだったのでライブでセット毎に数分間ソロ演奏を披露する機会を与えて貰ったそうで、これは得難いチャンスでした!そういえばElvin自身もアルバムでギタープレイを披露しています。67年録音「Heavy Sounds」収録のその名もElvin’s Guitar Blues、アコースティックギターをイントロでご愛嬌程度に、でも気持ち良さそうにつま弾いていますが、ドラムを叩く時のような例の声は聴こえません(笑)。
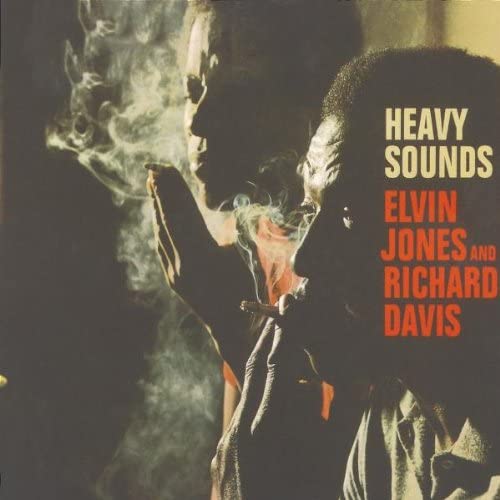
こういった背景があり、彼はBach, Tarrega, 本作のVilla-Lobos, そしてRodrigo, Ravel, Debussy, Stravinskyらの名曲を人前で演奏したり作品として収録できる程度まで習得しました。アコースティックギターによるクラシック演奏にはごく自然な流れが存在したのです。
それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目Kawasakiのオリジナルにして表題曲Nature’s Revenge、当時(現在もそうですが)世界的な異常気象により地球温暖化、洪水、巨大ハリケーン、海水位の上昇が問題となり、これらは地球を弄んだ人類に対する自然の復讐であり、警鐘を鳴らすべく書かれたナンバーと言うことです。
アップテンポのサンバ、しかしタイトルが持つ重厚感は感じさせない軽快なリズム、メロディで、随所に聴かれるキメやアンサンブルは当時のフュージョン、クロスオーバーを彷彿とさせます。Williamsのテクニカルで軽快なドラミングが曲調に相応しいカラーリングを施します。バスドラムと皮もののバランスがよく取れているドラマーです。
全編に渡りギターのバッキングがオーバーダビングされ、2拍3連のパターンを基本に次第に発展していきます。
テーマのメロディ部とは別に巧みなベースソロ、アコースティック・ギターとソプラノのトレードのセクションを有し、その後スパニッシュモードによるメロディ・パートがあります。この部分の延長線上でソプラノサックスのソロがスタートしますが、しかしLiebman、これは猛烈なイメージの演奏です!ミステリアスな雰囲気で音量を抑えた序章から、次第に様々なモチーフや細かいセンテンス、アウトするラインを巧みに用い、起承転結を持たせながらストーリーをエグく構築して行くプレイは圧倒的です!場を活性化するべくドラムがソプラノソロに呼応しますが、Liebmanがここではいつになくon topでプレイしています。スピード感と言う次元より、むしろ前のめりなグルーヴを感じさせるので、せっつかれたようにも、また何かに追われているかのようにも聴こえます。実はこのLiebmanのソロ自体がNature’s Revengeを表現しているのかも知れませんね。
まさにほど良きところでギターによるメロディがバックリフ状態で演奏され、最後はソプラノもユニゾンでプレイしギターソロへと続きます。ディストーションを施したトーン、ロックフレーバー満載のラインの連続でバンド一丸となってバーニング!その後ラストテーマへ、ここでも再びアコギとソプラノのバトルが聴かれますが、ハードな構成の曲中、幾山も超え、やっとラストテーマに辿り着いた安堵感すら感じさせる余裕のトレード、そしてFineです。

2曲目はギターとテナーのDuoによるBody and Soul、印象的なコードワークから始まるギターソロには旋律を感じさせるラインが用いられ、テーマの前半AAを演奏、そして同様にメロディ・フェイク的なテナー奏、この時点で素晴らしい音色にノックアウトされます!サブトーン主体の付帯音に満ち満ちた、テナーの周囲をシュワーっという音の粒子によるスモークが焚かれたかのようなサウンド、Coleman Hawkinsに始まりStan Getz, Sonny Rollins, John ColtraneたちTenor Titanの名演に並び称されるクオリティの演奏です!テナーはテーマの後半BAをプレイ、再びギターがAA部でソロを取ります。Kawasakiお得意のフレーズの嵐、即断で彼の演奏と分かる勢いです!その合間を縫うように繰返しのAからテナーがオブリを入れ、その返答の如くギターの大変気持ちのこもったピアニシモでのフレージングがあり、サビのBから同様にテナーソロへ。ギターも同時進行でソロを取りますが、実にナイスなコラボレーション、合計2コーラスをありそうで無かったフォームで、そして緻密にして崇高な美学に貫かれたインタープレイを聴かせ、エンディングcadenzaでのスリリングのやり取りも絶妙で、間違いなくBody and Soulの名演奏の一つに挙げられるテイクに仕上がりました!
David Liebman

3曲目ChoroはVilla-Lobosの代表曲、アコースティックギターでクラシックを志す者なら必ず演奏するナンバーの1曲です。ChoroはBrazilのポピュラー音楽のスタイルの一つで、19世紀に既にRio de Janeiroで成立しました。ポルトガル語で「泣く」を意味する「chorar」から名付けられたと言われており、Choroを米国ではBrazilのJazzと例えられることがありますが、即興を重視した音楽としてはJazzよりも歴史が古いと言えます。
アコースティックギターを手にしてこの曲を練習する、人前で演奏する、ましてやこのテイクのように自分のリーダー作でプレイするに当たり、常に身の引き締まる思いを抱いた事でしょう。ジャズプレーヤーにとっては襟を正して演奏すべきナンバーです。
Heitor Villa- Lobos

4曲目LiebmanのオリジナルThe Straw That Broke the Lion’s Back、この曲にも作曲者自身のコメントがオリジナル曲集「30 Compositions」に記載されています。「had to do with an incident in my life, where something occured which finally caused me to take action, literally ≫the last straw≪. The melody is straight-forword with common changes and intended to have lyrics. The second section was grafted from another song and puts the melody in the bass. The feel is eighth note and bossa-nova like.」
元はことわざ「It’s the last straw that breaks the camel’s back」ギリギリのところまで重荷を背負ったラクダはその上わら1本でも積ませたら参ってしまう<たとえわずかでも限度を越せば、取り返しのつかない事になる>を捩ったタイトル、曲に歌詞を付ける予定だそうです。
テーマメロディを用いたリリカルなギターイントロから始まり、コードワークに導かれてインテンポ、Liebmanの逞しくも深いトーンを湛えたテナーが朗々とテーマを奏でます。
ギターのバッキング、フィルインが実にカラフルです!Blakeもコントラバスに持ち替え、よく伸びる深い音色でサポートはもとより、曲中のベースによるメロディラインを美しく演奏しています。
リズムはコメントにもあるようにボサノヴァがかった8ビート、コード進行は確かに良くあるものですが、何よりLiebmanのプレイが素晴らしく、リラックスした中に耽美的な表現が自然に散りばめられ、魅惑的な世界へと誘います。
彼独自のニュアンスは比較的too muchになりがちですが(代表的な演奏例としてSteve Swallow / Home)、ここではバランスを保ち聴き手に決して押し付ける事なく、王道を行くスタンスで表現されており、僕にとっては彼のソロの中で格別にフェイバリットな、ウタを感じさせる、何度聴いてもグッと来てしまうソロです!続くギターの演奏もLiebmanに刺激されイメージを膨らませた、曲想に合致したプレイを聴かせます。
その後のラストテーマは素晴らしいコンビネーションによるインタープレイを存分に重ねた成果でしょう、表現力が一段と増した成果を聴かせ、この曲の持つ魅力を十二分に発揮しています。
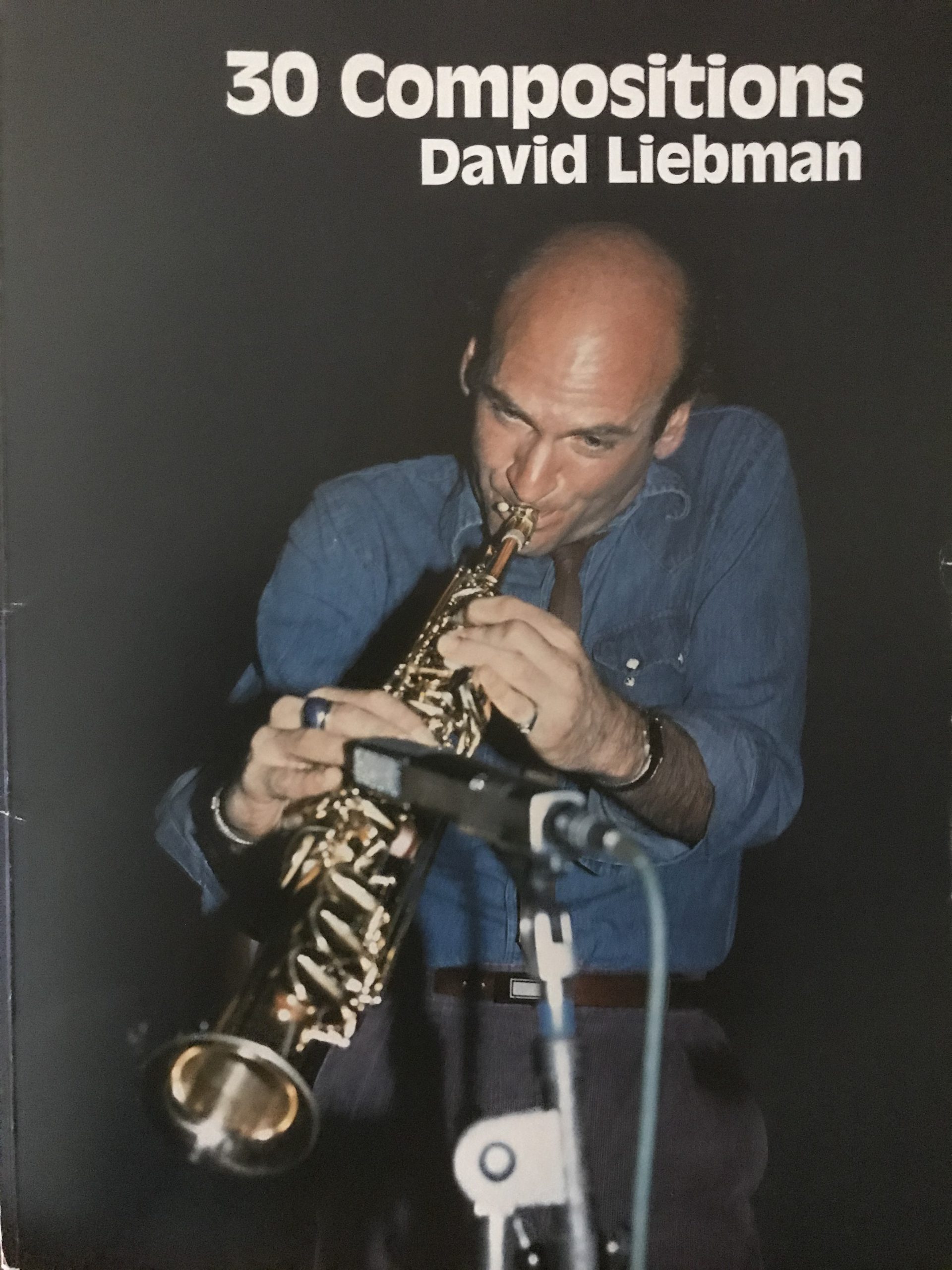
5曲目ThunderfunkはKawasakiのオリジナル、エレクトリックベースのスラップによるイントロからドラム、ギターのカッティング、オーヴァーダビングによるメロディが加わり、テナーとのキメ、そしてイケイケのチョーキング・ギターによるテーマ、サビで対比的にムードが変わる、いかにも70年代ライクなテナーによるライン等が提示されギターソロへ。Funk魂全開のプレイです!
そういえばLiebmanのJames Brown, Van Morrisonバンドの重鎮テナーPee Wee Ellisとのコラボレーションで制作した76年録音のアルバム「Light’n Up, Please!」、こちらでもファンキーな、ホンカーライクなプレイを聴かせています。
Liebmanのここでのソロは7thコード#9thの響きをギタリストのように全面にプッシュしたプレイ、コンパクトにまとめラストテーマに繋がります。

6曲目Prelude No. 2、再びVilla- Lobosのナンバーを外連味なくアコースティックギターのソロで演奏しています。前曲のエグさを一掃するかのような(笑)アカデミックさ、心が洗われるようです。違和感なくすんなりと耳に入って来るのは演奏自体が限りなくピュアだからでしょう。
Ryo Kawasaki(2018年クロアチア)

7曲目Snowstormは大作です。曲冒頭にDon Luis Milanの名曲Pavaneをアコースティックギターソロで奏で(オーヴァーダビングだと思われます)、その後アップテンポでファンクのリズムが刻まれ、ベース、ギターと加わり、ソプラノによるテーマが提示されます。ギターのバッキング、ベース、ドラム、全員かなりのハイテンションでプレイしています!ギターソロが先発を務め、Blakeの縦横無尽なベースワークと実に良く絡み合っています。その後ソプラノによるテーマの後、世界が一新します。これは3拍子+3拍子+3拍子+2拍子という構成による11拍子、リズム隊の作り出す怪しげな世界を背景に、民族音楽のような旋律から成るメロディを経てLiebman存分に咆哮します。次第にサウンドはFade Outに向かい、Snowstorm=吹雪、まるで全てが雪に埋もれてしまい静寂の世界が訪れたかのようです。
2021.03.22 Mon
今回はDavid Liebman Quintetによる1978年2月NYC Village Vanguardでのライブレコーディングを収録した作品「Pendulum」を取り上げたいと思います。テナー・ソプラノサックスDavid Liebman、トランペットにRandy Brecker、盟友Richie Beirachをピアノに迎え、ドラムAl Foster、ベースFrank Tusaらの素晴らしいサポートを得て、バンド一丸となった名演奏を聴かせています。
Recorded: February 4th and 5th, 1978 at The Village Vanguard, NYC by David Baker, assisted by Chip Stokes
Mixed: September 12, by David Baker with David Liebman, Frank Tusa, and Richie Beirach at Blank Tapes Studio, NYC
Mastered by Rudy Van Gelder
Art by Eugene Gregan
Produced by John Snyder
Label: Artist House
ts,ss)David Liebman tp)Randy Brecker p)Richie Beirach b)Frank Tusa ds)Al Foster
1)Pendulum 2)Picadilly Lilly 3)Footprints

70年代後期Liebmanの絶好調ぶりがダイレクトに伝わる優れた作品です。Elvin Jones, Miles Davisとの共演で培われた音楽性をベースに、自身に備わっていたユダヤ的なテイスト(サウンド、ハーモニー、スケール感)と結合した独自なスタイルが開花した時期に該当します。楽器の表現力、テクニックやタイム感も格段に向上し作曲やアレンジにも深みが加わり、確実な方向性を確認することが出来ます。
作品クオリティの充実ぶりには加えて本作レーベル、Artist Houseの貢献もあります。プロデューサーJohn Snyderは数々の名演奏を生み出したNYCの老舗ライブハウスVillage Vanguardでの録音を挙行(Liebman初ライブ録音になります)、レコーディング・エンジニアに彼の演奏を熟知しているDavid Baker、更に録音テープからレコード盤作成時最後の関門とも言える重要なマスタリング(ここが充実せず最悪の場合音質が劣化することさえあります)にBlue Note, Prestige, Impulse, CTI等で数々の名録音を手掛けた鬼才Rudy Van Gelderを起用、このコンビネーションにより素晴らしい音質に仕上がりました。
アルバムジャケットのデザインにはLiebmanの絶大な信頼を得ているEugene Gregan、ダブルジャケット仕様のレコードには全8ページからなる詳細な内容を記載したブックレットを付属させました。こちらには録音使用機材等のディテールやインフォメーションのほか、Liebman自身によるメンバー、スタッフ、演奏曲に対する紹介、解説が掲載され、アルバムリリース79年当時のコンプリート・ディスコグラフィー(Liebmanお気に入りアルバムのクレジット入り!)、更には収録曲PendulumとPicadilly Lillyのリードシートも付録され、米国制作とにわかには信じ難い繊細なレベルでの作品リリースに仕上げています。良い作品を世に出したいという欲求と情熱を痛感しますが、推測するにかなりの経費がかかった割には売れ行きが芳しくなかったのでしょう、Artist Houseは78年から81年にかけて合計14作を発売しましたが、残念ながらその後活動を停止してしまいました。

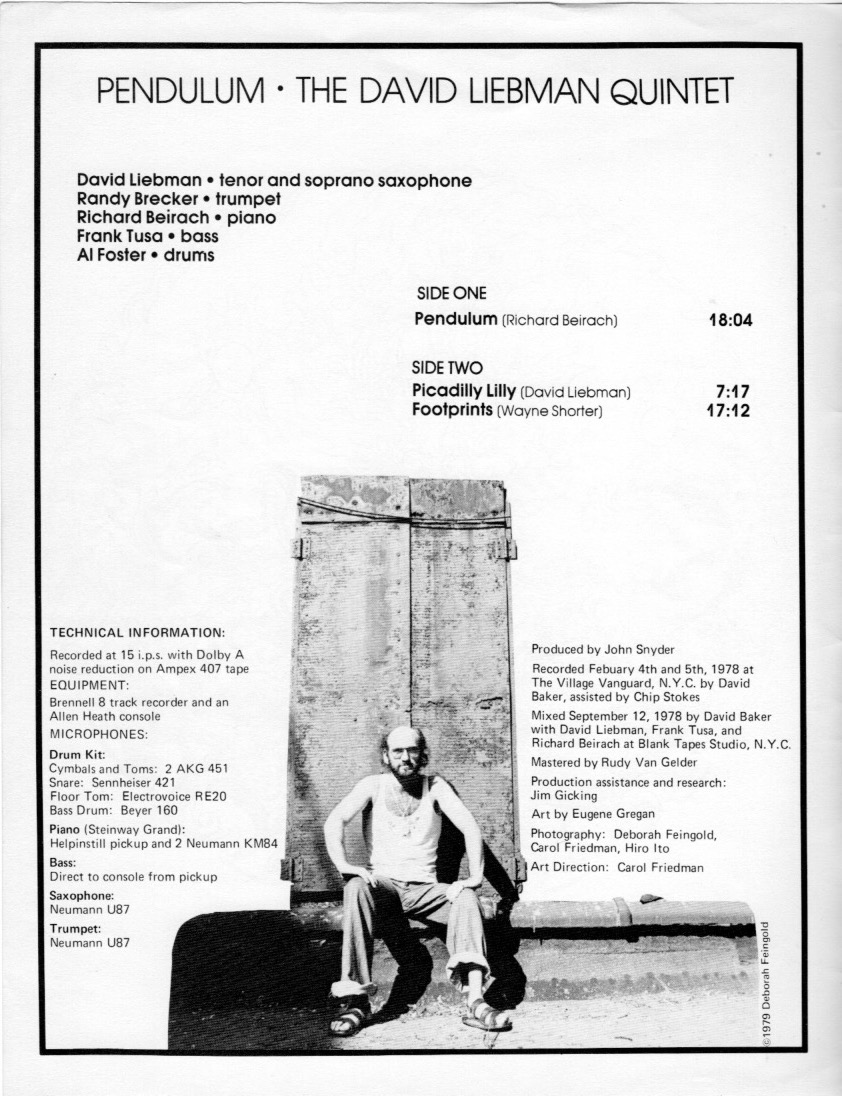


また08年にはMosaic Labelから8曲の未発表演奏を追加したCD3枚組がリリースされました。There’s No Greater Love, Solar, Night and Day, Blue Bossa, Well You Need’t, Impressions等のスタンダード・ナンバーを中心とした追加テイクはいずれもがライブならではの長時間に及ぶ白熱した演奏です。ジャムセッションで取り上げられるようなこれらのナンバーはLiebman, Brecker, Beirachにとって他で聴くことの出来ない貴重なテイクとも言えますが、合計11曲、収録時間191分以上、全ての曲で演奏は完全燃焼を遂げており(汗)、しかもバラードやリラックスした雰囲気の曲が皆無というのも凄まじい、Liebmanらしいセレクションです!3枚通して聴くことはまず無理でしょう(熱狂的なLiebmanフリークの僕でもギブアップです!)、圧倒的なまでの内容の濃さ、ボリュームを有し、他にこれだけの作品の存在を知りません(爆)。
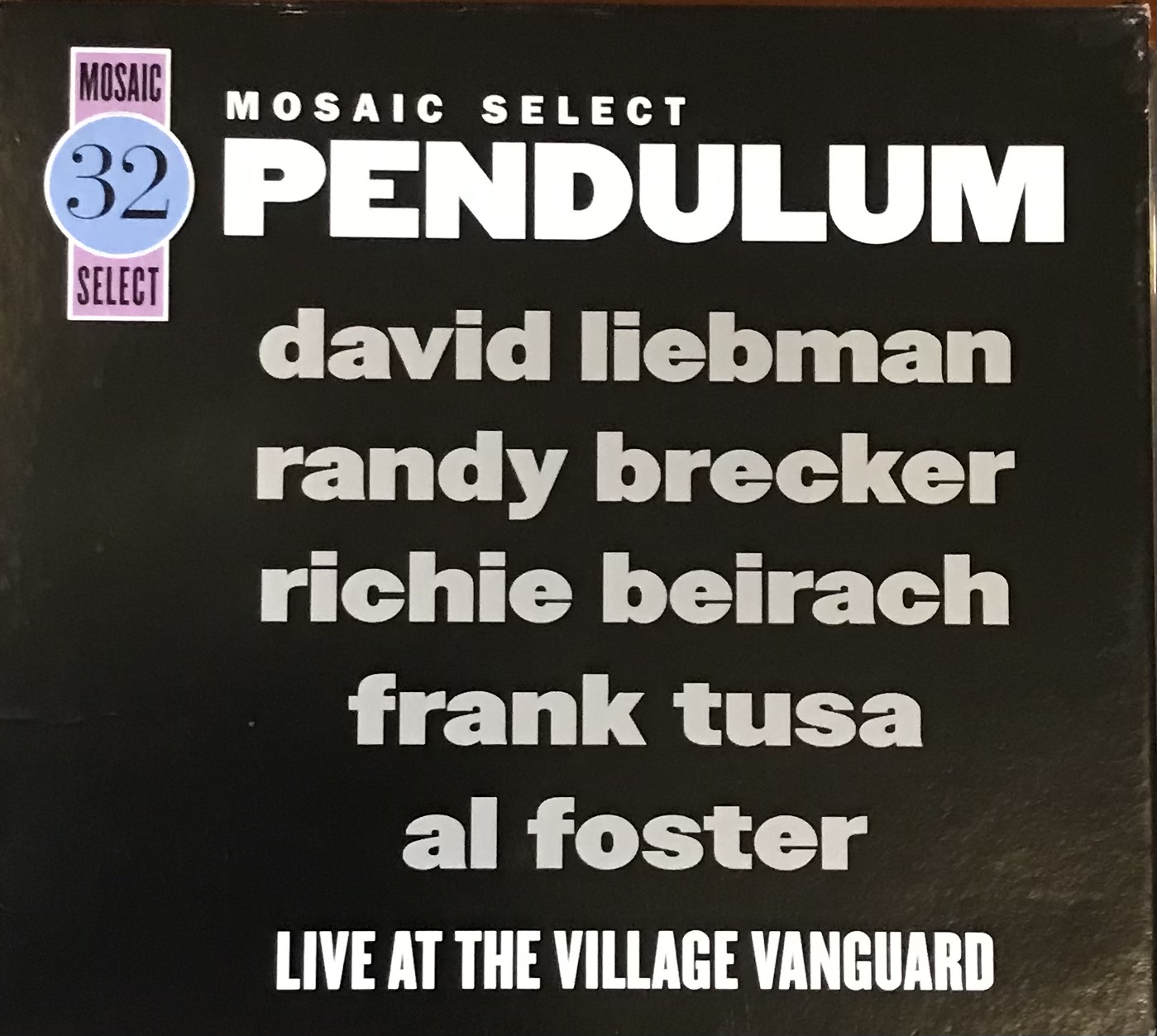
LiebmanとBreckerはManhattanのロフトで70年代初頭からセッションを繰り返した間柄です。そこには弟Michael Brecker, Steve Grossman, Bob Mintzer, Bob Bergたちも加わり、ユダヤ系の知的で高度な音楽性を湛えたフロント陣が研鑽を遂げた場所でもありました。意外なことにLiebmanとRandy(Brecker)の2フロントによる共演作は殆ど存在せず本作はその意味では貴重な作品です。他には98年3月NYC Town Hallにて行われたコンサートを収録した作品「70s Jazz Pioneers / Live at the Town Hall」で共演を果たしており、他にPat Martino, Joanne Brackeen, Buster Williams, Al Fosterたちと60〜70年代のナンバーをセッション風に演奏しています。

ベーシストFrank Tusaは70年代初頭からLiebmanと活動を共にし、Bob Mosesを含めたOpen Sky Trioでの活動、またBeirachともコンスタントにプレイを展開していました。Liebmanのアルバムには7作参加し、また自身の作品75年7月録音「Father Time」にLiebman, Beirachを招き、ドラマーも当時のLiebmanバンドのレギュラーJeff Williamsが加わり、リーダーが代わっただけのLiebmanグループの様相を呈しています。ここにTusaのオリジナル曲Doin’ It(クリックすると試聴できます)が収録されLiebmanに存分に吹かせていますが、前回Blogで取り上げたLiebmanの作品「Doin’ It Again」表題曲との関係の有無がずっと気になっています。曲想は異なりますがDoin’ It〜Doin’ It Again、たまたまタイトルがオーバーラップしただけの別曲なのか、曲のコンセプトを何らかの形で受け継いだのか…機会があれば是非本人に尋ねてみたいと思っています。

それでは収録曲に触れていきましょう。1曲目BeirachのオリジナルPendulum(クリックすると試聴できます)。18分以上を有する演奏、レコードのSide Aを1曲で占めています。作曲者自身のリズミカルなイントロからスタートしますが、この人のピアノタッチは実に素晴らしいです!濃密さとクリアネスが同居したトーン、さすがSteinway & Sonsのアーティスト!ピアノという楽器を深い領域で良く響かせる、更に自身のオリジナリティを音色に反映させた魅力的なサウンドを奏でていて、まさしく心の琴線に触れるプレイです。ベース、ドラムがごく自然に加わり、ピアノひとりでもリズミックであったのに3人が織りなすグルーヴで、より立体的にリズムが構築されます。Al Fosterのタイトなレガート、Paisteシンバルの使用でスティックのチップ音がドライかつシャープに響きます。Tusaのベースもリズムのスイートスポットにバッチリ嵌っています。テーマはテナーがメロディを奏で、トランペットがハーモニーを担当、メロディが下の音域でハーモニーが上に位置するので不思議なサウンドですが、Randyは音量を抑え目に吹いていてしっかりと主旋律を立てています。
ソロの先発はトランペット、この頃のRandyはThe Brecker Brothers Bandでの活動真っ最中、Bros.の代表曲Some Skunk Funkを筆頭とするワウやオクターバー等のエフェクターを施した演奏で、100%フュージョンのミュージシャンと勝手に認識していましたが、ここでのハードなドライヴ感を伴ったスインガー振りには正直驚かされました!同じトランペッターFreddie Hubbardも大変にタイム感の良いプレーヤーですが、Randyも全く遜色なく、リズムマスターの称号を授与されて然るべきです!フレージングのアプローチ、方法論にもオリジナリティを感じさせつつ、淡々とストーリーを展開して行きます。彼の話し方は比較的「ぶつぶつ、ボソボソ」と独白的でアイロニーを含みますが、この演奏にもどこか感じ取ることができます。
リズム隊はパターンをキープしつつ様々なアプローチを仕掛け、今度は逆にRandyに仕掛けられたりと丁々発止のやり取りを行いながらスイングのリズムに変化して行きます。Fosterのバスドラの軽やかさは実にパーカッシヴ、両手から繰り出されるフィルインの数々も決してtoo muchにならず、ほど良きところをキープしています。かのMiles Davisのバンドを72年から85年まで長きに渡り勤め上げた、真に伴奏に長けたドラマーです!音量のアベレージが小さい彼はダイナミクスの振れ幅が半端なく、ppとffを自在に行き来しています。
Beirachのバッキングのまた物凄いこと!付かず離れずを繰り返しながらもソロに確実に付ける部分と放置プレイのバランスを保ち、そして複雑な和音を内包しながらリズム楽器と化しつつ問題提起的なアプローチ三昧、いわゆるリック的な決まり事とは一切無縁の自然発生的、リアルジャズプレーヤーを実感させます。クラシックを徹底的に学び、幼い頃からピアノの神童として育てられたに違いないでしょう、ノーブルさ、緻密さをベースにプレイをとにかく楽しむ事を念頭に置く演奏姿勢、それらがあり得ない次元で備わっています。Michel Petruccianiはピアノの化身と言われましたがBeirachも全く同じ、いやそれ以上かも知れません!
トランペットソロ後は再びリズムパターンに戻りそのままBeirachのソロが始まります。右手のシングルノートを中心にメロディの提示やパルス的なフレージングを積み重ね、次第に世界を作り上げて行きます。その際Fosterのドラミングとのやり取りが素晴らしい!彼も決まり事に一切決別を宣言したかのプレイ、豊かな泉の如く溢れ出るアイデアは他のドラマーにはない全く独自のセンスで。Tusaのベースともあくまでお互いの協議と合意のもと、ジワジワと物語を作り上げ、前人未到の高みにまで辿り着かんとしています!そしてここぞと言う場面をプレーヤーたちは決して逃しません、三つ巴でピークに向けて、しかしこの後に控えるリーダーのプレイの盛り上がりも視野に入れつつ、一段階手前の絶頂、八合目を目指してGo!Fosterのバスドラ連打祭りでもあります!
ややクールダウンし再びパターンに戻り、壮絶な音色を伴ったテナーソロがスタートです。トーンも凄ければ吹いているラインも情念のこもった、問題提起どころではない世界の終焉にまで向かわんとするテンションの連続、しかしBeirachはLiebmanのシリアスさとは無縁のように、何処か楽しげにバッキングノートを繰り出しています。このバランス感が50年以上も演奏を共有する事ができる秘訣のような気がします。
もう一山越えの手前でLiebmanラストテーマを吹き始め、Randyがすかさずハーモニーを付け呼応します。総じてこの演奏のピーク、実は作曲者Beirachのソロ中で迎えていたのかも知れません。

2曲目Picadilly Lilly(クリックすると試聴できます)はLiebmanのオリジナル、彼の作品の中でも最もストレートアヘッドな1曲です。スタンダードナンバーInvitationを彷彿とさせるメロディライン、曲のキーもin B♭でF#メジャー、複雑な構成、コード進行からかなりの難曲です。冒頭ルパートでテナーとピアノによるイントロが演奏され、すぐさまインテンポとなりテーマが奏でられます。その後はいわゆる吹きっ放し、Liebmanの独壇場で演奏され、彼のプレイのショウケースとなり絶妙なストーリー展開を行なっています。前出のCD3枚組にはこの曲の別テイクが収録されていて、そこではRandyのトランペットソロも聴くことが出来ますが、こちらのオリジナルテイクの方はLiebmanの演奏にフォーカスしているので、より統一感を感じます。
♩=160のallegroテンポ、Liebmanの素晴らしいリズム感、レイドバック、対する16分音符の正確さ、スイングフィール、独自のニュアンスが施された歌いっぷりもしっかり堪能できるプレイです。それにしてもこの怪しげな(汗)節回しは他には一切ない彼ならではのスタイル、本人は気持ちよく自身の唄、それこそ口笛、鼻歌感覚でテナーを吹いているように感じますが、ここから感じ取れるエグさは実にone & onlyで、一聴すぐ彼と判断できる個性を発揮していて、彼のアドリブソロの代表的なもののひとつと断言出来ます。
途中4’30″過ぎ辺りからブルーノートとベンドを用いたフレージングが聴かれますが、彼のブルーノート使用よる表現はいわゆる他のジャズメンとは異なり、言ってみればブルージーさを通り越したダークさに到達しています。感極まったオーディエンスのアプローズが絶妙なところで聴かれますが、間違いなく熱狂的なLiebmanファンでしょう、ちなみに僕の声ではありません(爆)
ソロの締め括りにはここ一番と言うべき思いっきり割れたフラジオ音を炸裂させ、Fosterは巧みなスネアロールで呼応していますが、この辺りのレスポンスは神がかっています!
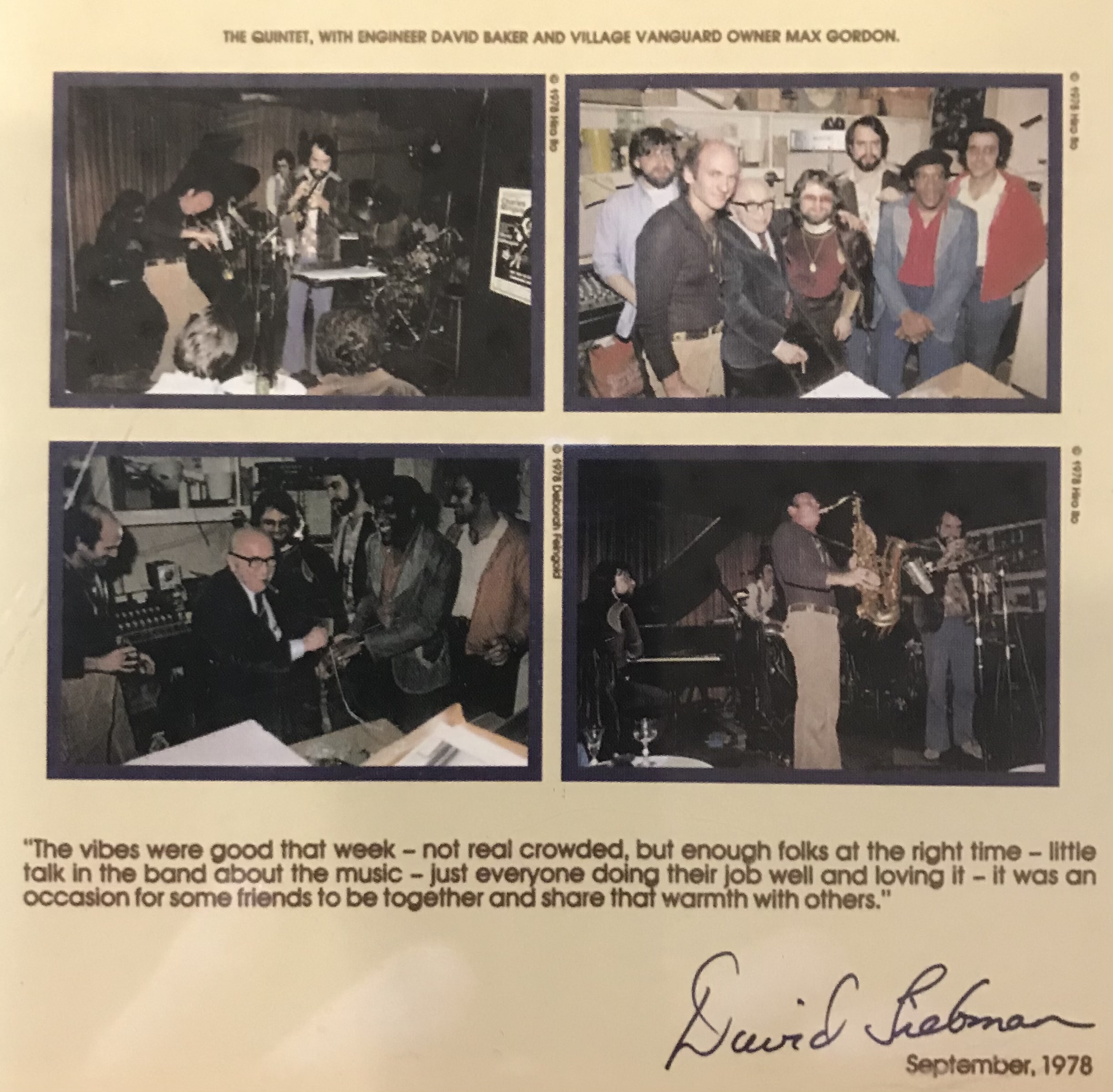
3曲目Wayne ShorterのナンバーFootprints(クリックすると試聴できます)、Tusaのベースパターンから始まり、BeirachとFosterで互いに呼応しイントロの雰囲気作りに一役買い、その後発情期の猫を思わせる(汗)Liebmanのソプラノが登場します。テーマはトランペットが主旋律を吹き、ソプラノがハーモニーに回りますが録音の関係か敢えてなのか、ソプラノの存在感の方が大きく、ハーモニーの方がメロディに聴こえます。実は狙っているかも知れませんね。テナー以上にLiebmanのソプラノは個性的で、80年頃から一時期テナーサックスを封印してソプラノに専念したのも頷けます。
ここでの縦横無尽なソロのアプローチは特筆すべきで、一つのチャレンジが結実した好例だと思います。常に進取の精神を忘れない彼の根底にあるのはJohn Coltrane、Liebmanが60年代にColtraneの生演奏を頻繁に聴きに行き、ある夜はアドリブソロを全てトリルのみで行っていたとも語っていますが、Coltrane’s spirit a la Liebmanとして彼の内面で脈々と育まれています。
メロディにスペースのある曲だけにテーマ時はBeirachのフィルインが大活躍、ここぞとばかりに華麗なプレイを聴かせます。さらにLiebmanの猛烈なソロ時、凄まじいまでに呼応する、反して放置するバッキングは、彼に対する演奏上のノウハウを熟知している者ならではのアプローチ、Liebmanも演奏上のパートナーとして必須、そして付かず離れずを含めて(長きに渡る間柄、没交渉の期間もありました)、彼の事が可愛くて仕方なかったと推測しています。ソロのファイナルには「一体これは何なんだ?」という壮絶なバッキングがあり、Liebman自身まだまだ長いストーリーを語れたのでしょうが、リズム隊のアプローチがフレッシュなうちにソロを終えようと言う目論見を感じました。
続くRandyのソロは実に端正に、リズミックに、イマジネイティブに、リズム隊の完璧とも言えるサポートを得て、彼の音楽歴の中でもベストに入るソロを聴かせています。
そしてBeirachの出番です。Liebman, Randyのプレイから深淵なジャズ・スピリットを得て、もはや囚われるものは何もない、思う存分自己解放を行えば良いのだ、と言う次元での猛烈な演奏を繰り広げています。これだけタガが外れた彼も珍しいかも知れません。
そしてFosterのドラムソロは美しい音色で的確にかつテクニカルに行われていますが、バッキング時の方が自身の表現をより行えているように感じます。伴奏に徹した演者ならではと再認識しました。ラストテーマはBeirachによりスムースに導かれ、メンバー全員思う存分好きな事をやりつつ(笑)猫の発情期も再来し(爆)、大団円です。
2021.03.09 Tue
今回はDavid Liebman 79年録音リーダー作「Doin’ It Again」を取り上げてみましょう。自身のレギュラーQuintetによる演奏、Terumasa Hinoとの2 管編成にギターの名手John Scofieldを配し、アコースティック、エレクトリック・ベースにRon McClure、ドラムAdam Nussbaum。ユニークなLiebmanとMcClureのオリジナル、そしてスタンダードナンバーであるStardustの名アレンジ、名演奏が光る意欲作です。
Recorded: 1979 at Platinum Studios, Brooklyn, New York
Recording and Mixing Engineer: David Baker
Producer: David Liebman and Arthur Barron
Executive Producer: Theresa Del Pozzo
Label: Timeless Records
ts, ss)David Liebman tp, flg, perc)Terumasa Hino g)John Scofield acoustic, el-b)Ron McClure ds)Adam Nussbaum
1)Doin’ It Again 2)Lady 3)Stardust 4)Cliff’s Vibes

多作家Liebman 11枚目のリーダーアルバムに該当する作品です。これまでにもフュージョン、クロスオーバー・テイスト(ブラコンもありました!)の作品とストレートアヘッドなアルバムのいずれも発表して来ましたが、本作はレコードのSide Aに該当する1, 2曲目がフュージョン・タッチ、Side Bの3, 4曲目がアコースティック・ジャズを聴かせています(ベーシストはアコースティック・ベースに持ち替え)。演奏自体はいずれも間違いなく、どこから聴いてもone & onlyなLiebman Musicなのですが、演奏の形態に拘りを感じさせるのは当時の風潮でしょうか。リリース80年、フュージョン全盛期にアコースティックなサウンドを敢えて演奏するのは、それなりに意味があったのでしょうが実はレーベルの意向のようにも感じます。
78年2月録音NYCの名門ジャズクラブVillage Vanguardでのライブを収録した「Pendulum」はRandy Brecker(tp), Richie Beirach(p), Frank Tusa(b), Al Foster(ds)らを擁したLiebmanのリーダー作、外連味なくストレートアヘッドな演奏を展開している名盤ですが、こちらに比べれば本作は確かにテイストとしてフュージョンを感じさせます。
Pendulum / David Liebman Quintet (クリックして下さい)
84年旧西ドイツで出版されたLiebmanオリジナル曲集「30 Compositions」(advance music)には楽譜・スコアの他、全ての楽曲に本人による解説が英語、独語の両方で掲載されており、表題曲にしてLiebmanのオリジナルDoin’ It Againも収録されています。ここで紐解いてみる事にしましょう。
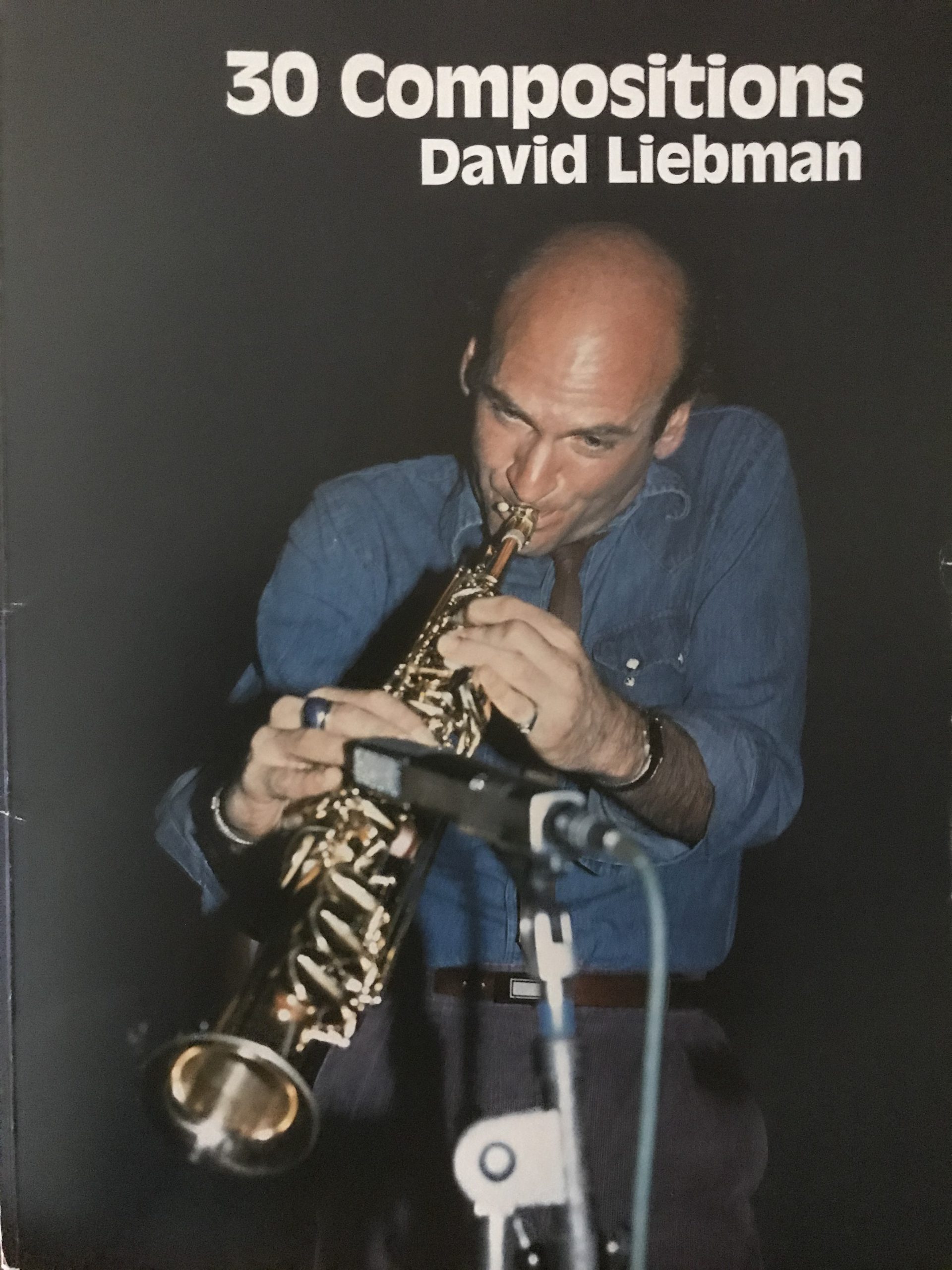
Doin’ It Again:「 celebrates my return home to New York City after a sojourn in California(1978). It also reflects the compositional influence of Chick Corea, with whom I did a three month world tour in 1978. This, and the future compositions show more formal writing through use of interludes, introductions and codas. This is my another compositions where the bass line plays an important part in the melody itself.」
Chick Coreaの作風からの影響が反映されているとありますが、僕にはこの曲にCoreaを感じ取るのは難しいです。そのような耳で聴いてみるとそうも聴こえなくもない…音楽家は各々独自のセンスと感受性を有しているので、捉え方が異なって当然なのですが。
またCoreaと78年に3ヶ月間ワールドツアーを行ったと記載され、実際に東京でもCorea Bandの公演が行われました。アルバム「Leprechaun」「My Spanish Heart」「Mad Hatter」の楽曲を、リズム隊に弦楽四重奏とホーンセクションから成る大所帯による編成で、加えてふたりは毎夜Lush LifeやCrystal SilenceなどをDuoで演奏しました。実に興味深く、録音が残っていたら是非聴いてみたいものです。
そのツアーの中頃、1週間のオフ最中にCoreaは彼に捧げたナンバー”Blues for Liebestraum”を書き上げたそうです。これは大変に名誉なこと、ツアー中にリーダーから書き下ろしのオリジナルを贈られるとは、音楽的信頼関係の成せる技、ふたりの蜜月ぶりを物語っている以外にはありません。Liebmanもさぞかし嬉しかった事と思います。この時点では二人の関係は大変良好だったのでしょう、と言うのもLiebmanの自伝「What It Is」によるとこのツアーの最後にCoreaがLiebmanに激昂し、右手の中指を立てて、”I never want to see you again!”と絶縁の宣言したそうです(汗)。様々な行き違い、食い違いの結果、LiebmanがCoreaを立腹させたのでしょう。
Coreaは自身の音楽史上、実に多くの共演者たちと頻繁にメモリアルな再演を行なっていましたが、Liebmanとは最後まで没交渉でした。しかしLiebmanの方は意に介さず、Coreaに捧げたオリジナルのラテン・ナンバーChick-Chat(クリックして下さい)を79年12月録音アルバム「What It Is」(自伝と同名)で演奏したり、共演者経歴への記載(Coreaとの共演はMiles DavisやElvin Jonesと匹敵する輝かしい経歴だったのでしょう)、また自身のクリニックでもCoreaの名前を度々口にしており、好印象をキープしていました。
What It Is
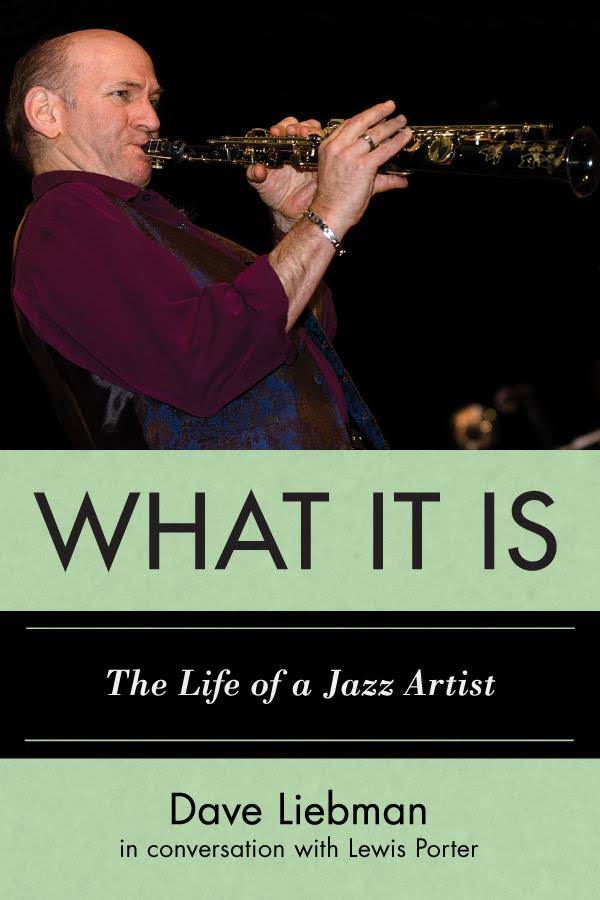
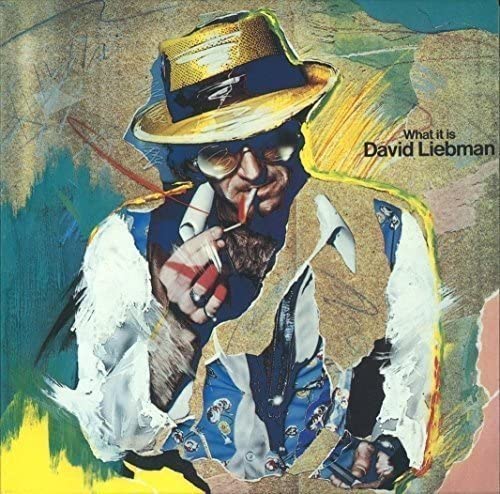
ちなみにLiebmanに捧げられたナンバーBlues for LiebestraumはJoe Hendersonの80年1月録音リーダー作、Coreaがサイドマンで参加している「Mirror, Mirror」で取り上げられています。Liebmanへのスペシャル・ナンバーだったにも関わらずJoe Henが演奏したのは興味津々、Joe Hen, Coreaとも素晴らしいプレイを繰り広げています。
Liebman曰くコード進行やサウンド的に難曲であるBlues for Liebestraum(クリックして下さい)、インスピレーションが湧いたのでしょう、この曲中に用いるshout chorus=ソリ、アンサンブル部分を既に書き上げているので、いずれこの曲をレコーディングしたいと発言しています。ミュージシャンとして様々な側面からの音楽的準備を怠らないクリエイティブな姿勢を、この発言から感じ取ることができました(同じテナー奏者として、自分自身も常にそうありたいと願っています)。Corea亡き後、Liebman自身による演奏は早急に具体化されるに違いありません。
Mirror, Mirror / Joe Henderson
それでは収録曲について触れて行くことにしましょう。1曲目Doin’ It Againは冒頭から印象的なベースパターンとギターのハイパーでエグエグの音色、ラインのプレイが支配しています。作曲者自身の解説にもありましたが、確かにベースラインがメロディと同等に重要な役割を果たしていて、またコード楽器がピアノではなく超個性派ギタリストによるプレイで、バンドのサウンドを決定付けています。John Scoのギターはピッキングの強さと正確さ、強力なタイム感から、エッジの効いたいわゆるホーンライクな要素が強く、トランペット、テナーサックスの他にもうひとり管楽器奏者が存在するが如しで、一方容易くコードプレイにもスイッチし、しかもコードプレイから発するサウンドが尋常ではありません!190cm近くある身長ゆえ掌も大きいことでしょう、左手のコードワークが他のギタリストでは真似できない離れたポジションを押さえ、とんでもない指の配置による掌の形がフレットを覆っているとイメージ出来ます!
テーマメロディはトランペット、テナーと交互に演奏されその合間にギターが「もう一人の」管楽器奏者的にバッキング、オブリガートが挿入されます。その後2管によるユニゾン〜アンサンブル、背後でのJohn Scoの有り得ない次元でのサウンドクリエイション!このフロント3人めちゃくちゃキャラ濃いです!サビに該当する部分はリズムがタンゴ・フィールに変わり、ギターの変態さ(笑)は相変わらずに、トランペットが朗々とメロディをプレイし、テナーが加わりアンサンブルを経てテナーソロへと続きます。Liebmanの人選によるサウンド構成、目論見はこのテーマ奏だけで既に大成功の様相を呈しています!
ダークで枯れた音色でいてパワフル、時折叫びを交えつつ、テクニカルなラインの中に内面から湧き上がる独自の歌い回しをこれでもか、とばかりにふんだんに織り込みながらLiebmanはソロを展開して行きます。前回取り上げた「Devotion」とは全く異なる世界観を表現しているので、音楽家としての懐の深さを再認識させられます!
インタールード後、ギターソロに続きます。コンビネーション・ディミニッシュ系のアウトしたラインは現代ではもはや耳馴染みですが、80年当時John Scoはその斬新さから超変態の称号(爆)を欲しいままにしていました(笑)。そして凄まじいまでの音符のスピード感!常々思うのですがタイムに正確で、スピード感を感じさせるプレーヤーは大勢存在するのですが、そこから更に一歩踏み込んだ、例えば椅子から腰が浮き上がり、踊り出したくなるようなグルーブを聴かせるプレーヤーはそうは数が多くありません。言ってみればダンサブル、この音符の筆頭株主がJohn Scoなのです。ここでの猛烈なプレイは彼の代表的な演奏の一つに挙げられると思います。
もっとも近年の彼の演奏はレイドバックし、80年代のバキバキ、イケイケのプレイからリズムのノリは良い意味でルーズに、どちらかと言うとオーソドックスさを感じさせる方向に向かっています。最新作2019年3月録音、全曲Steve Swallowのナンバーを本人とBill Stewartのトリオでプレイした「Swallow Tales」は、本作から40年を経て枯淡の境地に至ったかのようです。
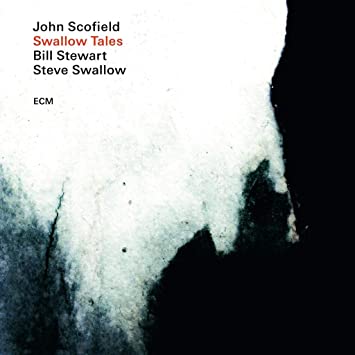
2曲目はRon McClureのオリジナルLady。McClureは41年11月生まれ、Buddy RichのコンボやMaynard Fergusonのビッグバンドを皮切りに、Cecil McBeeの後釜で加入した名門Charles Lloyd Quartet(Keith Jarrett, Jack DeJohnette)で名を馳せました。74年にはBlood, Sweat and Tearsにも参加しています。ほか多くのバンドで活躍し安定したプレイには定評がありますが、SteepleChaseレーベルを中心にリーダーアルバムを20作近くリリースしています。近年の作品はオリジナルが中心になっていますが、89年12月録音の初リーダー作「McJolt」はRichie Beirach, John Abercrombie, 本作共演Nussbaumと名手を揃えたカルテットで、スタンダード・ナンバーの魅力をアピールしています。

Ladyの演奏に話を戻しましょう。一聴爽やかなイントロからスタートしますが、Liebmanが取り上げるだけあって、やはりエグさを湛えたユニークな曲想のナンバー、ソプラノとトランペットのメロディの間隙を縫って繰り出されるギターのフィルインが気持ち良いです。ここでも2管編成に別なホーンが絡んでいるかのようなアンサンブルを聴かせています。テーマ後はソプラノとトランペットの壮絶なバトルが繰り広げられます!ソプラノの音色もメチャメチャ個性を感じさせますが、楽器本体はCouf(独Keilwerthの米国モデル)、マウスピースはDukoff D7番、リードはSelmer Omegaをトクサで削って合わせていました。
しかしここまで自身のテイストを本気でぶつけ合えるのは、ふたりの音楽的相性の良さが不可欠なのは勿論、音楽的レベルが拮抗していなければ成り立つことは出来ません。Liebmanに全く匹敵する日野さん、ワールドクラスの音楽性を痛感しました!そしてバトルを確実なものにする、リズムセクション、特にNussbaumの素晴らしいサポートぶりにも感銘を受けます。
とことん盛り上がった後はギターソロ、しかし何というスピード感でしょう!そして時折聴かせるリズムのタメに入魂ぶりを見せ、良い味を出していますが、やはりこの頃はタイム感が全体的にかなりon topに位置していると感じました。使用する身体のパーツとして、管楽器奏者は運指の他に息を使うのでその分気持ちを入れやすい楽器です。ギターは運指のみになるので(ギター奏者に言わせると呼吸も大事な要素になるのでしょうが、楽器から音を発生させるという観点で)気持ちの入れ具合が1パート減る分難しくなると思うのですが、John Scoの入魂ぶりには凄まじいものがあります。聴くところによると人柄も大変フランクな方だそうで、芸術的表現の発露がたまたまギターなのであって、彼はどんな楽器を自分のボイスとしようと自己を確実に出せたのでは、と思います。
その後はバンプを用いてドラムソロ、そして締め括りを行うべくフロントふたりによる短いスパンでのバトルがあり、ラストテーマへ、最後まで大変密度の濃い構成のナンバーに仕上がりました。
John Scofield

3曲目は本作のハイライト、Hoagy Carmichael不朽の名曲Stardust(クリックして下さい)。当時Liebmanが取り上げた事がとても新鮮に感じたのは、どこかに時代がジャズを過去のものと決めつけた風潮があったからのように思えます。ここでは彼による斬新なアレンジが施されたフレッシュな、この曲をリニューアルするかのように演奏されており、しかしStardustの魅力は全く損なわれずむしろ曲の妙味を存分に炙り出す事に成功しています。各人のソロ、的確なバッキング、構成がバランス良く折り重なり、この曲の代表的な、そしてエバーグリーンの演奏と相成りました。
テンポはミディアムスローに設定され、ドラムはブラシではなくスティックを用い、フロントによる印象的で色気あるアンサンブルと良く絡み合い、ベースはホーン側のキックに寄り添い、途中からギターが怪しげでいてスパイシーなラインを奏でます。
メロディ先発は日野さん、この手の旋律は彼の十八番です!Liebmanがオブリを付けつつハーモニーにも回り、柔軟にアンサンブルを厚くしています。続いてテナーがメロディ担当、「毒を放つ色気」とでも表現しましょうか、このテイストが堪りません!日野さんがバックで同様に対応し、その後担当が入れ替わりながらメロディとアンサンブルが進行し、バンプを経て日野さんのソロがスタートします。ブリリアントな音色と豊富な付帯音、イマジネーション、スペースを生かしつつ音量のダイナミクス、音域の上下を駆使したブロウは実に説得力に満ちています!
バンプのアンサンブルを経てJohn Scoのソロ、この妖しい雰囲気は一体どこから湧き上がるのでしょう?曲想に対する猛烈なイメージとインプロビゼーションの発露とのせめぎ合い、時折聴くことの出来るコードプレイ、オクターブ奏法、テーマメロディを引用する際のレイドバック感、全て高次元で一体化し、「ダンサブル」な音符が合わさった結果リスナーを桃源郷に誘うが如しです!
そしてリーダーの登場です!John Scoとはアプローチの異なる変態ぶりを思いっきり聴かせていますが(爆)、音楽的に高度な次元でのプレイは言うまでもなく、フリークトーンを交えた効果音的奏法もここぞと言う場所に入り、ストーリー展開を巧みに行います。日野さんがこれまたハイノートでのトリル、McClureと Nussbaumも相応しい対応を熟知しているが如きプレイで場を盛り上げ、バンプではクインテットが一体化した壮絶な盛り上がりへ!ラストテーマは何事も無かったかのように日野さんがクールにテーマ奏を開始、Liebmanにスイッチしエンディングに向けバンプを何回かリピート、NussbaumもElvin Jonesライクにヘビーなリズムのフィルインを繰り出します。エンディング部も一層クールに音量を下げ、心地よさを伴ったリタルダンドを経てFineです。ライブでの演奏展開は時間の制約がないので、きっとここでの何倍も深い世界に到達していた事でしょう!聴いてみたかったです!
Hoagy Carmichael

4曲目ラストを飾るLiebmanのオリジナルCliff’s Vibes、こちらにも自身の解説があります。「was written for a child I met, who though he could’t talk due to an illness, still sent out very strong vibrations. This is one of the most bebop oriented tunes I’ve written. It’s all about chord and lines.」
その子供の名前がCliff君なのでしょうが、話をする事が出来ないにも関わらずLiebmanに強力なバイブレーションを与え、作曲行為にまで導いたのは驚きです。
これまでに書いて来た曲の中で、コード進行とメロディラインから最もビバップ志向ナンバーの1曲とありますが、ビバップというよりも特にメロディラインから個性的なモーダル・チューンとして聴こえます。これまた彼の使う用語〜ビバップの定義、もしくはイメージに隔たりを覚えますが、誰もが同じ感じ方をする必要はなく、むしろ異なっている事が大切なのかも知れません。
それにしてもオリジナル・チューンを作曲者本人の解説と共に鑑賞できるのは、音楽に一層の広がりを感じることが出来、ジャズ〜音楽ファンにはとっては大きな喜びです。
いや〜カッコいいナンバーですね!リズム隊の緻密かつ一体化したグルーブが素晴らしいです。ソロの先発はMcClureのアルコから、この時点でJohn Sco, Nussbaumのふたりは聴き応えのあるバッキングを繰り出しています。McClureはごく自然にwalkingに移行してギターソロ続きます。シングルノート・オンリーでのプレイなので、ホーンライク感が一層際立ちます。そしてトランペットソロへ、リズムに端正に乗りつつ、テクニカルに、決して自身のウタを忘れずメロディアスに熱くブロウします。ラストはLiebman、変幻自在なオリジナリティ溢れるアプローチがこの人の特徴ですが、案の定ここでも存分に発揮の巻です!途中ここぞと言うところでギター、ベースが演奏をストップし、テナーとドラムのデュオとなりますが、とんでもないテンションです!トランペットの合いの手も一役買っています!リズム隊戻りつつ、更なる高みを目指して盛り上がっています!その後ドラムソロ突入、ラストテーマを迎え大団円です!
David Liebman Quintet: Terumasa Hino, Adam Nussbaum, David Liebman, John Scofield, Ron McClure

2021.02.23 Tue
今回はBob Mosesの1979年8月録音のリーダー作「Devotion」を取り上げたいと思います。当時の彼のレギュラー・クインテットによる演奏、80年にレコードでリリースされ、96年CD化に際しオリジナルテイクに全く遜色のない未発表テイクを3曲追加収録し、Bob Moses Quintetの全貌を新たにした素晴らしい仕上がりの作品です。
Recorded on August, 1979 at Platinum Sound, Bed-Stuy, Brooklyn, N. Y.
Engineer: David Baker
Remixed on 1994, Boston, MA
Engineers: Max Rose, Ben Wittman and Bob Moses
Producers: Bob Moses and Ben Wittman
Executive Producer: Flavio Bonandrini
Label: Soul Note
Cover Painting: Bob Moses
cor, perc)Terumasa Hino ts)David Liebman p)Steve Kuhn el-b)Steve Swallow ds)Bob Moses
1)Autumn Liebs 2)Heaven 3)Radio 4)Snake and Pigmy Pie 5)St. Elmo 6)Portsmouth Figurations 7)Christmas ’78 8)Devotion
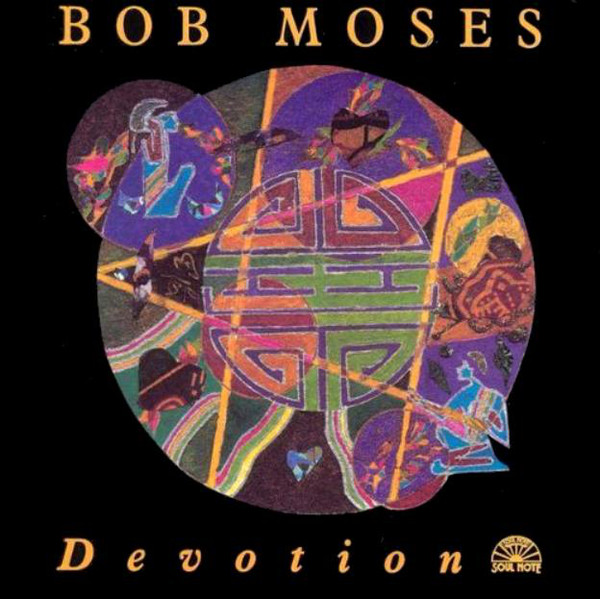
「Devotion」レコード時リリース「Family」のジャケット、そしてそこで用いられていたイラストの元となっている写真がこちらです。

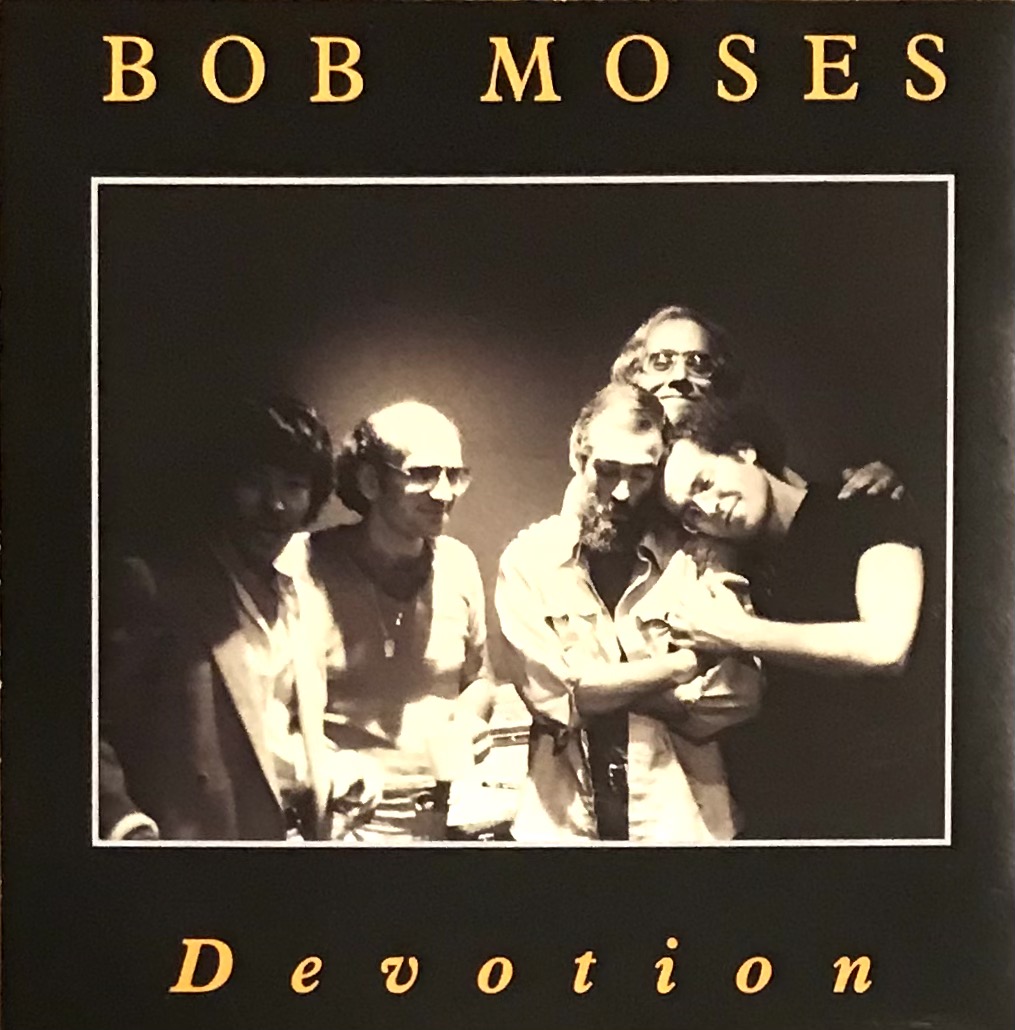
左からTerumasa Hino, David Liebman, Steve Swallow, Steve Kuhn(背が高いです!), Bob Moses。ミュージシャンの親密さ、音楽的信頼関係が手に取るように伝わって来る写真、MosesはSwallowにぞっこんですね!さぞかし充実したバンド活動を展開していたことでしょう。トランペット、テナーサックスの2管編成によるクインテットはジャズ黄金のフォーマット、メロディをユニゾンで吹いて良し、ハーモニーに至っては互いにない音色成分を補って余りある豊かなアンサンブルを聴かせます。フロントふたりの他の追従を許さない充実ぶりと、コンビネーション抜群のリズム隊とのインタープレイがこのバンドの売りと言って良いでしょう。
日本が世界に誇るトランペッターTerumasa Hino(実際にはコルネットを吹いています)の独創的でイマジネイティブなスタイル、彼のソロにはストーリー性、メッセージが必ず込められ、ジャズ・トランペッターの宝庫米国内において全く遜色なく、寧ろ誰風でもないオリジナリティを存分に聴かせています。75年から音楽活動拠点を米国に移し、八面六臂の活躍を繰り広げます。当クインテットの他、David Liebman Quintetにも参加し79年米国録音「Doin’ It Again」(ここではStardustの名演奏が光ります)、80年7月14日オランダ録音「If They Only Knew」と立て続けに名盤に加わります。


テナーサックスのDavid LiebmanはElvin JonesやMiles Davisのバンドで培われた音楽経験を活かして、オリジナリティを確立させました。ごく端的に述べるならばElvinからはタイムの重要性(Elvinの伸び縮みするリズム、ゆったりとしていながらスピード感のあるグルーヴ、史上有数のたっぷりとした1拍の長さに柔軟に適応する)、Milesからはサウンドに対するラインの構築、展開(共演中Miles自身に如何に納得できるアドリブ・ラインやストーリーを確実に提供できるか)を仕込まれたように推測しています。John Coltraneを敬愛する彼、スタートラインにはテイストとしてのColtraneが存在しましたが、その後の精進、研究・研鑽、努力の賜物でしょう、全く独自のセンスでのテナー表現法を獲得し、誰にも真似の出来ない芳醇、枯れた味わいと付帯音豊富な音色、構造的で知的なインプロビゼーション、しかし時として一切の理性を排除したかの如き炸裂プレイも聴かせ、表現者としての森羅万象をアピールしています。
彼のユニークなオリジナル・ナンバーの収録や、アルバム・プロデュース力を活かしつつ色々なカラーを配した作品群の量産ぶりには目を見張るものがあり(数多くリーダー作をリリースしています)、やはり多くのミュージシャン作品へのサイドマン参加も強力な自己表現の発露を感じます。Terumasa Hinoの作品には79年「City Connection」80年「Daydream」と互いの返礼のように参加しています。


フュージョンブーム真っ只中の80年、ジャズファンにとって70年代から夏の風物詩になっていたLive Under the Sky ’80が、7月に田園コロシアムで5日間開催されました。この時の出演者中、目玉はやはり当時ブレークし彼の音楽生活の中で何度目かのピークを迎えていたTerumasa Hinoのグループ、メンバーはLiebman(ts,ss), Anthony Jackson(el-b), John Tropea(g), Gerry Brown(ds), Leon(key) & Janice(vo) Pendarvisらに日本人のホーンセクションが加わり、Still Be Bop, Late Summer, Antigua Boyなど新作Daydreamのナンバーを中心に演奏していましたが、その時のLiebmanの凄まじいまでの絶好調ぶりと言ったら!これは超弩級テナー奏者を乗せた黒船来航!浦賀の港から田園調布に直行です(笑)!
特にテナーサックスのあまりにもエグエグな音色とプレイに「なんて汚い音だろう!」と本気で感じました(汗)。雑味成分、付帯音の尋常ではない豊富さによるダークで枯れた複雑なサウンドは、当時の僕の耳では全く理解不能の音色でした。
この時使用していたテナーサックス本体はYAMAHAから借り受けたゴールド・ラッカー、ピカピカに輝いていたこの楽器からどうしてあんな凄まじい音が出るのだろう、ラッカーのハゲまくったビンテージ楽器から出るような音だと、遠くを見つめるように感じました。マウスピースはOtto Link Metal Florida Modelを9番か9★にリフェイスしたもの、リードはLa Voz Medium HardかHardをトクサで調整して使っていました。彼はここ何年もツアーにはソプラノサックスだけを持参し、テナーはマウスピース以外現地調達しています。80年当時から既にこのシステムを用いていた様ですね。自分の楽器ではないにも関わらず、これだけの音色で鳴らし、テクニカル的に見事にコントロール出来るのは奏法を極めている以外の何物でもありません!
彼曰く「ピアニストは世界中どんな場所に行ってどんな状態のピアノを弾いても、最上の音を出さないとならないだろ?サックス奏者も同じで、どんな楽器を吹いてもベストな音を出せるように自分の奏法を洗練させておかなければならないんだ。」相当偏った持論ですが、一理あると思います。youtubeで彼の演奏を観るとその都度様々なテナーを使ってライブを行っています。要は旅先で楽器をレンタルしているのですが、素晴らしい音色でプレイしている時もあれば、明らかにこの楽器は調整不足だろうと思われるクオリティの鳴り方の場合もあります。その時にはテナーを諦め、ソプラノ1本で最後まで通す様です。
Liebmanにたっぷりとソロスペースを与えていた日野さん、彼の演奏はもちろん人柄も愛してやまない気持ちが伝わってきました。以下のエピソードにも表れています。日野さんがステージで彼を紹介する際に「テナーサックスはDavid Baker!」彼流のジョークで、ふたりの演奏を度々録音していた彼らの親しい友人でもあるレコーディング・エンジニア(本作も担当しています)に引っ掛け、わざと名前を間違えていたのですが、いきなりの展開に全く意味の分からない聴衆のシラっとした感じや(汗)、Liebmanのはにかんだようなポーズを良く覚えています(笑)。
別日には今は亡きChick Corea率いるグループやJohn McLaughlin, Larry Coryell, Christian Escoudeのギター3人による演奏、Stanley Clarkeのバンドや出演者全員によるジャムセッション、現在進行形のジャズを学生の身でたっぷりと堪能出来ました。

リーダーBob Mosesのバイオグラフィーを紐解くことにしましょう。1948年1月28日New York City生まれ、64年から1年間Roland Kirkのバンドにビブラフォン奏者として参加します。アルバムとしては「I Talk with the Spirits」、おそらく彼の初レコーディングだと思われます。ジャズ界で最も個性派ミュージシャンのひとりと共演した事による影響は、10代の若者に計り知れないものがあったでしょう。以降の彼の音楽活動の方向性を間違いなく決定付けました。

66年Larry CoryellのバンドThe Free Spirits、67年から69年までGary Burton Quartet、その後もCarla Bley, Dave LiebmanのバンドOpen Sky, Pat Metheny, Michael Gibbs, Hal Galper Quintet, Gil Goldstein, George Gruntz, Emily Remlerなどの硬派なリーダーのもと、豊かな音楽性を披露しています。彼自身のリーダー作も現在までに20枚近くリリースされ、オリジナルナンバーを中心に比較的大きな編成による演奏で、独自の音楽性を追求しています。
楽理派の彼は「Drum Wisdom」というドラムの教則本も出版しており、現在はFree Download状態で後続のミュージシャンに貢献しています。本作ジャケットのイラストと同様、こちらも本人の筆によるものです。
MosesのドラミングにはRoy Haynesのスタイルが基本にありますが、楽曲のカラーリング、共演者各々への方向性を違えたレスポンスの巧みさ、その瞬発力、オリジナリティを感じさせる自作曲の高度な音楽性、いちドラマーではなくトータルなミュージシャンとしての姿勢を作品を通して感じることが出来ます。またサイドマンとしてプレイした時の、リーダーの音楽への溶け込み方と自己主張のバランス感も絶妙です。
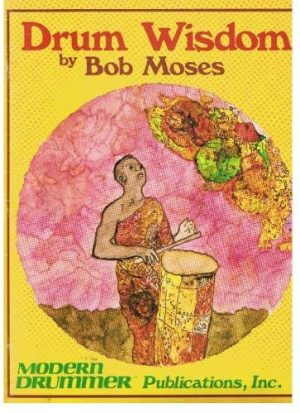
余談ですが本作が録音されたPlatinum Sound StudioはNew York, Brooklynの中心部Bed-Stuyに位置します。多くのジャズミュージシャンのレコーディングに愛用されました。地名はBedford-Stuyvesantの略称なのですが、黒人、ヒスパニック、アジア系が住民の9割近くを占める地域で、Spike Lee監督の89年映画「Do the Right Thing」の舞台になりました。こちらは黒人の人権運動をテーマに人種差別と対立、衝突をLee独特のユーモアのセンスを用いて表現した素晴らしい作品です。

それでは収録曲に触れて行きましょう。1曲目MosesのオリジナルAutumn Liebs、お察しの通りスタンダードナンバーAutumn Leaves〜枯葉のタイトルを捩ったもの、LiebとはLiebmanの愛称です。実際に枯葉のコード進行を用い、キーは全音下がったFマイナーでMoses独自の素晴らしいメロディラインにより、ジャジーでコンテンポラリーな名曲に仕上がりました。いわば替え歌状態、他のミュージシャンにも枯葉のチェンジを使って作曲されたナンバーがあり、思い付くものでテナー奏者Billy Harperの79年作品「Knowledge of Self」収録のナンバーInsight、コード進行を多少変えてありますが、ドラマー古澤良次郎氏の同じく79年録音アルバム「キジムナ」収録のエミ(あなたへ)。


なんとゴージャスなサウンドによるメロディ奏でしょうか!2管による抑揚の素晴らしいコンビネーション(テナーのサブトーンがたまりません!)、Kuhnのバッキングが密濃に絡み合い、Mosesのカラーリングの絶妙さはコンポーザー、リーダーならでは、音の選択にさすがのセンスを感じるSwallowのベース、全てが予めアレンジされたかの様な合わさり具合、難易度の高いパズル制作を完璧に行ったかの如きプレイですが、予定調和ではない間違いなく自然発生的に音が集約された演奏、瑞々しく全ての音がフレッシュでプリプリしているのです!
ソロの先発はLiebman、幾重にも異なる色合いのトーンが組み合わさったかのような深い音色からは、伝統的なテナー奏者のテイストも聴き取ることができますが、他には無いコクや雑味成分が加わり一聴Liebmanと判断できる個性を発揮しています。さすが知的作業に長けたユダヤ系プレーヤー、トーンを徹底的にクリエイトしています。ソロのアプローチ、いやー実に素晴らしい!申し分のないストーリーの構築感、音形選択の巧みさ、テンションの用い方のスリリングなこと!加えてタイム感のゴージャスさ!このプレイを受けて立つリズム隊、テーマ時に提示したアプローチを基本に、放置する部分はひたすらクールに伴奏し、テナーソロが1コーラス目第1楽章的な展開「序奏」、2コーラス目第2楽章の如き疾走感あるストーリー「飛翔」を語り、一度落ち着いて3コーラス目第3楽章に入り、まとめ上げるべくMoses, Swallowの猛攻があってソロを終えるに相応しく、何事もなかったようにゆったりと着地〜「大団円」となります。Liebmanの音楽史上有数のクオリティを持つ演奏だと思います。
続く日野さんのソロ、Mosesがグルーブに変化を持たせるべく4拍目にリムショットを入れ始めます。スペーシーに、大胆に抑揚を付けながらソロを展開し、グロートーン、突如として高音域でのトリル、リズム隊とのカンバセーションを試みるべく様々にアプローチし、確実性を持ってレスポンスするMoses、そしてKuhnのバッキングが切れ味鋭く入り込みます。こちらも見事なストーリーテラーぶりを発揮しました。
Kuhnのソロはフロントふたりとは異なったテイストを持たせるべくでしょうか、ラグタイム〜スイング的コーニーな雰囲気で開始されます。端正で明確なピアノタッチは背の高い、腕が長く、掌の大きなピアニストならではのもの、強力です!そして表現したい事項が猛烈に溢れ出ています!ドラムは1コーラス目ブラシに持ち替えましたが、その後の展開を予期し2コーラス目から再びスティックへ。やはり持ち替えて正解でした(笑)、Kuhn3連譜を多用し超絶を聴かせつつ、更に3コーラス目からは左右の手で全く異なるアプローチを展開、それに伴いMoses, Swallowのふたりは”やわくちゃ”状態になりそうでしたが(汗)しっかりと踏み留まり、キメのフレーズを伴ってラストテーマに突入です。
Bob Moses

2曲目はDuke Ellingtonの知られざる名曲Heaven、なんと美しく、気品、雰囲気のある曲でしょう!Heavenの言葉自体に色々な意味がありますが、Ellingtonはどの意味のイメージを表現したのでしょうか。それにしてもMosesの選曲センス、そして演奏の形態に敬服してしまいます!
16小節単位の構成、1コーラス目は2管はユニゾンで、2コーラス目はLiebmanがオブリガードに回り、3コーラス目からコルネットソロへ、その後ろでもテナーのオブリが続きます。Kuhn, Swallowのバッキングもキレキレです!その後は単独でのコルネットソロに続き、コーラス終わりのフレーズに再びテナーが参加、グッと引き締まりますね!
ピアノソロはレイドバック感、そして「大きく歌う」イメージが実に提示されています。倍テンポのスイングに変わりリズミックに、ゴージャスに、何よりメロディックにアドリブが展開され、ソロ中に再びホーンのオブリやメロディが効果的に入り、ムードを更に高めます。
ラストテーマに入ってピアノはバッキングに回りますが全くエネルギーを失わず、エキサイティングに継続します。1コーラス演奏されドラマチックにリタルダンドしてFineです。この演奏こそBob Moses Quintetの本領発揮と感じています。
Steve Kuhn
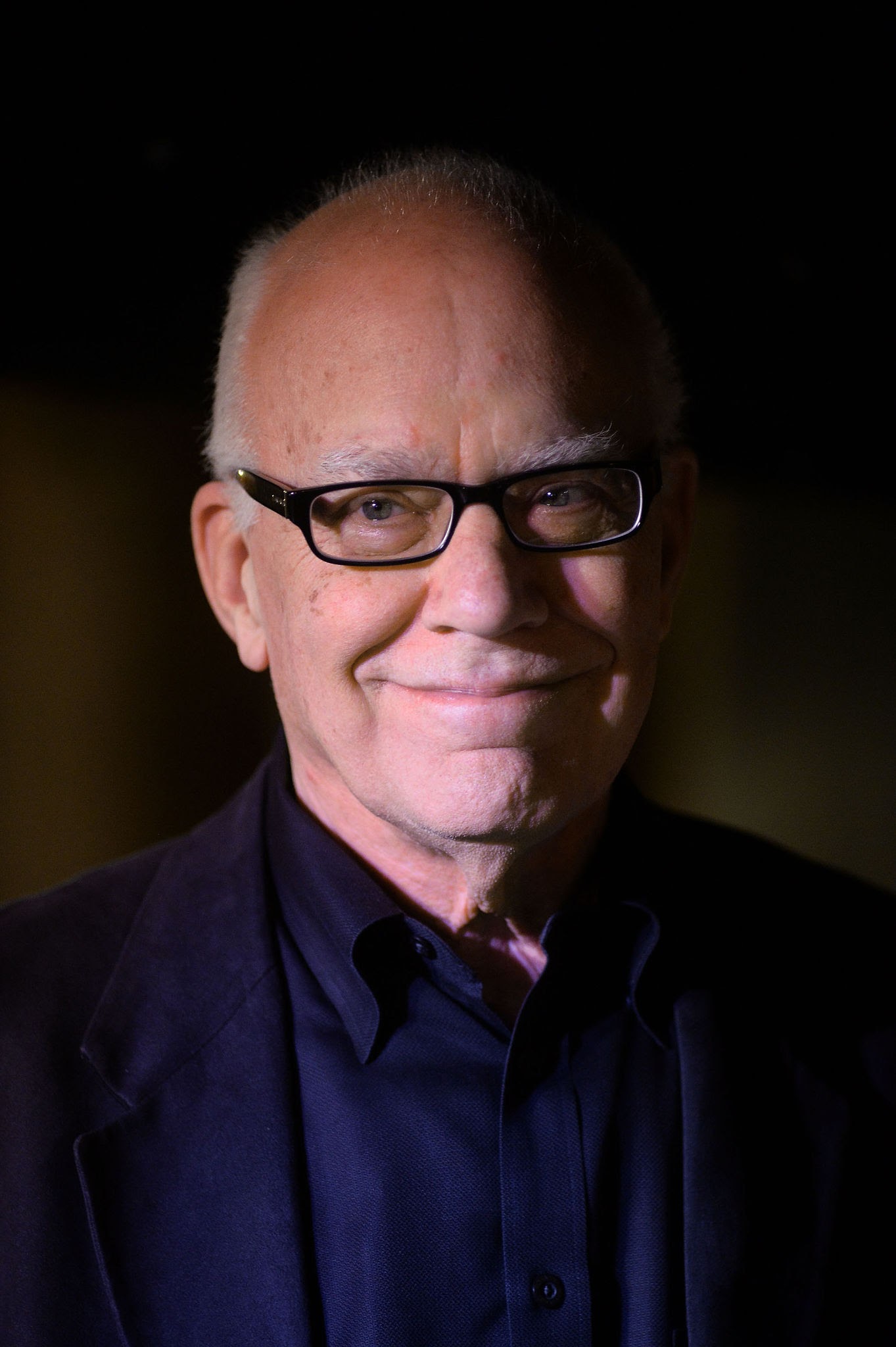
3曲目SwallowのナンバーRadio、こちらも素晴らしいナンバーです!レコード発売時にこの曲が未収録であったのが信じられません!早めのスイング・ナンバー、ポピュラーな32小節構成ですが、同じモチーフを繰り返す部分は存在せず、A-B-C-Dフォーム、しかもメロディラインが8小節単位を跨ぎ、複雑に成り立っています。自然に耳に入ってくるので一聴難解な作りとは感じさせません。
ベース、コルネット、ピアノ、テナーと全員コンパクトに淀みなくソロが続きますが、やはり難しい楽曲なのでしょう、手枷足枷感を感じさせる部分も若干あり、なかなか自在にならないもどかしさも演奏から聴き取ることが出来ます。しかしLiebmanはひとり異彩を放ち、スインギーにして正確な16分音符による超絶テクニカルフレーズの洪水、この人のまた違った側面を垣間見ることが出来ました。テナーソロ中のコルネットのバックリフが必然を感じさせる場面で登場、これはエキサイティングです!伴奏はリズム隊だけの特権ではないぞ、と言いながら吹いているように思えました。
Kuhnの常に場を活性化させるバッキング、Swallowの自然体でいてソロイストを鼓舞するラインの連続、そしてリーダーMosesの抜群のセンスによる伴奏なしにはこの演奏は絶対に成り立ちません!Lebmanのソロ後、実にナチュラルにラストテーマを迎えます。
Steve Swallow

4曲目Snake and Pigmy PieはMosesのオリジナル、この演奏も追加テイクになります。4分の5拍子と8分の7拍子が連続する複雑なリズムは延々と続くユニークなベースライン、印象的なピアノのコンピング、2管のスペーシーにして抑揚に満ちたメロディラインに裏付けされ、曲名通りの怪しげな世界を構築して行きます。Mosesの作曲センスは実に多面的です!長いテーマ後、ドラムだけを相手に2管が互いを良く聴き、一方が主体、従属を繰り返しながらソロを取ります。ライブではさぞかし物凄い展開を聴かせた事でしょう!このリズムの上でドラムソロも行われます。皮ものにエフェクターを施しているので変わった響きを聴くことが出来ます。途中パーカッションが鳴っていますがおそらくフロントふたりで楽しげに演奏しているのでしょう。ラストテーマはさらに色々な事象が繰り広げられていますが、意外にあっさりとFineを迎えました。
5曲目St. ElmoもMosesのナンバーにして追加テイク、美しいバラードです。ミュートを施したコルネット、テナーの実に息のあったユニゾンによるメロディは、リタルダンド、アテンポを繰り返しソロ中には長いフェルマータも用いられ展開して行きます。日野さんはミュートによるバラード奏が昔から大変素晴らしいですが、ここでも本領を発揮しています。フェルマータ後今度はピアノソロ、ウネウネしつつリズムにしっかりと纏わりつくタイム感でラインを提示し、再びフェルマータ、コレクティブ・インプロビゼーション後にラストテーマへ、レギュラーバンドならではの演奏方法によるバラード、作者Mosesのやり方も、コンセプトもあったでしょうが、メンバーで様々にアイデアを出し合った結果の演奏のように感じました。
Terumasa Hino

6曲目Swallow作のPortsmouth Figurationsは本作最速のナンバー、いや〜これはまたまたムチャクチャカッコ良いナンバー、演奏です!ベースとドラムのコンビネーションは全く信じられない相性の良さです!写真にあるSwallowの肩にもたれ掛かるMosesの気持ちが痛いほどに分かる抜群の音楽、リズム的相性の素晴らしさから、さぞかしMosesは何度も「My Soul Bother, Steve !」と叫んでいた事でしょう!
タイムの構図としてはMosesのシンバル・レガートが少し前に位置するon top、Swallowが少しだけ後ろに位置します。コルネットが先発ソロ、こちらも超アップテンポにも関わらず素晴らしいタイム感とグルーブ、そしてバーニング!少し間を置きLiebmanのソロがスタートします。3曲目Radioで聴かれた16分音符の延長線上、正確でスインギーな8分音符による圧倒的な音空間、怒涛のソロです !コルネットの合いの手も効果的に入りドラムソロへ続きます。フレージングのテイストとしてはオーソドックスですが、彼ならではのタイムの取り方、リズムフィギュアを聴かせ次第に独自の個性を発揮して行きます。「ヨッ!」と言う合図とともにラストテーマに入り難曲を完璧なまでに仕上げました!
David Liebman

7曲目Christmas ’78はMosesのナンバー、メロディアスで美しいコード進行を有し、哀愁を帯びた曲想を持つ名曲です。Bob Moses Quintetのファンであれば、ライブでこの曲の演奏を聴かずに帰りたくないでしょうね、きっと(笑)。ソロの先発は日野さん、なんとイマジネイティブな語り口でしょう!リズム隊もこれだけスペーシーに、ダイナミクスでメリハリを持たせたソロであれば、伴奏が楽しくて仕方ないでしょう!音と音の間に何もしない、敢えて合いの手を入れないで放置する楽しさ、喜びを日野さんはリズムセクションに提供していると思います。続くKuhnのメロディ、唄を大切にしたソロは異なったテイストを放ち、当然のようにリズム隊は違ったアプローチを聴かせます。Liebmanはこれまた本作中いずれとも異なる歌い回しを提示し、彼の中で鳴っているユニークな旋律の一端を初披露したかの如しです。言ってみればユダヤ的なラインでしょうか、例えばクレズマー、明るさも感じさせますが決して晴れない曇り空を抱えていると表現すべきか、育った環境、音楽的経験、自身の内面を全てストレートに表現しているのですが何処か屈曲したものを僕は感じます。でも決して悪い意味でははく、一筋縄では行かない彼の音楽表現の個性の表出と捉えています。この曲もテナーソロから見事にラストテーマに繋がり、Fineです。
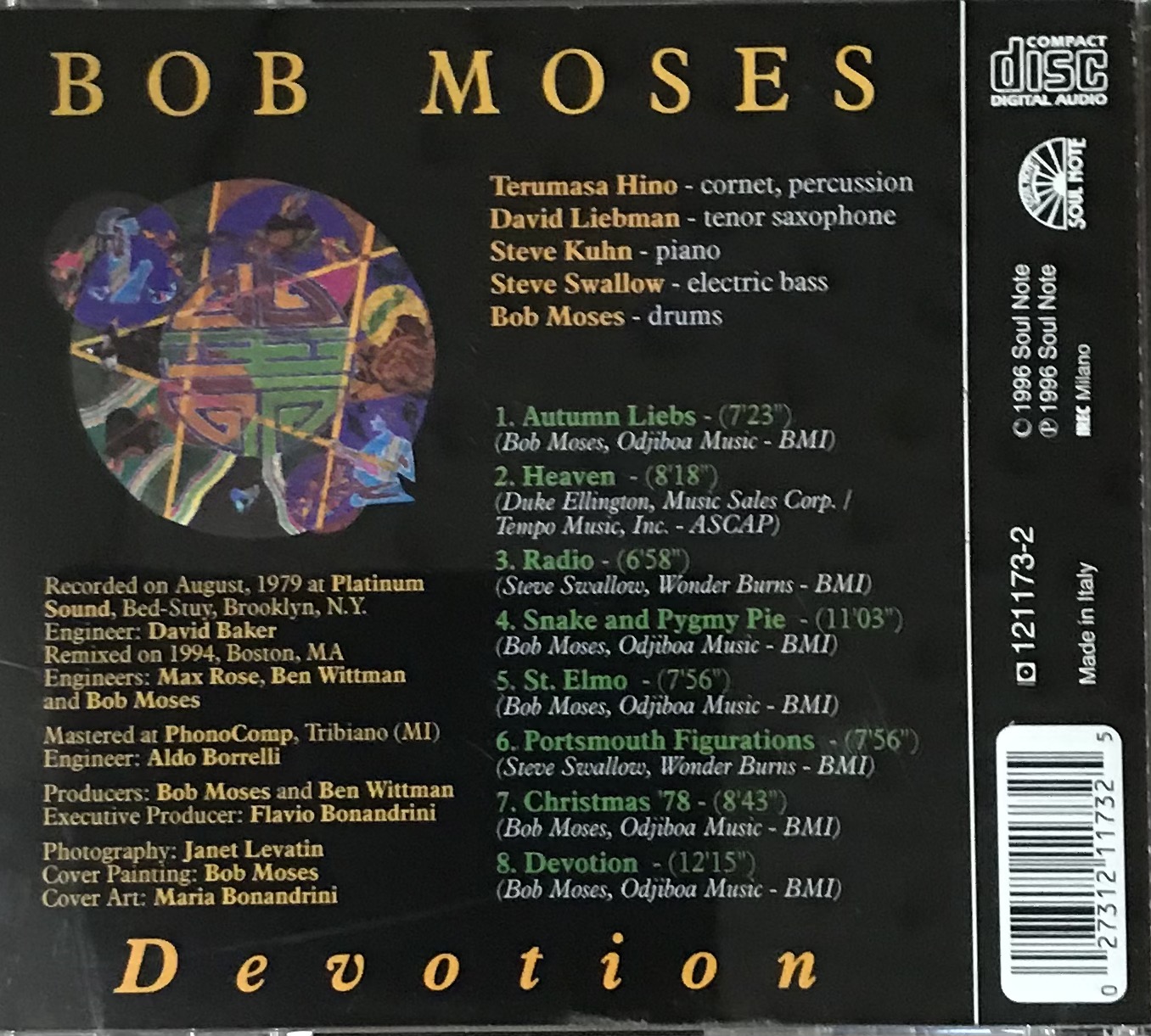
8曲目ラストを飾るのは表題曲Devotion、コルネットが一頻り内省的な表現によるアカペラを聴かせます。ラインの基本としてはマイナーのクリシェを感じさせ、付帯音の豊富さが音色に深みを加えています。その後ベースが同様にクリシェのライン演奏を開始、ドラムが加わりますが実にゆったりと、時間をかけてメロディまで到達します。2管によるユニゾンは実に深さとダークさ、そして誰かに対する哀悼の意を感じさせます。バラードから次第にリズムが明確になり、Mosesがリードしダイナミクスを表現しています。Mosesもユダヤ系アメリカ人、この曲は曲想から彼らが背負っている歴史的事象に対するレクイエムではないかと感じました。
2021.02.11 Thu
今回はSteve Swallowの79年録音リーダー作「Home」を取り上げてみましょう。全曲Swallowのオリジナルに作家であり詩人であるRobert Creeleyの詩をSheila Jordanが歌唱、朗読し、David Liebman, Steve Kuhn, Bob Moses, Lyle Maysら当時の先鋭的な共演者が素晴らしい演奏を繰り広げ、通常の歌伴とは手法が異なる、ユニークな作品に仕上がっています。
Recorded: September 1979 at Columbia Recording Studios, New York City
Recording Engineer: David Baker
Cover Photo: Joel Meyerowitz
Design: Barbara Wojirsch
Producer: Manfred Eicher
Label: ECM (ECM1159)
electric bass)Steve Swallow voice)Sheila Jordan p)Steve Kuhn ts,ss)David Liebman synth)Lyle Mays ds)Bob Moses
1)Some Echoes 2)She Was Young…* 3)Nowhere One…* 4)Colors 5)Home 6)In the Fall 7)You Didn’t Think…* 8)Ice Cream 9)Echo 10)Midnight
*(From “The Finger”)

実にセンス溢れる素晴らしいアルバム・ジャケットです。ECMレーベルは常々欧州的なテイストを基本とし、作品内容のイメージと合致する印象派的ジャケットを提供し続けています。物凄いこだわりです。米国を代表するジャズレーベルBlue Noteも同様にアートを感じさせるアルバム・ジャケットを50~60年代制作していました。いずれもAlfred Lion, Francis Wolf, Reid Milesたち制作スタッフの情熱が痛いほどに伝わります。他の主要ジャズレーベルであるRiverside, Contemporary, Verve, Impulse, Prestige, CTIにもある程度に同様の事が言えますが、ECMレーベル・プロデューサーManfred Eicherの意地にはまた格別のものを感じさせます。ECM新作がリリースされる度に次は一体どの様なジャケットを見せてくれるのだろうかと、現在でもわくわくしている自分がいます。
ただ本作においては独特のダークさ、エグさを基本とした内省的サウンド、明るいか暗いかといえば暗さの方に軍配が上がる、実はジャケットから感じさせる清潔感、クールさ、ある種の幸福感とは真逆の内容に仕上がっているように感じるのです。例えばクラシックを基本とした爽やかな、心地良いサウンドにジャズのテイストを散りばめたオシャレな環境音楽的なサウンド。ジャケットから判断すれば、こちらが作品の売り文句であっても全く違和感は無いでしょう。どこまで作為的に内容と包装の対極感を打ち出しているのかは分かりませんが、本作ほど際立ったギャップを感じさせるアルバムはそうはないと思います。Steven Kingのホラー映画の導入部とその後の展開にも通じると言っても良いでしょう。もっともHomeとは個単位の集合体、様々な価値観を持った家族構成員の日々の生活、営みには色々な側面があります。ジャケ写のパースペクティブはその現れの様な気もします。
本作録音のメンバー、彼らとSwallowの周辺の作品について触れてみましょう。まずボーカリストSheila Jordanとは彼女の62年初リーダー作「Portrait of Sheila」からの付き合い、音楽的なパートナーとして相性の良さを感じます。サイドマンとしてもいくつかの作品で共演しています。

Steve Kuhnとは生涯の共演仲間、盟友としてKuhnのリーダー作ほか実に多くのアルバムで共演しています。最初期66年作品「Three Waves」はPete La Rocaとのトリオ盤、若者たちによる初々しい演奏です。

David Liebman, Steve Kuhn, Bob Mosesとはほとんど同時期79年8月Brooklyn, N.Y.C.録音Mosesのリーダー作「Family」があります。コルネットにTerumasa Hinoを迎えたクインテット編成、実に素晴らしい演奏です!各々のメンバーが対等に語り合い、互いの音楽性を尊重しつつ大いに刺激を受け合い、丁々発止のやり取りを聴かせています。Moses, Swallow自作曲のクオリティの高さほか、Ellingtonのバラードのチョイスも良いですね。ドラマーがリーダーということでまとめ役、ご意見番としてサウンドを的確にプロデュースしており、結果バンドとしての音楽が確立された申し分ないアコースティック・ジャズの名盤です。タイトルやジャケット・デザインからもメンバー同士の結束、繋がりの強さを感じます。日野さんからこのバンドでの思い出話を聞いた事がありますが、ひとつご紹介すると車1台にメンバー5人乗車し米国内をツアーしていたらしく、車内に常に充満する煙(おそらくタバコだと思いますが…)が何しろ物凄く、辟易したという事でした。

この作品の未発表テイクを収録した事により、内容的にさらにヴァージョンアップしたのが96年リリース「Devotion」です。CDという録音媒体の、レコードよりも長い収録時間の恩恵を感じました(笑)。このバンドの全貌を垣間見る事のできる、ドキュメント性を湛えた作品にまで昇華しています。未発表演奏のいずれもが本テイクと全く遜色のないクオリティで、サウンドやリズム、テンポ、色合いが悉く異なる楽曲が配され、作品としてのバランス感が飛躍的に向上しました。さぞかしレコード・リリース時には、選曲に際しての取捨選択に苦労したことと想像できますし、追加テイクが残り物、オマケという概念を見事に打ち破ってくれた1枚です。
ちなみにここでのLiebmanの演奏は絶好調に次ぐ絶好調(テナーだけに専念しています)、信じられない次元での入魂ぶりを発揮しています。
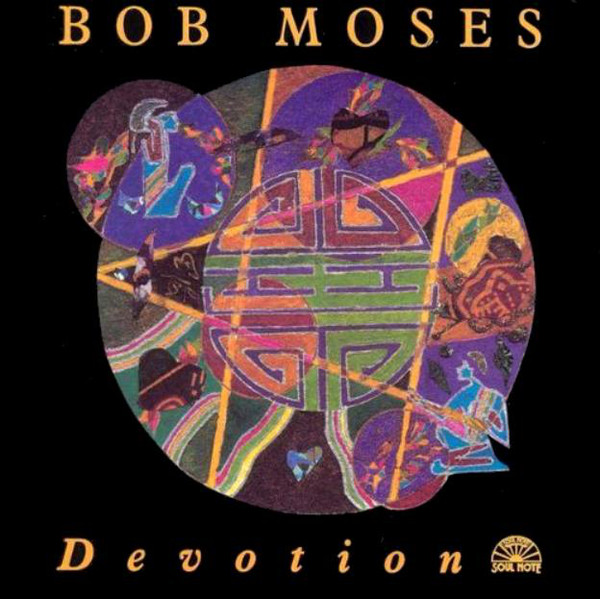
Robert Creeleyとは本作が初コラボレーションになる模様ですが、2001年8月録音作「So There / Steve Swallow with Robert Creeley」で再コラボ、Steve Kuhnとストリングス・カルテットに今回はCreeley自身のトークや詩の朗読を交えた、崇高な美の世界を構築しています。
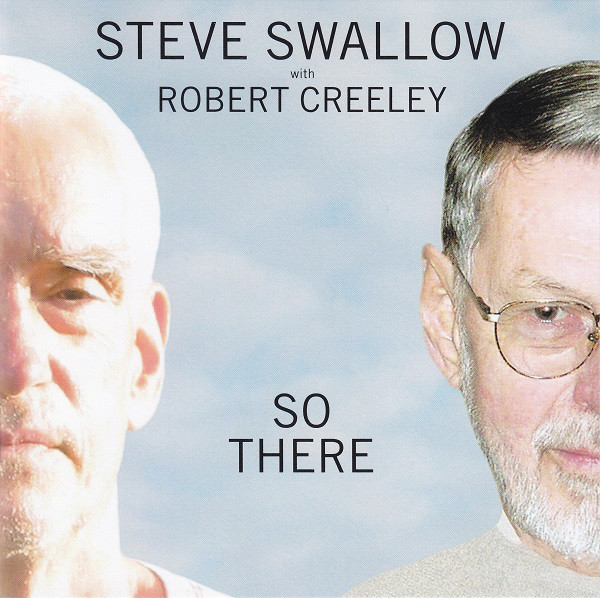
LiebmanはかつてECMから2枚リーダー作をリリースしており、73年録音「Look Out Farm」74年録音「Drum Ode」、ECMではそれ以来のレコーディングになります。2作とも70年代のジャズシーン+ECMサウンド+Liebmanの独自の音楽性がブレンドした作品で、学生の時に愛聴しました。その後もECMからリーダー作をリリースし続けて然るべきでしたが、Eicher, Liebmanともかなり個性が強い者同士、確執があったために疎遠になったという話を聞いたことがあります。本作の仄暗さはLiebmanのプレイが発するムードがかなりの要因であると思うのですが、スタジオ内でふたりの静かな相克があったようにも感じられ、これがバイアスとなり結果Liebmanの演奏にいつもとは異なる、(言ってみればより辛辣な)エグさが加わったと推測しているのですが。もしくは80年頃からソプラノサックス1本に自分のボイスを絞る事になり、テナーサックスを休止する直前、体力的にテナーを自在に吹くことが辛かった故なのかも知れません。

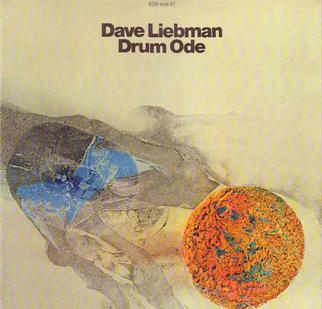
それでは内容について触れて行きましょう。1曲目Some EchoesはKuhnのピアノプレイによるオスティナートとLyle Maysのシンセサイザー、Swallowのベースの上でLiebmanがソプラノでソロを取ります。大海原を泳ぐイルカの如く水中深く潜ったり、海上に現れては跳ね回ったり、様々な動きを見せ、ひと段落したところでSheilaが登場します。スタンダードナンバーを歌唱するときとは当然ですが異なった表現を聴かせ、感情移入と抑揚が深いビブラートと相俟って強いメッセージを打ち出しています。それにしてもシンセサイザーが余りにも支配的、もう少し音量、音像が小さくても良かった気がします。
2曲目She Was Young…の歌詞はCreeleyの詩集「The Finger」からのセレクションです。ワルツナンバー、いきなりベースによる美しい音色でメロディが提示されますが、実に個性的です。ピアノのバッキング、ドラムのサポート、そしてシンセサイザーがSE風に演奏されますが、ここでは隠し味的な音量で寧ろ耳には心地良いです。その後Sheilaが短いセンテンスによる詩を朗読するが如く歌い、ピアノのソロに続きます。いや、Kuhnのタイムの取り方は実に好みです!彼の初期のプレイではタイムがラッシュする傾向にあり、演奏自体もいささかヒステリックなところが目立ちましたが、演奏経験を積み次第に成熟〜円熟の境地を迎えました。ピアノのタッチも素晴らしいですね!何年か前にマイブームで彼の演奏を徹底的に追ったことがありますが、スタイル確立後は一貫した透徹な美学が冴える、本物のプレイを聴かせています。
Mosesのプレイもジャズドラマーとして表現すべきポイント、個性を確実に発揮しています。グルーヴ、フレージング、タイム、ドラミングの音色にはRoy Haynesからの影響を顕著に感じますが、自身の個性的表現を十分に行っているので、語法としてのHaynesライクと受容することができます。

3曲目Nowhere One…も歌詞はThe Fingerから、冒頭ファルセットの如き高音域からボーカルがスタート、緊張感を伴い歌唱しますが音域が下降するにつれて音楽的な安堵感が訪れます。その後Liebmanのテナーソロ、ミディアム・スイングのリズムに大きく乗り、朗々と吹いており、音色の枯れた味わいと付帯音の豊かさからテナー奏者としてトップクラスのクオリティです。ですがここでのメッセージとしては「こうあらねばならぬ」という思いが強く聴こえ、聴き手に強いるものを感じさせます。前述の「確執」が作用しているかも知れません。続くピアノソロのレイドバック感と1拍がメチャクチャ長いプレイ、ウタを感じさせるストーリー性とは良い対比となっています。リズムセクションの好演、特にMosesのサポートの素晴らしさが光ります。

4曲目ColorsはいきなりLiebmanのソプラノソロが炸裂します。独自のスタイル、誰にも真似の出来ない個性的な音色、発情期の猫の唸り声の如きニュアンス(笑)、フレージングもトーナリティの領域を超えたところでの自在なアプローチ、バッキングのリズム隊もさすがレギュラー活動の成せる技、巧みにして緻密、Liebmanの手の内を読みつつ、音楽を何処にどう持って行けば良いのかを熟知した流れに徹していて、彼自身も逆にインプロビゼーションの展開を容易く読ませない音楽的裏切りを忍ばせています。Sheilaの短い詩の朗読後はKuhnのソロ、こちらもMosesのレスポンスが実にスリリング、Kuhnのプレイと付かず離れずを繰り返し大胆に盛り上がり、コード・クラスターを用いた粘着気質的な展開にまで及びますが、Swallowの地を這うような安定したサポートがあってこそです。

5曲目表題曲HomeはSheilaとKuhnふたりによるルパートから始まります。実に美しい歌唱、そして必要最小限にして全てが有効な音使いによる的確な伴奏、その後はスロー・スイングでLiebmanのテナーソロへ。それにしてもこの吹き方のニュアンスとイメージは一体何でしょう?まるで漆黒の暗闇の中で思いっきり大声で不平不満を述べ、そのパワーで音空間をねじ曲げているかのようなアプローチです(爆)!テナーの音程感にも独特のものを感じます。精神状態が良く無い時に聴くことは決してオススメしません(汗)。一体どんな”Home”なのでしょう?ひょっとしたら事故物件の類いかも知れません(涙)

6曲目In the Fall、今度はピアノとベースによるパターンの上でのMosesのドラムソロから開始します。皮ものを中心としたドラミングはそのフレージングからHaynesの他、Tony Williamsのテイストも感じさせます。収束したところにLiebmanのテナーによるメロディ奏、ソロにそのまま突入しまるで咆哮状態、2000年の歴史〜ユダヤ人の情念を一人で全て背負ったかのようなエグさを感じさせます。Sheilaの歌が入り、暗がりにやっと一筋の光明が差し込んだかの様です。シンセサイザーとテナーのユニゾンのメロディも演奏され、次第にボーカルとも合わさりFineへと向かいます。演奏で聴く者をここまでの気持ちにさせることの出来るパワーに、良くも悪くも圧倒されます。

7曲目は再びThe FingerからYou Didn’t Think…、ボーカルからスタートし、テナーが裏メロディのようなオブリガードを入れつつ、ソロに移行します。ここでの表現にも凄まじいものがあり、一体どんな精神状態でアプローチしているのか、常人には理解し難い次元です。テナー・マエストロとして高度なテクニック、サウンド・メイキング、余人の追従を許さない深い表現を行っていますが、曲想とも離れ気味のテイストを受け入れるのはいささかハードです(彼の中ではインサイドなのでしょうが…)。それともテナーサックスを封印してソプラノに賭けるとの決意のもと、とことん自己表現をやっておこうと言う事 だったのかも知れませんね。ユダヤ系Coltraneスタイル・テナー奏者の両巨頭、Michael Brecker, Steve Grossmanのふたりとは何度も会って色々な話をしましたが、もうひとりの巨頭Liebmanとは未だ会ったことはありません。会う機会があれば尋ねたいことは山ほどありますが、この作品のアプローチについては是非質問してみたいと思っています。

8曲目Ice CreamはMaysのシンセサイザーを携えてSwallowのメロディ奏からスタートします。7thコードの4度進行が印象的ですが、実はSwallowのコンポジションには多く用いられています。軽快なスイングのリズムのもと、Sheilaのボーカルも冴えています。Kuhnがソロを取りますが、ピアノ・トリオのコンビネーションが素晴らしいです!エレクトリック・ベースによる早めのスイングではボトム感が希薄になりがちですが、ここではその分をMosesのバスドラムがしっかりと補い、バランスを取っています。この曲の演奏が本作中最もスイング感に満ちています。

9曲目Echoは再びLiebmanの登場です。ひとしきりOne & Only、彼の世界をリズム隊を巻き込んで提示し、Sheilaのボーカルに繋げます。その後のピアノソロもウネウネ、ウニウニとKuhn節を披露、つくづく濃い芸風の人たちです(汗)。それにしてもプレイヤー互いに気心が知れていると言うのは素晴らしいですね!彼らが演奏を楽しんでいるのがストレートに伝わってきます。
10曲目ラストを飾るのはMidnight、SE風にMaysのシンセサイザー、Kuhnの弾くピアノの高音部が深夜の静寂を予感させます。不安感がよぎるコード・ワークの後Sheilaの朗読が開始されますが、メロディに施された複雑なコードが、夜のしじまから押し寄せる不安感をイメージさせます。短くエピローグ的に演奏されFineとなります。
2021.02.01 Mon
今回はボーカリストSheila Jordanの62年録音、初リーダー作「Portrait of Sheila」を取り上げましょう。彼女は現在92歳(!)、音楽活動は特に行ってはいない模様ですが、ビバップ勃興の頃よりCharlieParkerを始めとするジャズジャイアンツと親交を持った、貴重なジャズシーンの生き証人です。そのParkerをして彼女は100万ドルの耳を持つシンガーと紹介されたそうですが、大変に名誉な事です。本作はインストルメンタル・ジャズ名門Blue Note Recordsからのリリース、Label中数少ない女性ボーカリスト作品の1枚です。編成もギタートリオにボーカルと言うシンプルさ、後年エレクトリック・ベースの第一人者となるSteve Swallowがここではアップライト・ベースで参加しています。
Recorded: September 19 and October 12, 1962 at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Label: Blue Note Produced by Alfred Lion
vo)Sheila Jordan g)Barry Galbraith b)Steve Swallow ds)Denzil Best
1)Falling in Love with Love 2)If You Could See Me Now 3)Am I Blue 4)Dat Dere 5)When the World Was Young 6)Let’s Face the Music and Dance 7)Laugh, Clown, Laugh
8)Who Can I Turn to Now 9)Baltimore Oriole 10)I’m a Fool to Want You 11)Hum Drum Blues 12)Willow Weep for Me

Sheila Jordanは1928年11月18日Michigan州Detroit生まれ、15歳の頃から地元のナイトクラブで歌手、ピアニストとして活動していました。彼女はCharlie Parkerのオリジナルに歌詞を付けて歌うコーラスグループのメンバーでしたが、Parkerが当地を訪れた際にメンバー一同で訪ね、彼にその場で歌って欲しいと頼まれた経験をしています。51年にNew Yorkに移り、Lennie TristanoやCharles Mingusにハーモニーと音楽理論を学び、かねてからParkerの音楽に心酔し師と仰いでいた彼女は、熱心にプレイを研究したそうです。さぞかし頻繁にライブに足を運んだ事でしょう、彼が亡くなる55年まで友人としての関係が続き、兄のように慕っていたとも言われています。52年にはParkerバンドのピアニスト、Duke Jordanと結婚、娘Tracyが生まれます。ですが幸せな日々はそうは長く続かず、Dukeの薬物使用量が増えた事により62年破局を迎えました。晩年のParkerの薬物使用もかなりの頻度だったに違いないのですが、兄と亭主では自ずと処遇も変わると言うものです(笑)
とあるインタビューでNew Yorkに移り住んだのは何故ですかという質問に対し、彼女は「私がBirdを追いかけたからよ=Chasin’ the Bird」と答えました。ParkerのオリジナルChasin’ the Birdは貴女のために書かれたのではないかと言われていますが、と尋ねられると「私は知らないの。どうしてそんな噂話が一人歩きしたのかしら」とも答えていますが、それは十分に考えられる話です。
彼女はNew York移住後、昼は秘書やタイピストとして働き、夜はGreenwich VillageのジャズクラブThe Page Three Club等でピアニストHerbie Nichols、以降も長きに渡り共演関係を保つSteve Kuhn達と演奏活動を行いました。夜クラブで歌う事が出来ない場合は昼間教会で歌う事を代用としながら、娘を育てるために20年間ほぼOLに専念し、演奏だけに専念できるようになったのは50歳を過ぎてから、80年代以降の話です。実際それ以前から断続的ではありますが音楽活動を続けていて、本作初リーダー以降第2作目「Confirmation」は13年後の75年リリース、そのときTracyも22歳、おそらく社会人として世に出たのでSheilaにも余裕が生じたのでしょう。

初期の彼女の演奏で特筆すべきものの一つとして、独自の音楽理論を展開するピアニスト、アレンジャーGeorge Russellのアルバムへの参加が挙げられます。62年8月録音「The Outer View」収録のYou Are My Sunshine、3管編成を生かしたアレンジの曲中、全くのアカペラで囁くように始まり、バンドが加わり次第にシャウトするが如く朗々と独白する様には、既に豊かな音楽性を感じさせます。ここでもSteve Swallowのコントラバスの活躍が印象的です。
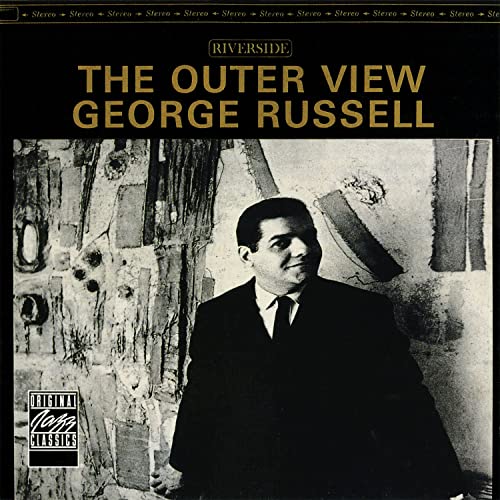
参加メンバーにも簡単に触れてみましょう。ギタリストBarry Galbraithは19年12月生まれ、Stan KentonやClaude Thorhillビッグバンドでのツアーほか、Miles Davis, Michel Legrand, Gil Evans, Coleman Hawkins, Stan Getzらとも演奏、録音し、スタジオミュージシャンとして膨大な数のレコーディングを残しています。New York市立大学、New England音楽院でも教鞭を執った楽理派でもあります。手堅く端正なプレイとコードワーク、出しゃばらず控え目でいて、ツボを押さえた伴奏はリーダーの音楽性を確実にプッシュする事から、引く手数多だったのでしょう。
ベーシストSteve Swallowは40年10月生まれ、幼少期にピアノやトランペットを学び、14歳でベースを始めます。New Yorkに移り住みArt Farmerのバンドに参加、この頃から作曲を積極的に始めます。以降数多くのオリジナリティ溢れる名曲をジャズシーンに送り込み、その名を不動のものにします。60年代からJimmy Giuffre, George Russell, Stan Getz, Gary Burton, Paul Bley, Steve Kuhn, Michael Mantler達と演奏し、70年代から盟友Roy Haynesに励まされつつ5弦エレクトリック・ベースに持ち替え、Carla Bley, John Scofield, Paul Motian, Joe Lovano達と八面六臂の活躍を遂げます。
ドラマーDenzil Bestは17年4月New York生まれ、Ben Webster, Coleman Hawkins, Illinois Jacquet, Lennie Tristano, Erroll Garner, Phineas Newborn, Miles Davisたちジャズジャイアントと共演しました。また彼にも作曲の才能があり、Move, WeeやThelonious Monkの名盤「Brilliant Corners」収録Bemsha Swing, Herbie NicholsとMary Lou Williamsが取り上げた45 Degree Angle、いずれもビバップ〜ハードバップの名曲です。同じドラマーであるElvin JonesやJake Hannaが彼の演奏に称賛の意を表していますが、特にブラシワークが素晴らしく、本作でも全編ブラシを用いて巧みに伴奏しています。

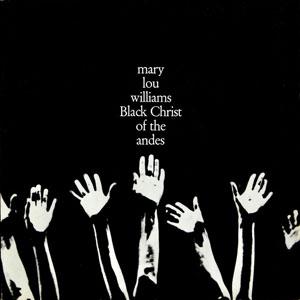
それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目Falling in Love with Love、ベースのwalkingから軽快なテンポでイントロがスタートします。ハスキーな成分が程よく混じる声質のSheila、ドラムを伴って歌い始め、1コーラスギターレスで、2コーラス目キーが半音上がってギターの伴奏も加わり、続いてメロディ・フェイクを用いてもう1 コーラス歌います。彼女は決してテクニシャンではありませんが、歌詞の内容を噛み締めるように、情感を込めつつ明るい透明感ある声質でリズミックに歌唱するプレイには溌剌さを感じます。Parkerの音楽に啓発されての歌唱ですが、超絶技巧にして常に創造性を全面に押し出す彼のプレイとは異なる、外連味なく、自分のテリトリーを大切にしての演奏と感じ取ることが出来ました。
2曲目If You Could See Me NowはピアニストTadd Dameronのペンによる名曲、元は同じボーカリストSarah Vaughanのために書かれたナンバーで、歌詞はCarl Sigmanによります。イントロ無しでボーカルのアカペラから始まり、半音進行のアレンジが施され意外性を感じさせます。バラードなので声量を控えているのでしょう、そのためハスキーさが際立ち、テンポのある前曲よりも気持ちの入り込みを感じ、説得力が増しています。Swallowの巧みなベースワーク、Bestの堅実なブラシ、Galbraithのさりげなさを伴った確実なバッキングで1コーラス丸々を歌い切ります。
3曲目Am I BlueはBillie HolidayやRay Charlesの歌唱も存在する映画音楽に使われたナンバーです。ギターとデュエットでしっとりとバースが歌われ、その後本編へ。ベースとデュエットやルパート部も設けられた、メリハリが利いた構成での演奏、深いビブラートも印象的です。
4曲目Dat DereはBobby Timmons作曲、Oscar Brown Jr.作詞によるナンバー、Swallowと全編デュエットで演奏されます。以前当Blogで取り上げたRickie Lee Jonesの作品「Pop Pop」でも取り上げられていますが、そちらも個性的で素晴らしい歌唱、いずれにせよシンガーにとってはチャレンジャブルなナンバーのようです。
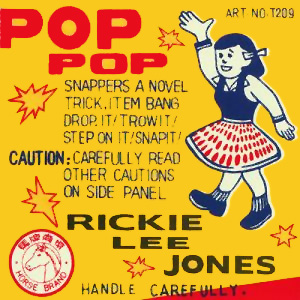
この当時ボーカリストがベースとデュオで1曲丸々を歌うという形態はなかったと思います。しかも早口言葉のような歌詞と旋律を持つ難曲をチョイスしてとなると、従来のシンガーとは一線を画する、インストルメンタル奏者の領域に足を踏み入れています。これはParkerからの影響の具現化の一つと言えるでしょう。テーマを歌った後はスキャットを歌唱、その後はごく自然にラストテーマに移行します。当初に比べるとテンポが随分と速くなっていますが、初めからアッチェルランドを想定していたようにも思います。
5曲目When the World Was Young、Galbraithはアコースティック・ギターに持ち替えイントロを奏でボーカルとバースを演奏します。曲の正式なタイトルはAh, the Apple Tree When the World Was Young、59年にEdith Piafが歌ったことで世に広まりました。本作録音62年頃ボーカリストの間で流行っていたのか、Eartha Kitt, Julie London, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Nat King Cole, Morgana Kingたち第一線の歌手達も録音しています。トリオの伴奏、特にGalbraithの爪弾きが良い味を出していて、彼女も思い入れたっぷりに気持ち良さそうに歌唱しています。
6曲目Let’s Face the Music and Danceは本作中最速のテンポ設定、Swallowが「勘弁してよ、こんなに速く弾けないよ!」とブツブツ言いながら演奏開始したのではないでしょうか? (笑)、彼が演奏放棄する直前(爆)、1コーラスで潔く終わり、テンポは若干遅くなりましたが印象に残るテイクに仕上がりました。
7曲目Laugh, Clown, Laughは28年米国の無声映画で使われたナンバー、ギターとボーカルでバースをスペースたっぷりに演奏し、テーマが始まります。彼女の声質に合った曲想を軽快に歌っています。59年にAbbey Lincolnが自身の作品「Abbey Is Blue」で取り上げ、こちらも素晴らしい歌唱を聴かせています
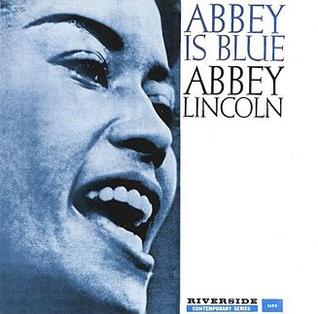
8曲目Who Can I Turn to Now、こちらもバースを朗々とギターふたりで演奏していますが、その後もデュオで最後までプレイしています。ここでのGalbraithのコードワークが実に巧みに行われています。さぞかし気持ち良く歌う事が出来たのではないでしょうか。
9曲目Baltimore OrioleはかのHoagy Carmichael42年作曲のナンバー、ここではギターの伴奏を無くしベースとドラムを相手にブルージーに歌っていて、SwallowのベースワークがSheilaを的確にサポート、そして曲想を支配しています。
10曲目I’m a Fool to Want You、マイナー調のどちらかと言えば「お先真っ暗」的な雰囲気のナンバーですが(笑)、彼女の持ち前の明るさからか、どっぷりと沈み込む事なくジャジーに聴かせています。この曲の新しい解釈と言っても良いでしょう。
11曲目Hum Drum Bluesは前述Dat Dereの作詞でお馴染のOscar Brown Jr.のペンになる曲、こちらもギターレスでSwallowのベースがコード感、サウンドを提供し当時に於ける新感覚のプレイを披露しています。
12曲目、アルバムの最後を飾るWillow Weep for Me、Swallowのベースと二人でテーマが始まります。程なくギターとドラムも参加、通常は3連のリズムで演奏されるのですがバラードで、曲の持つ雰囲気に流されずドライなテイストのプレイを聴かせます。
2021.01.19 Tue
今回はSweden出身ギタリストGustav Lundgrenの2018年録音作品「The Jerome Kern Songbook」を取り上げてみましょう。
米欧混合の若手俊英を擁したギタートリオにテナーサックスの逸材Chris Cheekを迎えたカルテット編成、Jerome Kernの名曲を外連味なくストレートに演奏しています。
今どき珍しいくらいと言う表現が相応しいでしょう、無駄な音を一切排除した如きシンプルさ、脱力感と自然体で臨んだプレイは好感度抜群です。
しかし単なる懐古趣味でのスタンダードナンバー演奏に終わらず、現代的なセンス、フレーバーも随所に感じさせます。
昨今のスタンダード・ナンバーに難易度の高い代理や変則的コード、構成の複雑さ、変拍子の多用が見られるのは、ジャズが若手ミュージシャンにとって学問として、
また探究する対象であリ、John Coltraneの昔から行われていましたが、本作の内容は逆に行き着くところまで辿り着いた結果の一つと言えるかもしれません。
アルバム収録時間もLPレコードを模したかのように42分強、この位の程よさもアリですね。
Recorded at Medusa Estudio (Barcelona) on 5th and 6th of September 2018 by Juanjo Alba
Mixed by Gustav Lundgren at Farmer Street Studio (Stockholm)
Mastered by Alar Suurna at Shortlist Studios (Stockholm) Produced by Gustav Lundgren Executive Producer: Jordi Pujol
Label: Fresh Sound Records
ss,ts)Chris Cheek g)Gustav Lundgren ds,vib)Jorge Rossy b)Tom Warburton
1)Why Do I Love You? 2)The Way You Look Tonight 3)Smoke Gets in Your Eyes 4)All the Things You Are 5)Nobody Else But Me 6)Can’t Help Lovin’ Dat Man 7)I’ve Told Ev’ry Little Star
8)Ol’ Man River
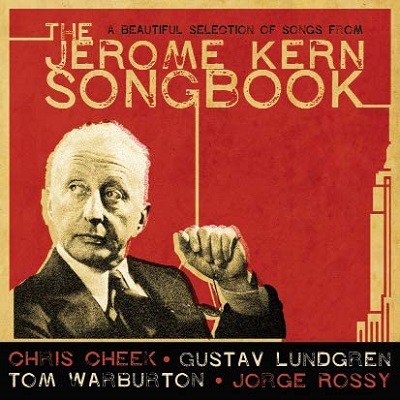
本作ディストリビュートのSpain BarcelonaにあるFresh Sound Recordsは、若手ミュージシャンを対象にしたNew Talent Recordsと言うレーベルを起こし、実に積極的に無名新人のアルバム制作を行なっています。今までに615枚(!)ものリリース、欧米ほか日本人の作品も含まれています。他にも1962年以前の米国メジャー、マイナー・レーベルから発売されたモダンジャズ名盤を高音質、デジパック、時にボックスセットにての再発作業も行い、ある種隠れた名盤発掘作業と言え、レーベルオーナーJordi Pujolのジャズに対する愛情、情熱を痛感します。
さて「Plays the Jerome Kern Songbook」と題されたアルバムは昔から他にも存在しますが、個人的には2枚思い浮びます。
1枚目はOscar Petersonの59年録音、Ray Brown, Ed Thigpen黄金のレギュラートリオでの演奏です。どこを切っても金太郎飴状態のPeterson Trioですが(笑)、Kernの華やかで気品があり、
他にはないイメージの楽曲とオリジナリティ溢れるコード進行がある種の縛りとなり、いつもの彼らとはやや違ったテイストを聴かせています。

もう1枚はElla Fitzgeraldの63年録音作品、Nelson Riddle Orchestraとの共演になります。このアルバムはよく聴きました!ポップで小粋、そして何しろチャーミングな歌いっぷり、
Kernの音楽性を踏まえてビッグバンドをバックにゴージャスに聴かせます。Ellaの歌唱には大編成がよく映えます。
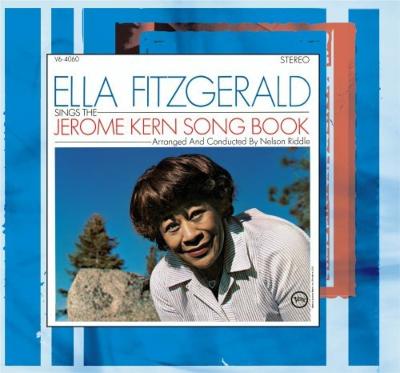
EllaのSongbookには他にも57年録音Duke Ellingtonの作品が素晴らしい出来栄えです。彼女は歌の大変上手いシンガー、何を歌わせても極上の歌唱を披露してくれますが、
尊敬するEllingtonとの共演でまた違った側面を見せてくれました。オーケストラ、トリオとの両編成が聴けるのも嬉しいです。

本作のリーダー、Gustav Lundgrenのプロフィールをご紹介しましょう。
80年Sweden Stockholm生まれ、12歳でギターを弾き始め、地元のナイトクラブで16歳から演奏活動を開始、様々なバンドを経て世界各国で演奏旅行を行い、
Swedenを代表するギタリストにまで成長しました。70枚以上のレコーディングに参加し、自己のリーダー作も25作以上リリースしています。
Kenny Burrell, Joe Pass, Wes Montgomery, Jim Hallを感じさせるスタイルは確固たる音楽性に裏付けされ、聴く者を魅了します。
それでは収録曲について触れて行きましょう。
1曲目Why Do I Love You?はブラシによる短い、しかし印象的なドラムのイントロから始まり、ボサノバのリズムで演奏されます。Cheekのメロディ奏には押し付けがましいところが皆無、
美しくも個性的なトーンを引っ提げてひたすらスイートにプレイしています。演奏時に脱力することの大切さを熟知し、至極自然体、共演者もそんなCheekとの演奏はさぞかしリラックスして
楽しめる事でしょう。
彼のテナー使用楽器はSelmer Super Balanced Action long bell、マウスピースはOtto Link Tone Edge Early Babbitt 7番、very long facing curve、low baffleにリフェイスしてあります。
リードはRicoかRico Royalの3 1/2。「コーッ」と言う木管楽器的な響きや、ハスキーさを伴った雑味等の成分のバランス値が絶妙で、更に「シュワー、ザワー」的な付帯音が
楽器を取り巻くかの如きに鳴っています。彼のセッティングにはこの魅惑的なトーンを出すための必然性を強く感じます。
youtubeを見ると、演奏中自分のソロを終えた際に愛器をいとおしく抱くように携えている彼の立ち姿が印象的です。楽器は自分の相棒、ましてや戦友と言うよりも、
大切なパートナーとして向き合っていると感じました。そしてCheekはサウンドや立ち振る舞いから、周囲の仲間や伴侶に対する気配りのある、優しい人柄を見取る事が出来ます。
テーマ後ギターとテナーで8小節づつのトレードが2コーラス行われます。互いのフレージングを聴き合い、受け止め、発展させ合っており、仲の良い友人同士の楽しげな会話のように
聴こえます。それにしてもCheekのタイムの良さ!リズムのスイートスポットにドンピシャ嵌っています。
Lundgrenは的確なピッキングを聴かせつつ、タイムが多少ラッシュする傾向にありますが、むしろ揺れを楽しんでいるかのような雰囲気です。
ナイスなカンバセーションの後にはJorge Rossyのブラシによる1コーラスの音楽的なソロがありますが、イントロのプレイを踏襲したかのテイスト、その後ラストテーマへ。
トレードの延長の如くテーマをギターにも任せ、その後ろでオブリガードをさりげなく吹いています。エンディングはターンバック、そしてシンコペーションによるキメを経て、
意外性のあるコードでFineです。
アルバム冒頭に位置する曲ではありますが、演奏の雰囲気としては何曲か録り終えた後、箸休め的に気楽にプレイしたテイクのように感じます。演奏時間が本作中一番短いのは
それも一因かも知れません。
2曲目The Way You Look Tonightは様々なミュージシャンに取り上げられているナンバー、本作ではどのように料理されているのでしょうか。
ミディアム・スイングでギターがカラフル、ユーモラスにメロディを演奏、サビでテナーが登場しその後のAメロもプレイします。
メロウで大らかさを感じさせる語り口は一聴Cheekと判るほどの個性を確立しています。ソロの先発はそのままCheek、間の取り方、
フレージングの音の選び方、ハネた8分音符のひょうきんさと相俟って大らかさを打ち出しています。
半コーラス演奏し(この曲は64小節を有するので普通のウタ物と同等の32小節)、ギターソロへ、オクターブ奏法を交えたアプローチを用いて
こだわりの美しい音色と合わさり、巧みに聴かせます。ラストテーマはAAを省きサビから始まり、テナーのメロディが再び演奏されますが、
より一層リラックスしたテイストを感じさせます。メロディの合間のギターによるフィルインも巧妙に響き、エンディングはバンプをリピートして
フェードアウトの巻です。
3曲目Smoke Gets in Your Eyes、タイトルは禁煙運動の推進に一役買った事でしょう(笑)、ここではCheekソプラノサックスに持ち替え、よりスイートにプレイしています。
セミカーブド・ソプラノを使用しており、曲管部分を有するので直管の楽器よりもアルトサックスに近い音色が特徴的です。ギターイントロ後テーマ奏、
テナーよりも更に脱力を感じるのは小さい楽器を鳴らす故でしょう、ほとんど囁くような、独り言の範疇に入りそうな吹き方です。
ソロもどこかハーモニカの音色をイメージさせる時のある、独特な奏法を感じます。
サビからギターソロに変わり、裏コードをはじめとする音の選び方にセンスを感じさせるアプローチと速弾きが印象的です。
ラストテーマはサビから、初めよりも幾分力強さを感じる吹き方で場を活性化させ、Aメロではポルタメントも用い、再びしっとりとプレイ、
エンディングもマイルドに、ギターの巧みなコードワークにバックアップされFineです。
4曲目All the Things You AreはKernの代表曲にして実に巧みなコード進行を有した名曲、多くの転調を有する事から演奏者には自ずと高いハードルが掛けられます。
ここでは加えて通常とは異なる3拍子で演奏されており、それに伴いイントロのメロディ、譜割がアレンジされていて新鮮に聴こえます。テーマ後にも再びイントロが演奏され、
テナーソロが始まります。持てる力の6割程度、鼻歌感覚で巧みにアドリブを繰り広げますが、コード進行の難易度はこの人には無関係のようです!むしろ込み入っている方が
より緻密なラインをクリエイト出来るのでしょうね、きっと。素晴らしいソロを2コーラス演奏していますが、もう少し聴きたいところを腹八分目で押さえているのは
Songbookと言うアルバム・コンセプトの成せる技、究極曲紹介のアルバムなのです。
自分が20代の頃はよくテナー奏者の興味あるソロを採譜、分析し、覚えるまで練習したものですが、久しぶりにこのソロを譜面にしたいと言う気持ちになりました(笑)。
その後ギターも同様に2コーラスを、多くの若きプレーヤーの規範となり得るクオリティの演奏を展開します。その後ラストテーマを迎え、イントロが再利用され
フェードアウトでFineです。
5曲目Nobody Else But MeはTom Warburtonのベースからスタートしますが、木の音がするプレイは気持ちが良いです。
小粋なウタもののテーマをCheek何の衒いもなくプレイ、これも良いですね!ソロはLundgrenから始まります。ギターの魅力を満載したラインはこれまたコード進行に対する
アプローチの良き手本となる事でしょう。続くCheekのソロは意外な出だしを提示、例えるならRollinsライクなテイストでしょうか。その後も何処となくおかしみを
匂わせる、他の曲とは異なる色合いでソロを聴かせます。彼はPaul Motian, Charlie Haden, Steve Swallow, Bill Frisell達つわものとの共演ではまた別なテイストを披露しており、
引き出しの多さを感じさせます。ソロの終盤戦で聴かれるWarburtonのペダルポイントも効果的です。
ラストテーマの前半はLundgrenが演奏、後半をCheekが担当し、エンディングはターンバックを経て短3度で転調して行き、巧みにFineです。
6曲目Can’t Help Lovin’ Dat Manはバラード、ギターとテナーのデュオでテーマが演奏されますが低音域をCheekはいつものサブトーンではなく実音でプレイ、これは意外と新鮮です。
古き良き米国南部の雰囲気を湛えた曲想、カントリー&ウエスタンも感じさせる楽曲を朗々と吹いています。8小節づつのソロをギターとテナーがトレード、ほのぼのとした様を一貫して表現したテイクに仕上がりました。
7曲目I’ve Told Ev’ry Little Starは、まず個人的にSonny Rollinsの演奏がイメージされます。58年10月録音の大名盤「Sonny Rollins with the Contemporary Leaders」

もう1枚あります。59年Stockholmでの録音「St Thomas – Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959」両演奏とも甲乙つけ難い出来です。

本作の演奏はボサノバのリズムで軽快にプレイされますが、Jorge Rossyのドラミングが良い味を出しています。彼はCheekのリーダー作の殆どに参加するお抱えドラマー、Barcelona出身、Fresh Sound Recordsでも数多くのアルバムに参加、こちらもハウス・ドラマー状態です。そのRossyのドラムソロから曲がスタートします。当然ですがRollinsの演奏とは全く異なる
コンセプトで曲が進行しますが、ナチュラルさと穏やかさを保ちつつ、実は音楽的に高度な演奏をさり気なく行っています。Cheek, Lundgren, Warburtonとソロが続き、ラストテーマはサビから演奏され。エンディングはギターとテナーが同時進行でソロを行いFade Outです。
8曲目Ol’ Man Riverは再びCheekがソプラノに持ち替え、Rossyもスティックからマレットに持ち替えビブラフォンを担当し、ベースもアルコで参加しています。メロディを淡々と、美しく演奏するだけのテイクですが、途中ソプラノが最低音のB♭よりも半音低い、あるはずの無いA音をやや危なげに4回吹いていて、身体の何処かに、例えば太腿や譜面台を利用し瞬時に楽器のベルを押し当て、7,8割閉じつつ吹いてピッチを下げると言う、実はアクロバティックな奏法をさりげに披露、危なげな出音は然もありなんです!
恐らくCheekが楽器を振り下ろしつつセンテンス毎にキュー出しをしているのでしょう、メロディの揺らぎがとても心地よくサウンドする、アルバムのエピローグとして相応しいテイクとなりました。
2021.01.06 Wed
今回はテナーサックス奏者Steve Grossman79年の作品「Perspective」を取り上げてみましょう。
彼は昨年(2020)8月に69歳で惜しくも亡くなったカリスマ・テナー、25枚以上のリーダー・アルバムをリリースしていますが、その中で最も作品としてのクオリティが高いアルバムと認識しています。
音楽の形態としては当時流行ったフュージョンですが、ジャズ・テイストを基本としたGrossmanミュージックを素晴らしい共演者、秀逸なプロデュースのもと、思う存分に発揮しています。
Recorded: 1979 at Electric Lady Studio, New York City. Recording engineer: David Wittman Produced by Raymond Silva, co-producer: Steve Grossman Label: Atlantic
ts,ss)Steve Grossman g)Howard “Bugzy” Feiten b)Mark Egan ds)Steve Jordan ds,bongos)Lenny White(on Arfonk) b)Marcus Miller(on Creepin’ & The Crunchies) p,Fender Rhodes)Onaje Allan Gumbs perc)Raphael Cruz congas)Sammy Figueroa g)Barry Finnerty(on Katonah) p)Masabumi Kikuchi(on Pastel) ds)Victor Lewis(on Creepin’ & King Tut) Creepin’ & The Crunchies arranged by Onaje Allan Gumbs
1)Creepin’ 2)Arfonk 3)Pastel 4)The Crunchies 5)Olha Graciera 6)King Tut 7)Katonah

僅か18歳にしてWayne Shorterの後任としてかのMiles Davisバンドに加入し、天才の名を欲しいままにしたSteve Grossman、スケールの大きいプレイ、John Coltraneのフレージングが基になってはいますが独自のインプロビゼーション・アプローチ、タイム感の素晴らしさ、50年代のSonny Rollinsを彷彿とさせる端正な8分音符、そして何より誰も成し遂げることの出来ない、あり得ないほどに素晴らしい楽器の音色と鳴らし方(単に音量の大きさと言う次元ではなく、倍音成分や付帯音の尋常ではない豊富さと言う観点で)を引っ提げてジャズ界に殴り込みをかけ、一大旋風を巻き起こしました。
「Live at the Lighthouse」を筆頭としたElvin Jonesバンドでの一連の作品では彼の本領が発揮され、歴史的な名演奏を繰り広げていますが、他のサイドマンや何より自身のリーダー作の多くでは不完全燃焼を否めません。そんなな中でも 5枚のリーダー作、77年「Born at the Same Time」78年「New Moon」84年「Hold the Line」「Way Out East」85年「Love Is the Thing」はGrossmanのプレイの真髄を捉えていると思います。





Grossmanフリークの僕自身、来日時には追っかけのようについて回ったのですが(笑)、その際に本作の素晴らしさについて尋ねてみました。ところが本人はあまり内容を気に入っていなかったのか、「あの作品はコマーシャルなもので、お金のために仕方なく録音したんだ」と言うとても意外な返答が。内容について突っ込んだ質問をしたかったのですが、見事に出鼻を挫かれた覚えがあります(汗)。
あの名盤、Grossmanを代表する名演奏がお金のために成されたとは、でも実はよくある事かも知れません。確かに米国大手Atlanticレーベル、当時のフュージョンシーンを代表する豪華なメンバーの起用、自身のオリジナルの他に菊地雅章氏とOnaje Allan Gumbsのオリジナル、アレンジが施されたStevie Wonderのナンバーを配した、言ってみればGrossmanの魅力を今までにない別な角度からも引き出そうというプロデュースによる、一大プロジェクトとも取れる作品です。かなりお金をかけていますね。当然彼へのペイも良かったと思いますが、co-producerとして名を連ねているものの、特にレコードのSide Aに該当する1〜4曲はプロデューサー・サイドの思惑で事が進行し、自己主張の強い彼が曲構成や編曲によく従ったと思います。とりわけ4曲目の曲想とアレンジが不本意だったのでは、と僕なりに想像しています。ですが選曲、演奏、編曲、メンバーの熱演がむしろ本作をGrossmanの魅力を凝縮した作品へと昇華させていて、レコードのSide Bに該当する5〜7曲目のオリジナルでの、いつも以上に彼らしい演奏との対比も加わり、他のリーダー作にはない強烈な魅力を放つアルバムに仕上がったのでは、と睨んでいます。
ジャズ・ミュージシャンの作品はセルフ・プロデュースの魅力もありますが、レーベル・プロデューサーがリーダー・ミュージシャンのポテンシャルを見極め、判断し、本人の価値観では思いもよらぬ、むしろ真逆の表現方法、形態を引き出す事が彼ら本来の仕事のひとつだと思います。Steve Grossmanという言わば野獣を見事に飼い慣らし、しかし野生動物としての本能もしっかりと残させつつ、あたかもサーカス興行として成り立たせた〜表現が露骨過ぎるかも知れません(汗)失礼!〜、プロデューサーRaymond Silvaの手腕によるところが大の作品です。
それでは演奏内容について触れて行く事にしましょう。
1曲目Stevie Wonderの名曲Creepin’、実は以前にもGrossman, Gene Perla, Don Aliasの3人から成るユニットStone Allianceの76年第1作「Stone Alliance」で演奏しています。こちらの演奏での彼はいつになくサブトーン気味に演奏していて、通常とは違ったテイストを聴かせています。
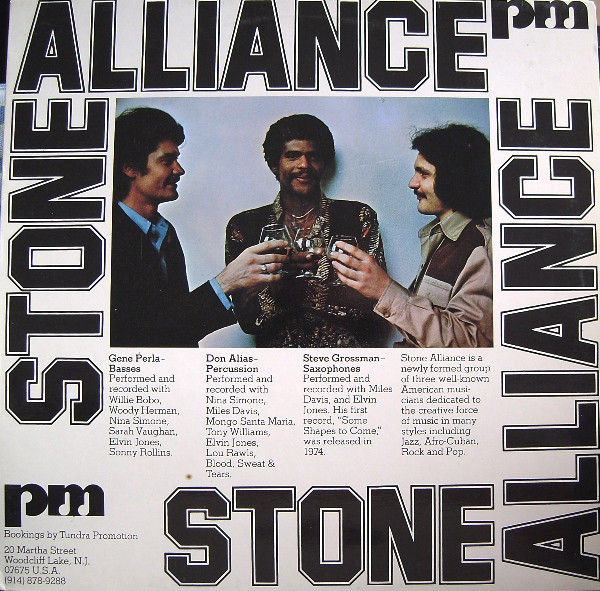
本作の方が速めのテンポ設定、上記の演奏がトリオなのもありますがパーカッションやギター、ピアノのバッキングがサウンドをぶ厚くしており、リズムのキメを始めとするアレンジが曲の雰囲気を高めています。
それにしても物凄いテナーサックスの音色です!超ルーズなアンブシュアとエアーの効率の良い使い方は間違いなく理想の奏法、これを基にBen Webster, Sonny Rollins, John Coltrane達のトーンのイメージが彼の中でメルティングポット状態で渾然一体化し、まさにテナーを吹くために生まれて来たかのような身体を媒体とし、ユダヤ人の情念、怨念を彼が一身に受け止めて咆哮しているが如き演奏です!ここではVictor Lewisの重厚なドラミングとMarcus Millerのスラップ・ベースがテナーソロによく合致しています。Elvinバンドでの盟友Dave Liebmanのやはり79年作品「What It Is」にもMarcusが参加、こちらはSteve Gaddがドラムを担当していますが、Rolling StonesのMiss Youの演奏を筆頭に、Liebmanのまた違った魅力を引き出そうとする、プロデューサーMike Mainieriの算段が感じられ、たまたまでしょうが作品のコンセプトに類似性を感じます。
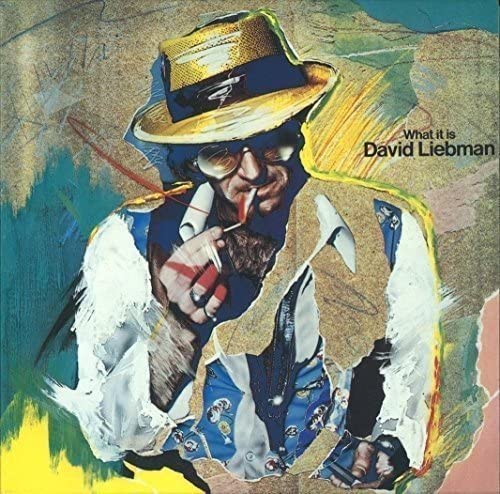
2曲目GrossmanのオリジナルArfonk、3部構成から成るドラマー、パーカッション奏者、ギタリストが大活躍するリズムの饗宴とも言うべき演奏です。まずはPart 1、Lenny Whiteのドラミングの素晴らしいこと!バスドラのタイミングがあまりにも好みです!音符がリズムのちょうど良い所に入る、とはこの事を言うのでしょう。Buzz Feitenのギターワークも音色といい、タイミングといいメチャカッコいいです!Grossmanは深いビブラートに基づいた自身のOne & Only ”Grossmanフレーズ”を駆使し、フラジオ音の割れ具合も相俟ってエグエグに盛り上がっています!続いてのPart 2、テンポがドラムのフレーズをきっかけにリタルダンド、ギターのカッティングがこれまたイカしてます!相変わらずWhiteのバスドラを始めとした、軽快にして重厚なドラミングが素晴らしい!Grossmanフレーズ絶好調!ありえない次元にまで聴き手を誘います!GumbsのRhodesによるバッキングも素敵!Part 3はFeitenのヤバいくらいにイケてるカッティングと、Whiteのハイハットからなるイントロでテンポがアッチェルします。ティンバレスとコンガによるグルーブ感が圧倒的なソロの連続!Raphael Cruz, Sammy Figueroaふたりのパーカッショニストのコンビネーションは完璧です!リーダーは曲の最後に少し演奏しただけですが、十分に存在感をアピールしています。ここでもGumbsのバッキングが良い味を出しています!プロデューサーの権限でこの曲の世界が設けられたと推測できますが、Grossman自身の発案ではこう言ったアイデアはまず生まれないと思います。
この曲はStone Allianceの77年Amsterdamでのライブ盤「Live in Amsterdam」にも収録されています。こちらはトリオ編成によるライブという事で本作よりもずっとラフな演奏ですが、テナーの音色は更に凄まじいです。
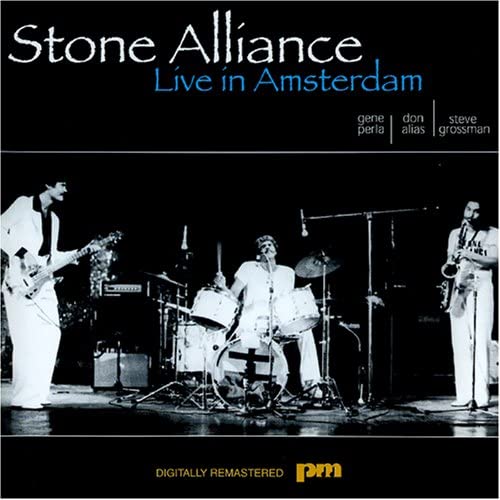
3曲目菊地雅章氏のオリジナルPastel、作者自身のリリカルなピアノ・イントロから始まります。Grossman追っかけ時(笑)の別な逸話ですが、確か彼が譜面を書く際に「これはPoo(菊地雅章氏の愛称)から貰ったんだよ!」と嬉しそうに鉛筆を見せてくれました。貰った鉛筆を後生大事に持っているGrossmanも可愛いですが(NYCのタクシーにソプラノ・サックスを置き忘れて出てこなかった伝説の持ち主です!楽器よりも鉛筆の方が大切かも?)、彼に対する敬愛の念を強く感じ、Pooさんの諸作で76年作品「Wishes/Kochi」から81年傑作「Susto」「One Way Traveller 」演奏参加の際の充実感を垣間見ることが出来ました。



美しくもダイナミクスの振れ幅が凄まじく、バンドの一体感がPooさんのピアノを軸として見事に成立し、Grossmanのシャウトぶりもハードさとメロウさが両立した相反する朗々さを聴かせます。フラジオC音吹き伸ばしの強烈なインパクトと言ったら!そしてMark Eganのフレットレスベース、Feitenのさまざまなテクニックを駆使したカラーリング、Jordanの「うん、間違いない」ドラミングの妙、後テーマのエンディング部は始まりと同様にピアノが担当しFineを迎えますが、曲自体、ソロ、伴奏、演奏の全てが極自然に進行するナンバーです。参加者のうち誰一人として不必要な我を出さずに見事な一集合体として成り立っているのです。
豊潤な音楽性、情感を湛えた名演奏となりました。
4曲目The CrunchiesはGumbsのオリジナル、本作中一番の問題曲です。LAのフュージョン・グループ、いやクロスオーバー・バンドの如きテイスト満載の曲想をGrossmanに演奏させたプロデューサー、大英断です!この曲をアルバム冒頭に持ってくるアイデアも間違いなく持ち上がった事でしょう!実現したらさぞかしキャッチーなアルバムに様変わりしたと思います。冒頭曲の第一印象で作品のカラーは決まりますから。
以前当Blogで取り上げたDon Cherryの77年作品「Hear & Now」も同じくAtlantic label、同様にRaymond Silvaがアルバム制作に携わっていますが、思うにリアル・ジャズマンにフュージョンを演奏させようという企画が70年代後期にAtlantic社内で持ち上がっていたのでしょう。Cherryの作品の方にも1曲、名プロデューサーNarada Michael Waldenの、とってもポップなオリジナルが収録されていますが、アルバム7曲目と末席に追いやられました。冒頭曲のおどろおどろしさが間違いなくアルバムを支配した作品、ヒットや売り上げとは縁がなかった事でしょう。大手レーベルに於いてミュージシャンの音楽性か、アルバムの売り上げどちらを取るか、現代は後者に間違いなく重きが置かれますが、70年代は比較的穏やかだったのでしょう、両作ともリーダーの意向を尊重した形でのリリースとなりました。

イントロのキメやトライアングル使用、ギターカッティング、そして縦ノリのグルーブは間違いなく70年代フュージョン、クロスオーバーの定番。ソプラノのテーマ奏も同一メロディをオーバーダビングして重ね、音を厚くしていますが、ポップス・ボーカリストGilbert O’Sullivanの72年大ヒットナンバーAlone Againのボーカル処理と同じ手法です。
もともと常人離れした音の太さを持つソプラノ・トーンの持ち主、「何故メロディをもう一度吹いて重ねる必要があるんだ?」と間違いなくGrossmanスタジオ内でごねた事と思います。宥めすかしてご機嫌を取りつつ演奏させたプロデューサーSilvaは、一体どのようにしてわがまま坊やを説得したのでしょう?(笑)
キャッチーなメロディは意外にも彼のソプラノにごく自然にマッチし、サビの展開部も心地よさを聴かせます。ソロにもそのままナチュラルに移行しますが、さすがにここではオーバーダビングは施されず、ひたすらメロウにソロが展開され、リズムセクションも的確にサポートします。GumbsのRhodesソロ、そしてFeitenのまさしくフュージョン・テイストの演奏に続き再びソプラノのソロへ。先程のソロよりも強くGrossman色を感じさせます。その後再びダブリングによるラストテーマへ、エンディングにもソプラノソロが聴かれますが早めにフェードアウトを迎えます。
この演奏を初めて聴いた時の戸惑いは忘れられず、Grossmanのスタイルとは水と油と感じましたが、今となってみれば本テイクの存在は彼の音楽史上にとっても大切だと思います。吹き過ぎず間を生かしたアプローチには新たなる展開の予感がしました。
全曲とは言わず、収録曲の半分程度、いや1/3でもこのコンセプトの楽曲を演奏した作品をリリースし、以降も定期的にこの路線を辿って行ったなら、孤高のテナーサックス奏者の名を返上し、欧州に籠らずとも(90年代以降Italy Bolognaに住んでいました)米国ジャズ・フュージョン・シーンに君臨していたと思うのは、僕が単にGrossmanフリークだからでしょうか?
もう一つ感じるのは、Side Aの4曲目に位置するナンバーにメロディのダブリングをする必然性を感じないという点です。この曲が作品中「浮いてる」感が強いのは、作品の真ん中あたりに位置していながら妙に主張が強い、これは曲想の違いに起因する以上に曲が厚化粧だからだと思います。厚化粧は接客や外出のため、対外的に好印象を与えるための装いの一つです。おそらくプロデューサーはDon Cherryの不発ぶりに懲りていて、Grossman作は何とかヒットに結びつけたい、方法としてはキャッチーなナンバーを冒頭に配したい。The Crunchiesのポップ色を既成事実化するためにも、嫌がるGrossmanを説得してメロディ処理を売れ筋仕様にデコレーションしたように思います。
さてレコーディングが終わりました。アルバムリリース前に選曲&曲順会議が開かれましたが、Silva以下制作スタッフはThe Crunchiesを1曲目にしたい、一方Grossmanは冗談じゃない、俺の音楽性とは合っていない。そもそもこの曲を収録するのも嫌だ!とひたすら平行線を辿り、結局は折衷案で比較的目立たないA面ラストに置かれたのではないでしょうか。その際にメロディのダブリングを解除し、シングル・トーンでの演奏に戻せば「浮いてる」感じは緩和されたのでは、とも思いました。

5曲目Olha GracieraはGrossmanのオリジナル、かなり頻繁に自己のアルバムで取り上げています。印象的なベースラインとユニークなコード進行、そして崇高なまでに気高さを感じさせるメロディ、彼の作曲の中でベスト3 に入る名曲です。Gracielaとはおそらく奥方かガールフレンドの名前、彼女に捧げられたナンバーですが、破天荒な殿方に寄り添っていくのはさぞかし大変だったのでは、と要らぬ心配をしてしまいます(汗)
テーマ後先発ソロはGumbsのピアノ。以前僕が日野皓正さんのバンドに参加させて貰っている時に、彼の米国でのバンドのメンバーがGumbs、日野さんは彼のプレイの事をとても褒めていた事が印象に残っています。リーダーの元で的確な演奏をする事に美学を感じているタイプのミュージシャンと認識しています。ここでのソロも曲想の中にしっかりはまり、決して埋没せず、自己主張をほど良きバランスで行っており、続くテナーソロに向けて低音域にシンコペーションでドラマチックに降りて行くフレージングが堪りません!そしてGrossmanはしっかりとその意思を受け継ぎ、ブリブリとした低音域からソロを開始しますが、イヤー、これはメチャメチャカッコ良い!鳥肌モノです!本作のハイライトの一つと感じます。受けて立つリズムセクションのアプローチも素晴らしい!Gumbs, Jordan, Eganとのコラボレーションはこの一作だけだったのがあまりに勿体ない!彼らはGrossmanのコンセプトを確実に、120%理解して演奏に臨んでいます!さらにありきたりの表現で申し訳ないのですが、これはOne & Onlyの演奏、真の天才だけが行える諸行なのです!エンディングの盛り上がりも凄過ぎです!
6曲目King TutとはKing Tutankhamenの事、厳かで神秘的なムードは古代エジプトの若くして亡くなった謎多きツタンカーメン王をイメージしているのでしょう。自身のリーダー作で同様に数多く取り上げていますが、ここでの演奏はその決定打かも知れません。
リズム隊によるフリーなイントロの後、Eganのベースから始まりますが、フレットレスの伸びる音が効果的です。テーマはテナーのオーバーダビングによるハーモニーを伴ったメロディ、本人この曲を取り上げる時にはいつも自身でハーモニーをダビングしていました。ソロ最中にもダビングが施されていますがメロディ・ユニゾンのダブリングとは意味合いが異なり、彼の表現に於いて必要な事なのです。ギター、テナー、ピアノとソロが続きますが各々抑揚のある構成で演奏されています。各ソロイストはツタンカーメン王に対する自身のイメージをふんだんに盛り込んでいるかの様で、いずれも深い次元にまで表現を行なっています。同様にギター、ピアノ、そしてパーカッションのバッキングも効果音的に曲想を盛り上げる役割を果たしています。この曲でドラマーにLewisをチョイスしたのはよりジャズ的なメリハリあるアプローチを求めたからなのでしょうが、大正解です!Stone Alliance「Live in Bremen」にも収録されています。

7曲目Katonah、曲名について本人に尋ねたところNew York州にある場所の名前だそうです。ハイウェイを運転している時にKatonahと書かれた標識をよく見かけたような事を言っていました。曲を書いたものの、タイトルが決まらず困っている時にたまたま眼にしたので、のような話です。
新宿にあるライブハウスSomedayでのGrossman単独来日、日本のミュージシャンと一週間に及ぶ伝説のライブを挙行、そのリハーサルに立ち会いましたがこの曲の練習最中に彼が、「スタンダード・ナンバーの何だっけ?譜割りで同じ曲があるよね」と言い出し、メンバーみんなでわいわいと探っていました。暫くしてGrossmanがVincent Youmansのナンバー「I want to be happyだ!」と曲のメロディを吹き始め、一同納得したのを覚えています。確かにこの曲とシンコペーションが同じフィギュアですね。
この曲も度々リーダー作に登場しますが、初演は77年作品「Terra Firma」です。

Jordan以下タイトなリズムセクションによる素晴らしいサポートで本作の演奏が真打になりました。I Want to Be Happyシンコペーションが(笑)曲全体を通して演奏されていることで、こちらはリズムの分厚さを誇示した狂宴(!)となっていますが、Barry Finnertyのギターによるカッティングが実に支配的です。凄まじいまでに気持ちの入ったテナー独演会の後、ラストテーマ、曲がカットアウトで終わったと思いきやテンポが半分に落ち、そのままインテンポでハードロックの世界に突入!Finnertyのギター素晴らしいです!適材適所!そして情念のこもったエグさ炸裂のソプラノソロが開始!Grossman参加のMiles作品に「Jack Johnson」がありますが、むしろ彼は不参加、Bill Evans演奏での「We Want Miles」の方をイメージしてしまいました。