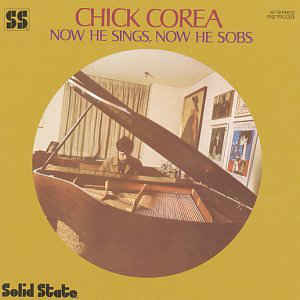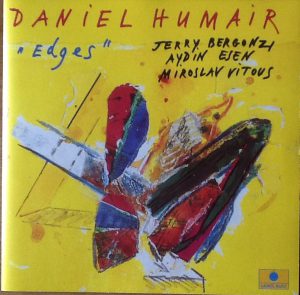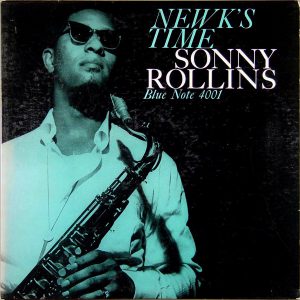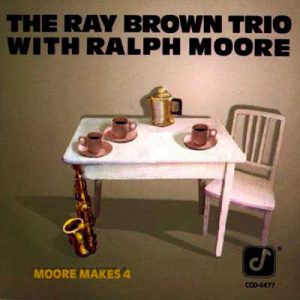2018.07.28 Sat
Steve Kuhn / Oceans In The Sky
今回はピアニストSteve Kuhnの1989年録音トリオ作品「Oceans In The Sky」を取り上げて見ましょう。
89年9月20, 21日Ferber Studio, Parisにて録音。p)Steve Kuhn b)Miroslav Vitous ds)Aldo Romano
1)The Island 2)Lotus Blossom 3)La Plus Que Lente / Passion Flower 4)Do 5)Oceans In The Sky 6)Theme For Ernie 7)Angela 8)In Your Own Sweet Way 9)Ulla 10)The Music That Makes Me Dance Owl Label France
Steve Kuhnが単身フランス・パリに赴き、Miroslav VitousとAldo Romanoの初顔合わせで録音した作品ですが、大変に優れた内容で多作家Kuhnの中でもなかんずく代表作に挙げられます。多くのベーシスト、ドラマーとトリオ編成でのレコーディングを行っているKuhnですが、これほど3者のバランスが取れている演奏は彼のキャリアの中でもトップクラスです。とりわけVitousの演奏が素晴らしく、明らかにKuhn自身の演奏は彼に触発されて更なる深遠な境地に達しています。Chick Coreaのトリオ作品68年リリース名盤「Now He Sings, Now He Sobs」、Vitous若干21歳の革新的な演奏がジャズ史に燦然と輝きますが、この頃の先鋭的な演奏よりも20年を経た本作品では超絶技巧はそのままに、音楽的に成熟した演奏を聴かせています。
ドラマーAldo Romanoはイタリア生まれのフランス育ちでDon Cherry、Steve Lacy、Dexter Gordonといった渡欧組アメリカ人ミュージシャンたちとキャリアを重ね、名ピアニストMichel Petruccianiのレギュラードラマーを務めた経歴を持つセンシティブなドラマーです。この作品でも超弩級ピアニスト、ベーシスト二人に対する的確なサポート、またある時は丁々発止とやり取りする二人のインタープレイのまとめ、調整役を担当しています。仮にこのレコーディングのドラマーがスイス出身のやはり超弩級、いやひょっとするとそれ以上のDaniel Humairであったなら(十分に可能性がありましたが)どのような演奏が繰り広げられていたか、どれだけの熱演を聞くことが出来たか興味は尽きませんが、RomanoはRay Brown, Ed Thigpenを擁していた時期のOscar Peterson TrioのThigpenと同様の立場にいると感じます。派手さは無くしかも決して出しゃばらないタイプなのですが、共演者を立てつつその場に最も相応しい場面を設定、提供しています。以前にも何かで書きましたがOscar Peterson Trio, Peterson, Brownの極めて同一なグルーヴ感、スピード感がそのまま放っておけば幾らでもOn Topで演奏の展開になるところをThigpenが背後から二人とも(特にPetersonは巨漢なので大変です!)羽交い締めにしてレイドバックさせています。おそらく同じグルーヴ・タイプのドラマーが参加したのなら、ぐんぐんとリズムが前に行くラテン、サルサ方面のトリオにも成りかねません。VitousのベースラインがOn Topで強力にスイングしているのでRomanoのトップシンバルが遅く聞こえますが、実はKuhn自体かなりレイドバックして演奏しているのでむしろRomano寄りで、Kuhn + Romano vs Vitousというリズムの構図が成り立っています。このようなピアノトリオ3者のリズム相関図もアリですね。本作はどのような経緯があってこのメンバーによるレコーディングが決まったのか、興味があるところですがなかなか表立ってメイキング・プロセスが露出することはありません。プロデューサーのJean-Jacques Pussiau, Francois Lemaireの采配によるところが大なのでしょう。
ちなみにVitousはDaniel Humairの91年録音リーダー作「Edges」(Label Bleu)にて迎えられ、Jerry Bergonzi(ts), Aydin Esen(p)らとのカルテット編成でアグレッシブでコアな演奏を繰り広げています。Humair, Vitousの共演作は他にもあるようです。
この作品でもう一つ特記すべきは、選曲とその並びのバランスが実に良く取れている点です。元来Kuhnはスタンダードナンバーを素材として取り上げ、その料理の仕方に彼なりの音楽性が発揮されるミュージシャンで、オリジナルを中心に演奏し自己のサウンド・カラーを表現するタイプではありません。どのようなスタンダード、ジャズ・ミュージシャンのオリジナルを取り上げるかにも手腕が問われるところです。今回は自身のオリジナル2曲、Romanoのオリジナル1曲、他Ivan Lins, Kenny Dorham, Debussy, Duke Ellington, Fred Lacey, Antonio Carlos Jobim, Dave Brubeck, Jule Styneらのナンバー計11曲(1曲はメドレー)を演奏し、バラエティに富みつつ各々の演奏曲の内容の素晴らしさも相俟って絶妙な配置を感じさせます。僕自身もこの作品の選曲、曲順はよくぞここまで練られたな、と感心せずにはいられません。もっとも、良いテイクの演奏が集まれば自ずと曲順が定まる、という考えも成り立ちますが。
それでは曲ごとに見て行きましょう。1曲目はIvan LinsのThe Island、Kuhnとしては意外なオープニングです。数多くのミュージシャンによってカヴァーされている名曲で作品の冒頭を飾るに相応しいクオリティの演奏、リラックスした中にも漲る緊張感、ミディアム・スイングにもかかわらずスピード感溢れるのは流石、ほのかに感じる男の色気、レイドバックしたタイム感、何度聴いてもワクワクしてしまいます!ピアニストは一人ひとり本当に音色が異なりますが、Kuhnの美しくリリカルなピアノのタッチ、音の粒立ち、とってもフェイヴァリットな中の一人です。そしてこのレイドバック感、気持ちが入れば入るほどさらにその度合いに拍車がかかるのは本物のジャズ屋の証拠、そしてこの演奏を巧みにバックアップしつつに絶妙に絡むVitousのベースライン、Kuhnを見守るが如くシンプルにサポートするRomano、Kuhnソロの冒頭から引用フレーズで攻めます。この人の演奏、フレージングから感じるのは、普段から良く喋り、ジョークを言い、ダジャレも連発していそうです。ライブを収録した彼のリーダー作の何かで聴いたことがありますが、引用フレーズが止まらなくなり、一体何の曲を演奏しているのか一瞬分からなくなりそうでした(爆)。本演奏はピアノの独壇場で終始します。ラストテーマの後奏でまたもや引用フレーズが登場、今度はSummertimeです。とっても濃い内容の演奏ですが全くtoo muchを感じないのは全てがスポンテニアスな内容だからでしょう。素晴らしい!
2曲目Lotus Blossom、Kuhnは60年デビュー当時トランペッターKenny Dorhamのバンドに参加していましたが、そこで良く演奏していたと思われるDorhamのオリジナル 。Sonny Rollinsが自身のリーダー作「Newk’s Time」に於いてこの曲をAsiatic Raesという曲名で録音しています。このヴァージョンでは6/8拍子のリズムとスイングが交錯します。
本作ではピアノのイントロの後、全編アップテンポのスイングで演奏されています。駆け出しの頃に大変世話になったバンマスDorhamへのトリビュート、アップテンポにも関わらず速さを感じさせない究極のゆったり感、たっぷり感、でも音符のスピード感は凄まじいものがあります。8分音符の的確なビートに対する位置、1拍の長さが十分でなければありえない事象です。この曲でも引用フレーズThe BeatlesのEleanor Rigbyの一節を聴くことが出来ます。とりあえずダジャレを言っておけばその場が和むと思い込んでいるオヤジの哀しいサガの表れでしょうか、おっと失礼、これは僕自身の事でした(笑)、ソロの1~2コーラス目は比較的音の間を活かしテーマのメロディも交えつつスロースタート、その後3コーラス目からのエンジンがかかったソロの展開と言ったら!徹底的にクールにイキまくっています!3’40″からの右手で同じシークエンスをずっと弾きながら左手のラインをリズムも含めて変化させて行く、超絶テクニック、タイム感!この人は一体どのような頭の構造をしているのでしょうか?またピアノソロを支えるVitousのラインの凄まじさ!ベーシストは各々のコードのルート音を弾くのが仕事の筈ですが、この人は敢えて、何故だか、喧嘩を売っているのか、ルートを弾かないのでベースラインだけを聴いていると何処を演奏しているのか、更には何の曲を演奏しているのか理解不能です!それにしても2’33″~35″で聴かれるベースのトレモロに聴こえるラインは何?正体不明ですが物凄いインパクトです!!気がついてみると実はこの曲の演奏時間が5’04″、こんなに短いとは信じられません!大変濃密で充実した演奏、起承転結含めたストーリー性、時間の長さは絶対的なものではなく相対的なものなのだと再認識させられます。聴き手を確実に引き込んでしまうクールで激アツな演奏です。
3曲目はドビュッシー作曲のLa Plus Que Lente(レントより遅く)とDuke EllingtonのPassion Flowerが続けて演奏されます。Lenteはピアノソロで、Passion Flowerはボサノヴァのリズムで演奏しています。美の世界がメドレーで構築されているのです。Romanoの繰り出すボサノヴァのリズムが大変気持ち良いのは、彼のグルーヴ自体がイーヴン系故でしょう。曲のミステリアスなメロディと美しいコードとの対比に心を鷲掴みされてしまいます。ソロ中Kuhnの左手が支配的に繰り出され、ダイナミクスをこれでもか、と表現しています。Passion FlowerはEllington楽団の名リードアルト奏者、Johnny Hodgesをフィーチャーしたバラード演奏が元になっています。https://www.youtube.com/watch?v=_ww-XDuaxcw
(クリックして下さい)こちらも蕩けるほどに美しい演奏です。
4曲目RomanoのオリジナルのワルツナンバーDo。ドラマーが書く曲が僕は好きです。特にメロディアスなワルツはドラマーの本質が聴こえて来るようです。メロディ、コード進行を聴かせるために全編ブラシで演奏しています。Vitousはこういったスペースのある曲でも縦横無尽にラインを繰り出し、ベースラインよりもメロディに対して最も相応しい音を瞬時選択して奏で、歌伴のオブリガードを演奏しているかのようです。ソロの先発はVitous、良く伸びる美しい音色と正確なピッチ、テクニカルな中にも歌がしっかりと織り込まれています。受け継ぐKuhnのソロも気持ちの入った叙情的な演奏です。
「癒し系」の演奏の後にはハードな場面展開があるものです。5曲目はタイトル曲で Kuhnのオリジナル、本作の目玉でもあるOceans In The Sky、自身の作品で何度か再演されています。自作の曲を度々レコーディングするのは良い事だと思います。そのミュージシャンの成長、進化を一つの尺度で測れるからです。この曲にはLaura Anne Taylorによるポエム、歌詞が付けられています。アップテンポのワルツ、ここでのKuhnのソロは曲のコード進行に基づいてフレージングすると言うより、曲のメロディやリズムにカラーリングを施しているように聴こえます。Romanoのドラムソロもフィーチャーされメリハリのある演奏になっています。
6曲目はFred Lacey作曲Theme For Ernie、若くして亡くなってしまったアルト奏者Ernie Henryに捧げられた曲、彼は40年代末から57年頃までの短期間活動しました。著名なところではThelonious Monkの「Brilliant Corners」での変態系名演が光っています。ヘロインの過剰摂取が死因とはあまりに50年代のジャズミュージシャンそのものですが。John Coltraneの代表作「Soultrane」でのCotrane自身の名演が忘れられません。この曲は通常キーがA♭ですがここではCで演奏されています。A♭よりも幾分明るく聴こえるのはCというキーの特性でしょうか。
7曲目はAntonio Carlos Jobim75年録音の美しいナンバー、このトリオのサウンドによりこの曲が再構築されました。やはりRomanoはここでも的確なボサノヴァのリズムを繰り出しています。Kuhnはこの曲のレイジーで、夏のフェスティヴァルの後の様な物悲しい雰囲気に相応しいソロを聴かせています。
8曲目は本作のもう一つの目玉、Dave Brubeckの名曲In Your Own Sweet Way、Vitousの壮大なフリーソロから印象的なイントロ、美しいメロディ奏、この曲の代表的な演奏の誕生です!1’49″~50″あたりのピアノの猛烈なグリッサンドにはびっくりしましたね!インタールードを経たソロの1コーラス目はピアノが主体のソロのはずが、ベースのチャチャ入れがあまりに音楽的でKuhnはフレーズに応じてソロの主導権をベースに明け渡しているかのようです。4’23″くらいから引用フレーズ、ダジャレコーナーでIf I Should Lose Youが聴かれます。時折聴かれるわざとハネた8分音符のイントネーションがユーモラスに聴こえます。インタールードでの3者の息のあったインタープレイが、また6’11″~13″あたりの先ほどよりもバージョンアップしたピアノのグリッサンドにはとても気持ちが入っています。
9曲目は再びKuhnのオリジナルUlla、美しいバラードです。Kuhnは低音から高音域を隈なく用いてダイナミックでリリカルな演奏を聴かせています。
10曲目ラストを飾るのはエピローグ的なソロピアノによる、ミュージカル作曲家Jule Styneの名曲The Music That Makes Me Dance、この曲で踊らせちゃうくらいのナンバーをソロで、というのが良いですね。曲自体の構成、歌詞の内容、メロディの仕組み、コード進行をしっかりと捉えた末の演奏として堪能出来ました。